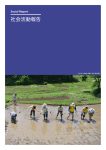Download CSR報告書2005(PDF形式、9.00Mバイト)
Transcript
2 会社概要 日立グループの事業概要 経済性報告 4 経営者メッセージ 6 日立グループの CSR 推進活動 8 コーポレートガバナンスとグループ運営 9 コンプライアンスの徹底 10 ステークホルダーとの対話 12 HITACHI CSR Activities next society 20 お客様と社会と日立 お客様満足 21 品質保証 23 社会貢献活動 28 株主・投資家の皆様へ 30 調達先(サプライヤー)とともに 32 日立を支える社員 36 2005 年度の活動計画 next eco 38 日立グループの環境活動 44 事業活動における環境負荷情報(2004 年度) 46 エコマインド&マネジメント 49 エコプロダクツ&ファクトリー 57 ステークホルダーとの共創 58 サスティナブルビジネスモデル 61 2005 年度の活動計画 62 「日立グループ CSR 報告書 2005」への第三者意見 64 日立グループの環境活動掲載データ 本文中のマークの説明 * 用語集:専門用語、固有名詞などでわかりにくいものには*のマークをつ け、P.62 ∼ 63 に用語集として参照できるようにしました。 WEB :関連するホームページのタイトルとアドレスを示しています。 PAGE :関連するページを示しています。 グラフなどには色覚障害に対応したユニバーサルデザインに取り組みました。 本文に掲載するお客様、調達先の会社名は敬称を略しています。 会社概要 経済性報告 商号 [2005 年 3 月末日現在] 株式会社 日立製作所 設立年月日 Hitachi, Ltd. 資本金 282,033 百万円 大正 9 年(1920 年)2 月 1 日 従業員数(個別) 41,069 名 [創業 明治 43 年(1910 年)] (連結) 347,424 名 本店の所在地 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号 連結子会社数 985 社(国内 539 社、海外 446 社) 代表者 代表執行役 執行役社長 兼 取締役 庄山悦彦 持分法適用関連会社数 167 社 [2005 年 3 月期(連結)] 日立グループの事業概要 売上高 90,270 億円(前期比 105%) 日立製作所 および 日立グル ープは、連結子会社 では 国内 539 社、 営業利益 2,790 億円(前期比 151%) 海外 446 社、持分法適用関連会社 では 国内 84 社、海外 83 社、計 設備投資額 9,595 億円(前期比 118%) 1,152 社で構成される企業集団です。事業内容は、以下の表に示す 研究開発費 3,886 億円(前期比 105%) ように、7 つの 部門にわたり、売上高 は 約 9 兆円、社員数 は 約 34 万 連結売上高に占める海外生産高比率 18% 人です。 事業部門名 情報通信システム 電子デバイス 電力・産業システム 代表製品 日立グローバルストレージテクノロジー ズの 1.0 型ハードディスクドライブ 日立 ディスプレイズ の IPS 技術 を 適用 した 携帯電話用 2.2 型高精細(QVGA) 英国ドー バー 海峡トンネル 連絡線 に 使 用される鉄道用車両(英国国内 サービ ス用)※ TFT 液晶 サーバ、通信、ストレー ジ、管理ソフト機能を統 合した エンタープライ ズ・ブレード・システム※ 日立ハイテクノロジーズの新型測長 SEM 東京国際空港(羽田)第 2 旅客ターミナ ルビルに納入した展望用エレベーター※ 指静脈認証システム※ 主な製品・サービス 主要な連結子会社 システムインテグレーション、アウト ソーシング、ソフトウェア、ハードディス クドライブ、ディスクアレイ装置、サー バ、汎用コンピュータ、パソコン、通信 機器、ATM(現金自動取引装置) 日立コミュニケーションテクノロジー、 日立オムロンターミナルソリュー ションズ、HITACHI COMPUTER PRODUCTS(AMERICA)、 日立建機の油圧ショベル 日立 ハイテクノロジーズの 心臓磁気計 測システム HITACHI COMPUTER PRODUCTS (EUROPE)、HITACHI GLOBAL STORAGE TECHNOLOGIES NETHERLANDS、日立電子サービ ス、日立情報システムズ、日立ソフト ウェアエンジニアリング、日立システ ムアンドサービス、HITACHI DATA SYSTEMS HOLDING 2 日立グループ CSR 報告書 2005 液晶ディスプレイ、半導体製造装置、 計測・分析装置、医療機器、半導体 日立ディスプレイズ、日立ハイテクノ ロジーズ、日立メディコ、HITACHI ELECTRONIC DEVICES(USA)、 HITACHI SEMICONDUCTOR SINGAPORE 原子力発電機器、火力発電機器、水力 発電機器、産業用機械・プラント、自動 車機器、建設機械、エレベーター、エ スカレーター、鉄道車両、空調装置 バブコック日立、日立空調システム、 日立建機、日立産機システム、日立 インダストリイズ、日立機電工業、日 立ビアメカニクス、日本サーボ、広州 日立電梯、HITACHI AUTOMOTIVE PRODUCTS(USA)、日立ビルシステ ム、日立エンジニアリング、日立エンジ ニアリングサービス、日立プラント建設 [連結業績] 年度部門別売上高(億円) 売上高推移(億円) 情報通信システム 金融サービス () () 物流及びサービス他 () 高機能材料 電子デバイス () () (年度) デジタルメディア・民生機器 電力・産業システム () () 部門別売上高小計 連結売上高 億円 億円 ※経済性報告の詳細はホームページをご覧ください。 http://www.hitachi.co.jp/IR/index.html 表中の※は日立製作所の製品 デジタルメディア・民生機器 高機能材料 物流及びサービス他 日立化成工業 のリチウムイオン 電池用 カーボン負極材 3PL サービスを提供する日立物流 日立キャピタルの多機能 IC カード プラズマテレビ※ 日立 ホーム&ライフソリューションの 洗 濯乾燥機 金融サービス 日立金属の液晶ディスプレイ用スパッタ リングターゲット材 エルピーダメモリ (株)の DDR2SDRAM に 採用された、日立電線 のμBGA パッ ケージ製品 日立マクセルのリチウムイオン電池 光ストレージドライブ、テレビ、液晶プ ロジェクタ、携帯電話、エアコン、冷蔵 庫、洗濯機、情報記録媒体、電池 日立ホーム・アンド・ライフ・ソリューション、 日立マクセル、日立メディアエレクトロニク ス、HITACHI HOME ELECTRONICS (AMERICA)、上海日立家用電器 電線・ケーブル、伸銅品、半導体用材 料、配線板、関連材料、有機・無機化 学材料、合成樹脂加工品、液晶ディス プレイ用材料、高級特殊鋼、磁性材 料、鋳鉄品、鋳鋼品 日立電線、日立化成工業、日立金属 電気・電子機器の販売、システム物流、 不動産の管理・売買・賃貸 中央商事、日立ライフ、日立モバイル、 日立物流、日京クリエイト、HITACHI AMERICA、HITACHI ASIA、日立(中 国)、HITACHI EUROPE リース、ローン、生命・損害保険代理業 日立キャピタル、日立保険サービス 会社概要 3 経営者メッセージ 4 日立グループ CSR 報告書 2005 経営者メッセージ 5 日立グループは、CSR とは自発的な活動によって推進するものであると考えます。 こうした風土を築いていくため、2005 年 3 月、 「日立グループ CSR 活動取り組み方針」を策定しました。 日立グループ 1,152 社は、本方針をもとに CSR 活動を推進することで 次世代の可能性を拓く企業をめざします。 CSR 取り組みの考え方 グループ CSR 推進体制 日立 では、自ら 進 んで 難局 を 切り開き、挑戦し 続 け 2004 年 6 月、日立グループの 経営戦略を担うグルー る「開拓者精神」 、真摯な議論を経 て、ひとたび 方向 プ 戦 略 本 部 に、グ ル ー プ 全 体 に お け る CSR 活 動 が 決まれば 一致団結してことにあたる「和」 、そして 方針 や 計画 などの 重要事項を 審議 する機関として、 常 に 相手 の 立場 にたち、何事 にも誠心誠意取り組む CSR 推進委員会 を 設置しました。 同時 に、経営会 「誠」 、といった 創業者 の 精神 に 基 づ いた「企業行動 議 で 決定した 内容を的確 かつスピーディに 実行 する 基準」 (1983 年制定、1996 年改正)を軸とし、企業活動 た め、CSR にかか わる 部署 の 担当者 で 構成 され た を 行ってきました。 この 普遍的 な日立 の 企業精神を CSR 推進 チームを設置しました。 これらの 活動 の 取 土台とし、さらに、今日の 社会 の 期待 に 応えるため、 りまとめ役を CSR 推進部が担当しています。 2005 年 3 月、CSR の 視点 で「日立グループ CSR 活 2005 年 4 月から、情報共有やグループ共通の課題に 動取り組み方針」を新たに策定しました。 この 方針を ついての検討など CSR 全般の包括的な活動をグルー グループ 共通 の 方針として 位置 づけ、今後も CSR 活 プワイドに推進しています。 動の強化を図っていきます。 T O P I C S 日立製作所の CSR 活動の 2004 年度、日立製作所 は、今日社会から求 められている 自己評価実施と今後の展開 CSR の 課題とそれに対 する活動状況を認識 する必要があ ると考え、自己評価を実施しました。 評価にあたり、CSR に関 する国際的なガイドラインや SRI ( 社会的責任投資 )などの 評価指標を 参考 に、5 つの 指標 ※ [日立の CSR 評価] を抽出、合計 382 の質問項目を 7 分野に区分した評価表を 2004 年 10 月実施 取引先との協調 地域共生・社会貢献 100 80 60 40 20 0 ガバナンス/倫理・遵法 作成し、評価を実施しました。 その 結果、人権にかかわる 考え方 や 取り組 み 方針 が 明示されていない、CSR 活動 の ブランド価値の向上 グローバルな対応 およびサプライチェーンにおける方針策 定とその 徹底 が不足しているといった課題 が明らかになり ました。 今後、日立製作所 はこれらを重点課題として、誠 コミュニケーション 実 に 取り組 んでいくとともに、グループ 各社と連携して、 グループ全体において自発的に CSR 活動が実践される風 土づくりに注力していきます。 働きやすい職場 お客様の満足度向上 ※ SAM、グッドバンカー、GRI ガイドラインなど。 環境 に 関しては、独 自の評価指標「GREEN 21」で評価しているため(P42)、自己評価の対 象から除きました 6 日立グループ CSR 報告書 2005 [グループ CSR 推進体制図] 日立製作所 社長 経営会議 事業グループ グループ戦略本部 CSR 推進委員会 事業所 グループ会社 社長 CSR 担当責任者 グループ会社 CSR 担当責任者 コーポレート・ コミュニケーション本部 CSR 推進部(事務局) 経営会議: 経営層による CSR 経営方針決定 CSR 推進委員会: 関係役員を主体とした CSR 活動の 方針、計画の審議 CSR 推進チーム: 関連部署の担当者による CSR 活動の 具体的計画策定、フォローアップ グループ長&CEO CSR 推進チーム 日立製作所および連結子会社 985 社、 持分法適用関連会社 167 社 グループ経営、ブランド戦略、 お客様満足(CS)、海外事業、 労政・人事、法務、社会貢献、 環境保全、コンプライアンス、 品質保証、資材調達、広報 企業行動基準 基本理念 日立製作所 は、その 創業精神 である“和”、 “誠”、 “開 明な企業行動 に 徹 するとともに、環境との 調和、積極 拓者精神”をさらに高揚させ、日立人としての 誇りを堅 的な社会貢献活動を通じ、良識 ある市民として 真に豊 持し、優 れた自主技術・製品 の 開発を通じて 社会 に 貢 かな社会の実現に尽力する。 献 することを基本理念とする。 あわせて、当社 は、企 1983 年 6 月制定(1996 年 9 月改正) 業 が 社会 の 一員 であることを深く認識し、公正 かつ 透 日立グループ CSR 活動取り組み方針 1. 企業活動としての社会的責任の自覚 日立グループ全役員及び全社員は、企業の社会的責 任(CSR)が 企業活動 そのものであることを自覚し、 行うと共に、人権の尊重及び高い企業倫理に基づい た行動を取ります。 5. 環境保全活動の推進 社会及 び 事業 の 持続的発展を図るべく、本取り組み 環境と調和した持続可能な社会の実現に向けて、環 方針に基づいて、社会的責任を果たしていきます。 境に与える負荷を低減し、限りある資源 の 有効活用 2. 事業活動を通じた社会への貢献 優 れた 研究・技術・製品開発を基盤とした 事業活動 を行います。 6. 社会貢献活動の推進 によって、安全 かつ 良質 な 製品・サービスをお 客様 良き企業市民として、より良い社会を実現するため、 に提供 すると共に、豊かで 活力のある社会の構築に 社会貢献活動を積極的に推進します。 貢献します。 3. 情報開示とコミュニケーション 7. 働き易い職場作り 全 ての 社員にとって、働きやすい、やりがいのある 日立グループを取り巻く多様なステークホルダーと 職場作りに努 めると共に、仕事を通じた自己実現 や の 信頼関係を維持・発展させるため、公正 で 透明性 自己成長を図ることのできる、意欲 ある社員を積極 の 高 い 情報開示を行うとともに、さまざまなコミュニ 的に支援します。 ケーションを通じてステークホルダーへの 責任 ある 対応を行います。 4. 企業倫理と人権の尊重 8. ビジネスパートナーとの社会的責任意識の共有化 全ての取引先に協力を求めて、社会的責任意識を共 有化し、公正、かつ健全な事業活動の推進に努めます。 文化や道徳観、倫理や法体系等が多様であるグロー バルな事業環境において、公正で誠実な事業活動を 2005 年 3 月策定 日立グループの CSR 推進活動 7 日立製作所および日立グループ各社は、 コーポレートガバナンス(企業統治)の一層の充実を図っています。 経営の迅速化と透明性の向上を実現することが、 ステークホルダーの皆様からの信頼につながると考えます。 ガバナンス体制 グループマネジメント 日立製作所は、2003 年 6 月より、委員会等設置会社 日立グループは 幅広 い 業種・業態 で 構成されていま に 移行し、取締役会 が 経営 の 基本方針を決定、執行 す。 その 強 みを生 かすために、それぞれのグループ 役 の 業務執行を監督 する一方、取締役会により選任 会社 の自主独創性を 尊重しながら、連携 によるシナ された 執行役 がより機動的 に 業務執行を 行うコーポ ジー 効果を生 み 出 す 関係を構築しています。 これに レートガバナンス 体制となりました。 また、あわせて よって、新しい価値創造をめざしています。 日立グループの 上場会社 18 社も委員会等設置会社 このグループシナジーの拡大など、日立グループの総 に移行し、各社における経営の迅速化と、日立グルー 合力発揮をめざした 経営戦略 の 構築と実行を行う組 プとしてのガ バナンスの 向上 を 図って います。 さら 織として、2004 年 4 月に「グループ戦略本部」を設置 に、日立製作所 では、取締役会 が 任意 に 設置 する委 しました。 また、この「グループ戦略本部」をマネジメ 「グループ経営委員会」を設置し、グルー 員会として、 ントして、日立グループを構成 する各社 およびグルー プ 経営全般 に 関 するモニタリングならびに 提言を 行 プ 全体 の 価値を継続的 に 向上させる施策を立案、提 い、取締役会の「経営の基本方針の決定と監督」機能 言、実行 する「グループ 経営執行役」を 設 けました。 を補完することとしています。 このような新 たなグループマネジメントにより、 「意思 ある統合経営」を進めています。 [日立製作所におけるガバナンス体制] 株主総会 選任 取締役会 (14 名、うち社外 4 名) 監査委員会 (5 名、うち社外 3 名) 指名委員会 (5 名、うち社外 3 名) 選任 報酬委員会 (5 名、うち社外 3 名) 監督 執行役:機動的な会社業務の執行 8 コーポレートガバナンスとグループ運営 コンプライアンス(法令遵守)や高い倫理観をもって行動することは、 企業の社会的責任における最も基本的な事項です。 日立グループは、公共性の高い事業を多く担っていることにかんがみ、 より一層のコンプライアンス体制の充実、強化を図っています。 コンプライアンス体制 通報制度を 導入、2004 年 10 月 からは、公益通報者 保護法 の 制定を受けて 内部通報制度 の 対象を、全グ 日立グループは、社会と深く関わり、公共性の高 い 事 ループの 社員 のほか、元社員、取引先 や 派遣社員な 業を多く担っています。自ら襟を正し、高 い 倫理観と どから広く通報を受け付けるように拡充しました。 正義感をもって、社会 の 模範となるべく行動 すること そのほか、執行を監督 する立場にある取締役に対し、 が重要であると考え、 「公正」であることをすべての行 社員が直接通報できる「取締役会 への窓」という制度 動基準としています。 も設け、コンプライアンス違反 の 再発防止 のために、 全社をあげて、体制と意識の強化を進めています。 しかしながら、2002 年、公共 の 入札 における妨害容 疑 で日立製作所 の 社員 1 名 および 贈賄容疑 でグルー コンプライアンス教育 プ 会社 の 社員 3 名 が 起訴され、有罪となる判決 が 下 日立製作所 にお い ては、2003 年 3 月 に 企業行動倫 されました。 この 判決を 厳粛 に 受 け 止 め、社内管理 理、製品安全、社員 への 人権教育、輸出管理 や 環境 の 徹底を欠 いたことを深く反省し、二度とこのような 保全など、広域 のコンプライアンス遵守に関 する「ビ ことが生じないよう、コンプライアンス意識 の 徹底に ジネス倫理 ハンドブック」を作成し、このハンドブック 努めています。 をもとにしたグループ 学習 や、さらには e ラーニング マレーシアでのコンプライアンス 教育セミナー を活用した 全社員 への 教育を実施し、遵法意識 の 徹 2002 年に、社長直属 の 組織として、グループ 会社を 底を図っています。 また、改正不正競争防止法 の 成 含 めた 公共営業 の 入札にかかわる遵法化を主な目的 立 を 受 け、2004 年 10 月 から 欧州、中国、東南 アジ とした「コンプライアンス本部」と、外部のメンバーに ア、米国などの日立グループの拠点に対し、外国公務 よる監視組織 である「 アドバイザリー 委員会」を設置 員 への 贈賄防止に関 する教育を展開しています。 今 しました。 コンプライアンス本部では、グループ会社 後は、改正独占禁止法の成立や 公益通報者保護法の を含 めた 遵法教育 の 徹底と、営業活動 の 監査を定期 施行などにあわせて、教育を推進していきます。 的 に 実施しています。 新 たな 法規制 などの 情報・教 育については、イントラネットで公開するとともに、定 期的にニュースを発行し、グループ内の全社員でこれ を共有しています。 個人情報保護への取り組み 日立グループはグループ 全体 で 個人情報 の 適正管理 WEB に 取り組 んでいます。日立製作所 は 従来よりお 客様 日立製作所 個人情報保護に関して からお 預 かりした 情報価値を尊重 する管理体制 の 確 http://www.hitachi.co.jp/ utility/privacy/ また、日立 の 事業 のひとつである原子力部門 におい 立とその 徹底を 進 めてきました。 今般「個人情報保 ては、その 高 い 公共性 にかんがみ、2002 年 10 月 か 護方針」を作成し、この方針に従い、個人情報の適切 ら原子力部門にコンプライアンス通報制度を導入し、 な保護に努 めています。 特に、お 客様 の 個人情報を 11 月には原子力部門企業倫理相談窓口を設けていま 扱う機会 の 多 い 情報通信グループではプライバシー す。 さらに、2003 年 4 月 には 全社コンプライアンス マークを取得しています。 コンプライアンスの徹底 9 八丁地 日立は 2004 年、グループ一丸となった CSR 震 では、首都圏を含む全国 で 4,000 台、中越地区 だ 活動を本格的にスタートさせました。日立には、創業 けでも 2,600 台 のエレベーターが停止しましたが、乗 時から「技術を通じて 社会に貢献 する」という基本理 客 がいる場合 は 2 時間以内 に、そうでない 場合 でも 念があり、常に社会的責任を強く意識し活動してきま 12 時間以内に復旧させました。 いかに素早く対応 で した。一方、今日、日立の活動を社会の目から見たら きるかは、災害に備えた情報システムを構築している どうなのか、CSR という視点 で 見 つ め 直し、またス ことが不可欠です。しかしそうした体制以上に、社員 テークホルダーの目線 で 捉え直 す、いわば「可視化」 「今、自分 は 何をすべきか 」を判断し、 一人 ひとりが、 する作業 が、重要 だと考えています。 私も、CSR 推 すぐに 行動 できることが 求 められています。 早期 に 進 の 責任を担う者として、ぜひ、CSR について 先進 対応 できたということは、当 たり前 のことかもしれま 的な活動をしておられる方々と対話したいと考え、こ せんが、私 たちにとって 誇るべき、自信を持ってよい のような機会を定期的に設定させていただいています。 ことではないかと思います。 CSR は継続性も大事だと思 います。日立には 6 つの 川北 日立 は、たとえば 2001 年 の 米国 での 同時多 財団があります。少壮 の 科学者 への 研究助成金 の 提 発 テ ロ で、救 助 支 援 に 油 圧 ショベ ル を、アジ ア の 供 や、東南 アジアの 若手大学教員を日本 の 大学 の 博 SARS 問題 では、医療用 X 線装置を提供しています 士課程 に 招くプログラムなどがあります。 すでに 20 ね。本業に関わるところで、できることから行う姿勢 年以上続けていますが今 や 立派な業績をあげる方 が は、素晴らしいと思います。 それは、トップダウンとボ 増えただけでなく、その教え子も次の対象者になって トムアップがうまく機能しているからではないかと感じ きました。 経営状態 の 良いときも悪 いときもあります ます。 が、継続する重要性をあらためて感じています。 災害時に、素早く対応できる 社員の行動力を誇りたい 長期的な視点で 日立らしい社会貢献を計画しています 八丁地 恐らくそれは、日頃私たちが「社会に貢献 す 川北 そうした 対応 や 活動 が 可能なのは、受 け 継 い る」という気持 ちを心 の 中に抱き、それを実践してき できた DNA の存在が大きいのですね。 た積み 重 ねによるのでしょう。 社会 インフラを支える 日立 は、2010 年 に 創業 100 年を 迎えます。 5 年先、 ビジネスを展開していることも影響していると思 いま さらにもっと先を見据えたときに、CSR としてどのよ す。 2004 年は、大きな自然災害に見舞われた 1 年で うなものにフォーカスしていくのでしょうか。 した。 こうした災害 が発生したとき、日立に何 ができ 10 るのか、私 たちは 常 に 問 われていると感じます。 大 八丁地 抽象的 かもしれませんが、社会と双方向 の 地震が起きたとき、エレベーターの中に閉じ込 められ 対話をして日立 の 持っている「知識」や「経験」など、 ている方はいないか、途中で止まってはいないか、確 人 の 力 がもたらす 価値を提供したいと願っています。 認し、すぐに復旧作業に取りかかることが 重要 です。 たとえば日立グループが 行っている社会貢献活動 の たとえば 2004 年 10 月 23 日に発生した新潟県中越地 注力分野 の1つに 教育 があります が、これをより深 日立グループ CSR 報告書 2005 社員とともに援農ボランティアに参加 めていくアイデアを 現在、構築しています。日立 の も多様 で、グループ 各社 の「自主独創経営」を尊重し 1,000 名を超える博士をはじめ、日立 の 社員が小・中 てきたこともあり、なかなかひとつの「顔」として 描き 学校に赴き、研究や学問の楽しさを子どもたちに話す にくいという部分もあるかと思 います。 そのためにも といったプログラムもいいでしょう。 さまざまな可能 グループ 総合力 の 発揮を目的にグループ 戦略体制を 性を、長期的な視点で計画したいと考えています。 整えてきました。 一方、現場レベルでの「可視化」も 進 めています。 たとえば、採用活動 において、社員 川北 日立 ならではの 知識と経験を 融合させて、社 との直接対話を通じて事業内容を理解 いただくため、 会に提案していくことは、特に環境保全活動において より多くの学生に会 おうというプロジェクトを実施しま も有効ですね。 した。 その 際 のキーワードが「未来を信じるから、こ としやる」 。社員たちは、 「日立を代表し、一人称で語 八丁地 日立 はモノづくりの 会社 です。 地球環境 に る」 「ありのままの日立を語る」 「仕事 の 誇りを伝える」 ついては 技術を活用して、環境、モノづくり、技術と ことを念頭に学生 の 皆さんに自らの 思 いを熱く語りま いう三位一体 で 展開したいと考えています。 その 一 した。 「製品含有化学物質一元管理シス 環として 2004 年、 テム 」という製品 のトレース( 追跡 )をしながら、対象 川北 「うちの 会社」でなくて、 「私」という一人称 で 化学物質を管理していくシステムを構築しました。当 語 るというの は 素晴らしい で す ね。 これを CSR ス 面 は日立グループで 扱う、150 万点以上 の 部品を 対 ローガンにしてもよろしいのではないですか。 象としますが、将来的には他企業と協力しながら、範 囲を広 げていくことも視野 に 入 れています。 持続可 八丁地 そうですね。 大きな組織 では 誰 かがやって 能な社会に向けてのインフラづくりを、熱心にやって いると思いがちなところもありますが、 「私が本気でや いきたいと考えます。 る」と、していきたいと思っています。 「神は細部に宿 「未来を信じるから、ことしやる。私がやる」 川北 150 万点以上 ですか、膨大な量 ですね。冒頭 る」という言葉 がありますが、この 視点を大切 に、一 人 ひとりが 本気 で 取り組むことから、日立 の CSR は 始まっています。 に、 「可視化」という言葉を使われましたが、近年日本 の企業もガバナンスやコンプライアンスの充実に力を 注 いでいます。 それはまさに「可視化」が期待されて の動きでもあると考えます。同時に、日本ではこれま で「言 わずもがな」ゆえに書かれていなかったルール を明文化 する段階 から、顔 の 見える CSR へと、動き つつあるように感じます。 八丁地 そういう点 では、日立グループは 事業内容 若手社員はこのカードを胸に 「日立」を伝えた ステークホルダーとの対話 11 H I TAC H I C S R Ac t i v i t i e s 「社会が変わる、日立が変える」 このブランドメッセージには、 まさに CSR への思いが込められています。 日立グループにとって、CSR 活動は企業活動そのものであり、 グループを束ねる根幹ともいうべき思いとして受け継がれてきました。 私たちは次なる時代も、よりよい社会づくりに取り組み、 社会との相互の信頼関係を築いていきたいと考えています。 ここでは、多様な日立グループの活動の中から、 よりよい社会をめざしたチャレンジングな取り組みをご紹介します。 ムバラクポンプ場全景 300 万人が入植する 街づくりのインフラとして ケールの大きさは想像を絶します。 エジプト・ アラブ共和国 川 広さがありますが、その 大部分 が 砂漠地帯 で、緑地 地化され、300 万人が入植 するというのですから、ス ル イ かけて 行われました。 エジプトは、日本 の 約 2.7 倍 の カイロ 都とほぼ 同一 の 2,250 平方 キロメートルの 土地 が 緑 ナ ムバラクポンプ 場 の 建設 は、1998 年 から 2003 年 に 入 れ、砂漠地帯 に 供給しようという計画 です。 東京 アスワン 砂漠でゼロから始まったプロジェクト はナイル川流域の 6%ほどに過ぎません。 そこでエジ ポンプ 場 の 建設プランは、30 年以上も前 から、計画 プト政府 は、緑地を増 やすために数々 のプロジェクト されてきたものでした。日立グループは、そのころか を 推進しています。 ムバラクポンプ 場もそのひとつ らエジプト各地の排水や灌漑施設にポンプを納めてき で、大統領 の 名を 冠した、文字通り最大規模 の 国家 ました。 一般には、建物をつくってからポンプ 設備を プロジェクトです。 入 れるのですが、今回 はムバラク大統領 の 発案 によ 有名 なアスワンハイダムの 建設 によって 生まれたナ り、設計と建設を同時かつ 短期間でつくる、世界的な セル 湖 の 湖岸に、日立製 の 大型縦軸渦巻きポンプ 21 プロジェクトになるというのです。数々 の 経験を積 ん 台を設置して、東京ドーム 23 杯分もの 水を毎日取り できた日立にとっても、まさに技術者魂を揺さぶられ ムバラク ポンプ場 HITACHI CSR Activities ナセル湖 13 スのスペースをきちんと確保 すること、そして 厳しい 経済状況のエジプトを考え、いかに低予算でつくるか に全力を注ぎました。 ポンプのケーシングなどの製缶 工程の大半は、エジプト国内の協力工場で行い、コス ト削減とともに、現地 の 雇用 の 確保 や、技術 の 移転 に貢献 することができました。 これまでの日立は海外 での納入実績は多いものの、現地で加工・溶接を行っ た実績はありませんでした。 そこで、国内生産と同じ 性能、高品質を保 つために、1,000t 近 い 鋼材を輸出 支給し、担当スタッフが現地に 1 年間滞在して、細か な技術指導にあたりました。 その甲斐あって、品質の 確保と現地 の 人々 への 技術移転 が 実現し、当初 の目 来日した組み立て実習中のエジ プト人技術者とともに 的を 達成 することができました。 私 たちが 作業 にお るテーマでした。 その 責任とリスクの 大きさから日立 いて留意したのは、工事現場における事故防止です。 は信頼ある英国とエジプトの会社と手を結 び、国際コ 日本 では 想像もできない 過酷な状況 の 中 で 工事 が 進 ンソーシアムを結成。機械・電気システムエンジニア められていたからです。 これに対しても、日立の経験 リングと機器の一括納入を担当しました。 を生かし徹底的な安全衛生の対策措置を行いました。 プロジェクトを開始した頃はまだ道路もなく、キャンプ 世界でも例のない 工事だっただけに、計画通りにはと 地は 40℃以上の暑さと、サソリ、毒ヘビもいる厳しい てもできないという声 が 多 かったにもかかわらず、5 環境 でした。日立グループからは 20 人 ほどが滞在し 年で 完成にこぎ 着けることができたのは、まさにチー ましたが、英国、エジプトのスタッフとともに、最盛期 ムワークのたまものであると感じます。 には約 3,000 人がここで 起居をともにしました。私た エジプトの地に入って、改めて感じたのは「水の貴さ」 ちは 2000 年 から本格的に始動し、エジプトで 現地コ です。 そして、アジアやアフリカなどの 開発途上 の ンソーシアム 内 の 調整 や、現地製作指導と据付指導 国々の多くが、今、水資源を求めています。 そうした を行い、2004 年 6 月まで滞在しました。 国々にも、私 たち日立グループとして、これからも貢 低予算化と技術の移転、安全確保に注力 これまでのポンプ製造で培われた経験を生かし、私た 献していけるのではないか。 そんな夢をこのプロジェ クトを通じて、強く抱いています。 (日立グループ ムバラクポンプ場建設プロジェクトチーム) ちは、全体をコンパクトにし、かつ 運用 やメンテナン グローバルな活動を行っている企業 は 今、2006 年7 月に施行される EU の RoHS 指令*をはじめ、分別回 収とリサイクルを 義務化 する WEEE 指令 など、新 た 「環境 CSR 対応モノづくり規程」で、 全プロセスの環境配慮ポイントを明確化 な環境規制 への 対応 が 急務となっています。日立グ そこで、グループ全体のモノづくりを捉え直し、2004 ループも 1998 年より、対象化学物質 の 全廃に向け、 年に策定したのが「環境 CSR 対応モノづくり規程」で 取り組みを進めてきました。 す。 経営、企画、設計開発、調達、製造、流通、使 私たちは、環境規制を単に「守っていく」という発想か 用、リサイクル、廃棄といった、企業活動 の 各プロセ ら、一歩踏 み 込 んで、汎用性 のある強 い 仕掛 けを構 スでの 責務と環境配慮 ポイントを明確化 することで、 築 すれば、一連 の 活動で 生じるコスト増を吸収し、新 製品( ハードウェア、ソフトウェア)、サービスのライフサ たな価値を生み出せるのではないか、と考えました。 イクル 全体 にこの 考えを 適用していきます。 この 中 で 製品 の 化学物質対応を視野に構築したシステムが 14 日立グループ CSR 報告書 2005 「製品含有化学物質一元管理システム 」です。 化学 ませ んが、およそ 1 機種 あたりの 部品点数 は 2,000 物質は、禁止物質として鉛、カドミウムなどの 13 物質 種にものぼります。 まず、設計段階において、日立グ 群と、管理物質として、アンチモン、ヒ素 など 12 物 ループで 禁止している対象化学物質を含まない 部品 質群を対象としました。 を、調達先から選び認定します。 各プロセスの担当者が、コンピュータに必要な情報を 部品納入の際は、調達先から部品データと、対象化学 入力し、一元管理 するもので、使用材料 や 成分情報 物質 の 不含有保証書を提出していただきます。 そし の 管理はもとより、材料・部品 の 購買情報を統合して て、その 部品をもとに、製造担当 が 商品を作ります。 管理 でき、トレーサビリティ( 生産履歴追跡 )も可能 に 完成品 は、製造個体番号と、すべての 部品 データを なるという仕組みです。 紐付けし、コンピュータ上でデータを一元管理します。 そして 個々 の 部品 だけでなく、製品個体 の 化学物質 サプライヤー 7,000 社以上、 部品 150 万点以上に対応 の含有量を算出し、管理基準値内であることを確認し このようなシステムを構築した背景には、日立グルー スなどで、お 客様 が 製品 に 手を 加える際 は、その 都 プならではの 事業 の 多様性 が 影響しています。日立 度、データを記録・更新していきます。 は、日立製作所をはじめ、国内外 の 約 1,100 社 で 構 成され、その事業内容も、高機能材料や部品から、コ てお 客様 に 納入します。 その 後、増設 やメンテナン 2006 年 6 月までにグループ全社で展開 ンシューマー 機器、社会 インフラシステムまで、きわ RAID シ ス テ ム 事 業 部 で は 2005 年 の 4 月 より、こ めて 広範囲に及 んでいます。 年間 で 扱う部品 の 種類 のシステム 対応 へと順次切り替 えを 始 めて います。 は 150 万点以上 にものぼり、部品 や 資材を、世界中 2005 年 6 月より、グループ 企業 での 導入を 開始し、 の 7,000 社以上 の 調達先( サプライヤー)から納入 い 2006 年 6 月までに徹底することを目標にしています。 ただき、また日立も同様 に、サプライヤーとしてさま グル ープ 全社 でシステムを 活用 すると、1 日平均 で ざまな企業に商品を納入しています。 3,000 ∼ 4,000 人の担当者がデータにアクセスし、入 こうした複雑な状況に対応しながら、グループ内 の 化 力 することになるでしょう。 その 一人 ひとりの 入力を 学物質 の 管理を 徹底させるには、製品、サービスの 集計 すると、日立グループとして、化学物質をどれだ 日立製作所 RAID システム事業部 生産 IT 統括部 築島俊尋 流れをすべて 捉えられる、まったく新しい 仕組みをつ くる必要がありました。 そのスケールを考えるとたや すいことではありませんが、一旦、システムが定着 す [製品含有化学物質一元管理システム] れば、データはどんどん 蓄積されていくことになり、 コーポレート部門 それはやがて日立の強みにもなります。 そしてシステ ムが軌道に乗れば、そのノウハウを、さまざまな企業 成分情報 の共有 と共有していくこともできるのです。 RAID システム 事業部 での 流 れを 例 に、具体的 に 説 明してみましょう。 RAID とは Redundant Arrays of 環境 CSR データベース 化学物質入出荷総量 部品使用事業所情報 出荷製品の 成分情報 の提供 成分 シミュレーター お客様・社会 このシ ステ ム が す で に 導入 され て い る日立製作所 調達先︵ サプラ イ ヤー︶ 紐付けと確認を繰り返す A Gree’ Net 部品成分情報 事業部門 (例:RAID システム事業部) Inexpensive Disks の略で、複数のハードディスクを 有害物質を 使用しない 製品の開発 まとめて、1 台 のハードディスクとして 管理 する技術 有害物質を 含まない 製品の出荷 を 採用したシステムをい います。 航空、金融、エネ ルギー、医療、行政など、情報社会 のライフラインを 製品固体管理 部品 構成情報 担っている企業が膨大なデータを蓄積 するためのスト データウェア ハウス 出荷製品の 情報提供 設計 レージシステムに 採用されています。 これを 活用し た日立 のストレージ 製品も、米国 や 欧州をはじめとし た、世界中の企業にご利用いただいています。 ハードディスクの 集積 であり、お客様 の 注文に応じて 有害物質を 使用しない 材料、部品 の購入 購買履歴 組立、 加工履歴 資材 製造 出荷履歴 販売・ 保守履歴 販売、保守 カスタマイズしていく商品 のため、厳密には数えられ HITACHI CSR Activities 15 け 扱ったかが 一目瞭然となるのです。 万一、問題 が いたと思っています。 そしてこの透明性を高めるチャ 発生した場合は、48 時間以内に、影響範囲を把握 す レンジは、有害な化学物質を含まない 製品を開発し、 ることが可能です。 出荷していくという日立 の 環境活動を加速させると、 このシステムにより、日立 の 活動を検証 することがで 私たちは信じています。 きます。 その 意味 では、社会 が 期待 する水準に近 づ (日立グループ 環境 CSR モノづくり対応プロジェクトメンバー) 昇降機 端末機 操作・表示画面 「100%の 障害者 はいない。 100%の 健常者もい 車両・交通 ない。 人間 は 皆、身体(または 精神 )のどこか に 障害部分 を 持って おり、なおか つ 健常 システム 家電 Public なる 部分 をも合 わ せ 持って いる。 ユ ニ Information ヴァーサルデザインとは、誰でもが豊か で快適な生活を送るためのものである」 。 Home 日立製品の広がりと ユニバーサルデザイン 日立もその立ち上げから参画している「国際 注 1:国際 ユニヴァーサルデザ イン 協議会=産・学 の 専門家 が 集う団体で、2003 年 11 月に発 足。日立製作所 は 理事会 にて 理事長を務める ユニヴァーサルデザイン 協議会(IAUD) ( 注 1)」の 総 きさを変えたり、移動や 使 い 勝手の自由なモノを生活 裁 である寬仁親王殿下 が、組織 の 設立にあたって 述 のあらゆる場面 で 生 み 出し、活用してきました。 UD べられたお言葉です。人間は誰しも完璧ではなく、日 は、日本 のモノづくりが 得意とする発想 でもあるとい WEB http://www.iaud.net/ 常に障害を感じることをふまえて、社会 のあり方を見 えそうです。 つめ直そうとする視点を、この言葉に感じます。 そして、UD は 同時 に、日立 の 視点とも重 なります。 それは人間中心に考えること ること」 。 UD をことさら新しい 概念としてではなく、 改めて見 つめると、さまざまな障害に気 づきます。 た 人間中心に考えることを再度、教えてくれるきっかけ とえば、エレベーターホールの呼 び 出しボタン付近に とし、その深化に取り組んでいます。 う。 外国人 にとっては、日本語 だけの 表示もひとつ 日立グループ ユニバーサルデザイン ガイドライン してきましたが、その 核にあるのは「人間中心に考え 普段はあまり意識していなくても、現代の都市生活を 灰皿があるだけで、車いすを使用する方は困るでしょ 注 2:ユニバーサルデ ザイン= 1980 年代 に 米国ノースカロラ イナ 州立大学 の 故 ロナ ルド・メ イスが「 できるだけ 多くの 人 が 利用可能 であるように製品、建 物、空間 をデ ザ イン すること 」 をユニバーサルデザインと定義 日立 は 技術 で 社会 に 貢献 することを使命と考え活動 ニーズの多様性に応えていく取り組み の 障害 です。 あるいは、ユーザーの 手に余るほど分 日立グループは、身近 な 家電製品 から、情報 サービ 厚い取扱説明書などもそうでしょう。 ス、公共システムなどの 基盤設備 にいたる、いわば つまり、ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イン( 以下 UD) ( 注 2)と 「社会」と「生活」そのものに 関 わって います。 お 客 は、特別な発見や革命的な技術ではなく、使いやすさ 様 の 層 は 広く、社会性も高 いからこそ、私 たちは UD を求め、当たり前のように製品やサービスの設計に導 を、社会的責任の視点で捉えたいと考えます。 入されるべき概念なのです。 そのための 具体的 な 活動として、基礎研究、商品開 実 は、その 言葉 の 生まれるはるか 昔より、日本に UD 発、社内啓発、ネットワーク・情報発信に 力を注 いで は 根 づいています。 風呂敷 や 扇子、ふすまなど、大 います。 基礎研究 では、視認性 に 対 する研究などを行 い、指 標となるガイドラインを広域にわたり作成しています。 商品開発 では、家電 からインフラまで、実際 のユー ザーにご 協力 いただき、モニター 調査と評価実験を 行っています。 啓発活動としては、たとえば 高齢者 のシミュレーションキットを使った社員の 擬似体験や、 教育プログラム、お 客様とのワークショップなどを行 い、理念としての UD の 理解を図っています。 さまざ 16 まなノウハウや 基礎データは、データベース化してい UD は、ニーズの 多様さに 応えていく取り組 みです。 ます。 そして、前述 の 国際 ユニヴァーサルデザイン すべての 人を満足させることが難しいように、終わり 協議会をはじめとした 各種団体などと協働し、ネット のない 活動ともいえるでしょう。しかし少しずつ、め ワークの構築と、情報発信を進めています。 ざす 環境 に 近 づくことはできるのです。 満足 する人 こうした活動をベースに、たとえば、商品の安全や 信 を 増 やして いくこの 活動 が日常的 になり、い つ の 日 頼性向上に応える、トレーサビリティシステムの 開発 か、UD という言葉 が 日立 の 中 で、そして 社会 の 中 など、持続可能な社会を導くための、新たな価値創造 で、当たり前のものになることを願っています。 につなげていきたいと考えます。 (日立製作所デザイン本部ユニバーサルデザイングループ) 法律 で 定 められた 民間企業 の 障害者雇用率 は 1.8% の指揮を、障害を持 つ身である私が担うことになった です( 注 3)。 しかし、一般 の 民間企業 における実雇 のも、日立が変わろうとする思いの表れと感じます。 用率の平均は 1.46%に留まっています(2004 年 6 月厚 生労働省調 べ ) 。求職者と仕事をマッチングする難しさ が、雇用促進の大きな障壁となっています。 日立が変われば、社会も変わる 社会の課題に取り組む ただ待つだけでは人材は集まりません。 ハローワーク 日立ホーム&ライフソリューショ ン(株) 取締役 商品計画本部 長 兼 日立製作所 研究開発本 部員 国際ユニヴァーサルデザイン協 議会 理事長 川口光男 「障害者 の 雇用 の 促進等 注 3: に 関 する法律」 (障害者雇用促 進法)。 常用労働者数 56 人以 上 の 規模 の 企業 が 対象。 障害 者雇用率 は、ほ か に 特殊法人 は 2 %、国 や 地 方 公 共 団 体 は 2.1% ( 公共職業安定所 )主催 の 面接会 に 出向 いたり、養護 学校 や 障害者訓練学校 に 紹介 いただくなど、まず 人 2003 年 6 月、日立製作所の障害者雇用率は、法定基 材との出会いの場を求めました。 準を下回る 1.66%となってしまいました。分社化など また、雇用後 の 働きやすさの 確保も重要 です。 バリ の経営改革の影響により、人材の動きが生じたことが アフリー 化など、ハード面 はすでに進 んでいますが、 直接要因 でしたが、法定基準を下回った 事実 は 軽視 難しいのはソフト面。 それぞれのケースに応じた、き できません。 障害者雇用 の 計画を見直し、実行を早 め 細かな対応 が不可欠 です。 そこで、入社後 の 悩み めた 結果、新 たに 63 名 の 人材を 雇用。 1.8%という やキャリア相談に応じる研修会と、雇用 する上司 への 基準は半年で達成しました。しかし、数字の達成が目 研修会を 開始しました。 またイントラネットに、相談 標ではないのです。 窓口も設けました。 日本の障害者雇用に課題がある今、日立に何ができる あわせて、大学生を実習生として受け入れるインター のか。日立が障害者にとって、働きやすく、魅力的な ンシップにも注力しました。 就職 するしないにかかわ 職場 になるにはどうすればいいか。日立製作所 には らず、これからもどんどん、彼らに 学 ぶチャンスを 提 約 4 万人 の 社員が、グループでは約 34 万人 が働く組 供したいと考えます。これは、障害者の可能性を発見 織です。 その規模を考えると、日立が変われば、社会 し、また気づくという、私たち自身も学べる機会です。 をも変える可能性を秘 めています。 これを機 に 課題 現在 の 最大 の 課題 は、他社 にもあまり事例 のない 重 に向かう「攻 め 」の 雇用をめざしていこう。 その 現場 度障害者 の 雇用と育成 です。 そこで 私 たちは、まず 日立製作所 労政人事部 藤原 敏 V O I C E 日立に就職して 業務を中心に 行っています。 皆さんとのコミュニケーショ ンも、だんだんスムーズになってきました。 たとえば「 あ 障害者枠 があっても、やはり軽度 の 方 が中心 で、私 のよう れ 」とか「こっち」とかの 指示語 では、私にはわからないの な全盲の重度障害者 へのハードルは高 いのではないでしょ で、そうした確認から始めました。 うか。 でも日立は、すごく情熱的に受け入れてくれました。 ただ会社 では、どうしても紙 の 資料 が多くなるのが難点 で 正直なところ、不安 は 抱 いています。 私 だけでなく、周り す。 点字化にはコストが 生じるので、それをどのように解 の 方もそうだと思 います。 でもそうした 不安を曖昧にしな 決するか、自らが、考えていきたいと思います。 いで、ストレートに伝えていけば、きっとさまざまな問題 の 目標 は、障害 があることを生 かして、商品 づくりや 社会 へ 解決につながると思います。 の 提案をしていくこと。 これからがんばっていこうという 現在は、音声ソフトがインストールされたパソコンを使った 気持ちでいっぱいです。 日立製作所 労政人事部 小野山亜矢 HITACHI CSR Activities 17 日立がリーダーシップを発揮 すべきと考え、2005 年、 「社会が変わるとき、変えるのは日立でありたい」とい 全盲の学生を採用しました。実習から手探りでまだ始 うチャレンジを、障害者雇用において、これからも実 動したばかりですが、彼女の意欲と才能に、すでに部 践していきます。 内スタッフは大きな刺激を受けています。 (日立製作所 労政人事部 藤原 敏) 私が対人地雷 の 惨状をこの目で 知ったのは 1994 年、 商用で訪れたカンボジアです。現在、世界に 1 億 1 千 万個の地雷が埋められ、所蔵数では 2 億 5 千万個にの ぼるともいわれます。 わずか 300 円 で 買える悪魔 の 兵器は、今も毎日 20 個の割合で増え続けています。 アフガニスタンの子どもたちと雨宮 清 アフリカでは 20 分 に 1 人 が、地雷 の 被害 に 遭ってい ます。 アフガ ニスタンでは、16 歳以下 の 子どもは、 も伴 います。 「田舎 の 小さな町工場にも国際貢献 の 道 1 日に 4 人死亡し、4 人負傷しています。 アンゴラで がある。 私にぜひ、世界 の 地雷と戦 わせてほしい 」 。 は、日本 の 国土面積以上 の 42 万平方 キロに 地雷 が こう訴える私に、社員とその家族は応えてくれました。 埋 められています。 子どもに 犠牲者 が 多 いのは、身 1,000 ℃にも及 ぶ 爆発温度 に 耐える強度。 石 や 岩盤 長が低く被爆しやすいことと、カラフルな地雷の色や に対 する摩耗性 や 耐久性。 悪戦苦闘 の 末、油圧ショ 形が気をひき、おもちゃと間違えて触ってしまうため。 ベルの 先端 に、高速回転 カッターを 付 けた 試作機 が そもそも多くの 子どもたちが「危険」の 文字を読 めま 完成したのが 4 年後。 さらに 2 年を費やし、遠隔操作 せん。 成長時に手足を失 い、想像を絶 する苦痛 が子 できる、世界に先駆けた地雷除去機が完成しました。 どもたちを襲います。義足も一体 30 万円かかります。 安全 で 効率的 で、50 年 で 地雷撤去 が 可能 です。 現 手作業で 1000 年、機械ならば 50 年 府に、世界 5 カ国、50 台を納品しており、2004 年 は 地雷は 50 年以上、威力を保ちます。 これを手作業で アフガニスタンで 4,000 発以上、ニカラグアで 8,000 除去 するのは、まさに 命 がけです。 しかも「1000 年 発ほどの除去に成功しました。 かかる」という。 カンボジアから戻る機内 でこの 事実 を聞き、私の憤りは収まりませんでした。 注 1:日立建機(株)製 の 油圧 ショベ ル。 山梨日立建機(株) は 1980 年より日立建機 の 特販 在は、日本国政府を通じ、国連や NGO また相手国政 自立支援への創意 私の会社で扱う油圧式ショベル(注 1)の技術を応用し まず 地雷を除去しないと、畑も学校もつくれません。 て、対人地雷の除去・処理機をつくろう。開発を心に アンゴラのように地下資源の豊富な国には、世界の視 誓い、帰国しすぐさま社内でプロジェクトを結成しまし 線が注がれていますが、地雷が前途を阻んでいます。 た。 とはいえ、社員 60 名の会社でできるのか。危険 この 開発 において 特 に 注力したのは、現地 の 人々 の 店・指定工場 アフガニスタンでの 地雷除去実験 自立支援 です。 操作 や 管理 の 技術移転を行うととも に、機械 には 汎用性をもたせました。 アタッチメント を 付 け 替 えれば、日常作業 に 活用 することができま す。 たとえばニカラグアの 村 では、地雷を 除去した 後の土地を耕し、果樹園として再生されました。現在 は、年間 60 万ケースのオレンジを出荷しています。 国際貢献として 10 年汗を流して、やっと認 められた と感じています。 そしてその 先 に、グローバ ルな 意 味での可能性が広がるのではないかと思います。 (山梨日立建機(株) 代表取締役 雨宮 清) 18 19 next society お客様と社会と日立 日立グループは企業活動のすべてにおいて、お客様の視点で行う姿勢を大事にしたいと考えます。 お客様は日立に何を期待しているのかを探究すること。 そして便利で安心な社会の実現に向け、 グループの知恵を結集することで、可能性を拓いていきます。 社会に対しては事業を通じて貢献することはもとより、 地域への参加や災害支援などの企業市民としての活動も重要な企業活動であると認識し、 グループ一丸となった取り組みを進めています。 グループ総合力と技術革新で社会に貢献 ています。 21 世紀 の 医療分野 において 重要 な 役割 日立グループは、日立製作所の創業の精神に基づき、 が 期待される DNA 解析技術 を 応用した 遺伝子診断 「便利 で 安心 できる社会 づくりに 貢献 すること」を 使 や、バイオメディカル 事業。 あるいは 個人認証を 安 命と考え、世界中 のお 客様 にとっての 価値 の 創出 に 全・安心、かつ 便利 に 実現 する IC カードや 無線 IC タ 努めてきました。視点を変えるとそれは、私たちはお グなどのキーデバイス。 それらを融合したネットワー 客様や社会との関わりの中で学 び、成長し、また支え クシステムなど。 多様なソリューションが、世 の 中 の られてきたということにほかなりません。 さまざまな課題の解決につながり、世界中の人々の幸 お客様の期待をこえるものを提供 することが、お客様 せに貢献できると、私たちは信じています。 の信頼に応えることにつながり、また多様な企業活動 注 1:ミュー チップ=世界最小 クラ ス 0.4mm 角 の 非 接 触 IC チップ 。 「 2005 年日本 国 際 博 覧 会( 愛・地 球 博 )」の 入 場 券 にも使用 2004 年 10 月 から 11 月 にかけ て、北京、上海、広州 の 3 都市 で 開催した日立の総合力を訴え る総合展示会「日立展 2004」 で 社会 に 満足 や 安心を 提供してこそ、日立グループ お客様満足 の存在意義があると考えます。 ― お客様の声を経営に反映する 今、世界はダイナミックに変貌し続けています。時代 何よりも日立 が 大事 にしているのは、お 客様 の 視点 の 変化 の 速さに対応しながら前進していくには、これ に立って考え、行動 することです。 たとえば、日立製 まで 以上 の 努力 が 必要 です。 そこで 私 たちは、日立 作所 では、0.4mm 角 のミューチップ( 注 1)から原子 グループ各社の個性を尊重しながらも、総合力を生か 力発電設備にいたるまで、物の大小にかかわらず、さ すためのグループ 連携を強化しています。 そして 開 らにお 客様 のその 先 のお 客様 にとっての 価値も無限 拓者精神をもって、高度で広がりのある技術力と提案 大に広がるよう常に意識しています。 その視点なくし 力、ユニークで人々の心を満たす 製品・サービスとい て、価値あるソリューションは創出できません。 う、的確なソリューションを創出 する企業 でありたい また、お客様の声を経営に反映 する取り組みも行って と考えます。 これを継続していくことが、日立グルー います。日立グループの 各事業部門 では、お 客様か プにとっての CSR の神髄であると捉えています。 らのご 質問 やご 要望、緊急時 の 要請などに 対応 する 日立グループの 研究部門 は、常に次 の 世代 の 繁栄を ための 窓口として、コールセンターを設けています。 視野に、エレクトロニクス、ナノテクノロジー、バイオ 寄せられたお客様の声は、社長をはじめとした経営層 テクノロジーなど、幅広 い 分野 で 最先端 の 研究開発 で 構成 する会議 で 審議し、商品 やサービスの 改善、 を行っています。 そうした研究を、たとえば新時代の 開発に反映しています。 ライフラインを支えるソリューション事業として展開し 日立 に 対 する期待 や 厳しいご 指摘など、お 客様 の 声 は貴重なメッセージです。 たとえば家電製品を扱う日 立ホーム & ライフソリューション(株)のお客様相談室 (コールセンター)には、年間 で 約 40 万件 の 電話 が 寄 せられています。 その中のひとつに、サイクロン掃除 機をお 使 いのお 客様から、フィルターの目詰まりラン プが 早期に 点灯してしまうようだ、といったご 指摘 が ありました。早速これを会議で審議し、商品の改善に 20 日立グループ CSR 報告書 2005 next society [品質保証活動の流れ] 商品製造プロセス お客様 品質保証活動 市場動向 デザインレビュー 設計 試作評価・認定 購入品 購入品管理 製造 インライン QC※ 検査 検査技術・改善 各活動へフィードバック 製品企画 納品出荷 取り組 みました。 ごみの 吸収力を維持しながら、フィ を 解決 するた めに、 「 ビー お客様 ルター 掃除 の 手間を省けるように調整し、結果、より トウィング 」という洗濯羽 使いやすい商品とすることができました。 根と、洗濯水を循環させる 商品製造プロセス ポンプ、高トルクを発生させる新駆動部という、3 つ [フィルターの目詰まり改善技術] の 新技術を開発。 飛躍的な進化を遂げることに成功 フィールドデータ 吸い上げ アフターサービス 品質保証活動との関わり ※ 製 品 ラ イフ サ イク ル* の 開 発、試作等の段階で、潜在不良 を見 つけ 出 すためのレビューや 検証を実施すること スパイラルワイヤー しました。 抗菌 HEPA クリーン ダストフィルター また、取り出しやすく、槽 の 底 のすみずみまで 見渡 せ 電源コード て、操作しやすくなるよう、デザインにも注力しまし た。多くのお客様に喜んでいただくことをめざした独 サイクロン掃除機 「たつまきサイクロン」 落としたチリは ダストケース下部へ 型式:CV-SH10 自の技術開発は、創造性の向上に寄与しました。 コードリール 電源コードを使う度(①)に、コードリールとスパイラルワイヤー が 連動し(②、③)、抗菌 HEPA クリーンダストフィルター(以下 フィルター)を振動させ、フィルターについたチリを自動的に落と します(④)。 フィルターのチリを常に少なくすることで、目詰ま りランプが適切に点灯するようになりました。 品質保証 ̶ 品質第一(Quality First) 日立 の 出発点 は、国産初 の 5 馬力誘導電動機( モー ター)の 開発 です 。 重工業を支え、かつ 長く使 われる 創造性を高めていくために という商品 の 製造を通じて、モノづくりは信用 が第一 開発時 に お い ても、お 客様 の 声 は 創造性 の 源泉 で であること、またそのための品質の確保が、いかに重 す。 商品開発というものは、 「10 年に 1 度」と形容 で 要 であるかを 教訓として 学 びました。 以来、誠心誠 きるような、飛躍的 な 進歩 を 遂 げる 時期 があります 意 のモノづくりに誠が宿ると考え、品質保証に力を注 が、これも日頃、お客様 の 声をアイデアとして 積み上 いでいます。 事業 が 多様化し、グローバルに 広 がっ げていくことから可能になります。 た 現在もその 想 いをより高 め、企業活動 の 中 で 実践 特 に 家電製品 は、お 客様 のニーズが 多様なため、お しています。 客様 が 何を求 めているのかを正確 に 把握 することが 「品質第一(Quality First)」で 日立グループの基本は、 重要です。 す。品質は製品企画・設計段階で確保し、製造・検査 2004 年に発売した洗濯乾燥機「ビートウォッシュ」は、 工程 に 不良を流さない。 また 良 い 仕事 のプロセスか 3 つの新技術を導入していますが、これも日々お客様 ら、良 い 製品 が 生まれるという考えです。 総合的 な から寄 せられた声が起点となっています。 これまでの 品質保証体制 により、製品 の 企画段階 から設計、製 洗濯乾燥機 に 対し、洗濯機能 ではもっときれ いに 洗 造、検査、出荷 の 各段階において、品質を「保証」す え、水を 節水 できるように。 乾燥機能 では 乾燥時間 るためのレビューを行 い、その基準やプロセスに反映 を短く、しかもシワなく仕上げたいという要望 が 寄 せ させています。 またグループ 内 において、事例 の 共 られていました。しかしこれをすべて満たすには、欧 有 や 改善プロセスの 検討を 行 い、グループ 全体とし 州生まれのドラム 方式などでは 限界 があり、まったく ての品質強化に努めています。 日立洗濯乾燥機 「ビートウォッシュ」 型式 :BW-DV8E ブライトシルバー(S) 楽な姿勢で取り出せる 浅底ラク出しボディ 新しい 発想 での 技術開発 が 必要 でした。日立 はこれ お客様と社会と日立 next society 21 グループで進める品質保証活動 業所を 指定し、重点的 な 品質改善活動を 通じて、体 品質保証活動をあらゆる側面 から支える具体的な活 質改善を図っています。 動として、次 のような取り組 みをグループ 一体となっ 落穂拾い て進めています。 製品 の 事故 に 対しては、お 客様 の 立場 に 立 ち、お 客 製品安全活動 様の利益を最優先に考え、行動 することが大切です。 製品安全に関 わる事故を防止してお 客様に安全 で 高 この 考えに 基 づく、事故 の 反省と再発防止 への 一連 品質な製品を提供 するための活動です。製造物責任 の活動を「落穂拾 い 」と呼 び、事故防止に役立ててい 法(PL 法 )の 対象 になる 事故(PL 事故 )だけ でなく、 ます。 PL 事故につながる可能性のある製品安全に関する事 「落穂拾 いの 心 はお 客様満足」との 考え方を重 んじ、 故 についても、特 に 細心 の 注意を 払って 発生 ゼロを 起こした 事故 は、必 ず 関係者全員に 報告し情報共有 目標 に 活動しています。 また日立グループ 間 での 安 しています。 その 上 で、技術的 な 原因と、事故 に 及 全相互診断を定期的に実施して、品質レベルの 向上 んだ 意識、無意識的原因までを徹底的 に 追究し、再 を図っています。 発防止策を導き出しています。 また 類似製品 や 業務 品質信頼性部会 プロセスなどへも確実に反映して、二度と同じような 品質と信頼性の向上をめざし、テーマごとにグループ 事故を繰り返さないよう努めています。 を横断 する分科会を開 いています。 定期的な会合 や 信頼性教育と技術者倫理意識向上活動 講演会などで、最新技術 の 情報交換や 共通課題 の 解 社員一人 ひとりに、品質 に 関 する基本理念 の 徹底と 決に努めています。 「品質 がすべてに優先 する」という意識 の 浸透を図る QF(Quality First)重点管理制度 ため、受講者 の 実務経験と技術的水準 によって 体系 年 に 1 回、品質改善 に 優 れた 事業所を 表彰 するとと 化された 全社レベルの 信頼性向上 への 教育を実施し もに、製品事故を発生させる潜在的な要因をもった事 ています。 2004 年 は日立グループで 約 250 人 が 受 講しました。 [主な品質活動] 基礎技術 また 技術 で 社会 に 貢献 する企業として、グループ 全 体 で 技術者倫理意識 の 向上・啓発 に 力を注 いでいま 製品安全活動 品質信頼性部会 す。 技術者全員 を 対象 に、専門家 を 招 い て の 研修 や、e ラー ニング(P.33 参照 )などを 実施 す るととも PAGE 「e ラーニング」 ⇨ P.33 参照 全社信頼性 教育 技術者倫理 啓発活動 に、各事業所 に 推進責任者を任命し、各事業所 の 活 品質保証 システム QF 重点管理制度 成 するための 管理者研修も行っており、2004 年は日 人材育成 品質向上 日立グループ QF21 強調運動 動活性化を図っています。 技術者倫理 の 指導者を育 落穂拾い 立グループで約 100 人が受講しました。 日立グループ QF21 強調運動(品質強化運動) 日立グル ープでは、2003 ∼ 2005 年 の 3 年間 で、品 「最高品 質保証 のレベルを飛躍的に向上させるため、 22 日立グループ CSR 報告書 2005 next society [社会貢献活動の考え方] 日立グループの社会貢献活動 ボランティア活動など 個の充実 地域社会 取引先 質の製品、サービスをお客 災害援助など、社会的責任を果たすための 社会貢献活動 主 財 団 社員のボランティア活動支援 株 社会貢献活動 日立グループ 各社 お客 様 ブランド価値向上をめざし主体的に取り組む 柔軟な発想や 働く意欲の増加による 事業活動の活性化 よ り よ い社 会 の実 現 日立グループ 社員 ブランド価値向上 日立グループの財団としての 活発な事業活動 積極的情報発信 様に提供 する」をスローガ ンに 重点的 な 活動 を 進 め ています。品質最優先 の 意識 の 浸透と、失敗 や 問題 に気 づき、豊かに成長していく機会にもなります。社 点を隠さず自ら明らかにする風土を確立 することを重 会 の 一員としての 貴重 な 体験を 通して、柔軟 な 発想 点テーマとし、各社ごとに独自に設定した品質指標を や 意欲、次世代 の 可能性を拓く力 が 培 われ、 「個」が 基に、活動の定量的評価・改善に努めています。 充実 することこそ、日立 の 原動力となるのです。 個 の充実と日立の成長が、ともによりよい 社会の実現に 社会貢献活動 役立つならば、それに勝るものはないと考えます。 ― 社会貢献活動が日立の可能性を拓く 日立グループの社員一人 ひとりが積極的にボランティ 日立 は 2002 年、社会貢献活動を、重要 な 企業活動 ア活動に参加し、その 体験を職場や 家庭で 話し合う。 のひとつとして 捉え直し、グループ 共通 の 理念・方針 少しずつではありますが、私 たちはそのようにして、 を 策定しました。 現在、グループ 各社 は、個別 にそ 自主的なボランティア 活動 や 社会貢献活動 の 輪を広 れまで 行ってきた 活動、および 業種業態 の 特性 や 地 げていきたいと考えます。 域性を生かしつつ、理念・方針に即した内容に近 づけ るよう活動内容の見直しを進めています。 こうした動 社会貢献活動の理念と方針 きを通じて、日立はよりよい 社会 の 実現に向けて、グ 理念 ループで 一貫性 のある社会貢献活動をグローバルに 日立グループは、よき企業市民として、社会の要請と 推進しています。 信頼 に 応え、豊 かな人間生活とよりよい 社会 の 実現 に貢献します。 企業活動 の 維持・発展 がますます 厳しくなっている現 方針 代、私 たちが 今、社会貢献活動 に 力を 注ぐのは、社 「教育」 「環境」 「福祉」の 3 分野にお 日立グループは、 会に支えられている企業 の 責務としてだけではなく、 この活動が日立をより成長させ、日立の潜在能力を引 き出すと考えるためです。 いて、知識と情報技術など、持 てる資源を最大限 に 活用し、次なる時代 の 変革を担う「人」を育む活動を 中心 に、いきいきとした 社会 の 実現 のため、様々 な 社会貢献活動を推進します。 日立 は 社会とともにある企業 です。 グループ 企業 の グローバル 化も進んでいます。 そうした中で、多くの 国、地域、人々と価値観を共有していくには、対話を 重 ねながら社会 の 課題 や 要求 に 主体的 に 取り組むこ とが重要であり、その積み重ねが、ステークホルダー の皆様からの信頼につながると考えます。 社員 の ボラン ティア 活動 へ の 参加 も 重視して いま す。企業は、 「個」の集合体です。 ボランティア活動は 「個」を生 かす 場 であり、社員一人 ひとりが 社会 の 声 お客様と社会と日立 next society 23 ボランティア活動支援 ランティア 活動につながる内容 であることなどをポイ 社員一人 ひとりが、企業 の 一員としてだけではなく、 ントとして 企画し、東京 ボランティア・市民活動 セン 社会 の 一員として「個 の 充実」を図るためには、ボラ ターの協力を得て、展開しています。 ンティア活動を通して地域社会と直接触れ 合 い、さま 「社会貢献イブニング講座」は、座学でじっくりと講師 ざまな体験を積み重 ねていくことが極 めて 重要 です。 の話を聞き、考えるスタイルの講座で、毎年下期を中 そこで日立製作所では、社員がボランティア活動をや 心に数回開催しています。 りたいと思った 時 に、やりたいことを、自由 にやれる セミナー・講座 への 参加者からは「自分 たちの 特技 や ような職場の環境づくりを支援しています。 経験を、ボランティアに生かしたい 」 「 ボランティアを まず、職場 の 理解を 得 やすくするために、社会貢献 するには社会 のニーズを知ることが重要」といった感 活動 の 重要性についての 各種研修をはじめとする教 想 があがっており、それらの 感想 や 実施報告 はイン 育活動と情報発信を積極的に行っています。 具体的 トラネットで 紹介しています。 これをきっかけに、グ には、 「情報」 「時間」 「資金」の 3 つの 面 から、ボラン ループ社員の一人 ひとりがボランティア活動を身近に ティア活動支援を推進しています。 考えながら、自主的な活動の輪が広がっています。 情報 ― セミナー・講座の開講 時間 ― 休暇制度 日立グループは、グループ 社員 に、イントラネットや 日立製作所は、1993 年より、ボランティア活動などの メー ルを 活用して、積極的 なボランティア 参加 を 呼 社会貢献活動 あるいは自己啓発活動を会社としても びかけて います。 しかし 参加意欲 はあるものの「何 積極的に支援 する趣旨 で、 「特別年次有給休暇制度」 かできることはないか、情報 が 欲しい 」 「きっかけが を設けています。翌年度に繰り入れられずに、打ち切 欲しい 」といった 声もあがっていました。 そこでボラ られた 年休日数 のうち、毎年 4 日を 限度 に、最大 20 ンティア 体験機会としての「日立 ボランティア・セミ 日まで 積み 立 てられる制度「積立年次有給休暇制度」 ナー」を実施しています。気軽に参加でき、講師との もあり、年休を 使 い 果 たしてもこの 積立年休を 行使 対話 ができる程度 の 参加人数 にすること、実際 のボ し、ボランティア活動に参加することができます。 V O I C E 日立ボランティア支援プログラム 「大きくなる樹」を活用して すのもままならないのが 現状 です。 「大きくなる樹」の 助成 を 受 け、私 た ち の 団 体 は 今 身近な地域に根ざした 活動として、子どもたちと自然 のふ 後 3 年ほどの活動経費 へのメ れあいを支援 する NPO に参加しています。 職業人として ドがたちました。 中期的 な、 の自分に加え、地域人とでもいうべき自分を発見 でき、人 また 具体的 な 実行計画 を 固 生 が 2 倍にも 3 倍にも広 がっている感覚を覚えます。 あく める上 で、大きな 助 けとなっ まで無理のないスピードで続けたいと思 います。私たちの ています。 ように、主 に 会費 でまかなっているような 小規模 NPO に とっては、財源確保 は 大きな 課題 です。 保険料 や 郵送費 など、日々 の 組織運営 に 費用 がかさみ、プロジェクトを興 24 日立グループ CSR 報告書 2005 next society 紙芝居 による 子 ども向 け 環境 学習プログラムにて 日 立 オ ム ロ ン タ ーミナ ル ソ リューションズ(株) 中塚隆雄 WEB 日立グループ 6 つの財団 http://www.hitachi.co.jp/Int/ skk/hsk10000.html 資金 ―「大きくなる樹」 を 公開し、93 件 の 活動報告を 掲載しています(2005 日立 ボランティア 支援プログラム「大きくなる樹」は、 年 4 月 15 日現在) 。 日立グループ 社員が行うボランティア 活動に対 する、 このデータベースでは、国内外 の日立グループ 各社 資金面における活動支援プログラムです。 社員がボ と財団 が 取り組む社会貢献活動 について、実施 の 時 ランティアとして 積極的 に 参画、または 資金面 でサ 期 や 地域、分野、活動内容 などを 掲載して おり、グ ポートしている非営利団体に対し、活動資金を支援し ル ープ 内 におい ても、情報共有化 のツー ルとして、 ます。実際にボランティア活動を行っている社員から 活動のさらなる活性化に貢献しています。 の申請に基づき、社内選考委員による選考の上、1 件 さらにニュースレター『The Caring Tree』を年 2 回発 あたり 30 万円を上限として、半年ごとに 数件 の 支援 行し、社外も含 め日立グループの 社会貢献活動 の 情 を行っています。 報を発信しています。 活動の輪を広げていくために 日立グループの 6 つの財団 社会貢献活動データベースの公開 日立に、最初の財団が誕生したのは 1967 年。以来、 日立グループの 社会貢献活動 は、日立グループ 各社 国内外 にあわせて 6 つの 財団を設立し、社会活動 に によるもののほか、6 つの財団が継続的に展開してい 取り組んでいます。 る活動もあり、全体としては非常に多種多様な活動を 推進しています。 それは私たち日立に集う社員にとっ http://www.hitachi.co.jp/Int/ skk/[日本語] http://www.hitachi.com/ Int-e/skk/[英語] 「The Caring Tree」 http://www. hitachicontribution.com/ (財)日立みらい財団(1967 年設立) もとより、ステークホルダーの 皆様に、その 内容を伝 青少年 の 非行・犯罪 の 予防や 青少年 の 健全な育 成を支援 する事業 および 矯正施設における各種 矯正教育や福祉に関する支援事業 え、活動に対 する関心を高 めていくことも重要 です。 (財)倉田記念日立科学技術財団(1967 年設立) こうした 思 いから、インターネットに 活動 の 全体像を 科学技術の研究に対する助成および振興事業 て、誇 るべき 活動 であると考 えます。 また、社員 は WEB 日立グループ社会貢献活動 (データベース) ニュースレター 『The Caring Tree』 網羅した「日立グループ 社会貢献活動 データベース」 T O P I C S 体験を通じたきっかけ作り ナーに、延 べ 131 人が参加しました。社会貢献イブニング 日立ボランティア・セミナー 講座では、教育と環境をテーマとした講演会を開催。日本 の教育の現状と企業のサポートを考える講座では、講師の 「子どもの事故 2004 年の日立ボランティア・セミナーでは、 お話を聞くだけでなく、子ど 予防と応急処置」や「援農(農業 のお 手伝 い )ボランティア 」 もたちの 教育 に 私 たちがで などを 開催。 子どもの 事故予防 については、日本赤十字 きることに つ い て、グル ー 社 から講師を招き、乳幼児 の 応急処置などを学 びました。 プディスカッションも行 いま 援農ボランティアでは、近年その保存が叫ばれている棚田 し た。 2004 年 度 は 3 回 開 に 出向き、NPO などの 講師 の 方々 から棚田 の 現状と課題 催し、延 べ 88 人が参加しま についてのお話を伺うとともに、人手不足で 維持が困難な した。 棚田 での 農作業 のお 手伝 いを 行 いました。 計 4 回 のセミ 日立ボランティア・ セミナ ー( 援 農 ボ ランティア) お客様と社会と日立 next society 25 日立日米欧教諭交流プログラム 左:日立市 の 中学校 で 授業をする 英国人教諭 右:英国 ボルトンの 中学校 で 授業 をする日本人教諭 (財)小平記念日立教育振興財団(1971 年設立) るフォーラムです。 2004 年 は 5 月 に、スウェーデン 家庭教育および学校教育の振興事業、社会的功 労者の顕彰事業 のストックホルムにて開催。 「交通と欧州社会」をテー (財)日立環境財団(1972 年設立) 環境問題に関 する調査、研究 および 環境保全活 動の普及・奨励事業 (財)日立国際奨学財団(1984 年設立) 東南アジア 6 カ国の大学教員の日本の大学院課 程 に 対 する奨学事業、自然科学系 および 人文・ 社会科学系研究者の招聘、卒業者支援と学術交 流への助成 日立ファウンデーション(米国) (1985 年設立) 米 国 地 域 社 会 の 発 展 や 教 育 活 動 へ の 支 援。 2004 年より、経済的・社会的に疎外された人々 の生活向上に注力した 5 カ年計画を推進中 マに、スウェーデン 研究開発投資局 やロンドン 大学、 フランス国土交通省など、欧州各界の有識者やメディ アなど、総勢 107 人が参加しました。 3 日間にわたる 討議 の 内容 は、白書 にまとめ、欧州委員会 や 欧州議 会などに広く配布しました。 日立ヤングリーダーズイニシアチブ アジアの 将来を 担う、次世代 のリーダーの 発掘と育 成、ネットワークづくり、そして 地域問題 への 理解促 進を目的とし 1996 年にスタートしたプログラムです。 インドネシア、日本、マレーシア、フィリピン、シンガ ポー ル、タイのアジア 6 カ 国 の 大学 から推薦 を 受 け たリーダー 候補 たち 24 人を 対象 に、5 日間 にわたる 活動事例紹介 ― 教育分野の取り組み フォーラム、学生分科会、地域貢献活動を行っていま 日立グループは、 「教育」 「環境」 「福祉」の 3 つを社会 す。 これまでの延べ参加者は、144 人にのぼります。 貢献活動の重点分野と位置 づけています。特に教育 参加者は、プログラムに参加した経験を生かし、現在 分野 では、日立グループの 技術者 や 研究者 の 知識、 さまざまな 分野 で 活躍しています。 たとえば、1999 施設・設備、およびグローバル 企業ならではの社員の 年にフィリピンより参加したパオロ・ベニグロ・アキノ 国際経験などを十分に生かした活動を進めています。 さんは、虐待児童 への 支援活動 や 環境保護プロジェ その活動事例の一部をご紹介します。 クトに従事した 後、フィリピン 大統領府直轄 の 青少年 日立日米欧教諭交流プログラム 機関 で 人材育成に携わり、2003 年よりアロヨ大統領 教育現場 の 視察 や 体験授業などを通じて、相互理解 任命による同機関の会長を務めています。 と国際交流をめざすプログラムで す。 欧米 の 中学・ 26 高校教諭を日本 に 招聘 する一方 で、日本 からも教諭 日立ファウンデーションの地域貢献活動支援 ― 小学生への朗読プログラム を派遣し、1987 年より延 べ 199 人の日米欧教諭が参 米国ワシントン DC にある日立ファウンデーションは 加しました。 2004 年 は 16 人 が 参加。 最終日には、 創立以来 20 年にわたり企業市民活動に取り組んでき 日米欧教諭による一般公開の教育フォーラムを実施し ました。 この 活動 は 設立当時よりもますます 重要性 「自ら考える力を 育 てる教育」をテーマに、討論を 行 が高まっています。 これまで 3 つの事業を展開してい いました。 ます。 経済的・社会的 に 疎外された 米国人 の 生活向 EU 日立科学技術フォーラム 上をめざす 活動を支援 する助成事業、米国 の 高校生 欧州社会 が 抱える問題 に 対して、科学技術 がいかに がコミュニティ活動において 発揮した優 れたリーダー 貢献できるかという視点で 1998 年から毎年行ってい シップに対して 贈る吉山賞(現相談役 の 吉山博吉 の 寄付 日立グループ CSR 報告書 2005 next society EU 日立科学技術フォーラム ロンドン 大学 の 教授 による IT を 通じた 交通 諸問題の改善に関する基調講演 日立 ヤングリーダーズ イニシアチ ブフォーラムにて質問する 日立ファウンデーション 吉山賞授賞式(米国) 日立アメリカ・日立ファウンデーション 朗読会に参加した子どもたち(米国) アキノさん により創設 ) 、北米日立 グル ープ 各社 が 拠点・地域ご 性を展望 する記念誌を発行、地域 の 子育 て 支援セン とに 組織 する地域活動委員会と連携して 寄付を行う ターや各種教育機関などに配布しています。 マッチング・ファンド・プログラムです。 また、日立 の グループ 会社と連携した活動例として、日立アメリカ 2004 年度の災害支援活動 が 2000 年より毎年開催している地元 ニューヨーク州 2004 年 は 大きな自然災害に見舞 われた 一年 でした。 タリータウンの小学一年生に向けた、本の朗読プログ 日立グループは、社会インフラの 構築・整備事業に携 ラムがあります。 2003 年は、ジョン・ホールディング わる企業として災害時は、電力、情報システム、産業 小学校を 対象 に、10 月 から翌年 5 月までの 期間 に、 機械、家電などを担当する各社員が、それぞれの立場 月一回 の 朗読会を実施。 異文化や 許容性、友情など でインフラの 維持に向けて 動 いています。社会 への のテーマに、児童 たちは、毎回熱心 に 話 に 耳を 傾 け 責任を自覚し、自ら動き出す風土は、日立の誇りです。 ていました。 教育分野への支援プログラム 日立グループの 持 つ 知識 や 技術を社会に還元 するこ とを目的 に、2004 年度 から始 めたプログラムで す。 日立の強みを生かした「ユニバーサルデザイン」と「IT 教育」の 2 つのテーマに、約 50 人 の日立グループ 社 員がボランティア 登録しており、その 中から、小学校 の 総合学習 や 学校 の 教諭 のサポートとして、講師を 新潟県中越地震(2004 年 10 月 )では、被災地域 に日 派遣しています。 立 のエレベーター、エスカレーターは 5,500 台ありま 日立家庭教育センター 30 年間の実践 したが、状況を即座 に 把握し、故障した 10 台 は 即日 昨今、家庭を取り巻く社会的・文化的状況は、激しい 修理しました。支援活動としては、義援金・救援物資 変動 の 中にあり、家庭 の 持 つすぐれた 教育的基盤 が のほか、被災者 の 生活面支援 のための 家電品 や、災 損 なわれ、保護者 の 育児 ストレスや 子どもの 虐待 な 害ボランティアセンターの 情報管理用 パソコンなどを ど、子どもたちの 健やかな発達がむしばまれる事態も 寄贈しました。 また心のケアとして、日立交響楽団の しばしば 起こっています。 (財)小平記念日立教育振 ボランティアが被災地に赴きオーケストラによる演奏 「日立家庭教 興財団 は、この 課題 にいち早く着目し、 を行いました。 育 センター(日立市 )」と「日立家庭教育研究所( 横浜 2004 年 12 月に 発生したインドネシア・スマトラ 島沖 市) 」を設立。 2004 年 で 30 周年を迎えた 同センター 大地震 では、世界各拠点 の日立グループ 企業 が災害 は、 「子育 て 」と「親育ち」を支援 する幼児教室と母親 義援金を提供したほか、被災国 で 事業を展開してい 教室を 開催し、子どもたちの 人格形成 に 必要 なもの る日立グループ 各社 が 結束して、被災国支援を行 い は何かを、保護者とともに真剣に考えてきました。教 ました。 インドネシアでは、日立建機グループが建設 室に 訪 れた 親子 は 4,500 組にも及 んでいます。 これ 機械の無償供与とオペレータの派遣を行うなど、被災 までに果たしてきた役割と意義をまとめ、今後の方向 地の状況に応じた支援を実施しました。 左:日立交響楽団による小学校 訪問(新潟県川口町) 右:日立建機グループによるス マトラ島沖大地震復興支援 WEB 日立グループ スマトラ島沖大地震・ インド洋沿岸大津波に対する 支援の概要 http://www.hitachi.co.jp/ information/support_1229/ お客様と社会と日立 next society 27 株主・投資家の皆様へ 日立製作所および日立グループは、株主・投資家の皆様の期待に応えるべく、 グループシナジーを拡大させ、グループ総合力をさらに発揮させていくことをめざしています。 そのための企業活動の核となるのが、CSR であると考えます。 また、将来の中核事業の開拓を目的とした先端研究や 日立グループ全体の生産性と開発スピードの向上を目的とした基盤研究の強化を図っています。 ガバナンスの強化によるグローバル経営へ 正確な情報をタイムリーに 日立製作所 および 日立 グル ープ 18 社 は、経営 のス 日立グループは、情報システム、社会インフラからコ ピードアップと透明性の確保を目的に、2003 年 6 月、 ンシューマー 製品、高機能材料、金融 サービスと事 「委員会等設置会社」 (P.8 参照 )に 移行しました。 加 業内容 が 幅広 いことから、株主・投資家 の 皆様 への えて、業務 が 適法かつ 効率的に行 われるための 社内 IR 活動においては、現在 の 経営状況と将来性をタイ 体制を再点検し、グローバルな事業環境において、よ ムリーに、かつ 公正・公平に、そして 正確にお 伝えす WEB り透明性 の 高 い 経営 の 実現を図っています。 グルー ることが、何よりも重要であると考えます。 日立製作所 株主・投資家向け情報 プ 経営 の 観点 からグループ 全体 でのガバナンスの 整 そのほか、日立製作所をはじめとする各上場企業 に 備と強化を進めています。 おいて、アニュアルレポートや 有価証券報告書による 日立 製 作 所 は 、2002 年 7 月 に 成 立 し た 米 国 企 業 財務状況を中心とした情報開示を行っています。 (注 1)の 適用を受ける米国 SEC 改革法(以下 SO 法) 国内外 の 機関投資家などの 皆様には、定期的な事業 ( 証券取引委員会 )登録企業 とし て 、2004 年度 より 戦略説明会 や、研究開発 インフォメーションミーティ 日立 グル ープ 全体 で の 内部統制 の 見直しと 再構築 ングなどを開催しています。 また、決算発表日当日に を、COSO フレームワーク( 注 2)に 基 づき 行ってき 開催している機関投資家・アナリスト向け 説明会の模 ました 。 様は、翌日にはホームページ上で公開しています。 2005 年 3 月末までに日立製作所を含むグループ会社 さらに 2004 年度 からは、研究開発、特許・ブランド 約 230 社において 内部統制 の 文書化をほぼ 終え、今 などの知的財産についてまとめた形で 報告 するため、 後 はそれを用 いた 運用体制 の 整備と経営幹部・社員 「研究開発及 び 知的財産報告書」を発行しています。 PAGE 「委員会等設置会社」 ⇨ P.8 参照 http://www.hitachi.co.jp/IR/ WEB 「研究開発及び知的財産報告書」 http://www.hitachi.co.jp/ about/strategy/ip/ 注 1:SO 法=Sarbanes-Oxley Act の略。2002 年 7 月に制定。 同法の 404 条は、経営者に対し て、財務報告 に 関 す る 内部統 制 の 構築・維持 の 責任 を 課し、 同時に外部監査人による評価を 要求して い る。 具体的 には 連 結 で の 財務報告 に 対 する 信頼 性を確保 するためにグループ全 体での対応が求められる の教育・訓練に重点的に取り組んでいきます。 本報告書を通じて、日立グループの研究開発および知 的財産を重視した取り組みを、ステークホルダーの皆 CSR を核に日立グループ全体での成長を 様にご理解いただきたいとの考えから発行しています。 日立グループは 、次 の 100 年を視野 に、私 たちが 果 こうしたさまざまな取り組 みは、経営環境 が 激しく変 注 2:COSO フレー ムワーク= たすべき社会的責任に応えていくために、CSR とい 動 する中 で、株主 や 投資家 の 皆様 に、より正確 な 経 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission う視点 を 核 にした 、さまざまな 改革 に 取り組 んで い 営状況をご理解いただくために行っているものです。 (米国トレッドウェイ委員会組織 委員会)により提唱され、現在 大多数 の 米国企業 にお い て 採 用されている内部統制システム 注 3:FIV(Future Inspiration Value)=税引後事業利益 から 資本コストを控除した 経済的付 加価値をベースにした日立独自 の 付加価値評価指標。 黒字化 を実現 するためには、資本コス トを上回る利益が必要 ます 。 まず、2003 ∼ 2005 年度 の 3 年間を、経営 の 質 の 転 株主総会 換を図る期間と位置 づけ、FIV(注 3)の黒字化をめざ 日立製作所 では、定時株主総会において、株主 の 皆 した 事業構造 の 大幅な変革と、事業 の「選択と集中」 様に日立の営業の状況をより深く理解していただくた による、ポートフォリオの 再構築を行っています。 ま めに、さまざまな映像を用 いた営業報告を行っていま た、社会 に 貢献し、将来 の日立を 支える新事業 の 創 す。 経営課題 については、社長 がプレゼンテーショ 出・育成に力を注いでいます。 ンを行って報告しており、その内容は、株主総会終了 後 の 一定期間、ホームページに 掲載しています。 ま た、2002 年 6 月の 株主総会より、インターネットによ 28 日立グループ CSR 報告書 2005 next society 上:機関投資家、アナリスト向 け、情報・通信事業戦略説明会 下:決算発表後に開催される機 関投資家・アナリスト向け説明会 [株主構成の推移(%)] その他の法人 平成 15 年 3 月 金融機関・証券会社 個人 外国人 36.83 30.44 29.38 3.34 政府・地方 公共団体 0.01 4.92 0.01 平成 16 年 3 月 30.62 29.79 34.66 平成 17 年 3 月 27.90 31.67 36.47 3.96 0.00 る議決権行使システムを導入しています。 SRI など 2004 年度の外部評価結果 企業を CSR の 視点 で 評価し、投資ファンドの 銘柄選 定に活用する SRI(社会的責任投資)の手法が活発化し ています。日立製作所 は、SAM 社 が 評価 する DJSI (ダウジョーンズ・サステナビリティ・インデックス ) ( 注 4) それぞれの 環境、社会貢献などの 取り組 み 姿勢 が 評 に お い て、5 年連続 で 推奨銘柄 に 選定 されました。 「社会的責任経営 の 進 んだ 企業」として 選定 価され、 ( 注 5) EIRIS 社による「FTSE4Good Global Index」 されました。 では、グループ 会社 6 社 が 対象銘柄 に 選定されまし 評価機関 の 求 める項目は 社会 が求 める客観的指標と た。 モー ニングスター SRI インデックスで は、ガ バ 捉 え、日立グループは、その 真意を 探求したいと考 ナンスの 取り組 み、社会貢献活動、環境 の 独自指標 えます。 また、自己評価 の 指標として 活用 するととも などからランク「A」の「社会性 に 優 れた 企業 150 社」 に、グループ全体での改善に努めています。 注 4:DJSI(Dow Jones Sustainability Index)= ダ ウ ジョーンズ 社(米国)と SAM 社 ( ス イス )が 開 発した 経 済・環 境・社会面の評価指標 注 5:FTSE4Good Global Index = FTSE 社( 英 国 )が 開 発した指数で、特定業種の排除 後に環境・社会・人権で評価 に評価され、日立グループとしても 6 社 が 選 ばれまし た。日本総研 が 行った「CSR 経営 の 動向に関 する調 査」においては、日立製作所 およびグループ 7 社 が、 [2004 年度の主な外部評価結果の詳細] SAM 評価機関 EIRIS パブリックリソースセンター 日本総研 評価指標 DJSI FTSE4Good Global Index モーニングスター SRI インデックス 「CSR 経営の動向に関する調査」 評価結果 推奨銘柄に選定 推奨銘柄に選定 SRI 構成銘柄に選定 「社会的責任経営の進んだ企業」に 選定 選定社名 日立製作所 日立金属、日立マクセル、 日立ハイテクノロジーズ、 日立化成工業、 日立キャピタル、 日立ソフトウェアエンジニアリング 日立製作所、 日立金属、日立建機、 日立マクセル、 日立ハイテクノロジーズ、 日立物流 日立製作所、 日立金属、日立化成工業、 日立キャピタル、日立建機、 日立ハイテクノロジーズ、 日立情報システムズ、日立マクセル 株主・投資家の皆様へ next society 29 調達先(サプライヤー)とともに 日立グループは、世界中の企業から、さまざまな原材料、部品、サービスを調達しています。 そのすべての活動において、調達先(サプライヤー)企業と対等な立場で行動し、 かつ互いの企業活動を発展させることをめざしています。 この視点から、サプライチェーンにおける環境保全に向けた活動をはじめ、 CSR の共有化にも取り組んでいます。 WEB 基本はパートナーシップとオープンドア 「環境保全活動」 「社会貢 具体的 には「人権 の 尊重」 調達先との関係において、まず重要なのは、強いパー 献活動」 「働きやすい 職場 づくり」などを尊重 すること トナーシップであると日立は考えます。日立グループ を、調達先の選定理由のひとつと位置づけています。 は、相互理解に 基 づいた 対等な立場 での 取引を行う この 徹底には、調達先各社に、CSR の 重要性を理解 ことで、調達先との 信頼関係を築 いています。 調達 してもらうことが不可欠です。 まず日立の購買担当の 先 の 選定については、オープンドア、つまり国内・国 基礎教育に、CSR のカリキュラムを取り入れ、社員の 外を問わず、自由な競争の原則に立つことを基本とし 周知・徹底を図るとともに、機会 あるごとに調達先に ています。 その 際、資材 の 品質、価格、納期、経営 CSR 方針を説明 するほか、インターネットなどでも情 の 信頼性や 技術開発力についての 十分な評価と適正 報を公開しています。日立グループが、グループをあ な手続きをもとに選定しています。 げて CSR 推進に取り組んでいる意思を理解 いただき 日立製作所 は、取引 の 基本となる「購買取引行動指 ながら、ともに実践する「協働」をめざしています。 日立グループ資材調達 http://www.hitachi.co.jp/ procurement/ 針」を 制定しています。 平等 な 取引機会 の 保証、対 等な立場 での 取引、話し合 いに 基 づく公正な取引条 品質管理と VEC 活動 件、取引上 の 立場を利用した 不当な要求を行 わない 日立グループは、高 い 信頼性と高品質な製品・サービ こと、購買取引において 知り得 た 情報 の 厳格な管理 スを提供していくために、調達先に対しても品質やコ などを明記した指針 です。 これに則り、公平・公正な ストの継続的な改善をお願いしています。 調達活動を行っています。 使用 する材料・部品 の「選定」から「受け 入れ 」にいた るまで、要求される特性・品質を確保 するための評価 PAGE 「CSR の自己評価」 ⇨ P.6 参照 サプライチェーンにおける CSR の協働 試験や検査を実施しています。 日立は、調達先とともに発展 するビジネスモデルを築 また、製 品 や サ ービ ス の も つ 機 能 を、より 高 い パ くには、CSR の 共有化 が 不可欠 であると考 えます。 フォー マンスで お 客様 に 提供 できるよう、設計・材 日立製作所 が 行った CSR 活動 の自己評価(P.6 参照) 料・加工など、あらゆる面から改善を図る活動、VEC からサプライチェーン( 調達関連 における連鎖 )におけ (Value Engineering for Customers)活動を行っていま る CSR 方針 や 教育などに、十分 でない 分野 があるこ す。 それぞれの 分野 の 専門家・知識を動員 する総合 とが判明しました。 「日立グループ CSR 活動取り組み 活動 で、調達先に対してもこれを共有化 することで、 方針」の策定を機に、サプライチェーンにおける CSR 同時 に 調達先 の 技術開発・新製品開発 に 役立 つこと の充実に向けて、2005 年 4 月、 「購買取引行動指針」 を期待しています。 に、CSR の 視点に基 づいた調達活動を行う旨を明記 しました。 30 日立グループ CSR 報告書 2005 next society グリーン調達の推進 その活動の証として、2006 年度末までに、ISO14001 日立グループでは、環境負荷 のより少ない 素材 や 部 などの外部環境認証を取得していただき、グリーンサ 品を調達 する「グリーン 調達」を継続的に実施してい プライヤ ー 率( 注 2)100% の 達成 を目標として いま ます。 その 際、インターネットを活用した自社開発グ す。 しかしながら調達先 の 大半を占 める中小規模 の リーン調達システム「A Gree’ (注 1)にて、環境 Net」 企業 では、環境保全活動をするにも、費用 や 制度整 保全活動の 取り組み状況や 納入資材 の 環境対応につ 備など、仕組 みづくりにさまざまな困難 が 伴ってしま いて、調達先に情報開示を依頼しています。 2004 年 うのも事実です。 度 の 情報開示状況 は、約 5,000 サイトの 調達先 から 約 60,000 点の部品について開示がありました。 この 情報 は、設計支援システムや 資材調達システムなど と連携して、環境に配慮した製品の開発やグリーン調 達の拡大に活用しています。 [HI-KES とは] 仕組み 運用 EMS 構築 日立グループの ノウハウを伝える HI-KES 認証取得 「Hi-Green セミナー」 の受講 情報 の 共有化として、環境負荷低減 の 事例を紹介 す る 定期情報誌「 グリーン 調達部品 ニュース 」の 配信 そこで、2003 年 10 月、 「日立認証制度」を 制定し、 や、環境に配慮した部品を展示 する「グリーン調達部 従来 の ISO14001 に 加え、中小企業対象 に KES( 注 品展示会」を開催しています。 2004 年 の 展示会 は 5 3) ・エコステージ( 注 4) ・エコアクション 21( 注 5)の 月に開催し、60 社の参加を得ました。 環境認証も ISO14001 に 準 ずる仕組 みとして 採用し 今後は、RoHS 指令*などの有害化学物質規制対応に ました。 さらに、2004 年 4 月、KES と協働活動 のか 加えて、減量化、長寿命化、再資源化、分解性、処理 たちで HI-KES( ハイ・ケーイーエス )登録制度を 導入 容易・省エネルギー性など幅広い 視点で、環境保全か しました。 HI-KES は、KES 認証取得後 に 日立独自 ら、持続可能性の革新に向けた製品づくりをめざし、そ の 環境セミナー(Hi-Green セミナー)を受講していただ のための情報の共有化と活用促進に努めていきます。 くシステムで、中小規模 の 企業 の 視点 に 立 ち、費用 が少なく取り組みやすく、かつ 最終的には ISO14001 グリーンサプライヤー率 100% をめざして をめざすことを基本としています。積極的なコンサル 製品のライフサイクル*全体における環境負荷の低減 ティング活動 が特徴 で、認証取得した調達先からは、 は、日立グループはもとより、ビジネスパートナーで 具体的なアドバイスが製造コスト削減など、経営改善 ある調達先も含め全体で協力 することによって、初め にも役立ったとの声が寄せられています。 て 実現 することができます。日立 は 主要な調達先 す 2004 年度末時点では、累計 43 社が KES 認証に取り べてに対し、環境保全活動の定着を進めています。 組んでおり、今後も積極的に拡大していきます。 注 1: 「A Gree’ Net」=取 引 先 企業 の 環境保全活動 や 調達品 に含まれている化学物質情報な どの環境関連情報について、イ ンターネットによって 情報収集 する自社開発システム 注 2:グリーン サプライヤ ー 率 = EMS(Environmental Management System) を構築済 み、または、構築中取 引先数÷主要取引先数(取引総 額 90%相当) 「 京( み やこ )の ア 注 3:KES = ジェンダ 21」によって 推進 され ている環境マネジメントシステム 注 4:エコステージ=エコステー ジ 協会 で 推進して い る 環境経 営 の 支援を目的とした評価シス テム 注 5:エコアクション 21 =環境 省が作成した環境活動評価プロ グラム 調達先(サプライヤー)とともに next society 31 日立を支える社員 日立が創業以来、大切に育んできた考えに、 人を大切に、また人と人のつながりを大切にすることがあります。 社員と社員のつながりと、一人ひとりの意欲が日立を支えてきました。 日立製作所は、社員一人ひとりの意欲に応える、より働きやすい職場環境をめざし、 2000 年よりさまざまな改革を行い、職場環境の整備を進めています。 働きやすい職場づくりへ、3 つのキーワード ドバックプログラム」を実施しています。 日立製作所 は 近年、さまざまな 改革を 進 めています 評価をもとに対象者 はワークショップに参加し、専任 が、変化 の 中にあってより重要となるのは、時代に対 ファシリテーター(進行役)のきめ細かな解説を受けな 応した「人」の 育成と、優れた人材 が存分に才能を発 がら、自らの 強 みや 改善 すべき点 について 認識 する 揮 できる職場環境 の 整備と考えます。 そこで、次 の というプログラムです。 また、プログラムにある能力 3 つのキーワードを中心とした、風土改革を進 めてい 開発計画 の 実行により、リーダーシップやマネジメン ます。 まず、率直 なコミュニケーションにより、社員 ト力のブラッシュアップを図ることができます。 なお、 が存分に才能を発揮 できる「オープン 」 。 次 に 高 い目 このプログラムは能力開発のみを目的にしています。 。 そして 標・変革 へ 挑戦 するという「チャレンジング」 現場主義 ― 社長と社員のコミュニケーション 多様な個性 が輝く「ダイバーシティ」 。 これを反映し、 組織が大きく成長すればするほど、一人ひとりの個性 2004 年度 は、特 に 人事処遇制度、勤務制度、年金 が大切となり、また個が輝く 「現場」の力が、より重要 制度の改革に力を注ぎました。 となります。 「庄山 オンライン 」は、現社長 の 庄山悦彦 が 就任した WEB オープン 1999 年以来続 けている、社員とのコミュニケーショ 人事処遇制度の改革 ン ツ ー ル で す。 イントラネット上 に て、社長 がメッ 社員一人 ひとりのやる気と能力を最大限 に 引き出 す セージを発信し、日立製作所をはじめ、グループ会社 ために、各人 の 実力 や 成果を 公正 に、また 透明性を の 社員 からメールで 意見 や 要望を 受 け 付 け、これに もって評価し、資格格付や 賃金、賞与といった処遇に 答えています。 反映 する人事処遇制度を導入しています。 この 制度 また、社長自ら率先して工場、事業所、グループ会社 においては、評価の要素、基準、方法をオープンにし など 多くの「現場」を訪 れ、対話と意見交換を図って た 上 で、評価 する者と評価を 受 ける者とが、一対一 います。 2004 年に訪問した 現場 は 40 カ所以上にの の面談を通して、評価に関 する認識を一致させるとと ぼります。 社長 にとっても社員にとっても、こうした もに、強 みや 改善 すべき点などをフィードバックする 直接対話 がもたらす 刺激と収穫は、たいへん 大きく、 ことで、次期 の 業務目標達成 や 能力開発に 向けた 指 「トップダウン」だ 地道なコミュニケーションの蓄積が、 導が行われる仕組みとなっています。 けではなく、社員一人 ひとりの「ボトムアップ」の 姿勢 また、制度 が正しく理解されているか、定 められた通 にもつながっています。 り面談が実施されているかなどについて、毎年実施し 全社員への意識調査 ている社員 の 意識調査において 実態を把握し、制度 日立製作所 は、2001 年 から、全社員( 約 4 万 1 千人 ) の適正運用に向けたフォローアップを行っています。 を 対象 に、意欲 やマネジメント実態 などにつ い ての 管理職層のブラッシュアップ制度 意識調査「ビジネスプロセス & オピニオンサ ー ベ イ 日立製作所 人事制度紹介 http://www.hitachi.co.jp/ recruit/institution/ 32 2003 年度より、課長相当職以上 の 管理職層( 約 1 万 (B.O. サー ベイ)」を 年 1 回、実施して います。 イント 人)を対象に、リーダーシップやマネジメント力の向上 ラネット上 で 展開し、社員は自分 のパソコンから回答 を目的に、上司・同僚・部下による評価「360 度フィー を行 います。 社員 の 生 の 意見を聞き、職場 における 日立グループ CSR 報告書 2005 next society [キャリア開発支援プログラム体系図] 30 歳 入社 40 歳 45 歳 新入社員向け キャリア開発支援 50 歳 新入社員教育 内定者 メールメッセー ジ キャリア・チャレンジ・ サポート・プログラム 対象:45 歳以上の管理職 全員受講 対象:30歳代 技師・主任・研究員 対象:40∼45歳 管理職 日立ライフプラン研修セミナ 選択型メニュー キャリア開発ワークショップ 多様な働き方に関するセミナ 社外転身サポートプログラム グループ公募制度・社内 FA 制度 問題点などを分析し、その結果は、一人ひとりの意欲 事業所階層別教育 に応える組織・制度改革に活用しています。 キャリア相談室(本社地区) チャレンジング たとえば「去 る職場を 思うと心配もありましたが、杞 キャリア開発の支援 憂でした。何より人脈が 2 倍に広がったのが良かった」 日立は、社員のキャリア開発を重視し、力を注 いでい 。そ 「入社時 のような緊張感。 気 が 引き締まります 」 ます。 キャリア開発においては、個人の意思・目標と、 して「本当にやりたい 仕事 は 何かもう一度考える、良 会社からの要請との「意思のすり合わせ」が重要です。 いきっかけとして、使ってほしい 」など。 こうした 声 方向性が一致し双方が納得することで、個人と会社の が、異動のアドバイスとなっています。 成長をともに実現することが可能になります。 また、社員自らが 直接異動を申請 できる「社内 FA 制 日立製作所は、そのための支援を「キャリア開発支援 度」を 2003 年度より導入しています。 2004 年度 は プログラム」として 展開しています。 その 代表的なプ 85 件の応募があり、41 人の異動が実現しました。 ログラムに「キャリア開発ワークショップ」があります。 発明報奨制度の刷新 1 泊 2 日または 2 泊 3 日の 合宿 で、社員は自らの 得意 日立では、約 1,200 人 の 博士をはじめ、さまざまな部 分野や価値観、意思・意欲を分析し、自己理解を深め 門の人材が、最先端の研究開発活動を行っています。 た上で、自らがめざす 将来像に向けたキャリアプラン その 活動をより活性化し優 れた 発明を 数多く創生 す ニングを行 います。 このワークショップを通じ、自分 ることを目的に、2004 年 3 月に発明管理本部を設置 の 意欲、働きがい、生きがいを確立し、仕事を通じた し、研究者 や 技術開発 の 第一線 で 働く社員 の 意欲を 自己実現 や 成長を 図 ることのできる人材育成を 行っ 高揚する施策を実施しています。 ています。 2002 年 10 月 の 開始から延 べ 1,400 人 が 2005 年 4 月 から施行された 改正特許法 35 条を踏ま 参加しました(2005 年 3 月現在)。 え、発明報奨制度を 社員 の 意見を 取り入 れながら改 人材 の 活性化と、適正配置を図るための 制度も整え 訂し、報奨の内容を具体的に開示しました。 それによ ています。自分の意思・意欲を異動というかたちで直 り、透明性と納得性の高 いものへと刷新しました。 こ 接的 に 実現 する手段として、募集業務を公開し社員 の 施策 では、特許 の 事業 への 活用について、発明者 自らが応募 する「社内公募制度」を 1991 年より導入。 が申告 することにより、事業部門との間で対話ができ 2004 年にはその 対象をグループ 会社に拡大した「グ る発明情報システムを導入しています。 今後も制度 ループ公募制度」へと発展させました。 グループ公募 の改善を継続しながら、社員の意欲向上を支援し、優 制度 では、2004 年 4 月からの 約 1 年間 で 延 べ 434 人 れた発明を数多く生む環境づくりを進めていきます。 の応募があり、 56 人が実際に希望の職場に移りました。 e ラーニングシステムによる能力開発 1991 年からの累計では、すでに 300 人以上がこの公 自発的 な 能力開発を 支援 する仕組 みとして、日立製 募制度を活用しています。今後さらに、制度を理解し 作所 は、ソフト開発 にお い てもてるノウ ハウを 活用 活用してもらえるように、利用者 の 声をイントラネット し、独自の e ラーニングシステム「Hitachi-Learning で紹介しています。 Gate」を 開発しました。 利用範囲 は、順次、日立グ 日立を支える社員 next society 33 e ラーニングシステム「Hitachi-Learning Gate」 PAGE ループ内に拡大し、現在では約 20 万人が利用してい 全面的に支援しています。 現在、正規保育 の 園児 は ます。 25 人、一時保育 では 4 人 が 利用しています(2004 年 この中で、コンプライアンス意識の向上をめざした学 4 月現在)。 習 は「e-Audit」と 名 づ け、倫理教育、情報 セキュリ また、障害者雇用(P.17 参照 )については、健常者と ティ、個人情報保護、輸出管理、環境などのテーマに 障害者 の 壁をなくすノーマライゼーション(注 1)の 考 ついて、社員がいつでも学習できるよう教材を提供し えに立 ち、意欲的に障害者 の 雇用と職域 の 拡大に努 ています。 たとえば 2004 年 9 月から開始した「情報 めてきました。具体的な取り組みとしては、養護学校 漏洩の防止」については、約 54,000 人が受講しました の 学生を 研修生として 受 け 入 れたり、車 いすに 対応 (2005 年 2 月現在 )。 今後 は、各分野 のテーマの 内容 したバリアフリー 化を進 めるなど、さまざまな施策を を拡充するとともに、学習者の理解度を高め、社員の 行うことにより、現在 の 雇用率 は 1.88% となってい 日常業務の中での実践的な行動により役立 つように、 ます 。 「障害者雇用」 ⇨ P.17 参照 注 1:ノーマライゼーション=障 害者に、すべての人がもつ通常 の 生活を送る権利を可能な限り 保障 することを目標に社会福祉 を進めること 積極的な活用を促進していきます。 [障害者雇用率] ダイバーシティ 「F.F. プラン」の導入と障害者雇用の促進 個性豊かな多様な人材 は、日立 の 財産 です。日立製 「ジェンダー・ 作所 は 多様性を 尊重し、2000 年 3 月、 フリー & ファミリー・フレンドリー・プ ラン(F.F. プ ラ (人) 1,350 1,311 1,300 1,250 1,200 1.82 1,150 1,100 1,050 1,000 ン) 」を社内外に発表。個を尊重した性別を意識しない 950 (ジェンダー・フリーな)人材活用と、仕事と家庭 の 両立 900 (%) 2.0 1,249 1.88 法定 雇用率 1.82 1.80 1.76 1,007 1.66 850 を支援し社員が働きやすい(ファミリー・フレンドリーな) 800 環境の整備に取り組んできました。 750 2003 年には、日立製作所労働組合 が、同ソフト支部 650 (2005 年 3 月) 1.5 731 700 労働会館内 に、日立グループ 社員用 の 託児所「 ゲン [男女雇用比率(%)] 822 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 6月 6月 6月 6月 6月 木くらぶ 」を開設し、運営しています。 その 運営にあ ニーズにあわせた福利厚生制度 たっては日立製作所と近隣 の日立グループ 19 社 が、 個人のライフスタイルの多様化に対応するために、福 利厚生 のあり方 に 対 する見直しも進 んでいます。日 [2004 年度男女別新卒採用者数(%)] 女性 立製作所 では、住宅融資制度 や 財形貯蓄制度といっ 女性 13 た 既存 の 福利厚生制度 に 加えて、2000 年度、 「必要 女性 18 12 な 人 に 必要 なサービスを 提供 する」という視点 を 基 女性 44 男性 87 男性 82 男性 88 男性 56 本 にした「カフェテリアプラン 制度( 選択型福利厚生プ ラン ) 」を 導入しました。 会社 が 用意した 福利厚生 メ 理工系 合 計 34 日立グループ CSR 報告書 2005 next society 文科系 ニューを、社員一人 ひとりが 一定 の 持 ち 点 の 範囲内 [労働災害度数率(100 万時間当り)] (%) 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 で、個々 のニーズにあわせて自由 に 選択して 利用 す 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (年) ※全産業、製造業、電機は、休業 4 日以上の度数率。 日立は、休業 1 日以上の度数率。 ることができる仕組みです。 これにより、より適切な 社員の支援が可能になりました。 全産業 製造業 電 機 日 立 とを 基本姿勢とし、常 に 高 いレベルの 安全衛生水準 [育児介護休職取得者数・短時間勤務利用者数] 育児休職取得者数 男性 1 人、女性 209 人 介護休職取得者数 男性 6 人、女性 5 人 短時間勤務利用者数 男性 0 人、女性 81 人 (2004.4 ∼ 2005.3) の維持と、一層の向上に努めています。 長年 の 安全衛生活動を通じ蓄積してきた 管理・教育・ 設備・環境に関 する知識や 経験、提案を「安全衛生ナ レッジ 」として活用し、将来に向け伝承していくととも に、労働安全衛生マネジメントシステムの導入を柱に 企業年金の見直し 展開しています。 企業年金 は、社員 の 老後生活を支える主要な柱 のひ 社員 の 健康確保 については、健康相談窓口を設 け、 とつであり、今後、ますます 重要な役割を担うものと 専門医を確保 するとともに、産業保健スタッフと連携 考えられます。日立製作所 では、近年、雇用 の 流動 をとり、積極的に社員の健康増進を支援しています。 化 や 社員 の 意識変化、法的枠組 みの 変更といったさ また、2003 年 4 月から、社員が抱えるさまざまな悩み まざまな環境変化を踏まえて、退職金・年金制度 の抜 や 心配事などの 解決を支援 する「EAP(注 2)相談」を 本的な見直しを行 い、2001 年には、他社に先駆けて 開始しました。 社内 に「EAP センタ」を設置 するとと 確定拠出年金制度を導入しました。 もに、EAP の 社内専門家 が 事業所に 出向き、面談 や 日立 の 確定拠出年金制度 は、社員一人 ひとりに 退職 電話・オンライン 相談 に 応じています。 EAP の 面接 後 の 生活設計 への 主体的な取り組 みを促し、自立意 結果 は、個人 のプライバシーを 保護した 上 で、経営 識を 醸成 することを目的としています。 社員個人 に 層にフィードバックされ、職場改善 の 提言として 活用 とっても、会社制度 の 枠組 みの 中 で 安心して 資産運 されています。 注 2:EAP = Employee Assistance Program の略。 社員の心理的、身体的、社会的 サポートを目的にしたプログラム 用 の 経験を 積むことができるほか、一定 の 範囲内 で 年金受給開始時期を選択し、各人のライフプランに応 じて 退職後 の 資金計画を立 てられるといったメリット があります。 HIV / AIDS に対する基本的な考え方 日立製作所 は 次 の 3 点 を 基本的 な 考 え 方 と 定 め、 1995 年よりグループ内で展開しています。 2003 年 には、さらにキャッシュバランスプラン(確定 「社員一人一人 の (1)HIV / AIDS の 最重要課題 は、 給付企業年金制度)を導入し、年金受給における選択肢 HIV / AIDS に対 する正しい 知識と理解を培う事 であ をより一層拡大し、あわせて仮想で個人口座を設ける ことで 本人持分を 明確化し、在職中 からの 意識喚起 を促しています。 る」との理念により啓発活動を積極的に推進する。 (2)感染者 が顕在化した場合には、本人 の 人権尊重 を第一義 に 考えるとともに 発症 の 遅延 に 配慮し対応 する。 (3)定期健康診断等社内で行う法定及 び 法定外健康 社員の安全を確保するために 診断における一律的な HIV / AIDS 検査は、本人のプ ライバシー保護の観点からこれを行わない。 社員 の「安全と健康を守ることは 全 てに優先 する」こ 日立を支える社員 next society 35 next society 2005年度の活動計画 持続可能な社会のための一歩として 「日立グループ CSR 活動取り組み方針」の周知徹底 2005 年 3 月に策定した「日立グループ CSR 活動取り組み方針」をグループ・グローバ ルに展開します。 グループ 全社員 34 万人を対象に、深く浸透させることにより、すべ ての事業活動がこの方針に基づき実践される仕組みを構築します。 「CSR3 カ年ロードマップ」の策定 日立グループ全体としての CSR 活動の計画「CSR3 カ年ロードマップ」を策定します。 グループプラットフォームの整備・活用 グループシナジーを 最大限 に 発揮していくために、組織を 横断したグループプラット フォームを充実させ、 「 ベストプラクティス」の 共有と、課題に早期対応できる体制を整 えていきます。 重点施策分野への対応 重点施策分野として「人権」と「サプライチェーン・マネジメント」に注力し、グローバル にこの活動を強化します。 「日立グループ CSR 活動取り組み方針」 「サプライチェーン・マネジメント」においては、 の調達先との共有化と、実施状況をモニターする体制づくりをグローバルに進めていき ます。 「人権」においては、グループ 共通 の「CSR ガイドブック」を 作成し、それをもとにグ ループ・グローバルに展開するとともに、地域や業容に応じた深化を図ります。 ステークホルダーとの情報共有 海外も含 めた日立グループの CSR の 活動状況について、報告書などを通じた 情報発 信と、ステークホルダーとの対話を継続して実施します。 next society 日立グループの環境活動 日立グループは環境経営を実現するために、 「環境ビジョン」を策定し、 「グリーンコンパス」を軸に活動を広げています。 また、 「日立製作所 環境保全行動指針」を全社に展開し、 2010 年に向けてのロードマップ「エコバリュープラン 2010」を基に、 これに則った年度行動計画を立案しています。 各活動内容は、点数評価システム「GREEN 21」により評価し、 計画に対する見直しを行っています。 N 環境活動のビジョンと指針 環境ビジョン Nature-friendly Products & Eco-factories [グリーンコンパス] エコプロダクツ&ファクトリー* ● ● 自然と調和した 企業コミュニティと循環型社 資源生産性の向上 エネルギー・資源の循環利用 会への新たな道を開拓します。 コア・バリュー 次なる世代のためにも、よき地球市民として 活動 を 強化 するとともに、製品・サービス・ W 技術を通じて、革新的な新しいビジネスモデ グリーンコンパス 積極的な情報開示 ● ステークホルダーとの 積極的なコラボレーション Eco-mind & Management エコマインド&マネジメント* ステークホルダーとの共創* ● E 開拓者精神 次世代への責任 地球市民の視点 Worldwide Stakeholder Collaboration ルを 社会 に 提唱し、積極的 に 4 つの 方向 に 取り組んでまいります。 自然と調和した 企業コミュニティと 循環型社会の創造 持続可能な企業活動を促進する マネジメント強化 ● 社員とその家族の高い エコマインドの醸成 ● 日立グループの 環境経営 の 羅針盤 です 。 基 S 本方針 であるコア・バリューと、環境ビジョ Sustainable Business Models ンで めざ す 4 つ の 方向と取り組 みを 示して サスティナブルビジネスモデル* います 。 ● ● サスティナブルビジネスモデルの拡大 環境負荷低減ビジネスの事業化拡大 日立製作所環境保全行動指針 本指針は、 「日立製作所企業行動基準」 (1983.6.28 制定 規第 2272 号) 環境保全活動 が適切に行 われていることを確認し、その 維持向上に努 を基本理念とし、日立製作所 の 事業活動に関 わる環境保全 への 取り組 める。 みに対する日立製作所の行動の指針を示すものである。 4. 製品の研究開発・設計の段階から生産、流通、販売、使用、廃棄な どの各段階における環境負荷の低減をめざしたグローバルなモノづくり スローガン を推進する。 製品・サービスを通じて環境と調和した持続可能な社会を実現 するため 5. モノづくりによって生じる環境への影響を調査・検討し、環境負荷を に、当社は製品の全ライフサイクルにおける環境負荷低減をめざしたグ 低減 するために省 エネルギー、省資源、化学物質管理、リサイクル 等、 ローバルなモノづくりを推進し、環境保全に努 めることにより社会的責 環境保全性に優れた技術、資材の導入を図る。 任を果たす。 6. 国際的環境規制並 びに国、地方自治体などの 環境規制を遵守 する にとどまらず、必要に応じて自主基準を策定して環境保全に努める。 行動指針 7. グローバルなモノづくりに際しては、当該地域の環境に与える影響 1. 地球環境保全は人類共通 の 重要課題 であり、環境と調和した持続 に配慮し、地域社会の要請に応えられる対策を実施するよう努める。 可能な社会 の 実現を経営 の 最優先課題 の 一 つとして 取り組み、社会的 8. 従業員の 環境に関 する法律遵守、環境 への 意識向上、広く社会に 責任を果たす。 目を向け、幅広い観点からの環境保全活動について教育する。 2. 地球環境保全 および 資源有限性 への配慮に関 するニーズを的確に 9. 環境問題 の 可能性を評価し、発生 の 防止に努 める。万一、環境問 把握し、これに対応 する高度 で 信頼性 の 高 い 技術及 び 製品を開発 する 題が生じた場合には、環境負荷を最小化するよう適切な措置を講ずる。 ことにより社会に貢献するよう努める。 10. 環境保全活動についてステークホルダーへの 情報開示と積極的な 3. 環境保全を担当 する役員は、環境保全活動を適切に推進 する責任 コミュニケーションに努め、相互理解と協力関係の強化に努める。 を持 つ。環境保全を担当 する部署は、環境関連規定の整備、環境負荷 削減目標 の 設定などにより環境保全活動 の 推進・徹底を図るとともに、 38 日立グループ CSR 報告書 2005 next eco 1993 年 3 月制定 2004 年 11 月改正 中期計画と実績報告 エコバリュープラン 2010 2010 年に向けたロードマップとして 2001 年に策定したものです。 その後毎年、年度行動計画策定に合わせ、改定しています。 エコマインド & マネジメント ❶環境経営の推進 グローバル環境経営グループシナジー効果の向上 「GREEN 21」ver.3 継続拡大 ❷自己評価制度の充実 ❸環境教育・啓発 エコライフスタイルの定着 ❹環境会計の定着化 効率的環境負荷削減の継続的実施 エコプロダクツ & ファクトリー エコプロダクツ ❺環境適合製品の拡大 環境適合製品の拡大(適用率 100%)、 温暖化防止ファクター 50% 以上向上、資源ファクター 70% 以上向上(00 年度比) (民生品など) ❻製品含有化学物質管理の推進 全製品での環境リスク物質管理の徹底 ❼グリーン調達の推進 調達先との環境適合製品の共同開発 ❽輸送の効率化 製品輸送時の CO2 排出量 10% 以上削減(00 年度比) エコファクトリー 地球温暖化防止 ❾ CO2 排出量 [国内] 7% 削減(90 年度比) 生産高 CO2 原単位 [海外] 25% 削減(90 年度比)または業界団体の個別目標[国内]、5% 削減(03 年度比) 温室効果ガスの削減 SF6(六フッ化硫黄)排出量 35% 削減(03 年度比)、 [半導体]、排出増加 0%[液晶] PFC(パーフルオロカーボン)排出量 10% 削減(95 年度比) 化学物質管理 排出量の削減 VOC(揮発性有機化合物)の排出削減 廃棄物削減 最終処分量の削減 70% 以下に削減(98 年度比) 廃棄物発生量の抑制 資源循環につながるモノづくりの推進 ステークホルダーとの共創 環境コミュニケーション 情報開示 共創をめざした情報開示の充実 対話 環境タウンミーティングの国際展開 地域、NGO との連携拡大による持続可能社会の実現 地球市民活動 サスティナブルビジネスモデル 資源循環モデルの構築 製品リサイクルシステム、リース、レンタルビジネスの拡大 サスティナブル社会に貢献する事業の拡大 環境ソリューションモデル事業の拡大、社会への普及 2004 年度行動計画と実績 各項目ごとの計画、2004 年度実績、目標値に対する達成状況と今後のプランを示しています。 エコマインド&マネジメント エコマインド&マネジメント エコマインド&マネジメント ❶ 環境経営の推進 ❷自己評価制度の充実 ❸ 環境教育・啓発 ●「GREEN ● 全社員と家族 への 「エコマインド」の醸成 ● 連結経営をめざし環境管理体制 の 整備強化 ● 21」ver.2 レベル 533 グリーンポイント(GP)達成 を図る 事業戦略 に 環境経営を 取り入 れ 環境価値創 造企業をめざす 2004 年度実績 環境負荷報告対象社数 国内:239 海外:36 合計:275 社 ● 社員教育、法定有資格者の充実 2004 年度実績 2004 年度実績 レベル 527GP 「GREEN 21 大賞」制度開始 インターネット教育 3 万 2 千人受講終了 2005 年度目標 レベル 640GP 達成 英語版の社員家族向けパンフレット配布 2005 年度目標 グローバル環境教育の充実 2005 年度目標 グローバルな環境経営の強化 PAGE P.46 PAGE P.42 PAGE P.42、48 日立グループの環境活動 next eco 39 エコマインド&マネジメント エコプロダクツ & ファクトリー エコプロダクツ & ファクトリー ❹ 環境会計の定着化 ❺ 環境適合製品の拡大 ❻ 製品含有化学物質管理の推進 ● 関連会社含み、定着化と環境経営を推進 ● 環境効率指標を組み込んだ ● RoHS 指令対象電気電子機器 における 6 化 ● 環境負荷削減指標の活用などの推進 「環境適合設計アセスメント指針」を発行 ● 各事業・各社の代表製品における 製品環境効率の実行 2004 年度実績 連結会社 275 社の環境会計の 04 年度集計 2005 年度目標 環境会計の内部活用推進 2004 年度実績 環境適合製品 学 物 質( 六 価 クロ ム 、 鉛 、 カドミウ ム 、 水 銀 PBB、PBDE)の全廃 2004 年度実績 6 化学物質全廃技術の開発ほぼ完了 05 年 4 月新製品から 順次 RoHS 指令対応製品を出荷 72% 「環境適合設計アセスメント指針」改訂 11 製品で環境効率を算出 2006 年度目標 6 化学物質不含有への適切な 2006 年度目標 環境適合製品 80% 達成 PAGE P.47-48 個体管理システムの構築(06/6) PAGE P.49-51 PAGE エコプロダクツ & ファクトリー[地球温暖化防止] エコプロダクツ & ファクトリー エコプロダクツ & ファクトリー ❼グリーン調達の推進 ❽ 輸送の効率化 ❾ CO2 排出量 ● 調達先の環境マネジメント支援制度の構築 ● 製品輸送時 の 環境負荷(CO2、NOx、PM など ● 国内 CO2 排出量の削減 ● RoHS 対象製品含有化学物質の調査 の排出量)の低減 2004 年度実績 CO2 排出量 20% 削減(90 年度比) ● 輸送負荷目標を策定し、活動推進 2004 年度実績 RoHS 対象製品含有化学物質の調査完了 2004 年度実績 輸送による CO2 総排出量 453kt-CO2/ 年(03 年度比 6% 増加) 2006 年度目標 グリーンサプライヤー率 100% 2007 年度目標 製品含有化学物質の特定調査 2005 年度目標 製品輸送(構内除く)時の CO2 排出量 2% 以上削減(00 年度比) 調達先環境マネジメント支援制度の構築 PAGE P.30-31 エコプロダクツ & ファクトリー[地球温暖化防止] 生産高 CO2 原単位 エコプロダクツ & ファクトリー[地球温暖化防止] PAGE 日立グループ CSR 報告書 2005 P.52-53 エコプロダクツ & ファクトリー[化学物質管理] 「削減対象物質」排出量の削減 2004 年度実績 「削減対象物質」 56% 削減(00 年度比) [半導体] PFC 排出 7% 削減(95 年度比) 2005 年度目標 国内 CO2 生産高原単位 20% 削減(90 年度比)または 業界団体の個別目標に基づいた目標値 P.52-53 ● 管理の徹底と排出量削減、 2004 年度実績 SF6 排出量 19% 削減(03 年度比) 1% 増加 PAGE 排出量の削減 (HFC、SF6、PFC)の削減 (90 年度比) next eco P.51 ● CO2 以外の温室効果ガス 2004 年度実績 国内生産高 CO2 原単位 24% 削減 40 PAGE 2005 年度目標 CO2 排出量 3% 削減(90 年度比) 温室効果ガスの削減 ● 生産高 CO2 原単位の削減 海外生産高 CO2 原単位 (03 年度比) P.49 2005 年度目標 SF6 排出量 30% 削減(03 年度比) PAGE P.52-53 2005 年度目標 「禁止物質」 排出全廃 「削減対象物質」 30% 削減(00 年度比) PAGE P.54-55 エコプロダクツ & ファクトリー[廃棄物削減] エコプロダクツ & ファクトリー[廃棄物削減] 最終処分量の削減 ステークホルダーとの共創[環境コミュニケーション] 情報開示 廃棄物発生量の抑制 ● 廃棄物の最終処分量の削減 ● 廃棄物発生量の抑制 ● 広報・宣伝、環境報告書の発行、 2004 年度実績 ● 展示会、講演会、地域活動など インターネットなどによる情報開示 ● ゼロエミッションの推進 2004 年度実績 廃棄物発生量 (98 年度比) 62%に削減(98年度比) ゼロエミッションを71サイトで達成 最終処分量 93% に抑制 社外団体への参画 2004 年度実績 2005 年度目標 廃棄物発生量の抑制継続 2005 年度目標 廃棄物の最終処分量 80% 以下に削減(98 年度比) 35 件 会社・事業所別ホームページ 48 件 会社・事業所別環境報告書 サイトごとに目標を設定し計画的に削減 「エコプロダクツ国際展」 「エコプロダクツ 2004」出展 2005 年度目標 グローバルであらゆる機会を 通じた情報発信 PAGE P.56 ステークホルダーとの共創[環境コミュニケーション] 対話 PAGE P.56 ステークホルダーとの共創 資源循環モデルの構築 ● 会社、地域ごとでの ● ボランティア活動 への社員の積極的な参画 「環境タウンミーティング」などの開催 ● アンケート 、 ヒアリング 、 見学などへの対応と意見交換 ● 事業所施設などの開放 ● 地域の緑化活動、清掃活動の実施 2004 年度実績 環境省主催ライトダウンキャンペーンに 64 施設で参加 日立の環境活動に対するアンケート 25 件回答 2005 年度目標 環境タウンミーティングの地域展開の拡大 ● 使用済み製品の回収・リサイクルの拡大 2004 年度実績 ● 地域の NGO と協力した活動 2004 年度実績 P.57 サスティナブルビジネスモデル 地球市民活動 日立製作所水戸事業所での 「環境タウンミーティング」実施 PAGE 事業所内にある自然地域 東京エコリサイクル(株) (「リサイクル技術開発本多賞」受賞) 2005 年度目標 製品リサイクルシステム、リース、 レンタルビジネスの拡大 52 カ所の登録、地域への開放 中学校、大学などへの授業協力 2005 年度目標 地域と連携した環境啓発活動の充実 PAGE P.57 PAGE P.24-27、P.57 PAGE P.58-60 ■カードの凡例 サスティナブルビジネスモデル サスティナブル社会に貢献する事業の拡大 ● 体制の構築と戦略 ● 環境保全に貢献 する研究開発の推進 日立グループの環境ビジョン 「グリーンコンパス」の 4 つのテーマ 取り組み項目 ● 環境ソリュ−ションビジネスの展開 具体的取り組み内容 ● 環境修復活動※の計画、実行 2004 年度実績 環境委員会内にサスティナブルビジネス モデル部会を設置し、情報の共有化を推進 HDRIVE(「エコプロダクツ大賞」受賞) 2005 年度目標 環境ソリューションモデル事業の拡大 サスティナブルビジネスの社会への普及 ※環境修復活動:生態系 の 修復、自家発電、再生可能 エネルギーへの投資、支援など 2004 年度実績 2005 から 2007 年度目標 2004 年度実績評価 達成 要改善努力 関連参照ページ PAGE P.58-60 日立グループの環境活動 next eco 41 [グリーンポイント平均点実績と目標] るインセンティブ(誘因)として機能しています。各グ エコマネジメント 02 年度:377GP 03 年度:441GP サスティナブル 04 年度:527GP(目標 533GP) ビジネスモデル 05 年度:640GP 56GP ループの経営層は、評価により強弱を再確認でき、さ 環境経営 65GP 80 エコマネジメント リスクマネジメント 86GP 2004 年度 は、527GP となり、前年度を 24% 改善し 40 ●評価項目 エコマネジメント:環境経営 環境マネジメント、行動計画、 環境会計 エコマネジメント :リスクマネジメント 法令遵守、自主基準の設定 ステークホルダー との共創 エコファクトリー :地球温暖化防止 サイトの省エネルギー エコファクトリー:資源循環 廃棄物削減、化学物質管理 ステークスホルダーとの共創 情報開示、対話・地球市民活動 サスティナブルビジネスモデル 体制、計画、製品リサイクル、 環境修復活動 ましたが、目標レベルの 533GP を 6GP 下回りました。 0 エコマインド 72GP 62GP 改善された 点 は 環境 マネジメントの 強化によるリスク マネジメントとサスティナブルビジネスの考え方の共有 化 が進 んだサスティナブルビジネスモデル*のカテゴ エコファクトリー エコプロダクツ 資源循環 56GP 71GP エコファクトリー エコマインド 社員への教育、啓発 エコプロダクツ 製品・サービスのアセスメント、 グリーン購入、物流 らなる改善や活動の活性化につなげています。 ダクツのカテゴリーでは、環境適合製品 のさらなる拡 地球温暖化防止 59GP 大およびグリーン調達の推進、エコファクトリーのカテ [グリーンポイント実績と目標] ゴリーでは、地球温暖化防止 の目標達成 に 向けた 計 (GP) 画的な投資など、さらに取り組みを強化していきます。 700 640 600 533 527 実績 500 400 リーです。2005年度の目標達成に向けて、エコプロ 目標 441 377 活動促進へのインセンティブ GREEN 21 大賞 426 日立グループは 2004 年、環境に関する先進的な活動 300 を表彰する「GREEN 21 大賞」を新設しました。 0 2002 2003 2004 2005(年度) トップレ ベ ル の 環 境 活 動 へ の イン セン ティブ を 与 えると 同 時 に、グ ル ー プ 内 で の 情 報 展 開 を 行 い、 自己評価制度 「GREEN 21 活動」を 中心とする環境活動 の 活性化 評価基準「GREEN 21」ver.2 の結果報告 をその目的としています。 具体的 には、環境 に 配慮 環境活動 の 継続的改善と活動レベルの 向上を図って したトップランナー 製品 や 技術、事業所 の 省 エネ、省 いくために、すべての 活動を一定 の 基準 で 評価 する 資源 などの 先進事例、環境活動を通じた 社会とのコ 「GREEN 21」ver.2 というシステムを 適用して いま ミュニケーションについて、その 先進性、効果、継続 す。目標達成年度に対し、それに向けた 活動 の 仕組 「GREEN 21」の 総合点 や 向上 性、外部からの 評価、 み、目標 の 設定内容、達成度をそれぞれ 採点します。 率などの総合的視点から審査を行い、表彰します。 環境活動をより効率的に推し進めるためのツールで、 第 1 回となる 2004 年は、海外の5件を含む 18 件の応 各事業で環境経営の実施に役立てられています。 募があり、審査の結果、4件の活動が受賞しました。 「環境経 評価対象 はグリーンコンパスを細分化した、 「リスクマネジメント( エコマネジ 営( エコマネジメント)」 PAGE GREEN 21 大賞受賞活動内容 メント) 」 「 エコマインド」 「 エコプロダクツ 」 「地球温暖 日立電線グループ ⇨ P.58 参照 「資源循環(エコファクトリー)」 化防止(エコファクトリー)」 [2004 年 GREEN 21 受賞活動] 表彰名 「 サスティナブルビジネ 「ステークホルダーとの 共創」 大賞 スモデ ル 」の 8 カテゴリー、53 項目です。 対象活動 期間は 2002 年度から 2005 年度。 点数は 0 ∼ 5 点 で 優秀賞 表し、2 点は平均的活動レベル、4 点は目標達成レベ ル、5 点は目標を超える活動としています。評価に項 100 グリーンポイント(以下 GP)、合計 800GP となる 受賞活動の名称 日立電線 「廃電線リサイクルシステムの 構築・運用と RoHS 対応電線 の開発」 日立製作所 都市開発システムグループ 水戸ビルシステム本部 「環境適合製品を軸にした 環境負荷削減活動」 日立グローバルストレージ 奨励賞 目ごとの 重 み 係数を 掛 けて、各 カテゴリーの 満点 が 受賞事業所 テクノロジーズ 「包装リユースプログラム」 (米国・サンノゼ拠点) 奨励賞 台湾日立股份有限公司 「地域社会 での 社会貢献活動 および 事業所での 廃棄物削減 とリサイクルの実施」 ように配分しています。業態により非該当項目が生じ た場合は補正を行います。 WEB 2002 年度から「GREEN 21」ver.2 は、グループ業績 日立 グル ープ で 環境活動 の 表 彰制度を設立 評価基準の一つとして加えられました。 この結果をふ http://greenweb.hitachi. co.jp/data/hyosyo04.html まえ、各グループの 適正 な 業績評価を 行 い、社会性 GREEN 21 大賞 と収益性 の 向上をめざすとともに、環境活動を 高 め 42 日立グループ CSR 報告書 2005 next eco 表彰式 2004 年度の環境活動について 日立グループの事業は多岐にわたり、環境で管理 すべき項目も多様なため、グループ全体での環境負荷削減をめ ざした環境活動を推進しています。日立グループ 連結子会社 985 社、持分法適用関連会社 167 社を対象にした 共通の環境方針を立て、方針の徹底、推進を図っています。 「エコマインド」の共有に力を注 1999 年度からグループ会社との環境推進会議をはじめとする管理体制を構築し、 いでいます。 またグループの CO2、廃棄物などの環境負荷データを集計 するシステムやグリーン調達システムな ど、情報 の 管理と共有化 の 徹底を行っています。 さらに IT を基盤とした独自のマネジメントシステムを活用し、タ イムリーで効率的、信頼性の高い環境経営を展開しています。 本報告書では、日立製作所および連結子会社 985 社のうち、環境負荷の割合で約 9 割を占めている 275 社(国内: 239 社、海外:36 社)を対象に、社員数、エネルギー使用量、廃棄物排出量、化学物質排出量などのデータをもとに 評価した結果を報告しています(2005 年3月現在)。 2004 年度の活動については、以下の項目を中心に取り組みました。 「環境に配慮したモノづくり」のルール化(環境 CSR 対応モノづくり規程)と、 製品含有化学物質管理のシステムづくり(製品含有化学物質一元管理システム)を推進しました 環境に配慮したモノづくりを日立グループとして徹底するために、製品に含まれる化学物質の管理と運用につ PAGE 「製品含有化学物質一元管理シ ステム」 ⇨ P.14 ∼ 15 参照 いて、プロセスやシステムの再構築を進めています。日立グループ「環境 CSR 対応モノづくり規程」として共 通 ルール 化し、システムづくりを行 い、代表モデルとして日立製作所 RAID システム事業部、日立ホーム&ラ イフソリューション(株)、日立マクセル(株)で製品含有化学物質一元管理システムの導入を開始しました。 環境適合製品の拡大を実施しました 「環境効率」の算出を 2004 年度は「環境適合設計アセスメント」に「環境効率」の算出機能を追加することで、 容易化し、ファクター 11 製品、環境適合製品の登録率を 72%まで拡大しました。 グループの最終処分量の目標を達成しました グループ目標である 2010 年度 の目標最終処分量 70%以下(1998 年度比)に対し、グループ全体で 62%とな り、約 76%の事業所が達成しました。 日立製作所都市開発システムグループ水戸事業所で、環境タウンミーティングを実施しました ステークホルダーとの環境タウンミーティング*は4回目を数えます。 2004 年度は、開催地をこれまでの東京 地区から茨城県 ひたちなか市に移し、日立製作所水戸事業所の工場を実際にご覧 いただきながら、生産拠点 における環境活動についての 質疑応答 や 意見交換を行 いました。 「地域社会 での日立」としての 期待事項な ど、今後のコミュニケーションの充実に向けて、地域開催ならではの成果が得られました。 43 next eco 事業活動における環境負荷情報(2004 年度) 日立グループ国内外 273 社の会社が事業活動を実施するにあたり 投入している資源の量と、排出している環境負荷の 2004 年度のデータを示したものです。 インプットは、製品づくりなどの事業活動を実施する際に使用しているエネルギー、 素材や化学物質などの総物質、水資源の投入量を アウトプットでは、製品および CO2、化学物質、廃棄物、排水など、 事業活動を実施することにより発生した環境負荷を表したものです。 INPUT 国内 事業活動 155.1 万 kℓ 総エネルギー投入量(原油換算) 電気 石油 新エネルギー 電気 熱 46.9 億 kWh ※ 0.54%(2004 年度) 36.4 万 kℓ ※ 0.15%(2004 年度) 0.7 億 kWh 1.6 万 kℓ 総物質投入量 金属 1,266kt 鉄(鋼板含む) ステンレス アルミニウム プラスチック 191kt 77kt 287kt その他非鉄金属 146kt 熱可塑性プラスチック 155kt 熱硬化性プラスチック 36kt 5kt 350kt その他の素材 PRTR 法対象化学物質取扱量 215kt オゾン層破壊物質取扱量 27t 温室効果ガス物質取扱量 1,296t 6,029 万 m3 水質源投入量(用水) 上水道 717 万 m3 工業用水 2,770 万 m3 地下水 2,543 万 m3 海外 事業活動 45.5 万 kℓ 総エネルギー投入量(原油換算) 電気 新エネルギー 34kt 銅 ゴム 化学物質 722kt 14.8 億 kWh 石油 7.7 万 kℓ 電気 0.8 億 kWh 総物質投入量 化学物質 PRTR 法対象化学物質取扱量 835 万m 3 水質源投入量(用水) 上水道 293 万 m3 工業用水 519 万 m3 地下水 44 日立グループ CSR 報告書 2005 next eco 20.2kt 23 万 m3 OUTPUT CO2 排出量 2,586kt(2,586kGWPt*) ※ 0.2%(2004 年度) ※日本全体 に 占 める 割合 と 比 較した 年度。 日本全体 に 占 め る割合を比較したデータは平成 16 年版「環境白書」、平成 15 年 度 PRTR 集計結果による 2,463kt(容器包装使用量含む) 総製品生産・販売量 化学物質排出量・移動量 PRTR 法対象化学物質排出量・移動量 5.8kt 温室効果ガス排出量 23t(412kGWPt) SF6(六フッ化硫黄) 14t(341kGWPt) PFC(パーフルオロカーボン) 9t(71kGWPt) HFC(ハイドロフルオロカーボン) 排出規制項目 0.05t(0.6kGWPt) SO X(硫黄酸化物) 548t ※ 0.05%(1999 年度) NO X(窒素酸化物) 2,969t ※ 0.25%(1999 年度) 561kt ※ 0.09%(2001 年度) 45kt ※ 0.02%(2001 年度) 561kt 廃棄物等総排出量 発生量 減量化量 再資源化量(率) 483kt(93%) リユース 110kt(23%) マテリアルリサイクル 336kt(70%) 37kt(7%) サーマルリサイクル 33kt(6%)※ 0.06%(2001 年度) 最終処分量(率) 5,235 万 m3 総排水量 水の 循環的利用 9,479 万 m3 排水先の内訳 水質 ※ 1.1%(2003 年度) 6.5t(0.4ODPt*) オゾン層破壊物質排出量 公共用水域 4,159 万 m3 下水道 1,076 万 m3 BOD(生物化学的酸素要求量) 384t COD(化学的酸素要求量) 266t CO2 排出量 1,346kt(1,346kGWPt) 化学物質排出量・移動量 PRTR 法対象化学物質排出量・移動量 0.8kt SO X 126t NO X 発生量 減量化量 排水先の内訳 水質 150kt 33kt 再資源化量(率) 58kt(50%) 最終処分量(率) 59kt(39%) 821 万 m3 総排水量 水の 循環的利用 347 万 m3 109t 150kt 廃棄物等総排出量 公共用水域 363 万 m3 下水道 457 万 m3 BOD 193t COD 232t 事業活動における環境負荷情報(2004 年度) next eco 45 エコマインド&マネジメント 社員一人ひとりの環境意識「エコマインド」。 その行動をサポートする体制「エコマネジメント」 。 日立グループは、個と組織がしっかり連携をとりながら、環境経営を展開しています。 エコマネジメント「環境管理体制」 ループ 会社 の 環境部門を統括 する環境推進責任者を 日立グループは、環境 への 取り組 みを 推進 するため 任命してこれに取り組んでいます。 さらに国内、海外 に、連結 べースのエコマネジメント「環境管理体制」 とも、地区別 に 法規制 やマーケット動向 はもとより、 を構築しています。 社長を議長とする経営層 で 構成 事例発表会などによる情報の共有化を行っています。 される「環境経営会議」を行 い、ここで日立グループ 海外の環境活動の強化については、2005 年度より欧 全体 の 環境に関 する取り組 み 方針 や 活動施策などが 州 および 中国に、各拠点 のグループ 内 での 環境情報 審議、決定されます。 の 共有化と活動 の 強化をめざし、環境推進体制 の 整 その 方針 や 活動施策 は、 「環境推進会議」などを通じ 備を行っていきます。米国、アジアについても順次、 て、グループ 全体 に 展開し浸透させています。 また これを推進していきます。 「環境委員会」や 各「部会」で、それ ぞれの目標 や 課 題について、達成と解決に 向けた 調査、技術 や 評価 ISO14001 に基づく環境マネジメントシステム 手法の開発などを行っています。 日立グループは、国際標準規格 である ISO14001 に 具体的 には、各事業 に 応じた 環境活動を推進 するた 基 づく環境マネジメントシステムを構築し、環境に関 めの 組織を 設置し、それぞれ 事業グループおよびグ する取り組みを進 めています 。 1995 年 7 月より認証 [環境管理体制] 環境経営会議: 経営層 による 環境経営方針 の 審議、 決定(年 2 回) 環境経営会議 社長 環境推進会議: 環境方針の徹底と環境情報・活動の展 開(年 2 回) 事業グループ 環境本部 環境委員会 63 46 主要グループ会社 社長 環境推進責任者 製造 非製造 55 4 アジア地域 アメリカ地域 ヨーロッパ地域 合計 一般社員 グループ研修 管理職 監査員教育 経営層 主任監査員教育 専門教育 エコプロダクツ開発教育 277 40 件 14 件 5件 事業所 事業所長 環境管理責任者 グループ会社 日立製作所および 社長 連結子会社 985 社、 環境管理責任者 持分法適用関連会社 167 社 [環境教育体系図] 日立グループ CSR 報告書 2005 next eco エコプロダクツ 部会 日立製作所 海 外 155 グループ会社 社長 環境管理責任者 サスティナブル ビジネス部会 国 内 取得数 エコマネジメント 部会 エコファクトリー 部会 [ISO14001 認証取得状況] 日本 北海道・東北地区 20 件 関東・甲信越地区 148 件 北陸・中部地区 19 件 関西地区 16 件 中国・四国・九州地区 15 件 合計 218 件 環境推進責任者 地区別環境会議 部会: 課題 の 整理、方針案 の 策定(随時)。 各部会 の 主なテーマは、エコマネジメ ント=環境管理・教育啓発活動・情報 発信、エコプロダクツ=環境適合製品 の 開発促進、製品使用有害物質削減 推進、エコファクトリー=生産活動 に おける環境負荷低減、サスティナブル ビジネス=サスティナブルビジネス 創 造支援、モデル構築と活動強化 非製造 事業所 事業所長 環境管理責任者 グループ長 &CEO 環境委員会: 環境課題の審議、方針の策定(年 2 回) 製造 環境推進会議 会社・事業所別研修 ISO に基づいた教育 一般教育 エコマインド教育(インターネット) 専門教育 特定業務者研修 一般教育 会社・事業所別のエコマインド教育 環境経営に関する教育 環境会計 [コスト] (単位:億円) 費 用 項 目 主な内容 2000 年度 2001 年度 2002 年度 2003 年度 2004 年度 359.6 382.1 350.0 290.2 318.2 費 用 事業所エリア内コスト 環境負荷低減設備の維持管理費、減価償却費など 上・下流コスト グリーン調達費用、製品・包装の回収・再商品化、リサイクル費用 35.8 32.7 24.0 27.6 26.9 管理活動コスト 環境管理人件費、環境マネジメントシステム運用・維持費用 83.5 110.9 104.1 122.9 107.6 研究開発コスト 製品・製造工程環境負荷低減の研究・開発および製品設計費用 300.3 343.6 382.1 354.8 395.1 社会活動コスト 緑化・美化などの環境改善、PR・広報費用 32.3 5.3 5.2 3.7 6.1 環境損傷コスト 環境関連の対策、拠出金課徴金 9.3 8.2 8.6 5.1 22.3 820.8 882.8 874.0 804.3 876.2 212.5 180.1 149.7 101.7 141.0 費用合計 投資合計 省エネ設備などの直接的環境負荷低減設備への投資 設備投資の減価償却費は 5 年間の定額方式で計算しています。 [効果] ◆経済効果※ (単位:億円) 効果額 項 目 主な内容 実収入効果 廃棄物リサイクル売却益 費用削減効果 省資源化による資源費低減、廃棄物削減による処理費削減、 省エネによる動力費削減 2000 年度 2001 年度 2002 年度 2003 年度 2004 年度 55.8 50.9 60.8 40.6 62.5 120.3 135.6 121.1 116.7 127.7 176.1 186.5 181.9 157.3 190.3 2000 年度 2001 年度 2003 年度 2004 年度 合計 ◆物量効果 削減量・世帯換算 項 目 主な内容 2002 年度 生産時のエネルギー 使用量の削減 省エネ設備の導入によるエネルギー使用量の削減 169 百万 kWh 331 百万 kWh 189 百万 kWh 127 百万 kWh 125 百万 kWh 49 千戸 95 千戸 55 千戸 37 千戸 36 千戸 生産時の廃棄物 最終処分量削減 分別、リサイクル等による最終処分量の削減 6,051t 20 千戸 製品使用時の エネルギー消費量削減 当社製品のお客様使用時におけるエネルギー消費量削減 844 百万 kWh 552 百万 kWh 742 百万 kWh 507 百万 kWh 730 百万 kWh 543 千戸 159 千戸 214 千戸 146 千戸 210 千戸 7,369t 25 千戸 5,210t 18 千戸 5,612t 19 千戸 5,922t 20 千戸 設備投資に伴う効果はコストと同様に 5 年間計上しています。 ※経済効果は以下の項目を計上しています。 ①実収入効果:有価物の売却および環境技術特許収入などの実収入がある効果 ②費用削減効果:環境負荷低減活動に伴う電気料・廃棄物処理費等の経費削減効果 [環境負荷削減効率※] 2000 年度 2001 年度 2002 年度 2003 年度 2004 年度 生産時のエネルギー使用量削減 4.1 百万 kWh/ 億円 6.6 百万 kWh/ 億円 5.3 百万 kWh/ 億円 4.4 百万 kWh/ 億円 3.3 百万 kWh/ 億円 生産時の廃棄物最終処分量削減 117t/ 億円 175t/ 億円 120t/ 億円 169t/ 億円 169t/ 億円 ※環境負荷削減の効率を表す指標で、環境負荷の削減量を、削減を行うための費用で割ったものです。 [費用の部門別内訳比率(%)] 1 [投資の部門別内訳比率(%)] 2 14 28 [経済効果の部門別内訳比率(%)] 1 8 8 11 [投資の対策別内訳比率(%)] その他 5 地球温暖化防止 29 2 8 50 28 55 22 8 41 9 4 情報通信システム 電子デバイス 電力・産業システム デジタルメディア・民生機器 高機能材料 物流及びサービス他 公害防止 60 廃棄物削減 6 エコマインド & マネジメント next eco 47 取得を開始し、製造拠点では、1999 年度中に認証 の取り組みを推進するための教育も実施しています。 取得を完了しました。また、ソフトやサービス会社な 環境影響が著しい作業などについては、特定業務研 ど非製造業務の事業拠点でも2002 年度に認証取得 修で作業手順や緊急時の訓練などを行っています。 を完了しました。なお、連結対象会社の対象範囲の 変更などにより、現在 277 サイトで、認証取得してい 環境会計の考え方について ます。 環境投資・環境活動の効率化と継続的改善を推進す グループとしての環境活動をさらに強化するために、 るために、日立グループは 1999 年度より、環境会計 各事業グループおよびグループ会社の環境推進部門 制度を導入しています。 経営資源の環境活動への配 を含めた新しいスタイルでの環境マネジメントシステ 分と、環境技術や環境適合製品がもたらす価値につ ム構築に現在、取り組んでいます。 いて情報を開示することで、企業姿勢をより深く理解 各事業所では、自らの取り組み状況を内部監査で評 していただくことを目的としています。 価するとともに、社外の認証機関から定期的に審査を コストについては、1997 年度から公表してきた環境 受けることで、継続的な改善を図っています。 内部 活動に関わる設備投資に加え、研究開発費用や保全 監査では、監査の質的向上のために、研修で養成、 設備の運転管理費用などの経常的費用についても対 認定された約 2,000 人の社員が監査員として登録 象としています。 効果については、金額で評価する し、監査を行っています。 「経済効果」と、環境負荷抑制量で評価する「物量 また 1973 年より、経営上の視点から見た環境監査 効果」の両面から捉えています。 経済効果は、確実 を、業務監査の一環として継続しています。 な根拠に基づいて把握される効果を算出しています。 物量効果では、優れた自主技術・製品の開発を通じて 環境教育の実施 「エコマインド」の醸成のために、環境活動に対する 品の生産時における環境負荷の抑制だけでなく、製 全社員の知識と意識を向上させる一般教育と、専門 品の使用時における環境負荷抑制効果についても算 分野における環境技術の習得・実行を促す専門教育 出しています。さらに、環境負荷項目の費用あたりの を実施しています。 削減量を評価する「環境負荷削減効率」により、効率 一般教育では、経営層に対する環境教育の充実を図 的な環境負荷削減を推進しています。 ることで、環境経営の重要性を再認識するとともに、 2004 年度は、費用では 9% の増加、経済効果では 経営方針への反映につなげています。一般社員に対 21% の増加となりました。 内訳で見ると、製品の環 しては、インターネットを利用した教育を実施し、累 境負荷低減のための研究開発・設計を行う「研究開発 計で約 3 万 2 千人が受講しました(2005 年 3 月現在)。 コスト」が費用の 45%を占め、この結果、 「製品使用 専門教育では、環境マネジメントシステムの監査員教 時のエネルギー消費量」を、7.3 億 kWh 削減するこ 育、設計者や製造部門を対象にしたエコプロダクツ開 とができました。 発教育などを実施しています。また、ISO14001 に 基づいた事業所の環境活動、省資源、省エネルギー 48 日立グループ CSR 報告書 2005 next eco 社会に貢献するという日立の基本理念に基づき、製 エコプロダクツ&ファクトリー 日立グループは、製品の設計段階からライフサイクル全般における 環境負荷を予測した上で、最適な方法を選択し、 自然環境に配慮する製品「エコプロダクツ」を生み出しています。 また製品を手がける各サイト(工場・事業所)は、 地球温暖化防止、化学物質管理、廃棄物削減に取り組み、 環境負荷を抑える「エコファクトリー」であることを基本としています。 [環境適合製品登録状況推移] 40 240 29 600 46 400 (1,504) (30) 2002 () 200 22 (714) (15) 3 2000 2001 内 は機種数] 登録比率︵売上高比︶ 800 目標 (60) (70) 60 0 Eco-Products 環境適合製品 80 20 1,000(件) 817 761 (3,294) (2,864) 72 (80) 568 (2,056) 66 製品登録数[ (%) 100 2003 0 2006(年度) 2004 実績値 目標値 [ライフサイクル全体での製品設計の考え方] 省 資 源 環境適合製品の拡大 環境適合設計 素材 生産 流通 日立グループでは、製品 のライフサイクル*の 各段階 ています。 環境適合設計 Design for Environment 適正 処理 再使用・再利用 において、環境負荷をできるだけ 小さくするように、 「環境適合設計 アセスメント」を 導入し、製品開発し 回収 ・ 分解 使用 環境適合アセスメント アセスメント項目:減量化、 長期使用性、 再生資源化、 分解・処理容易性、 環境保全性、 省エネルギー性、 情報提供、 包装材 (DfE)の 概念を取り入 れた 評価法 で、1999 年より適 用を始めました。減量化、長期使用性、再生資源化、 分解・処理容易性、環境保全性、省エネルギー性、情 報提供、包装材の 8 項目を製品ごとに評価し、各項目 が基準 5 点満点中 2 点以上を満たし、かつ 平均点が 3 点以上となる製品は、環境配慮に優れていると考え、 「環境適合製品」と定義しています。 [環境効率の定義] ■温暖化防止効率= 製品寿命※ 1×製品機能 ライフサイクルでの 温暖化ガス排出量 ■資源効率= 製品寿命×製品機能 Σ各資源価値係数×(ライフサ イクルで新規に使用する資源 量※ 2 +廃棄される資源量※ 3) ファクターの定義 ■温暖化防止ファクター= 評価製品の温暖化防止効率 ■資源ファクター= 評価製品の資源効率 基準製品の温暖化防止効率 基準製品の資源効率 ※ 1:設定使用時間 ※ 2:使用する資源量−リユース (再使用) ・リサイクル資源量 ※ 3:使用 する資源量−リユー ス(再使用) ・リサイクル 可能資 源量 2005 年 3 月現在、環境適合製品は 817 製品、3,294 機種で、売上高比(環境適合製品売上高 / 売上高)では、 合設計アセスメント」に「環境効率」の算出機能を追加 72% でした。 し、これまでの「環境適合設計アセスメント」を実施 す 環境適合製品 は、環境 マークとして「eco」マークを ることにより「環境効率」もあわせて算出できるように 付け、その情報はカタログやホームページなどに掲載 して日立グループでの適用を進めました。 WEB 日立グループ 環境適合製品 し、お客様に開示しています。 http://greenweb.hitachi. co.jp/ecoproducts/index. html 環境効率 製品含有化学物質管理の推進 資源をより有効 に 活用 するために、環境負荷と資源 RoHS 指令への対応 消費を抑制しながら、どれだけ価値を生み出したかを 日立グループは、EU の RoHS 指令*への対応として、 示 す 指標「環境効率」を 導入しています。 製品 の 価 鉛・六価クロム・カドミウム・水銀・PBB*・PBDE*の 値を「機能」と「寿命」として 捉えて、その 製品 のライ 6 化学物質 の 全廃 に 取り組 んできました。 グループ フサイクルにおいて排出される温暖化ガス量との割合 内 での 技術開発 はもとより調達先 の 協力を 得 て、鉛 ( 温暖化防止効率 )と、その 製品 のために 新 たに 地球 フリー、六価クロムフリー 部品 の 採用などを実施しま から取り出された資源量と廃棄される資源量の合計と した。 そ の 結果、2005 年 3 月時点 で、大部分 の 新 の 割合( 資源効率 )の 2 つの 効率を 算出し、評価 する 製品 で 対応を完了しており、HDD( ハードディスクドラ ものです。 イブ )などの 製品 で、す でに RoHS 適合製品 を 出荷 さらに 基準年度 における環境効率 に 対して、その 向 しています。 対応 が 未完 の 一部 の 製品 についても、 上度合 いを 表 すものとして、指標「ファクター」を 設 順次、新製品 から 切り替 えて いきます。 また、サプ け、それぞれ「温暖化防止ファクター」と「資源ファク ライヤーの 立場としても、電線 などの 素材 に 関 する ター」とし目安 として います。 2004 年度 は「環境適 RoHS 対応を行っています。 [新「eco」マーク] 従来 今後 使用例 従 来 の マ ークに「eco」を 入 れ 製品ごとの環境配慮がわかるよ うに使用 エコプロダクツ & ファクトリー next eco 49 エコプロダクツ紹介 心臓磁気計測システム MC-6400 心臓内 の 電気現象 により自然 に 発生 する磁場を測定し、心臓各部位 の 電気生理現象を、X 線・超音波・強磁場などを一切使 わず 、安全 に 検査 する装置 です。 着衣 のままベッドに横たわり、胸部を装置 のセン サ 部 に 近 づけ、数十秒 で 検査 が 完了 するため、患者 の 負担も軽減 で きます 。 「超電導センサ 環境配慮ポイント ランニングコストの大部分を占める、 環境効率の向上度合い (ファクター)算出値 (基準製品:試作機) 冷却用液体 ヘリウム」の消費量を、装置の断熱性を高めて蒸発量を低 減することで、従来品より 50% 減量しました。またコンパクト化により、 温暖化防止ファクター:2.1 資源ファクター :2.4 装置の占有面積は従来よりも 41%、装置質量も 12% 減少しました。 (株)日立ハイテクノロジーズ製 MC-6400 心臓磁気計測システム スーパーコンパクトスイッチギヤ 日立 7.2kV 縮小型受変電設備 オフィスや 工場 で 送電線から受電 する 6,000V の 電気を、安定供給 す るための高圧スイッチギヤです。一般家庭でのブレーカに相当する設 備ですが、より多くの 電気を配電 するために必要なスペースをいかに 小型化するかが環境性能向上の要点のひとつです。 環境配慮ポイント 先進の絶縁技術を駆使し、設置面積を従来機器に 比 べて 1/3 まで縮小しました。 これにより省資源化と軽量化(66%:従 環境効率の向上度合い (ファクター)算出値 (基準製品:1998 年) 温暖化防止ファクター:6.5 資源ファクター :8.3 来比)を実現しました。 またユニット式を採用したことで、材料 の 共有 化と再利用性が高まり、ユニットごとの分割による機動性向上を実現し ました。 ルームエアコン フレッシュ給排白くまくん RAS-S28T 業界最高水準 の 省 エネと高暖房力を 実現した、ル ームエアコン「フ レッシュ給排白くまくん」です。 2004 年度省 エネ大賞の省 エネルギー センター会長賞を受賞しました。 ダブルアクセルシステムの冷媒圧縮の模式図 アクセルシステム 」 (東北電力(株)共同開発)と「 ベクトル 制御 PAM」を 搭載し、革新的な省 エネと最高水準 の 暖房力を実現しました。 また、 高圧 吐出口 空気と臭 いを清浄化 するために、次 の 新技術を搭載しています。 給 温暖化防止ファクター:12.6 資源ファクター :4.0 。新開発の「ナノチタン触媒」を採 現 する「給・排・気流制御システム」 。 そしてエアコン内部の 用した「ナノチタン除菌・脱臭空清フィルター」 ニオイを低減する「ナノチタン脱臭熱交換器」 。 ディスクアレイサブシステム SANRISE Universal Storage Platform 高度情報化社会 でのデータ蓄積において、情報管理 の 高速化 や 安全 性、信頼性の向上を図るために、複数台の「ストレージ装置」を仮想的 に統合し、1 台 のストレージ 装置 ハードディスクとして 利用 できるよう にした IT 社会に 必要不可欠な装置 です。 既存 の 異種 ストレージ 環境 PAGE 「製品含有化学物質一元管理シ ステム」 ⇨ P.14 参照 を高度な統合ストレージシステムへと進化させて 、 ストレージとデータ 利用の効率化、管理・運用の負荷低減や高度なデータ活用を実現して います。 環境効率の向上度合い (ファクター)算出値 (基準製品:2000 年) 温暖化防止ファクター:26.1 資源ファクター :25.8 50 日立グループ CSR 報告書 2005 next eco 中間圧 吸熱 に適 し た 液状 の冷媒 環境効率の向上度合い (ファクター)算出値 (基準製品:1994 年) 排気ユニットのダンパーの切り換えにより給気・排気・気流制御まで 実 環境配慮 ポイント 製品含有化学物質一元管理システム(P.14 参照 ) を適用しています。 エネルギー 消費効率 の 向上を図るとともに、ニッ ケ ル 水素電池 の 採用 や、製造 プロセスの 鉛レス 化 を 実施しました。 RoHS 指令*適合製品(2005 年 4 月∼)です。 低圧 吸込口 気液分離器 ガス状冷媒 が 液状冷媒 と 混 じった液状 の冷媒 ガス状冷媒 を分離 世界初(インバーターエアコンにおいて。 2004 年 11 月 16 日現在)の「ダブル ガスインジェク ション ロスと なる ガス状冷媒 を リ サイ クルして 効率アップ 環境配慮 ポイント エアコンの心臓部である圧縮機と冷凍 サイクルに [輸送による CO2 排出量] CO2 排出量(kt/ 年) 総輸送量(kt・km/ 年) 3,000 595 344 362 2,000 600 輸送による CO2 排出量 453 425 400 1,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 200 航空機 船舶 鉄道 0 トラック (年度) [改善された HDD の外装箱] Eco-Products 輸送における負荷低減 改善前 改善後 輸送の効率化 梱包材の削減とその事例 CO2 排出量の削減 梱包材の削減は、省資源化はもとより、輸送の合理化 モノづくりには、部品の調達や 完成品の輸送など、物 を可能にし、CO2 削減にもつながります。容器包装リ 流が不可欠ですが、それにより CO2 も排出されます。 サイクル 法に 基 づく、日立グループの 2004 年度 の 容 2004 年度の日立グループが関わる輸送作業によって 器包装委託料は、98 年度比 28% 削減を実現しました。 生じた CO2 の排出量は 453kt でした。2001 年度以降 日立製作所ユビキタスプラットフォームグループと(株) 増加していますが、その理由は、海外のハードディスク 日立物流は、DVD レコーダー「Wooo[ウー!]」の 包装 事業、国内 の自動車機器事業 の 拡大による事業所 の において、省資源設計にユニバーサルデザイン(P.16 参照)を取り入れた、新しい外装箱を開発しました。 現在、日立グループでは、梱包 の 省資源設計 による パソコン 包装設計 で 培ったノウハウを 生 かしたもの 製品積載効率 の 向上 やリターナブル 化 による輸送 の で、耐衝撃性を 確保しながら、段 ボール 展開面積を 効率化、また長距離輸送においては、トラック輸送か 18% 削減 することに 成功。 パソコンに 続き、2 年連 ら鉄道・船舶輸送との 併用 へと切り替えていく、モー 続で「グッドパッケージング賞」を受賞しました(注 2)。 ダルシフト(注 1)の拡大を推進しています。 また、梱包 のリターナブル 化 においては、 (株)日立 モーダルシフトによる CO2 削減とその事例 グローバ ルストレージテクノロジーズと(株)日立物 (株)日立産機 シ ス テ ム 習志野事業所 は、2004 年 流が、海外生産拠点 へのHDDの輸送時に、使用 する 10 月より、関西物流 センタ向 け 製品( モーター、ポン 外装箱の繰り返し利用回数を1回から4回に改善。包 プ 製品 )の 60% を、鉄道を利用した 配送に切り替え、 装材 の 廃棄量 を 80% 削減しました。 これ は、外装 2005 年 3 月までに、CO2 の 排出量で、約 60t の 削減 箱に強化段 ボールとスチール 製 のパレットを使用し、 を実現しました。 キャップを外装箱の上下に配置し、耐久性を向上させ モーダルシフトには、鉄道輸送とトラック輸送との 組 ることにより実現しました。 また、マガジンケースの み 合 わせなど、細 かな管理 が 必要 です。 そこで 同社 収納方法 や、緩衝材枚数 の 見直しを行 い、製品積載 は、出荷関連情報 の 電子化(出荷指示情報・倉庫管理情 効率の向上とテープ封止も廃止しました。 [DVD レコーダーの外装箱] 注 2: (社)日本包装技術協会主 催 の日本 パッケージングコンテ ストで「グッドパッケージング賞」 (電気・機器包装部門)受賞 [モーダルシフト:日立産機システムと日立物流の事例] 績検証や改善に活用しています。 日立 マクセル(株)京都事業所 では、ビデオテープ、 PAGE 「ユニバーサルデザイン」 ⇨ P.16 参照 増加(環境面の実績データ範囲拡大)によるものです。 報 )を進 め、最適な配車を行うほか、データによる実 注 1:モ ーダ ル シ フト=主 とし て、幹線貨物輸送 から省 エネ・ 低公害 の 大量輸送機関 である 鉄道または 海運 へと転換し、鉄 道・海運 とそ の 末端 のトラック 輸送 を 機動的 に 組 み 合 わ せ た 輸送を推進すること 習志野 事業所 東京 600 km ターミナル 関西地区 共同発送 関西 物流センタ 梅田 ターミナル ミニディスク、コンピュータテープなどの 国内営業倉 庫向 けの 輸送 において、これまで 実施してきた 関東 [モーダルシフト:日立マクセルの事例] 営業倉庫 方面 への 鉄道輸送に加え、新 たに京都−福岡間 の 輸 鉄道輸送へ切替え 送に鉄道利用を開始しました。 2004 年度は、鉄道輸 送 の 比率を前年比 で 約 40% 拡大し、約 550t の CO2 京都事業所 鉄道輸送へ切替え 排出量の削減を実現しました。 鉄道輸送へ切替え 600 km 野田 600 km 東京 700 km 福岡 エコプロダクツ & ファクトリー next eco 51 Eco-Factories 地球温暖化防止 CO2 削減の目標と成果 点を目標に掲げています。 国内 1. CO2 総排出量を7% 削減(1990 年度比) 日立 グ ル ー プ 全体 の 温暖化防止 へ の 活動 に 対し、 2. 生産高 CO2 原単位を 25% 削減(1990 年度比) または業界団体の個別目標(注 2) 2004 年度 は、50 億円 の 省 エネ 投資( 注 1)を 行 い、 注 1:省エネ投資=ポンプやファ ンのインバータ化と台数運転化 のための制御装置、電力監視と 空調 の 最適制御 システムの 導 入などの費用 原油換算で 26 万㎘ / 年の削減を行いました。 この 達成 に 向 け、2003 年度 から、日立 グ ル ープ は 地球温暖化の主要因と考えられる CO2 の排出量では、 「CO2 排出量削減制度」を 導入して います。 第 1 種 2004 年度 の 日立 グ ル ープ( 国内 )は、2,586kt-CO2 エネルギー 管理指定工場を対象に、各年度 の 排出量 で、基準年比(1990 年度比)では、20% 削減していま 目標を定め、目標達成度合いに応じて A から D までの す。 前年度 の 2,283kt-CO2 より 13% 増加して いま ランク付けを行うものです。客観化された評価が、グ す。 これは 新 たに 8 つの 第 1 種 エネルギー 管理指定 ループ各社の経営層の指標にもなっており、これが契 工場 が日立グループの 連結子会社として 加 わったこ 機となり省 エネ活動 の 予算を重点的 に 配分 する会社 と、生産高 が 前年度より 13% 増えたこと、および 電 も増えています。 力 の CO2 換算係数を従来と異なる方法 で 算出したこ 2004 年度 の 評価結果 は、当該年度目標を 達成した とが 要因 です。 従来 は、電気事業連合会 が 公表した A ランクの 事業所数 が 26 から 32 へと増加して いま 2010 年予測値を直線補間 で 算出した 換算係数を使 す。 この 結果は、イントラネットに掲載 するとともに、 用していましたが、2004 年度から、経済産業省産業 グループ 会社 の 経営層に報告しています。 この 制度 構造審議会 での 予測値 0.36t-CO2/MWh に固定しま が、CO2 排出量削減 への 活動を加速させることを期 した。 これにより、自助努力 が 明確 になるとともに、 待しています。 換算係数 の 変動 に 毎年左右されることなく、CO2 排 海外 出量を算出することができるようになります。 地球温暖化防止 は日本 だけの 問題 ではなく、グロー 一方生産高 CO2 原単位 でみた 場合 は、国内 で 81% バルに 取り組むべき課題 です。 また 近年、海外 に 生 から 76% に改善しています。 産拠点 が 移行して い る 影響 から、海外 で の CO2 排 日立グループは、2010 年度において、国内 で 次 の 2 出量 が 1990 年度に比 べて 1.3 倍に増加しています。 注 2:業界団体 の 個別目標=グ ループ会社が会員になっている 各業界団体 の CO2 削減 に 関 す る自主行動計画 そのため、2004 年度から CO2 削減目標 は、2003 年 [生産高 CO2 原単位、CO2 排出量推移] CO2 排出量 (kt-CO2/ 年)100 101 海外 5,000 国内 4,000 3,000 4,125 3,215 3,630 3,910 0 2,283 (100) 1990 2001 日立グループ CSR 報告書 2005 next eco 80 75 2002 2003 2,586 2,829 2,713 2004 1. 生産高 CO2 原単位を 2010 年度までに 5% 削減 (2003 年度比) 100 80 なお、2004 年度の結果は事業拡大などにより、2003 60 (80) (97) (93) 基準 52 76 3,628 3,932 2,755 2,914 2,000 1,000 81 95 度を基準とする次の内容に変更しました。 生産高 CO2 原単位比(%) 2005 2010 年度比で生産高 CO2 原単位が 1% 増加しました。 40 省エネルギー事例 20 0 灯油加熱方法の改善 新規 従来 (年度) 中間目標 最終目標 国内 海外 (株)日立金属若松 は、遠心鋳造法をはじめとした 各 [取鍋加熱装置の従来加熱との比較] 従来 (取鍋を縦置き) 項目 改善後 (取鍋を横置き) 不完全燃焼による 黒煙の発生 前面カバー 完全燃焼 簡易バーナ 損失熱 加熱方法 灯油バーナ (ブロア、 灯油) 圧縮空気 灯油 灯油消費量 (加熱条件) 毎時 100ℓ 加熱時間:60 分 / 回 毎時 60ℓ 加熱時間:20 ∼ 60 分 / 回 燃焼状態、作業環境 不完全燃焼による失火、 黒煙発生の可能性あり 完全燃焼 種 の 鋳造法 で、圧延ロールや 射出成形機用部品など を製造しています。 鋳物 の 製造工程 で、高温(1,400 ℃以上 )の 溶 けた 鉄 ( 溶銑 )を 搬送 する 容器 を 取 鍋 とい います。 主 に 耐 2004 年度は 5 台の除害装置の導入と、SF6 に代わる 火レンガでできていますが、溶銑の温度低下防止と、 代替 ガスの 導入を 図り、CO2 換算 で 7 万 GWPt*の 製品 の 品質保持 のために、あらかじめ 十分 に 加熱し 削減を図りました。 ておく必要 があります。 一般 にその 汎用性 から、簡 SF6 については日立グループでは 総排出量規制 の 考 易式 の 縦置き手動式 の 灯油 バーナが、使用されてい えを取り入れ、以下の削減目標を導入しています。 ます。しかしこの方法では、熱放散が大きく、不完全 1. 中間目標:2005 年度までに 30% 削減 (2003 年度比) 燃焼 や、灯油 の 過剰消費を招きエネルギーロスを生 じます。 これを 解決 するために、 「省 エネ 部会」など 取鍋の加熱状況 2. 最終目標:2010 年度までに 35% 削減 (2003 年度比) で 作業方法を 検討し、自家設計 による横置き式 の 加 熱装置を 7 台新設しました。 さらに 、 この 装置 の 稼働 運転開始時における、鍋加熱条件 の 見直しと最適化 [温室効果ガス排出量および構成] 温室効果ガス排出量(万 GWPt) 150 を 検討し、不完全燃焼 や 過剰加熱 の 防止を 行うこと 130 により、従来と比 べ 56% の 灯油使用量を削減しまし 40 た。 7 台総計では、灯油 320 ㎘ / 年の削減を実現しま した。 海外の省エネ事例 100 10 85 80 21 58 50 6 70 17 50 3 49 42 7 41 34 日立グローバルストレージテクノロジーズは、2004 年 度 に 1 億 8 千万円 の 省 エネ投資を行 い、原油換算 で 0 2000 注 3:温室効果 ガス= CO2(二 酸化炭素)、CH4(メタン)、N2O ( 一 酸 化 二 窒 素 )、PFC( パ ー フルオロカー ボン )、代替 フロ ン 類 の HFC( ハイドロフルオロ カ ー ボ ン )、SF6( 六 フッ 化 硫 黄)の 6 種類。 代替フロン 類 の 温室効果 は CO2 の 数百∼数万 倍とされる HFC PFC SF6 2001 2002 2003 7 2004(年度) 3,100 ㎘ の 効果をあげました。 このうち、シンガポー ル 事業所 では、クリーンルーム 内 の 空調環境をかえ 新エネルギーの導入 ずに 空調 の 冷水温度を 1 ℃上 げるといった 対策 によ 太陽光発電 などの い わゆる 新 エネル ギ ー の 導入量 り、原油換算で 600 ㎘ / 年の省エネを実現しました。 は、2004 年度 は 熱 1.6 万㎘( 原油換算 )、電気 7,400 万 kWh で し た。 占 有 割 合 は 熱 で 4.3%、電 気 で 温室効果ガスの削減 1.6% と前年度とほぼ 同じで す。 また日本自然 エネ 工場 の 製造工程 では、CO2 だけでなく温室効果 ガス ルギー(株)を通じて風力発電の委託を行っています。 ( 注 3)で あ る、PFC、HFC、SF6 も 排 出 さ れ ま す。 「2005 年日本国際博覧会( 愛・地球博 )」に おける日 日立グループでは、これらの 3 ガスは 主に「薄膜プロ 立グループ館では、その電力使用量の約 90% をこの セス」 「高圧遮断機製造プロセス」から排出されていま 風力発電でまかなっています。 す。 これを削減 するため、ガスの 代替化と除害装置 日立製作所 は 地球温暖化防止 の 国民運動「 チー ム・マイナス 6%」に参加しています。 の導入を進めています。 エコプロダクツ & ファクトリー next eco 53 Eco-Factories 化学物質削減 注 1:CEGNET = Chemical Environmental Global Network の略 化学物質のリスク管理 以下の取扱量の物質についても、年間 10kg 以上の取 日立グループでは、IT ネットワークを用 いたグループ り扱 いのある物質を集計しています。大気 や 公共水 共通の化学物質総合管理システム「CEGNET」 ( 注 1) 域などへの 排出量、廃棄物としての 事業所外 への 持 を、国内 では 1998 年から取り入 れ、化学物質 のリス ち出し、下水道に排出した移動量を管理しています。 注 2:削 減 対 象 物 質=日 立 グ ル ープ の「禁止」 、 「削減」物質 および事業所が選定した物質 ク管理を行っています。 2004 年度 は、対象 354 化学物質群 のうち、127 物 注 3:SPM =浮遊粒子状物質。 大気中 に 浮遊 する 粒子状物質 で あって、そ の 粒径 が 10 マイ クロメートル以下のもの 化学物質を新規に導入 する際 は、有害性と法規制な 質群 の 使用実績 が あり、全取扱量 は 約 23 万 t でし どの 情報を 収集 するとともに、化学物質専門委員会 た。 このうち、排出量・移動量 はそれ ぞれ 全取扱量 などが使用の可否を評価 する制度を運用しています。 の 1.4% であり、排出量の上位 3 物質は、塗料などに また、法律 や 条例 で 規制された 有害な化学物質 の 使 含まれているトルエン、キシレンと、プラスチックの 用 に 際しては、事業所内 の 設計、製造、購買 などの 溶媒に使用されるエチレングリコールモノメチルエー 関連部門と連携した管理を行っています。 テルでした。 また、108 事業所 が自治体 に PRTR 法 注 4:光化学オキシダント=オゾ ン、パーオキシアセチルナイト レートその 他光化学反応 により 生成される酸化性物質(中性ヨ ウ 化カリウム 溶液 からヨウ 素を 遊離 するものに限り、二酸化窒 素を除く) 注 5:PRTR 法 対 象 化 学 物 質 = Pollutant Release and Transfer Register の略。 1999 年日本 で 制定 され た「特 定化学物質 の 環境 へ の 排出量 の 把握等及 び 管理 の 改善 の 促 進 に 関 する法律」により、対象 となっている 354 物質群(施行 令別表第一) の届け出を行いました。 [化学物質リスク管理の概要] CEGNET システム 法規制情報 自主管理情報 PRTR 排出・移動量 集計機能 届出 環境負荷低減への自主管理 上記 のほかに、自主的 に、約 1,400 の 化学物質 につ いて、禁止・削減・管理に区分し、排出 や 移動量を管 リスク情報 排出データ フィードバック 理しています 。 また、削減対象物質( 注 2)の 総排出 新規導入時事前審査 化学物質 取扱い 排出削減 量 を 2005 年度 に 70%(2000 年度比 )に 低減 する目 標を定 め、取り組 んできました。 その 結果、2004 年 漏洩防止 度 で 44% まで 削減 することができました。 今後 は、 SPM( 注 3)や 光化学 オキシダント( 注 4)の 低減 の PRTR 法対象化学物質の調査結果 ため、PRTR法 の 対象とならないアルコールなどの 日立グループでは、2001 年 4 月に 施行された PRTR 法「特定化学物質 の 環境 への 排出量 の 把握等及 び 管 理 の 改善 の 促進 に 関 する法律」において、報告義務 (%)] [PRTR 法対象化学物質(注 5)の調査結果(排出・移動量実績(2004 年度)) [削減対象物質の総排出量推移] (kt/ 年) 100 (% ) 15 10 10.6 4.4 10.8 3.9 移動量 1.4 5 6.1 7.4 50 4.7 1.4 3.3 3.3kt 製品などへの使用 (除去処理量含む) キシレン トルエン 24 50 97.2 next eco 5.8 1.8 排出量 235kt 日立グループ CSR 報告書 2005 6.2 6.9 4.0 エチレングリコール モノメチルエーテル 7 取扱量 54 44 スチレン 3 エチルベンゼン 6 取扱量と排出・移動量 70 9.7 3.6 その他 10 排出量 1.4 100 削減対象物質の 総排出量推移 排出量の内訳 0 2000 2001 2002 2003 新規 従来 2004 0 2005(年度) 目標 PRTR 法第 1 種以外 PRTR 法第 1 種 [自主管理物質] 「特定化学物質 の 環境 への PRTR 法: 安衛法 対象物質 禁止物質(100 物質) オゾン層 破壊物質 ベンゼン、ダイオキシンなど 危険物 排出量 の 把握等及 び 管理 の 改善 の 促 (略称「化学物質管 進 に 関 する法律」 理法」) 高圧ガス: 「高圧ガス保安法」 危険物: 「消防法」 安衛法: 「労働安全衛生法」 毒物・劇物 PRTR法 対象物質 削減物質(270 物質) 化審法 対象物質 化審法: 「化学物質 の 審査及 び 製造等 の規制に関する法律」 ジクロロメタン、鉛など 水濁法: 「水質汚濁防止法」 大防法: 「大気汚染防止法」 毒物・劇物: 「毒物及び劇物取締法」 温室効果 ガス オゾン 層破壊物質: 「特定物質規制等 によるオゾン 層 の 保護 に 関 する法律」 (略称「オゾン層保護法」 ) 管理物質(1,030 物質) 高圧ガス スチレンモノマー、 エタノールアミンなど 大防法、水濁法 対象物質 温室効果ガス: 「地球温暖化対策 の 推 進に関する法律」 VOC( 揮発性有機化合物 )にも範囲を 拡大し、排出量 化学物質排出量の削減[日立化成グループ] 削減に取り組んでいきます 。 日立化成グループは、継続的な化学物質排出量 の 削 減 に 取り組 んでいます。 2004 年度 の 化学物質大気 土壌、地下水の汚染予防 排出量は 2,400t で、2000 年度比では 64% 削減しま 化学物質 の 漏洩防止管理として、地下に 埋設されて した。 2005 年度 は 70% 以上 の 削減を目標に 推進し いる配管、ピット、タンクなどを地上設置式に変更し、 ています。 点検 の 充実を進 めています。 地上化 が完了していな 2004 年度の大気排出量削減 への取り組みとして、五 い 地下タンクについては、超音波検査、腐食進行防 所宮事業所 では、粘着フィルム 塗工機 で 使用してい 止対策などの 詳細な点検も行 い、漏洩防止を図って る粘着剤希釈溶剤(トルエン主体)の排出ガス処理設備 います。 (蓄熱燃焼装置)を導入しました。 化学物質 の 使用歴 のある約 200 サイトの 中 で、すで これにより、トルエン排出量を、2003 年度比で 1,000t に 9 割 のサイトについては、地下水・土壌 の 浄化完了 削減しました。 または問題がないことを確認しています。残りのサイ この 排出ガス処理設備は、乾燥炉 や 局所排気 の 溶剤 トでも対策を進 め、浄化完了後も、引き続き地下水の 排出 ガスをすべて 集合ダクトに 集 めて 蓄熱燃焼装置 監視を行っていきます。 に 導入し、高温下 で 完全燃焼させてクリーンな 浄化 排出ガスにし、排出口から大気に放出します。 PCB 使用機器の保管 また燃焼熱は、熱回収装置によって蒸気として回収さ かつて 絶縁油などに使用された PCB(注 6)は、 「ポリ れます。 塩化ビフェニル(PCB)廃棄物 の 適正な処理に関 する 2005 年 度 は VOC 規 制 に 特別措置法」により、保管 の 管理強化と、2016 年 7 対応 するために、さらに排 月までに 処理 することが 義務 づけられています。日 出 ガス 処理装置 を 追加設 立グループでは、長期保管 の 中 での 紛失・不明を 防 置して、自主管理による削 止 するための 施錠・固体管理と、万一 の 機器破損 に 減を推進していきます。 注 6:PCB =その 毒性 から日本 では 製造・輸入ともに 禁止され て いる 油状 の 物質。 長期 にわ たる 保管 の 中 で、PCB 廃棄物 の 不明・紛失 が生じ環境汚染 が 懸念 され、2001 年 7 月 に 法律 が 施 行 され、2016 年 7 月 まで に処理が義務づけられている 備え、漏洩を防止する防液堤・保管箱の使用による適 切 な 保管を 継続 するとともに、適正処分実施 に 向 け て検討を進めています。 排出ガス集合ダクト 燃焼滞留層 蓄熱層 熱回収装置 排出口 浄化排出ガス [溶剤排出ガス処理設備の排出ガス処理フロー] 排出口(大気へ) 排出ガス処理装置(蓄熱脱臭方式) 製造現場 排出ガス 粘着フィルム 排出ガス 排出ガス 燃焼滞留層 (酸化分解) 集合ダクト 塗工機 蓄熱層 (溶剤排出ガス導入) 浄化排出ガス 熱回収装置 蓄熱層 (加熱昇温) 蒸気(熱回収) エコプロダクツ & ファクトリー next eco 55 (国内)] [最終処分量の部門別内訳(%)] [リサイクル方法の内訳(%) 電子デバイス 3 デジタルメディア・ サーマルリサイクル 7 [水の使用量] 情報通信システム 2 物流及びサービス他 1 民生機器 4 使用量(万 m3/ 年) 8,000 電力・産業システム 6 リユース 23 6,000 4,000 マテリアル リサイクル 70 高機能材料 84 732 157 588 197 1,018 77 956 77 2,665 3,114 3,708 4,378 2,000 0 2001 2002 海外上水道 海外工業用水 海外地下水 Eco-Factories 287 293 494 519 774 216 717 23 2,770 2,855 2,344 2,543 2003 2004(年度) 国内上水道 国内工業用水 国内地下水 廃棄物削減と水資源の有効利用 注 1:最終処分量=焼却 などの 処理後、廃棄物を埋立 てによっ て処理する量 注 2:ゼロエミッション=資源循 環を追求し、生産過程全体にお ける廃棄物発生量を限りなくゼ ロにすること。 詳細 な 定義 は、 各社異なる 少人数での実践型の実務教育 最終処分量の削減 リサイクルネットワークの構築 日立 グ ル ー プ は、3R ― リデュー ス( 発生抑制 )、リ 日立製作所電機グループ、電力グループ、東京エコリ ユース(再使用)、リサイクル(再資源化)の推進による サイクル(株)は、建設現場 で 発生 する制御盤などの 最終処分量( 注 1)の 削減 に 努 めています。 1998 年 電機品をリサイクルするネットワークを構築しました。 度 を 基準 に 2005 年度までに 80% 以下、2010 年度 電機品 の 多くは鉄スクラップとして、海外も含 めた市 までに 70% 以下 に 削減 することが目標 で、2004 年 場に一般的に売却されていますが、東京エコリサイク 度 は 62% を 達成しました。 2003 年度 から 2 年連続 ルはこれを手分解し、その 90% を再資源化していま して、2010 年度 の目標値を達成しており、新規目標 す。 コストは発生しますが、不法投棄、不当転売など の設定に向けた検討も進めています。 のリスクを低減することが重要と考えています。 また、最終処分量 の 削減指標 であるゼロエミッション また、日立金属(株)では廃プラスチック再生設備を導 ( 注 2)を日立 グル ープは「当該年度最終処分率 1% 入し、自社 のみならず、お 客様も含 めた社外 の 廃プラ 以下かつ最終処分量 5t 未満」と定義し、これを推進し スチックをプラスチック原料としてリサイクルしていま ています。 2004 年度は前年比 29 事業所増え、71 事 す。日立グローバルストレージテクノロジーズのタイ工 業所が達成しています。 場 では、クリーンルームから廃棄されるアルコール 含 有布をセメント工場の燃料に再利用するなどし、各所で [廃棄物最終処分量削減推移] (kt/ 年) 100 150 0 国内 海外 最終処分量削減推移 148 82 135 63 147 81 100 50 (%) 新規 従来 200 72 66 1998 1999 (62) 98 51 103 59 96 53 47 44 43 2001 2002 2003 92 59 66 2000 103 57 53 2005 目標 50 0 2010(年度) 目標 (排出量 kt/ 年) 800 新規 従来 600 400 国内 海外 再資源化率推移 79 765 216 549 702 113 589 772 670 48 622 678 130 117 84 85 708 711 143 150 56 日立グループ CSR 報告書 2005 next eco 物処理を委託 することが 多 い日立製作所日立事業所 では、実務 に 直結した 講義を 行 い、受講後 は 試験を 565 2004 年度までに、90 人が認定されました。 100 水資源の有効活用 冷却水 の 循環利用、生産性向上を図り、用水使用量 50 642 561 (%) の 削減を行っています。 たとえば(株)日立 ディスプ レイズでは、イオン 交換、逆浸透膜、限外濾過 の 設 561 備を導入し、再生水を利用しています。 これにより、 200 0 法投棄に巻き込まれないためのリスク対策として、担 実施し 合格者 を 環境管理者として 認定して います。 [廃棄物発生量推移] 1,000 廃棄物 の 適正処理を徹底し、廃棄物 の 違法処理 や 不 当者 の 教育を重視しています。 特に現地工事 で 廃棄 46 33 2004 適正処理教育の実施 70 80 119 66 業務形態に合わせた廃棄物削減を進めています。 100 1998 1999 2000 2001 2002 2003 0 2004(年度) 2004 年度は日立グループ 全体 で 水 の 使用量を 78% (2001 年度比)まで削減しました。 ステークホルダーとの共創 日立の行動の原点であるお客様や地域社会。 ビジネスをともに創る株主・投資家の皆様。 イコールパートナーである調達先。そして日立を支えている社員。 日立グループは、こうしたステークホルダーの皆様と 「持続可能な社会を共に創ること」をめざしています。 そのためのパートナーシップの構築として、情報開示と対話、 地球市民としての活動に力を注いでいます。 写真左 から時計回り:エコプロ ダクツ 国 際 展、日立 製 作 所 中 央研究所での社会科見学実施、 環境タウンミーティング グローバルな情報開示 地球市民活動 エコプロダクツ国際展への出展 事業所内の自然を地元に開放 日立 の 環境活動を開示 する活動 はグローバルに推進 創業者・小平浪平 の 言に「よい 立木は切らずによけて して います。 2004 年 9 月 2 日∼ 9 月 4 日、マレーシ 建 てよ」があります 。 これを受け 継ぎ、事業所 の自然 ア・クアラルンプール 市で、日本以外のアジアでは初 環境 は 大切 に 守り、地元 に 開放し、交流を 図ってい となるエコプロダクツ展「エコプロダクツ国際展 2004 ます 。 マレーシ ア 」 ( 注 1)が 開催 されました。 世界 から 集 たとえば 1942 年、東京都国分寺市 に日立製作所 の まった 約 80 の 企業・団体とともに日立グループも参 中央研究所を建設 する際、構内 の自然環境保全に努 加。 「Next Eco Together with HITACHI」をテーマ め、庭園には今も、約 27,000 本の樹木や、 「野川」の にマレーシアの日立グループの 生産拠点、環境配慮 源流 の 一 つである湧き水も見 ることができます。 大 製品、鉛フリー 対応プリント基材、アモルファス材料 池には白鳥 が、周辺 の 林には数種類 の 野鳥 が飛来 す などを紹介しました。 る、豊 かな自然環境 です。 年 に 2 回、地域 の 方 に 庭 園を開放し、毎年約 3,500 人 が 訪 れ、小学校 の 社会 教育・啓発の冊子 『みんなでエコのおはなし』 WEB http://greenweb. hitachi.co.jp/pdf/ecomorisurpraise.pdf 対話 科見学にも活用されています。 環境タウンミーティング 教育・啓発『みんなでエコのおはなし』 2001 年度より毎年、環境活動 への 対話 の 場「環境タ 子どもたちに「 エコマインド」を伝えることを目的 に、 ウンミーティング*」を実施しています。 4 回目となる 2004 年 3 月に発行した『みんなでエコのお話』。日立 2004 年度は、開催地をこれまでの 東京地区から、初 グル−プ 社員と地域 の 方々など、20 万世帯 に 配布し めて日立製作所 の 生産拠点 がある茨城県 ひたちなか ました。 2005 年は『みんなでエコのおはなし ― 森 市 で 行 いました。 地域 の 皆様に水戸事業所をご 覧 い の小さなサプライズ』編を発行。自然環境への興味を ただきながら、生産拠点 における環境活動 について 高 めるために、森 の 役割 や 力、日立グループの 事業 の質疑応答や、パートナーシップに対 する率直なご意 所内 にある自然環境とこれを守る技術 について 紹介 見などを伺いました。 しています。 対話を通じて明らかになったのは、広大な敷地を有し 総合学習への支援 長く活動しながら、地元 の 皆様 に 事業所内 での 生産 将来を担う子どもたちに、地球環境の向上に向けて、 活動 や 環境管理活動について、十分には 伝 わってい 企業がどのように取り組んでいるかを伝える努力も重 ないという事実でした。 要 です。日立製作所は、中学校 の 総合学習 の 一環と 課題は、より伝 わりやすく、よりわかりやすく、より双 して、中学生の会社訪問を受け入れています。 2004 方向での情報開示を推進していくことです。今後、長 年度は、東京都板橋区立志村第四中学校 の 6 人 の 生 Federation of Malaysian Manufacturers)、 マレーシア生産性本部(NPC、 National Productivity Corporation, Malaysia)主催 期的な視野 で 取り組 み、地域に根ざした、深 いコミュ 徒が会社を訪問しました。現在、日立が最も力を注ぐ WEB ニケーションへと、発展させていきたいと考えます。 環境対策や、製品製造時 の 対策、地球温暖化防止 の 注 1: エ コ プ ロ ダ ク ツ 国 際 展 2004 マレーシア=国際機関 ア ジア 生産性機構(APO、Asian Productivity Organization)、 マレーシア製造連合会(FMM、 環境タウンミーティング ための 技術 のほか、紙 のリサイクル 方法 について 紹 http://greenweb.hitachi. co.jp/stakeholder/ townmeet04.html 介しました。 ステークホルダーとの共創 next eco 57 サスティナブルビジネスモデル 日立グループは、経済・社会・環境のバランスをとり、 永続性のある「サスティナブルビジネスモデル」の構築に取り組んでいます。 すでに、リサイクル、リユース、リデュースを中心とした循環型社会に向けたビジネスモデルを実現し、 推進しています。また、サスティナブルビジネス部会を設立し、 日立グループ各社の情報を共有化することにより、技術・研究開発を含む、 サスティナブル社会を拓く新しいビジネスモデルを推し進めています。 資源循環モデル 立 て 処分 ではゼロエミッションを 3 年連続達成してい PVC 材リサイクル率 95%[日立電線グループ] ます。 2005 年、 「家電リサイクル 分野でのゼロエミッ 使用済 みの 電線を建設現場などから回収し、再資源 ション達成」で第 9 回「リサイクル 技術開発本多賞」を WEB 化 するビジネスモデルにおいて、日立電線グループ 受賞しています。 日立電線 廃電線回収ネットワーク & は、先駆的な役割を担ってきました。 近年、同社が注力しているのがパソコンのリサイクル 1972 年に廃電線 のリサイクル 技術に着手し、銅と被 です。 それには、HDD に残ったデータの 流出防止 が 覆材の回収・粉砕・再ペレット化を確立してきました。 重要となりますが、物理的な破壊による漏洩防止サー 2000 年に廃電線回収を全国規模で展開し、北海道か ビスを導入して対応しています。 お客様のオフィスに ら九州までの 6 カ所 の 拠点 で 回収を実施しています。 出向き、実施することも可能なサービスです。工場内 回収後 の 電線は種類別に分類し、太 い 電線は解体作 では指静脈認証などセキュリティ管理を施した専用の 業により、細 い 電線は細かく破断し、銅材と被覆材に 作業室を設け、パソコンのリサイクル 処理を行ってい 分けます。 ます。処理後は、家電品と同様のリサイクルシステム 被覆材 の 分離には、素材 の 比重 の 違 いを利用した 水 により、金属、プラスチックなどへ 再資源化を行 いま 比重分別方式と業界に先駆けて 導入した帯電度合 い す。 HDD 以外にもフロッピーディスク、磁気テープ、 の 相違を 利用 する静電分離方式を 使用 することで、 CD-ROM などの媒体も同様の処理を行っています。 リサイクルシステム http://www.hitachi-cable. co.jp/eco/recycle.htm PVC 材のリサイクル率は 95% までに達しています。 PCリサイクルに情報漏洩防止サービス導入 [東京エコリサイクル(株)] 静電分離システム 摩擦帯電された 混合プラスチック 東京 エコリサイクル(株)は、家電リサイクル 法 に 対 WEB 東京エコリサイクル http://www.tokyo-eco.co.jp/ 応する会社として、1999 年に設立されました。 2004 −帯電 +帯電 年度実績 で、家電 4 品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコ 電極(+) 供給トレー 高圧電源 ン )の 再商品化率( 有価物 )は 基準を 大幅 に 超え、埋 回転ドラム電極 分離回収容器 接地 [廃電線リサイクルフロー] ナゲット 外 皮 解 体 銅 分 離 精 製 選 別 イ 回 収 ナゲット被覆材 サ 廃 電 線 皮はぎ解体 リ 回収された 廃電線の山 ク ル 特徴 一般工事現場からの回収 ビル新築 : 作業屑 ビル解体 : 撤去廃電線 58 日立グループ CSR 報告書 2005 next eco 電線の種類 選別 振動比重分別 ナゲット銅 エネルギー循環モデル [機密情報の処理・リサイクル] 省エネサービス・ソリューション「HDRIVE」 IT 機器 (PC、サーバなど) 情報記録媒体 ドライブ ) 」事業を展開しています。 これは省 エネ効果 の 見込 めるファン・ポンプ・ブロワを 対象 に、日立 の HDD FDD MO CD VTR インバータと高圧モーターをお客様に無償 で 設置し、 リ サイ クル・適正処理 に省エネを実現する、省エネサービス「HDRIVE(英知 ユーザー責任 データ消去・破壊 日立製作所は、お 客様 の 初期設備投資費用をかけず ユーザー資産(機密データ) 作業委託 産廃委託 10 年間の契約中に毎月の省エネ効果の一部をサービ 東京エコリサイクル ス 使用料としてお 支払 いいただくサービスです。 省 エネ 効果 は、稼働状況監視装置 で 計測 され た 設備 例)HDD 破壊サービス→物理破壊、オンサイトサービスも 資源回収 の 稼働 デ ータから 計算 されます。 また、HDRIVE は 1 台あたり 約 15 秒で 穿孔 お 客様 の 操業変動などの 投資リスクを軽減しながら、 キャッシュフロー 重視型の経営に適合した新しい 省 エ ドリル穿孔 (4 ヵ所) ステンレス原料 アルミ原料 貴金属ほか ネ方法 です。 「 エコプロダクツ 2004」において、新し い 環境配慮型 サービスであるとして「第 1 回 エコプロ [ 「HDRIVE」のシステム概要] ダクツ大賞推進協議会会長賞( サービス部門)」を受賞 しました。 2004 年度までに、50 セットの 納入実績 が 稼働状況データ あります。 サスティナブル社会に貢献する事業 日立インバータ 日立モーター ファン・ポンプ・ブロワ 省エネ計算書 機材搬入 お客様工場 新都市交通としてのモノレール開発[中国・重慶市] 日立製作所 アフターサービス 世界各地 で 現在、交通渋滞を解消し、かつ 環境負荷 の 低 い 輸送システムの 導入 が 期待されています。日 メリット通知 使用料お支払い 立 は、跨座型 モノレールシステムを、開発・納入して きました。 東京 モノレールの 開業以来、約 40 年 の 実 績があります。 使用料 ファイナンス窓口 (日立キャピタル(株)) メリット通知 遠隔監視 中国・重慶市 においても 2005 年 6 月、13.7km が 開 業します。重慶市は、急速なモータリゼーションによ る交通渋滞と大気汚染が、年々、深刻化しています。 跨座型モノレールは、これらの課題を解消 する、重要 な新都市交通システムと位置 づけられています。 こ の ほか、シンガ ポー ル のセントー サ 島 に お い ても、 2006 年開業に向け、建設工事が進められています。 跨座型モノレール (中国・重慶市) サスティナブルビジネスモデル next eco 59 T O P I C S ユビキタス技術、 また日立グループ 館 の 開催中 に 使用される電力 の 約 9 割 クリーンエネルギーから環境評価まで を、風力発電 でまかなっています。 これは、日本自然 エネ 愛・地球博「日立グループ館」にみる環境技術 ルギー(株)を通じて 購入した「グリーン 電力」を活用した ものです。 WEB 日立グループは 2005 年 3 月 25 日∼ 9 月 25 日に 開催され さらに、会期終了後 は、パビリオンのコンクリート、アス 愛・地球博 日立グループ館サイト ている「2005 年日本国際博覧会( 愛・地球博 )」に、日立グ ファルト、建築木材、鉄 の 4 品目につ い ては 再資源化率 http://www.hitachi-pavilion. com/ ループ 館を出展しています。 ここでは、 「愛・地球博」のメ 100% を、その他も 95% 以上を計画しています。 インテーマである「自然の叡智」と、日立グループが追求す これら日立グループ館における展示の環境配慮効果を、事 る「最新の IT によるユビキタス社会の実現」というコンセプ 前に CO2 排出量 で 評価しました。 その 結果、従来方法に トに沿って、環境ソリューション技術を紹介しています。 比 べて 約 6 割、441tの CO2 削減効果となることがわかり ました。 この 評価 には、日立製作所 が 開発した 環境効果 の 評価ソ リュ ー ション「SI-LCA( シ ル カ )」を 活 用 し まし た。 「SI- LCA」とは System Integration-Life Cycle Assessment の 略 で、システムやサービスなどについて、設計・開発か らリサイクルにいたるまでの各ステージにおける CO2 排出 量を算出し、評価するものです。 たとえば、今回乗り物に乗っていただくコーナーは 以下 の ように 評価しました。 まず、多くのテーマパークでは、背 注 1:FRP = Fiber Reinforced Plastics の 略。 繊 維 と 樹 脂 を 景 に FRP( 注 1)造形 でジオラマを造り、ロボットを動 かし 日立グループ館外観 ています。 今回導入した MR(Mixed Reality(複合現実感)) 用 い てプラスチックを 成型し、 強度を向上させたもの 出展 テーマは「Nature Contact ∼日立 の IT で 蘇る希少動 技術により背景 はポリウレタン 造形、登場動物 は CG で 制 物達とのふれあい∼」。 絶滅 の 危機 に 瀕 する希少動物を 作されており、センサーの 位置情報をもとに動物の画像は 映像上で 蘇らせ、来場者が希少動物とふれあうことができ 背景のジオラマ像と瞬時に合成されます。 つまりロボットの る体験ゾーンです。 ショーで 使用 する情報表示端末には、 動力や保守の必要性がなく、再生・リサイクルも容易です。 「 モバイル 機器向け 燃料電池」を採用しました。 燃料電池 その 結果、CO2 排出量 は 367t、 標準的な家庭 の 電力使用 とは、メタノールを燃料とし、水素 イオンを空気中 の 酸素 の約 7 万世帯 / 日分に相当 する削減が可能であるとの評価 と反応させ、電気を発生させる発電装置です。振動がなく 結果を得ました。 静かで、排出するのは炭酸ガスと水蒸気のみですが、日立 なお、 「愛・地球博」では入場券システムに世界最小クラス はさらに水が出にくい「電解質膜」を自社開発しています。 0.4mm 角 の 非接触 IC チップ「ミューチップ 」を採用してい パビリオンの 屋外 には「両面受光太陽電池」を 設置しまし ます。 「SI-LCA」を 適用して、従来 の 半券もぎり入場券方 た。 発電した 電力をパビリオンの 一部 で 使用しています。 式と比較した 結果、CO2 排出量 で 27tが 削減可能と評価 両面から効率よく受光 できるため、従来型に比 べて 1.3 倍 できました。 の発電量が得られます。 両面受光太陽電池 燃料電池を搭載した情報表示端末 開催期間中 準 備 ロボット方式 塗料(揮発性有機化合物) ・素材・エネルギー FRP造形 燃料 ロボット制作制御 CO2など CO2 燃料 ポリウレタン造形、HDD(Hand Held Display) 基幹サーバーなど、映像コンテンツ 方式 M R CO2 電力、水、ほか 電力 ①MR映像運用動力 ②ライド運行・制御動力 ③オペレータ工数 ライド制御 軌道構造製作+ライド(乗り物)製作 CO2 軽油 ①ロボット運行動力 ②ナビゲータ付きライド運行・制御動力 ③オペレータ、ライド・ロボット保守工数 軌道構造+ライド(乗り物)制作 素材・エネルギー 終 了 電力、水、ほか CO2など [SI-LCA による日立グループ館の環境評価概要例] 60 日立グループ CSR 報告書 2005 next eco 愛知県内で 産廃処分 CO2など CO2廃棄物 軽油 電力 再生リサイクル ライド制御 CO2 電力 IT機器リユース CO2など CO2廃棄物 next eco 2005年度の活動計画 持続可能な社会のための一歩として 2015 年に向けた環境ビジョンの検討 現在 の 環境ビジョンは 2010 年 へのビジョンです。 2005 年度を迎え、環境ビジョンの シナリオを見直し、2010 年までの目標達成のための具体的計画と 2015 年に向けた長 期プランを検討しています。 環境 CSR 対応モノづくりシステムの導入展開 (P.14 ∼ 15)の 考え方に基 づき、日立グループの 製品 「環境 CSR 対応 モノづくり規程」 含有化学物質管理システムの構築と展開を進めていきます。 RoHS 指令*対象製品に ついては、2006 年 6 月までにシステムの導入を完了させ、また、それ 以外の製品につ いても 2006 年度中 の 構築をめざしながら、日立グループの 製品含有化学物質 の 一元 管理を実施します。 新規目標の達成にむけた活動の推進 ■製品環境効率の向上と環境適合製品の拡大 製品 の 環境効率について 2010 年までの 具体的目標を策定しました。全事業グルー プ、グループ会社に展開し、対象製品を 37 製品に拡大します。 ■調達先の環境活動強化支援 主要調達先 すべてに対し、環境保全活動 の 定着を図るために、2006 年度末までに ISO14001 などの外部環境認証の取得を支援していきます。 ■製品輸送の効率向上 輸送による CO2 排出量の削減を、2010 年度に 2000 年度比で 10% 削減する目標を 定め、輸送効率の向上、モーダルシフトなどの取り組みを推進します。 next eco 「日立グループ CSR 報告書 2005」への第三者意見 本書全般に対して − CSRの自己評価の改善を図りながら 継続してほしいと考えます。 バルディーズ研究会(左から田中宏二郎さん、岡田泰聿さん、緑川芳樹さん、山口民雄さん) ・現状を評価し、課題を将来像に結 びつける方向を提起しており、は ・化学物質の取り扱いに関しては、ツール面での意欲的な取り組みが じめての CSR 報告書作成にあたって 積極的な姿勢 がうかがえます。 ありますが本来的には「使用量削減」が主題であるだけに、これにつ すでに 策定されている「企業行動基準 基本理念」を CSR の 視点 で いての方針や戦略、経年の実績についても記載すべきです。 改 めて 意識化 することによって 実効性を高 めようとしていることは、 ・ 「 ステークホルダーとの 共創」や「 サスティナブルビジネスモデル 」 CSR の 取り組 みの 一 つの 方向性を 提起しており注目されます。 た は、環境、社会、経済 の 全 ての 要素を包含した 概念として、広 い 視 だ、企業の未来像と CSR 自己評価、取り組み 8 方針などを有機的に 点で取り扱ってほしいテーマです。 結びつけ、その構造を明らかにする必要があります。 ・特に目を引くのは 他社にもまだ 例 がない CSR 自己評価 の 実施、開 日立製作所からの回答 示です。 その結果をレーダチャートに示し、ほとんどの分野が高得点 「日立グループ CSR 活動取り組 み 方針」を軸 に、経済、環境、社会 となっていますが、CSR でこれほど高 いレベルの日本企業が存在 す 面 で 企業としての CSR ビジョンを明確にしていきます。 また、自己 るのか 疑問も生じます。 評価 の 仕組み、評価メンバー 等を明確にす 評価については 今回重点的に取り組むべき分野を明確にするため、 ることにより評価の信頼性を高め、改善を図りながら継続してほしい 外部評価機関 の 調査票 などを 参考 に、日立製作所 の 活動を 中心 に と考えます。 試行的 に 行 いました。 今後 は、評価精度を向上させるとともに、グ 「 エコバリュー 2010」に 沿った 堅 ・グループの 環境活動に 関しては、 ループ各社で 共有活用 するための改善に取り組み、日立グループ全 実な活動が理解できます。 また、独自の評価基準「GREEN 21」は、 体としてのレベルアップに努めていきます。 インセンティブとして機能し、実効性の高 い 取り組みを行っているこ 環境面についても 2005 年度に 検討 する環境ビジョン、長期計画に とが高く評価されます。 基づき、CSR 全体の概念との整合などを検討していきます。 「GREEN 21」の評価や 環境効 ・環境経営を一層進展させるために、 率と財務指標を組み合わせた環境経営指標の開発を課題としていた だきたい。 *用 語 集 エコプロダクツ & ファクトリー 日立グループの 環境ビジョンの 1 つのテーマで 、環 境に配慮した製品づくり、生産活動を行うこと ➡P.38、39、40、41、42、49 エコマインド & マネジメント 日立グループの 環境ビジョンの 1 つのテーマで 、社 員 およびその 家族 の 環境教育、啓発活動と環境管 理活動を実施すること ➡P.38、39、40、42、46 62 日立グループ CSR 報告書 2005 環境タウンミーティング ステークホルダーの方々と日立グループが、環境活 動に関して意見交換をする会の呼称 ➡P.39、41、43、57 サスティナブルビジネスモデル 日立グループの 環境ビジョンの 1 つのテーマで 、資 源循環を事業に織り込 んだ製品、サービス、静脈産 業でサポートする事業、エネルギー循環を提供 する システムなどを 通してサスティナブル(持続可能) 社会をつくるビジネスモデルを構築すること ➡P.38、39、41、42、58 ステークホルダーとの共創 日立グループの 環境ビジョンの 1 つのテーマで 、ス テークホルダーの 方々とコミュニケーションを通じ て 共有価値を 育 て 、サスティナブル(持続可能)な 社会をともに創造していくこと ➡P.38、39、41、42、57 ライフサイクル 製品 の 企画、製造 から使用、廃棄または 再利用 に いたるまでのすべての段階(素材、生産、流通、使 用、回収、分解、適正処理) ➡P.14、21、31、38、49 主に社会面を中心に − 持続可能な社会の構築に向けて 将来に向かってのコミットメントを期待します。 麗澤大学 教授 高 厳 本報告書では、日立グループの活動すべてを CSR という観点から整 する将来像が見えてこないことです。 グループ全体の活動紹介に力 理紹介しています。 を注 いだため、 「今後どのような方向をめざすのか 」は 捨象されてし 34 万人 の 社員を擁 する日立グループが CSR への 取り組みを本格化 まいました。 筆者 は CSR 報告書を 現状報告手段 であると同時 に、 すれば、世界 に 少 なからざる影響を与えることは 間違 いないでしょ 将来に向かってのコミットメントを表明 する宣誓媒体 であるとも捉え う。 その 意味 で「社会 が変 わる、日立 が変える」という経営姿勢 は、 て います。 たとえば、キャリア 開発、ダイバ ーシティ、グリーン 調 技術や 製品開発 のみならず、持続可能な社会 の 構築にもそのまま貫 達、土壌浄化コストの事前積立など、自らチャレンジすべき課題を選 徹する考えと感じた次第です。 択し目標年度 や目標値を示し、その 進捗状況を紹介していけば、よ この姿勢は CSR 方針や 推進体制からもうかがい 知ることができます り理解しやすい報告書になるのではないでしょうか。 が、筆者が最も注目したのは、コンプライアンスに関 するグループの 実践志向的な取り組みです。日立の業態からすれば、公共部門との 日立製作所からの回答 仕事が多く独禁法違反リスク、あるいは世界的規模での 事業展開か CSR 報告書 の 初年度版として、今回 は 創業 の 精神 に 基 づく日立 の らすれば、途上国政府関係者等 への 利益供与リスク等が高 いと考え CSR に対 する思想と、今まで 取り組 んできた活動を中心にまとめま られます。日立グループはあえてこれを 直視し、そうしたテーマに した。次年度以降は、コンプライアンスの 徹底、コミュニケーション 焦点をあてた研修や 監査を実施しています。 ここに本気で 取り組む の充実など、従来からの活動はもとより、1,100 社を超えるグループ 姿勢を見て取ることができるのです。 会社 の 多様な活動をより多く紹介し、より具体的な方向性を示して ステークホルダー 別に整理した事例も示唆に富 んでいます。 わけて いきたいと思 います。 また「日立グループ CSR 活動取り組 み 方針」 もダイアローグを通じて 得 た 情報を製品開発に生かし、競争力につ に基づき具体的活動を実践していく過程で、さまざまなステークホル なげていく試みは高く評価しなければなりません。 これが CSR を持 ダーとの 対話を行 いながら、日立 のめざすべき目標に対しての 計画 続的に実践する上で欠かせない前提と思われるからです。 を明示していきます。 社会性報告に関 する改善点をあげるとすれば、それは取り組みに関 GWPt Global Warming Potential(地球温暖化係数 (CO2換算)t)。温室効果ガスの 排出量に地球温暖 化係数(GWP)を乗じて CO2量(t)に換算。地球温 暖化係数 は 温室効果ガスの 地球温暖化をもたらす 効果 の 程度をCO2 の 当該効果に対 する比 で 表した もの ➡P.45、53 ODPt Ozone Depletion Potential(オゾン 層破壊係数 ➡P.45 (CFC(フロン)換算)t) PBB ポリ臭化ビフェニール類、特定臭素系難燃剤の一種 ➡P.40、49 RoHS 指令 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment(EU指令「電気電子機器の中の特定有 害物質 の 使用制限指令」)。電気電子機器を対象と して 、2006 年 7月1日以降 に EU 加盟国 で 発売 する 製品 への 6 化学物質 の 使用を禁止している。EU 加 盟国は現在、25カ国 ➡P.14、31、40、42、49、50、61 PBDE ポリブロモジフェニルエーテル 、特定臭素系難燃剤 の一種 ➡P.40、49 「日立グループ CSR 報告書 2005」への第三者意見 63 「日立グループの環境活動(hitachi green web)」 掲載データ 「日立グループの環境活動(hitachi green web)」では、さらに詳細なデータがご覧になれます。 http://greenweb.hitachi.co.jp/data 項目 カテゴリー next society 報告書関連ページ P.ⅰ 会社概要 掲載データ 実績データ範囲(環境)の対象会社リスト P.2 ∼ 3 2004 年度決算の概要 お客様と社会と日立 P.23 ∼ 27 日立グループ社会貢献活動 調達先(サプライヤー)とともに P.30 ∼ 31 資材調達 グリーン調達ガイドライン P.34 日立を支える社員 男女雇用比率 男女採用者数 障害者雇用率 P.35 育児介護休職取得者数・短時間勤務利用者数 労働災害度数率 next eco 日立グループの環境活動 エコマインド& マネジメント ISO14001 に基づく環境 P.39 取り組みの歴史 P.39 ∼ 40 2004 年度行動計画と実績 P.42 グリーンポイント平均点実績と目標 P.44 ∼ 45 事業活動における環境負荷情報(2004 年度) P.46 ∼ 48 ISO14001 認証取得状況 マネジメントシステム ISO14001 認証取得リスト 環境教育の実施 P.48 法定資格者の必要数と保有数 環境会計の考え方について P.47 ∼48 費用、投資、効果、環境負荷削減効率 費用の部門別内訳比率 投資の部門別内訳比率 投資の対策別内訳比率 経済効果の部門別内訳比率 エコプロダクツ& ファクトリー 環境適合製品 P.49 ∼ 50 環境適合製品登録状況推移 環境適合製品リストおよびデータシート 製品の環境効率 RoHS 指令対象物質の分析ガイドライン 輸送における負荷低減 P.51 輸送負荷状況 自社保有台数に占める低公害車の比率 容器包装委託量 地球温暖化防止 P.52 ∼ 53 生産高 CO2 排出量原単位、CO2 排出量推移 CO2 排出量の部門別内訳比率 使用エネルギー構成の推移 温室効果ガス排出量および構成推移 新エネルギー量 化学物質管理 P.54 ∼ 55 PRTR 法対象物質の調査結果概要 PRTR 法調査結果 PRTR法対象物質の取扱量の部門別比率 PRTR法対象物質の排出量・移動量の部門別内訳 削減対象物質の排出量推移 廃棄物削減 P.56 最終処分量削減推移 最終処分量の部門別内訳 最終処分量の種類別内訳 排出量(再資源化量、減量化量)削減推移 ゼロエミッション達成事業所 廃棄物・有効利用物などの処理フロー リサイクル方法の内訳 ステークホルダーとの共創 情報開示 P.57 サイト別報告書発行状況 サイト別のホームページ公開状況 各社・各サイトの報告書問合せ先 各社・各サイトの環境 Web リンク 表彰 エコプロダクツ展 エコプロダクツ国際展 環境タウンミーティング実施状況 対話 サスティナブル ビジネスモデル 資源循環 エネルギー循環 64 日立グループ CSR 報告書 2005 next eco P.58 ∼ 59 家電リサイクル処理台数と再商品化率 パソコン回収台数と資源再利用率 省エネルギーソリューション サスティナブル社会に 日立環境グループ(環境保全装置などのビジネス紹介) 貢献する事業 日立環境情報ソリューション(環境ソリューションシステム紹介) 2005 年 6 月 株式会社 日立製作所 CSR 推進部 各 位 「日立グループ CSR 報告書 2005」の送付について 拝啓 平素は、当社の事業活動に格別のご高配、ご関心を賜りまして厚く御礼申し上げます。 日立グル−プ の CSR 活動 の 取り組 みをご 報告 する初 めてのレポートである「日立グル ープ CSR 報告書 2005」をお送りいたしますので、ご査収ください。 本報告書では、日立グループの CSR、すなわち企業の社会的責任活動を社会性報告(next society)と環境 報告(next eco)のカテゴリーに分け、昨年度の活動成果を中心に報告しております。 また、報告書の作成・企 画段階と最終段階の 2 度にわたりバルディーズ研究会の方にご意見をいただき、より外部の視点から見たご意 見を反映させるとともに、CSR の権威である麗澤大学の高教授にも日立グループへの期待も含めてご 意見を いただきました。 また、本報告書に加えてホ−ムペ−ジにおいても、その詳細を公開しております。 日立グル−プは、今後も CSR 活動の継続的改善に向けて 一層努力 するとともに、取り組み内容を広くご 理解 いただけるよう、情報開示の充実を図ってまいります。 ご一読いただき、皆様の忌憚のないご意見、ご感想をいただければ幸いでございます。 敬具 (お問合せ先) 株式会社 日立製作所 CSR 推進部 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号 〒100-8280 Tel 03-3258-1111 Fax 03-4564-1454 E-mail : [email protected] 「環境経営報告書 2004」へのご意見 ― アンケート結果(総回答数 67 件) 報告書のわかりやすさ 未回答(6%) 評価いただいた点 普通 (25%) わかりやすい (66%) ・社長 が CSR を 幅広 い 視点 でとらえて 自分 の 言葉で語られているのがよい わかりにくい(3%) ボリューム 未回答(9%) 多すぎる (10%) ちょうどよい (75%) 少なすぎる(6%) 内 容 未回答(12%) (51%) 日立グループ社員(3%) 研究教育 環境NPO 機関 (10%) (9%) お客様 (30%) その他 (40%) 事業所近隣に在住(5%) 新聞 (36%) 今回報告書で反映した点 展示会(3%) ホームページ (13%) 雑誌 (12%) その他 (15%) セミナー(3%) ・全 て を 網 羅 的 に 報 告 す る だ け で は な く、 2004 年度の主張したい報告を明確にしてほ しい お取引先(3%) 報告書の存在を知られた媒体 ・環境負荷情報 で 海外事業所 の 情報 を 明確区 分 し 開示 し て い る 点 は、グ ロ ー バ ル 企業 と しての先進性を感じる ・社会性報告 の 内容 が 少 ない。内容 に 拡大 を 望む よくない(3%) 読み手のお立場 ・内容 が 簡潔 に 表現 さ れ、し か も 用語集 ま で 用意され大変読みやすかった 主なご要望 普通 (34%) よい 主なご要望・ご意見 未回答 (18%) ・今回 の 報告 のポイントを 明確 にし、CSR を 実現している事例を特集で紹介した ・社会性報告の充実 アンケート 株式会社 日立製作所 CSR 推進部 以下にご記入の上、右記までお送りください。 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号〒 100- 8280 FAX 03 - 4564 - 1454 Q1. この CSR 報告書をお読みになってどうお感じになりましたか?(1 つだけお選びください) (1)わかりやすさ □ わかりやすい □ 普通 □ わかりにくい (2)ボリューム □ 多すぎる □ ちょうどよい □ 少なすぎる (3)内容 □ よい □ 普通 □ よくない ● 上記のようにお感じになった理由を具体的にお答えください(内容、読みやすさなど)。 Q2. 報告書の記載内容で特に印象に残った事項を下からお選びください(複数回答可)。 □ 経営者のメッセージ □ 日立グループの CSR 推進活動 □ コーポレートガバナンスとグループ運営 □ コンプライアンスの徹底 □ ステークホルダーとの対話 □ Hitachi CSR Activities 社会性報告(next society) □ お客様と社会と日立 □ 株主・投資家の皆様へ □ 調達先(サプライヤー)とともに □ 日立を支える社員 □ next society 環境報告(next eco) □ 日立グループの環境活動 □ エコマインド&マネジメント □ エコプロダクツ&エコファクトリー □ ステークホルダーとの共創 □ サスティナブルビジネスモデル □ next eco □ 第三者意見 ●上記で印をつけられた中で、具体的に印象に残ったことがございましたらご記入ください。 Q3. 主にどのようなお立場でお読みになられているかをお聞かせください(1 つだけお選びください)。 □ お客様 □ 株主・投資家 □ 調達先 □ 政府・行政関係 □ 研究・教育機関 □ 報道機関 □ NPO 関係 □ 日立グループの事業所近隣に在住 □ 日立グループの社員・家族 □ その他( ) Q4. この CSR 報告書をどのようにお知りになりましたか?(1つだけお選びください)。 □ 新聞 □ 雑誌 □ ホームページ □ セミナー □ 展示会 □ その他( ) Q5. この CSR 報告書では、従来の環境主体の報告から社会面重視の報告に刷新しました。 内容に関しお気づきの点などございましたら、お聞かせください。 Q6. 日立グループの CSR 活動に関してご要望があればお聞かせください。 ●ご協力ありがとうございました。以下、お読みの上ご同意いただけるようでしたら下記欄にご記入ください。 ご記入いただきましたお客様の個人情報(住所、氏名、電話番号、年齢、メールアドレス、ご職業・勤務先)については、 「日立グルー プ CSR 報告書 2005」へのご意見を把握し、お問合せや報告書の継続送付等のご依頼があった場合には、その対応のために使用いた します。 お名前 (ふりがな) ご住所 〒 E-mail ご職業・勤務先 男 性 ・ 女 性 年齢 歳