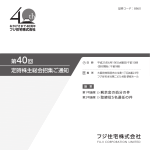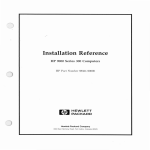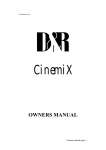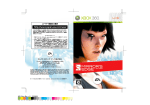Download アップ事項21年
Transcript
H21.12.23 生死事大(しょうじじだい) 生死事大とは、生き死の問題は重大であって、それをいかに超越するかが最大事で あることです。生死を繰り返す、この世の迷いを捨てて悟りを開くことは、いま生き ているこの時しかなくて、最も大切なことであるといいます。生死事大は仏教、特に 禅宗の語です。 禅宗の僧堂では、毎日欠かすことなく、朝夕の時を告げたり、法要の知らせとして 木板(もっぱん)と言う法具を撃ち鳴らします。この木板の表には「生死事大」の墨 書があり、仏教者としての真実を求める最重要課題である生死の問題を明らかにすべ き事を投げかけられています。 しょうぼうげんぞう しょうろく しゅうしょうぎ 道元禅師の主著「正法眼蔵」の抄録ともいえる「修証義」の最初に「生(しょう) いんねん を明らめ死を明むるは仏家一大事の因縁なり、生死(しょうじ)の中に仏あれば生死 あ なし、ただ生死即ち涅槃と心得て、生死として厭うべきもなく、涅槃として欣う(ね こ きゅう じ ん が う )べ き も な し 、是 の 時 初 め て 生 死 を 離 る る 分 あ り 、唯 一 大 事 の 因 縁 と 究 尽 す べ し 」 とあります。 生死の問題は人生そのものの一大の命題であり、生死を明らかにすることは、すな わち迷い、煩悩を超脱し悟りの境地そのものを築くことに他ならないのです。 い か 生とは何か、死とは何か、人間如何に生きるベきか、その究明こそ人として最も大 事な課題なのです。だからこそ、その究明に時間を惜しんで修行すべきだと言う激励 の 言 葉 と し て「 生 死 事 大 」の 語 が あ り 、そ の 語 に 続 く 言 葉 と し て「 光 陰 可 惜 」 (こうい ん お し む べ し )が あ り 、さ ら に「 無 常 迅 速 時人不待」 (むじょうじんそく ときひと をまたず)の語がつづくのです。 し ゅ き 朱子学で知られる朱喜の「少年易老学難成 一 寸 光 陰 不 可 軽 」( 少 年 、 老 い や す く 、 とうえんめい 学なり難し、一寸の光陰 軽んず可からず)の句は有名である。また詩聖・陶淵明の 「歳月不待人」 ( 歳 月 、人 を 待 た ず )の 語 が そ の 句 と 一 つ に 重 な り 、織 り な し て 、生 死 事大 光陰可惜無常迅速 時人不待の語となり、禅門では今も大事な言葉として、修 さくれい 行者を木板のコーン、コーンの響きを通して朝晩、策励し続けているのです。 生まれて死ぬ一度の人生をどう生きるか、それが仏法の根本問題です。長生きする ことが幸せでしょうか。そうでもありません。短命で死ぬのが不幸でしょうか。そう でもありません。問題はどう生きるかなのです。この世において、生まれたものは死 に会ったものは別れ、持ったものは失い、作ったものはこわれます。時は矢のように 去っていきます。すべてが「無常」です。無常ならざるものはあるでしょうか。 平成21年10月26日の第173回国会における鳩山内閣総理大臣所信表明演説 三 「 居 場 所 と 出 番 」 の あ る 社 会 、「 支 え 合 っ て 生 き て い く 日 本 」 ( 人 の 笑 顔 が わ が 歓び) H 21. 12.19 先日、訪問させていただいたあるチョーク工場のお話を申し上げます。 創業者である社長は、昭和三十四年の秋に、近所の養護学校の先生から頼まれて二 人の卒業生を仮採用しました。毎日昼食のベルが鳴っても仕事をやめない二人に、女 性工員たちは「彼女たちは私たちの娘みたいなもの。私たちが面倒みるから就職させ てやってください」と懇願したそうです。そして、次の年も、また次の年も、養護学 校からの採用が続きました。 ある年、とある会でお寺のご住職が、その社長の隣に座られました。 社長はご住職に質問しました。 「文字も数も読めない子どもたちです。施設にいた方がきっと幸せなのに、なぜ満員 電車に揺られながら毎日遅れもせずに来て、一生懸命働くのでしょう?」 ご住職はこうおっしゃったそうです。 「 も の や お 金 が あ れ ば 幸 せ だ と 思 い ま す か 。」 続 い て 、 「人間の究極の幸せは四つです。 愛されること、ほめられること、役に立つこと、必要とされること。 働 く こ と に よ っ て 愛 以 外 の 三 つ の 幸 せ が 得 ら れ る の で す 。」 「 そ の 愛 も 一 生 懸 命 働 く こ と に よ っ て 得 ら れ る も の だ と 思 う 」、こ れ は 社 長 の 実 体 験 を 踏まえた感想です。 こ の チ ョ ー ク 工 場 は 、従 業 員 の う ち 七 割 が「 障 が い 」と い う「 試 練 」を 与 え ら れ た 、 いわば「チャレンジド」の方々によって構成されていますが、粉の飛びにくい、いわ ゆるダストレスチョークでは、全国的に有名なリーディングカンパニーになっている そ う で す 。障 が い を 持 っ た 方 た ち も 、あ る い は 高 齢 者 も 、難 病 の 患 者 さ ん も 、人 間 は 、 人に評価され、感謝され、必要とされてこそ幸せを感じるということを、この逸話は 物語っているのではないでしょうか。 私が尊敬するアインシュタイン博士も、次のように述べています。 「人は他人のために存在する。何よりもまず、その人の笑顔や喜びがそのまま自分の 幸せである人たちのために。そして、共感という絆で結ばれている無数にいる見知ら ぬ 人 た ち の た め に 。」 周利槃特(しゅりはんどく)愚路とも呼ばれた。 H 21,11,23 みょうが 茗荷の名前の元になったお坊さんは、周利槃特(しゅりはんどく)という。周利槃 特は、天竺(インド)の北部に生を受け、兄の摩河槃特(まかはんどく)と共にお釈 迦様に弟子入りした。兄は賢く、お釈迦様の教えをよく理解し、深く仏教に帰依した が、弟の周利槃特は物覚えが悪く、自分の名前すら覚えられなかった。そのため、托 鉢に出かけても、お釈迦様の弟子として認められず、乞食坊主扱いをされ、お布施を 貰 う こ と が 出 来 な い 。お 釈 迦 様 は こ れ を 憐 れ み 、 「 周 利 槃 特 」と 書 い た の ぼ り を こ し ら えて「明日からこれを背負って托鉢に行きなさい。もし名前をたずねられたら、これ で ご ざ い ま す と 、の ぼ り を 指 差 し な さ い 。」と い わ れ た 。次 の 日 か ら 托 鉢 の 時 に の ぼ り を背負っていくと、人々はお釈迦様の書かれたのぼりをありがたがり、たいそうなお 布施をいただくことができるようになったそうである。 さて、兄は、物覚えの悪い弟に、何とかお釈迦様の教えを覚えさせようと手を尽く してやるが、弟の方は、朝に覚えていたものを昼には忘れてしまう。周利槃特は、自 分のおろかさに涙を流して途方にくれた。それを見ていたお釈迦様は「自分が愚かで あると気づいている人は、知恵のある人です。自分の愚かさを気づかないのが、本当 の 愚 か 者 で す 。」と い わ れ 、ほ う き を 周 利 槃 特 に 渡 し て「 ご み を 払 お う 、あ か を 除 こ う 」 と唱えて掃除をしなさいと教えた。 その日から周利槃特は、雨の日も、風の日も、暑い日も、寒い日も、毎日「ごみを 払 お う 、ち り を 除 こ う 」と 唱 え な が ら 掃 除 を し 続 け た 。や が て「 お ろ か 者 の 周 利 槃 特 」 と呼ぶ人はいなくなり、 「 ほ う き の 周 利 槃 特 」と 呼 ば れ る よ う に な っ た 。そ し て 数 十 年 経ち、周利槃特は自分の心のごみやあかを全て除き、阿羅漢と呼ばれる聖者の位にま で な っ た の で あ る 。お 釈 迦 様 は 、 「悟りを開くということは決してたくさんのことを覚 えることではない。わずかなことでも徹底すればよいのである。周利槃特は徹底して 掃 除 を す る こ と で つ い に 悟 り を 開 い た で は な い か 。」と 大 衆 の 前 で お っ し ゃ っ た 。そ の 後、周梨槃特が亡くなり、彼のお墓にあまり見たこともない草が生えてきた。彼が自 分の名を背に荷(にな)ってずっと努力し続けたことから、この草は「茗荷(みょう が )」 と 名 づ け ら れ た と い う こ と で あ る 。 H ,21,11, 7 覆水盆に返らず し ゅ う い き (意味)一度したことは、元には戻すことができない。 出典:拾遺記 周 の 国 に『 呂 尚( り ょ し ょ う )』と『 馬 氏( ば し )』と い う 夫 婦 が い ま し た 。呂 尚 は 、 学問を修めることに力を注ぐ余り、働くわけでもなく、夫婦の生活は苦しかったので す 。そ れ で も 呂 尚 は 、気 に も 止 め ず に 勉 学 に 励 ん で い た た め 、つ い に 妻 は 夫 に 呆 れ て 、 「 と て も あ な た に は つ い て い け ま せ ん 。」 と言って、出ていってしまいました。 呂尚は、なおも努力を重ね、深い学識を備えましたが、依然として貧しいままでし い す い た。しかし、ある日、渭水のほとりで、1人釣り糸を垂らしていると、通りかかった 身分のあると思われる者が、声をかけてきました。話をしてみると、その人物は、賢 せいはくしょう 人 と し て 誉 れ の 高 い 周 の 西 伯 昌 で 、西 伯 は 、 「 あ な た こ そ 、我 が 太 公( 祖 父 )の 望 ん だ 人 物 だ 。」 と 言 っ て 、 彼 を 太 公 望 と 呼 び 、 師 と し て 敬 い ま し た 。 西伯との出会いによって、呂尚は、天下にその名を知らしめることとなりました。 その彼の元に、ある日、出ていった妻がひょっと現れ、 「昔は、食事にも事欠くほどの貧しさでしたのでお暇をいただいておりましたが、 このように立派になられたので、やっぱりあなたの妻としてお側に仕えさせていただ き ま す 。」 と 言 い ま し た 。 く 呂尚は、無言のまま盆に水を汲み、それを庭先の土へこぼすと、別れた妻にその水を すくうように言いました。彼女はその水をすくおうとしましたが、水は土にしみ込ん で救うことができません。そこで呂尚は、言いました。 「 覆 水 盆 に 返 ら ず ( 一 度 こ ぼ れ た 水 は 元 に 返 す こ と は で き な い )。 一 度 別 れ た も の は 、 再 び 一 緒 に は な れ な い も の だ 。」 と 復 縁 を 断 っ た 。 この話から一度起きてしまった事はけっして元に戻す事は出来ないと言う意味で覆 水盆に返らずと、言うようになった。 太公望 周 の 西 伯 は 、あ る 日 、猟 に 出 か け よ う と し て( 獲 物 を )占 い ま し た 。す る と 、 「竜で は お う も な く 、熊 で も な く 、虎 で も 豹 で も な い 。今 日 の 収 穫 は 、覇 王 を 補 佐 す る 人 物 だ ろ う 」 い す い と結果がでました。猟に出た西伯が、渭水のほとりまで来ると、1人の老人が悠然と 釣 り 糸 を 垂 ら し て い ま す 。「 今 朝 の 卦 ( 占 い の 結 果 ) は 、 こ の 人 か も 知 れ な い 。」 と 思 い、老人に声をかけてみると、人物・識見ともに覇王の補佐たるに十分であることが 分 か り ま し た 。「 私 の 太 公 ( = 祖 父 の こ と ) が 、『 周 に 聖 人 が 来 て 、 そ の 者 の お か げ で 周 が 栄 え る だ ろ う 』と 望 ん だ 人 物 と は 、ま さ に あ な た の こ と だ っ た の だ 。」西 伯 は 、大 喜びで語り、太公が望んだ人物ということで、その人物を太公望と名付けました。そ して、この故事が由来で、釣りをする人を太公望と呼ぶようになったのです。 H 21,10,31 耐用年数 耐用年数とは、減価償却資産が利用に耐える年数をいう。長期にわたり反復使用に 耐える経済的に価値があるものの使用又は所有の価値の減価を、各年度に費用配分し ていく場合の、計算の基礎となる。 法定耐用年数 耐用年数は、その性格上、長短によって納税額に影響を及ぼす。そのため法人税法 し い に お い て は 、恣 意 性 を 排 除 す る 目 的 で 、 「資産の種類」 「構造」 「 用 途 」別 に 耐 用 年 数 を 詳細に定め、画一的に扱うこととしている。このように税法で規定される耐用年数を 「法定耐用年数」という。法定耐用年数と会計上の耐用年数は一致しないことがある が、その差額に対しては税効果会計が適用され、繰延税金資産が計上される。 し い 恣意性 「恣」は「し」と読み「ほしいまま」の意味です。典型的な用法:原理原則に基づく のでなく、自分の気の向くままにものごとを決めてしまう状態。 (a) 法 定 耐 用 年 数 減 価 償 却 資 産 の 耐 用 年 数 に 関 し て 、実 務 で は ほ ぼ す べ て の 法 人 で 、税 法 の 定 め る 耐用年数が採用されています。 本来、固定資産はそれが同種のものであっても、操業度の大小、技術水準、修繕 維 持 の 程 度 、経 営 立 地 条 件 の 相 違 な ど に よ り 耐 用 年 数 も 異 な る は ず で す 。と こ ろ が 、 課税の公平化の観点から恣意性を排除するため、原則として税法では、個々の資産 の 置 か れ た 特 殊 条 件 に か か わ り な く 画 一 的 に 定 め た 耐 用 年 数 (「 法 定 耐 用 年 数 」) に よるべきことを要求しています。 使用可能期間を見積もる 購入後、業務の用に供した後に使用が可能である年数を見積もり、その年数を耐用 年数とできる。 減価償却 減 価 償 却 は 企 業 会 計 に 関 す る 購 入 費 用 の 認 識 と 計 算 の 方 法 の ひ と つ で あ る 。長 期 間 に わ た っ て 使 用 さ れ る 固 定 資 産 の 取 得( 設 備 投 資 )に 要 し た 支 出 を 、そ の 資 産 が 使 用 で き る 期 間にわたって費用配分する手続きである。 製造物責任法(PL)法とは 製品の欠陥によって生命,身体又は財産に損害を被ったことを証明した場合に,被 害者は製造会社などに対して損害賠償を求めることができる法律です。本法は円滑か つ適切な被害救済に役立つ法律です。 具体的には,製造業者等が,自ら製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡し た製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害したときは,過失の有無にか かわらず,これによって生じた損害を賠償する責任があることを定めています。また 製造業者等の免責事由や期間の制限についても定めています。 (製造物責任) 第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号 の 氏 名 等 の 表 示 を し た 製 造 物 で あ っ て 、そ の 引 き 渡 し た も の の 欠 陥 に よ り 他 人 の 生 命 、 身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 期間の制限 本法に基づく損害賠償請求権は、原則として、損害及び賠償義務者を知ったときか ら 3 年 の 消 滅 時 効 、ま た は 製 造 物 を 引 き 渡 し た と き か ら 10 年 の 除 斥 期 間 に よ り 消 滅 す る。 ※ 除斥期間(じょせききかん)とは、法律関係を速やかに確定させるため、一定期 間の経過によって権利を消滅させる制度。 製 造 物 責 任 法 の 責 任 期 間 は 引 渡 し 後 10 年 で す 。 2003 年 03 月 20 日 (木 ) 11 時 36 分 医療事故で製造物責任初認定 5000万賠償命令 (共同通信) 東 京 都 立 豊 島 病 院 で 人 工 呼 吸 回 路 が 機 能 せ ず 死 亡 し た 乳 児 の 両 親( 埼 玉 県 在 住 )が 、 医療器具会社2社と都に計約8200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地 裁は20日、2社の製造物責任と病院の事前点検ミスを認め、計約5060万円の支 払いを命じた。 判 決 理 由 で 山 名 学 裁 判 長 は「 そ れ ぞ れ の 医 療 器 具 に 設 計 上 の 欠 陥 は な い 」と し た が 、 接続すると回路が閉塞(へいそく)する点について「使用上の適切な指示、警告がな かった」として2社の製造物責任を認定した。 製造物責任法(PL法)に基づき、医療器具の不備を認めた判決は初めて。病院の 担当医については「接続して安全に機能するかを事前に点検する注意義務を怠った」 と判断した。 問題となったのはアコマ医科工業(東京)の換気器具とタイコヘルスケアジャパン ( 同 ) の チ ュ ー ブ で 、 接 続 し て 呼 吸 回 路 と し て 使 用 す る 。( 共 同 通 信 ) 4、責任期間と耐用年数 P L 法 で は メ ー カ ー の 責 任 期 間 は 、製 造 物 を 引 き 渡 し て か ら 10 年 と 定 め ら れ て い る が、これは厚生省の定める耐用年数より著しく長い。例えば補装具の中で最も多く作 られていると思われるPTB型下腿義足の場合、耐用年数は2年である。責任期間と 耐用年数との関係はどうなっているのか、との疑問がある。これに対する厚生省の見 解は、耐用年数はあくまでも新しく交付するための1つの目安に過ぎない。頻繁に使 う人とめったに使わない人とでは耐用年数は異なる。しかし、製造者側からみると、 10 年 間 の 使 用 に 耐 え る よ う 作 ら れ て い る 補 装 具 は 全 く 無 い と 言 っ て も 過 言 で は な く 、 こ れ に 対 応 す る 何 ら か の 手 段 を 講 ず る 必 要 が あ る 。も し 、10 年 間 壊 れ な い 物 を 作 れ ば 、 恐らく製造価格は数倍にはねあがり、重さも数倍になり、実用的見地からは存在し得 ないことは明らかである。そこで取扱説明書に、耐用年数を明記する、保証書を発行 し、保証期間を耐用年数期間とするなどの方法が考えられるが、果たしてこれらが法 律的に有効であるか否か、疑問が残り、今後の重要な検討課題であることは間違いな いと思われる 家庭製品 2 割 が 10 年 超 え 使 用 P L 法 責 任 期 間 20 年 に 製造物責任法 (PL法) の早期改正を求めている全国消費者団体連絡会PLオンブズ 会 議 は 6 月 26 日 、 ガ ス 湯 沸 し 器 や 石 油 フ ァ ン ヒ ー タ ー な ど の 事 故 は 製 造 か ら 1 0 年 以 上 経 過 し た 製 品 に 多 く 発 生 し て い る と し て 、 同 法 の 責 任 期 間 を 「 10 年 」 か ら 「 20 年 」 に 延 長 す る こ と を 提 言 し た 。 独 自 に 3 0 0 世 帯 を 調 査 し た 結 果 、 石 油 ・ガ ス フ ァ ン ヒ ー タ ー 、 ガ ス 湯 沸 し 器 を 11 年 以 上 使 っ て い る 人 は 2 割 を 超 え た 。 自明灯(じみょうとう) H .21.1 0.18 のぞ お釈迦さまが死に臨んだ際、弟子たちは、誰もたいへん嘆き悲しみました。 「お釈迦様が亡くなられたら、私たちはどうやって、いったい何にすがって生きて 行 け ば い い の で し ょ う ! ..」 集 ま っ た 暗 い 顔 の 弟 子 た ち に 、お 釈 迦 さ ま は 、 「 自 明 灯 、法 明 灯 」と い う「 自 ら を 灯 明とし、法を灯明とせよ」をお伝えになりました。 これは、明かりのない暗い道を、自ら照らす灯りとなれという意味で、意識して常 に自分の心に明かりを灯すように心がけなさい、自分の足できちんと歩き、自らの心 の中に灯を灯しなさいということです。 自分の心の中に灯がない人は、自分自身を照らせないことはもちろん、他の人を照 らすことはできません。人様の灯りに頼ろうとせず、自ら進んで灯してあげよう、と いう気持ちが大事だと思います。 心はどういうわけか放っておくと、暗い考えに偏ってしまいます。ですから、意識 して常に自分の心に明かりを灯すように心がけることが必要です。 そんな感動の灯が、次から次へと点火されて行くことを「灯々無尽」と言います。 これからの人生、周囲から多少の助けはあるかもしれないが、自ら歩む道は自分で 照らしていかなくてはならないと思います。 そんなに努力したわけでもないのに、何故かトントン拍子にうまく行く時がありま す。また逆に、必死に血の出るような努力をしても、全くうまく行かず、どんどん後 退してしまって、落ち込んでしまうような時期もあります。 その波は、ある時は大きく、またある時は小さく、振幅を繰り返し、全体として大 きくうねりながら、人生模様を刻み込んで行きます。たとえ失敗して過ぎ去った日々 があったとしても、それを後悔し悩んでみたところで、覆水は盆に返ることは決して あ り ま せ ん 。重 要 な こ と は 、過 去 に す が り 執 着 す る の で は な く 、こ れ か ら 先 、 「何をし よ う と し て い る の か ? 」、と い う こ と で は な い で し ょ う か 。失 敗 し た り 挫 折 し た と き に こそ、それをバネに変えれば良いのです。 シェークスピアの「過去のことはプロローグにすぎない」という言葉は、今日の、 想像を絶するような激変する時代には、とりわけ当てはまる言葉かも知れません。あ の 時 は 良 か っ た 。 あ の 頃 は 幸 せ だ っ た ..。 そ ん な こ と ば か り 思 っ て い る の は 、 現 在 の あ な た 自 身 が 、そ の 頃 に 比 べ て 、 「 充 実 し て い な い 」、 「 つ ま ら な い 」、 「 何 も な い 」等 々 と、現在の自分を否定的に見つめ、自分自身の心を閉ざしているからではないでしょ うか。過去の栄光にすがらなければいけないほど充実していない自分自身の「現在の 姿」こそが問題なのだと思います。もう一度、頑張って来た自分自身に、改めて暖か く 優 し い 眼 差 し を 向 け て み ま し ょ う 。せ め て 、 「 あ の 時 は 良 か っ た 」、け れ ど 、 「今の自 分 も 素 晴 ら し い ! 」。 「 あ の 頃 は 幸 せ だ っ た 」、で も 、 「 今 も 十 分 幸 せ な ん だ 」。そ う 心 か ら思える自分でありたいものです。 真人(しんじん) 『 荘 子 』( 抄 )・ 大 宗 師 篇 H 21.10 .12 〔真人〕天の働きを知り、人の働きを知る者は、最高の境地に至った者である。天 の働きを知るとは、天に随って生きることである。人の働きを知るとは、人知の限界 を守り、人知の及ばないところ(天)を養うことである。天寿を終えて、若死にしな い 者 は 、知 が 盛 ん な の で あ る 。そ う で は あ る が 、 ( こ の よ う な 者 に も )患 い は あ る 。知 は 対 象 が あ っ て 働 く 。対 象 は 定 ま る こ と が な い( つ ね に 変 化 す る )。ど う し て 、天 が 人 でないのか、人が天でないのか、知ることができるだろうか。してみると、真人があ って、真知というものがあるのである。 な に を 真 人 と い う の か 。古 の 真 人 は 不 幸 に 逆 ら わ ず 、成 功 に 誇 ら ず 、事 を 謀 ら な い 。 このような者は、誤っても悔いず、的を得ても得々としない。このような者は、高い 所に登っても恐れず、水に入っても濡れず、火に入っても熱くない(物事に動揺しな い )。 知 を 道 に 仮 託 す る こ と が で き れ ば 、 こ の よ う な 真 人 の 境 地 に 達 す る 。 〔運命随順〕上古の真人は生を喜ぶことを知らないし、死を憎むことも知らない。 こ の 世 に 生 ま れ 出 る こ と を 喜 ぶ の で も な く 、死 の 世 界 に は い る こ と を 拒 む こ と も な い 。 ただゆうぜんとして行き、ゆうぜんとして来るだけである。生のはじめである無の世 界を忘れることはないが、そうかといって生の終わりである無の世界だけを求めるこ と も な い 。与 え ら れ た 生 は 喜 ん で 受 け る が 、こ れ を 返 す と き も 未 練 を 残 す こ と が な い 。 このような態度を、 「 は か ら い の 心 を も っ て 自 然 の 道 を す て ず 、人 為 を も っ て 自 然 の は たらきを助長しようとしない」というのであり、このような境地にあるものを真人と よぶのである。このような境地にあるものは、その心は一切を忘れ、その姿は静寂に 満ち、その額はひろく平らである。秋の日差しの厳しさがあると思えば、春の日差し の暖かさがあり、その喜怒の情は、ちょうど四季のように、自然のままに移り変わっ てゆく。その心は物と調和を保ち、無限の広さをもつのである。 故に、聖人が兵を用いるとき、国を滅ぼしても人心を失わない。利益を万世に施し て も 、人 を 愛 す る か ら す る の で は な い( 自 然 の は た ら き に 身 を 委 ね た だ け )。故 に 、物 を思い通りにしたいと願うのは、聖人ではない。親しみがあるのは、仁ではない。天 の時に随うのは、賢ではない。利害の道に通じないのは、君子ではない。名を求めて 己を失うのは、士ではない。身を滅ぼして真を失うのは、人を使う者ではない(人為 か ら 解 放 さ れ て い な い か ら )。 真人が好むものは一であり、好まないものも一である。一であるものも一であり、 一でないものも一である。一であるものは天の(無差別の)立場であり、一でないも のは人の(差別の)立場である。天と人とが互いに入り混じる、これを真人という。 随処作主(ずいしょにしゅとなる) <臨済録> H21.9.20 随処に主となる ぎ げ ん さと この語は臨済宗の開祖である臨済義玄禅師が修行者に対して諭された言葉で「随処 に主となれば立処(りっしょ)皆真なり」の一句である。いつどこにあっても、如何 なる場合でも何ものにも束縛されず、主体性をもって真実の自己として行動し、力の 限り生きていくならば、何ごとにおいても、いつ如何なるところにおいても、真実を ほんろう 把握出来、いかなる外界の渦に巻き込まれたり、翻弄されるようなことは無い。その みょうきょうがい と き 、そ の 場 に な り き っ て 余 念 な け れ ば 、そ の ま ま 真 実 の 妙 境 涯 で あ り 自 在 の 働 き が 出来るというものである。 法句経の「おのれこそおのれ自身の主(あるじ)である。おのれこそ自身の拠りど ころである。おのれがよく制御されたならば、人は得がたき主を得る」と云う言葉に まんえん も通じることであるが、その主となっての自在の働きが万縁万境の中で生き生きとし りっしょ て輝いてこそ立処真なりといえることなのだ。 しゃくそん 釈尊最後の説法の「自灯明 法灯明」として知られるが、汝らは自らを灯明とし、 法を灯明とし他を拠りどころとすること無くて修行するものこそ最高処にあり」とあ るように他により所を求めず、己れ自身の中に真実の自己を見いだすことが肝要であ る。即ち「随処に主」たれば如何なるマインドコントロールにも影響されることは無 いはずである。 ちょうしゅう 趙 州 和 尚 は 修 行 僧 の「 一 日 二 十 四 時 間 、ど の よ う に 心 を 用 い た ら よ い の か 」と 云 う 問いに「汝(なんじ)は二十四時間に使われているようだが、この老僧は二十四時間 を使いこなしておるぞ」と答えている。人は皆同じ二十四時間を与えられているが、 時間に追われ時間に使われている人の方多いのではなかろうか。 現代においては、昼夜の隔てが薄く社会は二十四時間稼動して休みがなくなってき ている。そこにわれわれも、ついついその社会の流れに巻き込まれ、主体性も無く、 動かされ忙しい忙しいとあくせくさせられていることを反省させられる。すっかりゆ とりをなくし、時間を失ってきたようにも思える。なんだか知らぬ間に二十四時間に しっせい 使われていることにあらためて気づき、 「 随 処 に 主 と な る 」こ の 語 が 厳 し い 叱 声 と な っ て迫る。 随処に主となるとは、いつ如何なるところにあっても「ここが仏さまから私に与え られた処」として受け止め精一杯、力の限り生き抜くことであろう。 虚無恬淡(きょむてんたん) ・ こ く い へん 出 典 :『 荘 子 』( 抄 )・ 刻 意 篇 H21.9.14 事物に対するいっさいの欲を消し去ったやすらかな心。 こうけつ 心を鍛えずして高潔になり、仁義がなくて身が修まり、功名がなくて国が治まり、 江海に行かずして静かに、導引(道家の呼吸法)をせずして長寿であれば、忘れない ことはなく、有しないものはない。無欲無極となり、あらゆる美が伴う。これが天地 の道、聖人の徳である。 てんたんせきばく き ょ む む い 故 に 、こ う い わ れ る 、「 そ も そ も 、恬 淡 寂 漠 、虚 無 無 為 は 、天 地 の 平 安 で あ り 、道 徳 の 本 質 で あ る 」と 。故 に 、こ う い わ れ る 、 「 聖 人 は 休 む 」と 。休 め ば 平 易 で あ る 。平 易 ゆうかん であれば恬淡である。平易恬淡であれば、憂患も心に入ることがなく、邪気も心を脅 かすことがない。故に、その徳は完全で、精神も損なわれないのである。 し り ょ 生 き て い る と き は 浮 か ん で い る よ う で あ り 、死 ぬ と き は 休 む よ う で あ る 。思 慮 せ ず 、 予想しない。知の光はあっても輝かさず、心の信はあっても無理に守ろうとしない。 寝るときは夢を見ず、起きているときは憂いがない。その精神は純粋で、その魂は疲 れない。虚無恬淡であって、はじめて天徳に合するのである。 地位や名誉、金、女これらは男にとって、欲望の対象である。この欲は何から生ま れて来るのだろうか。 地位や名誉は、人から認められたいからか。それとも威張りたい見栄を張りたいか らか。偉くなり人を見下したいからか。 金は、金さえあれば、何でも手に入るからか。食うに困らないからか。生きてゆく ために必要だからか。金を持っていない者に対して優越感に浸れるからか。苦労しな くて済むからか。 女は、性欲や快楽を満たしたいからか。子孫を残したいからか。 これらは、全て自分の物にしたいという独占欲からくるのではないだろうか。この 独占欲が良いか悪いかは、個人々の考えであるが、これを逆に授かりものと考えたら どうだろうか。 地 位 や 名 誉 、金 は 、自 分 が 一 生 懸 命 に 働 き 努 力 し た 結 果 か ら 授 か っ た も の 。女 性 は 、 お互いに愛し合ったから結ばれたものと考えれば、全ては無欲のなかから自然に生ま れてくる。しかし、人の世はそうは簡単には行かない。努力したから結果が出るわけ でもない。愛し合ったからといって長く続かないことだってある。 良いも悪いも、本来は欲である。全て捨て去り、何があってもそれを素直に受け入 れ、是非に囚われないことが、虚無恬淡に繋がるのではないだろうか。 H 21.9. 7 一行三昧(いちぎょうざんまい) ぼ ん ご じょう と う じ 三 昧 と は 梵 語 の サ マ デ ィ ー( 三 摩 地 )を 音 訳 し た も の で 、 「定」 「 等 持 」の 意 が あ り 、 心を一境に専注することです。 いちじきしん この三昧と、 「 常 に 一 直 心 を 行 ず 」と い う 言 葉 が 合 体 し て 、何 時 と は な し に 一 行 三 昧 の言葉が生まれました。 「 常 に 一 直 心 を 行 ず 」の 語 意 が 理 解 で き れ ば 、自 ず か ら 一 行 三 うなず 昧の意も 頷 くことができると思います。 直 心 と は 、「 直 心 是 道 場 」 の 直 心 で 、 ま っ す ぐ な 心 、 混 じ り け の な い 純 一 無 雑 な 心 、 ど こ 分別執着のない心です。ゆえに、何時でも何処でも何事をなすにしても、そのことに 純一であれというわけです。 仕事をする時には仕事三昧、遊ぶ時には遊び三昧、食事の時には食事三昧、勉強の 時には勉強三昧、その間に一点の雑念妄想をはさむことなく、全身全霊をもって事に あたる、これがまた、一行三昧でもあるわけです。いってみれば「禅」の生命もその 一行三昧から始まり、一行三昧に終わると言っても過言ではありません。 一行三昧に徹した面白い話があります。 こと 漢の李将軍は音に聞こえた勇猛な武人で、殊にその弓術は天下無敵で並ぶ者なきと 称された人です。ある時、猟に出かけて山また山を踏み越えて進みます。と、突然一 はる か な た 匹の大きな虎に出会います。遙か彼方にうずくまっていたのです。将軍は急ぎ矢を番 ちが えて、力一杯、満月の如く引き絞りサッと切って放ちます。狙いは違わず、矢は虎の は 体に立ちます。しめたと思い馳せよってよく見ると、虎ではなく、虎の形をした岩で した。岩に矢が立ったのです。将軍は得意になって、岩に矢が立った例は古今東西聞 いたことがない、もう一度やってみようとばかりに、再び射てみます。四たび、五た び、幾たび打っても矢はついに立ちませんでした。 最初虎と思った時には、一行三昧になることができたのです。射ようとする一念の しか 他 に 何 も な か っ た の で す 。然 る に 岩 と 知 っ て か ら は 、 「 俺 の 弓 術 は 岩 を も 通 す ぞ 、見 て おれ」という雑念妄想が入ったのです。一行三昧になり切れなかったのです。 「 一 行 三 昧 」、 実 に 簡 単 な 言 葉 で す 。 し か し 、 行 じ 難 く 、 到 り 難 い 言 葉 で す 。 H 21,8,30 完 璧 ( 出 典 : 史 記 「 藺 相 如 伝 」) [意 味 ] 1:きずのない玉をいう。転じて欠点がなくてすぐれてよいこと。 2:璧(たま)を完(まっと)うする。 ちょう か し へき しん 趙 の 国 に 和 氏 の 璧 と い う 名 玉 が あ っ た の を 、秦 の 昭 王 が 欲 し が っ て 、十 五 城 と 交 換 しようと強制した。玉を取り上げたまま、城をよこす意志のないことが明らかであっ りんしょうじょ たが、その時、秦に使いした藺相如の働きで、璧をまっとうして帰ることができたと いう故事によって、人から借りた物を返すことを完璧または完趙という。 <史記・藺相如伝> 一つも欠点がなく、完全なこと。完全無欠。璧は、ドーナツ型で平たく、中央に穴の ある宝玉。 和氏の璧:天下の名宝の名。貴重な宝。出典:韓非子 春秋時代、楚人の和氏(かし)は楚の山中で玉の原石を見つけて、これを厲王(れ いおう)に献上した。厲王がこれを玉の細工師に調べさせた。玉の細工師は言った。 「ただの石でございます」和氏は王をたぶらかそうとした不届き者として、左脚を斬 る刑に処された。まもなく厲王が亡くなり、武王が即位した。和氏はまたその原石を 武 王 に 献 上 し た 。武 王 が こ れ を 玉 の 細 工 師 に 調 べ さ せ た と こ ろ や は り 、 「ただの石でご ざいます」と言った。和氏は王をたぶらかそうとした不届き者として、今度は右脚を 斬る刑に処された。武王が亡くなり、文王が即位した。和氏はその原石をかき抱き楚 山のふもとで声をあげて泣いた。三日三晩泣いて、涙は涸れはて血の涙を流した。王 が こ れ を 聞 い て 、人 を や っ て 尋 ね さ せ た 。 「世の中には脚切りの刑を受けたものは多い、 お 前 は な ぜ 嘆 き 悲 し む の か 」和 氏 は 答 え て 言 っ た 。 「私は脚切りの刑を受けたのが悲し いのではありません。宝玉を石と言われ、正直者であるのに嘘つきであると言われた のが悲しいのです」文王は玉の細工師にその原石を磨かせ、宝を手に入れることがで きた。そして、その宝を「和氏の璧」と名づけた。 世に完璧という言葉があるが、本当に完璧はあるのだろうか。私は、仕事には完璧 という言葉はないと思う。どんな仕事でも、どこかに無駄があり改善することがある はずである。プロや職人の世界ではこれでいいという言葉がない。常に「まだまだ」 と自分を精進して行く。これがなければ進歩発展はない。 自 分 を 見 つ め 直 し 、こ れ で い い の か 、こ れ で い い の か と 自 分 に 問 い か け て 行 き た い 。 守 破 離( し ゅ は り ) H 21.8.9 空手道でも、剣道でも、書道でも、茶でも、花でも、その修行の過程を「守」・ 「破」・「離」の三段階に分けている。 「守」というのは、一から十まで型通りにやることであり、それが一通り終る頃に なると、型にはまり融通のきかないものになるので、「破」の段階に入れというので す。「破」とは文字通り「破る」ことで、型にはまったことを破って行く努力をする ことであり、一寸考えると何でもないことのようですが、それは「守」の段階をふま ない人の考えることで、本当に「守」の型にはまった人がそれを破るということは実 に容易でないことです。 空手の中で、型が大変に上手であるが、組手が出来ない人たちを見かけます。大 会でも型は型、組手は組手というふうに分けているようです。本当は型が上手で組手 が強いという様にならなければならないと思います。一つ一つの技が上手になれば、 組手に生かせなければ意味がなく、「守」から「破」ることがむずかしく、出来ない のではないかと思っています。 と こ ろ で 、 「破 」の 段 階 を 卒 業 す る と 、 は じ め て 「 離 」 の 段 階 に 入 る の で す が 「 守 」 からも「破」からも離れて型通りやらなければならぬ時には型通りにやり、型を破る 必要のある時には、これを破りそれこそ「心の欲する所に従って矩をこえず」の境に 達す るの です が、 それ が 仲々 容易 のこ とで はな く、 それ こそ 、一 所 懸 命−一所懸 命 −一所懸命 のこ とな ので す。 と いう のは 、一 応は 「守 」− 「破 」 −「 離」 −の 段階 を経て、自由の境地に遊び得たと思っているうちに、あるいは内的にあるいは外的に その時の自己の力量以上の問題にぶつかると、これではならないという自己疑惑、も し く は 自 己 否 定 に 陥 り 、更 に よ り 高 き 段 階 の 新 た な る も の を 求 め て 、こ れ に 対 し て「 守 」 の修行に進み、「破」に進み、「離」に進み、守破離−守破離、と進むのが真面目 な人生のすがたと思います。 H 21.7. 25 入木道(じゅぼくどう) いしょう 「 入 木 道 ( じ ゅ ぼ く ど う )」 と は 「 筆 道 ( ひ つ ど う )」 の こ と で あ り 、 書 道 の 異 称 で す。既に中国の書論には「入木」のことが記されています。 かんぼく しょう よ れつ 「 余 、志 学 の 年 よ り 心 を 翰 墨 に と ど め 、鍾 ・張 の 余 烈 を 味 わ い 羲・献 の 前 規 を く み 、 りんけい へだ (中略)入木の術に背くも(筆道を十分に極めておりませんが)臨池の志を隔てるこ と な し 」( 孫 過 庭 『 書 譜 』) 近 頃 は 書 家 の 間 で も あ ま り 耳 に す る こ と は な い が 、 出 典 は 唐・張懐懽の『書断』にある王羲之のエピソード。羲之が書いた祝版を工人が削った と こ ろ 、木 に 墨 が 三 寸 も 入 っ て い た と い う 話 で す 。 「 羲 之 の 祝 版 に 書 す 。工 人 、こ れ を 削る。筆、木に入る三分」 この話、木の中に何センチ何ミリも墨が染み込むという、まず起こりえない現象が “書 聖 ”だ か ら こ そ で き た と い う 驚 愕 を 語 っ た も の で す 。 わが国の書道を入木道と呼び慣わしたのは、それだけ王羲之の感化が大きかった証 拠 で 、『 万 葉 集 』 に 「 羲 之 」 と 書 い て 「 て し ( 手 師 )」 と 読 ま せ た の が そ の 好 例 で す 。 「入木道とは書道の異称、藤原行成以来の伝統的な世尊寺家以来の秘説を集大成し た『 夜 鶴 庭 訓 抄 』を は じ め『 才 葉 抄 』 『 入 木 抄 』を 収 録 」と あ り ま す 。い ず れ も 平 安 末 期 か ら 中 世 に 著 さ れ た 書 の “ 奥 伝 ”を 記 し た 秘 本 で あ り 、 江 戸 期 ま で の 日 本 書 道 史 を 代 表する三大書論です。 三 書 と も 通 底 す る 考 え 方 は お お む ね 一 致 し て い ま す が 、異 な る 意 見 も 散 見 さ れ ま す 。 とりわけ目を引いたのは、 『 才 葉 抄 』の 楷 書 先 習 論 と『 入 木 抄 』の 行 書 先 習 論 の 違 い で す。 H 21.7.19 ブリダンのロバ ひ ゆ ブリダンのロバという比喩がある。これは、あるロバがいて、そのロバから等距離 に 二 つ の 食 料 が 置 か れ た と す る と 、ロ バ は ど う な る( ど う す る )か と い う 問 題 で あ る 。 等距離にある(条件が同じである、均衡状態にある)のだから、ロバはどちらを選ぶ ことも出来なくて、飢えて死んでしまうのではないか、というわけである。これはブ リダンという中世の学者の考えたものだとされているが、ショーペンハウアーが調べ たところでは、ブリダンの著作には見あたらないという。我々がこの比喩について具 体的に知ることができる例はスピノザの『エチカ』にある。そこでは、二つの餌では なく、飲み水と食料となっている。 この問題は、人間の自由意志問題の比喩として語られる。もし、自由意志が存在す るなら、ロバ(人間)は、外的条件が同じであっても、内的=自発的にどちらかの餌 を選ぶだろうし、自由意志がなければ、どちらも選べないままに飢えてしまうだろう というのである。 スピノザは後者だと考える。スピノザの考えでは、我々は外的な諸条件によって決 定されているのだ、と言いたいわけである。これに対してライプニッツは、どちらの 解答を選ぶのでもなく、そもそもこの問題そのものがおかしいと指摘している。つま り 、世 界 に は 、そ の よ う な 絶 対 的 な 均 衡 状 態 な ど な い の だ 、と い う わ け で あ る 。実 際 、 スピノザの場合でも、水と食料になっているのは不思議である。これなら二つの同じ 食料が等距離にあるのだとする方が、均衡状態を描くには適している。しかし、これ は 比 喩 で あ っ て 、ス ピ ノ ザ も そ う し た 均 衡 状 態 が 起 こ り 得 る と 述 べ て い る の で は な い 。 サイトカイン・ストーム H 21.7. 10 サイトカインの過剰産生をサイトカイン・ストームと呼ぶ。スペイン風邪やトリイ ンフルエンザによる死亡原因と考えられている。この場合サイトカインは免疫系によ る感染症への防御反応として産生されるのだが、それが過剰なレベルになると気道閉 塞 や 多 臓 器 不 全 を 引 き 起 こ す( ア レ ル ギ ー 反 応 と 似 て い る )。こ れ ら の 疾 患 で は 免 疫 系 の活発な反応がサイトカインの過剰産生につながるため、若くて健康な人がかえって 罹患しやすいと考えられる。 サ イ ト カ イ ン (cytokine) と は 、 細 胞 か ら 分 泌 さ れ る タ ン パ ク 質 で 、 特 定 の 細 胞 に 情報伝達をするものをいう。多くの種類があるが特に免疫、炎症に関係したものが多 い。また細胞の増殖、分化、細胞死、あるいは創傷治癒などに関係するものがある。 ホルモンと似ているが、ホルモンは分泌する臓器があり、比較的低分子のペプチドが 多 い( し か し 、サ イ ト カ イ ン と ホ ル モ ン は 、は っ き り と し た 区 別 が あ る も の で は な く 、 エ リ ス ロ ポ エ チ ン (erythropoietin) や レ プ チ ン (leptin) な ど 両 方 に 分 類 さ れ る こ と が あ る )。 ま た 、 リ ン パ 球 に 由 来 す る サ イ ト カ イ ン を 、 リ ン フ ォ カ イ ン (lymphokine) と い う ことが多い。 一部は医薬品として用いられている サイトカインは多機能的、つまり単一のサイトカインが標的細胞の状態によって異 なる効果をもたらす。例えば免疫応答に対して促進と抑制の両作用をもつサイトカイ ンがいくつか知られている。 ま た サ イ ト カ イ ン は 他 の サ イ ト カ イ ン の 発 現 を 調 節 す る 働 き を も ち 、連 鎖 的 反 応( サ イトカインカスケード)を起こすことが多い。このカスケードに含まれるサイトカイ ンとそれを産生する細胞は相互作用して複雑なサイトカインネットワークを作る。た とえば炎症応答では白血球がサイトカインを放出しそれがリンパ球を誘引して血管壁 を透過させ炎症部位に誘導する。またサイトカインの遊離により、創傷治癒カスケー ドの引き金が引かれる。 サイトカインはまた脳卒中における血液の再還流による組織へのダメージにも関与 す る 。さ ら に 臨 床 的 に は サ イ ト カ イ ン の 精 神 症 状 へ の 影 響( 抑 鬱 )も 指 摘 さ れ て い る 。 明 珠 在 掌( み ょ う じ ゅ た な ご こ ろ に あ り ) りんざいしゅう H. 21. 6. 6 へきがんろく この言葉は臨済宗でよく使われる公案書である「碧巌録」に収録されています。読 みは「みょうじゅたなごころにあり」です。明珠とは計りきれないほどの価値のある 「宝」のこと、それをあなたはすでに持っています、という意味です。 その宝は、遠くに探しに行かなくても、すぐそばにあるのと言います。それはあな た の 手 の 中 に 宝 物 が す で に あ る か ら で す 。し か し 、宝 は 目 に 見 え る 金 や ダ イ ヤ モ ン ド 、 地位や名誉などと思いがちになってしまいます。 禅の考えで意訳すると、「あなたはすでに充分に幸せですよ」となります。「私は す で に 充 分 に 幸 せ 。」な ん だ か 、改 め て 身 の 回 り と か 自 分 の 内 側 と か を 見 直 す き っ か けになりませんか。 「私はすでに充分に幸せ。」よくよく考えてみれば、自分って、本当に幸せなんだ なと思います。妻、かわいい子供たちに囲まれ、素敵な友達がいて、人に恵まれ、健 康に恵まれ、仕事に恵まれ、平和でご飯の美味い日本に生まれ、お笑い番組で笑い転 げて、好きなものをたらふく食べることができ、おまけに、無駄な脂肪までたくわえ て。そして、どんな宝物にも代えられる可能性を秘めた「未来」まで与えられている から、そう思うと、私は、すでに充分に幸せなんだな思います。 人は宝物がきっとどこかにあるはずだと、一生懸命外に探しにいきます。けれど、 掌(てのひら)を見れば、そこにあるかもしれません。『どこにいかずともみんな幸 せ を つ か ん で い る 。』も う 一 度 自 分 を 見 つ め 直 し て 、改 め て 身 の 回 り と か 自 分 の 内 側 とかを見直せば、今おかれている環境がどれだけすばらしいものか。 今ある環境に感謝して、感謝の気持ちを忘れずに今、自分ができることをやるべき ことを、一生懸命に全力で、自分らしく取り組んで行くことができれば、本当の幸せ 明珠に気づくことができるかも知れません。 因果応報(いんがおうほう) H21.5.6 因 果 応 報 と は 、こ と わ ざ な ど に 含 ま れ る 用 語 で あ る 。 「 善 い 行 い を す れ ば 、感 謝 な ど の善い行いで返り、悪い行いをすれば、懲罰などの報いで返る」と、主に後者の「悪 行は必ず裁かれる」という意味で使われることが多い。しかし実際の起源・意味とし ては間違っており、ただ単に「行動」と「結果」は結び付いているという意味でしか ない。 仏教的な解釈では、釈迦は、原因だけでは結果は生じないとし、直接的要因(因) と間接的要因(縁)の両方がそろった(因縁和合)ときに結果はもたらされるとする ( 因 縁 果 )。そ こ で 、縁 起 と 呼 ぶ 法 に よ っ て す べ て の 事 象 が 生 じ て お り 、 「 結 果 」も「 原 因」も、そのまま別の縁となって、現実はすべての事象が相依相関して成立している とする。 仏教で通俗的に因果と言う場合には、業(ごう)思想と結びつき、自己の存在のあ ぜんいん ら く か り方にかかわる因果性をいうことが多い。 「 善 因 楽 果 ・悪 因 苦 果 」と 言 う よ う に 、人 間 や天人として生まれる善の結果や、地獄・餓鬼・畜生として生まれる悪の結果を得る のは、前世の自己の善業あるいは悪業を原因とするという、方便(本来の教説に導く ための一種の方法)としてしばしば使われる。この因果は自然科学的法則ではなく、 われわれの行為に関するものである。すなわち、自分のやった善は善果を生み、また 悪を行えば悪果が返ってくる、と教える。因果応報とも言われ、人間の行為を倫理的 に規定する教説として言われたものであろう。 しかし、このような一般的考え方は、縁起説から考えられない俗説であり、仏教本 来の考え方にはそぐわない。 仏 教 に お け る 縁 起 (え ん ぎ )は 、仏 教 の 根 幹 を な す 思 想 の 一 つ で 、世 界 の 一 切 は 直 接 にも間接にも何らかのかたちでそれぞれ関わり合って消滅変化しているという考え方 を 指 す 。 縁 起 の 語 は「 因 縁 生 起 」( い ん ね ん し ょ う き )の 略 で 、「 因 」 は 原 因 、「 縁 」は 条件のことである。 経典によれば、釈迦は縁起について、 縁 起 は 、「 此 が あ れ ば 彼 が あ り 、」「 此 が な け れ ば 彼 が な い 。」 と い う 二 つ の 定 理 に よ しゅうじ っ て 、簡 潔 に 述 べ ら れ う る 。こ の よ う な 有 と 無 と 二 つ の 文 句 が 並 べ ら れ る の は 、修 辞 学 的 な 装 飾 や 、文 学 的 な 表 現 で は な く 、こ の 二 つ は 論 理 的 に 結 び 付 け ら れ て お り 、 「此が あ れ ば 彼 が あ る 」 と い う こ と の 証 明 が 、「 此 が な け れ ば 彼 が な い 。」 と い う こ と な の で あ る 。 具 体 的 な 例 と し て は 、「 生 が あ る 時 、 老 い と 死 が あ る 」「 生 が な い 時 、 老 い と 死 がない」の二つがあげられる。なぜなら、生まれることがなければ、老いることも死 ぬ こ と も な い か ら で あ る 。こ の よ う に 後 者 の「 此 が な け れ ば 彼 が な い 。」は 、前 者 の「 此 があれば彼がある」ことを証明し、補完する、必要不可欠なものである。 行 雲 流 水 ( こ う う ん -り ゅ う す い ) H21.4.28 意味 空行く雲や流れる水のように、深く物事に執着しないで自然の成り行きに任せて行 動するたとえ。また、一定の形をもたず、自然に移り変わってよどみがないことのた と え 。▽「 行 雲 」は 空 行 く 雲 。 「 流 水 」は 流 れ る 水 。諸 国 を 修 行 し て ま わ る 禅 僧 の た と え に も 用 い ら れ る こ と が あ る 。「 流 水 行 雲 り ゅ う す い こ う う ん 」 と も い う 。 しゅってん 出典(蘇軾(そしょく)が友人の謝民師推官(しゃみんしすいかん)に宛てた書) おうさい じゅぶつどう ぶっきょう 蘇 軾 は 号 を 東 坡 (と う ば ) と い い 、 博 学 宏 才 、 儒 佛 道 ( 儒 教 、 佛 教 、 道 教 ) の 三 教 に ほくそう 通 じ て お り 、詩 文 の 他 に 書 画 に も 優 れ 、北 宋 第 一 の 文 化 人 と い わ れ て い ま す 。 「行雲流 水」は、その蘇軾が友人の謝民師推官(しゃみんしすいかん)に宛てた書の中で、謝 し ふ 民 師 の 文 章 に 対 し て 、次 の よ う に 評 し た こ と に 由 来 し て い ま す 。 「あなたの詩賦や文章 は、行雲流水のごとく、形式にとらわれず、流れるままに流れ、しかも止まるべきと ころにはきちんと止まっています。思想や言葉はまことに自然に表出され、その描写 は と て も 自 由 で 生 き 生 き と し て い ま す 。」行 雲・流 水 は 文 字 ど お り 空 行 く 雲 と 流 れ る 水 、 どちらも作為のない自然のままの流れを象徴しています。自然で伸びやかな文章のた とえ、あるがままの自然な生き方のたとえ。また何事にも執着せずに自然の成り行き に任せて行動することのたとえとして用いられます。さらに雲水と略して、諸国を行 脚して修行を積み重ねる禅僧のたとえとしても用いられています。 禅僧の雲水 ゆうぜん 雲は悠然として浮かび、しかもとどまることなく、水はまた絶えることなくさらさ む げ らとして流れて、また一処にとどまることがない。この無心にして無碍自在のありよ うが禅の修行にもあい通じることから、この語を禅者は好んで用いた。今も禅の修行 僧 を「 雲 水( う ん す い ) 」と 云 う の も 雲 が 悠 々 と 大 空 を 行 く 如 く 、ま た 流 れ る 水 の 如 く一処にとどまらず師をたずね修行の行脚したことから名づけられたことばです。 「行雲流水」は自然現象である。空を行く雲、川を流れる水は一時も同じ状態では ない。雲の表情は一瞬一瞬ごとに変わり、湧きては消え、消えてはまた生ず、であり また流れる水も常に変化して様々な表情があるように、この行雲流水の語は世の無常 を表わした語でもあります。 それはそのままわれわれの人生にも通じることです。雲にはやさしい風ばかりでは せ ありません。吹きちぎり吹き飛ばす風もあります。水の流れにも瀬があり曲がりくね しか る淵があり一様な流ればかりではなく、長い人生もまた然りです。人生、順風満帆ば あいらく かりなんてありえません。どんなに障害があり、喜怒哀楽様々な出来事の連続の中に あっても、常に心はその一処にとどまらず、執着せず、雲の如く無心にして淡々と、 さわやかに生きるところにこの「行雲流水」の語が生きます。余談ですが、墨染めの あ じ ろ 衣にわらじ履き、網代笠を被った雲水の姿が自然の風光の中にあれば、ひとつの風景 い か 画に見えるかもしれません。ですが、雲水である当人は如何がな心境でしょうか。 燈燈無尽(とうとうむじん) H21. 4. 17 この言葉は、 「維魔経」 ( ゆ い ま き ょ う )と い う 古 い 仏 教 の 経 典 に あ る「 無 尽 燈 (む じ ん と う )」 と い う 言 葉 か ら 生 ま れ て い ま す 。 そ の 昔 ・・・・。 釈 尊 (ぶ っ た ) ( 釈 迦 牟 尼 世 尊 (し ゃ か む に そ ん )の 略 ) は 亡 く な ら れ る 前に、お弟子さんを伴って北へ北へと旅をしていました。その旅の途中に「ヴェーサ ー リ 」 と い う 美 し い 街 に 立 ち 寄 ら れ ま す 。 そ の 街 に 維 魔 ( ゆ い ま )と い う 人 が 住 ん で い ま し た 。 維 魔 は 「 資 財 無 量 」( 裕 福 で 人 望 が あ る ) な 人 で 、 悟 り を ひ ら き 不 思 議 な 力 をもって、いつも苦しんでいる人や貧しい人たちを助けていました。その維魔が病気 になって床に伏せた時、釈尊はお弟子さんたちを集めてこう言いました。 「誰か私の代わりに維魔を見舞ってはくれないか」 しかし、お弟子さんたちは、何でも良く分かる維魔に尻込みをして、誰も行こうと は し て く れ ま せ ん 。 釈 尊 が 、 お 弟 子 さ ん の 一 人 で あ る 持 世 菩 薩 (じ せ ぼ さ つ ) に 見 舞 い に行くよう言いましたが、やはり見舞いには行けないと言います。どうして行けない のかと釈尊が尋ねると、持世菩薩は、昔維魔と出会った時の話をします。 あ る 日 ・・・。持 世 菩 薩 が 静 か な 部 屋 に 座 っ て い る と 、魔 波 旬 (ま は じ ゅ ん )( 正 し い 教 えを破壊する魔王。仏やその弟子たちに付きまとって仏道修行・解脱の妨げをする) が 、 た く さ ん の 天 女 を 従 え て 、 音 楽 を 奏 し な が ら 帝 釈 天 ( た い し ゃ く て ん )の 格 好 を し てやってきました。帝釈天が魔波旬とは知らない持世菩薩は、帝釈天に説法をし始め たのです。 「いい話をしてくれた」 魔波旬はそう言って、私の天女を侍女としてさしあげようと言います。 「とんでもない」と押し問答が始まってしまいます。 そこへ維魔がやってきて「わたしがもらってあげよう」と言います。 神通力のある維魔の前にあっては、さすがの魔波旬も慌てふためいて、逃げようと しますが逃げることができません。 すると天上から「悪魔よ天女を維魔に与えるなら逃げることができるぞ」という声 が聞こえてきました。魔波旬は慌てて天女を維魔に与えて去ってしまいます。その時 維魔は残された天女たちに説法し、さとりに向かいたいという気持ちを起こさせまし た。天女たちは、皆魔波旬のところには帰りたくないと言い出してしまいました。困 ったのは魔波旬です。 「なんとかしてくれ」と維魔に助けを乞います。 そ こ で 、維 魔 が 天 女 た ち に 教 え た の が「 無 尽 燈 (む じ ん と う )」と い う 言 葉 な の で す 。 「た った一つの燈が、百千もの無数の燈に火を付けていく。そして、皆が明るくなり、そ の燈が絶えることがない。それが無尽燈という考え方だ。あなたたちも自分自身の心 の中にあるさとりの燈を、魔波旬のところにいる大勢の天子や天女たちの心の燈に火 をつけて歩くのだ。一人の人が百千の人々をさとりに向かわせたとすると、それが無 尽 燈 で あ る 。」 こ う し て 、 天 女 た ち は 新 し い 気 持 ち に な っ て 帰 っ て い く の で し た 。 ともしび運動 つきることのないともしびを人の心に点していこう。 この思いを形にする運動を起こそうと、昭和51年に当時の神奈川県知事 長洲一二 が提唱した運動が「ともしび運動」です。 一燈をもちよろう ともしび運動県民のみなさまへ 肩が触れあうような都会の中で、ひとり暮しのお年寄りがひっそりと果てて、何日 も発見されなかった−こんなニュースが繰り返されています。悲しいことです。 今 “物 ”の 面 だ け で い え ば 、 豊 か で 、 便 利 で 、 日 常 生 活 の す み ず み ま で 、 き め 細 か い 工夫が凝らされています。それに引きかえ、何か寒々と冷えきってしまったかに見え る “心 ”の 世 界 。 一見、自由に、合理的に生きているようで実は、ひとりひとりがバラバラで、寂し く味気なく感じられる世の中。 いや、私は固く信じます。私たちがもともと持っていた隣人へのあの何げなく温か い思いやりの心は、けっしてなくなったわけではない。人が人を求め、心が心を呼び あう人間本来の願いは、いまも私たちの胸の底深く、静かに燃えているはずだ。 その火を思いきって外に出しましょう。みんなで高々とかかげましょう。 人 生 と い う 長 い 旅 路 に は 、山 も あ り 、川 も あ り 、天 気 の 日 も あ ら し の 日 も あ り ま す 。 運悪く足を傷めることもあります。 人間はすべて、多かれ少なかれ重荷を背負って歩む、共に旅する仲間です。特別重 い荷を負う疲れた仲間が身近かにいれば、声をかけ、励ましあい、肩をかして、いっ しょに歩いていく これが人生の生き方でありましょう。 私たちはだれでも例外なく老人になります。このひしめき合う現代、思いもよらぬ 事故に出合って、あすにも不自由な身になることもありえます。 お年寄りも若者も、健常者も障害者も、みんなが手を握り、肩を組みあって、生き がいを見いだす世の中をつくりたい そ ん な 願 い を こ め て 、 “と も し び 運 動 ”を 始 め ま した。 “と も し び ” こ れ は 古 い 仏 典 の 一 句 “燈 々 無 尽 ” か ら お 借 り し た こ と ば で す 。ひ と り の 胸にともった小さなともしびも、それを次から次へと点じてゆけば、尽きることなく 広がって、太陽のように明るく暖かく、この神奈川を照らすことを、私は確信いたし ます。 県 は 、行 政 の 立 場 で 、全 力 を 傾 け て 努 力 い た し ま す 。ど う ぞ 、ご べ ん た つ く だ さ い 。 同時に、県民のみなさまにもお願いします。 み な さ ん そ れ ぞ れ 、ご 自 分 の お 考 え で 、お で き に な る 場 所 で 、お で き に な る と き に 、 お で き に な る こ と で 、 “と も し び 運 動 ”に ご 参 加 く だ さ い ま せ ん か 。 た と え ど ん な に 小 さ な 火 で も 、 ひ と り ひ と り 、 み ん な が 持 ち 寄 る “一 燈 運 動 ”を 、 お 考 え く だ さ い ま せ ん か。 H 21.3. 21 破 草 鞋( は そ う あ い ) 「 草 鞋 」と は わ ら で あ ん だ 履 物 、わ ら じ の 事 で す 。 「 草 鞋 を 破 る 」と 読 め ば 草 鞋 を す り いわゆる あんぎゃ へんさん 切らして長旅をする意、所謂「行脚」の事で、名師を求めて諸方の禅寺を遍参して修 ろ ぼ う 行する事です。 「 破 れ 草 鞋 」と 読 め ば 履 き 古 さ れ て す り 切 れ 、今 は 路 傍 の 片 す み に 打 ち 捨てられて誰一人として見向きもしない破れわらじの意となります。 きょうがい 禅の修行は一切の妄想執着を断ち切って、真の「無一物」の境涯になりますが、そ みょうきょうがい の 妙 境 涯 に も と ど ま る 事 な く そ れ を 捨 て 去 っ て 、学 ん だ 法 や 修 し た 道 を 少 し も ち ら つ かせることなく、悟りだの、仏だの、禅だの、その影さえ窺い見る事が出来ない、馬 鹿 な の か 利 巧 な の か 、偉 い の か 凡 夫 な の か さ っ ぱ り わ か ら な い 、長 屋 に 住 む 八 つ ぁ ん 、 熊さんの手合と同じく、人知れず平々凡々、一個の破れわらじのように、その存在す ら知られずに生きていく消息こそが、本当の禅僧の境涯だというのです。他人から有 り難がられるようでは未だというわけです。 か ん こ す い きり は さ ぼ ん 「 破 草 鞋 」 が 、「 閑 古 錐 古 び た 錐 」「 破 沙 盆 門で重用されるのはその辺の理由からです。 こわれたスリバチ」等々と共に禅 破草鞋のように生きた人を紹介します。 きんせい なんいん たんそう つ 近世の名僧、渡辺南隠禅師(一八三四∼一九〇四)は、はじめ広瀬淡窓に就いて儒 は く さ ん そうぞく 学を学び、後に出家して修行し、東京・白山道場を築いて多くの僧俗を教化された人 です。 せ ん げ こ の 南 隠 和 尚 が 遷 化 ( 死 亡 )さ れ た 後 、近 所 の お 婆 さ ん が い う に は 、 「老師ご存命中 は私達のいいお茶飲み友達だと思って、しょっちゅう参りましたが、おかくれになっ て か ら 聞 け ば 、 た い そ う 偉 い お 方 で あ っ た そ う で す ね ……」。 つぐ い ぶ か 妙心寺の関山国師は大灯国師の法を嗣ぐと、独り美濃の国伊深の里に隠れ、村人達 ばつぼく に頼まれるにまかせて、田畑の耕作、牧牛、伐木に炭焼等々、手伝いの日々でした。 村人達にとっては誠に便利で重宝な老爺としかうつりませんでした。 ち ょ く し へきそん い ふ か 優雅な勅使が山間の僻村、伊深の里に入ってくるのを見て、村人達はまさに青天の へきれき 霹靂でした。これまでは単なる老爺だと思っていた関山国師を花園法皇の命で迎えに 来たのですから、村人の驚きはひとしおでした。 ち ょう で ん す 東福寺の画聖兆殿司は、破草鞋の如く生きんと、自ら「破草鞋」をもって号とした と い わ れ て い ま す 。「 破 草 鞋 の よ う に 生 き る ! 」、 口 で 云 う は 易 し 、 実 行 す る 事 は な か なか難しいようです。 益者三友(えきしゃさんゆう) 三益友(さんえきゆう) H21. 3 . 20 《「 論 語 」 季 氏 か ら 》 有 益 な 3 種 類 の 友 達 。 す な わ ち 、 正 直 な 友 、 ま ご こ ろ の あ る 友 、 物知りの友。益者三友。三損友 孔子の曰わく、益者(えきしゃ)三友。直きを友とし、諒(まこと)を友とし、多 聞を友とするは、益なり。便辟(べんへき)を友とし、善柔を友とし、便佞(べんね い)を友とするは損なり。 孔子が言われた、 「 有 益 な 友 達 が 三 種 、有 害 な 友 達 が 三 種 。正 直 な 人 を 友 達 に し 、誠 心の人を友達にし、物知りを友達にするのは有益だ。体裁ぶったのを友達にし、うわ べ だ け の へ つ ら い 者 を 友 達 に し 、 口 達 者 な の を 友 達 に す る の は 、 害 だ 。」 付 き 合 っ て 為 に な る 友 、為 に な ら な い 友 に そ れ ぞ れ 三 つ の タ イ プ が あ る と い う 意 味 。 剛直な人、誠実な人、教養のある人、この三者が付き合って為になる友であり楽なほ うに付きやすい人、人に媚びるような人、口先だけうまい人、この三者が為にならな い、と孔子は教えています。 友だちを見れば、その人となりがわかるといいますが、良い友人を選ぶことはもち ろんのこと、自分自身が損者三友の部類に入らないよう、心しなければなりません。 H 21.3.11 一口吸盡西江水(いっくに きゅうじんす せいこうの みず) へきがんろく 禅 語 「 法 演 禪 師 語 録 」 よ り 。『 碧 巌 録 』「 第 四 十 二 則 」 居士問馬大師。不與萬法為侶是什麼人。 大師云。待汝一口吸盡西江水。即向汝道。 師云。一口吸盡西江水。洛陽牡丹新吐蘂。 [読 下 例 ] こ じ 居 士 馬 大 師 に 問 う 。「 万 法 と 侶 [と も ]た ら ざ る も の 是 れ な ん び と ぞ 。」 きゅじん 大 師 云 く 。「 汝 が 一 口 に 西 江 の 水 を 吸 盡 せ ん を 待 っ て 、 即 ち 汝 に 向 か っ て い わ ん 。」 ぼ た ん しべ 師 云 く 。「 西 江 の 水 を 一 口 に 吸 盡 す れ ば 、 洛 陽 の 牡 丹 ほう こ は 新 に 蘂 を 吐 く 。」 じ 『 龐 居 士 語 録 』に「 居 士 後 之 江 西 參 馬 祖 大 師 。 問 曰 。不 與 萬 法 為 侶 者 是 什 麼 人 。 祖 曰 。待 汝 一 口 吸 盡 西 江 水 即 向 汝 道 。士 於 言 下 頓 領 玄 旨 。遂 呈 偈 。有 心 空 及 第 句 。」( 居 士 、後 の 江 ば そ 西 、馬 祖 大 師 に 参 じ 、問 う て 曰 く 、万 法 と 侶( と も )と 為 ら ざ る 是 れ な ん び と ぞ 。祖 曰 く 、 お とみ 汝 の 一 口 に 西 江 の 水 を 吸 尽 す る を 待 ち て 、即 ち 汝 に 向 っ て い わ ん 。士 、言 下 に 於 い て 頓 し むね つい けい 領 玄 旨 を 領 す 。 遂 に 偈 し て 、 有 心 空 及 第 の 句 を 呈 す 。)と あ り 、『 法 演 禪 師 語 録 』 に「 龐 居 士 問 馬 大 師 。 不 與 萬 法 為 侶 是 什 麼 人 。 大 師 云 。待 汝 一 口 吸 盡 西 江 水 。即 向 汝 道 。師 云 。一 口 吸 盡 西 江 水 。洛 陽 牡 丹 新 吐 蕊 。」( 龐 居 士 、 馬 大 師 に 問 う 。万 法 と 侶( と も ) と 為 ら ざ る 是 れ な ん び と ぞ 。大 師 云 く 、汝 の 一 口 に 西 江 の 水 を 吸 尽 す る を 待 ち て 、即 ち 汝 に 向 っ て い しべ わ ん 。 師 云 う 。 西 江 の 水 を 一 口 に 吸 尽 す れ ば 、 洛 陽 の 牡 丹 、 新 た に 蕊 を 吐 く 。) と あ り 、 『 碧 巌 録 』に 「 不 與 萬 法 為 侶 。 是 什 麼 人 。祖 云 。 待 爾 一 口 吸 盡 西 江 水 。即 向 汝 道 。 士 豁 然 大 悟 。 作 頌 云 。十 方 同 聚 會 。 箇 箇 學 無 為 。此 是 選 佛 場 。心 空 及 第 歸 。」( 万 法 と と も と 為 ら ざ る 是 れ な ん び と ぞ 。祖 云 く 。な ん じ が 一 口 に 西 江 の 水 を 吸 尽 せ ん を 待 っ て 、即 ち 汝 に 向 し か つ ぜ ん た い ご しょう じ っ ぽ う ど う し ゅ えん か か が く む い かっていわん。士豁然として大悟し、 頌 を作って云く。十方同聚会。箇箇学無為。これ こ け い は 是 れ 選 仏 場 。 心 空 及 第 し て 帰 る と 。) と あ る 。 利 休 は 古 渓 和 尚 に 参 じ て 、 こ の 「 一 口 吸 しょうふういっせつにきょうす 盡西江水」の語によって悟りを開いたという。 「 松 風 供 一 啜」 と同じ境地という。 私 の 解 釈 は こ う で す 。 人 と い う " 部 分 " が 、 江 (自 然 の 代 表 )と い う " 全 体 " と 一 体 に な こ け い おしょう った時、初めて真理が見える。また、利休は古渓和尚に参じて、この「一口吸盡西江 水」の語によって悟りを開いたといわれているそうです。 植物社会に学ぶ 健全に生きる生物社会の掟 H 21.3.8 「 競 争 」 と 「 我 慢 」、「 共 生 」 物言わぬ植物たち。それでも、私たち人間に多くのことを語りかけてくれます。植 物 と 関 わ っ て 約 60 年 、 森 づ く り に 生 涯 を か け る 植 物 生 態 学 者 で あ る 横 浜 国 立 大 学 名 誉 教 授 の 宮 脇 昭 さ ん ( 80 )。「『 競 争 、 我 慢 、 共 生 』 こ そ 、 植 物 が 生 き 延 び る た め の 生 物 社 会 の 掟 」と 明 言 し て い ま す 。一 方 、 「 同 じ 生 物 社 会 で あ る 人 間 社 会 も 似 て い る 」と 共 鳴 す る の は 、 山 田 英 生 ・ 山 田 養 蜂 場 代 表 ( 51 )。 企 業 経 営 者 の 立 場 か ら 「 個 性 的 で 多様な人材こそ、組織には必要」と強調しています。先の見えない不透明な時代、植 物社会から学ぶべきことは、限りなく多いようです。 宮脇 昭(みやわき・あきら) 横浜国立大学名誉教授 1928 年 、岡 山 県 生 ま れ 。ド イ ツ 国 立 植 生 図 研 究 所 で 潜 在 自 然 植 生 理 論 を 学 ぶ 。 横 浜 国 立 大 学 教 授 、国 際 生 態 学 会 会 長 な ど を 経 て 現 在 、( 財 ) 地 球 環 境 戦 略 研 究 機 関 国 際 生 態 学 セ ン タ ー 長 。 国 内 外 約 1 600 ヵ 所 以 上 で 植 樹 指 導 。91 年 、「 日 本 植 生 誌 」 の 完 成 で 朝 日 賞 、92 年 、紫 綬 褒 章 。06 年 、 ブ ル ー プ ラ ネ ッ ト 賞 、「 植 物 と 人 間 」 な ど 著 書 多 数 。 山 田 英 生 ( や ま だ ・ひ で お ) ㈱ 山 田 養 蜂 場 代表 1957 年 、岡 山 県 生 ま れ 。198 3 年 、学 卒 後 勤 め た 会 社 を 脱 サ ラ U タ ー ン し て 養 蜂 場 の 後 継 者 と な る 。自 前 で 研 究 所 を 持 ち 、添 加 物 を 排 し た 自 然 派 化 粧 品 、予 防 医 学 的 見 地 か らの健康食品など独自の商品開発を行っている、直販方式により、全国に根強いファ ン を 持 つ 。 ネ パ ー ル や 中 国 ・内 モ ン ゴ ル ヘ の 植 樹 活 動 や 世 界 遺 産 保 護 活 動 、全 国 の 小 学 校 へ 図 書 を 寄 贈 す る「 み つ ば ち 文 庫 」な ど の 社 会 貢 献 活 動 に 積 極 的 に 取 り 組 ん で い る 。 よく似ている植物と人間社会 宮脇 森の中では、高木、亜高木、低木、下草が、さらに士の中ではカビやバクテ リアなどいろんな生き物が限られた空間で、お互いにいがみあいながらも我慢し、種 の 能 力 に 応 じ て 精 一 杯 生 き て い ま す 。 こ の 「 競 争 」、「 我 慢 」、「 共 生 」 こ そ 生 物 社 会 の 掟です。森の中では、好きな植物同士が好きなところで勝手に生きているわけではあ りません。厳しい条件下で、ちょっと我慢しながら嫌な奴とも共生しているのです。 共生とは、決して仲良しクラブではありません。競い合いながらも、互いに少し我慢 して、すみ分けて共に生き続けること。これが健全な生物社会の姿であり、植物が生 き延びるための条件です。 山田 人 間 社 会 も 、 ま っ た く 同 じ だ と 思 い ま す ね 。「 競 争 」 に つ い て 言 え ば 、 同 じ 種同士、近い種同士が競い合うことによって早く伸びようとするのですね。先生の植 樹 方 法 で と く に 間 隔 を あ け て 植 え る よ り も 密 植 の 方 が 、互 い に 早 く 成 長 し よ う と す る 、 と の 話 は 大 変 興 味 深 い で す 。人 間 社 会 で は 、い つ も 全 員 が 、ラ イ バ ル で は 困 り ま す が 、 互いに競争し合う関係、つまり、よい意味でのライバル関係は必要ではないでしょう か。 「 我 慢 」は 、今 は 成 長 す る チ ャ ン ス が な く て も 、じ っ と 時 を 待 つ と い う 意 味 で す ね 。 しっかりと力を蓄えた、成長する前の熟成期間、成長期と考えてもよいかもしれませ ん。我慢は、人間にとっても組織にとっても、たいへん重要な意味を持っています。 そして「共生」は、いろんな人が、それぞれの役割、責任を分け合って共に生きてい る状態。共生だけに流れ過ぎるのは、よくありませんが、それぞれが各自の役割を自 覚 し 、分 担 し な が ら 目 標 に 向 か っ て 進 む こ と は 、組 織 と し て 欠 か せ ま せ ん 。 「 競 争 、我 慢、共生」という3つの言葉は、人間社会が健全に発展するためのキーワードでもあ ると思います。 多種多様な樹木混ぜて植える 宮脇 生物は、競争を通してのみ発展しています。だから人間社会も、生物社会を 見習ってすべての競争を拒否しないでいただきたい。好きなものだけを集めるのは、 危険だし、いろんな種類が集まる多様性こそが自然界では健全な姿です。だから植樹 する場合でも、好きな木だけを植えない。土地本来の主役の本となるトップとそれを 支える3役5役の木を中心にできるだけ多くの樹種を「混ぜる、混ぜる、混ぜる」の が鉄則です。重要なことは、それぞれの地域のトップと3役5役の木の種類を取り違 えないこと。会社だって同じだと思いますが・・・。 山田 本当にそう思いますね。同じようなことばかり考えている人や同じような性 格の人ばかり集めていると組織は、もろくなってしまいます。いろんな人開かいるほ う が 、い ざ と い う 時 に 、思 わ ぬ 威 力 を 発 揮 す る も の で す 。例 え ば 多 少 、う る さ い と か 、 性格が扱いにくいとか、目の上のたんこぶのような個性的な人たちがいた方が組織と しては、健全だと思いますね。自らの組織の方針や考え方も全員が肯定しているより は、異なった見方や考え方ができる人がいた方がよいのです。全部が全部気の合う人 ばかりだと、かえって危険で、組織として長続きはしないでしょう。 トップに必要な現場至上主義 宮脇 よく見ておられます。それと、自然は人それぞれの顔ほど違い、何ひとつ同 じものはありません。私は、植物の研究をする時は、まず緑の現場に出かけ、自分の 体を測定器にしながら、自分の目で見て、においを嗅ぎ、なめて、触って調べてきま した。これは、ドイツに留学したとき、恩師のラインホルト・チュクセン教授に連日 の よ う に 山 野 に 連 れ て 行 か れ 、 現 場 で 徹 底 的 に 教 え 込 ま れ た 哲 学 な の で す 。 以 来 58 年間、現場一筋でやってきました。人間社会だってそうですよ。トップはすべて部下 に任せず、自ら現場に足を運び、現場が発している微かな情報から正しい全体像を把 握し、的確な指示を出すべきでしょう。 山田 まったく同感ですね。私もこの世界に入って以来、現場一筋でやってきまし た。今、経営者として現場の重要さを身を持って感じています。 宮脇 まさに「現場、現場、現場」です。現場に出れば、お金や最新の機械でも測 れない「いのちのドラマ」が展開しているわけですから。 山田 話しは変わりますが、世界中の伝統的な農作物のうち4分の3の品種が、こ の100年間で失われたと言われ、機械化に適した作物が重点的に生産されるように なりました。単一栽培の拡大によって、遺伝資源の多様性が失われつつあります。農 業の商業化と食生活の変化によって栽培品種が限定されるようになった結果だと思い ま す 。一 説 に よ る と ぃ 今 世 界 的 に 話 題 に な っ て い る 、 「 ミ ツ バ チ の い な い い な い 病 」も 、 これが原因ではないかと言われております。単一作物の栽培が過ぎて、ミツバチの栄 養に偏りがでたためだというのです。昔の農業には知恵があり、そんな無茶はしませ んでした。例えば、アンデスのジャガイモ栽培では、気象の変化や病害虫に対応でき るように、同じ畑に何種類もの品種を組み合わせて植えていたといいます。 宮脇 確かに知恵がありました。しかし、生き物は、厳しい環境の中でこそ本性を 発揮します。厳しい環境条件に耐えて長持ちするものが本物です。 山田 人間には思わぬ可能性というか、秘めた力が備わっていると、つくづく思い ますね。ただ、現実には、誰もがそうした能力や潜在力があるとは気づいていないか ら、その力を引き出そうとしないのではないでしようか。私事で恐縮ですが、198 8 年 10 月 下 旬 、 当 時 社 長 だ っ た 父 が 倒 れ 、 そ の 2 日 後 に は 、 自 宅 を 全 焼 す る と い う 災難に遭いました。短期間の間に予期せぬ不幸に直面しましたが、私はこの二重の災 難を大きな転機ととらえ、死に物狂いで仕事に取り組みました。その結果、思いもよ らなかった事業の発展につながったのです。 「人は誰しも無限の可能性を持って生まれ て い る 」。こ の 言 葉 は 、幕 末 の 教 育 者 、吉 田 松 陰 の 言 葉 で あ り ま す が 、人 は 誰 で も 無 限 の可能性を持っていることを私は、自分の経験から学びましたね。 宮脇 私 の 経 験 か ら 言 っ て も 、人 間 本 気 に な れ ば 98 % 、希 望 は 叶 う と 思 う ん で す ね 。 もしうまくいかなかったならば、それは手を抜いていたか、油断していたかのどちら かではないでしょうか。 山田 先生のおっしゃる通り、自然のしわざを人間が行うのは無理ですけど、自分 の 願 い を 9 8% 実 現 す る の は 、 で き な い こ と で は な い と 思 い ま す 。 原油高騰で痛感現代文明の弱さ 宮脇 もう一つ、生物社会では最高条件と最適条件は、適うということをぜひ、知 っておいていただきたい。すべての敵に打ち勝ち、すべての欲望が満足できる最高条 件というのは、長い地球の生命の歴史で見ると、マンモスや恐竜の絶滅の例を見るま でもなく、むしろ危険な状態といえます。これに対し、生態学的な最適条件というの は、生理的な欲望をすべて満足できない、少し厳しく少し我慢を強要された状態のこ とを言います。人間社会でも地位、名誉、金、異性の問題などすべてがうまくいって いる人は、いつドンデン返しを食うかも知れません。逆に、少し我慢を強いられてい る人は、あすに向かって大いに希望を持って生きてほしいと思います。 山田 なるほど。最高条件と最適条件は違うんですね。 宮脇 はい。例えば、これはドイツでの私の経験なんですが、日本人はドイツに行 く と 、 有 名 ブ ラ ン ド の カ ミ ソ リ を 10 個 も 2 0 個 も 大 量 に 買 い 込 も う と し ま す か ら 、 すぐ在庫がなくなってしまいます。しかし、メーカー側は、小売店にすぐカミソリを 卸 そ う と し な い か ら I カ 月 た っ て も 、そ の カ ミ ソ リ は 、店 頭 に 並 び ま せ ん 。た ま た ま 、 そ の メ ー カ ー を 訪 れ る 機 会 が あ っ た の で 、「 日 本 で は 商 品 が 売 れ る と 、 工 場 を 24 時 間 稼動して大量生産します。こちらではこれだけ売れているのに、なぜ生産制限をして いるのですか」と尋ねました。すると、担当者は「私たち社員や店もこれで十分、食 べていけます。もし生産を増やし、売れ残ったら処置に困るじゃないですか」と逆に 言 わ れ 、「 な る ほ ど 」 と 感 心 し た こ と が あ り ま し た 。「 節 度 を わ き ま え る 』 と い う か 、 「ほどほどでいい」というか、日本とドイツの考え方の違いなんてすね。人間社会も 最高条件と最適条件について真剣に考えなければならない時代がやってきたと思いま す。 山田 3年前、アメリカ南部をハリケーンが襲い、産油地帯が洪水に見舞われ油の 価格が一気に上がったことがありましたね。また、最近のサブプライム問題に端を発 した石油の急騰についてもしかり、 もっと大きな自然災害やテロ、戦争が起き、例 え ば 、油 の 価 格 が 1 ℓ あ た り 、2 0 0 円 、3 0 0 円 に ま で 高 騰 し 、油 の 供 給 が 完 全 に 止 まってしまったら、果たして今の文明が将来も維持していけるのか、現代文明の足腰 の弱さを痛感しました。人間が最高条件を求め過ぎたために、文明の足腰がもろくな ってしまったのでしょうね。 宮脇 その通りです。戦後、会社も役所も、ちょっと頭が出たらすぐ押さえて横並 び 、縦 割 り の 人 事 管 理 を し て き ま し た 。経 済 が ど ん ど ん 発 展 し て い る 時 は 、部 下 に「 規 格品」を置いておけばトップは居眠りをしていてもうまくいっていたわけです。しか し 、 バ ブ ル が は じ け て 20 年 近 く た っ た 今 も 、 困 難 に 対 応 で き る エ ネ ル ギ ー を 持 っ た 人材が中央政府にも地方自治体にも、企業にも出てきていません。戦後の規格品づく りの教育や人事管理の影響が暗い影を落としています。緑の管理も、人事管理も、伸 びてきたものは、伸ばし、頭は切らないでいただきたいですね。 ゲシュタルトの祈り H21.2.23 ド イ ツ の 精 神 医 学 者 、 フ レ デ リ ッ ク ・ S ・ パ ー ル ズ (1893∼ 1970)の 詩 私は私のために生き、あなたはあなたのために生きる。 私はあなたの期待に応えて行動するためにこの世に在るのではない。 そしてあなたも、私の期待に応えて行動するためにこの世に在るのではない。 もしも縁があって、私たちが出会えたのならそれは素晴らしいことだ。 出会えなくても、それもまた素晴らしいこと。 訳 私は私のことをします。ですから、あなたはあなたのことをして下さい。私は、あ なたの期待に添うために生きているのではありません。そして、あなたもまた、私の 期 待 に 添 う た め に 生 き て い る の で は あ り ま せ ん 。あ な た は あ な た 、私 は 私 で す 。で も 、 私 た ち の 心 が 、た ま た ま 触 れ 合 う こ と が あ っ た の な ら 、ど ん な に 素 敵 な こ と で し ょ う 。 でも、もしも心が通わなかったとしても、それはそれで仕方のないことではないです か 。( 何 故 な ら 、 私 と あ な た は 、 独 立 し た 別 の 存 在 な の で す か ら … ) この祈りはドイツの放浪の精神科医と言われ、半分聖人、半分ルンペンとも呼ばれ た 、 フ レ デ リ ッ ク ・ S・ パ ー ル ズ に よ っ て 提 唱 さ れ た 詩 で あ る 。 他 者 へ の し が み つ き 、 他者を操縦しようとする努力を未成熟の兆候として徹底的に排除し、自立、自律性、 自 己 責 任 の 確 立 を 目 標 と し た 。そ の た め に 、「 今 、こ こ 」の 気 づ き の「 体 験 」の 重 要 性 を 主 張 し た 。そ れ は 頭 で 考 え る 観 念 論 的 な 体 系 化 を 否 定 し 、 「 今 、こ こ 」で 直 感 的 に つ かむものである。ゲシュタルトとは「全体性」または「全体のかたち」ということで ある。 # ゲシ ュタ ルト のモ ッ トー であ る「 私 は 私」とい うこ とは利 己 主 義 と いう こ と では ない。自主性の確立ということであり、利己主義や孤立無援とは違う。自分が自分で あるということは、必要なことを他者に依頼することや、自発的に他者を愛すること を 含 む 。 し か し 、こ の 場 合 の「 愛 」と は「 し が み つ き 」で は な く 、「 私 は 私 」と い う 成 熟を目ざしていく。人間の成熟性というのは他者が思うように動かないという欲求不 満の状態の時、よく観察できる。このような場合、成熟した人は自分の能力の限界を よく受容して、いさぎよくあきらめるか、実現可能な方策を探る。未成熟な人は怒っ たり、悲しんだり、あわてたり、ぐちをこぼしたりする。そして、子供のように、悲 しそうな顔をしたり、不安がったり、同情を引こうと事実以上のことをいう。 # 人間が生きていく上で言葉は重要な役割を占めるが、また言葉ほど頼りにならな いものはない。例えば、怒っている生徒に、先生が「お前怒っているね」と聞く、生 徒 は「 い い え 」と 答 え る が 、 「 怒 っ て い る 」と い う 感 じ は 全 体 像 と し て 、誰 が 見 て も 明 白である。そして怒っているのは昨日でもなく、明日でもなく、5 分前でもなく、5 分 後 で も な く 、「 今 、 こ こ 」 で 言 葉 に 関 係 な く 、 存 在 し て い る こ と を 確 認 し て い く 。 # 「∼したい」という人間と「∼するべき」という人間では本質的な違いがある。 「 ∼ し た い 」は 自 分 が 確 立 し て い る 。 「 ∼ す る べ き 」は 自 分 以 外 の も の に 縛 ら れ て い る 。 # 「なぜ」という質問は相手に想像の答えを強いる。子供が窓ガラスを割ったとす る。理由をいくら述べても大して役に立たない。割れたものは割れたのである。そこ で、 「 な ぜ 」を「 ど の よ う に 」に お き か え て み る 。 「どのようにしてそれは起こったか」 という質問には事実が返ってくる。 # 「 ∼ で き な い 」と い う 言 葉 を 嫌 う 。 「 ∼ で き な い 」と い う 語 は 責 任 を と ら な い こ と の表明である。大部分の「∼できない」は「∼したくない」と表せば自己責任が明確 になる。 1 今に生きる。過去や未来でなく現在に関心をもつ。 2 ここに生きる。眼の前にないものより、眼の前に存在するものをとり扱う。 3 想像することをやめる。現実を体験する。 4 不必要な考えをやめる。むしろ、直接味わったり見たりする。 5 他の人を操縦したり、説明したり、正当化したり、審判しないで、ありのままの 自分を表現する。 6 快楽と同じように、不愉快さや苦痛を受け入れる。 7 自分自身のもの以外のいかなる指図や指示を受け入れない。偶像礼拝をしない。 8 自分の行動、感情、思考については完全に自分で責任をとる。 9 今のまま、ありのままの自分であることに徹する。 人生、主体的に生きていけたら素晴らしいことだと思います。そこには自立性や創 造力があり、自分の考えで動き自分の行動や感情にも責任がもてるのではないでしょ うか。 自分を大切にし、大切な誰かも尊重する。考えの違いを赦せなくなるのではなく、 そ う ゆ う 考 え 方 も あ る ん だ な と 思 う こ と が で き た ら 、も っ と お 互 い に 分 か り 合 え た り 、 話し合えたりできるかもしれません。 自分と他者との違いを認めたり、受け入れることができれば、差別やいじめはなく なるかもしれません。 ゲシュタルトの祈りを読んで私は、自他の尊重、他者と自分との違いを受け入れた り、認めたりすることの大切さを感じます。 死にたいほどの無理をして誰かの期待に添う必要はないと思うし、自分の人生を変 えられるのは自分だけだと思います。 「今・ここ」からが未来へのスタートです。