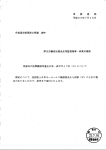Download デザイン手法生成のための言語表現と形態表現の関連性について
Transcript
SURE: Shizuoka University REpository http://ir.lib.shizuoka.ac.jp/ Title Author(s) Citation Issue Date URL Version デザイン手法生成のための言語表現と形態表現の関連性 について 伊藤, 文彦 静岡大学教育学部研究報告. 人文・社会科学篇. 43, p. 6978 1993-03-25 http://doi.org/10.14945/00004104 publisher Rights This document is downloaded at: 2015-11-06T02:09:02Z 静岡大学教育学部研究報告 (人 文・ 社会科学篇)第 43号 (1993.3)69∼ 78 69 デザイン手法生成のための言語表現 と形態表現の関連性について A Shrdy of The Belationship between Linguistic Expression and Artistic Products for Generating Design Methods 伊 藤 文 彦 Fumihiko ITo (平 成 4年 10月 12日 受理) は じめ に 前報告 までのデザイ ン・ プ ロセ ス研究 によ り、 デザイ ン 0プ ロセスを進行 させ る推論 の形態 が、 アイ コニ ックな ものを主体 として い ること (第 一報)。 。 さらに、 “ 形 の生成"過 程 の思 考 特性 としてア レゴ リー (寓 意)や レフ テレンス (引 用)の 使用 とそ の方法 が 明 らか にされた (第 四報)の 。 この ことは、 デザイ ンの過程 にお いて広義 のアナ ロジー (類 推 的思考)が 深 く関 与 して い ることを意 味す るもので あ った。 ところでデザイ ン・ プ ロセ スにおいて類推的思考 の有効性 は、従来 の研究 か らもあるいは経 験的 な実践 か らも認識 されてきた問題 にほかな らない。 しか しなが ら、従来 のアナ ロジーの と らえ られかたは、主 としてあるデザイ ン対象 のハ ー ドな形態生成に対 して、既存 の 自然及 び人 工形態、構造、機構、 あるいは文化的 な記号 などの可視的 な要素 を端緒 とす る方法 に多 くの比 重 がかけ られてきた。 これは、従来 のデザイ ン実践 が対象 としてきた ものの特性 であり、可視 的 な要素 のデザイ ン改良 がその製品 の価値 を高 めることに寄与 して いたか らである。 一方、今 日の電子 テクノロジーの急速 な進展 によ って日常化 してきた情報機器 などの生産品 のデザイ ンは、可視的でハ ー ドな形態表現 に加 えて、操作 に関す る情報 のや りと りやそれに伴 う操作者 の知識 の変容 などの不可視的 なイ ンター フェイス設計 まで、そのデザイ ン領域 の拡張 を余儀 な くされて きた。 このよ うな状況 にあ って は従来 の思考法 の拡張 が必然的 に求 め られ、 デザイ ン手法 に新 たな軸 の挿入、再編成 が急務 となって い る。 本 研 究 の概 要 本研究 では、従来 のデザイ ン領域内でその主 な思考展開を司 って来 たアナ ロジカルなデザイ ン手法 を拡張 して、 イ ンター フェイス設計等 の概念 まで取 り込 めるデザイ ン手法 の基本要素 を 抽出す ることを 目的 として いる。 そ こで、人間 の意図や知識 の伝達・ 表現・ 理解 などにとって主 たる方法 である言語表現 の特 性 を形態表現 のベースに取 り込 む ことが、拡張 してきたデザイ ン領域 に対 して新 たなデザイ ン 手法 を提案す ることになるだろうことを仮説 とした。 これは、言語表現 と形態表現 が異 な った 表現媒体 と形式 を もって いることは明 らかであるが、意図や思 いの伝達・ 表現 とい う視点 か ら は、多 くの共通性 が見 いだせること。 さらに、今 日のデザイ ン対象 が、物理 的・ 行動的 な効用 伊 藤 文 彦 を求 める ものか ら認知的 な理解促進 や知識・ 感覚変容 を期待 されるものへ と拡張 され、それ ら に対するデザイ ン解 を得 るためには、言語表現特性 のアナ ロジーが有力 な端緒 とな りうるもの と考 え られたか らである。 方法 については、種 々の言語表現 を概観 しなが ら、 その表現 による知識 の変容 の しかたに着 目 して い くつか の特性 を抽出 し、 その特性 と形態表現 との対応 づ けをオ リジナル設計 や既存製 品 の分析 を通 じて明 らかに し、言語表現特性 のデザイ ン手法へ の適用可能性 について考察 して い く。 言 語 表 現 と知 識 の 変 容 、 われわれは自 らの意図や思 いを伝達・ 表現 しようとする際に、最 も端的な手段 として言語 を 用 い るが、 その表現形式 は内容 や表現 され る場 などに応 じて多種多様 な様相 を呈 して い る。言 語学上 の厳密 な分類以前 に、一般的 にも、説明文、小説、詩、俳句・ 短歌、 ジ ョーク、電報文 等 々、様式 や論理展開 の違 いによってその内容 が伝 え られる側 に様 々な意識 の変化 を及 ぼす こ とは日常的 な経験 か らも明 らかである。 こうした中で形態表現 との関連性 を考察す る際 に、注 目すべ き点 は、 ある特定 の言語表現 は我 々の知識構造 にある特定 の変化 を もた らしてい るとい う視点である。 この ことは、現在拡張 しつつ あるデザイ ン対象 の様態 とよ く符号 して い る。例 えばイ ンター フェイスのデザイ ンは、情報 の対話的 な送受信 のなかで変化す る知識 のあ り方 を 問題 としなければ効果的 な解決策 を導 くことが不可能 である。 またきわめて今 日的なデザイ ン コンセプ トである遊戯性 や快適性 の問題 も、 それを感 じる知識 のメカニズムの理解 な しには単 な る思 い付 きに止 どま つて しまう。 さらに、先端的 なVR(Virtual Reality=仮 想現実感)技 術 においては、知識構造 の拡張 と認識 の限界 こそが現実 であるとい う観点 も導かれてお り、知 識構造 の変化 をデザイ ン手法 の新 たな軸 として導入す る必要性 が生 じて来 て い る。 知識構造 の変化 を言語表現 のい くつかの特性 と対応づ けるにあた り、知識 とい うものをど う 記述 (表 現)す るか とい う難問 は、諸学問領域 にお いて も見解 の分 かれるところである。 ここ では、知識 それ 自体 の記述 をす ることが本意 ではないため、仮 にM.Minskyが 提唱す る フ レー ム (Frame)の 概念 を援用 してみたい。Minskyに よれば、 われわれが これ まで の経験 の中 で 身 につ けて きたある構造 (=Frame)の が、知覚的 な経験 のひとつ ひとつによって活性化 され る ことが心的経験であるとされる。 フレーム とは一種 の骨組 みのよ うな もので あ り、外 か ら入 っ て来 た情報 とそのフレームを接続 す るための ター ミナルの集合 された もので ある。 さらにこの ター ミナル は暗黙 の仮定 に結 び付 いていることによ ってすべての情報 が入力 されなくともフレー ムを活性化す ることがで きる。 この考 え方 に基 づいたとき、知識構造 の変化 は、暗黙 の仮定 を もった ター ミナルに接続 される情報 と経験的 に構築 された構造 との接続 の され方 によ つて起 こ るもの考 えることができる。 こうした フレーム概念 と何種類 かの言語表現 を照 らし合 わせたとき、大 きく3種 類 の知識構 造変化 を仮定す ることがで きる。第一 に “フレーム準拠 (強 化)"と 呼ぶ ことがで きるような ものである。 これは、単文 で言 えば意 味的 にも文法的 に も破綻 のない ものであ り、文章化 され た ものについて は、前後 の脈絡 が適切 な接続詞 によ って結 ばれて い る論理 的 な説明文 のよ うな 表現 がその典型 と言 える。 これ らの表現 は、経験的 に理解 しやす いルールに基 づいたフ レーム に準拠す るかたちで情報 が ター ミナルに接続 されるため、 フレームはより強化 されたかたちで 活性化 される。 デザイ ン手法生成 のための言語表現 と形態表現 の関連性 について 第二 には、 “フレーム置換"と 呼 ぶ ことので きるような変化 が見 いだせ る。 これはユ ーモア を感 じるジ ョー クの ような表現 がその典型例 である。 ジ ョー クやユーモアを理解す る過程 につ いては後 に詳述す るが、 こうした表現 は、最初 はあるフ レームに対 して準拠す るかたちの情報 が接続 されるが、突然 ター ミナルの もつ暗黙 の仮定 に破綻 を生 じさせるような情報 が挿入 され ることによ り、 ま った く別 の フレームが活`性 化 される。 第二 には、 “フレーム併存"と 見 なせ る変化 が想定 される。 これは、 ある種 の詩的 な表現 に 見 られ るもので、明確 な文脈 をもたず、独立 した表現 の併置 とい うかたちをとっていなが らも、 全体 としてあるイメージや思 いが、受 け手側 の心的状況 に応 じて浮 かび上が って くるような場 合 である。 これはある特定 フレームが活性化 されるとい うよ りも、 い くつか の活性化 された フ レームが リンクす るといった変化 を想定 してみることがで きよう。 (た だ し本論文 においては、 このフレーム併存 を論証す る方法 が定 ま ってお らず、仮説 の提案 までにとどめたい) 以上 の三点 は、言語表現 の もつ膨大 な特性 の総体 か らみれば、 きわめて表層的で部分的 に抽 出 された特性 に過 ぎない。 けれども、 フレーム概念 に基 づいた我 々の知識変容 の様相 か ら言 え ば明確 に分類 される概念 であると考 え られる。以下 では、 “フレーム準拠 (強 イ D"、 “フレー ム置換"の それぞれについてよ り具体的 に概念規定 を試 みると同時 に、 それ らと形態表現 を 目 的 としたデザイ ン手法 との接点 について、既存製品 の分析 やオ リジナル設計 を通 して考察 して い く。 フ レーム 準 拠 (強 化 ) 言語 は一定 の秩序 を もった記号 の系列 であると言 える。 したが って、言語表現 をわれわれが 理解す るためにはあ らか じめ理解 して い るその秩序 を利用す るといった操作 が必要 となる。 こ うして考えたとき、 この秩序 によって構成 されて い るものが言語表現 に関す るフ レーム として 位 置付 け られよう。 そ して この フレームに接続 されて い るター ミナルに入力 される情報 が言語 秩序 に則 った もので あるとき、す なわちフレームに準拠 したかたちの情報 であるときに、 きわ めて 自然 な理解 が可能 とな り、結果 としてよ り安定 して強化 されたフ レームに更新 されること が予測 される。 ここではこうした知識 の変容 をフ レーム準拠 (強 化)と 呼ぶ ことに したい。 言語表現 の秩序 に関 しては、典型的な言語理解 システムに見 られるような解析 の視点 がその の ガイ ドライ ンを示 して い る。 (1)形 態素解析 =文 を構成す る単語 の認定 侶)構 文解析 =単 語 の品詞 の並 び、主述関係、修飾/被 修飾関係 の妥当性、文 の型 と構造抽出 ほ)意 味解析 =意 味 をなすか否 か に)文 脈解析 =先 行文 と後続文 のつなが りの整合性 以上 か ら理解 されるよ うに、単語、構文、意味、文脈 などが、 その言語 を用 い る集団 に対 して 共通 の理解 が及 ぶよ うな適切な用 い られ方 を したとき、 それが秩序 に則 った言語表現 であると い うことができる。 したが って形態表現 にお いて もフレーム準拠 (強 化)を 求 めるためには、 こうした秩序構成 を もった言語表現 を類推 し、対応 づ けることがデザイ ンの手法 として措定 さ れる。 以下 ではフ レーム準拠 (強 化)さ せ る形態表現 に関 して、概念 モデルの設計 と既存製品 の分 析・ 再解釈 の両面 か ら、本 デザイ ン手法 の可能性 と限界 について検討す る。 伊 藤 文 彦 図 1は 、複写機 や ワー ドプ ロセ ッサ ーなどのよ うに、言語 や映像情報 を編集 0加 工 しハ ー ド コ ピー として出力するような機器 に特徴的 なキー配列 の概念 モデルである。 Aは い ささか極端 なキー配列を示 したものであるが、 [120%][変 形][私][C-3P][平 体]な どの単語 が 品詞 の区別 な く失語症的 にランダムに配置 された例 である。 この場合操作者 は、すべての単語 =キ ー に対 して正 しい設定・ 変更 を した上で、最後 に全体 の中か ら [変 形]を 選択 して操作 を実行 し なければな らない。一方、操作者 の行為 を秩序 だった言語表現 に置 き換え、 この羅列 された単 語 の品詞 を特定 した場合、<[私 ]は [C-3P]を [120%]の [平 体]で >[変 形]す るといっ たフ レームに準拠す る表現 が導 かれる。 ここで、操作行為 の特性 として重要度 の高 い述語を中 心 にキー配列 を考 えてみると、 Bの ような概念 モデルを描 くことがで きる。前者 との違 い は、 述語を中心 に 目的語 や補語 となるキーを周辺 に配置す ることで、操作 の重み付 けを変えてある 点 である。必 ず実行 されねばな らな いキー と毎回設定・ 変更 を必要 としないキーをグルーピン グす ることは、 誤操作 の防止 を含 めた操作効率 の向上 が 期 待 で きるデザ イ ンにな って い る。D 図 2は 、 カメラの各種設定 ダイアルを図示 した もので ある。 これ は、 図 1の 概念 モ デ ルが Nikon社 のF801に お いて変形 されて実現 された例 とも言 えよ う。 従来 の一 般 的 なカメラにお いては、 Aの ように各種 の設定 ダイアルによって、<フ ィルム感度を100に 合 わせ る><絞 り 優先 オー トで撮 る><3枚 多重露出す る>な どを 目盛 り合わせ方式 やプッシュボタン方式 など、 それぞれ独立 したかたちで設定す るものがほとん どであ った。一方 Bの 方式 は、左側 に集合配 置 された各種設定 ボ タ ンのいずれかを押 しなが ら、右側 の コマ ン ドダイヤルによ って設定・ 変 更 を実行 するといった両手操作 によるもので、 さらに設定・ 変更 の情報 は、中央部 のディスプ A <【 欄 は 図 1 キ■配列の構文化 A 図2 66 B 〉 〉 〉 コマンドダイアルによる構文化 T]を 〔 2溺 ]の IC‐ [平体lで >I変 形する] デザイ ン手法生成のための言語表現と形態表現の関連性 について レイに表示 され るといったイ ンター フェイスを実現 してい る。 この操作 を言語的 な表現 に置 き 換 えれば、<[ISO]を 100に [設 定す る]+[MODE]を 絞 り優先 に [設 定す る]十 [ME] を 3枚 多重露出 に [設 定す る]十 [DRⅣ E]を 高速連続撮影 に [設 定す る]>と なる。 それ 自 述語"を 強力 に支援す る コマ ン ドダイアル 身 では何 の役割 も果たさない [設 定す る]と い う “ を表現 したことによ り、独立併存 して いた操作 を統括 し、構文論的 にフレームに準拠 できる操 作性 をデザイ ンして い る。 図 3は 、 ポー タブル・ ラジオのデザイ ンモデル (Tomas Stark,1985-87)の でぁる。最小限 の大 きさのチューナーが中心 に配置 され、 そこか ら上 に向か って真 っす ぐ伸 びるアンテナ、 さ らに剥 き出 しに近 いス ピーカーが左右一対配置 された構成 は、一般的 な ラジオの形態 デザイ ン か らみればその異様 な形態 にのみ 目を奪 われがちである。 しか しなが ら、 フレーム準拠 (1日 D の視点 か ら眺 めたとき、 ある種 の言語表現 ときわめて近 い類似性 が認 め られる。 ポー タブル・ ラジオの操作行為 は、例 えば<私 は、FM放 送を受信 して音楽 を聞 く>と 表現す ることがで き るが、 ここか ら助詞 を除 いて単語 を羅列 してみ ると、<[私 ][FM放 送 ][受 信 ][音 楽 ][聞 く]>と いった電報文 のよ うな表現 ができあがる。 このよ うな電報文的な表現 の特徴 は、伝 え る内容 を最小限 の文字数 で表す ことで あるが、単語 の順序配列 が狂 って しまうと意味が伝 わ り にくくな って しまう。逆 に言 えば、単語 の順序配列 さえ フレームに準拠 して いれば、最小限 の 構成 であるがゆえに、 それを単刀直入 に表現す ることがで きるわけである。本製品 モデル は、 言語表現 と対応 させれば、 チューナーが [FM放 送]を 、 ア ンテナが [受 信]を 、 ス ピーカ ー が [音 楽][聞 く]を 表 し、 それ らの単語 が適切 な順序配列 (空 間配置)で 構成 されて い る。 そのため、異様 な形態 であるにもかかわ らず、 それが ラジオであること、す なわち「 放送 を受 信 して聞 くもの」 であること及 びその使用法 が明確 に理解 されるデザイ ンとなって い る。 以上 の 3事 例 は、言語表現 における適切 な “ 構文化"が もた らす フレーム準拠 (強 化)を 形 文脈性"に よって形態表現 を支援す る方 態表現 に対応づ けた もの と言 える。 さらに、適切 な “ 法 を示 して いるのが次 の事例 である。 図 4は 、 デ ュアル・ イ ンター フェイス (Dual lnterface)と 呼 ばれる操作 パ ネルの概念 モ デ ルである。例 えば新聞・ 雑誌等 における見出 しと内容、取扱説明書 にお ける基本説明と詳細説 明 といったように、言語表現 においては、 その内容 の骨子 を迅速あ るいは平易 に伝えるために、 その表現 に文脈的 な階層化 を施す場合 がある。先行文 と後続文 の関係 で言 えば、先行文 として の “ 内容説明"に 結 ば 見出 し"は 、<つ まり><す なわち>な どの接続詞 で後続文 としての “ 基本操作"を 示す ときは、<そ して><さ らに>な どの接続詞 で後続文 と れ、 また先行文 が “ ︵ И ︶ m ] □□ □□ □□ A く 口:][FM放 送][受 信][音 莉 [開 く]》 図3 単語の配置 と形態構成 図4 表現の階層化 〉 〉 〉 74 伊 藤 文 彦 しての “ 応用操作"に つ なげ られ るような階層化 が行 われる。本概念 モデル は、後者 のよ うな 事例 である。 Aの よ うに通常 の操作 パ ネルには、各種設定・ 実行 などのボタ ンが、最悪 の場合 ラ ンダムに、良 くて も名称、色、大 きさ、形 などによって同一平面上に分類配列 される程度 で ある。 これに対 して Bは 、基本操作 にかかわるボタ ンのみを露出 させ、応用操作 ボタ ンは利用 時 にのみ表示 され るように通常 はカバ ー して しまうといった物理 的なデザイ ン解決 で、文脈 の 階層化 が表現 されて いる。 図 5は 、 オ ー デ ィオ シス テ ムの デザイ ンモ デ ル (石 川 ,1992)つ で あ る。 Flow Control Systemと 名付け られたこのシステムは、 よ り直接的 に文脈性 を表現す ることで フ レ=ム 準拠 (強 化)に よる操作理解 を向上 させると共 に、機能 が形態 を決定 できない この種 の製 品 に対 し て新 たなデザイ ン解 を示 した ものと言 える。 オーデ ィオ システムは、 ラジオ・ テープ OCDな どの再生 ソースを選ぶ ことか ら、 ボ リュー ム・ トー ン・ バ ラ ンスの設定 など、言語表現 で言 えば、複数 の構文 が複雑 に絡 み合 ったシステ ム と言 える。 これに対 して本 モデルは、最初 の選択項 目を<ま たは>で 表 し、選択 が実行 され ると<そ して>を 意味す る光 の流 れが、次 の<ま たは>に 接続 されるといったフローチャー ト 形式 によってその文脈性 を支援す る方式 を提案 して いる。具体的 に言 えば、 例 えばまずCDを 選択すると、接続 ライ ンに示 された光 の流 れがボ リュームにたど り着 く。 そこで小 か ら大 へ の グ レー ドの中か らあるものを選択す ると、 さらに光 の流れが次 の選択項 目に向か う。 そ して最 終的 には左右 のス ピーカーのバ ラ ンスを選択す るとい うもので、選択項 目についてはいずれ も 再選択可能 な システムである。 本 モデルの操作性 に関 してはユ ーザーによって賛否 の分かれるところであろうが、従来 ブラッ クボ ックスであ った操作 の流 れを可視化 したことは、操作理解 の面 はもちろん のこと、 さらに 操作 自身 を楽 しむ といった別 の側面 か らも注 目に値す る。 そ して何 よ りも、形態デザイ ン自体 が、 “ 操作 の文脈性 の可視化"を ベースに表現 されて い る点 である。 以上 の事例 か ら、 フレーム準拠 (強 化)の 概念 は、 イ ンター フェイスのデザインに関 しては、 構文化 や文脈 の階層化 などを応用す ることによって実現 される。 また、 ラジオやオーデ ィオシ ステムのよ うに物理的に機能 が限定 されない製品 の形態 デザイ ンに関 して、単語配列 の強調 や 文脈性 の可視化を表現する ことで、形状 を決定 できる可能性 が見 いだされた。 [Radb]or[TTl° rIP] ・・・・ dand vol:・ ne 1° r[31● 田 :ぜ 』 」 こ ● ● ■ Tone lll or[21 or[3]● ●● land ll 国・守 ll鷲 州 ISp‐ eF] 図5 文脈性 と可視化された操作 デザイ ン手法生成のための言語表現と形態表現の関連性 について フ レーム 置換 言語表現 のなかで も、 ジョークやユ ーモア表現 は日常生活 の随所 で使用 され、我 々のフレー ムにきわめて特異 な影響 を与 え られ ることが経験的 に も理解 されて い る。 しか しなが ら、 これ らの表現 が言語学等 の本流 か ら外 れるためか、 その役割 や機能、知識構造 の変化 について明 ら かにされていない部分 も多 い。 ここではフレーム概念 を適用 しなが らジョー クやユーモア理解 過程 のモデル化 を行 い、形態表現 へ の類推可能性 について考察 したい。 まず ジ ョーク/ユ ーモ ア表現 の具体例 として、次 のよ うな ものがあげ られる。 (1)あ る夜、狂人 の家 が大火事 にな った。逃 げ出 して来 た狂人 に向か って、 や じ馬 の男 が「 突 然 の出来事 でび っ くりしただろう ?」 、狂人 は「 ああ、気 も狂わんばか りだ ったよ」 侶)サ ラ リーマ ン川柳 :「 一戸建 て まわ りを見れば 一戸 だ け」 ほ)あ る女 の子 が、水道 が出 しっばな しで浴槽 か ら水 が溢 れて い るのを見つ けて叫んだ。 の 「 ママたいへん。 お風呂が足 りない !」 これ らを ジ ョー クとして理解す るためには、二段階 のプロセスを想定す ることが必要 となる。 第 1段 階 としては、MoMinsky(1980)が "予 期 しないフレーム置換"と 呼 んだ よ うに、 「 最初 シーンは 1つ の観点 か ら記述 されて い るが、次 に突然、別 の全 く異 なった様式 で見 るように仕 向 けられる」。 これは言 い換 えれば、 話 の進行 と同時 に初期 フ レー ムに準拠 した暗黙 の仮定 (シ ナ リオ)が 描 かれ るが、突然不一致 が起 こり、初期 フレームは 2次 フ レー ムに横滑 りす る (Frame Slipping)こ とを意味する。 ただ し、 このままでは混乱状態 にあるため、 この状態 を 解消す るために第 2段 階 のプ ロセ スヘ移行す る。 ここでは、初期 フ レーム と 2次 フレーム間 の それぞれの振 る舞 いのパ ター ンを支配す るルールを発見 して二者 を接続す ること、す なわちA. Koestler(1967)が 指摘す る "隠 れた類似性 の発見"を 行 って い るものと考 え られる。 ここで重 要 となるのが不一致 の状態 である。 これがま った く非論理的 な らば、隠 れた類似性 を発見 で き ず笑 いや驚 きも起 こらない。 ところが先 の事例 は、(1)で はパ ラ ドックス121で は語 呂合 わせ(3)で は相対化 によ って、疑似論理 的 あるいは局所論理的 に不一致 を解消 できるために、笑 いや驚 き のよ うな認知的な楽 しみが可能 となるのである。A.Ziv(1984)は さらに、 この不 一 致解消後、 侶)の 事例 にみ られる優越感 や攻撃性、G)の 事例 にみ られる新 たな洞察な どの機能的な楽 しみが ゆ 起 こること もジ ョー ク表現 の特性 として指摘 して い る。 図 6は 、 こうした ジ ョー ク/ユ ーモア理解 の過程 をモデル化 したものである。特 に知識構造 の変化 に注 目すれば、 フレームス リップによる「 フレーム置換」 が重要 な概念 として浮上す る ことが理解 される。以下 ではこの フレーム置換 を軸 に形態表現 との対応づ けを試みたい。 ⇒ 螂 暗黙の仮定 lst Frame 曲 囃 源 魏 L︺ Fmme StippE■ 8 同形態 上 同文脈 上 2回己 FFme の 警 :爾 再 図6 フレーム置換の17 JИ ヒ 認知的な 楽 しみ 機能的な 楽 しみ 伊 藤 文 彦 灰皿"で 起 こるフレーム置換 をモデル化 したもので 図 7は 、川崎和男氏 のデザイ ンによる “ あり、前述 のフレーム置換 モデル と対応 して図式化 されて い る。 ところで、 この鋳物製品 を “ 灰皿"と 称 して い るのはあ くまで商品分類上 のことであり、本製品 の もつ特性 か らは、必ず しも適切 であるとは言 えない。 この理 由 は以下 の分析か ら明 らかになるが、 このことが フレー ム置換 を軸 とした形態表現 の特性 ともな って い る。 形態的 な特徴 に関 しては、上面 にい くつかの くぼみが格子状 に並び、 その うちの 3カ 所 に 3 つの球体 が置かれて い るといった シンプルな構成 である。 ここで仮 に図 7の 左上 のよ うな配 置 で 3つ の球 が置かれて い る場合 を考 えてみたい。 これを見 ると、 その形態 の見 えか ら3× 3の 9つ の くぼみの上 に、 3つ の球 を配置 してい くゲームであるといった初期 フレームが構築 され る。 そのため、 いずれか の球 を手 にとつて移動 させる行為 が次 に起 こる。 ここで端 に置かれた 2つ の球 に関 しては何 の問題 もないのだが、中央 に置かれた球 を移動 させようとした瞬間、初 期 フレームに接続 された暗黙 の仮定 に突然 の不一致 が生 じる。 とい うのは、中央 の球 の置かれ て いた場所 だ けが くぼみではな く穴 にな ってお り、 それによ って この製品 をゲ ーム盤 として眺 め られな くなって しまうか らである。 こうしてユ ーザーにフ レーム置換 がお こり、 2次 フレー ムではその材料・ 形態 か ら灰皿 としての機能 を理解 するとともに、球 の配置 によってはタバ コ を置 くことがで きた り、球 が穴 の蓋 となるといった洞察 を生んで い くことになる。 以上 は、 「 ゲ ニム」 か ら「 灰皿」 へ の置換 を説明 したが、初期状態 によ って は「 灰 皿」 か ら 「 ゲ ーム」 へ の置換 も当然起 こり得 る。 このように、 フレーム置換を含む形態表現 は驚 きや洞 察 を誘発す ると共 に、両義的 な働 きを支援す ることで機能 を限定 しない表現 が可能 となる。 図 8は 、PoStark(1990)の デザイ ンによる レモ ン絞 り器 である。本製品 は従来 のモ ダニ ズ ム の生み出 してきた製品表現 とは著 しくその表現形式 が異 なっている。 そのため、初 めてこれを 見 たとき、 それが昆虫や未知 の生物体 をイメー ジ した彫刻・ オブジェの類 であるとす る初期 フ レームが活性化 され る。 イメージされるもの は見 る側 によって異 なるであろ うが、 そこでは少 な くとも、何 らかの機能 を果 たす製品・ 道具類 であろうといった連想 は不可能 であろう。 ところが、 いったん この製品 に、 二つ割 りにされた レモ ンがかぶせ られた らどうなるであろ うか。、オブジェとして認識 して いたフ レームはス リップ し、 レモ ンに関係す る道具 として認識 す るフ レームに置換 させ られ る。 これによ り、 それまで生物 の胴体 に見立て られて いた中央上 ヽ ゝ ノ いき 笑露 図 7 ゲームー灰皿 ■ゝ ノ ●●● ● 00 ●● ● 笑い 露● 洞察 図 8 オブジェー レモン絞 り デザイン手法生成のための言語表現 と形態表現の関連性 について 部 に配置された紡錘形 は、 レモンを圧 し潰す道具 として理解され、 さらに、 その紡錘形 に施 さ れていた模様 は果汁を垂 らすための溝 に、1動 的に伸 びた 3本 足 はコップのセ ッ トを可能 にする ための構造体であることへ と理解が進む。その過程でフレーム間の不一致が解消 されてい くの である。 このように、本例 における「 オブジェ」か ら「 レモン絞 り器」へのフレーム置換 は説 明 されるが、 これ も前例 と同様 に「 レモ ン絞 り器」 か ら「 オ ブジェ」 へ のフレーム置換 も起 こり得 るはずである。 その理 由は、本商品が「 レモ ン絞 り器」 の名称 で販売 されて い るに もかかわ らず、 「 オブジェ」 として使用 して い るユー ザ ーが 圧倒的 に多 いことか らも明 らかであろう。 こうした ことは、 従来 のメ タファー (Metaphor=隠 喩)を 軸 と した製 品記号 論 における「 オブジ■のよ うな レモ ン絞 り」 といった解釈 に 止 どま らず、 「 レモ ン絞 りのよ うなオブジェ」 といった修飾・ 被修飾 の関係 が可逆的 に転移す るといったフ レーム置換 の特 性 を示す ものと言 える。 図 9は 、HyperCardの スタックを利用 した、対話す るため の コンピュー タアプ リケーシ ョン (『 脳 のシワ』大重美幸 1990)。 の使用例 である。通常 の対話表現 か ら見れば い ささ か混乱 した文脈 とな って しまう理由は、 アプ リケーシ ョン側 の不完全 な言語表現 デー タベースによるものである。 こち ら ; が入力 した文章 か らキー ヮー ドを特定 し、 そのキー ワー ドを 含 んだ肯定文、疑問文、否定文、否定疑 問文 のいずれかを検 索 して応答するので あるが、 あ らか じめ準備 された文章表現 の乏 しさか ら意味的 に文脈 がずれて しまう。例 えば「 ライバ ルを [料 理する]」 が食事 の料理 に、 「 水泳 で [勝 つ]」 が強 い相撲取 りにといった具合 である。 これを要領 を得 ない対話 ソフ トだと言 えばそれまでであるが、 フレーム概念 か らみれ ばい くつかの重要 な視点 が見 いだせ る。 それは使用例 か らも 明 らかであるように、何度 とな くフレーム置換 が連鎖す る こ とによ り対話 自身 が活性化・ 促進化 され、同時 に、効率 の良 い帰納的 な結論 は得 られない ものの、遊 びの中で演繹的に発 想 のフィール ドが広が って いる点 である。 よ り具体的 に言 え ば、 フレーム置換 の概念 は、医療診断 の エキスパ ー トシステ ,"年 9月 水颯口面餞●パッキー ■42E9PM "日 Oこ れはどうも 0水 泳は好きかい? ●マット●ピヨンディが好きなんです 0パ タフライだれ ●パタフライはかつこいいですね 0■ のよう出 ●それはそれは 0大 会では、こんどこそライパルを料理したい. ●簡単な料理を紹介しtし ょう。 うどの皮のさんびら。アポガ ドの 書. 脅しそ風味のごぼうと牛肉のうま“ 露 , どれにしましようか。 0そ うでなくて、日つ方油だよ。 ■: ●それにしても小諄は強υ 0■ いかられ ●昭に注目してるんですよ _ : Oア メリカ人だつけ? ー ●シンガボ ルに行つたことがあります 0海 はされいだつたかい? ● 保層がプームで終わらなければいいですね =境 0ユ 空がみえなくなるのはさみしいれ ●そうてい 。知りませんでした O二 を見たことがないのかい ? ●それで? 0宇 宙の風だよ。 ●ホーキングはどこまで解明してくれるでしよう 0国がいいかられ 0日 頃連動をしていま悧 0蛛 泳をしています。 ●マット ・ ピヨンディが好きなんです Oさ よなら ●ばいばい │ … PM fじ ムなどがもつ分析的な思考を支援するためでなく、 「 発想や 図9'対 話 ― アイデア展開」を支援するツールのインターフェイスやシステムのデザインにとって主要な軸 とな り得 ることが想定 されるのである。 ま とめ と考 察 言語表現 が我 々の知識 に与 える変化 と して フレーム準拠 (強 化)と フレーム置換 の二つ の概 念 を導 き、 それ らを形態表現へ類推 す ることの可能性 とその手法及 び効果 にういて考察 した。 その結果、種 々の形態表現 の中 に同概念 を措定 できることか ら、 これ らを対応付 け られる こと 78 伊 藤 文 彦 が明 らか とな った。 その手法 と効果 については、 1.フ レーム準拠 (強 化)は 、我 々の使用す る言語的な秩序 (文 法)を 形態 の部分 (ex.操 作 パ ネル)ま たは全体 の配置構成 に反映 させることによ って起 こる。 これによ り、 イ ンター フェ イスのデザイ ンに関 して「 理解」 を支援す るとともに (事 例 1∼ 5)、 機能 が特定 で きない製 品 の形状 に関 して「 表現」 を支援す ることが可能 となる (事 例 3、 5)。 2.フ レーム置換 は、通常 の理解 における暗黙 の仮定 に基づ く表現 と、 それに破綻 を引 き起 こ す ような表現 とを交錯 させ ることによ つて起 こる。 これによ り、 形態表現 に「 笑 いや驚 き」 「 洞察」 などを組 み込む ことが出来 るとともに、 「 置換す る機能」 をもった製品 デザイ ンが可能 となる (事 例 7、 8)。 さらに、 イメージプ ロセ ッサーなどの新種 の シス テ ム デザイ ンに関 し て「 発想や アイデア展開」 を支援す る (事 例 9)。 以上 のよ うに、新 たなデザイ ン手法 の軸 として措定 できたフ レーム準拠 (強 化)と フレーム 置換 は、道具・ 機器 の形状 デザイ ン、 イ ンター フェイスデザイ ン、 システムデザイ ンと拡張す るデザイ ン分野 に共通 して適用可能 な概念 としてその意義 が認 め られるものと言 えよう。 それ はまた、 モ ダ ンデザイ ン支持 してきた「 形態 は機能 に従 う」 といった命題 の今 日的 な破綻 に対 す るひとつの打開策 で もある。 なぜな ら、 フ レーム準拠 (強 化)は 、機能主義 の拡張概念 であ こ り、 フレーム置換 は、機能主義 がそ ぎ落 として きた 重要 な無駄"の 見直 しにほかな らないか らである。 謝辞 本研究 は、 1992年 日本 デザイ ン学会ID部 会 セ ミナー発表「 形態 の文脈」 をベー スと して い る。 当 セ ミナーの共同発表者であ った石川輝記君 には、本論文作成 にあたって も多数 のアイデアに 富んだ示唆 をいただいた。 この場 を借 りて感謝 の意を示 したい。 注及 び引 用文 献 1)伊 藤文彦 ;「 デザイ ン・ プロセスの諸特性 について」,静 岡大学教育学部研究報告 ひdい 社会科学篇)第 38号 ,pp.47∼ 56,1987 2)伊 藤文彦 ;「 デザイ ン・ プ ロセスにおける “アレゴ リー"と “レフ ァレンス"に ついて」 , 静岡大学教育学部研究報告 (人 文 0社 会科学篇)第 41号 ,pp.75∼ 84,1991 3)マ ー ビン ,ミ ンスキー ; 疇いの社会」,産 業図書 ,p.393∼ 458,1990 4)渕 一博 編著 ;「認知科学へ の招待」,NHKブ ックス,p.148,1982 5)原 田,須 永 ,伊 藤他 ;「 シンフォニア :参 加型情報環境装置の提案」,第 35回 日本 デザイ ン 学会作品 0設 計発表 ,1988 6)向 井周太郎 監修 ;「 今 日の デザイ ンー世界 イ ンダス トリアル デザイ ン展 カ タ ロ グ」 , p.109,1989 7)石 川輝記 ;『「 つ くられた もの」 と「 書 かれた もの」 との関連 について』 ,静 岡大学大学 院教育学研究科修士論文抄録 ,p.42,1992 8)織 田正吉 ;「 ジ ョークと トリック」,講 談社現代新書 ,p.62,1983 9)KoS.ウ ィル ソ ン ;「 ユーモア理解 の過程」,理 想617号 所収 理想社 ,pp。 209∼ 224,1984 10)大 重美幸 ;「 人工知能 (も どき)ス タックー脳 のシヮ」,日 本 ス タックマガジン社 ,1990