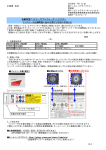Download 家計における資産構成の在り方について
Transcript
平成 26 年度『証券ゼミナール大会』 第 5 テーマ 「家計における資産構成の在り方について」 5 10 15 20 25 関西学院大学 阿萬ゼミナール 藤原班 1 目次 序章 第一章 5 10 p4 日本の資産構成 第一節 資産構成の現状分析・問題点 第二節 貯蓄から投資へ 第三節 資産構成の海外比較 第二章 家計を取り巻く環境 p10 第三章 三世代世帯と家計資産 p16 第一節 三世代同居のメリット・デメリット 第二節 高齢者における金融教育 第三節 三世代世帯のリスクに対する耐性 第四節 三世代同居の促進方法 第四章 15 p3 はじめに p28 家計資産構成の改善策 第一節 学生金融教育の推進 第二節 NISA 制 度 と 投 資 信 託 の 改 善 第三節 好ましい資産構成の在り方 終章 p35 おわりに p36 参考文献 20 25 30 2 序章 は じめ に 本稿では家計における資産構成を、日本の資産構成の現状 ・問題点と、家 計を取り巻く環境の二つの面から考察していく。ここで、 家計を取り巻く環境 を「雇用・生活・再分配」の三つに分類した。 5 第一章では、家計金融資産を構成する項目を①現金・預金、②株式以外の証 券 、③ 株 式 ・ 出 資 金 、④ 保 険 ・ 年 金 準 備 金 、⑤ そ の 他 と し 1 、現 状 ・ 問 題 点 や 海 外比較などを通して、日本の資産構成を見ていく。 第二章では、家計を取り巻く環境から「雇用形態の現状・教育面から見た家 計の経済的負担・高齢化」という問題の存在を浮き彫りにし、これらの問題が 10 家計の資産構成に対してどのような影響を及ぼすのか、考察していく。 第三章では、わたしたち独自のアイデアとして、 三世代世帯を構成すること を提案する。第一章より「資金的余裕のなさや金融知識のなさが投資妨げ要因 と な る 」、第 二 章 よ り「 雇 用 の 不 安 定 や 教 育 費 の 問 題 、少 子 高 齢 化 に よ る 社 会 保 障制度存続の危機」という問題を導き、これ らを解決するために三世代同居が 15 有効ではないかと考えた。三世代同居のメリット・デメリットも踏まえて、ど のように資産構成に影響していくのか考察したい。 第 四 章 で は 日 本 の 資 産 構 成 を 変 え て い く た め に 、 金 融 教 育 と NISA 制 度 ・ 投 資信託の改善を提案した。現在、日本の教育課程で行われている金融教育では 「金融システム」を中心に学習しており、個人の生活に関する金融(パーソナ 20 ルファイナンス)についての内容が取り入れられていない。このため、金融商 品に関しての知識が乏しく、多くの日本人が現預金を選択していると考えられ る。パーソナルファイナンス教育を行うことにより、この問題を改善していき た い 。 そ し て 、 NISA 制 度 と 投 資 信 託 は 複 雑 化 ・ 多 種 多 様 化 さ れ て い る 。 そ の ため、金融知識が乏しい人にとって理解が困難であり、金融商品の選択肢を狭 25 めていると考えられるので改善の必要がある。 以上のことを踏まえ、家計における資産構成の在り方について検討していく こととする。今回の私たちの論文により、各家計の資産構成が再考されると 幸 いである。 1 この分類は日本銀行調査統計局による。 3 第一章 第一節 日本 の資 産 構成 資産構成の現状分析・問題点 日 本 で は 今 日 ま で 、 家 計 金 融 資 産 の 約 半 分 を 現 預 金 が 占 め て い る ( 図 表 1‐ 5 1 参 照 )。な ぜ 現 預 金 中 心 の 資 産 構 成 な の か 、主 に 考 え ら れ る 理 由 を 三 つ 挙 げ る 。 一つ目に安全志向の高まりがある。土地・株式投資のパフォーマンスが悪かっ た こ と が あ る ( 図 表 1‐ 2 参 照 )。 二 つ 目 に 、 年 金 ・ 社 会 保 障 な ど に 対 す る 将 来 不安が高く家計の生涯所得期待が高まらないことなどから安全志向が高まり 、 貯蓄型の資産構成となったと考えられる。生命保険文化センターによるアンケ 10 ー ト 調 査 2 よ り 、 老 後 の 生 活 に 対 し て 「 不 安 あ り 」 の 人 は 全 体 の 86% に も 及 ん だ。三つ目に歴史的な政府の政策による影響がある。明治維新以来、国民が郵 便局などに預けたお金を産業に回すために政府は貯金を奨励 してきた。企業も 株式や債券を発行し直接資金調達するより、 家計の余剰資金を、銀行から間接 的に調達している。現在も間接金融への依存度は高いままである。 15 預金金利が低金利である今、現預金に依存していても 資産は増えず、また株 式市場も活性化しない。株式を保有していないと経済が上向いても、 家計はそ の効果を享受することができないのである。株式投資が増加すると、リスクマ ネ ー 供 給 量 が 増 加 し 、経 済 が 活 性 化 す る 3 。そ の 結 果 家 計 の 金 融 資 産 が 増 加 す る 。 家 計 の 金 融 資 産 総 額 が 増 え て い る こ と が 図 表 1‐ 1 よ り 読 み 取 れ る 。 2014 年 20 6 月 末 に は 1,645 兆 円 4 と な り 過 去 最 高 と な っ た 。近 年 の 増 加 要 因 に は 、図 表 1‐ 2 からわかるように、アベノミクスによる株高により、保有している株式や投 資信託の評価額が上昇したことが挙げられる。また、新たに投資信託を購入す る人が増えたことも影響しているだろう。 相対的な金融資産額の増加には、日 本経済規模の拡大が起因していると考えられる。 25 2公 益 財 団 法 人 生 命 保 険 文 化 セ ン タ ー に よ る 「 生 活 保 障 に 関 す る 調 査 」 ア ン ケ ー ト 調 査 ( 2013) よ り 引 用 ( http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/oldage/5.html ) 3家 計 の 株 式 の 保 有 率 が 高 く な る と 、 企 業 に リ ス ク マ ネ ー が 回 る 可 能 性 も 高 く なり、経済向上につながると考えた。 4 「 資 金 循 環 統 計 ( 2014 年 第 2 四 半 期 速 報 ) 」 p2 日 本 銀 行 調 査 統 計 局 よ り デ ータ引用 4 【 図 表 1‐ 1 日本の家計の金融資産構成の推移】 家計の金融資産推移 (万円) 1,800 1,600 5 1,400 1,200 1,000 800 600 400 10 200 0 1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 (年度) 現預金 投資信託 債券 株式・出資金 保険・年金準備金 その他 出 所 :「 デ ー タ コ ー ド 一 覧 」 日 本 銀 行 調 査 統 計 局 ( 2014) p7 よ り デ ー タ コ ー ド 引 用 15 「時系列統計データ検索サイト」日本銀行よりデータ引用、筆者作成 【 図 表 1- 2 日経平均株価の推移】 日経平均株価の推移 (円) 25,000 20 20,000 15,000 10,000 25 5,000 0 1990 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 (年) 出 所 :「 日 経 平 均 プ ロ フ ィ ル 日 経 平 均 資 料 室 年 次 デ ー タ 」 よ り デ ー タ 引 用 、 筆 者 作 成 30 5 し か し 金 融 資 産 の 約 70% を 世 帯 主 60 歳 以 上 の 世 帯 が 保 有 し て お り 、 少 子 高 齢化により将来、金融資産額は減少すると予測される。金融資産額が減少する と経済に悪影響が及ぶ。例えば、現在のように金融資産が潤沢であれば、 国債 を国内消化できると言われているが、それが減ると、国債を海外投資家に売ら 5 なければならない。海外の投資家に購入してもらうために金利を高くする必要 性が出てくるが、そうなればさらなる財政悪化が起こり、さらに住宅ローン金 利 が 上 昇 す る な ど 家 計 に と っ て 痛 手 と な る 5。 つまり、現預金中心の資産構成では経済が活性化せず、その結果 、税収の落 ち込みによる財政悪化や雇用の不安定化などが起こり、家計自身が苦しむこと 10 になるのだ。この点が日本の家計資産構成の最大の問題点であろう。 【 図 表 1‐ 3 世帯主年齢階級別金融資産保有額】 世帯主年齢階級別金融資産保有額 (千円) 20,000 15 15,000 10,000 5,000 20 0 -5,000 平 均 30 歳 未 満 30 ~ 二人以上世帯 25 39 40 ~ 単身世帯 49 50 ~ 59 60 ~ 69 70 歳 以 上 (歳) 総世帯 出 所 :「 平 成 21 年 全 国 消 費 実 態 調 査 世 帯 主 の 年 齢 階 級 別 1 世 帯 当 た り 資 産 額 」 総務省統計局よりデータ引用、筆者作成 注 1) 金 融 資 産 = 貯 蓄 - 負 債 で 求 め て い る 注 2) 二 人 以 上 の 世 帯 ・ 勤 労 者 世 帯 の デ ー タ を 使 用 5 毎 日 新 聞 東 京 朝 刊 6 貢 2014 年 10 月 5 日 掲 載 を 参 照 6 第二節 貯蓄から投資へ 第一節で挙げた問題点を解決するために、家計の現預金を投資に向けるべき だ と 考 え た 。 日 本 経 済 新 聞 の 記 事 6 に よ る と 、『 我 が 国 に は 1,600 兆 円 を 超 え る 家 計 資 産 が あ る 。 そ こ か ら 生 ま れ る 運 用 リ タ ー ン は 、 国 内 総 生 産 ( GDP) の 成 5 長 よ り も 、経 済 的 な イ ン パ ク ト は 大 き い 。運 用 リ タ ー ン が 1% 向 上 し た だ け で 、 得 ら れ る 税 収 は 消 費 税 の 1% 分 を 上 回 る 。』と あ る 。こ の 記 事 よ り 、家 計 に 滞 る 資産は投資に回るべきだと考えられる。 し か し 図 表 1‐ 4 か ら 分 か る よ う に 、 投 資 に は 様 々 な 妨 げ 要 因 が 存 在 す る 。 回答割合が高かった上位 3 つを日興アセットマネジメントのアンケート調査よ 10 り引用した。投資に向ける資金的余裕がなかったり、株式などは元本保証がさ れていないため元本割れリスクが存在したり、そもそも金融知識がないため、 知らないものには手を出さないとする考えなど多く存在する。 投資をする資金 をつくる策は後の第三章で、世帯構成のあり方(三世代世帯・核家族世帯)の 面 か ら 考 察 す る 。知 識 を 身 に つ け る た め の 金 融 教 育 に つ い て は 第 四 章 で 述 べ る 。 15 そして、元本割れリスクに関して、万が一金融機関が破たんしたとしても預 金保険機構により保護されているので安全だと考える人が多い が、ペイオフ制 度 に よ り 一 般 預 金 等 は 元 本 1,000 万 円 ま で と 利 息 し か 保 護 さ れ な い 。 さ ら に 、 預金を時間外に引き出しをすれば時間外手数料が発生し元本割れをする。その ことに気が付かず、投資だけが元本割れリスクがあると考えるのは金融知識不 20 足の表れである。そして、現預金が必ずしも安心・安全だとは限らない。現預 金にはインフレリスクが伴っている。インフレーションが起こ ると物価が上昇 し、そのぶんお金の価値が目減りするのである。 ここまで預金のリスクを挙げたが、投資にもリスクは付き物である。 主なリ スクに、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスクが挙げ 25 られる。リスクはリターンと密接な関係があり、リスクが高ければリターンも 高 く な る 7 。し か し ハ イ リ ス ク 商 品 を 購 入 す る と き 、少 し で も リ ス ク を 制 御 し た 「 大 機 小 機 家 計 か ら 成 長 へ の 循 環 」 日 本 経 済 新 聞 朝 刊 2014 年 8 月 6 日 17 貢より引用 7 リスクとリターンは経済情勢などによって変化し、必ずしもいつも同じとは 限らないことに注意が必要である。 6 7 いと考えるであろう。その時に有効な方法が分散投資である。分散投資の方法 には、金融商品の分散や国際分散、通貨の分散、時間の分散など存在し、これ らを組み合わせることによってリスクを制御することができる。 金融商品を自由に選択することができるかわりに、利益と損失について責任 5 を持つことを「自己責任の原則」という。自己責任とは「選ぶ力」を身につけ ることであり、このために、ディスクロージャー誌を利用したり相場変動を把 握できるようにしたりすることが重要である。この力を身につけることもリス クの制御につながる。 【 図 表 1‐ 4 10 こ れ ま で 投 資 を し な か っ た 理 由 ( 複 数 回 答 可 )】 これまで投資をしなかった理由(複数回答可) 投資をする資金がない 15 元本割れのリスクを冒したくないから 知識がない 20 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 出 所 :「 投 資 信 託 に 関 す る 意 識 調 査 」 日 興 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト ( 2011) よ り 筆 者 作 成 ( http://www.nikkoam.com/products/g oikenban/questionnaire/09 ) 25 第三節 資産構成の海外比較 こ こ で 諸 外 国 の 資 産 構 成 の 特 徴 を 見 て み る 。 図 表 1‐ 5 よ り ア メ リ カ は 投 資 信託や株式・出資金の割合が非常に高い。 このタイプの資産構成は景気変動な どの影響を受けやすい。イギリスは保険・年金準備金の割合が高い。 イギリス の保険・年金準備金は日本でいう「確定拠出型年金」や「変額年金保険」など 30 に類似する。日本ではまだまだ運用型の保険が普及しておらず、イギリスとの 8 内容の違いに着目すべきである。ドイツは債券の割合が高く、全体的にバラン スがよい。以前は日本と同じくリスク回避的だと言われていたが、近年は投資 信託を通じて株式を保有している。日本はドイツに後れをとっている。 フラン スは株式・出資金や保険・年金準備金の割合が比較的高い。 フランスは金融改 5 革 を 行 い 、そ の 結 果 1984 年 に 5 割 を 占 め て い た 現 預 金 の 比 率 8 は 下 が り 、株 式 等の比率を高めていった。 【 図 表 1‐ 5 家計金融資産の国際比較】 家計金融資産の国際比較 現預金 債券 投資信託 株式・出資金 10 アメリカ イギリス 1.8% 5.0% 9.1% 53.1% 日本 13.1% 5.0% 13.1% 28.6% 保険・年金準備金 その他 26.8% 33.5% 4.2% 32.3% 3.3% 10.63% 0.9% 2.9% 53.2% 3.4% 15 38.2% ドイツ フランス 20 28.4% 出所:日米 その他 7.5% 1.4% 6.7% 16.5% 11.9% 7.9% 33.9% 39.9% 0.6% 7.0% 「 資 金 循 環 の 日 米 欧 比 較 」 日 本 銀 行 調 査 統 計 局 ( 2014) p2 よ り 「 統 計 で み る 日 本 」 日 本 統 計 協 会 ( 2014) p52,p53 よ り 筆 者 作 成 図 表 1‐ 5 で 挙 げ た 国 の 中 で 、 現 預 金 が 50% を 占 め て い る 国 は 日 本 だ け で あ る。現預金は決して活用されていないわけではないが、投資に比べて経済に与 25 え る 影 響 が 少 な い 。 第 一 節 の 図 表 1‐ 3 で 示 し た よ う に 、 金 融 資 産 総 額 が こ れ から減少することが予測される。つまり、金融資産を増額させるためにはアメ リカ型のように株式・出資金を高める必要がある。 アメリカの金融資産総額は 8 「フランスにみる企業金融と個人金融資産動向‐ユーロ導入前夜‐」村岡ひ と み p199 よ り 引 用 9 2014 年 6 月 末 時 点 で 約 67 兆 ド ル 9 で あ り 、1 ド ル =107 円( 2014 年 10 月 23 日 時 点 ) 1 0 で 換 算 す る と 約 7,169 兆 円 の 金 融 資 産 を 保 有 し て い る こ と と な る 。 し かし、貯蓄型の資産構成をアメリカ型に完全移行するより、株式・出資金より ローリスクな債券や、投資信託の割合を高めたり、保険・年金準備金の割合を 5 高めたりしてドイツ型のようなバランスのよい資産構成を目指すほうが実現可 能性は高い。好ましい資産構成の在り方については 第四章第三節で述べる。 第二章 10 家計 を取 り 巻く環 境 次に、家計を取り巻く環境を雇用・生活・再分配の3つに分類し家計の資産 構成のあり方を考察する。まず、家計の資産に与える問題点として ①雇用形態 の現状、②教育面から見た家計の経済的負担、③高齢化を挙げる。これらが、 家計の貯蓄率の低下を招いている主な要因と 推測されるからである。因果関係 を以下で導くことにする。 15 第一に雇用の面から分析していく。雇用は家計の所得を支える大きな要素で あり、バブル崩壊以降の経済成長は鈍化し、失業率は上昇するなど国民の生活 水準は低下傾向が続いている。また少子高齢化の進展や製造業 に立脚した産業 構造は国際競争の影響により、企業は非正規雇用などを多く生み出した。なぜ なら日本の産業構造の特徴として、産業全体に占める製造業の割合が海外に比 20 べて高く、そういった産業構造が損益分岐点の引き下げを狙っていたからであ る。 図 表 2- 1 よ り 、 非 正 規 雇 用 者 の 割 合 は 就 業 者 全 体 の 3 分 の 1 を 超 え 、 特 に 女性は半数以上が非正規雇用によって所得を得ていることが分かる。こういっ た非正規雇用の拡大は先進国共通の現象で ある。非正規雇用者の特徴は、収入 25 を支出に回さざるを得ず、貯蓄ができないことである 。 「 資 金 循 環 の 日 米 欧 比 較 ( 2014 年 第 2 四 半 期 速 報 )」 日 本 銀 行 調 査 統 計 局 p2 よ り デ ー タ 引 用 1 0 Yahoo フ ァ イ ナ ン ス よ り デ ー タ 引 用 9 10 【 図 表 2‐ 1 男女別雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合の推移】 男女別雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合の推移(%) 70 5 60 52.9 50 40 44 39.1 31.9 30 21.7 10 38.2 35.5 24.6 20 10 57.5 55.2 9.9 11.1 平成4年 平成9年 22.1 19.9 16.3 0 総数 平成14年 男性 平成19年 女性 平成24年 出 所 :「 就 業 構 造 基 本 調 査 」 総 務 省 統 計 局 ( 2014) よ り 筆 者 作 成 15 第二に、生活の面として子供の養育費について分析する。文部科学省による と 、平 成 24 年 度 の 子 供 の 学 習 費 総 額 の 平 均 は 図 表 2‐ 2 の 通 り で あ る 。例 え ば 、 す べ て 私 立 の 学 校 に 通 っ た 場 合 で あ れ ば 、15 年 間 の 総 学 習 費 は 約 1,678 万 円 に な る 。 こ れ に 、 出 産 ・ 育 児 費 用 や 食 費 、 医 療 費 な ど を 加 え る と 、 約 3,000 万 円 以上にのぼる。 20 【 図 表 2‐ 2 子 供 の 学 習 費 総 額 (平 成 24 年 度 ) 公立 幼 稚 園 (3 年 ) <単 位 ; 円 >】 私立 660,000 1,460,000 小学校 1,830,000 8,540,000 中学校 1,350,000 3,890,000 高等学校 1,160,000 2,890,000 出 所 :「 平 成 24 年 度 子 供 の 学 習 費 調 査 」 文 部 科 学 省 よ り 筆 者 作 成 しかし、先述の通り現状では非正規雇用の拡大により収入が低下しているに も 関 わ ら ず 、共 働 き が で き て い な い 。内 閣 府 が 平 成 24 年 3 月 に 発 表 し た 、「 都 市と地方における子育て環境に関する調査」によると、未就園から小学校まで 11 の 子 を 持 つ 女 性 の 保 育 所 、幼 稚 園 、子 育 て 支 援 サ ー ビ ス に 対 す る 不 満・要 望 は 、 「 送 り 迎 え の 時 間 な ど に 融 通 を 利 か せ て 欲 し い 」 が 22.7%と 最 も 多 く 、 次 い で 「 受 入 児 童 枠 が 少 な い 」が 18.9%、 「 延 長 保 育・預 か り 保 育 が で き な い 、し に く い 」 が 18.5%と な っ て い る 。 こ の 調 査 か ら 、 共 働 き が で き る 環 境 が 整 備 さ れ て 5 い な い こ と が う か が え る 。 そ れ に 対 し 図 表 2‐ 3 を 見 る と 、 子 ど も 一 人 世 帯 の 平均貯蓄率は、子どもが大学に入るころにはマイナスになっていることが分か る。多額な養育費に対し、収入は低下し ており、さらに共働きさえできないの である。また、低賃金であるがゆえに支出に回さざるを得ないという事態であ り、ますます貯蓄率は低下傾向になる。 10 【 図 表 2‐ 3 15% 子ども 1 人世帯の平均貯蓄率】 14.0% 11.7% 10% 15 9.8% 9.4% 5% 0% -1.6% -5% -7.6% 20 -10% 2歳以下 3~6歳 小学生 中学生 高校生 大学生 出 所 :「 平 成 21 年 全 国 消 費 実 態 調 査 」 総 務 省 統 計 局 よ り 筆 者 作 成 25 ま た 、 図 表 2‐ 4 か ら も 経 済 的 負 担 の 大 き さ や 出 費 が か さ む こ と が 挙 げ ら れ ており、家計の経済状態を圧迫していると読み取れる 。 30 12 【 図 表 2‐ 4 子 育 て を し て い て 、 負 担 ・ 不 安 に 思 う こ と に つ い て 】 19.0% 負担に思うことは特にない 11.8% 37.6% 40.0% 将来予想される子どもにかかる経済的負担 5 33.5% 36.9% 子どもが病気のとき 7.1% 仕事が十分にできない 10.7% 25.1% 夫婦で楽しむ時間がない 10 18.7% 子育ての出費がかさむ 36.5% 41.5% 18.6% 子育てによる身体の疲れが大きい 27.6% 夫 妻 出 所 :「 都 市 と 地 方 に お け る 子 育 て 環 境 に 関 す る 調 査 」 内 閣 府 ( 2012) p75 よ り 筆 者 作 成 第三に、人口高齢化の面から分析していく。高齢化により、今後社会保障費 15 は増大していくことが予想される。また、現行の公的年金制度の持続可能性も 懸 念 さ れ て お り 、第 一 章 第 一 節 で 挙 げ た ア ン ケ ー ト 調 査 1 1 か ら も わ か る よ う に 、 年 金 に 対 し て 不 安 を 抱 い て い る 人 は 多 い 。 実 際 、 平 成 12 年 年 金 改 正 に よ る 見 直し後もなお、将来の厚生年金給付額のうち、現在の保険料率、国庫負担でま か な え る 部 分 は 全 体 の 約 4 分 の 3 に と ど ま り 、不 足 分 約 530 兆 円 を 将 来 世 代 の 20 負担を増やすことでまかなうことになっている。 日本では、現役時代が所得の一部を貯蓄に回し、高齢期にその貯蓄を取り崩 して消費するライフサイクル仮説というものが存在する。このような考え方に よ り 、近 年 高 齢 化 に 伴 っ て 貯 蓄 率 が 低 下 し て い る 。 「 日 本 の 高 齢 者 の 貯 蓄 行 動 12」 か ら も 、60 歳 以 上 の 家 計 貯 蓄 率 が 大 き く 低 下 し て い る こ と が 分 か る 。ま た 、日 25 本 全 体 の 家 計 貯 蓄 率 を 見 て も 、1970 年 代 に は 20%以 上 で あ っ た が 2010 年 に は 2.5%に な っ て い る 。 一 方 、 図 表 2‐ 5 の 通 り 、 高 齢 化 が 進 ん で い る ド イ ツ や フ ランスでは、貯蓄率はそれほど低下しておらず、高齢化と貯蓄率低下の関係性 11公 益 財 団 法 人 生 命 保 険 文 化 セ ン タ ー に よ る 「 生 活 保 障 に 関 す る 調 査 」 ア ン ケ ー ト 調 査 ( 2013) よ り 引 用 http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/oldage/5.html 1 2 日 本 銀 行 調 査 統 計 局 ワ ー キ ン グ ペ ー パ ー ( 平 成 12 年 8 月 ) よ り 引 用 13 は見られない。フランスでは手厚い家族手当などの社会保障に加え、比較的早 い段階から多様な保育システムを整備した結果、女性の社会進出が進んだ。し か し 、「 年 金 な ど の 社 会 保 障 制 度 を 維 持 す る た め に 国 と し て 必 要 な 家 族 政 策 を 行うのは当然の責務」であるとの認識から、他の先進国と比べて高い出生率を 5 維持することが可能となっている。一方ドイツは、児童手当はフランスなみに 手厚いものであるが、保育施設の整備が遅れていたことや保育時間の短さなど から、女性にとって育児の負担が大きく、低い出生率となった。このような社 会保障制度の水準の違いから、日本人は自分の将来のために貯蓄するという考 え 方 を 持 つ よ う に な っ た と 考 え ら れ る 。日 本 郵 政 公 社 の 調 査 に よ る と 、60 歳 代 10 の 約 6 割 、 70 歳 以 上 の 約 5 割 が 病 気 や 介 護 に 備 え る た め に 貯 蓄 を 増 や す と 回 答 し て お り 、 図 表 2‐ 6 か ら も 分 か る よ う に 高 齢 者 の 予 備 的 貯 蓄 動 機 は 強 い 1 3 。 【 図 表 2‐ 5 (%) 15 日独仏の貯蓄率動向】 日独仏の貯蓄率 18 16 14 12 10 8 6 20 4 2 0 1995 2000 2005 日本 2010 ドイツ 2011 2012 2013 2014 (年) フランス 25 出 所 :「 統 計 で み る 日 本 」 日 本 統 計 協 会 ( 2014) p51 よ り 筆 者 作 成 13 「 家 計 貯 蓄 率 の 低 下 は 今 後 も 続 く の か 」 み ず ほ 総 合 研 究 所 ( 2007) p5 を 参 照 14 【 図 表 2‐ 6 年齢階層別貯蓄動機】 5 10 出 所 :「 家 計 貯 蓄 率 の 低 下 は 今 後 も 続 く の か 」 み ず ほ 総 合 研 究 所 ( 2007) p6 よ り 引 用 しかし、少子高齢化が与える影響は悪いものばかりではない。我が国の家計 15 は、金融資産の多くの割合を高齢者が保有しているため、高齢化により、こう した傾向はますます強くなると言われている。また、高齢期の生活 スタイルと して、高齢期を自己啓発し、積極的かつ活動的に行動しようと考えている層が 現れ始めているとの指摘がある。これらの人たちはアクティブシニア層と呼ば れ 、金 融 資 産 選 択 に 対 す る 考 え 方 と し て は 、利 回 り や キ ャ ピ タ ル ゲ イ ン を 重 視 、 20 証券会社の利用の経験が多い、有価証券保有比率が高いなどの特徴があるとさ れている。アクティブシニア層は、時間に余裕がある富裕層でかつ金融に関す る知識も比較的豊富である層だと考えられるので、この層が増加すると将来の 高齢者層のリスク資産への選択志向が高まることになる。 したがって、高齢化による社会保障制度の悪化に対し、貯蓄をするという今 25 の日本の考え方ではなく、アクティブシニア層にターゲットを絞ったり、方法 を明確にしたりするなどして、投資に回す必要がある。可能性としては、財務 省によれば、公的年金制度の見直しにより、私的な年金制度または個人による 長 期 の 資 金 運 用 の 重 要 性 が 高 ま っ て く る こ と が 考 え ら れ る と さ れ て い る 14。 特 14 「家計の貯蓄率と金融資産選択行動の変化及びそれらの我が国の資金の流 れ へ の 影 響 に つ い て 」 財 務 省 21 世 紀 の 資 金 の 流 れ の 構 造 変 革 に 関 す る 研 究 会 15 に、老後のための資産形成を目的として個人で長期の資金運用を行っていく場 合、短期的には価格変動リスクがあっても、長期運用により比較的高い収益率 が期待できるような資産に投資するインセティブが高まる。また、現在検討さ れている確定拠出型年金の導入は、家計の投資信託に対する学習効果や投資家 5 教育の充実が期待できることから、これが投資信託等のリスク資産へのシフト のきっかけとなることが考えられるとされている。さらに、公的介護保険制度 の導入は、個々の家計の介護リスクを限定することにより、 介護のための貯蓄 の 必 要 性 を 低 下 さ せ る と と も に 、そ れ に 伴 っ て 発 生 す る 余 資 の 一 部 に つ い て は 、 リスク資産へ配分される可能性もある。このような可能性を、確実に投資に向 10 けるための方法を第三章で述べる。 第三章 第一節 15 三世 代世 帯 と家計 資 産 三世代同居のメリット・デメリット 第 二 章 で は 、家 計 を 取 り 巻 く 環 境 か ら 今 の 日 本 の 資 産 構 成 の 問 題 点 を 挙 げ た 。 具体的には、非正規雇用の拡大により収入が低下しているうえ、環境が整備さ れていないため共働きもできず、貯蓄や投資に回す資金的余裕がないという現 状が明らかになった。ここで私たちは独自案として、三世代同居を推進し、家 計の支出を効率化して資金的余裕をつくることを提案する。 なぜ三世代同居を 20 すると資金的余裕ができるのか説明すると、 「 規 模 の 経 済 」が 核 家 族 世 帯 の よ う な少人数の世帯には働きにくく、一人当たりの消費額が大きくなるからだ。さ ら に 図 表 3‐ 1 か ら わ か る よ う に 、高 齢 者 世 帯 と 世 帯 主 60 歳 以 下 の 世 帯 で は 支 出 項 目 に 違 い が あ る 。一 つ 目 に 教 育 費 、二 つ 目 に 保 険 医 療 費 だ 。世 帯 主 60 歳 以 下の世帯では子どもに教育費がかかるため、大きな負担となる。それに対し高 25 齢者世帯では病気やけがをする機会が増え、保険医療費の負担が増える。これ を三世代同居することによりお互いにカバーしあえると考えた。 を参照 ( http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/henkaku/report/hk007b2.ht m#0 2-02) 16 【 図 表 3‐ 1 高 齢 者 世 帯 と 世 帯 主 60 歳 以 下 世 帯 の 支 出 内 訳 】 高齢者世帯と世帯主60歳以下世帯の支出内訳 (円) 70,000 60,000 5 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 10 0 60歳以下 高齢者 出 所 :「 家 計 調 査 年 報 ( 家 計 収 支 編 ) 平 成 25 年 家 計 の 概 況 」 総 務 省 統 計 局 よ り 筆 者 作 成 15 【 図 表 3‐ 2 同居のメリット】 同居のメリット (子世帯) 育児の日常的サポート 20 家事の日常的サポート 親の健康状態をすぐに把握できる (親世帯) 万が一の時に安心 孫の成長を間近に見る楽しみ 25 生活面で相互に助け合える 0% 20% 40% 60% 出 所 :「 同 居 に 関 す る WEB ア ン ケ ー ト 調 査 」パ ナ ホ ー ム 株 式 会 社( 2012)よ り 筆 者 作 成 ( http://www.panahome.jp/kurashi/report/04/ ) 図 表 3‐ 2 よ り 、 三 世 代 同 居 の メ リ ッ ト と し て 生 活 を 互 い に 助 け 合 う こ と が 30 できるほか、親から育児・家事のサポートを受けることや、親の健康状態をす 17 ぐに把握できることが挙げられる。生活面で助け合えることに生活費の抑制も 含まれる。 さらに、住宅購入費を削減することができるという回答もあり、支出を削減 で き る こ と は 確 か だ 。 図 表 3‐ 1 か ら わ か る よ う に 、 住 居 費 は 家 計 に と っ て 大 5 き な 負 担 に な っ て い る 。住 宅 の 購 入 は 家 計 の 三 大 支 出 と い わ れ て き た 。図 表 3‐ 3 よ り 個 人 の 持 ち 家 率 は 5 割 を 超 え て い る が 、 全 国 の 土 地 の 価 格 は 1991 年 を ピ ー ク に 減 少 し 、 近 年 は 横 ば い で あ る 15。 現 状 で は 人 気 の 高 い 都 市 の 地 価 は 高 く、地方を含め人気のない土地の価格は下がり続け、全体的にみると今後も上 昇するとは考えられない。さらに現在は超低金利で落ち着いているが長 期国債 10 の金利がインフレーションにより回復し、住宅金利が上昇する可能性がある。 3,000 万 円 の ロ ー ン で 年 利 5% と す れ ば 年 間 150 万 円 の 負 担 で あ る 。 や は り 家 計資産としての住宅の持つ価値は大きい。 【 図 表 3‐ 3 持ち家率の推移 (%) 15 持ち家率の推移】 65 63 61 59 20 57 55 1983 1988 1993 1998 2003 2008 (年) 出 所 :「 住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 」 総 務 省 統 計 局 よ り デ ー タ 引 用 、 筆 者 作 成 25 次にデメリットとして、食事の好みの違いや 、ジェネレーションギャップ、 生 活 ス タ イ ル の 違 い な ど が 挙 げ ら れ る( 図 表 3‐ 4 参 照 )。高 齢 者 は 若 年 層 に 比 べ就寝時間が早い傾向にあり、それに対して気を遣いストレスになることもあ る よ う だ 。さ ら に 、親 世 帯 の 回 答 で「 子 世 帯 に 干 渉 し す ぎ て し ま う 」と あ る が 、 15 土 地 代 デ ー タ HP を 参 照 ( http://www.tochidai.info/) 18 この点に関しては子世帯も同様で、親に金銭面で依存してしまうという問題が 起こりうる。しかしメリット・デメリット両者を見比べて みると、子世帯も親 世 帯 も デ メ リ ッ ト が メ リ ッ ト に 比 べ て 全 体 的 に 低 い こ と が 読 み 取 れ る 。つ ま り 、 三世代同居には悪い面もあるけれど、良い面のほうが多くあり、家事・育児の 5 サポートや生活面での相互援助など家計の経済に関わる事項はメリット に集中 していることがわかる。ここで、同居のデメリットを解消するために、二世帯 住宅や近居、隣居を提案する。近くに住むことによって、育児のサポートなど 生活の助け合いは可能になり、保育費などの養育費を削減する ことができ、さ らに共働きも可能となる。そして、気遣いによるストレスや、食事の好みの違 10 いなどのズレが生じることもない。 【 図 表 3‐ 4 同居のデメリット】 同居のデメリット (子世帯) 親世帯への気遣いのストレス 友人を家に呼びづらい 15 (親世帯) 世帯間の価値観の違い 世帯間の価値観の違いによるストレス 子世帯に干渉し過ぎてしまう 食事の好みの違い 20 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 出 所 :「 同 居 に 関 す る WEB ア ン ケ ー ト 調 査 」パ ナ ホ ー ム 株 式 会 社( 2012)よ り 筆 者 作 成 ( http://www.panahome.jp/kurashi/report/04/ ) このように、三世代同居には費用を削減することができるというメリットが あり、資金不足を要因に挙げている人が投資をできるようになる。さらに住宅 25 の継承もでき、非金融資産である住宅を持つことが可能と なる。資産構成の在 り方を変えていくには三世代世帯を構成することが効果的である。 近年、都市化が進み地方流出が増え 、三世代世帯数が減少していることは図 表 3‐ 5 よ り 明 ら か で あ る 。 こ の よ う な 時 代 の 流 れ の 中 で ど の よ う に 三 世 代 世 帯を促進していくのか、第三章第四節で述べたい。 30 19 【 図 表 3‐ 5 三世代世帯数】 三世代世帯数 (万世帯) 700 650 5 600 550 500 450 400 10 350 1975 80 85 90 95 2000 05 10 (年) 出 所 :「 国 勢 調 査 」 総 務 省 統 計 局 よ り デ ー タ 引 用 、 筆 者 作 成 15 ここで私たちは、核家族世帯と三世代世帯に場合分けし、独自のライフプラ ンを考案してみる。 【 図 表 3‐ 6 筆者のライフプラン】 筆者のライフプラン(三世代世帯) 年齢 イベント 筆者のライフプラン(核家族) 支出・収入 25 歳 結婚 夫婦の年収 27 歳 出産 費用 31 歳 私立幼稚園入園 教育費 年間 33 歳 私立小学校入学 39 歳 年齢 イベント 支出・収入 500 万 25 歳 結婚 夫婦の年収 45 万 25 歳 賃貸 賃貸料 48 万 27 歳 出産 費用 教育費 年 間 142 万 28 歳 公立保育園入園 教育費 年間 22 万 私立中学校入学 教育費 年 間 129 万 33 歳 公立小学校入学 教育費 年間 30 万 42 歳 私立高校入学 教育費 年間 96 万 39 歳 公立中学校入学 教育費 年間 45 万 45 歳 私立大学入学 教育費 年間 82 万 42 歳 公立高校入学 教育費 年間 38 万 50 歳 子ども結婚 結婚費用 200 万 45 歳 国立大学入学 教育費 年間 52 万 60 歳 退職 退職金 2,280 万 50 歳 子ども結婚 結婚費用 65 歳 年金受給開始 夫婦 月 23 万 60 歳 退職 退職金 20 500 万 年間 120 万 45 万 180 万 2,280 万 65 歳 海外旅行 費用 200 万 65 歳 年金受給開始 夫婦 65 歳 国内一周旅行 費用 注 1) 高 校 ま で の 教 育 費 は 「 子 ど も の 総 学 習 費 調 査 」 文 部 科 学 省 ( 2012) よ り 引 用 注 2) 大 学 の 教 育 費 は 「 国 立 大 学 と 私 立 大 学 の 授 業 料 等 の 推 移 」 文 部 科 学 省 ( 2004) より引用 注 3) 退 職 金 は 「 労 働 条 件 総 合 調 査 」 厚 生 労 働 省 ( 2008) よ り 引 用 5 注 4) 年 金 は 「 報 道 発 表 資 料 平 成 25 年 4 月 か ら 9 月 ま で の 年 金 額 は 平 成 24 年 度 と 同 額 」 厚 生 労 働 省 ( 2013) よ り デ ー タ 引 用 注 5) 上 記 以 外 の 支 出 ・ 収 入 は 筆 者 考 案 まず、三世代世帯の場合、両親に子育てを支援してもらえると考えて 、幼稚園 から入園することとした。共働きをしていても、延滞 保育をする必要がないの 10 で余分な養育費を出費しなくてよいと考えた。この余裕資金となった資金の一 部を、将来の教育費や旅行費のために運用することができる。運用により利益 を得て、定年後には海外旅行に行きたいと考え、そのために若い世代にリスク を許容し積極的に運用することにした。 一方、核家族世帯は、まず住居費が必要となる。ここが三世代世帯との最も 15 大きな違いである。そして、共働きをしたいのであれば、子どもを保育園に預 けなくてはならない。さらに、退勤が遅くなるのであれば延滞保育をしなくて はいけないので、養育費の負担が大き くなる。収入と支出に差がなくなり、貯 蓄をすることで精いっぱいとなってしまうと考えられる。 しかし、定年後に国 内 一 周 旅 行 を し た い と 考 え る が 、 リ ス ク を 回 避 し た い の で 、 財 形 貯 蓄 16を 開 始 20 する。 このようにライフプランと資金計画を立てると、いつどのようなイベントが あり、どれだけの資金が必要か、さらに自分に合った世帯構成は三世代世帯な のか、それとも核家族世帯なのか把握することができる。そして、三世代世帯 16 ここでは、財形貯蓄の中の勤労者財産形成貯蓄(一般財形貯蓄)とする。 勤労者財産形成貯蓄とは『勤労者が、金融機関などと契約を結んで 3 年以上 の期間にわたって、定期的に賃金からの控除(天引)により、事業主を通じて 積 み 立 て て い く 目 的 を 問 わ な い 使 途 自 由 な 貯 蓄 の こ と 。』 と 定 義 さ れ て い る 。 厚 生 労 働 省 HP よ り 引 用 。 ( http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/rousei/kinrousya/980831_2.htm ) 21 月 23 万 100 万 のほうが支出を削減でき資金的余裕が生まれることが明確になるのである。 第二節 高齢者における金融教育 私たちは独自案として、高齢者に金融教育を行い、三世代世帯内で祖父母か 5 ら子供、孫に金融教育を施すことを提案する 。そのためには高齢者の特有の性 質や高齢者の金融教育の現状をきちんと理解する必要がある。 かつての貯蓄増 強から「貯蓄から投資へ」という時代の変化を経験しながら、その変化に対応 する難しさを感じ、その変化にどのように対処すればよいのか、その対処方法 に困っている多くは、高齢者なのではないだろうか。これまでのように、退職 10 まで働いたお金を預金し、その金利と年金で老後を過ごすことが難しくなって きていて、また、近年成立した、医療制度改 革関連法案なども高齢者にとって 老後の生活に不安を与える一要因となっている。 高齢者に多くみられるのが、リスクに対する考え方の違いである。リスクと はたしかに、危険、危険度という意味であるが、 金融では『預貯金や証券投資 15 などの資金運用に際してのリスクとは、 「 将 来 、損 を す る の か 、少 し だ け 得 を す るのか、それとも予想以上に得をするのか」等が決定されていないことを指す 17。 』の で あ る 。し か し 、高 齢 者 を 含 め 一 般 の 多 く の 人 は 、前 者 の 意 味 で と り や す い 。以 前 の よ う な「 銀 行 に 預 け て お け ば 大 丈 夫 」と い っ た 考 え は 、 「リスクが ない」=「安全である」といった意味であったように思われる。しかしペイオ 20 フ解禁によりその神話も崩れ去ってきている。また、高齢者の年代になると教 育というよりも、意欲のある人だけが啓発的に学んでいるのが現状である。 高齢者における金融教育において、今後必要となってくることとは何であろ うか。私たちが必要だと思う一つ目は、高齢者の方が老後豊かな生活を送るた めに、現状をしっかり把握し、そのために何が必要かを学ぶことができる金融 25 教育である。これだけでは曖昧なので、老後に必要な貯蓄額という形で例に挙 げてみる。 総 務 省 統 計 局 の 平 成 17 年 家 計 調 査 の デ ー タ に よ る と 、 60 歳 以 上 の 人 の 貯 蓄 額 の 平 均 は 2,195 万 円 と な っ て い る 。 し か し 、 実 際 に 多 く の 貯 蓄 を 持 っ て い る 17 「証券用語解説集」野村證券株式会社ホームページより引用 22 の は 一 部 の 資 産 家 の 高 齢 者 で 、 ほ と ん ど の 場 合 、 1,000 万 円 以 下 の 貯 蓄 し か な い事が推測できる。これらをふまえて、老後に必要な生活費から、一生涯に 貰 える年金を差し引いた、老後に必要な貯蓄額は以下のようになる。 厚 生 労 働 省 の 統 計 調 査 1 8 に よ る と 、平 均 余 命 は 男 性 79 歳 、女 性 86 歳 で あ り 、 5 60 歳 か ら 年 金 が 支 給 さ れ る と す る と 、男 女 そ れ ぞ れ の 年 金 受 給 年 数 は 、男 性 19 年 、 女 性 26 年 と な る 。 平 均 す る と 、 22.5 年 と な る の で 、 年 金 受 給 年 数 を 22.5 年として以下の計算を行う。 【一生涯で貰える夫婦の年金額】 22.5 年 ×276 万 円 = 6,210 万 円 10 毎 月 の 年 金 額 は 、 夫 婦 で 月 額 23 万 円 ( 年 額 276 万 円 ) と す る 1 9 。 【老後に必要な生活費】 生 命 保 険 文 化 セ ン タ ー の 調 査 デ ー タ よ り 最 低 日 常 生 活 費 の 平 均 は 、月 額 24.2 万 円( 年 額 290.4 万 円 )で あ り 、ゆ と り あ る 老 後 の 生 活 費 は 、月 額 37.9 万 円( 年 額 454.8 万 円 ) で あ る 。 15 【最低日常生活費の老後の総生活費】 290.4 万 円 ×22.5 年 = 6,536 万 円 【ゆとりある老後の総生活費】 454.8 万 円 ×22.5 年 = 10,233 万 円 日常生活費用以外の支出として、住宅の修理・改築費、子供の結婚援助費用、 20 海 外 ・ 国 内 旅 行 費 用 、 車 の 買 い 換 え 等 が 存 在 し 、 一 般 的 に 約 2,000 万 円 必 要 だ と言われている。これらを踏まえて老後に必要な貯蓄額を算出すると、 【最低日常生活を送る場合】 6,536 万 円 - 6,210 万 円 + 2,000 万 円 = 2,326 万 円 必 要 。 【ゆとりある老後の生活を送る場合】 25 10,233 万 円 - 6,210 万 円 + 2,000 万 円 = 6,023 万 円 必 要 。 このことを知らされたとき、多くの高齢者は驚くだろう。なぜなら、平均貯蓄 額より老後に必要な額が多いからである。つまり、ある一定の年数が経つと、 「 平 均 余 命 の 年 次 推 移 」 厚 生 労 働 省 ( 2010) よ り デ ー タ 引 用 「 報 道 発 表 資 料 平 成 25 年 4 月 か ら 9 月 ま で の 年 金 額 は 平 成 24 年 度 と 同 額 」 厚 生 労 働 省 ( 2013) よ り デ ー タ 引 用 18 19 23 貯 金 を 切 り 崩 し て 生 活 す る ど こ ろ か 、赤 字 の 生 活 で あ る 。高 齢 者 の 多 く は 、 「貯 蓄から投資へ」と環境が変わったものの、そのために日常生活において、どの ような変化が起きていて、なぜ必要なのか実感する機会が少ないように思われ る。このことを三世代世帯間で祖父母から孫へ教える過程としてまず高齢者に 5 きちんと金融教育を施し、投資に関する知識を持った上で、子や孫に伝えて行 くことが肝心である。具体的な例を挙げて現実に目を向けてもらい、そのため には何が必要か、不足分をどのように補うのか、低金利の時代では預金だけで は資産が増えないので投資も必要ではないのか、という段階をふんだ教育が必 要になってくる。 10 図 表 3‐ 7 の よ う に 、 50 歳 以 上 の 個 人 投 資 家 は 7 割 以 上 で 高 い と い う 特 徴 が 挙げられる。高齢者は時間に余裕があり、投資する環境は整っている からだと 言える。その高齢者が個人投資家として株式投資を行うことで、市場の活性化 を図り家庭内金融教育の普及を期待する。 【 図 表 3‐ 7 15 年齢層 20歳代 証券(株式、投資信託、公社債)保有額 100万円未満 2% 30歳代 17% 50歳代 23% 60歳代 25 300~500万円 14% 500~1000万円 14% 10% 20% 19% 6% 無回答 18% 0% 25% 1000万円以上 31% 70歳代以上 22% 100~300万円 10% 40歳代 20 個 人 投 資 家 の 年 齢 層 と 証 券 保 有 額 ( 時 価 )】 30% 40% 0% 5% 10% 15% 20% 出 所 :「 個 人 投 資 家 の 証 券 投 資 に 関 す る 意 識 調 査 」 日 本 証 券 業 協 会 ( 2012) p1、 p2 よ り データ引用、筆者作成 日本における個人投資家の現状は、インターネットの普及及び超低金利時代 の影響もあり株式投資を始めとする金融商品に対して非常に高い関心をもって いる。しかし現状は個人投資家の数が市場全体に占める割合は低いものとなっ 30 て い る 。現 在 株 式 投 資 を 行 っ て い な い が 、株 式 に 対 し て 興 味 を 持 っ て い る 人 (以 24 25% 30% 下「 潜 在 投 資 家 」)の 存 在 が 影 響 し て い る か ら で あ る 。潜 在 投 資 家 が 株 式 投 資 を しない理由の大半は株式に対する間違った考え方や、そもそも株式を はじめと する金融に対する知識がないため投資に踏み切れないという消極的な理由 が考 えられる。これまでに投資教育を受けた事のない人は、そもそもどうすれ ば株 5 式投資等の投資を始められるのか、ということがわからないケースがある。し かし、以上の問題は金融教育を受けていれば比較的容易に解決できるはずであ る。それはなぜかというと、投資スキルを身につける事で合理的な投資行動が 可能であると考えられるからである。また証券会社や金融機関等の 情報を鵜呑 みにしないためにも金融の知識を身に付ける事は非常に重要である。金融商品 10 を売る側は、自社の都合のいいように商品の勧誘を 行い、商品について良い点 は強調するが、欠点はあまり言わない誘因がある。潜在的投資家は、せっかく 貯めた資金を目減りさせないように、また騙されないように自分のことは自分 で守れるだけの知識を身に付けておかなければならない。 高 齢 者 に お け る 金 融 教 育 は ど の よ う に 行 う べ き で あ る か 、 こ れ は NPO 法 人 15 の投資クラブや公的機関がセミナー等を開いて行うのが最もよいと思われる。 証券会社がセミナー等を行っている場合もあるが、証券会社が開催する講義な どは、その証券会社にとっては顧客獲得の格好の場であるから、自社にとって 有利な点は教えるが、不利な点は教えないのではないかという懸念があるから である。全く知識のない人は、講義の内容を鵜呑みにしてしまう可能性が極め 20 て高い。したがって高齢者に対しての金融教育を行う機関は、営利目的でない ことが望ましい。 第三節 三世代世帯のリスクに対する耐性 図 表 3‐ 8 よ り 、 三 世 代 世 帯 の 平 均 所 得 額 が 最 も 高 い こ と が わ か る が 、 こ れ 25 は一世帯当たりの勤労者数がほかの世帯より多いからであると考えられる。さ らに、夫婦共働きができることも平均所得増額の要因であろう。私たちは、世 代の異なる勤労者が同一世帯に存在することで、世代間でリスクシェアをする ことができ、所得変動のリスクが低減されると考えた。さらに三世代世帯は、 ほかの世帯に比べ、資産規模が大きくなることも読み取れる。 30 25 【 図 表 3‐ 8 世帯構造別平均所得金額】 世帯構造別平均所得金額(2013) (万円) 900 800 5 700 600 500 400 300 200 10 100 0 単独世帯 核家族世帯 三世代世帯 その他の世帯 出 所 :「 平 成 25 年 国 民 生 活 基 礎 調 査 」 厚 生 労 働 省 よ り デ ー タ 引 用 、 筆 者 作 成 15 図 表 3‐ 9 は 世 帯 構 造 別 一 世 帯 当 た り 平 均 所 得 金 額 の 増 減 率 を 示 し て い る 。 リ ー マ ン シ ョ ッ ク が 2008 年 9 月 に 起 こ り 、 家 計 に 対 し て 大 き な ダ メ ー ジ を 与 え た 。 2007 年 か ら 2008 年 に か け て の 対 前 年 比 は 、 核 家 族 世 帯 は 上 昇 、三 世 代 世 帯 は 低 下 し て い る が 、2008 年 か ら 2009 年 に か け て 核 家 族 世 帯 は 低 下 、三 世 代 世 帯 は 上 昇 し て い る 。 ま た 、 2011 年 3 月 に 東 日 本 大 震 災 が 起 こ っ た 。 2011 20 年の対前年比は、総世帯で見ても核家族世帯で見ても 低下しているが、三世代 世 帯 は 影 響 を 受 け て い な い と い え る 20。 こ の 事 実 よ り 、 三 世 代 世 帯 の ほ う が 景 気変動などのリスクに左右されにくく、経済的ショックが起こっても回復が早 いと言える。三世代世帯を構成することにより、家計を経済的ショックに左右 されにくく、所得変動リスクを回避できる主体にする。そして、資金的余裕を 25 生み出し、資産構成を変えられるようにするべきである。 20 特に震災の影響が大きかった地域(岩手 県、宮城県、福島県)のデータを 除くものであることに注意が必要である。 26 【 図 表 3‐ 9 世 帯 構 造 別 1 世 帯 当 た り 平 均 所 得 金 額 増 減 率 ( 対 前 年 比 )】 世帯構造別1世帯当たり平均所得金額増減率(対前年比) (%) 5% 4% 3% 5 2% 1% 0% -1% -2% 10 -3% -4% 2005 2006 2007 2008 総数 2009 核家族 2010 2011 2012 2013 (年) 三世代 出 所 :「 国 民 生 活 基 礎 調 査 」 厚 生 労 働 省 よ り デ ー タ 引 用 、 筆 者 作 成 15 注 1) 増 減 率 = ( 分 析 対 象 年 の 金 額 −分 析 対 象 年 の 前 年 の 金 額 ) 分析対象年の前年の金額 × 100( % ) よ り 算 出 注 2) 2010 年 の 数 値 は 岩 手 県 、 宮 城 県 、 福 島 県 を 除 く デ ー タ 注 3) 2011 年 の デ ー タ は 福 島 県 を 除 く デ ー タ 第四節 20 三世代同居の促進方法 日本では核家族化が進み、同居を望む人も年々減少傾向にある。同居を望ま なくなっているなかで、どのようにして同居を促進するのかを考えた。一つ目 に、同居用の住宅を購入する際に、住宅ローンの金利を優遇する。二つ目に転 居費用やリフォーム費用の援助を提案 する。 一つ目の住宅ローン金利優遇について、 埼玉県では親と子が同居するために 25 住宅を建設、購入する人向けに、りそな銀行と共同して住宅ローンの金利マイ ナ ス 1. 5% と す る 制 度 が あ る 。こ の 制 度 は 2014 年 6 月 2 日 に「 埼 玉 の 家 家 族 の き ず な 応 援 ! ! 住 宅 ロ ー ン 2 1 」と し て 発 表 さ れ た 。こ の 政 策 の 特 徴 と し て 、 県と地方金融機関が協力していることだ。金利の引き下げは金融機関の協力な 埼 玉 県 HP を 参 照 ( http://www.pref.saitama.lg.jp/site/renkei/renkei ki.html) 21 27 しには行えないものである。三世代同居数がとりわけ低く、家賃や住居費が高 額な都市部において、この策は有効的であると考える。 二つ目の転居費用とリフォーム費用の援助については 高槻市が行っている三世 代 世 帯 同 居 の 推 進 方 法 に つ い て 説 明 し た い 22。 高 槻 市 で も 少 子 高 齢 化 が 急 速 に 5 進んでおり、深刻な問題とされている。人口は、その地域の勢いを示すものさ しのひとつで、ピラミッド型の方がバランスも良く安定していると言われてい るため、団塊ジュニア世代以降の人口を増やすべく、子育て世代に高槻市に転 居、定住してもらいたいと今回の補助金制度を打ち出している。子ども世代が 市 外 か ら 高 槻 市 に 転 入 す る 場 合 は 最 大 で 20 万 円 を 補 助 し 、 市 内 で の 転 居 の 場 10 合 は 、最 大 で 10 万 円 を 補 助 さ れ る 。ま た 、親 が 高 槻 市 に 居 住 、孫 の い る 子 ど も 世代が親と同居するために家をリフォームされる場合にも補助金を交付される。 こ の 場 合 も 、 子 ど も 世 代 が 市 外 か ら 高 槻 市 へ 転 入 す る 場 合 は 最 大 で 20 万 円 を 補 助 し 、 市 内 で 転 居 す る 場 合 は 最 大 で 10 万 円 を 補 助 さ れ る 。 こ の 制 度 の メ リ ットは引っ越し費用程度を市が補助することで、転居を考えておられる子ども 15 世代の背中を押すことにつながると考えられる。このような補助金は大阪府内 で は 初 の 制 度 で 、 全 国 的 に 見 て も 非 常 に 先 進 的 な 制 度 で あ る 23。 こ の 他 に も 近 居 促 進 制 度 と し て 、 UR 都 市 機 構 で は 対 象 の 物 件 に 近 居 し た 場 合 5 年 間 家 賃 を 5%下げるといったプランを実行している。また、 福井県で同様に同居促進の ために企画があり、三世代同居をしたいと考える世帯と三世代同居推進に意欲 20 的 な 行 政 側 と が よ く 合 致 し て い る と 考 え ら れ る 24。 第四章 第一節 25 家計 資産 構 成の改 善 策 学生金融教育の推進 第三章では三世代世帯によって、資金的余裕をつくり 、貯蓄や投資に向ける 高 槻 市 HP を 参 照 ( http://www.city.takatsuki.osaka.jp/shisei/kohokocho/buchoshitsu/kako/h2 5/toshi_h25/toshi250703.html ) 23 こ れ ら 促 進 方 法 だ け で は マ イ ホ ー ム を 取 得 す る 費 用 等 に 比 べ て 補 助 金 が か なり少額であるという問題は残っている。 24 福 井 県 は 、 ふ く い の 未 来 を 創 り 隊 に よ る 「 ふ く い 子 宝 大 作 戦 」 に よ る 引 越 費用の助成を行っている。 22 28 ことを中心に述べた。しかし、資金的余裕があっても 金融知識がないために投 資を避ける傾向があると第一章で述べた。 そこで、学生に対して金融教育をす るために二つ提案する。 一つ目は中学校から大学で「個人の金融教育」を導入することである。日本 5 では、 「 パ ー ソ ナ ル フ ァ イ ナ ン ス 」と い う 個 人 の 金 融 リ テ ラ シ ー を 高 め る た め の 専門的な授業が行われていない。文部科学省の学習指導要領に中学校の社会で は 公 民 的 分 野 に お い て 、『 身 近 な 消 費 生 活 を 中 心 に 経 済 活 動 の 意 義 を 理 解 さ せ るとともに、価格の働きに着目させて市場経済の基本的な考え方について理解 さ せ る 。』と あ る 。高 校 の 政 治・経 済 で は『 現 代 の 日 本 経 済 及 び 世 界 経 済 の 動 向 10 について関心を高め、日本経済の国際化をはじめとする経済生活の変化、現代 経済の機能について理解させるとともに、その特質を探究させ、経済について の 基 本 的 な 見 方 や 考 え 方 を 身 に 付 け さ せ る 。』と あ る 2 5 。こ の よ う に 、金 融 の 仕 組みや機能、経済の動向について学んでいることがわかる。そして、大学の講 義でも金融システムや金融の歴史などを学ぶ機会が多い。日常生活のために必 15 要な金融知識としては、金融の仕組みを学ぶことよりも、預貯金や投資信託な どの金融商品の種類や、クレジットカード などについて学ぶことが重要である と考える。日本版ビッグバンにより銀行はさまざまな金融商品を取り扱うよう になった。金融商品の多種多様化に伴い、私たちの金融知識も 豊富にすべきで あ る 。ま た 、ラ イ フ プ ラ ン の 作 成 方 法 も 金 融 教 育 の 一 環 と し て 行 う べ き で あ る 。 20 ライフプランを作ることは、自分にあった金融商品を考えることにつながり、 資産を形成する上で非常に重要なことである。例えば、将来マイホームを持ち たい、旅行に定期的に行きたいなど、ライフデザインに応じたプランを立てて いくことが必要となる。少子高齢化などの影響により一生独身で暮らすシング ル 世 帯 や 、共 働 き で 子 育 て を す る 世 帯 な ど ラ イ フ デ ザ イ ン も 幅 広 く な っ て き た 。 25 多くの人は近視眼的であり、将来の見通しを立てる機会が少ない。しかし金融 商品を選択する際にはライフプランを明確にし、資金目的を確かめて、それに 「 学 習 指 導 要 領 」 文 部 科 学 省 HP よ り 引 用 。「 学 習 指 導 要 領 」 と は 「 全 国 の どの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするため、 学 校 教 育 法 等 に 基 づ き 、 各 学 校 で 教 育 課 程 を 編 成 す る 際 の 基 準 。」 と さ れ て い る 。( 中 学 : http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/1320067.htm )( 高 校 : http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/1320154.htm ) 25 29 ふさわしい金融商品の選択をしていかなければならない。 しかしながら、金融教育の問題は世界各国で起こっている。総授業時間数が 限られているがために「金融」という授業科目を取り入れられなか ったり、金 融の指導ができる教師が不足していたりと、満足に教育を行うことができる環 5 境 が 整 っ て い な い 26。 授 業 数 確 保 の た め に 課 外 授 業 を 行 っ た り 、 土 曜 日 午 前 中 の授業実施をしたりすると、金融教育を良く思っていない人から批判を受ける だ ろ う 。 そ ん な 中 ア メ リ カ は 、 CEE( 経 済 教 育 協 議 会 ) と い う 非 営 利 団 体 が パ ーソナルファイナンス教育の基準を定め テキストも出版し、金融教育の普及を 担 っ て い る 。日 本 と ア メ リ カ の 大 き な 違 い は 国 家 の 学 習 指 導 要 領 の 有 無 で あ り 、 10 日本では文部科学省が学習指導要領を定めているので、早急に 学習指導要領に パーソナルファイナンス教育を盛り込ん でいくべきである。 二つ目に、わたしたちは独自の提案として、大学に金融教育の場を兼ねた銀 行 の 支 店 を 誘 致 す る こ と を 提 案 す る 。大 学 生 に な る と 銀 行 に 行 く 機 会 も 増 え る 。 口座開設したい人だけでなく投資信託を始めたい 人、保険に加入したい人など 15 のためにも大学に銀行の支店があれば活用できる。 また、大学内銀行での金融 教育プログラムとして、大学生向けの投資信託を開発し、現預金以外の金融資 産の保有を促す。例えば、次のような大学生向け商品の企画が考えられる。 ( A) 販 売 手 数 料 無 料 、 信 託 報 酬 の 引 き 下 げ ( B) 業 界 別 投 資 信 託 2 7 20 ( C) 学 生 自 身 が フ ァ ン ド 設 計 に 参 加 す る 販売手数料により損失がでることを防ぐために無料化する。さらに信託報酬 は信託財産の資産額に応じて徴収されるのが一般的であるが、 それを資産額の 半分に応じて徴収するようにし、手数料を引き下げ る。そうすることで、アル バイトで稼いだお金で投資信託を購入しやすくなる 。 25 続いて、業界別投資信託とは、興味がある業界に投資できる商品である 。例 26 「高まる金融教育の重要性 国家が取り組むべき課題に」週刊エコノミスト 2013 年 10 月 15 日 2 貢 を 参 照 27 実 際 の 販 売 例 と し て 、 野 村 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社 の 「 野 村 世 界 業 種別投資シリーズ」という商品がある。金融・半導体・資源・ヘルスケアに分 けられている。 ( http://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140470 ) 30 えば、食品業界に興味があり就職を考えているとする。業界分析も兼ねて動向 を知りたいときに、業界別投資信託があればよいと考えた。しかし、同一業界 に投資して、万が一その業界のみに危機が訪れるといけないので、専門家によ り一部資金を他の業界へ分散投資を行うこととする。 5 最後に学生がファンドをつくるとは、専門家とともにどこに投資をするか考 える機会を設けて、自分で投資先を決定すること である。これも業界分析を兼 ねることができる。興味関心のある企業を選択し分散投資を行う。投資先は格 付けや業界動向をみて専門家が決めた企業 から選択することとする。類似例と し て 「 日 経 STOCK リ ー グ 2 8 」 が 挙 げ ら れ る 。 日 経 STOCK リ ー グ は バ ー チ ャ 10 ル 株 式 投 資 で あ り 、( C)の 商 品 と 実 際 に 運 用 す る 点 が 異 な る が 、ポ ー ト フ ォ リ オを作成する点が似ているので挙げた。 これらは、投資に興味関心を持ち卒業後も投資を継続して行えるように力を つけることを目的とする。投資をする際には経済の動きや企業についても知っ ておかなければならない。これにより身につけた情報は就職活動においても有 15 効活用できるので一石二鳥だと考える。 こ こ で 、大 手 銀 行 の 営 業 姿 勢 を 見 て み る 2 9 。三 菱 東 京 UFJ 銀 行 は「 初 心 者 向 け 商 品 を 開 発 す る 。」、 三 井 住 友 銀 行 は 「 グ ロ ー バ ル か つ 高 度 な サ ー ビ ス を 望 む 富裕層向けの金融商品の開発、また若年層向けに休日や平日の時間外の活 用に よ り 利 便 性 の 向 上 を 図 る 。」、 み ず ほ 銀 行 は 「 ビ ッ グ デ ー タ の 活 用 や ス マ ー ト フ 20 ォ ン を 利 用 し た サ ー ビ ス の 拡 大 を 図 る 。」と 唱 っ て い る 。こ の よ う に 、各 銀 行 は 、 顧客に合わせた商品開発や営業方法を取り入れている ので、これに倣い大学生 向け投資信託も学生のニーズや資産規模に合わせた商品として企画した。 我々が所属する関西学院大学の上ヶ原キャンパスにおいては、在籍者数 17,120 人 ( 2014 年 5 月 1 日 時 点 ) 3 0 。 約 2 万 人 も の 顧 客 が 存 在 す る 大 学 に 銀 25 行を誘致すれば、顧客増加や金融への興味関心の高まりにつながると考える。 日 経 STOCK リ ー グ は 「 支 給 さ れ る 仮 想 の 500 万 円 を 元 手 に 、 実 際 の 株 価 に基づいて、インターネットで株式売買シミュレーションを行い、ポートフォ リオの作成、運用を体験することができるシステム」とされている。 ( https://stockleague.nikkei.co.jp/login/index.aspx ) 2 9 「 金 融 ニ ッ ポ ン 」 日 本 経 済 新 聞 朝 刊 2014 年 10 月 17 日 31 項 を 参 照 3 0 関 西 学 院 大 学 HP 在 学 数 よ り 引 用 ( http://www.kwansei.ac.jp/kikaku/kikaku_004166.html ) 28 31 顧客数が増えることによって、大学生向け投資信託による手数料収入の減少も 少なからず補うことができ、銀行側にメリットがある。そして、銀行行員によ る金融セミナーを定期的に大学で開催することによって、自己資産に関心を持 たせ、資産管理を促し、資産構成の在り方について 、学生が自らのライフプラ 5 ンと絡め合わせ考えさせる機会を提供する 。 第二節 NISA 制 度 と 投 資 信 託 の 改 善 こ の 節 で は 、 NISA 制 度 と 投 資 信 託 の 改 善 す べ き 点 を 挙 げ た い 。 第 三 章 で 三 世代同居をして費用を削減し、資金的余裕を生み出して貯蓄や投資に回すべき 10 だ と 述 べ た 。そ こ で 、余 裕 資 金 を 投 資 に 向 け 、資 産 構 成 で 15.9% し か 占 め て い ない有価証券のシェア拡大を目指すために制度と商品の改善が欠かせないと考 えたので述べる。 1、 NISA 制 度 の 改 善 日 本 経 済 新 聞 3 1 に よ る と 、「 積 み 立 て 型 」 NISA を 申 し 込 ん だ 口 座 数 が 9 月 末 15 で 18 万 強 、 投 資 額 が 約 450 億 円 に な っ た 。 積 み 立 て 型 は 毎 月 一 定 額 で 同 じ 金 融商品を購入することができ、リスク分散効果もある。 NISA の も と と な る ISA 3 2 は 非 課 税 期 間 の 制 限 が な く 年 間 の 非 課 税 投 資 額 の 制限はあるものの非課税投資額の上限はない。預金よりハイリスクではあるが 利益が非課税になり、年間の非課税投資額が引き上げられると魅力が増すので 20 はないか。そして、対象商品の制限を緩和することが日本の投資促進に必要だ 2014 年 10 月 20 日 朝 刊 1 貢 よ り 引 用 ISA と は 、『 英 国 で 投 資 ・ 貯 蓄 の 譲 渡 益 ・ 配 当 ・ 利 息 が 非 課 税 と な る 口 座 。 個 人 向 け の 投 資 ・ 貯 蓄 奨 励 制 度 と し て 1999 年 に 導 入 。 毎 年 1 万 1,880 ポ ン ド を 上 限 と し て 配 当 ・ 譲 渡 益 ・ 利 息 が 非 課 税 と な る ( 2014 年 3 月 現 在 )。』 と 定 義 さ れ て い る 。 コ ト バ ン ク よ り 引 用 。( https://kotobank.jp/word/ISA 10280) 『 2009 年 度 の ISA 口 座 開 設 者 に よ る 拠 出 額 の 所 得 分 布 別 の 分 析 で は 、 ISA 口 座 保 有 者 が 最 も 多 い の は 年 間 所 得 が 1 万 ポ ン ド ~ 1 万 9,999 ポ ン ド ( 約 140 万 円 ~ 約 279 万 9,860 円 ) の 水 準 で 全 体 の 約 3 割 を 占 め 、 年 間 所 得が 2 万ポンド未満の層が口座保有者全体の半分以上を占める。高所得者 層 は 、 株 式 型 ISA に 資 金 を 拠 出 す る 傾 向 が 強 く 、 低 所 得 者 層 は 預 金 型 ISA を 好 む 傾 向 が あ る 。 総 じ て ISA 制 度 は 定 着 し つ つ あ り 、 投 資 家 の 裾 野 拡 大 に 一 定 の 効 果 を あ げ て い る 。』「 金 融 所 得 税 制 の 変 遷 と 現 状 ‐ 日 本 版 ISA の 導 入 を 踏 ま え て ‐ 」 国 立 国 会 図 書 館 ( 2013) よ り 引 用 31 32 32 と考える。債券はミドルリスク・ミドルリターンの商品とされており、リスク 回避的な日本人にとって始めやすいものだと考える 。これをかなえるためには 制限の撤廃が必要不可欠となる。 2、 5 投資信託の改善 投 資 信 託 を 購 入 す る と 販 売 手 数 料 、保 有 期 間 に は 信 託 報 酬 な ど 費 用 が か か る 。 販売手数料がかからないノーロード型と呼ばれる商品もあるが、まだまだ少な い 。 ち な み に ノ ー ロ ー ド 型 の 例 と し て MRF や MMF が 挙 げ ら れ る 。 リ タ ー ン を得られても手数料を差し引かれて元本割れするケースもあり、本当に投資信 託の販売数を増やしたり、家計の投資割合を増やして資産構成を変えたりする 10 には手数料を引き下げるか無料にするかすべきである。 以 上 の 二 つ の 改 善 策 は 、現 在 投 資 を し て い る 人 、こ れ か ら 始 め る 人 、NISA 制 度を利用している人、これから利用を始める人、両者にとってメリットが生ま れるように考案した。 15 第三節 好ましい資産構成の在り方 第一章で現預金比率を下げ、有価証券比率を高めてアメリカ型に近づけるべ きだが、完全移行するのは困難極まりない。そこで 、ドイツ型のようにバラン スのよい資産構成を目指せばよいと述べた。 これは日本全体を平均した際の家計における理想的な資産構成であり、個々 20 の家計を考察すると、現在の日本型資産構成のほうが家計にとって身の丈に合 っている場合もある。そこで、私たちは家計属性ごとの好ましい資産構成を提 案する。これまで、三世代世帯と核家族世帯に分類して考察してきたので、こ の節においても三世代世帯における資産構成の在り方と、核家族世帯における 資産構成の在り方を提案したい。 25 まず、三世代世帯には養育費や住居費などの諸費用削減効果があり、余裕資 金 が 生 ま れ や す い 。 2010 年 の 日 本 全 体 に お け る 三 世 代 世 帯 の 割 合 は 7.9% 3 3 で あり、三世代世帯の貯蓄を投資に向けることができれば、日本全体の資産構成 における有価証券比率が少しでも高まるだろう。社会保障制度維持の不確実性 「 平 成 24 年 グ ラ フ で み る 世 帯 の 状 況 国 民 生 活 基 礎 調 査 ( 平 成 22 年 ) の 結 果 か ら 」 厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 統 計 情 報 部 p6 よ り デ ー タ 引 用 33 33 が高まり、さらにインフレーションによる物価高騰で、家計経済は悪化してい く 一 方 で あ る 。有 価 証 券 比 率 を 高 め て い か な け れ ば 、赤 字 家 計 が 増 加 し て い く 。 日本経済にとっても家計にとっても、三世代世帯の有価証券比率向上は欠かせ ない。よって、三世代世帯における好ましい資産構成の在り方は、現預金比率 5 を下げ、有価証券比率を高めたものである。 続いて、核家族世帯における資産構成の在り方を提案する。核家族世帯は夫 婦共働きをしようと思えば、子どもを保育園に預けなくてはいけない。さらに 賃貸契約し毎月家賃を支払って住むか、住宅購入をし住宅ローンを組まなけれ ばならない。三世代世帯に比べ支出が多くなり、その結果、余裕資金が生まれ 10 ない。余裕資金がないにも関わらず、リスク性資産である有価証券の比率を高 め る こ と は 困 難 で あ る 。近 視 眼 的 な 考 え 方 に よ っ て 起 こ る 年 金 未 納 問 題 を 防 ぎ 、 保険・年金準備金の比率を低下させないためにも、財形貯蓄を すべきだと考え た。財形貯蓄については第三章第一節で述べたとおりだ。核家族世帯には今の 日本の資産構成が合っていると考える。 しかし、核家族世帯でも、近居や隣居 15 をし、養育費などを削減し余裕資金を生み出して有価証券の比率を高めること も 可 能 で あ る 。 核 家 族 世 帯 は 日 本 の 59.8% 3 4 も 占 め る 世 帯 構 造 で あ り 、 核 家 族 世帯の経済に対する影響は非常に大きいものだと考える。少しでも多くの核家 族世帯に有価証券比率を高めてもらうために、近居・隣居を推進したい 。そし て、近居・隣居が困難な核家族世帯には現在の日本型資産構成が好ましい資産 20 構成であると考える。 明確に資産構成の割合を算出することは非現実的だと考えたので、以上のよ うな結論を導いた。資産構成の有価証券比率を、日本経済に刺激を与えられる ように高め、そこから日本にとって最適な資産構成の割合を導き、日本独自の 資産構成の在り方を創出すべきである。 25 経済の担い手でもある家計に良い影響を与えるためには、リスク性資産 で ある有価証券の割合を増やすべきであり、そのためには国を挙げて金融教育に 取り組み、商品や制度を改善すべきである。私たちは、家計の資産構成の在り 方を変えて、家計を、日本を、豊かにするために、以上のことを提案した。 「 平 成 24 年 グ ラ フ で み る 世 帯 の 状 況 国 民 生 活 基 礎 調 査 ( 平 成 22 年 ) の 結 果 か ら 」 厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 統 計 情 報 部 p6 よ り デ ー タ 引 用 34 34 終章 お わり に 本稿では家計における資産構成の在り方について、まず現状分析を行い、問 題点を導いた。その結果、現預金中心の資産構成では リスクマネーが供給され 5 ず経済が低迷し、最終的に家計に悪影響が及ぶことがわかった。しかし貯蓄型 の資産構成を投資型に向けていく過程で 、様々な投資妨げ要因が存在する。そ の中で、どのように投資を促進し資産構成を変えていくか 、大きく分けて、三 世代同居を促進して投資資金をつくる方法と金融教育を行う方法提案した。 三世代世帯となり、両親に子育ての支援をしてもらうこと で夫婦共働きがで 10 きるようになり、資金を増やすことができるという考えである。三世代同居に は多くのメリットがあり、その中でも 養育費など諸費用の削減効果や景気変動 リスクに対する耐性があることは家計にとって大変大きな利点になる。 そして 三世代世帯を増やすための具体策が住宅ローン金利の引き下げと、転居の際に 補助金を交付する方法である。そして、余裕資金を生み出し投資に向け、有価 15 証券比率を高め、資産構成を変えていく ことを目指す。 そして第一章で、日本で投資がすすまない理由として安全志向と金融教育不 足を挙げた。その中で金融教育に視点を置き、第四章では個人のファイナンス 教育をしていくべきだと論じた。多種多様な金融商品が存在する中で、最適な 金融商品を選択できるようになるために、金融教育を普及させ、ライフプラン 20 を立てられるようにするべきだと考える。 ただし、今の日本にとって大幅に投資を増やすことが本当に良いことなのか については疑問が残る。アメリカなどの投資が活発な国に追随しても、国民性 や文化が異なるので成功するとは限らない。 ドイツのようにバランスのよい資 産構成を目指し、海外の成功例を取り入れつつ、日本ならではの家計における 25 資産構成を構築していくべきだと私たちは考える 。 将来、経済に不安を抱かず、豊かな生活を送るために資産構成は見直されな ければならない。そのために、私たちの提案が活用され、深く議論されるべき である。 30 35 参 考 文献 ウェブページ ・「 資 金 循 環 統 計 」 日 本 銀 行 調 査 統 計 局 http://www.boj.or.jp/statistics/sj/index.htm/ 5 ・「 ワ ー キ ン グ ペ ー パ ー ・ 日 銀 レ ビ ュ ー 」 http://www.boj.or.jp/research/wps_rev/index.htm/ ・「 第 一 章 家 計 負 担 の 現 状 と 教 育 投 資 の 水 準 」文 部 科 学 白 書 平 成 21 年 度 文 部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpab200901/detail/1296707 10 .htm ・「 国 立 大 学 と 私 立 大 学 の 授 業 料 等 の 推 移 」 文 部 科 学 省 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kokuritu/005/gijiroku/06052921/00 5/002.htm ・「 学 習 指 導 要 領 」 文 部 科 学 省 15 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/cs/index.htm ・「 金 融 教 育 に 関 す る 国 際 比 較 」( 2005) 金 融 庁 http://www.fsa.go.jp/news/newsj/16/singi/f-20050524-1/02.pdf ・「 第 1 部 第 1 章 消 費 者 を 取 り 巻 く 社 会 経 済 情 勢 の 動 向 と 消 費 者 行 動 ・ 意 識 」 消 費 者 問 題 及 び 消 費 者 政 策 に 関 す る 報 告 ( 2009~ 2011 年 度 ) 消 費 者 庁 20 http://www.caa.go.jp/adjustments/houkoku/setumei_1_1_2.html ・「 全 国 消 費 実 態 調 査 」 総務省統計局 http://www.stat.go.jp/data/zensho/2009/index.htm ・「 家 計 調 査 年 報 ( 家 計 収 支 編 ) 平 成 25 年 家 計 の 概 況 」 総 務 省 統 計 局 http://www.stat.go.jp/data/kake i/2013np/index.htm 25 ・「 住 宅 ・ 土 地 統 計 調 査 」 総 務 省 統 計 局 http://www.stat.go.jp/jyutaku_2013/index.htm ・「 国 勢 調 査 」 総 務 省 統 計 局 http://www.stat.go.jp/data/kokus ei/2015/index.htm ・「 家 計 の 貯 蓄 率 と 金 融 資 産 選 択 行 動 の 変 化 及 び そ れ ら の 我 が 国 の 資 金 の 流 れ 30 へ の 影 響 に つ い て 」 財 務 省 21 世 紀 の 資 金 の 流 れ の 構 造 変 革 に 関 す る 研 究 会 36 http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/henkaku/report/hk007b2.htm#0 2-02 ・「 労 働 条 件 総 合 調 査 」 厚 生 労 働 省 http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/11 -23.html 5 ・「 報 道 発 表 資 料 平 成 25 年 4 月 か ら 9 月 ま で の 年 金 額 は 平 成 24 年 度 と 同 額 」 厚生労働省 http://www.mhlw.go. jp/stf/houdou/2r9852000002tg08.html/ ・「 財 形 貯 蓄 制 度 」 厚 生 労 働 省 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/rousei/kinrousya/980831_2.htm 10 ・「 平 均 余 命 の 年 次 推 移 」 厚 生 労 働 省 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life10/sankou02.html ・「 お 金 の 取 扱 説 明 書 」 日 興 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社 http://www.okanenotorisetsu.jp/jyunbi/step4/st ep4-3.html ・金融広報中央委員会 15 http://www.shiruporuto.jp/ ・「 個 人 投 資 家 の 証 券 投 資 に 関 す る 意 識 調 査 」 日 本 証 券 業 協 会 http://www.jsda.or.jp/shiryo/chousa/kojn_isiki.html ・ Yahoo フ ァ イ ナ ン ス マーケット日経平均株価 http://finance.yahoo.co.jp/ 20 ・「 く ら し ラ イ ブ ラ リ ー 快適な二世帯同居の秘訣とは」パナホーム株式会社 ホームページ http://www.panahome.jp/kurashi/report/04/ ・公益財団法人生命保険文化センターによる「生活保障に関する調査 」 http://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/oldage/5.html 25 ・日経平均プロフィル http://indexes.nikkei.co.jp/nkave/archives/data ・ 日 経 STOCK リ ー グ https://stockleague.nikkei.co.jp/login/index.aspx ・土地代データ 30 http://www.tochidai.info/ 37 ・「 証 券 用 語 解 説 集 」 野 村 證 券 株 式 会 社 http://www.nomura.co.jp/terms/ ・「 野 村 世 界 業 種 別 投 資 シ リ ー ズ 」 野 村 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社 http://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=140470 5 ・「「 埼 玉 の 家 」 の ご 案 内 」 埼 玉 県 ホ ー ム ペ ー ジ http://www.pref.saitama.lg.jp/site/renkei/renkei -ki.html ・「 高 槻 市 は 、 住 宅 政 策 で 3 世 代 の 同 居 、 近 居 を 応 援 し ま す ! 」 高 槻 市 ホ ー ム ページ http://www.city.takatsuki.osaka.jp/shisei/kohokocho/buchoshitsu/kako/h2 10 5/toshi_h25/toshi250703.html ・「 在 学 数 」 関 西 学 院 大 学 http://www.kwansei.ac.jp/kikaku/kikaku_004166.html ・コトバンク https://kotobank.jp/word/ISA -10280 15 ・ UR 都 市 機 構 http://www.ur-net.go.jp/kosodate -net/system/system03.html 図書 ・「 普 通 の 人 が ゼ ロ か ら 始 め る 資 産 づ く り 」 日 本 経 済 新 聞 出 版 社 ( 2012) 日 本 20 新聞経済社 ・「 学 校 で は 教 え て く れ な い お 金 の 授 業 」 PHP エ デ ィ タ ー ズ ・ グ ル ー プ ( 2014) 山 崎 元 ・「 超 簡 単 お 金 の 運 用 術 」 朝 日 新 書 ( 2013) 山 崎 元 ・「 金 融 商 品 な ん で も 百 科 」 と き わ 総 合 サ ー ビ ス 株 式 会 社 ( 2010) 金 融 広 報 中 25 央委員会 ・「 統 計 で み る 日 本 」 日 本 統 計 協 会 ( 2014) ・「 国 家 が 個 人 資 産 を 奪 う 日 」 平 凡 社 ( 2013) 清 水 洋 ・「 お 金 を 知 る 技 術 殖 や す 技 術 」 朝 日 新 書 ( 2008) 小 宮 一 慶 30 38 文献 ・太田智之「家計貯蓄率の低下は今後も続くのか」 みずほ総合研究所 ( 2007) ・ 森 祐 司 「 高 齢 化 が も た ら す 家 計 貯 蓄 率 へ の イ ン パ ク ト 」 大 和 総 研 ( 2012) 5 ・菅井徹郎「パーソナルファイナンスとパーソナルファイナンス教育につい て 」 東 洋 英 和 女 学 院 大 学 大 学 院 ( 2010) ・前田俊之「対照的なフランスとドイツ~その問題点ばかりが似通っている日 本 の 悩 ま し さ ~ 」 ニ ッ セ イ 基 礎 研 究 所 ( 2012) ・保志泰、矢作大祐「アベノミクスと家計資産~「貯蓄から投資へ」の実現メ 10 カ ニ ズ ム を 考 え る ~ 」 大 和 総 研 調 査 季 報 ( 2013) ・村岡ひとみ「フランスにみる企業金融と個人金融資産動向 ‐ユーロ導入前夜 ‐」 ・ 金 融 広 報 中 央 委 員 会 「 行 動 経 済 学 の 金 融 教 育 へ の 応 用 の 重 要 性 」( 2012) ・ 内 閣 府 「 都 市 と 地 方 に お け る 子 育 て 環 境 に 関 す る 調 査 」( 2012) 15 ・ 内 閣 府 「 年 次 経 済 財 政 報 告 ‐ 需 要 の 創 造 に よ る 成 長 力 の 強 化 ‐ 」( 2010) ・ 文 部 科 学 省 「 平 成 24 年 度 「 子 供 の 学 習 費 調 査 」 の 結 果 に つ い て 」( 2014) ・ 厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 統 計 情 報 部 「 平 成 24 年 グ ラ フ で み る 世 帯 の 状 況 国 民 生 活 基 礎 調 査 ( 平 成 22 年 ) の 結 果 か ら 」 ・福井県ホームページ「ふくい子宝大作戦」 20 ・ 国 立 国 会 図 書 館 「 金 融 所 得 税 制 の 変 遷 と 現 状 ‐ 日 本 版 ISA の 導 入 を 踏 ま え て ‐ 」( 2013) 雑誌 ・週刊エコノミスト 25 「〔 金 融 教 育 〕 高 ま る 金 融 教 育 の 重 要 性 忠 克 」 2013 年 10 月 15 日 30 39 国家が取り組むべき課題に=淺野 新聞記事 ・毎日新聞 「 1645 兆 円 10 月 5 日 5 6 月末の家計の金融資産 株 高 ・ 預 金 増 で 過 去 最 高 」 2014 年 東京朝刊 ・日本経済新聞 「金融ニッポン ト ッ プ ・ シ ン ポ ジ ウ ム 「 成 長 へ の 次 の 一 手 」」 2014 年 10 月 17 日 朝 刊 「 大 機 小 機 家 計 か ら 成 長 へ の 循 環 」 2014 年 8 月 6 日 朝 刊 「「 積 み 立 て 型 」 NISA 拡 大 」 2014 年 10 月 20 日 朝 刊 40