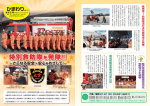Download ここをクリック!
Transcript
鉄骨切断機等の新たな解体用機械に係る 労働安全衛生法令の改正について 鉄⾻切断機 コンクリート圧砕機 解体用つかみ機 平成25年7月1日から上記3つの機械が 新たに労働安全衛生法の規制対象にな りました。 宮古労働基準監督署 1 本日の説明内容 1 新たな解体用機械による労働災害の発生状 況と問題点 2 車両系建設機械に対する労働安全衛生法令 上の規制の体系 3 具体的な改正の内容 4 その他関係する法令 5 皆さんにお願いしたいこと 2 1 新たな解体用機械による労働災害 の発生状況等と問題点 (1)解体用機械に係る労働災害の状況 (2)鉄骨切断機による労働災害の事例 (3)コンクリート圧砕機による労働災害の事例 (4)解体用つかみ機による労働災害の事例 (5)沖縄県内の解体現場に係る災害事例 (6)新たな解体用の車両系建設機械による労働災害発生 上の問題点 3 (1) 解体用機械に係る労働災害の発生について労働安全衛生法令が改正され、今 まで対象外であった災害の約1割を占める解体用機械が法規制の対象になり、 労働災害防止対策を行う義務が平成25年7月1日より生じています。 平成23年度の建設機械に起因する休業4日以上の死傷者数 1590人のうち8%が解体用の車両系建設機械 解体用車両系建設機械による被災者数127人 (8.0%) 解体用機械の種類別、災害の種類別の発生状況は、次のとおり。 コンクリート圧砕機 鉄骨切断機 その他 ①アタッチメント に挟まれる ⑤破砕した 物が飛来 ④アタッチメント 交換作業中 解体用つかみ機 ②掴んだ物が落下 ⑤破砕した物が飛来 ⑤破砕した 物が飛来 ③アタッチメン トに当たる その他 ④アタッチメント 交換作業中 ②掴んだ物が落下 ③アタッチメントに当たる 休業4日以上災害 合計11人 ①アタッチメント に挟まれる ②掴んだ物が落下 ④アタッチメント 交換作業中 休業4日以上災害 合計5人 休業4日以上災害 合計100人 4 (2) 鉄骨切断機による労働災害の事例 労働災害の発生状況 (かっこ内は23年の被災者数) 1 問題点 対策の方向(案) アタッチメントに挟まれる(3人) (例1) ビル解体工事でALCを引き倒すため ① 鉄骨切断機の運転手とワイヤロープ ① 運転中の鉄骨切断機に接触することにより労 ワイヤロープをかけてアタッチメントで をかける労働者との合図、調整が不 働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労 つかむ際に手を挟んだ。 十分だったこと。 働者を立ち入らせないこと。 (例2) アタッチメントにワイヤーを巻いて荷 ② アタッチメントでワイヤーを使って物を ② 鉄骨切断機による物の吊り上げを禁止するこ 物を吊り上げようとした際、合図応答 吊り上げようとしたこと。 と。(アタッチメントにワイヤロープ等を玉掛け の確認をしないでアタッチメントを閉じ することは禁止すること。) たため、指を挟まれた。 (3) 3 コンクリート圧砕機による労働災害の事例 掴んだ物等が落下(1人) (例1) コンクリートガラをアタッチメントで掴 んだ際に、当該コンクリートガラに連 結されていたコンクリートガラが落下 して受傷した。 ① コンクリート圧砕機で掴んだ物が落下 ① コンクリート圧砕機で掴んだ物が落下して労 するおそれのある場所に労働者が立 働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労 ち入っていたこと。 働者を立ち入らせないこと。 5 (4) 解体用つかみ機による労働災害の事例 労働災害の発生状況 (かっこ内は23年の被災者数) 問題点 対策の方向(案) 1 アタッチメントに挟まれる(27人) (例1) 廃材をトラックに積み込む作業中、 ① つかみ具で帯ひもを使って物を吊り上 ① つかみ機による物の吊り上げを禁止するこ 吊り上げ用帯ひもを爪に引っかける げようとしたこと。 と。(つかみ具にワイヤロープ等を玉掛け 際につかみ具に挟まれた。 することは禁止すること。) ② つかみ機の運転手と帯ひもを引っか ② 運転中のつかみ機に接触することにより労 ける労働者との合図、調整が不十分 働者に危険が生ずるおそれのある箇所に だったこと。 労働者を立ち入らせないこと。 5 破砕して飛来、掴んだ物が飛来(5人) (例1) 解体工事で発生した木材を仕分け ① つかみ機で木材を強く掴んだため、 ① していた際に、グラップルで掴んだ 木が破砕し、破片が飛び散ったこと。 木材が破砕して飛来し、作業員に 当たった。 ② 破片の飛び散る距離内に作業員が ② いたこと。 つかみ具で木材等を掴む際には、当該木 材等を破砕しないよう掴むこと。 つかみ具で掴んだ物が破砕して飛来し、 労働者に危険が生ずるおそれのある箇所 に労働者を立ち入らせないこと。 6 (5) 沖縄県内の解体現場に係る災害事例 H25.4.19 沖縄タイムズ H25.4.19 琉球新報 7 (6)新たな解体用の車両系建設機械による労働災害発生上 の問題点(解体用車両系建設機械の新たな安全対策に係る検討会報告書より) (1)アタッチメントにワイヤロープ等をかけ、玉掛けをして物を吊る作業で労働災害 が発生していること。 (2)掴んだ物が落下したり、掴んだ物が破砕して飛来し、それが作業従事者に当 たって災害が発生していること。 (3)物を掴んだ機械が旋回する際等にアタッチメントや掴んだ物に作業従事者が当 たる災害が発生していること。 (4)アタッチメントの交換作業や修理作業中に災害が発生していること。 (5)機械が転倒したり、機械に轢かれたりして災害が発生していること。 (6)機械の運転について、運転者が必要な知識、技能を有していないために災害が 発生していること。 (7)新たな解体用車両系建設機械について、以上のような災害状況に対応する安 衛法令上の規制がないことから、事業者が労働災害防止のために必要な措置を講 ずることなく使用していることや必要な運転技能を有していない労働者が運転してい ることが、これら災害発生の要因となっていると考えられること。 8 2 車両系建設機械に対する労働安全衛生法 令上の規制の体系 (1)労働安全衛生法施行令別表第7に規定される建設機 械 (2)鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機 の労働安全衛生法施行令別表第7に定める車両系建 設機械への解体用機械として追加されました。 (3)解体用機械には安衛法令により次の義務がかかる。 9 (1)労働安全衛生法施行令別表第7に規定される建設機械 一 整地・運搬・積込み用機械 1 ブル・ドーザー 2 モーター・グレーダー 3 トラクター・シヨベル 4 ずり積機 6 スクレープ・ドーザー 7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 5 スクレーパー 二 掘削用機械 1 パワー・シヨベル 2 ドラグ・シヨベル 3 ドラグライン 4 クラムシエル5 バケット掘削機 6 トレンチャー 7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 三 基礎工事用機械 1 くい打機 2 くい抜機 3 アース・ドリル 4 リバース・サーキユレーシヨン・ドリル 5 せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。) 6 アース・オーガー 7 ペーパー・ドレーン・マシン 8 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 四 締固め用機械 1 ローラー 2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 五 コンクリート打設用機械 1 コンクリートポンプ車 2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 六 解体用機械⇐(今回説明する機械はここに該当します) 1 ブレーカ 2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械 10 (2)鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ 機の労働安全衛生法施行令別表第7に定める車両系建 設機械への解体用機械として追加されました。 労働安全衛生規則 第二章 建設機械等 第一節 車両系建設機械 第一款 総則 (定義等) 第151条の84 この節において解体用機械とは、令別表第七第六号に掲げる機械で、 動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。 2 令別表第七第六号2の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりと する。 一 鉄骨切断機 二 コンクリート圧砕機 三 解体用つかみ機 11 (3)解体用機械には安衛法令により次の義務がかかる。 ① 機械等貸与者(リース業者)は、貸し出すに際しあらかじめ、点検、整備 を実施(法33条) ② 厚生労働大臣が定める構造規格を具備しないと、譲渡、貸与等を禁止 (法42条) ③ 定期自主検査(1年以内、1月以内ごと)を実施(法45条第1項) ④ 1年以内ごとに行う定期自主検査は一定の資格者が実施 (特定自主検査、法第45条第2項) ⑤ 3トン以上の機体重量の機械の運転の業務は、技能講習の修了者以外 は禁止(法61条) ⑥ 3トン未満の機体重量の機械の運転の業務に就かせるときは、 特別の教育を実施(法59条第3項) ⑦ その他使用上の規制の履行(安衛則第2編第2章第1節) 12 3 具体的な改正の内容 以下の点が改正されました。 (1) 新たな解体用機械 (2) 構造 (3) アタッチメントを交換できる車両系建設機械の使用 (4) 解体用機械の使用 (5) 長い作業装置を有する解体用機械 (6) 鉄骨切断機等の運転業務 13 (1)新たな解体用機械 ・ 鉄骨切断機とは、 鉄骨(非鉄金属の工作物を含む。)を切断するためのはさみ状のアタッチメ ントを装着した建設機械をいいます。 ・ コンクリート圧砕機とは、 コンクリートを砕くためのはさみ状のアタッチメントを装着した建設機械を いいます。 鉄筋を切断する機能を付加したものも、これに含まれます。 ・ 解体用つかみ機とは、 木造の工作物を解体し、又はその解体物をつかんで 持ち上げるための フォーク状のアタッチメントを装着した建設機械をいいます。 14 鉄骨切断機 コンクリート圧砕機 鉄骨造の工作物の解体、コンクリート造の工作物の解体等に用いられる。 鉄骨切断機 コンクリート圧砕機 使用するアタッチメント 鉄骨切断具 コンクリート大割圧砕具 15 長い作業装置を有する解体用機械⇒特定解体用機械 特定解体用機械とは ブーム及びアームの長さの合計が 12メートル以上である解体用機械 鉄骨切断機とコンクリート圧砕機が 存在 特定解体用機械 16 日立建機株式会社製 解体用つかみ機 木造家屋の解体等に用いられる。 つかみ具(内部シリンダー作動型) つかみ具(外部シリンダー作動型) キャタピラージャパン株式会社製 17 解体用の車両系建設機械に該当しない機械の例 解体用の車両系建設機 械として設計・製造され ていない機械 =工作物の解体用に設 計・製造されていない機 械は、車両系建設機械 に該当しない。 林業クラップル 本船荷役用マテリアル ハンドリング機 自動車解体用切断機 しかし、車両系建設機械 として、設計・製造された 機械が、アタッチメントを 取り替えることにより一 時的に令別表第7の車 両系建設機械でなくなる 場合も、その機械は車両 系建設機械である。 金属リサイクル用 ハンドリング機 左の2機種は日立建機株式会社製、右の2機種はコベルコ建機株式会社製 18 (2) 構造 ア 構造関係の改正事項(その1) 事業者の皆さまへ 1 ヘッドガード(安衛則第153条) 岩石の落下等(鉄骨切断物を含む。)により労働者に危険が生ずるおそれのあ る場所で解体用機械を使用するときは、堅固なヘッドガードを備えたものを使って ください。 2 転倒時保護構造及びシートベルト(安衛則第157条の2) 路肩、傾斜地等で転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で解体 用機械を使用するときには、転倒時保護構造を有し、かつシートベルトを備えたもの以外 の機械を使用しないよう努めてください。 また、運転者にはシートベルトを使用させるよう努めてください。 シート ベルト ① 1、2の措置とも、解体用機械に限らず車両系建設機械全般を 対象に課しているが、1は義務、2は努力義務。 ② 2に関しては、路肩、傾斜地等での転倒、転落防止のための誘 導者の配置や路肩の崩壊防止等の措置も徹底することが必要。 (安衛則第157条) 19 イ 構造関係の改正事項(その2) 事業者の皆さまへ 3 運転室のない解体用機械の使用禁止(安衛則第171条の5) 物体の飛来等により運転者に危険が生ずるおそれのあるときは、運転室を有しない解体用 機械を用いて作業を行わないでください。(ただし、物体の飛来等による危険の防止措置を講 じた場合を除きます。) 危険の防止措置は、次の例があります。 ① アタッチメント自体への覆いの取付け ② 物体の飛来又は激突の強さに応じた 防護設備の取付け ③ 物体の飛来の強さが十分弱い場合、 顔面の保護面を有する保護帽等の使用 フロントガード(物 体の飛来による 危険を防止する ための設備) ヘッドガート(岩石等の 落下による危険を防 止するための設備) 前面ガラス (安全ガラス) 運転室周りの飛来物防護設備の例 ※上の写真:キャタピラージャパン株式会社製、同社提供 20 製造者の皆さまへ 4 運転に必要な視界等(運転室の飛来物防護設備)(構造規格第9条) 鉄骨切断機及びコンクリート圧砕機の運転室には、その前面に、物体の飛来による危険を 防止するための設備を備えてください。 飛来物の防護の措置について、整理をすると、次のとおり。 運転室(運転席を含む。)前面の飛来物防護措置 根拠条文 措置 車両系建設機械(ブレーカを除 く。)の運転室 ブレーカの運転室 鉄骨切断機又はコンクリート 圧砕機の運転室 解体用つかみ機の運転室 運転室のない解体用機械 構造規格第9条第3項 安全ガラス 構造規格第9条第4項 安全ガラス or 飛来物防護設備 構造規格第9条第5項 安全ガラス+飛来物防護設備 構造規格第9条第3項 安全ガラス 安衛則第171条の5 アタッチメントの覆い、飛来物防護設備又は保護具 21 (3) アタッチメントを交換できる車両系建設機械の使用 ア その1(アタッチメントの交換の際の措置) 事業者の皆さまへ 1 修理、アタッチメント交換時の措置(作業指揮者)(安衛則第165条) 車両系建設機械の修理又はアタッチメントの装着又は取り外しの作業を行うときは、当該作業を 指揮する者を定め、その者に、ブーム等の降下による危険を防止するための安全支柱、安全ブロッ ク等(第166条)及びアタッチメントの倒壊等による危険を防止するための架台(安衛則第166条の2) の使用状況を監視させてください。 2 アタッチメントの倒壊等による危険の防止(安衛則第166条の2) 車両系建設機械のアタッチメントの装着又は取り外しの作業を行うときは、アタッチメントが倒壊す ること等による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に架台を使用させてくだ さい。 ① 架台は、専用の架台に限らず、敷角等アタッチメントの倒 壊等を防止できるものであれば可。 ② 安定的に地面に置くことができるアタッチメントにまで架台 の使用を義務付けているものではない。 架台 22 イ その2(アタッチメントの装着の制限) 事業者の皆さまへ 3 アタッチメントの装着の制限(安衛則第166条の3) 車両系建設機械には、その構造上定められた重量を超えるアタッチメントを装着しないでくだ さい。 改正条文(労働安全衛生規則) 第166条の3(アタツチメントの装着の制限) 事業者は、車両系建設機械にその構造上定められた重量を超えるアタツチ メントを装着してはならない。 解釈例規(166条の3関係) ① アタッチメントを交換できる車両系建設機械について、その構造上定められた重量を 超えるアタッチメントを取り付けた場合、当該車両系建設機械が転倒する危険があること から、その構造上定められた重量を超えるアタッチメントの装着を禁止したこと。 ② 「その構造上定められた重量」とは、車両系建設機械構造規格(昭和47年労働省告示 第150号)に規定される安定度が損なわれない範囲内のアタッチメントの重量をいうこと。 ③ 本条は、鉄骨切断機等以外の車両系建設機械にも適用されるものであり、アタッチメ ントには、鉄骨切断具、コンクリート圧砕具及び解体用つかみ機のつかみ具のほか、バ ケット、ジッパーが含まれること。 (平成25年4月12日付け発第0412第13号) 23 ウ その3(アタッチメントの重量の表示等) 事業者の皆さまへ 4 アタッチメントの重量の表示等(安衛則第166条の4) アタッチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタッチメントの重量(バケット、ジッ パー等を装着したときは、当該バケット、ジッパー等の容量又は最大積載重量を含む。)を表示し、 又は当該車両系建設機械に運転者がアタッチメントの重量を容易に確認できる書面を運転席周辺 の容易に取り出せる場所に備え付けてください。 ① アタッチメントには、鉄骨切断具、コンクリート圧砕具、解体用つかみ具、ブレーカユニット、バケット、 ジッパーが含まれます。 ② 「バケット、ジッパー等」の「等」には、「解体用つかみ具」が含まれ、その場合は最大積載重量は、最大 持上げ重量を示します。 ③ 平成25年6月30日までに譲渡等された機械について、その機械を譲渡等した者は、相手方の求めに 応じてアタッチメントの重量の情報を提供する必要があります。 ④ アタッチメント自体にも同様の表示を行うことが望ましいものです。 製造者の皆さまへ 5 取り替えられるアタッチメントへの表示等(構造規格第15条第3項) 取り替えられるアタッチメントを有する車両系建設機械は、製造者名等の事項に加え、運転者の 見やすい位置に当該アタッチメントの重量及び装着することができるアタッチメントの重量が表示さ れているか又は運転者がアタッチメントの重量を容易に確認できる書類が備え付られているものと してください。(※容易に確認できる書類とは、取扱説明書のような厚いものでなく、アッタチメント の重量をすぐ確認できる1枚程度のものです。) 24 取り替えられるアタッチメントを有する車両系建設機械への表示を整理す ると、 製 造 時 製造者が次の事項を表示 ・装着したアタッチメントの重量等 ・装着可能な範囲のアタッチメン トの重量等 譲渡 使 用 時 アタッチメントを交換した使用者は 次の事項を表示 ・交換後のアタッチメントの重量等 25 (4) 解体用機械の使用 事業者の皆さまへ 1 地形等の調査及び記録(安衛則第154条) 解体用機械を用いて解体作業を行うときは、転落、転倒による労働者の危険 を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形等(地盤の強 度、傾斜等を含みます。)の状態等を調査し、その結果を記録してください。 2 作業計画(安衛則第155条) 解体用機械を用いて作業を行うときは調査により知り得たところに適応する 作業計画を定め、その作業計画により作業を行ってください。作業計画には、 機械の種類及び能力、運行経路、作業方法(機械の位置や立入り禁止区域等を 含む。)を示すとともに、関係労働者に周知してください。 26 記載例(宮城労働局から抜粋) 27 3 主たる用途以外の使用の制限(安衛則第164条) 解体用機械のアタッチメントにワイヤロープをかけて荷のつり上げ作業を行 う等解体用機械の主たる用途以外の用途に使用しないでください。 ※建災防提供 4 定期自主検査(安衛則第167条及び第168条) 解体用機械については、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行ってく ださい。 この場合、その検査(特定自主検査)は検査業者又は一定の資格者に行わせ てください。また、1月以内ごとに1回、定期に、自主検査を行ってください。 5 特定自主検査(安衛則第169条の2) 上記4とともに、1年以内ごとに1回、有資格者による特定自主検査を行っ てください。特定自主検査実施後には、特定自主検査の記録を3年間保存する とともに、ベースマシンには「特定自主検査済標章」を貼付しなければなりま せん。 特定自主検査記録表 3年間 保管 事業内検査用 検査業者検査用 28 アタッチメント検査済シールについて 「アタッチメント検査済シール」は特定自主検査(事業内検査または 検査業者検査)を実施した際、本体に貼付する「検査済標章」に加 え、「 ブレーカ」、「鉄 骨切断機 」、「コンクリート圧砕機 」、「 解体用 つかみ機 」の解体用機械のアタッチメントに貼付し、特定自主検査 を実施したことを証するためのものです。 注)この件は、解体用機械のみならず、取替え可能なアタッチメントを 有する車両系建設機械にも適用されます。 厚生労働省通達平成25年6月3日付基安発0603第1号 取替え可能なア タッチメントにも、当該検査を実施したことを証するシールを貼るよう努めること。 29 ※建荷協パンフレット抜粋 30 6 立入禁止等(安衛則第171条の6) 解体用機械を用いて作業を行うときは次の措置を講じてください。 ① 物体の飛来等により労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の労 働者を 立ち入らせないこと。 ② 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるとき は、当 該作業を中止すること。 ① この立入禁止の範囲は、物体の飛来に加え、解体用つか み機によりつかんだ物やアタッチメントに激突されるおそれの ある範囲も含まれる。 カラーコーン等で区分けすることが必要。 ② 解体用機械の誘導者も立入禁止区域への立入りは禁止さ れる。飛来等のおそれのある区域外から誘導するようにする。 31 (5)長い作業装置を有する解体用機械 事業者の皆さまへ 1 1月以内に実施する定期自主検査の項目の追加(安衛則第168条) 解体用機械のうちブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上である機械(以下「特定 解体用機械」という。)については、1月以内ごとに定期に、操作装置、作業装置等の異常の有 無に加え、逆止め弁、警報装置等の異常の有無について、自主検査を実施してください。 ① 逆止め弁は、油圧ホースの損傷等により油圧が急激に低下したときにブームの急降下 を防止するための弁でブームシリンダーの下部に備えられます。1月以内の検査では、油 漏れの有無をチェックします。 ② 警報装置は、作業範囲を超えてブーム等が操作されたときに警音を発する装置のこと。 作業範囲を超えた時に作動するかをチェックします。 ③ 「警報装置等」の「等」には、自動停止装置、ブーム角度計、水準器が含まれます。これ らが、正常に作動するかをチェックします。 32 2 傾斜地等での使用の禁止(安衛則第171条の4) 路肩、傾斜地等であって、「特定解体用機械」の転倒又は転落により労働者に危険が生ずる おそれがある場所では、特定解体用機械を用いて作業を行わないでください。 ① 「労働者に危険が生ずる場所」には、傾斜角が5度を超える傾斜地、岩石、根株等が あって転倒等のおそれのある場所が含まれます。 ② 補強やガードレールを設置した路肩、必要な広さ及び強度を有する鉄板の敷設や締め 固めを行った地盤は、「労働者に危険が生ずる場所」には含まれません。(安衛則第157条、 第157条の2も同様。) 傾斜したと ころでは使 わない 33 製造者の皆さまへ 3 前方安定度(構造規格第4条第5項) 特定解体用機械は、ブーム及びアームが向けられている側の転倒支点にお ける安定モーメントの値をその転倒支点における転倒モーメントの値で除し て得た値が1.5以上である前方安定度を有するものとしてください。 4 作業範囲を超えたときの自動停止装置等(構造規格第13条の2) 特定解体用機械で作業範囲を超えてブーム又はアームが操作されるおそれ のあるものは、作業範囲を超えてブーム及びアームが操作されたときに、起 伏装置等の作動を自動的に停止させる装置又は警音を発する装置を備えてい るものとしてください。 5 安全弁等(構造規格第14条第2項) 油圧を動力として用いる特定解体用機械の起伏装置等は、当該油圧の異常 低下によるブーム及びアームの急激な降下等を防止するための逆止め弁を備 えているものとしてください。 34 (6) 鉄骨切断機等の運転業務 1 3トン以上の鉄骨切断機等の運転の業務に就くことができる者(安衛則別表第3) 3トン以上の鉄骨切断機等の運転は、平成25年7月1日以降に開始される車両系建設機械 (解体用)運転技能講習を修了した者等に行わせてください。 ① 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(以下「解体用技能講習」という。)は、ブレーカを 対象としたものから、ブレーカ及び鉄骨切断機等の4機種を対象としたものに変わります。( 平成25年7月1日) ② 講習内容が充実したことにより、講習時間は改正前の35時間から改正後は38時間となり ます。また、整地・運搬・積込み用及び掘削用の技能講習を修了した者に対する特例の講 習の時間は、改正前の3時間から改正後は5時間となります。 ③ 改正前の解体用技能講習を修了した者は、平成25年7月1日以降も引き続きブレーカの 運転業務に就くことができます。 ⑤ 国土交通省資格の建設機械施工技士の方も鉄骨切断機等の運転に当たっては、講習の 受講が必要です。 35 車両系建設機械(解体用)運転技能講習(国交省資格取得者別)比較表 改正前 車両系建機(解体用) 技能講習規程 解体用 建設機械施工技士の資格と車 フルの 両系建設機械(解体用)の各 講習 種技能講習の講習科目 (第2 条) ショベル 系・トラク ター系以 外 (第3条) 整地・運 搬・積込 み用及び ショベ 掘削用 ル系 (トラク ター系) (第4条) 改正後 車両系建機(解体用) 技能講習規程 解体用 フルの 講習 (第2 条) ショベル 系・トラク ター系以 外 ( 第4条 第3項) 整地・運搬・ 積込み用及 び掘削用(ト ショベル系 ラクター系) (第4条第2 (第4条第1 項) 項) (短縮講習) 学科講習 講習科目 走行に関する装置の構造及び取扱 4時間 いの方法に関する知識 作業に関する装置の構造、取扱い 4時間 方法及び作業方法に関する知識 運転に必要な一般的事項に関する 2時間 知識 関係法令 1時間 小 計 11時間 講習時間 講習時間 免除 免除 免除 4時間 免除 免除 免除 4時間 1時間 免除 5時間 5時間 2時間 1時間 免除 0.5時間 免除 3時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 免除 4時間 0.5時間 2時間 免除 0時間 1時間 13時間 0.5時間 6時間 0.5時間 3時間 0.5時間 2時間 実技講習 講習科目 走行の操作 作業のための装置の操作 小 計 合 計 20時間 4時間 24時間 講習時間 免除 免除 4時間 1時間 4時間 1時間 免除 免除 0時間 20時間 5時間 25時間 35時間 8時間 0時間 38時間 3時間 講習時間 免除 免除 5時間 2時間 5時間 2時間 11時間 5時間 免除 1時間 1時間 3時間 (注1)表中ショベル系は、建設機械施工技術検定の1級合格者でショベル系の選択者、2級の第2種合格者、トラク ター系は1級合格者でトラクター系の選択者、2級の第1、3種合格者、ショベル系・トラクター系以外は1級合格者でトラク ター系、ショベル系を選択しなかった者(モーター・グレーダー、締め固め、ほ装用、基礎工事用を選択した者)、2級の第 4、5、6種合格者を示します。 36 2 3トン以上の鉄骨切断機等の運転の業務に就くことができる者(安衛則改正省令附則第3条 第1号) 改正前の解体用技能講習(ブレーカに係る技能講習)を修了した者については、平成27年6月 30日までの間に行われる都道府県労働局長の定める講習(技能特例講習)を修了した場合には、 鉄骨切断機等の運転の業務に就くことができるため、できるだけ早く受講させてください。 3 3トン以上の鉄骨切断機等の運転の業務に就くことができる者(安衛則改正省令附則第3条 第2号) 平成25年7月1日時点で、鉄骨切断機等の運転の業務に従事しており、かつ、当該業務に6月 以上従事した経験を有する者については、平成27年6月30日までの間に行われる都道府県労働 局長の定める講習(技能特例講習)を修了した場合には、鉄骨切断機等の運転の業務に就くこと ができるため、できるだけ早く受講させてください。 ④ 技能特例講習の種類は、資格、経験に応じて4種類です。 技能特例講習の種類 技能講習修了証の保有状況 車両系建設機械(解体用)運転技能講習修了証 車両系建設機械(整地等用)運転技能講習修了証 運転技能講習修了証なし 鉄骨切断機 等の運転経 験6月以上 (平成25年7 月1日現在) の有無 有 第1種技能特例講習 無 第2種技能特例講習 有 第3種技能特例講習 無 改正後 短縮講習 有 第4種技能特例講習 無 解体用フルの講習 37 車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習の基準 車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習比較表 車両系建設機械(解体用)の技能特例講習の講習科目及び範囲 第1種 第2種 第3種 第4種 学科講習 講習の範囲 車両系建設機械(解体用)の 走行に関する装置の構造 ①原動機 ②動力伝達装置 ③走行装置 ④かじ取り装置 及び取扱いの方法に関す ⑤ブレーキ ⑥電気装置 ⑦警報装置 ⑧走行に関する附属装置 る知識 の構造及び取扱いの方法 作業に関する装置の構 ①車両系建設機械(解体用)の種類及び用途 造、取扱い方法及び作業 ②作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱いの方法 方法に関する知識 ③車両系建設機械(解体用)による一般的作業方法 ①車両系建設機械(解体用)の運転に必要な力学 運転に必要な一般的事項 ②コンクリート造、鉄骨造又は木造の工作物等の種類及び構造 に関する知識 ③建設施工の方法 講習時間 講習科目 関係法令 労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則中の関係条項 小 計 免除 免除 免除 2時間 1時間 1時間 2時間 2.5時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 1.5時間 0.5時間 0.5時間 0.5時間 1時間 2時間 2時間 3時間 7時間 実技講習 講習科目 走行の操作 範 囲 基本操作 定められたコースによる基本走行及び応用走行 講習時間 免除 免除 免除 免除 免除 1時間 免除 免除 計 0時間 1時間 0時間 0時間 合 計 2時間 3時間 3時間 7時間 作業のための装置の操作 基本操作 定められた方法による基本施工及び応用施工 小 (注)技能特例講習の対象者については、それぞれ第1種は改正前の解体用技能講習修了者で6カ月以上の鉄骨切断機等の運転経験者、第 2種は改正前の解体用技能講習修了者で6カ月未満の鉄骨切断機等の運転経験者、第3種は整地・運搬・積込み用及び掘削用技能講習修了 者で6カ月以上の鉄骨切断機等の運転経験者、第4種は6カ月以上の鉄骨切断機等の運転経験者が対象である。 38 別紙様式3 平成○年○月○日 (技能特例講習実施機関名) 御担当者 殿 (元方事業者名) (事業場名) 社印 代表者印 (事業者名) 新たな解体用車両系建設機械運転の実務経験について 今般、新たな解体用車両系建設機械の技能特例講習(第_種)の受講申込みに当たり、標記につ いて、下記のとおり証明しますので、よろしく取り計らい願います。 記 1 証明対象労働者職氏名等 職名 氏名 2 1の者が現在所有している資格等(該当するものに○を付すこと。申請時に原本を提示すること。) (1)車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 (2)車両系建設機械(解体用)運転技能講習 3 1の者の新たな解体用車両系建設機械運転の経験期間及び業務従事予定等 平成 年 月∼平成 年 月 年 ヶ月間 平成25年7月1日時点で新たな解体用車両系建設機械の運転業務に 従事予定 又は 従事 (どちらかに○を付すこと) 4 1の者が運転経験を有する新たな解体用機械の種類(該当するものに○を付すこと) (1)鉄骨切断機 (2)コンクリート圧砕機 (3)解体用つかみ機 5 1の者が従事した解体工事等 (上記4(1)∼(3)の機械を使用した解体工事等名及び工事等の期間を記載すること。紙面が足りな ければ別紙に記載して良いこと。) 工事名: 工 期:平成 年 月∼平成 年 月 39 労働安全衛生規則の一部を改正する省令の附則 (就業制限に関する経過措置) 第三条 事業者は、新安衛則第百五十一条の八十四第二項各号に掲げる機械の運 転の業務については、新安衛則第四十一条の規定にかかわらず、次の各号のいず れかに該当する者を当該業務に就かせることができる。この場合においては、その者 については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。 一 平成二十五年七月一日前に、この省令による改正前の労働安全衛生規則の規 定により行われた車両系建設機械(解体用)運転技能講習を修了した者であって、平 成二十七年六月三十日までの間に行われる講習で都道府県労働局長が定めるもの を修了したもの 二 平成二十五年七月一日において現に当該業務に従事し、かつ、当該業務に六月 以上従事した経験を有する者であって、平成二十七年六月三十日までの間に行われ る講習で都道府県労働局長が定めるものを修了したもの 40 4 3トン未満の鉄骨切断機等の運転の業務に就かせるときの特別教育 (安衛則第36条第9号) 平成25年7月1日以降に、3トン未満の鉄骨切断機等の運転の業務に 労働者を就かせるときは、改正された安全衛生特別教育規程の教育科 目、範囲及び時間に基づく特別教育を実施してください。 ① 小型車両系建設機械(解体用)運転の業務に係る特別教育(以下「小型解体用 特別教育」という。)は、ブレーカを対象としたものから、ブレーカ及び鉄骨切断機等 の4機種を対象としたものに変わります。(平成25年7月1日) ② 教育内容が充実したことにより、教育時間は改正前の12時間から改正後は14 時間となります。 ③ 改正前の小型解体用特別教育を受けた者は、平成25年7月1日以降も引き続 き機体重量3トン未満のブレーカの運転業務に就くことができます。 ④ 改正後の小型解体用特別教育の講習科目及び時間は次のとおりです。 1)学科教育 走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識 運転に必要な一般的知識に関する知識 関係法令 2時間 2.5時間 1.5時間 1時間 2)実技教育 走行の操作 作業のための装置の操作 合計 4時間 3時間 14時間 41 4 その他関係法令 (1)建築物の解体作業について (2)事前調査(石綿則第3条第1項、2項) (3)建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する 技術上の指針 (4)届出(安衛則第90条又は石綿則第5条) (5)石綿の含有する建築物の解体等に係る届出について (6)特別教育 (7)石綿粉じん濃度測定(石綿則第36条) 42 (1)建築物の解体作業について 建材の種類により、解体作業における石綿粉じんの飛散の「レベル」が変わる ことから、建材をレベル分けし、それぞれのレベルごとに必要な措置を定めてい る。 レベル1:吹付け石綿の除去、封じ込め(※)、囲い込みの作業 ※ 吹付け石綿の切断等の作業が伴わない場合はレベル2相当 レベル2 保温材耐火被覆材等が張り付けられた建築物等の解体等の作業(※) ※ 石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る。 レベル3:その他の建材(スレート材等) ※厚生労働者パンフレット抜粋 43 (2)事前調査(石綿則第3条第1項、2項) 建築物等の解体等の作業を行うときは、事前に石綿等の使用の有無を 目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければなら ない。 石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の有 無を分析により調査し、その結果を記録しておかなければならない。(た だし、石綿等が吹き付けられていないことが明らかである場合において、 石綿等が使用されているものとみなして措置を講ずるときは、この限りで ない。 不適切な調査の結果、石綿の使用を見過ごした場合、石綿則に基づく措 置が講じられずに解体等の作業が行われることになることから、事前調査 は適切に行う必要があり、石綿について相応の知識を持つものが行うことが 望ましい。 44 (3)建築物等の解体等の作業での労働者の 石綿ばく露防止に関する技術上の指針 事前調査 調査結果の記録及び掲示 ・調査結果には、写真や図面を添付 【調査結果の記録項目】 ア事業場の名称 ウ発注者からの通知の有無 オ調査結果(分析結果を含む) キ調査を終了した年月日 イ建築物等の種別 エ調査方法及び調査箇所 カ調査者氏名及び所属 クその他必要な事項 ・調査結果の記録のうちの一部を周辺住民にも見やすいよう掲示 ・調査結果の記録については、原本又は写しを作業場に備え付け ・石綿等が使用されていなかった場合でも、結果を記録・掲示・備え付け ・調査結果の記録を40年間保存(発注者等も同様の保存が望ましい) 45 建築物等の解体等の作業での労働者の 石綿ばく露防止に関する技術上の指針 事前調査の結果の表示の例 〔RC建築物の解体等〕 石綿の使用状況の調査結果 事業場の名称: ○○建設株式会社 ○支店 現場責任者 ▲▲ 建築物等の種別: ビル 調査方法: (調査箇所) 設計図書の確認、現場における目視及び石綿含有率の分析 (1階から5階まで) 発注者からの通知 有り(設計図書と改修記録) 調査結果: (1階)アモサイト (2階)アモサイト (3階)アモサイト (4階)アモサイト (5階)アモサイト 調査者氏名及び所属: 調査終了年月日: %、クロシドライト % % % % % ○○分析化学(株)(○○(Aランク認定分析技術者)) 平成 年 月 日 (出所)「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」の制定 について(平成24年5月9日 基発0509第10号) 46 【アスベストばく露防止対策等の実施内容の掲示】(平成17年8月2日 基安発第0802001号) ※下の掲示は周辺住民向けに適切にばく露防止対策を実施していることを周知するためのもので、 上述の事前調査の結果の掲示とは異なる。しかし、両掲示の項目が網羅されていれば、1枚の掲 示でもよい。 (別紙1) (例-届出対象) (別紙3) (例-石綿を含有していない建築物の解体) 47 (4)届出(安衛則第90条又は石綿則第5条) 事業者は、保温材、耐火被覆材等の除去、吹付け石綿の除去、封じ 込め又は囲い込みの作業を行うときは、あらかじめ、所轄労働基準監 督署長に提出しなければならない。 耐火建築物等に吹付けられた石綿の除去の作業 → 14日前まで(安衛法第88条、安衛則第90条) その他の作業 → あらかじめ(石綿則第5条) なお、レベル3の建材の除去作業については、届出義務無し 48 (5)石綿の含有する建築物の解体等に係る届出について ※厚生労働者パンフレット抜粋 49 (6)特別教育 (安衛則第36条及び石綿則第27条) 事業者は、建築物等の解体等の作業に労働者を就かせるときは、当該労働 者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 一 二 三 四 五 石綿の有害性(石綿の性状等、0.5時間) 石綿等の使用状況(石綿製品の種類・事前調査の方法等、1時間) 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置(作業方法、1時間) 保護具の使用方法(保護具の性能・管理等、0.5時間→1時間) その他、石綿等のばく露の防止に関し必要な事項(法令等、1時間) ※下線部は、石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程 (平成17年厚生労働省告示第132号)より抜粋 50 (7)石綿粉じん濃度測定(石綿則第36条) 事業者は、石綿等を取り扱う屋内作業場等について、6月以内ごとに 1回、定期に、石綿の空気中における濃度を測定しなければならない。 臨時に行われる作業については、作業環境測定の実施を要しないこと。 作業期間が継続して省令において定められている測定間隔を上回る場合は、 実施を要すること。 (昭和52年3月24日付け基発第163号) 解体作業において測定が行われるケースは少ない。 51 ※厚生労働者パンフレット抜粋 52 5 皆さんにお願いしたいこと (1) 基本的ルールの遵守 (法令を理解し、遵守することは基本) (2) 工夫と改善 (リスクアセスメントで、より安全な作業に) (3) コミュニケーション (災害の芽を摘み取る) (4) 健康管理 (自分の体を大事に、治療より予防) 53 ご清聴ありがとうございました 54