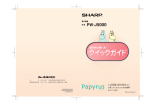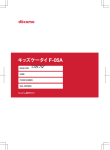Download JF日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック [第二版]
Transcript
JF日本語教育スタンダード 2010 利用者ガイドブック [第二版] JF Standard for Japanese-Language Education 2010 User’s Guide (Second Edition) JF 日本語教育スタンダード 2010 利用者ガイドブック [第二版] 国際交流基金(ジャパンファウンデーション) JF 日本語教育スタンダード2010 全体マップ 『JF 日本語教育スタンダード2010』では、JF 日本語教育スタンダードの概要や、簡単 な活用方法を知ることができます。 〈JF 日本語教育スタンダード2010〉 JF 日本語教育スタンダードの 全体像を知りたい 1. JF 日本語教育スタンダード を使う前に JF 日本語教育スタンダードを 使って何ができるか知りたい 2. JF 日本語教育スタンダード を使ってみる みんなの「Can-do」サイトを 3. みんなの「Can-do」サイト を使ってみる 使って何ができるか知りたい みんなの「Can-do」サイト(http://jfstandard.jp/cando) みんなの「Can-do」サイトは、日本語で何がどれだけできるかを「∼ができる」という 文で示した「Can-do」のデータベースです。コースデザイン、授業設計、教材開発など、 「Can-do」を使った日本語教育実践をサポートします。 ログイン Can-do を探す わたしのページ 自分が作った Can-do フォルダを編集し たり、新しい Can-do を作ったりできます。 ii 目的や対象者にあ わせて、必要とな る Can-do を 選ぶ ことができます。 JF 日本語教育スタンダードの、より詳しい活用方法を示したものが、『JF 日本語教育ス タンダード2010 利用者ガイドブック』です。 あわせて、みんなの「Can-do」サイトや JF 日本語教育スタンダードのホームページも ご利用ください。 JF 日本語教育スタンダード2010 〈利用者ガイドブック〉 JF 日本語教育スタンダード を活用するときに必要な知識 を得たい 知識編 1.1 JF スタンダードの木 話題について知識のな い聴衆に対しても、自 信を持ってはっきりと 複 雑な話 題について、 明確なきちんとした構 複 雑な内容 を口頭 発 表できる。 造 を 持 った プ レ ゼ ン 事前に用意されたプレ テーションができる。 ゼンテーションをはっ 自分の専門でよく知っ ている話 題について、 きりと行うことができ る。 事前に用意された簡単 1.2 6つのレベル 身 近な話 題について、 リハーサルをして、短 非常に短い、準備して 練習した言葉を読み上 なプレゼンテーション ができる。 い 基 本 的なプレゼン テーションができる。 げることができる。例 えば、話し手の紹介や 乾杯の発声など。 「Can-do」 1.3 1.4 ポートフォリオ JF 日本語教育スタンダードを どうやって活用すればいいのか、 詳しく知りたい 実践編 2.1 コースをデザインする 2.2 コースデザインに 「Can-do」を使う JF 日本語教育スタンダードの最新情報はホームページで確認することができます。 JF 日本語教育スタンダード(http://jfstandard.jp) 「活用事例」では、JF 日本語教育 スタンダードを実際に活用した 事例報告を充実させていきます。 iii JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック[第二版] 目 次 JF 日本語教育スタンダード2010全体マップ ............................. ii 知識編 1章 知識編 1.1 「JF スタンダードの木」を理解する ........................ 3 1.2 6つのレベルを理解する ......................................... 8 1.3 「Can-do」を理解する ........................................ 10 1.4 ポートフォリオを理解する .................................. 22 実践編 2.1 コースをデザインする ......................................... 37 実践編 2章 2.2 コースデザインに「Can-do」を使う .................. 49 (1)学習目標一覧と自己評価チェックリストを作る 49 (2)話す力を測るための評価基準と 評価シートを作る ............................................ 57 【JF スタンダードご利用にあたっての免責について】 ●国際交流基金は、JF スタンダードの内容の正確性の確保に努めています。また、掲載する文書・ 写真・イラストその他各種コンテンツ等については、慎重に作成しておりますが、当基金がこれら の完全性を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。 ● JF スタンダードを利用してコースデザインやカリキュラム作成、試験作成や試験を行った場合、 その正確性や有効性の責任はそれぞれの実施主体にあり、国際交流基金および欧州評議会は一切の 責任を負いません。以上の内容をご理解頂いた上、ご利用ください。 参考資料 参考資料 ....................................................................... 70 知識編 1章 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 知識編 1.1 「JF スタンダードの木」を理解する(1) JF スタンダードは、「相互理解のための日本語」を理念としています。相互理解のためには日本語を 使って何がどのようにできるかという「課題遂行能力」と、さまざまな文化に触れることでいかに視野 を広げ他者の文化を理解し尊重するかという「異文化理解能力」が必要であると考えます。この考え方 にもとづいて、各教育現場において学習者の「課題遂行能力」の向上を目指した教育実践を行いやすく ニケーション言語活動(communicative language activities)の関係を整理し、一本の木で表現しました。 その図を「JF スタンダードの木」(pp.6-7)と呼びます。 知識編 するために、CEFR のコミュニケーション言語能力(communicative language competences)とコミュ 木の根として表現され、言語によるコミュニケーションを支えるのが言語能力です。「JF スタンダー ドの木」では、言語能力の構成要素を例示しました。言語能力を基盤として、木の枝のように広がる おもな言語活動を例示しました。 「カテゴリー」と呼びます。言語能力と言語活動のカテゴリーは全部で53あります。 (1) コミュニケーション言語能力(communicative language competences)とコミュニケーション言語活動 (communicative language activities)の考え方や構成は CEFR に準じています。 3 J F スタンダードの木﹂を理解する 「JF スタンダードの木」のひとつひとつの根や枝で表された言語能力の構成要素とおもな言語活動を ﹁ のが言語活動です。実際の言語使用は多様で広がりのあるものですが、「JF スタンダードの木」では、 ■コミュニケーション言語能力(communicative language competences( )以下、言語能力) コミュニケーション言語能力(communicative language competences)をめぐっては、さまざま な考え方がありますが、「JF スタンダードの木」では、CEFR の考え方にもとづいて、言語構造的能 力(linguistic competences(2))、社会言語能力(sociolinguistic competences)、語用能力(pragmatic competences(3))の3つから構成されると考えます。 言語構造的能力(linguistic competences) 知識編 言語構造的能力(linguistic competences)とは、語彙、文法、発音、文字、表記などに関する能力で、 言語教育では古くから注目されてきた能力です。この能力を語彙能力、文法能力、意味的能力、音声 能力、正書法の能力、読字能力の6つでとらえます(4)。 社会言語能力(sociolinguistic competences) 社会言語能力(sociolinguistic competences)とは、相手との関係や場面に応じて、いろいろなルー ルを守って言語を適切に使用する能力です。 ﹁ スタンダードの木﹂を理解する J F 語用能力(pragmatic competences) 語用能力(pragmatic competences)は、ディスコース能力と機能的能力の2つでとらえます。ディ スコース能力とは、ディスコース(談話)を組み立てたりコントロールしたりする能力です。機能的 能力とは、コミュニケーションの中での言語使用の役割や目的(例:事実を報告する、説得するなど) を理解したうえで適切に使用できる能力です。 ■コミュニケーション言語活動(communicative language activities) (以下、言語活動) 言語を学習する場合も使用する場合も、言語能力は、実際の言語使用場面で言語活動として表れます。 その活動例を、読む・聞くなどの「受容的活動」(以下、受容)、一人で長く話す・書くなどの「産出活 動」 (以下、産出)、会話や手紙のやりとりなどの「相互行為活動」(以下、やりとり)の3つに分類し ました(5)。そして、受容 ・ 産出 ・ やりとり、それぞれの言語活動の例を、より詳しいカテゴリーに分類し その例を示しました。 さらに、受容・産出・やりとりに分類しにくい「メモやノートをとる」 「要約したり書き写したりする」 の2つの言語活動を、受容と産出の両者を仲介する言語活動の例として、 「テクストに関する言語活動」 (以下、テクスト)としました。 言語能力を 効果的に 使っ て 言語活動を 行う た め の「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 方略(communicative (以下、方略)の例についても、受容・産出・やりとりの3つの言語活動ごとに示しました。 strategies)」 方略は、言語能力と言語活動をつなぐ役割をしています。 (2) ‘linguistic competences’の日本語訳は、「言語構造的能力」「言語能力」「言語学的能力」などさまざまな 訳がありますが、 「JF スタンダードの木」では、「言語構造的能力」とします。 (3) ‘pragmatic competences’の日本語訳は、「語用能力」「語用論的能力」「言語運用能力」などまざまな訳 がありますが、 「JF スタンダードの木」では、「語用能力」とします。 (4) 「意味的能力」と「読字能力」については、能力として明記されていますが、現段階では 「Can-do」の記 述はありません。 (5) CEFR では、この3つの分類に加え、翻訳・通訳などの仲介活動の4つに分類しています。 4 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 教育現場では、 「JF スタンダードの木」のどの部分を学習目的とするかを考えることで、 目標をより明確にし、多様な学習者のニーズや学習成果をとらえやすくなります。 たとえば、海外で日本語を学びはじめた日本語を使う機会が少ない学習者でも、日本語 を使ってどんなことができるか・したいかを意識しながら学習を進めることができます。 学習者のニーズや目的によっては、枝や根の一部分を集中的に学習する必要がある場合も あるでしょう。 また、学習者の中には、個別の能力や知識は身に付けていても、実際に日本語を使用す 知識編 る機会が不足しているため、言語使用の文脈や状況に応じて個別の能力や知識を複合的に 組み合わせて課題を遂行することが難しい学習者もいるでしょう。その場合教師は、「JF スタンダードの木」を使って、すでに身に付けている能力や知識を確認して、それらを使っ てできる言語活動を具体的にイメージしながら、練習機会を多く提供するということもで きるでしょう。 ﹁ さらに、日本語で専門知識を学ぶ大学生に必要な日本語能力について考える場合など、 ターゲットとなる学習者に必要な具体的な言語活動とそれを支える言語能力を関連づけて J F スタンダードの木﹂を理解する 学習目標を設定することもできます。 このように、JF スタンダードは、「各教育現場が多様な学習者のニーズや学習環境に応 じて柔軟に活用できるツールであること」が大切であると考えています。 「JF スタンダードの木」の枝や根で示した言語能力と言語活動は、言語によるコミュニケーショ ンを網羅しようとしたものではなく、言語教育の現場で理解しやすく扱いやすくするために具 体例を示したにすぎません。各教育現場のニーズや学習環境に応じて、新しい枝や根を付け加 え新しいカテゴリーとしたり、不要だと思われる枝や根を取り除くこともあるでしょう。 また、学習者が言語をコミュニケーションのために使用する時、「JF スタンダードの木」で示 した言語に関係する能力だけでなく、学習者が経験を通して身に付けたさまざまな知識や技能、 言語以外の能力を複合的に組み合わせて課題を遂行することになります。それらの能力の日本 語教育での取り扱いについては、各教育現場の学習者のニーズや学習環境に応じて、柔軟に対 応する必要があります。 5 知識編 ﹁ スタンダードの木﹂を理解する J F 図 1-1 JF スタンダードの木 6 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 知識編 ﹁ スタンダードの木﹂を理解する J F 7 1.2 6つのレベルを理解する(1) JF スタンダードが学習者の日本語の熟達度の尺度として採用した CEFR の共通参照レベルについて 理解を深めます。 各教育現場において学習者の「課題遂行能力」の向上を目指した教育実践を行いやすくするために、 CEFR のコミュニケーション言語能力(communicative language competences)とコミュニケーショ 知識編 ン言語活動(communicative language activities)の関係を整理し、「JF スタンダードの木」で示した ことはすでに述べました。木のひとつひとつの枝や根で表された、言語能力の構成要素とおもな言語活 動の例をカテゴリーと呼び、日本語の熟達度を「~できる」という形式で示した文(「Can-do」)は、 これらのカテゴリーに分類し、カテゴリー内の「Can-do」は CEFR の6つのレベルに分けて提供して います。 言語熟達度は、 「A:基礎段階の言語使用者(Basic User) 」 、 「B:自立した言語使用者(Independent つのレベルを理解する 6 User)」、「C:熟達した言語使用者(Proficient User)」の3つの大きな段階に分かれています。そし て各段階がさらに2つに分かれ、全部で6つのレベル(A1、A2、B1、B2、C1、C2)となります。 言語熟達度の尺度である6つのレベルは等間隔ではなく、A2、B1、B2の幅は、A1、C1、C2よりも 図 1-2 「Can-do」の 6 レベル 話題について知識のな い聴衆に対しても、自 信を持ってはっきりと 複 雑な話 題について、 明確なきちんとした構 造 を 持 った プ レ ゼ ン 事前に用意されたプレ テーションができる。 ゼンテーションをはっ 自分の専門でよく知っ ている話 題について、 きりと行うことができ る。 事前に用意された簡単 身 近な話 題について、 リハーサルをして、短 非常に短い、準備して 練習した言葉を読み上 なプレゼンテーション ができる。 い 基 本 的なプレゼン テーションができる。 げることができる。例 えば、話し手の紹介や 乾杯の発声など。 (1) JF スタンダードの言語熟達度の尺度は CEFR の6つのレベルに準じています。 8 複 雑な内容 を口頭 発 表できる。 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 広いため、A2、B1、B2をそれぞれ A2.1/A2.2、B1.1/B1.2、B2.1/B2.2に分けて、全部で9つの レベルとすることもあります。図 1-2は、「講演やプレゼンテーションをする」という言語活動がレベ ルによってどうかわっていくのかを「Can-do」で示したものです。「Can-do」については、1.3で詳 しく説明します。 各レベルの「Can-do」からは、そのレベルの熟達度がどのようなものか、レベルが変わると何がで きるようになるか理解することができます。6レベルの大まかなレベルイメージをつかむときには、 CEFR の共通参照レベルの「全体的な尺度」を、学習者の技能別のレベルを確認するときには、CEFR の 知識編 「自己評価表」 (参考資料 1、pp.70-71)を使うと便利です(2)。 図 1-3 CEFR 共通参照レベル:全体的な尺度 つのレベルを理解する 6 仕事、学校、娯楽で普段出合うような身近な話題について、標準的な話し方であれば主要点を理解できる。 その言葉が話されている地域を旅行しているときに起こりそうな、たいていの事態に対処することができる。 身近で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結びつけられた、脈略のあるテクストを作ること ができる。経験、出来事、夢、希望、野心を説明し、意見や計画の理由、説明を短く述べることができる。 (2) JF ス タ ン ダ ー ド の「 み ん な の 「Can-do」 サ イ ト 」で は、CEFR の 共通参照レ ベ ル の「 全体的尺度」や 「自己評価表」の「Can-do」は、検索対象となっていません。この CEFR の共通参照レベルの「全体的尺度」 や「自己評価表」は、みんなの 「Can-do」 サイト < http://jfstandard.jp/cando/ >「サイトの使い方」の 「このサイトで使う用語について」の「レベルとは」からダウンロードできます。 9 1.3 「Can-do」を理解する 「Can-do」とは、言語の熟達度を「~ができる」という形式で示した文です。どのような文型や文法 を知っているか、単語や漢字をいくつ知っているかという熟達度のとらえ方に対して、「Can-do」は、 たとえば「好きか嫌いかを述べることができる」のように、言語の熟達のある段階でできる言語活動や 持っている言語能力の例を示し、目安とするものです。 知識編 JF スタンダードでは、言語によるコミュニケーションを「JF スタンダードの木」で示したように整理し、 熟達度を6レベルに分けています。「Can-do」は言語能力と言語活動の53のカテゴリーに分類され、 各レベルで何がどのくらいできるかを言葉で表現しています。「Can-do」を活用することによって、日 本語の熟達度を客観的に把握したり、今後の学習の目標を明確にしたりすることができます。また、他 の人や他の機関とも熟達度や目標を共有できるようになります。 ここでは、まず、 「Can-do」のレベル、種類、使い方などについての理解を深めてから、各現場に合っ ﹁ た 「Can-do」を作る方法を紹介します。 ﹂を理解する Can-do ■「Can-do」とは (1) 「Can-do」のレベル 言語熟達度の尺度は、低い方から高い方に向かって A1、A2、B1、B2、C1、C2の6つのレベル(1) となります。各レベルの「Can-do」を見ると、そのレベルがどのようなものか、レベルが変わると何 ができるようになるのか理解することができます。レベルの全体的な把握のためには、「全体的な尺度」 (p.9)や「自己評価表」 (参考資料 1、pp.70-71)にある「Can-do」が参考になりますが、ここでは、 1つの活動を取り上げて見てみましょう。 たとえば、図 1-4は、【F 講演やプレゼンテーションをする】という言語活動の「Can-do」の例ですが、 「Can-do」を読むとレベルが上がるにつれてどのような講演やプレゼンテーションができるようになる かがわかります。 (1) A2、B1、B2をそれぞれ A2.1/A2.2、B1.1/B1.2、B2.1/B2.2に分けて、全部で9つのレベルとすることも あります。 10 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 図 1-4 「Can-do」の 6 レベル(【F 講演やプレゼンテーションをする】) 話題について知識のない聴衆に対しても、自信を持ってはっきりと複雑な内容を口頭発表で C2 きる。聴衆の必要性に合わせて柔軟に話を構造化し、変えていくことができる。 難しい、あるいは敵意すら感じられる質問に対処することができる。 複雑な話題について、明確なきちんとした構造を持ったプレゼンテーションができる。補助 C1 事項、理由、関連事例を詳しく説明し、論点を展開し、立証できる。 聴衆からの不意の発言にも対応することができる。ほとんど苦労せずに自然に反応できる。 事前に用意されたプレゼンテーションをはっきりと行うことができる。ある見方に賛成、反 対の理由を挙げて、いくつかの選択肢の利点と不利な点を示すことができる。 知識編 B2 一連の質問に、ある程度流暢に、自然に対応ができる。話を聞く、あるいは話をする際に聴 衆にも自分にも余分な負荷をかけることはない。 自分の専門でよく知っている話題について、事前に用意された簡単なプレゼンテーションが B1 できる。ほとんどの場合、聴衆が難なく話についていける程度に、はっきりとしたプレゼンテー ションをすることができ、また要点をそこそこ正確に述べることができる。 質問には対応できるが、そのスピードが速い場合は、もう一度繰り返すことを頼むこともある。 話し終えた後から出される簡単な質問に答えることができる。 ﹂を理解する Can-do A1 身近な話題について、リハーサルをして、短い基本的なプレゼンテーションができる。 ﹁ A2 非常に短い、準備して練習した言葉を読み上げることができる。例えば、話し手の紹介や乾 杯の発声など。 (2) 「Can-do」の種類 「Can-do」は、「JF スタンダードの木」で示した言語能力と言語活動を例示的に記述したものです。 言語能力を例示する「能力 Can-do」と、言語活動を例示する「活動 Can-do」「テクスト Can-do」「方 略 Can-do」の4種類に分類されます。 ①言語能力を例示する「Can-do」 • 能力 Can-do は、「JF スタンダードの木」の根にある「Can-do」で、言語活動を行うために必要な言 語能力を例示したものです。言語構造的能力、社会言語能力、語用能力の3つに分かれます。 ②言語活動を例示する「Can-do」 • 活動 Can-do は、JF スタンダードの広がる木の枝にある「Can-do」で、実社会で行う具体的な言語 活動を例示したものです。受容・産出・やりとりの3つに分かれます。 • テクスト Can-do は、 「JF スタンダードの木」の受容と産出の枝の間とやりとりにある「Can-do」で、 ノート取りや要約など、まとめたり言いかえたりする活動を例示したものです。受容と産出の両者を 仲介する言語活動で、受容・産出・やりとりに分類しにくいものです。 • 方略 Can-do は、「JF スタンダードの木」の受容・産出・やりとりの枝の付け根にある「Can-do」 で、言語活動を効果的に行うために言語能力をどのように活用したらよいか方略を例示したものです。 受容・産出・やりとりの3つに分かれます。 11 (3) 「Can-do」のカテゴリー (2)で述べた4種類の「Can-do」は、それぞれ、さらに細かいカテゴリーに分類されています。 たとえば、活動 Can-do の産出に関わるものには、前述の【F 講演やプレゼンテーションをする】のほ かに、 【C 経験や物語を語る】 【I レポートや記事を書く】など、受容に関わるものには、【4 指示やア ナウンスを聞く】【; 説明を読む】など、やりとりに関わるものには、【N インフォーマルな場面でや りとりをする】【Q 情報交換する】などのカテゴリーがあります。 そして、同じやりとりの活動でも、カテゴリーによって「Can-do」の内容は異なります。たとえば、 知識編 【N インフォーマルな場面でやりとりをする】と【Q 情報交換する】の B1の「Can-do」を見てみましょう。 【N インフォーマルな場面でやりとりをする】 【Q 情報交換する】 • どこに行くか、何をしたいか、イベントをど • 事実に 基づ く 簡単な 情報を 見つ け 出し、人に のように準備するか(例:外出)などの、実 際的な 問題や 問い の 解決に 関し て、自分の 意 伝えることができる • 詳細な説明を求め、理解できる ﹁ 見や反応を相手に理解させることができる ﹂を理解する Can-do 【N インフォーマルな場面でやりとりをする】の場合は自分の意見や賛成・反対についてやりとりを するのに対し、【Q 情報交換する】では事実に基づいた情報をやりとりします。 能力 Can-do、テクスト Can-do、方略 Can-do も細かいカテゴリーに分かれています。それぞれのカ テゴリーがどのような言語活動や言語能力を表しているかは、「言語能力と言語活動のカテゴリー一覧」 (参考資料 2、pp.72-73)を参照してください。また、各カテゴリーの「Can-do」を読むことで、カ テゴリーの内容についての理解が深まります。 (4) 「Can-do」の記述内容 「Can-do」を読むことによって、記述されているカテゴリーの特徴だけでなく、熟達度が上がるにつ れて何がどのように変わるのかを理解することができます。能力 Can-do の記述内容については、「能 力 Can-do 一覧」(参考資料 4、pp.80-84)を参照してください。 活動 Can-do の記述内容を見ると、以下のような構造を持っていることがわかります。活動 Can-do の構造にもとづいて 「Can-do」 を理解することで、各カテゴリーとレベルの記述の特徴がとらえやす くなります。 【活動 Can-do の構造】 「Can-do」= 条件 + 話題・場面 + 対象 + 行動 12 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 活動 Can-do を構成している条件、話題・場面、対象、行動は、それぞれ次のようなものです。 条件:ゆっくり話すなどの相手側の配慮、事前準備の有無など、実現のための条件 話題 ・ 場面:日常的な話題、会議の場など、取り上げられる話題や、言語活動が行われる場面 対象:手紙や記事、ニュースや講義など、聞いたり、読んだり、話したり、書いたりするもの 行動:聞いて理解する、読んで理解する、話す、書く、会話するなど、実際の言語活動 ここでは、A2と B1の受容【⑪テレビや映画を見る】に関する「Can-do」を見てみましょう。 B1 + 本人の関心事であ 話し方が比較的 る話題について ゆっくりと、はっ きりとしていれば 話題・場面 + 対象 行動 内容をおおかた インタビュー、短 い講演、ニュース + レポートなど + + 知識編 条件 理解できる + 多くのテレビ番組 ﹁ の 映像と実況説明が ほとんど重なるな 出来事や事故を + 伝える テレビのニュース + 番組の 要点がわかる + らば たとえば、話題・場面と対象を見てみると、A2では、 「出来事や事故を伝える」 「テレビのニュース番組」 が理解できる段階であるのに対して、B1は「本人の関心事である話題」に関する「インタビュー、短 い講演、ニュースレポート」などの「多くのテレビ番組」が理解できる段階であるということがわかり ます。 この4つの要素ごとの特徴的な表現を見ることによって、活動 Can-do のレベルを理解することがで きます。全レベルの特徴については、「活動 Can-do のレベル別特徴一覧」(参考資料 3、pp.74-79) を参照してください。 (5) 「Can-do」間のつながり 「JF スタンダードの木」で表したように、言語の熟達を示すうえで、能力 Can-do、活動 Can-do、テ クスト Can-do、方略 Can-do は、互いに関連しあったものです。 たとえば、先ほどの【F 講演やプレゼンテーションをする】という言語活動を考えてみると、まず、 言語能力としては、語彙や文法に関する能力やディスコース能力などが必要となるでしょう。また、表 現方法を考える、自分の発話をモニターする、などの方略を使うことによって、言語活動をより効果的 に行うことができます。 次の図 1-5は、B1レベルの【F 講演やプレゼンテーションをする】という言語活動において関連し ている「Can-do」を示したものです。この場合、活動 Can-do、方略 Can-do、能力 Can-do の3種類の 「Can-do」が関連しています。また、異なる言語活動の例として、講義を聞きながらノートを取るといっ 13 ﹂を理解する Can-do A2 図 1-5 「Can-do」のつながり Can-do 自分の 専門で よ く 知っ て い る 話題に つ い て、事前に 用意さ れ た 簡単な プ 知識編 Can-do レゼンテーションができる。 【F 講演やプレゼンテーションをする】 伝えたいことの要点を伝達する仕方を 考えることができる。その際、使える 言語能力を 総動員し て、表現の た め の 手段が思い出せる、あるいは見つかる 範囲内にメッセージの内容を限定する。 【W 表現方法を考える】 ﹁ ﹂を理解する Can-do 家族、趣味や関心、仕事、旅 行、時事問題など、本人の日 常生活に関わる大部分の話題 事柄を直線的に並べていって、 について、多少間接的な表現 比較的流暢に、簡単な語りや記 を使ってでも、自分の述べた いことを述べられるだけの語 彙を持っている。 【b 使用語彙領域】 Can-do 述ができる。 【j 話題の展開】 た言語活動の場合には、まとめたり言いかえたりするテクスト Can-do も関連する「Can-do」となります。 このように、言語活動は、その言語活動の内容によって、必要な言語能力やその能力を効果的に使お うとする方略やテクストが変わります。つまり、言語活動を、言語能力、方略、テクストなど異なる 「Can-do」の動的な組み合わせで考えることができます。また、あるレベルの言語能力や方略があると どのような言語活動ができるのかを考えることもできるでしょう。 14 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック (6) 「Can-do」を使う 「Can-do」は、教育現場で学習目標の設定と学習成果の評価に利用できます。 ①学習目標の設定に利用する 相互理解のために必要なものの1つとして、言語を使って何がどのようにできるかという課題遂行の 能力があります。具体的な言語活動を例示する活動 Can-do は、この課題遂行能力の育成を目指した学 習目標の設定に利用することができます。目標設定にはどの種類の「Can-do」も利用できますが、特 かりやすく、教師にとっては授業活動をイメージしやすい目標になります。 ②学習成果の評価に利用する 知識編 に具体的な実社会での言語活動を記述した活動 Can-do は、学習者や言語教育を専門としない人にもわ 学習成果の評価には、能力 Can-do のカテゴリーを参考に評価の観点を設定することができます。能 力 Can-do は学習目標の達成度を測る評価基準や評価シートの作成にも利用できます。そのほかにも、 るか、何ができるようになりたいか、あるいは、授業後に何ができるようになったかなどを見ることが できます。 コースの目標、評価への活用方法については、2章で詳しく扱います。 (7) 「Can-do」を使うときの留意点 このように「Can-do」を教育現場で利用することで、日本語の熟達度を客観的に把握し、目標を明 確にし、他の人や他の機関とも熟達度や目標を共有できるようになりますが、「Can-do」を利用するに あたって、留意すべき点が2つあります。 ① 「Can-do」 のほかに必要なもの 「Can-do」 だけでは目標設定や評価は行えません。各現場で、実際の教育活動を行うために必要な言 語材料(語彙や文法項目などのリスト)を準備する必要があります。さらに、専門知識や学習能力など、 現時点では「Can-do」で記述されていない能力などについても、各教育現場の学習者のニーズや目的 に応じて検討を行うことが必要となるでしょう。 ②自分の現場に合った 「Can-do」 を作る 「Can-do」は、あくまでも言語活動と言語能力の例示であり、すべてを網羅したものではありません。 言語能力や言語活動のカテゴリーも、網羅的なものではありません。したがって、各教育現場では、 言語能力や言語活動のカテゴリーや、すでにある「Can-do」を参考にしながら、自分の現場に合った 「Can-do」を新たに作っていく必要があります。 15 ﹂を理解する Can-do る自己評価チェックリストに利用することができます。これにより、教師や学習者は現段階で何ができ ﹁ 教師だけでなく学習者自身が目標と評価を意識できるように、「Can-do」をコースの前後などに実施す (8)JF Can-do JF スタンダードの「Can-do」は、CEFR が提供する「Can-do」(以下、CEFR Can-do)と、国際交 流基金が独自に作成した「Can-do」(以下、JF Can-do)です(2)。JF Can-do は、日本語の使用場面を 想定し、日本語での具体的な言語活動を例示した「Can-do」です。活動 Can-do を各カテゴリーに分 類しているだけでなく、トピックを付与することで言語活動の場面を具体化し、「Can-do」の記述から 言語活動がよりイメージしやすくなっています。そのため、JF Can-do は抽象的な CEFR Can-do に比 べ日本語教育の現場で使いやすい「Can-do」となっています。付与したのは以下の15のトピックです。 知識編 「自分と家族」「住まいと住環境」「自由時間と娯楽」「生活と人生」「仕事と職業」 「旅行と交通」「健康」「買い物」 「食生活」「自然と環境」 「人との関係」「学校と教育」「言語と文化」「社会」「科学技術」 「JF スタンダード2010」の JF Can-do は A1から B2までの活動 Can-do があります。 ﹁ ﹂を理解する Can-do (2) CEFR Can-do と JF Can-do の一覧は、JF スタンダードのウェブサイト < http://jfstandard.jp> からダウン ロードできます。 16 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック ■各現場で MY Can-do を作る (1)目標設定のための活動 Can-do 「みんなの「Can-do」サイト」では、CEFR Can-do と JF Can-do を提供しています。これらの「Can-do」 は各教育現場でそのまま利用できますが、各現場に合った新しい「Can-do」を作ることもできます。 利用者が各現場で新しく独自に作成した「Can-do」を MY Can-do と呼びます。MY Can-do を作成す ることで、多様な教育現場の目標設定が柔軟に行えます。 Can-do は、一般によく使われる目標記述や他の「Can-do」とどこが違うのでしょうか。 たとえば、教育現場に次のような目標があるとします。 知識編 目標設定の た め に MY Can-do を 作る に は、活動 Can-do に つ い て 理解す る こ と が 必要で す。活動 a 異文化体験の話を読んで、自分の異文化体験も話すことができる。 どれもよく目にする目標記述の例ですが、活動 Can-do として使うためには、いくつかの点で改良の 余地があります。 a の例は実社会で行う言語活動を記述していますが、b や c の例は、授業活動としてできることを目 標にしており、学習の結果として何ができるかがわかりにくいものとなっています。特に、c の例のよ うな文法項目の記述は、教室外の社会では理解しにくいものです。b の例ではその授業活動が実社会で どのような言語活動になるのかを、c の例ではその文法項目を使うことによりどのような言語活動が可 能になるのかを考えれば、活動 Can-do として目標を作り直すことができるでしょう。 a の例は、活動自体は問題ありませんが、1つの記述の中に「読む」と「話す」という2つの活動が 含まれていると、それぞれの活動の比重を考えたり、目標の達成度を評価したりするときに使いにくく なります。これは、2つの「Can-do」に分けておくと便利です。 そして、どの例も、「どのくらいできるか」という到達度については記述されていません。「このクラ スならこの程度のレベル」という関係者内の暗黙の了解で省略される場合もありますが、やはり誰が見 てもわかることを目指すのであれば、「短い簡単な言葉で(話すことができる)」 「詳しく(話すことが できる) 」 などの共通の言語熟達度の尺度にもとづいたレベルの記述が必要となります。 このように、すでに現場にある目標記述を見直し、実社会の言語活動とつながる記述に書きかえたり、 新しく MY Can-do を作ったりするときには、p.12の「(4)「Can-do」の記述内容」で述べたような 活動 Can-do の構造を知っていると便利です。条件、話題・場面、対象、行動という活動 Can-do の4 つの要素を確認することによって、目標が明確になり、話題や場面などが現場や学習者の状況に合い、 学習者に合ったレベルを示した 「Can-do」 を作ることができます。 17 ﹂を理解する Can-do c「V たことがある」と形容詞の過去形が使えるようになる。 ﹁ b レストランでの会話のテープを聞き、内容を理解することができる。 (2)目標設定のために MY Can-do を作る それでは、活動 Can-do の構造を使って、新しい MY Can-do の作成と、すでに現場にある目標の見 直しの2つの方法を具体的な例にそって見ていきましょう。 全体の流れは、図 1-6のようになります。 知識編 図 1-6 新しい活動 Can-do 作成の流れ コースや授業の具体的な目標はすでにありますか? はい 1.どんなコースにしたいかイメージする 1.コースの概要を確認する ﹁ いいえ ﹂を理解する Can-do 作成方法 1 作成方法 2 「みんなの「Can-do」サイト」の「Can-do」 を使って MY Can-do を作成する す で に あ る 目標を 見直し て、MY Can-do を 作成する 2. 「みんなの 「Can-do」 サイト」を利 用して参考になりそうな「Can-do」 を探す 2.言語活動を確認する 3.選んだ「Can-do」が自分の教育現場 に合うかどうか考える 3.言語活動のカテゴリーを確認する 4.自分の教育現場に合うように書きか える 4.レベルを確認する MY Can-do の完成! 18 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 作成方法 1 「みんなの 「Can-do」 サイト」を使って、MY Can-do を作ってみる 新しいコースや授業の目標設定のために、MY Can-do を作成する場合の流れを見てみましょう。 1.どんなコースにしたいかイメージする たとえばこんなコースの場合… 「対象者は韓国人大学生で、レベルは中~上級程度。コースの全体的な目標として、 口頭能力(特にプレゼンテーション能力)を伸ばしたい」 4.自分の教育現場に合うように書きかえる ☝ MY Can-do 作成における確認ポイント 活動 Can-do = 条件 + 話題・場面 + 対象 + 行動 対象 + 行動 … 活動やカテゴリーはコースや授業でやりたいものになっていますか? やりたいのはプレゼンテーションですか? 友人との会話ですか? 話題・場面 … 学習者のニーズに合っていますか? 学習者の、実際の社会生活の中で起こりそうなことですか? 条件 、「Can do」全体…レベルは難しすぎたり、簡単すぎたりしていませんか? MY Can-do の完成! たとえばこんな MY Can-do を作ってみました! 日本人が集まる韓国文化研究会で、あらかじめ準備してあれば、韓国事情(地理・ 歴史・文化など)について、まとまりのある簡単なプレゼンテーションをすること ができる。 レベルやカテゴリーは参考にした「Can-do」のままにし、書きかえたのは以下の点です。 ※「自分の国について学ぶ集まり」を実際にある「韓国文化研究会」にし、具体的に 場面が想像しやすくしました。 ※トピックを「韓国事情(地理・歴史・文化など)」とより具体的にし、何について話 すのかイメージしやすくしました。 19 ﹂を理解する Can-do 3.選んだ「Can-do」が自分の教育現場に合うかどうか考える 選んだ 「Can-do」に記述されている話題や言語活動が、教育現場の状況に合っ ているかどうか考えます。合っている場合は、そのまま使うことができますが、 合っていない場合は、教育現場の状況に合うように各自で書きかえる必要があ ります。 ここでは、書きかえる場合を想定して、次のステップに進みましょう。 ﹁ 「Can-do」の探し方について知りたい方は、『JF 日本語教育スタンダード2010』の 「3 みんなの 「Can-do」 サイトを使ってみる」を参照してください。 知識編 2. 「みんなの 「Can-do」 サイト」を利用して参考になりそうな「Can-do」を探す たとえばこんな「Can-do」があります! 自分の国について学ぶ集まりで、あらかじめ準備してあれば、自分の国や町 の様子などについて、まとまりのある簡単なプレゼンテーションをすること ができる。 レベル :B1 カテゴリー:産出【F 講演やプレゼンテーションをする】 トピック :言語と文化 作成方法 2 すでにある目標を見直してみる すでに教育現場で使っている目標を見直す場合の流れを見てみましょう。 1.コースの概要を確認する たとえばこんなコースの場合… 「対象者は高校生で、レベルは初級終了~中級程度。コースの全体的な目標とし て、口頭能力(特にプレゼンテーション能力)を伸ばしたい」 知識編 すでにある目標を見直す たとえばこんな目標記述の場合… (例)異文化体験の話を読んで、自分の異文化体験も話すことができる。 2.言語活動を確認する ﹁ 活動 Can-do =条件+話題・場面+ 対象 + 行動 ﹂を理解する Can-do まず、 対象 と 行動 に着目し、目標とする活動が受容、産出、やりとりの うちのどれなのかを明確にしましょう。1つの「Can-do」には基本的に1つの 言語活動を記述します。そうすると、評価方法についても考えやすくなり、他 の「Can-do」と組み合わせて使うこともできます。 たとえば、上の(例)の目標記述は、次の2 つに分けられます。 (a)異文化体験の話を読んで、理解することができる。 (b)自分の異文化体験を話すことができる。 (a)の言語活動は、受容(読む)です。 (b)は、一人で話す産出の場合と、 他の人と会話をするやりとりの場合が考えられます。ここでは、 (b)の言語活 動を選んで次のステップに進みましょう。 3.言語活動のカテゴリーを確認する 活動 Can-do =条件+ 話題・場面 + 対象 + 行動 「話す」という言語活動は、その状況や場面がいろいろ考えられます。(b) の言語活動が産出なのかやりとりなのかを明確にするために、 場面 や状況を考 えてみましょう。 • 一人の語り? 他の人とのやりとり? • 相手は? 一人? 大勢? • どんな場面? 友人との打ち解けた会話? フォーマルな会場? ここでは、ステップ1 で出したコースの大きな目標に合わせて、大勢の前で 準備したスピーチをするような場面を想定しましょう。その場合、カテゴリー は産出(話す)の【F 講演やプレゼンテーションをする】になります。 これで、言語活動のカテゴリーが決まり、言語活動が明確になりました。 クラスメートの前で、自分の異文化体験についてのスピーチをすることがで きる。 20 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 4.レベルを確認する 活動 Can-do = 条件 + 話題・場面 + 対象 + 行動 ステップ3 で、活動は具体的になりましたが、このままでは、目標とする熟達度、 「どのぐらいできるのか」が明確ではありません。 レベルは、該当するレベルの特徴的な表現を「Can-do」の構造の4 つの要素 に入れることによって表わすことができます。たとえば、A2と B1を参考にす ると、産出(話す)に特徴的な表現として、次のような表現があります。 対象 行動 • 聞き手が集中し て聞いてくれれ ば、練習した上 で • 家 族、 住 居 環 境、学歴、現在 やごく最近まで していた仕事に ついて • 自分の毎日の生 活に直接関連の ある話題につい て • 短いプレゼン テーション • 簡単な言葉で述 べることができ る • 要点を短く述べ ることができる • アクセントとイ ントネーション にはかなり耳慣 れない部分もあ るが • 自分の関心のあ るさまざまな話 題について • ある程度の長さ の、簡単な記述 やプレゼンテー ション • 順序だてて詳細 に述べることが できる • 事実を述べ、理 由を説明するこ とができる A2 ここでは、A2を目標のレベルとして、「聞き手が集中して聞いてくれれば、練習し た上で」と「簡単な言葉で(述べることができる)」という表現を使います。 レベルの記述については、 「レベル別特徴一覧」 (参考資料 3) 、 「みんなの「Can-do」サイト」を参考にしてください。 MY Can-do の完成! すでにあった目標を見直して、書きかえてみたら、たとえばこんな MY Can-do になり ました! 聞き手が集中して聞いてくれれば、練習した上で、クラスメートの前で、自分 の異文化体験について、簡単な言葉でスピーチをすることができる。 この MY Can-do のレベル、カテゴリー、トピックは、以下のとおりです。 レベル :A2 カテゴリー:産出【F 講演やプレゼンテーションをする】 トピック :言語と文化 以上、新しい活動 Can-do を作成したり、すでにある目標記述を見直したりする方法を紹介しました。 みなさんも、これらを参考にして、今ある目標を見直したり、MY Can-do を作ったりしてみてください。 そして、作成した MY Can-do を、コースの目標設定や自己評価チェックリスト作成などに活用してみ てください。 21 ﹂を理解する Can-do B1 ﹁ 話題・場面 知識編 条件 1.4 ポートフォリオを理解する ■ポートフォリオとは JF スタンダードでは、「相互理解のための日本語」を理念としています。相互理解のためには「課題 遂行能力」と「異文化理解能力」が必要です。ポートフォリオとは、この2つの能力を育成するために、 知識編 学習者一人一人が学習過程を記録し、保存するものです。学習者は、日本語の熟達度を自己評価し、自 分の言語的・文化的体験を記録します。学習過程を記録し、ふり返ることで学習成果の評価のツールと して使うことができます。 ■ポートフォリオの効果 ポートフォリオを理解する ポートフォリオには、次のような効果があります。 • 教師と学習者が学習目標と学習の過程を共有できます。 • 学習者が日本語能力を自己評価したり、体験を記録したりすることによって、自律的学習能力や、学 習の動機づけを高めることができます。 • 日本語能力だけでなく、学習者が教室の中や外で学んださまざまな知識や技能の学習成果の評価を行 うことができます。 • 学習者が他の教育機関に移動したときにそれまでの学習成果を正確に伝えることができます。 ■ポートフォリオの構成 ポートフォリオを評価のツールとして教育現場で活用するためには、学習者が自分の学習過程を記録 し保存しやすい構成や形式で提供し、ふり返りやすくすることが大切です。そこで、JF スタンダード では、ポートフォリオを、次のような「評価表」「言語的・文化的体験の記録」「学習の成果」の3つの 構成要素で考えます(1)。 (1)JF スタンダードでは、CEFR の理念を教育現場で実現するための道具であるヨーロッパ言語ポートフォリ オ(European Language Portfolio)を参考にし、この3つの要素を考えました。ヨーロッパ言語ポートフォ リオについては、 『JF 日本語教育スタンダード試行版』(2009:68~91)をご参照ください。 22 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 図 1-7 JF スタンダードのポートフォリオの構成 (1)評価表 (2)言語的・ 文化的体験の記録 言語的・ 文化的 体験と学び 評価基準 評価シート 学習計画と ふり返り 成果物一覧 作文・ レポート 発表原稿など 知識編 自己評価 チェック リスト (3)学習の成果 プロジェクト の成果 各教育現場では、学習者のニーズや目的に応じて、これら3つの構成要素を組み合わせて、要素間の ポートフォリオを理解する つながりを意識しながら、独自のポートフォリオをデザインします。各現場で使いやすいように、ファ イルのし方を工夫したり、新しい要素を追加することもできます。 ■ポートフォリオに入れるもの ポートフォリオの3つの構成要素として、具体的にどのようなものを入れたらよいか、見ていきましょう。 (1)評価表 (2)言語的・文化的体験の記録 (3)学習の成果 評価表には、「Can-do」を利 用して教師が作成した「自己評価チェックリスト」や「評価基準」 「評価シート」などを入れます。 ①自己評価チェックリスト 【例 1 p.27】 自己評価チェックリストは、学習者が自分の日本語の熟達度を、コースのはじめと終わりや、コー スの途中で確認できるようにしたものです。 ②学習活動の評価基準や評価シート 【例 5 p.32】【例 6 p.33】 話す、書くなどの能力を評価するための、教師が作った評価基準と、評価活動の際に記入した 「口 頭発表の評価シート」や「作文活動の評価シート」などをポートフォリオに入れます。評価シー トは、教師からの評価シートだけでなく、学習者の自己評価やクラスメートからの他者評価の シートなども含みます。 23 (1)評価表 (2)言語的・文化的体験の記録 (3)学習の成果 言語的・文化的体験の記録には、学習者自身の言語的・文化的体験やその体験を通じて考えたこ とや感じたことを書いたシートや、学習者自身の学習計画や学習をふり返るためのシートを入れま す。各教育現場の環境やレベルによって、学習者が母語で書く場合も、日本語で書く場合もあるで しょう。 知識編 ①言語的・文化的体験と学び 【例 2 p.28】 言語的・文化的体験を記録することによって、学習者は自分と異なる言語や文化に対する意識 を高めることができます。それが、複合的な視野を持ったり、自文化について新しい視点や態 度を得ることにつながります。日本語を使う機会が少ない海外の場合でも、日本語で書かれた マンガを読む、インターネットで日本語の記事を読むなど、間接的な体験について記録するこ とができます。 ポートフォリオを理解する ②学習計画とふり返り 【例 3 p.29】 言語を使ってコミュニケーション上の課題を遂行するためには、文化知識、専門知識、価値観 や美意識、問題解決の方法など、言語以外のさまざまな能力や知識が必要となります。コース を通して、学習者が自分のニーズや興味に応じて目標を立て、実行し、結果をふり返る機会を 持つことで、そのような能力や知識についても自分で学び続けることができる学習者を育成す ることにつながります。 (1)評価表 (2)言語的・文化的体験の記録 (3)学習の成果 コースの目標や自己目標にそって学習者が集めた、作文・スピーチなどの音声資料・テスト・プ ロジェクトの成果物などの、学習の成果を入れます。作文の場合は、授業で書いたものすべて(書 くためのメモ、最初に書いた作文、書き直した作文など)を入れる場合も、たくさん書いた作文の 中で、自信作を学習者が選んで入れる場合もあります。このように集めた学習の成果は次の学習の ための素材にもなります。「成果物一覧」のような目次をつけると、学習の成果を分類し整理する ために効果的です。 【例 4 p.30】 ■ポートフォリオを使うときの留意点 このように、ポートフォリオは、学習者が日本語の熟達度を自己評価し、自分の言語的・文化的体験 を記録しふり返ることで、学習者の「課題遂行能力」と「異文化理解能力」の2つの能力を育成し、学 習成果の評価のツールとして効果的に使うことができます。ここでは、ポートフォリオを教育目的で活 用するときの留意点を整理しておきます。 • 対象者の年齢、教育目的や目標に合わせて柔軟にデザインします。構成要素のつながりを意識して 24 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 全体構成を考え、各現場で使いやすいようにファイルのし方を工夫します。 • 学習活動の評価基準は、教師間で十分に検討し、くり返し使って改善することで、妥当性と信頼性を 高めていくことができます。 • 学習成果についてのふり返りは、学習者自身の自主性にまかせるだけではなく、コース内の活動とし て組み込みます。教師やクラスメートと一緒にふり返る機会を設けることで、継続的に学習者の自律 的な学習能力を育成できるようにします。 国際交流基金関西国際センターで行われた大学生のための訪日研修(以下、大学生研修)と、国際交 流基金日本語国際センターで行われた外国人日本語教師のための訪日研修(以下、教師研修)の2つの 知識編 ■ポートフォリオの具体例 研修で実際に使ったポートフォリオの例を見てみましょう。 ●学習者数 海外の大学で日本語を学ぶ学習者を対象とした訪日研修 :20名~38名 ●日本語能力 :A2,B1,B2 ●コース期間 :6週間 ●担当した教師数:7名~11名 ●研修目的 :日本語学習および日本文化・社会理解を深めるための機会を提供 ●研修目標 短期の訪日機会を最大限に活かすため、文法や漢字などの項目学習は行わず、以下 の3点を目標とし、大学生との交流会や小学校訪問、ホームビジットなどの文化体 験や交流といった活動を軸として日本語や日本文化・社会を学び、帰国後の継続学 習へつなげることを目指す。 ①学習してきた日本語を使う ②日本語を体験し理解する ③これからの日本語学習に役立つ発見をする ●ポートフォリオ活用の目的 体験や交流活動を中心としたコースにおける、学習者の主体的な取り組みを促す自 律学習支援のために活用。 25 ポートフォリオを理解する 関西国際センター大学生研修「自律学習支援」のためのポートフォリオ活用 それでは、大学生研修で使ったポートフォリオの中から、(1)~(3)の構成要素ごとに入れたも のの実例を見てみましょう。 (1)評価表に入れたもの 「自己評価チェックシート」【例 1 p.27】 (2)言語的・文化的体験の記録に入れたもの 「研修活動の記録」【例 2 p.28】 「この研修での自己目標と自己評価」【例 3 p.29】 (3)学習の成果に入れたもの 知識編 ポートフォリオを理解する 26 「スピーチ原稿」【例 4 p.30】「日本理解科目まとめレポート」など (1)評価表 (2)言語的・ 文化的体験の記録 例1 自己評価 チェックリスト 例2 研修活動の記録 例3 この研修での 自己目標と自己評価 (3)学習の成果 例4 スピーチ原稿 日本理解科目 まとめレポート JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック (1)評価表に入れたもの 【例 1 自己評価チェックリスト】 研修中に行われた日本語使用を意識的にとらえられるように作成しました。このコースでは、それぞ れの国に帰ってからも学習を継続できるように自己評価は最後に行い、次の目標を立てることを促しま した。 じ こ ひょう か No. 名前 自己評価チェックリスト インタビュー インタビュー じゅん び 準備 A2 ひつ よう 1 かん たん B1 しつ もん ぶん つく なが インタビューに必要な簡単な質問文が作れる。 B2 てき せつ しつ もん ぶん つく ひつ よう しつ もん ぶん しつ もん あい て はな かく にん じゅん び おこ こた あ つぎ しつ 準備してインタビューを行い、答えに合わせて次の質 もん 確認できる。 おも しろ こた インタビューをなめらかにおこなえる。面白い答えを と あ よう い しつ もん きゅう きょ か 取り上げて、用意した質問を急遽変えるなどしてさら 問ができる。 きょう み う 3 4 き あい て しめ てき せつ う かい わ はこ ぶ こた ひ だ てき せつ う あい て 自然に適切なあいづちを打って、会話をスムーズに運 バリエーションのあるあいづちを適切に打ち、相手の できる。 ぶことができる。 話を引き出すことができる。 インタビューをしながら、キーワードが少しメモできる。 インタビューをしながら、キーポイントがメモできる。 あと じ ぶん はなし み ひ だ じゅう よう てん と インタビューの重要な点をノートに取ることができる。 と ひょう げん き り かい インタビューのテープを聞いて、キーワード、表現、 インタビューのテープを聞いて、キーポイントを理解し、 みじか みじか ぶん ぬ だ か 短い文を抜き出して書ける。 けっ か だん ぺん てき じょう ほう よう やく かん たん はっ ぴょう げん こう か じょう ほう あ はっ ぴょう げん こう き ひつ よう じょう ほう ばっ すい インタビューのテープを聞いて、必要な情報を抜粋し、 よう やく 短い断片的な情報を要約することができる。 要約することができる。 か 情報を集めてまとめた発表原稿を書くことができる。 さま ざま あつ じょう ほう ぎ ろん じゅう よう 様々なところから集めた情報や議論をまとめ、重要な てん とができる。 きょうちょう かん れん しょう さい ほ そく くわ 点を強調したり、関連する詳細な補足を加えたりした はっ ぴょう げん こう か 発表原稿を書くことができる。 はっ ぴょう 7 クラスメート さ ぎょう との作業 き ほん てき し かく し りょう 発表のための基本的な視覚資料(PPT など)が作れる。 じょう ほう 11 12 き つぎ クラスメートから簡単な情報を聞いたり、次にするこ はな し かく し りょう はっ ぴょう 発表のためのわかりやすく要点をまとめた視覚資料 い けん すす みじか はっ ぴょう じゅん び けっ か はっ ぴょう わかりやすくある程度正確に要点が述べられる。 てき ど せい かく かえ たす 発表の後、時々質問を繰り返してもらったり、助けて かん たん しつ もん こた もらわなければならないが、簡単な質問に答えられる。 はっ びょう ほ そく じょう ほう しめ こう か てき つく の うなが さ ぎょう さき クラスメートに意見を述べるように促して、作業を先 準備すればインタビュー結果について発表ができる。 ほか てん こう けん に進めることに貢献できる。 けっ か く じゅう よう い けん クラスメートの意見にコメントができる。 練習すればインタビューの結果について短い発表がで とき どき しつ もん そ し かく し りょう な視覚資料(PPT など)が作れる。 あ あと はっ てん 発表の展開に沿って重要な点や補足情報を示す効果的 つく きる。 はっ ぴょう 10 はっ ぴょう 発表 よう てん とを話し合ったりできる。 れん しゅう 9 はっ ぴょう (PPT など)が作れる。 かん たん 8 つく わ だい なに はっ ぴょう あと しつ もん よう てん の こた はや か ほか はっ ぴょう よう てん り かい 他のグループの発表の要点が理解できる。 れん しゅう 練習すれば、準備したとおりに司会ができる。 もん だい しょう てん はっ てん はっ びょう あ はっ ぴょう あと しつ もん たい じゅん び りゅうちょう たい おう ほか はっ ぴょう すべ り かい 他のグループの発表がほぼ全て理解できる。 し かい ば 練習すれば、だいたい問題なく司会ができる。その場 おう しょう さい に自然に対応ができる。 れん しゅう し かい り ろん てき てん 発表の後の質問に対して、準備していなくても、流暢 し ぜん は繰り返してもらわなければならない。 他のグループの発表の話題が何かわかる。 じゅん び じゅう よう できる。重要な点や詳細に焦点が当てられる。 発表の後の質問に答えられるが、スピードが速いとき く けっ か インタビュー結果について、論理的に展開した発表が たい しょ はっ ぴょう てき ぎ くわ めい かい りゅうちょう 発表について適宜コメントを加えながら、明快に流暢 し かい に応じて対処できる。 に司会ができる。 スピーチ み ぢか わ だい かん たん みじ か 身近な話題について、簡単で短いスピーチを書くこと 13 きょう み わ だい か 興味のある話題について、まとまったスピーチが書ける。 きょう み ぶん や さま ざま わ だい めい りょう くわ 興味のある分野の様々な話題について、明瞭に詳しく、 じょう ほう ができる。 ぎ ろん もと じ ぶん い けん の さまざまな情報や議論に基づいて、自分の意見を述べ か るスピーチが書ける。 かく スピーチを書く はじ お ひょう げん 「そして」 「し スピーチを始めたり、終えたりする表現や、 14 かん たん せつ ぞく し かし」「なぜなら」などの簡単な接続詞を使って、まと てき せつ せつ ぞく し てん かい ひょう げん つか ぐ たい れい まじ 適切な接続詞や展開表現を使い、具体例を交えたわか こう せい こう せい わ だい い けん つか の てき せつ せっ とく りょく こう せい きる。 れん しゅう みじ 簡単な話題について、練習すれば、短いスピーチがで 15 てん かい な展開表現を使って、説得力のあるスピーチを構成で まったスピーチを構成できる。 かん たん わ だい 話題を展開したり、意見を述べたりするために、適切 てん かい ひょう げん りやすく、まとまったスピーチを構成できる。 じ ぶん し わ だい じゅん び 自分がよく知っている話題について、準備すればスピー てい ど せい かく きる。 よう てん の チができる。わかりやすくある程度正確に要点が述べ り ろん てき てん かい じゅ よう 論理的に展開したプレゼンテーションができる。重要 てん しょう さい し ぜん はつ おん しょう てん あ な点や詳細に焦点が当てられる。 られる。 に ほん じん 16 き はつ おん 日本人が聞いてわかる発音やポーズでスピーチができる。 18 あと とき どき しつ もん 20 か たす かん たん しつ もん こた もらわなければならないが、簡単な質問に答えられる。 日本人がよく理解できるくらいはっきりとした発音と とも だち はっ ぴょう わ だい なに あと しつ もん こた はや 発表の後の質問に答えられるが、スピードが速いとき く か し かい はっ ぴょう よう てん れん しゅう り かい もん だい しめ かん たん せつ めい くに しょう かい たい しょ しめ てい ど くわ しつ もん たい じゅん び りゅうちょう たい おう とも だち し かい ができる。その場に応じて対処できる。 国紹介シートを示しながら、簡単に説明ができる。 あと はっ ぴょう すべ り かい 友達のスピーチ発表がほぼ全て理解できる。 はっ ぴょう かい ができる。 おう はっ ぴょう 発表の後の質問に対して、準備していなくても、流暢 し ぜん 練習すれば、だいたい問題なくスピーチ発表会の司会 ば てい に自然に対応ができる。 友達のスピーチ発表の要点が理解できる。 はっ ぴょう かい てん ど きょうちょう は繰り返してもらわなければならない。 とも だち 友達のスピーチ発表の話題が何かわかる。 じゅん び はっ ぴょう じゅう よう 自然な発音やイントネーションで、重要な点をある程 度強調しながら、スピーチができる。 練習すれば、準備したとおりにスピーチ発表会の司会 くに しょう かい くに しょう かい 国紹介 く 発表の後、時々質問を繰り返してもらったり、助けて れん しゅう 19 はつ おん し ぜん はっ ぴょう 17 り かい 自然なスピードでスピーチができる。 はっ ぴょう 発表する に ほん じん はっ びょう てき ぎ くわ めい スピーチ発表について適宜コメントを加えながら、明 かい りゅうちょう し かい 快に流暢に司会ができる。 せつ めい くに しょう かい しめ し りょう かん れん しゃ かい 国紹介シートを示しながら、ある程度詳しい説明がで 国紹介シートを示しながら、その資料に関連する社会 きる。 的な事象まで詳細な説明ができる。 てき じ しょう しょう さい せつ めい に ほん り かい 日本理解 じ こく 自国について せつ めい 説明する じ ぶん 21 くに じょうきょう ど し りょう たい ぶん くに じょうきょう かん た せつ めい じ こく じょうきょう げん いん はい けい しめ た かく 自国の状況について、原因や背景を示しながら、多角 てき なに 表やグラフが何についてのものかがわかる。 ひょう よう てん よ と 表やグラフから要点を読み取ることができる。また、 かん たん せつ めい せつ めい し りょう よ 漢字にルビのついた資料を読んで、キーワードがわかる。 かん じ し りょう ひょう もん だい り かい てき せつ ひょう げん せつ めい 表やグラフを問題なく理解し、適切な表現で説明した はい けい 簡単に説明ができる。 かん じ 23 じ ぶん 自分の国の状況について、簡単に説明できる。 的に説明できる。 よ 資料を読む すい そく い けん り、背景を推測して意見をのべたりすることができる。 よ り かい 漢字にルビがついた資料を読んで、だいたい理解できる。 なま し りょう ふく し りょう よ り かい 生の資料を含むさまざまな資料を読み、だいたい理解 できる。 みじか り ゆう の かん たん い けん い 短い理由を述べたりして、簡単な意見が言える。 り ゆう の せつ めい い けん 理由を述べたり、説明したりして、はっきりと意見が い 24 い けん ぶん てい せつ めい 度で説明できる。 ひょう 22 しつ もん 自分の国の状況についての質問に対して、1文か2文程 り てん ふ り てん もん だい し てん せつ めい てき せつ 利点、不利点をあげて問題の視点を説明したり、適切 ろん てん 言える。 きょうちょう ちょう よう かん れん じ こう くわ と あ に論点を強調し、重要な関連事項を詳しく取り上げ、 めい かく い ろん きょ てん かい い けん の 明確に論拠を展開しながら意見が述べられる。 意見を言う ひと 25 い けん さん せい はん たい ほかの人の意見に賛成や反対ができる。 ひと い けん たい り ゆう あ じ ぶん ほかの人の意見に対して、理由などを挙げながら自分 い けん の くわ の意見を述べ、コメントを加えられる。 せっ きょく てき ぎ ろん じ こう せつ めい さん か ほか ひと い けん ろん きょ かん れん 積極的に議論に参加し、他の人の意見に論拠や関連す い けん し てん しめ る事項を説明し、意見や視点を示すことができる。 27 ポートフォリオを理解する 後で自分で見てわかるメモが取れる。 インタビュー結果についての簡単な発表原稿を書くこ 6 し ぜん あいづちを打ち、聞いていることを相手に示すことが き 5 はっ ぴょう げん こう さく せい ろん り てき に興味深い答えを引き出せる。 インタビュー 発表原稿作成 しゅうしゅう つく 展開の質問文が作れる。 じゅん びん する じょう ほう インタビューで必要な情報を収集するための論理的な てん かい インタビューで準備した質問をし、相手の話したことを 2 そ インタビューの流れに沿った適切な質問文が作れる。 知識編 例 1 自己評価チェックリスト (2)言語的・文化的体験の記録に入れたもの 【例 2 研修活動の記録】 体験中心の訪日研修中の気づきを、日本語で記録するようにしたものです。「1. 日本語について気づ いたこと」 「2. やってみて気づいたこと」「3. 生活の中で気づいたこと」、最後に「1~3について考え たこと」を記録します。この記録を使って、週ごとにクラスの仲間や教師とふり返りました。 知識編 ポートフォリオを理解する 28 例 2 研修活動の記録 ( 記入例 ) JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 【例 3 この研修での自己目標と自己評価】 研修のはじめに「この研修でしたいこと」を記入し、研修の終わりに「できたこと」を記入します。 日本語と体験について、教師やクラスの仲間と話し合って、自己目標を立て評価します。 例 3 この研修での自己目標と自己評価 ( 記入例 ) 知識編 ポートフォリオを理解する 29 【例 4 スピーチ原稿】 研修中に作成したスピーチ原稿の例です。他にも、インタビュー発表原稿及び資料などがあります。 例 4 スピーチ原稿 知識編 ポートフォリオを理解する 30 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 日本語国際センター教師研修「作文評価」のためのポートフォリオ活用 海外の日本語を母語としない日本語教師を対象とした 訪日研修における「総合日本語」作文活動 ●対象とした学習者数 : 13名 : A2,B1 ●学習時間 : 40時間 ●担当した教師数 : 2名 ●研修目的 : 日本語学習および日本文化・社会理解を深めつつ日本語教 授能力を高める機会を提供 ●研修目標 知識編 ●日本語能力 「総合日本語」 「文法」 「教授法」 「日本事情」科目のほか「日本文化体験プログラム」 を設け、次の4点を研修の目標とする。 ●「総合日本語」作文活動の目的 「自分・家族」「旅行・交通」「学校・教育」「自然・環境」「異文化」などのトピッ クに関連する学習活動を、「読む・聞く・話す・書く」4技能のバランスを取りな 「総合日本語」 がら行う。作文活動は、各トピックの学習活動の集大成の活動とする。 の授業は、「①日本語運用力の向上」と「③日本の文化や社会に対する理解の深化」 を目指した授業であるが、学習成果を自己評価し学習活動をふり返ることは、教師 としての目標「②日本語の教授能力の向上のための情報や知識の整理および新しい 視点や方法の導入と活用」にもつながる。 ●ポートフォリオ活用の目的 ポートフォリオは、研修全体の学習成果の評価として活用したが、ここでは「総合 日本語」の作文活動の評価のために活用した部分についてのみ紹介する。 教師研修で使ったポートフォリオの、(1)~(3)の構成要素ごとに入れたものは、次の通りです。 (1)評価表に入れたもの 「自己評価チェックリスト」 「意見文・説明文のための評価基準」【例 5 p.32】 「作文評価シート」【例 6 p.33】 (2)言語的・文化的体験の記録に入れたもの 「日本での体験と学びの記録シート」「学習計画シート」 「作文活動をふり返って」【例 7 p.34】 (3)学習の成果に入れたもの 「成果物一覧」「作文」「集めた教材」「作成した教案」など これらの中から、 (1)評価表に入れた「意見文・説明文のための評価基準」【例 5】、「作文評価シート」【例 6】 (2)言語的・文化的体験の記録に入れた「作文活動をふり返って」【例 7】 31 ポートフォリオを理解する ①日本語運用力の向上、②日本語の教授能力の向上のための情報や知識の整理およ び新しい視点や方法の導入と活用、③日本の文化や社会に対する理解の深化、④帰 国後の自己研修の促進 の実例を見てみましょう。 (1)評価表 (2)言語的・ 文化的体験の記録 (3)学習の成果 自己評価 チェックリスト 「日本での体験と 学び」の記録 シート 成果物一覧 知識編 例5 意見文・説明文の ための 評価基準 学習計画シート 例7 作文活動を ふり返って 例6 作文評価シート 作文などの 成果物 作成した教案 ポートフォリオを理解する 【例 5 意見文・説明文のための評価基準】 このクラスの「作文」では、意見文と説明文を書く活動を行いました。教師は、「Can-do」を利用し て各トピックの作文活動の目標を考え、例 5のような「意見文・説明文のための評価基準」を作成しま した(2)。 例 5 意見文・説明文のための評価基準 達成度 目標以上を達成 目標を達成(B1) もう少しで目標に達成 努力が必要 4 3 2 1 評価項目 内容 伝えたい(主張したい)こ 伝えたい(主張したい)こ 伝え たい( 主張したい )こ 伝えたい(主張したい)こ とに必要な情報について、 とに必要な情報について、 とがだいたい理解できる。 とを漠然と理解することは 正確、かつ詳しい説明を書 具体的な 説明を あ る 程度詳 十分理解す る た め に は、確 できるが、説明が不足して いている。 しく書いている。 認しないと分からない点が い て、全体的に 何を 伝え た ある。 構成 いのかわかりにくい。 主張したい論点を補強する 文を続けていくつも書いて 文と 文の 関係が 部分的に 分 文や単語をばらばらに書い た め に 詳し い 情報や 具体 い る。段落を 使っ て 簡単な かりにくい部分もあるが、 ている。文章としての構成 例、理由な ど を 書き、分か 筋や描写を書いているため、 大きな流れをつかむことは がない。 りやすく描写している。 構成が分かりやすく読みや できる。 すい。 読み手への配慮 読み手にとって必要な情報 読み手にとって必要な情報 読み手にとって必要な情報 情報を断片的に書いている や 説明を 詳し く 書い て い や説明を書いている。その や説明が不足しているため、 ため、何を伝えようとして る。ま た、読み 手の 興味を ため、伝えたいメッセージ 伝えたいメッセージが伝わ いるかわかりにくい。 引くような工夫をしている。 をほぼ的確に伝えている。 語彙・文法など らない部分がある。 トピックに関連した適切な トピックに関連した語句・ 部分的に 語彙が 不適切だ っ 不 適切 な 語句・表現 や 文法 語彙や 表現、複雑な 構文を 表現・構文を 正確に 使っ て たり、文法的な誤りもある 的な誤りがやや多いため、 使って、自分の考えを示し、 い る。ま た、文体や 表記な が、文の 理解に 影響を 与え 文を理解しにくいことがある。 明瞭に 説明し て い る。誤解 どに書きことばとしての適 るほどではない。 につながるような文法上の 切さがある。 誤りもない。 (2) 「Can-do」を活用した評価基準や評価シートの作成手順については、pp.57-68をご参照ください。 32 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 【例 6 作文評価シート】 例 5の評価基準にもとづいて、例 6のような「作文評価シート」を作成し、学習者は自分の作文を自 己評価しました。また教師は、作文の添削をするとともに、この「作文評価シート」を使って評価し、 コメントを記入しました。 例 6 作文評価シート ( 記入例 ) て ん な い よ う 点 内 容 4 伝えたい(主張したい)ことに必要な情報に ついて、具体的な説明をある程度詳しく書い てあり、読み手にとってたいへん理解しやすい。 3 伝えたい(主張したい)ことがだいたい理解 できる。十分理解するためには、具体的な説 明が不足していたり、確認しないと分からな い点がある。 つ た し ゅ ちょう ぐ ひ つ よ う た い て き て い て つ た ど く わ り か い じょう ほ う か し ゅ ちょう じゅう ぶ ん め い ふ り り か い ぐ そ く か く に ん た い て き 知識編 よ せ つ め い か い せ つ わ て ん つ た し ゅ ちょう ば く ぜ ん り か い 2 伝えたい(主張したい)ことを漠然と理解す ることはできるが、説明が不足していて、全 体的に何を伝えたいのかわかりにくい。 1 伝えたい(主張したい)ことに必要な情報が 正確でないか、トピックと関係がないため、 何を伝えたいのかわかりにくい。 せ つ め い た い て き な に ふ そ く ぜ ん つ た つ た し ゅ ちょう ひ つ よ う せ い か く じょう ほ う か ん け い つ た ぶ ん つ づ て ん こ う 点 せ い 構 成 か だ ん ら く つ か 4 文を続けていくつも書いている。段落を使っ て簡単な筋や描写を書いているため、構成が 分かりやすく、たいへん読みやすい。 3 文と文の関係が部分的に分かりにくい部分も あるが、大きな流れをつかむことはできる。 2 短い文や語句を使ったり、基本的な接続助詞 で文と文をつなげたりして、伝えたいことの ポイントだけを並べて書いている。 1 文や単語をばらばらに書いている。文章とし ての構成がない。 か ん た ん す じ びょう し ゃ か こ う せ い わ よ ぶ ん ぶ ん か ん け い ぶ お お みじか ぶ ん ぶ ん ご ぶ ん て き わ ぶ く つ か き ぶ ん た ん ぶ ん な が ほ ん て き せ つ ぞ く じ ょ し つ た な ら ぶ ん か ご か ぶ ん しょう こ う せ い て ん よ 点 て は い り ょ 読み手への配慮 よ 4 ポートフォリオを理解する な に て ひ つ よ う じょう ほ う せ つ め い く わ か 読み手にとって必要な情報や説明を詳しく書 いている。また、読み手の興味を引くような 工夫をしている。 よ く て きょう み ひ ふ う よ て ひ つ よ う じょう ほ う せ つ め い か 3 読み手にとって必要な情報や説明を書いてい る。そのため、伝えたいメッセージをほぼ的 確に伝えている。 2 読み手にとって必要な情報や説明が不足して いるため、伝えたいメッセージが伝わらない 部分がある。 1 情報を断片的に書いているため、何を伝えよ うとしているかわかりにくい。 つ た か く つ た よ て て き ひ つ よ う じょう ほ う せ つ め い つ た ぶ ふ そ く つ た ぶ ん じょう ほ う だ ん ぺ ん て き て ん か ご 点 な に い つ た ぶ ん ぽ う 語彙・文法など か ん れ ん ご く ひょう げ ん こ う ぶ ん せ い か く トピックに関連した語句・表現・構文を正確 に使っている。 また、文体や表記などに書きことばとしての 適切さがある。 つ か 4 ぶ ん た い ひょう き か て き せ つ ぶ ぶ ん て き ご い ふ て き せ つ ぶ ん ぽ う て き あやま 3 部分的に語彙が不適切だったり、文法的な誤 りもあるが、文の理解に影響を与えるほどで はない。 2 不適切な語句・表現や文法的な誤りがやや多 いため、文を理解しにくいことがある。 1 暗記した表現や文をばらばらに書いている。 必要な語・表現が使えず、文法的な誤りが多 いため、文を理解することが難しい。 ぶ ん ふ て き せ つ ご く ぶ ん あ ん き ひ つ よ う ひょう げ ん り ひょう げ ん ご り え い きょう あ た ぶ ん ぽ う て き あやま ぶ ん り お お か い ひょう げ ん ぶ ん か い か つ か か い ぶ ん ぽ う て き あやま お お む ず 33 【例 7 作文活動をふり返って】 次のようなシートを使って、作文活動全体についてふり返りました。 学習者に、最初と最後に書いた作文の比較、作文のテーマについての感想、作文を自己評価すること に対する感想などを自由に記述させた後に、クラスで共有しました。感想の中には、作文活動や作文の 評価方法についての教師としての感想も多く見られました。 例 7 作文活動をふり返って ( 記入例 ) 知識編 ポートフォリオを理解する 以上、JF スタンダードのポートフォリオについての考え方と、実際に教育現場で学習成果の 評価のツールとして活用したポートフォリオの例を紹介しました。各教育現場で、コースの目 的や内容に合ったポートフォリオをデザインし、くり返し使うことで、教育効果を高め、使い やすいものにしていくことが大切です。 34 実践編 2章 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 実践編 2.1 コースをデザインする これまで、JF スタンダードを利用するにあたって大切な考え方について説明してきました。学習者 の熟達度を考えるために、 「1.1「JF スタンダードの木」を理解する」では「JF スタンダードの木」 、 「1.2 6つのレベルを理解する」では言語熟達度、 「1.3「Can-do」を理解する」では「JF スタンダードの木」 と6つのレベルにもとづいた「Can-do」の概要と目標設定におけるその利用方法、「1.4 ポートフォリ オを理解する」ではコースを通した学習者による自己評価や活動の記録について説明しました。図 2-1 は、これらの「JF スタンダードの木」や「Can-do」、「ポートフォリオ」がコースデザイン全体の流れ の中でどのように関わっているかを示したものです。 実践編 コースをデザインする 37 図 2-1 コースデザインの全体像 (1)コースの方針、目標を考える コースの目標の設定 目標レベルの設定 (2)目標に合った学習内容を考える 各授業の配置 各授業の学習目標設定 自己評価 チェック リスト 学習目標 話題について知識のな い聴衆に対しても、自 信を持ってはっきりと 複 雑な話 題について、 明確なきちんとした構 一覧 (シラバス) 造 を 持 った プ レ ゼ ン 事前に用意されたプレ テーションができる。 ゼンテーションをはっ 自分の専門でよく知っ ている話 題について、 きりと行うことができ る。 事前に用意された簡単 身 近な話 題について、 リハーサルをして、短 非常に短い、準備して 練習した言葉を読み上 なプレゼンテーション ができる。 い 基 本 的なプレゼン テーションができる。 げることができる。例 えば、話し手の紹介や 乾杯の発声など。 学習内容の検討 「Can-do」 (3)学習成果の評価について考える 実践編 いつ評価するか 評価基準 評価シート どのような方法で評価するか 評価項目や評価基準はどうするか ポートフォリオの活用方法について 検討する コースをデザインする 38 コースで学んだことを記録し、 保存するために ポートフォリオを活用します (1)評価表 (2)言語的・ 文化的体験の記録 自己評価 チェック リスト 言語的・ 文化的 体験と学び 評価基準 評価シート 学習計画と ふり返り (3)学習の成果 成果物一覧 作文・ レポート 発表原稿など プロジェクト の成果 複 雑な内容 を口頭 発 表できる。 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 図 2-1では、コースデザインの内容を大きく以下の3つの段階に分けました。 (1)コースの方針、目標を考える (2)目標に合った学習内容を考える (3)学習成果の評価について考える これら3つの内容は、相互に関連しています。図 2-1で黒の矢印で示しているように、必要に応じて 前の段階で検討した内容をふり返って、お互いが関連のあるものになっているかどうかを確認しながら コースデザインを進めます。このような確認作業によって、コース全体として、目標・学習内容・学習 成果の評価方法が一貫したものとなります。 『JF 日本語教育スタンダード2010』の2章では、コースをデザインするときに「JF スタンダードの木」 、 「Can-do」 、 「ポートフォリオ」をどのように活用するか、簡単に紹介しました。ここでは、その流れに そって、JF スタンダードを実際の日本語コースでどのように活用できるか、次のような具体的なコー スを想定して、コースデザインの詳しい手順を見ていきましょう。 A 国 ○△□日本語学校 大人を対象とした日本語コース ●学習者 教師、ビジネスマン、大学生など20名 実践編 学習者に関する情報 来日経験のある人もない人もいる。 ●学習歴 日本語学習経験がある。 ●学習目的/動機 • 日本の社会・文化についての理解を深め、仕事などで出会う日本人と日本語で円滑な コミュニケーションができるようになりたい。 • 身近で簡単なことだけでなく、いろいろな話題について、詳しく、わかりやすく話せ るようになりたい。 カリキュラムに関する情報 ●学習時間 総学習時間:42時間(3時間× 14回) ただし、初回は「オリエンテーション」、最終回は「まとめ」の時間とするため、 授業は、3時間× 12回となる。 ●使用教材 特に教材は決まっていない。教師が独自に作成した教材を使用する。 39 コースをデザインする 日本人と基本的なやりとりはあまり問題なくできる。 (1)コースの方針、目標を考える まず、コースの方針や目標を決めます。学習者のニーズや学習目的を考慮して、コースの目標や伸ば したい能力を考えます。コースの目標について検討するとき、「JF スタンダードの木」を見て、どの側 面に重点を置くのかを考えることができます。たとえば、「JF スタンダードの木」の根で示された語彙 や文法などの言語能力の育成に力を入れるコースであるとか、枝で示された言語活動の中の産出に力を 入れるコースであるとか、教育現場の現状や特色、学習者のニーズなどに合わせて検討することができ ます。 次に、学習者の現在のレベルを確認し、コースで目標とするレベルを検討しましょう。 「全体的な尺度」 (p.9)や「自己評価表」 (参考資料 1、pp.70-71)を見て、学習者が今どのようなレベルなのか、コー スではどのようなレベルを目指すのかを大まかに考えることができます。 ■このコースの場合… 「全体的な尺度」や「自己評価表」を見て、このコースの学習者の現時点のレベルは A2程度であると 確認し、目標とするレベルを B1としました。学習者の学習目的やレベルなどから、コースの目標とし て以下の2点を設定しました。 実践編 • 日本人の考え方や習慣・文化について、また日本人が A 国についてどのような知識や印象を持ってい るかなどについて理解を深め、自分自身の考え方や自国の習慣・文化などの相違点や類似点に気づく ことができる。 • 仕事などで出会う日本人と、身近で簡単なことだけでなく、いろいろな話題について社会的・文化的 な相違点や共通点にもふれながら、ある程度の長さで、わかりやすく話すことができる。 コースをデザインする また、B1レベルの産出(話す)の 「Can-do」や、B1レベルで使用できそうな市販教材の学習内容を見て、 「ある程度の長さで、わかりやすく話すこと」に関して、このレベルで身に付けてもらいたいこととして、 手順関係を述べる、描写する、対比する、という項目を取り上げることにしました。 A 国 ○△□日本語学校 大人を対象とした日本語コース ●コースの目標 • 日本人の考え方や習慣・文化について、また日本人が A 国についてどのような知識や 印象を持っているかなどについて理解を深め、自分自身の考え方や自国の習慣・文化 などの相違点や類似点に気づくことができる。 • 仕事などで出会う日本人と、身近で簡単なことだけでなく、いろいろな話題について 社会的・文化的な相違点や共通点にもふれながら、ある程度の長さで、わかりやすく 話すことができる。 ●レベル レベルは現在 A2程度。目標とするレベルは B1。 40 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック (2)目標に合った学習内容を考える ここでは、コースの目標を念頭に置き、具体的にどのような学習活動を取り上げ、コースの中にどの ような順番で配置し、各授業でどのような学習活動を行うのかを考えます。これらの学習内容を考える ときには、 (1)で考えたコースの目標とつながっているかを常に確認しながら考えることが大切です。 授業で行う学習活動を考え、具体的な学習目標を設定するとき、「みんなの「Can-do」サイト」にあ る「Can-do」を参考にしたり、利用したりすることもできます。学習目標設定については、「学習目標 一覧を作る」 (p.50~)で説明します。 授業の具体的な学習目標が決まったら、その目標を達成するために必要となる知識、語彙や文型など を考えます。そして、それらをどのように組み合わせ、どのような順番で提示するかなど、授業で行う 学習活動をイメージしながら、具体的な学習内容を決めていきます。 ■このコースの場合… ①各授業の配置を考える このコースでは、コースの目標や学習者の学習目的などを考慮して、JF Can-do のトピックでもある 「自分と家族」 「仕事と職業」「買い物」「旅行と交通」「食生活」「言語と文化」の6つのトピックを取り 内容をイメージしながら考えます。各トピックの授業は、3時間× 2回で行います。コース全体の流れ が決まったら、コースの目標をふまえて、各トピックでどのような学習活動を行うかを考え、具体的な 学習目標を設定します。(1)でコースの目標を考えたとき、各トピックの学習活動の中で中心的に学 実践編 上げます。これら6つのトピックをコースの14回の授業でどのような順番で扱うのか、大まかな学習 習する機能として、手順を述べる、描写する、対比する、の3つを取り上げることを決めました。「仕 事と職業」のトピックで手順を述べること、「買い物」「旅行と交通」で描写すること、「食生活」「言語 以下、具体的な学習目標の設定と学習内容の検討については、「仕事と職業」のトピックを例に見て みましょう。 ②各授業の学習目標を設定する まず、 (1)で考えたコースの目標と、中心的に取り上げたい「手順を述べる」という学習項目をふまえ、 このトピックの学習目標を以下のように設定しました。 「新しく日本から赴任してきた人などに、自分たちの部署の仕事内容について、日本人が知っておい たほうがいい情報や、日本の会社との違いや共通点にふれながら、ある程度詳しく説明することができる。 」 ③学習内容を検討する 次に、この学習目標を達成するためには、仕事に関する語彙や、手順を表わす表現、対比を表わす表 現が必要だと考え、それらを学習項目として扱うことにしました。また、「仕事と職業」というトピッ クでは、日本の会社や日本人の労働観についての社会文化的な知識を提供することも大切だと考えました。 そして、これらの学習項目をどのように組み合わせ、どのような順番で学習活動として提示するかを 考えます。このトピックの学習活動の流れは以下のようになります。 41 コースをデザインする と文化」で対比することを中心に学習することにします。 学習目標提示 インプット(聴解・読解)、言語知識・社会文化的知識・談話構成の学習 …2時間 自分の発表の全体構成を考える …1時間 原稿作成 … 宿題 ペア練習(リハーサル) …1時間 口頭発表 …1時間 ふり返り …1時間 実践編 このトピックは、最終的に「新しく日本から赴任してきた人などに、自分たちの部署の仕事内容につ いて、日本人が知っておいたほうがいい情報や、日本の会社との違いや共通点にふれながら、ある程度 詳しく説明することができる。」という学習目標にそった口頭発表ができることを目指すため、以下の ような流れで行います。 コースをデザインする 〈前半 3時間〉 ①「ふり返りシート」に、日本人の仕事のし方や、仕事に対する考え方などについて、 知っていることや興味のあることを記入する。 ②インプットとして、日本人が新しいスタッフに対して自分たちの仕事内容や仕事に 対する考え方などについて話しているビデオをいくつか見る。 ③そのスクリプトを読み、内容や構成を確認する。 ④発表のために必要な仕事に関する語彙、社会文化的知識、発表するときの談話構成 などを学習する。 ⑤自分の発表の全体構成を考え、新しいスタッフに自分たちの仕事内容を説明するこ とを想定して発表原稿を書く。内容には、A 国の会社で働くときに日本人が知って おいたほうがいい情報や、日本との相違点・共通点などを含める。(終わらなけれ ば宿題にする) 〈後半 3時間〉 ⑥練習として、発表原稿をもとに、ペアになって、お互いに自分の仕事内容を相手に 説明する。 ⑦原稿を見ずに、グループ内で、仕事内容について説明する。(録音する) 42 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 表 2-1は、6つのトピックをコースの中に配置し、「仕事と職業」トピックの学習目標や学習活動、 語彙や知識などの学習内容をまとめたものです。他のトピックも同様に決め、記入します。 表 2-1 A 国○△□日本語学校のコースの学習内容一覧 【コースの目標】 ■日本人の考え方や習慣・文化について、また日本人が A 国についてどのような知識や印象を思っているかなどについて理 解を深め、自分自身の考え方や自国の習慣・文化などの相違点や類似点に気づくことができる。 ■仕事などで出会う日本人と、身近で簡単なことだけでなく、いろいろな話題について社会的・文化的な相違点や共通点に もふれながら、ある程度の長さで、わかりやすく話すことができる。 【目標とするレベル】 B1 回 時間 トピック 学習目標 1 3時間 (オリエンテーション) 2 3時間 語彙・文型 社会文化的知識 … … … 新しく知り合った日本人に、 自分と家族 3 学習活動 3時間 自分自身の長所や短所につい て、ある程度詳しく話すこと ができる。 ・社員が新しいスタッフに自 4 貿易会社、担当し ているビデオをいくつか見 ます… たり、そのスクリプトを読 3時間 んだりして、必要な語彙や 新しく日本から赴任してきた 人などに、自分たちの部署の 発表のためのフォーマット (談話構成)を学習する。 仕事内容について、日本人が ・自分の発表の全体構成を考 仕事と職業 知っておいたほうがいい情報 ・会議、出張、営業、 ・日本の会社文化 分たちの仕事内容を説明し ・日本人の労働観 ・手順を表わす表現 (まず、~てから、 ~場合、…) ・対比を表わす表現 (A は~ですが、B は~です。…) える。 通点にふれながら、ある程度 詳しく説明することができる。 5 実践編 や、日本の会社との違いや共 ・新しいスタッフに自分たち の仕事内容を説明すること を想定して発表原稿を書く。 ・ペアになって仕事内容を相 3時間 手に説明する。 ・グループ内で仕事内容につ いて説明する。 (録音する) ・ふり返り 日本人と一緒に買い物に出か けたとき、自国で人気のある 3時間 特産品やファッションなど 買い物 7 について、日本の特産品や … … … … … … … … … … … … ファッションとの違いや共通 3時間 点にふれながら、ある程度詳 しく紹介することができる。 8 日本人旅行者に、有名な観光 3時間 地について、日本人が持って 旅行と交通 9 いる情報をふまえて、ある程 度詳しく説明することができ 3時間 る。 日本人と食事をしていると 10 3時間 き、自国と日本の食生活(マ 食生活 ナーや食べ物など)の違いや 共通点について、例をあげて、 ある程度詳しく説明すること 11 3時間 ができる。 日本人を自宅に招待したと 12 3時間 き、自国と日本の生活習慣 言語と文化 (結婚式や年中行事など)の 違いや共通点について、例を あげて、ある程度詳しく説明 13 3時間 することができる。 14 3時間 (まとめ) 43 コースをデザインする 6 (3)学習成果の評価について考える (2)で、コースの目標に合った学習内容を考えました。ここでは、その学習成果をいつ、どのよう に評価するかを考えます。コースの目標にそった評価について考えるうえで、(2)に戻って学習内容 を変更することもあるでしょう。 ■このコースの場合… このコースの目標は(1)で以下のように設定しました。 • 日本人の考え方や習慣・文化について、また日本人が A 国についてどのような知識や印象を持って いるかなどについて理解を深め、自分自身の考え方や自国の習慣・文化などの相違点や類似点に気 づくことができる。 • 仕事などで出会う日本人と、身近で簡単なことだけでなく、いろいろな話題について社会的・文化 的な相違点や共通点にもふれながら、ある程度の長さで、わかりやすく話すことができる。 これらの目標が達成できたかどうかを評価するために、ポートフォリオを活用して学習成果の評価を 行います。そして、学習者自身が熟達度や目標を意識化し、学習動機につながるよう、コースの開始時 実践編 と終了時に「自己評価チェックリスト」を利用して自己評価を行います。また、 「評価基準」と「評価シー ト」を用いて口頭発表を評価します。 口頭発表については、6つのトピックのうち、「仕事と職業」 「旅行と交通」 「言語と文化」 の3つのトピッ クで評価をします。また、3つのトピックで行った口頭発表のうちの1つをコースの終わりにもう一度 行い、最終的な「会話テスト」とします。 コースをデザインする 「JF スタンダードの木」を使って、まず学習目標や学習活動として扱う言語活動のカテゴリーを 確認し、その言語活動を支える言語能力のカテゴリーを考えることによって、言語活動とレベ ルに合った評価の観点や達成基準を考えることができます。その際に、「みんなの 「Can-do」 サイト」などを利用して、各カテゴリーの中に、どのレベルでどのような「Can-do」があるか を確認することが効果的です。 B1レベルの産出(話す)では、図 2-2に示すように、能力 Can-do の中の言語構造的能力の【b 使 用語彙領域】や、語用能力の【j 話題の展開】などのカテゴリーの言語能力の向上が熟達の鍵をにぎっ ていると考え、これらを評価の観点として選びました。 図 2-2は、学習目標や学習活動として扱う産出の言語活動と、その言語活動を支え、評価の観点とす る言語能力のカテゴリーを示したものです。 44 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 図 2-2 産出(話す)の評価の観点として選んだカテゴリー Can-do 産出 ⑯講演やプレゼンテーションをする 言語構造的能力 b 使用語彙領域 c 語彙の使いこなし d 文法的正確さ e 音素の把握 Can-do 語用能力 j 話題の展開 k 一貫性と結束性 l 話しことばの流暢さ 実践編 このコースでは、B1レベルの産出(話す)の言語活動を達成するために必要な言語能力を評 価の観点とするため、図 2-2で示したようなカテゴリーを選びましたが、レベルや言語活動が異 なる場合は、評価の観点として選ぶ言語能力のカテゴリーも変わってくるでしょう。たとえば、 B1レベルのやりとり(話す)であれば、産出の場合と違って、図 2-3のように、【j 話題の展開】 【k 一貫性と結束性】のかわりに、【g 社会言語的な適切さ】や【i 発言権】などが評価の観点 となるでしょう。 コースをデザインする 図 2-3 やりとり(話す)の評価の観点として選んだカテゴリー Can-do やりとり M インフォーマルな場面でやりとりをする Can-do 言語構造的能力 b 使用語彙領域 c 語彙の使いこなし d 文法的正確さ e 音素の把握 社会言語能力 g 社会言語的な適切さ 語用能力 i 発言権 l 話しことばの流暢さ 45 このコースでは、口頭発表の評価や自己評価以外に、異文化理解能力を育成することを目的に、各ト ピックの学習を通じて、日本人の考え方や習慣・文化、および自分自身の考え方や自国の習慣・文化に ついて、学習者が新しく気づいたこと、考えたことなどを「ふり返りシート」(図 2-4)に毎回記録さ せました。 図 2-4 ふり返りシートの例 実践編 コースをデザインする 以上のように、このコースでは、「評価基準」と「評価シート」を用いて口頭発表を評価し、コース の開始時と終了時に「自己評価チェックリスト」を利用して学習者が自己評価を行います。また、各ト ピックでの気づきなどを「ふり返りシート」に記入します。 図 2-5は、このコースのポートフォリオの構成です。このコースで学習成果の評価のために使用する 自己評価チェックリスト、評価基準、評価シート、ふり返りシート、および発表原稿や口頭発表の録音 などを整理したものです。ファイルのし方は、このように3つの構成要素ごとにファイルしてもいいで すし、トピックごとに関連するシートをまとめてファイルすることもできます。 46 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 図 2-5 このコースのポートフォリオの構成 (1)評価表 自己評価 チェックリスト (2)言語的・文化的 体験の記録 ふり返りシート 評価基準 評価シート (3)学習の成果 発表原稿 録音 このコースの評価のし方をまとめると次のようになります。 A 国 ○△□日本語学校 大人を対象とした日本語コース ●学習成果の評価 実践編 • ポートフォリオを活用して学習成果の評価を行う。 • 学習者はコースの開始時と終了時に「自己評価チェックリスト」を使った自己評価を 行う。 • 授業の中で、3つのトピック(旅行と交通、仕事と職業、言語と文化)で口頭発表を行い、 「評価基準」と「評価シート」を使って評価する。 • 最終回に3つのトピックで行った口頭発表のどれか1つを「会話テスト」として行う。 コースをデザインする • 学習者はトピックごとに、学習を通じて、日本人の考え方や習慣・文化、自分自身の 考え方や自国の習慣・文化について、新しく気づいたことや考えたことなどを「ふり 返りシート」に書く。 * 「自己評価チェックリスト」 と口頭発表の「評価基準」 「評価シート」を、ポートフォ リオの【①評価表】に入れる。 「ふり返りシート」を、ポートフォリオの【②言語的・ 文化的体験の記録】に入れる。発表原稿や提示資料、録音した音声などを、ポートフォ リオの【③学習の成果】に入れる。 自己評価チェックリストの作成については p.54~、口頭能力の評価基準と評価シートの作成につい ては p.57~で説明します。 47 ここまで、コースデザインの流れと内容を見てきました。図 2-6は、このコースの全体像を示したも のです。 図 2-6 A 国○△□日本語学校のコースの全体像 <コースの目標> • 日本人の考え方や習慣・文化について、また日本人が A 国についてどのような知 目 標 識や印象をもっているかなどについて理解を深め、自分自身の考え方や自国の習 慣や文化などの相違点や類似点に気づくことができる。 • 仕事などで出会う日本人と、身近で簡単なことだけでなく、いろいろな話題につ いて社会的・文化的な相違点や共通点にもふれながら、ある程度の長さで、わか りやすく話すことができる。 <目標とするレベル> B1 自己評価 チェックリスト 学習活動 自分と家族 実践編 ふり返り シート 【手順を述べる】 【描写する】 【対比する】 仕事と職業 買い物 食生活 評価基準 評価シート ふり返り シート ふり返り シート コースをデザインする 【描写する】 【対比する】 旅行と交通 言語と文化 評価基準 評価シート 評 価 ふり返り シート ふり返り シート 評価基準 評価シート ふり返り シート 評価の観点 コースの目標や学習活動、評価の方法について検討するとき、常に、目標と学習活動は合って いるか、評価の観点や評価方法が学習活動を評価する方法として適切か、また、評価の観点と する項目を学習内容で扱っているか、目標と評価につながりがあるかどうかなどを考えながら 検討することによって、目標から評価までが一貫性のあるものとなります。 48 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 2.2 コースデザインに「Can-do」を使う ではここから、A 国○△□日本語学校のコースを例として、コースデザインの中での「JF スタンダー ドの木」や「Can-do」の次のような活用方法について紹介します。 (1) 「学習目標一覧」と「自己評価チェックリスト」を作る (2)話す力を測るための「評価基準」と「評価シート」を作る (1)「学習目標一覧」と「自己評価チェックリスト」を作る 「Can-do」を使って、「学習目標一覧」と「自己評価チェックリスト」を作成します。これらは、教 師と学習者が目標を共有し、学習者が目標を意識化するのに役立ちます。JF スタンダードの「Can-do」 は、共通の尺度にもとづいているため、他の機関や他の言語との比較、共有ができるようになります。 学習目標一覧と自己評価チェックリストを作成する全体の流れは、以下のようになります。 図 2-7 「学習目標一覧」と「自己評価チェックリスト」作成の流れ 自己評価チェックリストを作成する 1.コースの目標に合う「Can-do」のカテゴリーを考える 実践編 学習目標一覧を作成する 2.「みんなの「Can-do」サイト」で「Can-do」を選ぶ 4.(必要であれば)「Can-do」を、学習者が理解しやすい形や 教育現場に合う内容に書きかえる 5.選択した「Can-do」のリストをフォーマットに加工する 学習目標一覧の 完成! 自己評価チェックリストの 完成! 49 コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 3.「Can-do」の一覧から、実際に授業で使う項目を選択する ■このコースの場合… ―学習目標一覧を作る― 「Can-do」を使って学習目標を設定することで、学習活動や評価方法がイメージしやすくなります。 そして、その目標を教師と学習者が共有することができます。ここでは、学習活動がイメージしやすい 活動 Can-do を利用して、各トピックの学習目標を作る流れを見てみましょう。 1.コースの目標に合う「Can-do」のカテゴリーを考える まず、「JF スタンダードの木」を見てみましょう。 このコース目標は、学習活動がイメージしやすい活動 Can-do の中の、以下のカテゴリー と関係ありそうだと考えて、次に進みます。 ◆活動 Can-do だと… 産出(話す) 【C 経験や物語を語る】 【F 講演やプレゼンテーションをする】 実践編 2. 「みんなの「Can-do」サイト」で、該当する トピック、レベル、カテゴリーの「Can-do」を選ぶ 前のステップで考えた【C 経験や物語を語る】と【F 講演やプレゼンテーションをす コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 50 る】のカテゴリーの「Can-do」のうち、このコースの目標レベルである B1で、このコー スで取り上げる6つのトピック(「自分と家族」、「仕事と職業」、「買い物」、「旅行と交通」、 「食生活」、「言語と文化」)の「Can-do」を選択します。「みんなの「Can-do」サイト」 で選択した「Can-do」は、エクセルファイルに出力することができます。 次の表 2-2は、選択した「Can-do」(トピックつき)をエクセルファイルに出力した 一覧です。 サイトの使い方については、 『JF 日本語教育スタンダード2010』の 「3 みんなの 「Can-do」 サイトを使ってみる」を参照してください。 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 表 2-2 サイトから出力した「Can-do」(トピックつき)の一覧 種別 レベル 種類 言語活動 JF B1 活動 産出 カテゴリー Can-do 本文(日本語) トピック 来客に自分の会社の工場などを案内するとき、機械 経験や物語を語る の機能や生産過程などを、ある程度詳しく紹介する 仕事と職業 ことができる JF JF B1 B1 活動 活動 産出 産出 講演やプレゼンテーショ ンをする 講演やプレゼンテーショ ンをする 電気屋などの職場で、あらかじめ準備してあれば、 客に電子辞書などの商品について、ある程度詳しく 仕事と職業 紹介し、想定した質問に答えることができる ガイドとして有名な観光地などを案内するとき、あ らかじめ準備してあれば、名所や名物などを、ある 仕事と職業 程度詳しく紹介することができる お土産を渡しながら、休み中に行った場所や出来事 旅行と交通 JF B1 活動 産出 経験や物語を語る などについて、まとまりのある話を友人に語ること ができる 電子辞書など、新しく買い替えた物について、前に 買い物 JF B1 活動 産出 経験や物語を語る 持っていた物と比べながら、ある程度詳しく友人に 話すことができる JF B1 活動 産出 経験や物語を語る JF B1 活動 産出 経験や物語を語る JF B1 活動 産出 講演やプレゼンテーショ ンをする 自分の得意な料理の作り方などを順序だてて友人に 説明することができる 異文化体験の出来事や感想について、まとまりのあ る話を友人に語ることができる 食生活 言語と文化 弁論大会などで、あらかじめ準備してあれば、異文 化体験の出来事や感想などを含んだまとまりのある 言語と文化 簡単なスピーチをすることができる 自分の国について学ぶ集まりで、あらかじめ準備し B1 活動 産出 ンをする まりのある簡単なプレゼンテーションをすることが 言語と文化 できる 表 2-2のような選択した「Can-do」の一覧の中から、授業の中で実際に行う学習活動 を記述した「Can-do」はどれかを考え、必要なものを選びます。 この一覧の中には、今回のコースの授業で行いたい学習活動に合うものがないため、 この一覧の「Can-do」を参考にしながら、コースの学習内容に合うように、MY Can- do を作成する必要があります。 51 コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 3.「Can-do」の一覧から、実際に授業で扱う項目を選択する 実践編 JF 講演やプレゼンテーショ てあれば、自分の国や町の様子などについて、まと 4. (必要であれば) 「Can-do」を学習者が理解しやすい形や教育現場に合う内容 に書きかえる 「みんなの 「Can-do」 サイト」で選んだ「Can-do」の記述内容が難しい場合は、学習 者の母語に翻訳したり、簡単な日本語に書きかえたりしましょう。 ■ MY Can-do を作成する 「みんなの「Can-do」サイト」で選んだ「Can-do」が教育現場や学習者の状況に合わ ない場合は、記述内容を書きかえる必要があります。ステップ2で作った表 2-2の一覧 の中には今回のコースに合うものがなかったため、この一覧の「Can-do」を参考にして、 具体例や B1レベルの記述の特徴を入れて、必要な場合は「Can-do」のトピックを変え たりしながら、次のような MY Can-do を作成しました。コースの目標に照らし合わせ、 人前でまとまった話ができることを目指して、【F 講演やプレゼンテーションをする】 のカテゴリーの MY Can-do とし、各トピックの学習目標としました。 「自分と家族」 実践編 新しく知り合った日本人に、自分自身の長所や短所について、ある程度詳しく話すこ とができる。 「仕事と職業」 新しく日本から赴任してきた人などに、自分たちの部署の仕事内容について、日本人 が知っておいたほうがいい情報や、日本の会社との違いや共通点にふれながら、ある 程度詳しく説明することができる。 コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 「買い物」 日本人と一緒に買い物に出かけたとき、自国で人気のある特産品やファッションなど について、日本の特産品やファッションとの違いや共通点にふれながら、ある程度詳 しく紹介することができる。 「旅行と交通」 日本人旅行者に、有名な観光地について、日本人が持っている情報をふまえて、ある 程度詳しく説明することができる。 「食生活」 日本人と食事をしているとき、自国と日本の食生活(マナーや食べ物など)の違いや 共通点について、例をあげて、ある程度詳しく説明することができる。 「言語と文化」 日本人を自宅に招待したとき、自国と日本の生活習慣(結婚式や年中行事など)の違 いや共通点について、例をあげてある程度詳しく説明することができる。 MY Can-do の作成方法については、 「1.3「Can-do」を理解する」 を参照してください。 52 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 5.選択した「Can-do」の一覧を学習目標一覧のフォーマットに加工する 「Can-do」の一覧を、目標一覧に加工します。この目標一覧は、各トピックの授業の はじめと終わりに、学習者と一緒にトピックの学習目標を確認するのに利用することが できます。学習者と共有するために、目標一覧には、たとえば以下の項目を記入する欄 が必要でしょう。 • コースの名前や期間 • 評価を行うトピック 次の図 2-8は、学習目標一覧の例です。 図 2-8 学習目標一覧の例 学習目標 ○△□日本語学校 2010年度 大人を対象とした日本語コース 【コースの目標】 ■日本人の考え方や習慣・文化について、また日本人が A 国についてどのような知識や印象を思ってい ■仕事などで出会う日本人と、身近で簡単なことだけでなく、いろいろな話題について社会的・文化的 な相違点や共通点にもふれながら、ある程度の長さで、わかりやすく話すことができる。 回 トピック 学習目標 1 2 4 5 オリエンテーション 自分と家族 仕事と職業 【評価 1】 6 7 8 9 10 11 12 13 新しく知り合った日本人に、自分自身の長所や短所について、ある程度 詳しく話すことができる。 新しく日本から赴任してきた人などに、自分たちの部署の仕事内容につ いて、日本人が知っておいたほうがいい情報や、日本の会社との違いや 共通点にふれながら、ある程度詳しく説明することができる。 日本人と一緒に買い物に出かけたとき、自国で人気のある特産品やファッ 買い物 ションなどについて、日本の特産品やファッションとの違いや共通点に ふれながら、ある程度詳しく紹介することができる。 旅行と交通 【評価 2】 食生活 言語と文化 【評価 3】 日本人旅行者に、有名な観光地について、日本人が持っている情報をふ まえて、ある程度詳しく説明することができる。 日本人と食事をしているとき、自国と日本の食生活(マナーや食べ物など) の違いや共通点について、例をあげて、ある程度詳しく説明することができる。 日本人を自宅に招待したとき、自国と日本の生活習慣(結婚式や年中行 事など)の違いや共通点について、例をあげて、ある程度詳しく説明す ることができる。 14 まとめ これで学習目標一覧が完成しました。 53 コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 3 実践編 るかなどについて理解を深め、自分自身の考え方や自国の習慣・文化などの相違点や類似点に気づく ことができる。 ■このコースの場合… ―自己評価チェックリストを作る− 「1.4 ポートフォリオを理解する」でも述べましたが、自己評価チェックリストを使うと、学習 者は自分の日本語能力をコースの前後、またはコース途中で把握することができ、目標の明確化 や学習への動機づけを行うことができます。ここでは、 「JF スタンダードの木」と6つのレベルを 利用して自己評価チェックリストを作成する流れを見てみましょう。 1.コースの目標に合う「Can-do」のカテゴリーを考える まず、「JF スタンダードの木」を見てみましょう。 このコースの目標は、具体的なコミュニケーション活動がイメージしやすい活動 Can- do と方略 Can-do の中の、以下のようなカテゴリーが関係ありそうだと考えて、次に進 みます。 ◆活動 Can-do だと… 産出(話す) 【C 経験や物語を語る】 【F 講演やプレゼンテーションをする】 実践編 ◆方略 Can-do だと… 産出 【W 表現方法を考える】 【X(表現できないことを)他の方法で補う】 【Y 自分の発話をモニターする】 コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 2. 「みんなの「Can-do」サイト」で、該当する カテゴリーとレベルの「Can-do」を選ぶ 前のステップで考えた【C 経験や物語を語る】、【F 講演やプレゼンテーションをす る】 、【W 表現方法を考える】、【X(表現できないことを)他の方法で補う】、【Y 自分の 発話をモニターする】のカテゴリーの「Can-do」のうち、学習者の現時点のレベルであ る A2と、目標とするレベルである B1の「Can-do」を選択します。 今回は、コースの開始時と終了時に自己評価チェックリストを使うため、トピックが 限定されていない CEFR Can-do を選びました。 サイトでは、選択した「Can-do」の一覧を「レベル別」と「言語活動別」にエクセル ファイルに出力することができます。 次の表 2-3は、レベル別出力した A2レベルと B1レベルの「Can-do」のうち、B1レ ベルの活動 Can-do と方略 Can-do の一覧です。 サ イ ト の 使い 方に つ い て は、 『JF 日本語教育ス タ ン ダ ー ド2010』 「3 みんなの 「Can-do」 サイトを使ってみる」を参照してください。 54 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 表 2-3 サイトから出力した活動 Can-do と方略 Can-do の一覧 種別 レベル 種類 言語活動 CEFR B1 活動 産出 経験や物語を語る カテゴリー 物語を語ることができる。 Can-do 本文(日本語) CEFR B1 活動 産出 経験や物語を語る 現実や想像上の出来事を述べることができる。 CEFR B1 活動 産出 経験や物語を語る CEFR B1 活動 産出 経験や物語を語る CEFR B1 活動 産出 経験や物語を語る CEFR B1 活動 産出 経験や物語を語る CEFR B1 活動 産出 経験や物語を語る CEFR B1 活動 産出 経験や物語を語る CEFR B1 活動 産出 自分の関心事で、馴染みのあるさまざまな話題について、簡単 に述べることができる。 事柄を直線的に並べていって、比較的流暢に、簡単な語り、記 述ができる。 自分の感情や反応を記述しながら、経験を詳細に述べることが できる。 夢や希望、野心を述べることができる。 本や映画の筋を順序だてて話し、それに対する自分の考えを述 べることができる。 予測不能の出来事(例えば事故など)を、順序だてて詳細に述 べることができる。 講演やプレゼンテーション 質問には対応できるが、そのスピードが速い場合は、もう一度 をする 繰り返すことを頼むこともある。 自分の専門でよく知っている話題について、事前に用意された CEFR B1 活動 産出 講演やプレゼンテーション をする 簡単なプレゼンテーションができる。ほとんどの場合、聴衆が 難なく話についていける程度に、はっきりとしたプレゼンテー ションをすることができ、また要点をそこそこ正確に述べるこ とができる。 伝えたいことの要点を伝達する仕方を考えることができる。そ CEFR B1.1 方略 産出 表現方法を考える の際、使える言語能力を総動員して、表現のための手段が思い 出せる、あるいは見つかる範囲内にメッセージの内容を限定する。 B1.1 方略 産出 の方法で補う めることができる。 (表現できないことを)他 伝えたい概念に類似した意味を持つ、簡単な言葉を使い、聞き CEFR B1.1 方略 産出 CEFR B1.1 方略 産出 自分の発話をモニターする CEFR B1.1 方略 産出 自分の発話をモニターする 自分が使った言語形式が正しいかどうか確認することができる。 の方法で補う 手にそれを正しい形に「修正」してもらうことができる。 コミュニケーションが失敗したときは、別の方略を用いて出直 実践編 CEFR (表現できないことを)他 母語を学習対象言語の形に変えて使ってみて、相手に確認を求 すことができる。 授業の中で実際に取り上げたい「Can-do」はどれかを考え、必要なものを選びます。 4. (必要であれば) 「Can-do」を学習者が理解しやすい形や教育現場に合う内容 に書きかえる 「みんなの 「Can-do」 サイト」で選んだ「Can-do」の記述が難しい場合は、学習者の 母語に翻訳したり、簡単な日本語に書きかえたりしましょう。 (今回は「Can-do」を書きかえずに、そのまま次のステップに進みます。) 55 コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 3.「Can-do」の一覧から、実際に授業で扱う項目を選択する 5.選択した「Can-do」の一覧を自己評価チェックリストのフォーマットに加工する 表 2-3のように「Can-do」が並んだリストを、自己評価チェックリストに加工します。 自己評価チェックリストには、たとえば以下の項目を記入する欄が必要でしょう。 • コースの名前や期間 • 学習者の名前 • 学習者による自己評価(コース開始時と終了時など、異なる時期に自己評価ができる ように複数の欄を作ることがおすすめです。) • 記入方法の簡単な説明(自信を持って「できる」と思う「Can-do」には◎を書く、など) 次の図 2-9は、作成した自己評価チェックリストの例です。 「1.4 ポートフォリオを理解する」 の自己評価チェックリストの例も参考にしてください。 図 2-9 自己評価チェックリストの例 自己評価チェックリスト 実践編 ○△□日本語学校 2010年度 大人を対象とした日本語コース 名前: A2 初日 最終日 B1 活 動 方 略 コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 出来事や活動の要点を短く述べることができる。 自分の関心事で、馴染みのあるさまざまな話題について、 簡単に述べることができる。 計画、準備、習慣、日課、過去の 活動や 個人の 経験を 述べることができる。 事柄を 直線的に 並べ て い っ て、比較的流暢に、簡単な 語り、記述ができる。 好きか嫌いかを述べることができる。 自分の 感情や 反応を 記述し な が ら、経験を 詳細に 述べ ることができる。 事柄を列挙して簡単に述べたり、物語ることができる。 自分の 周り の 環境、例え ば、人や 場所、仕事、学習経 験などの日常を述べることができる。 夢や希望、野心を述べることができる。 自分の毎日の生活に直接関連のある話題については、リ ハーサルして、短いプレゼンテーションができる。意見、 計画、行動に 対し て、理由を 挙げ て、短く 述べ る こ と ができる。 自分の専門でよく知っている話題について、事前に用 意された簡単なプレゼンテーションができる。ほとん どの場合、聴衆が難なく話についていける程度に、はっ きりとしたプレゼンテーションをすることができ、ま た要点をそこそこ正確に述べることができる。 話し終えた後、限られた数の簡単な質問に対処するこ とができる。 質問には対応できるが、そのスピードが速い場合は、 もう一度繰り返すことを頼むこともある。 自分のレパートリーの中から適切な表現形を思い出し て、使ってみることができる。 伝えたいことの要点を伝達する仕方を考えることがで き る。使え る 言語能力を 総動員し て、表現の た め の 手 段が思い出せる、あるいは見つかる範囲内にメッセー ジの内容を限定する。 手持ち の 語彙の 中か ら 不適切な 言葉を 使っ て も、言い たいことをはっきりとさせるためにジェスチャーを使 うことができる。 母語を 学習対象言語の 形に 変え て 使っ て み て、相手に 確認を求めることができる。 伝え た い 概念に 類似し た 意味を 持つ、簡単な 言葉を 使 い、聞き手にそれを正しい形に「修正」してもらうこ とができる。 コミュニケーションが失敗したときは、別の方略を用 いて出直すことができる。 自分が使った言語形式が正しいかどうか確認すること ができる。 マーク ◎ 自信がある ○ できる △ 難しい ✓ これからがんばりたい これで自己評価チェックリストが完成しました。 56 初日 最終日 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック (2)話す力を測るための「評価基準」と「評価シート」を作る このコースでは、学習する6つのトピックのうち、 「仕事と職業」 「旅行と交通」 「言語と文化」の3つ のトピックで口頭発表の評価を行います。各トピックでは、コースの目標や、各トピックの学習目標、 あらかじめ決めた評価の観点などをふまえて授業を行うことを前提とします。 ここでは、 「仕事と職業」のトピックを例にして、口頭発表の「評価基準」と「評価シート」を作成 する流れを見てみましょう。「仕事と職業」のトピックの学習目標は、「新しく日本から赴任してきた人 などに、自分たちの部署の仕事内容について、日本人が知っておいたほうがいい情報や、日本の会社と の違いや共通点にふれながら、ある程度詳しく説明することができる。」です。まず、この目標を達成 できたかどうかを評価するための、評価基準を作成する流れを見てみましょう。全体の流れは、以下の ようになります。 図 2-10 「評価基準」 と 「評価シート」 作成の流れ 評価基準を作成する 1.評価の観点を決める① 1、2 3 【仕事と職業】 評価基準表 評価の観点 1 2 3 4 がんばって! もう少し! できた! すばらしい! 人などに、自分たちの部署の 人などに、自分たちの部署の 人などに、自分たちの部署の 人などに、自分たちの部署の 仕事内容について、日本人が 仕事内容について、日本人が 仕事内容について、日本人が 仕事内容について、日本人が 2.評価の観点を決める② 内容・活動 知っておいたほうがいい情報 知っておいたほうがいい情報 知っておいたほうがいい情報 知っておいたほうがいい情報 や、日本の会社との違いや共 や、日本の会社との違いや共 や、日本の会社との違いや共 や、日本の会社との違いや共 通点に少しふれながら、短い 通点に少しふれながら、事が 通点にふれながら、ある程度 通点にふれながら、順序だて 簡単な言葉で説明することが らを列挙して、ある程度詳し 詳しく説明することができる。 て、わかりやすく説明するこ できる。 く説明することができる。 とができる。 ポイントを簡単に並べ、 「∼て」「それから」 「しかし」などの 短いいくつかの要素を「まず」 要点の 組み 立て は 直線的だ 4、5 「∼ が 」な ど の 簡単な 接続表 よく使われる接続表現を使っ 「∼てから」 「∼場合」などの が、ある程度流暢にまとまり 談話構成 3.評価基準で扱うレベルを決める 実践編 新しく日本から赴任してきた 新しく日本から赴任してきた 新しく日本から赴任してきた 新しく日本から赴任してきた 現を使って語句や簡単な文を て文をつなげて、何かを描写 接続表現を使ってつなげて、 のある話をすることができる。 つなげて話すことができる。 したり、語ったりすることが 直線的だが、単純な筋を語っ できる。 たり、描写したりすることが できる。 言葉に詰まったり、言い直す 間があいたり、言い直したり、 文法や語彙を正確に使おうと 言いたいことを比較的困難な ことがかなり多いが、なじみ 言い換えたりすることが多い して間があいたり言い直した く表現できる。間があいたり 流暢さ 度言いたいことを表現でき、 いことを相手に理解させるこ 困難なく、ある程度の長さの が、人の助けを借りずに話を 短いやり取りを行うことがで とができる。 わかりやすい話をすることが 続けられる。 きる。 できる。 自分の仕事について、ごく基 自分の仕事に関する事がらに 自分の仕事に関する事がらに 複雑な考えを述べるのは難し 本的なコミュニケーションが ついて、日常生活上の交渉を ついて、多少回りくどい言い いが、自分の仕事に関する大 語彙 できる程度の語彙を持ってい 行える程度の語彙を持ってい 方をしても自分の述べたいこ 部分の事がらについて、自分 て、使うことができる。 て、使うことができる。 とを述べられる程度の語彙を の述べたいことを述べられる 持っていて、使うことができ 程度の語彙を持っていて、使 る。 うことができる。 いくつかの文型を使うことが 依然としてくり返される間違 比較的予測可能な 状況で、頻 母語の影響や誤りも見られる できる。いつもくり返される いがあるが、簡単な文型であ 繁に使われる文型をだいたい が、なじみのある状況であれ 文法 基本的な間違いがあるが、何 れば正しく使うことができる。 正確に使うことができる ば、だいたい正確に文法を使 を言おうとしているのかはた うことができる。 いてい明らかである。 明らかな母語の発音の影響が 母語の発音の影響があり、少 ときどき母語の発音の影響が 多少母語の発音の影響があっ あり、相手が聞き返すことも しわかりにくいところもある 目立ったり、発音を間違える たり、発音を間違えることも 発音 あるが、短い簡単な語句や文 が、相手がだいたい理解でき こともあるが、相手が理解で あるが、相手にわかりやすく、 であれば、理解できる程度の る程度にははっきりした発音 きる程度にはっきりとした発 はっきりとした発音で話すこ 発音で話すことができる。 で話すことができる。 音で話すことができる。 とができる。 5.「Can-do」を わかりやすい文に書きかえる 評価基準の完成! 6.評価基準をもとに 評価シートを作成する 評価シートの完成! 57 コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 4. 「みんなの 「Can-do」 サイト」 を利用して、該当するレベルとカテ ゴリーの「Can-do」を選び、選んだ 「Can-do」をフォーマットに入れる のある話題であれば、ある程 が、短い話であれば、言いた りすることはあるが、あまり 行き詰ったりすることはある ■このコースの場合… ―評価基準と評価シートを作る― このコースでは、縦軸に評価の観点、横軸に達成度を配置した以下の表 2-4のような評価基準フォー マットを使います。 表 2-4 評価基準のフォーマット例 達成度 評価の観点 実践編 では、評価基準を作成する流れを詳しく見ていきましょう。 コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 1.評価の観点を決める① 「自己評価チェックリストを作る」で選んだ「Can-do」をよく吟味し、 「JF スタンダードの木」を見て、目標レベルである B1の産出(話す) の言語活動に必要な言語能力はどのようなものであるかを考えます。 「2.1コースをデザインする」の「(3)学習成果の評価について考 える」でも述べたように、このコースでは、B1レベルの産出(話す)では能力 Can-do の中の以下のようなカテゴリーの言語能力の向上が熟達の鍵をにぎっていると考え、こ れらを評価の重要な観点として選びました。 【j 話題の展開】 【k 一貫性と結束性】 【l 話しことばの流暢さ】 また、語彙や文法などもこのレベルでは必要であると考え、以下のカテゴリーも評価 の観点に含めることにしました。 【b 使用語彙領域】 【c 語彙の使いこなし】 【d 文法的正確さ】 【e 音素の把握】 58 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 2.評価の観点を決める② このコースでは、ステップ1で選んだカテゴリーのほかに、以下のトピックの学習 目標も、評価の観点の1つとして利用し、異文化理解の視点も含めて評価します。 「仕事と職業」新しく日本から赴任してきた人などに、自分たちの部署の仕事 内容について、日本人が知っておいたほうがいい情報や、日本 の会社との違いや共通点にふれながら、ある程度詳しく説明す ることができる。 「旅行と交通」日本人旅行者に、有名な観光地について、日本人が持っている 情報をふまえて、ある程度詳しく説明することができる。 「言語と文化」日本人を自宅に招待したとき、自国と日本の生活習慣(結婚式 や年中行事など)の違いや共通点について、例をあげて、ある 程度詳しく説明することができる。 この評価の観点は、「内容・活動」と名づけます。 ステップ1で選んだカテゴリーも、カテゴリーの名前が長く難しいものは、適宜、 【l 話しことばの流暢さ】 → 「流暢さ」 【b 使用語彙領域】【c 語彙の使いこなし】 → 2つまとめて「語彙」 【d 文法的正確さ】 → 「文法」 実践編 わかりやすい名前に変えましょう。次の表 2-5の例では、以下のように変更しました。 【e 音素の把握】 → 「発音」 「流暢さ」、「語彙」、「文法」、「発音」の7項目を評価の観点とします。 表 2-5 評価基準のフォーマット例(評価の観点を記入したもの) 評価の観点 内容・活動 話題の展開 一貫性と結束性 流暢さ 語彙 文法 発音 59 コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 以上のように、このコースでは、 「内容・活動」 、 「話題の展開」 、 「一貫性と結束性」 、 3.評価基準で扱うレベルを決める このコースでは、学習者の話す力の差が小さいため、コースの目標レベルである B1の「Can-do」と、学習者の現在の熟達度である A2の「Can-do」を利用して、評 価基準を作成します。 学習者の話す力に大きな差がある場合は、A1から B2までを利用するなど、教育現 場の現状に合わせて、評価基準で扱うレベルの幅を検討してください。 このコースでは、評価基準の達成度を4段階に設定します。このコースの目標レベ ルである B1(さらに細かく分かれている場合は B1.1)は、4段階の達成度の「3」 に置き、その少し上のレベルを「4」としました。これは、B1レベルのことが達成 できて学習は終わりではなく、次の目標が見えるような形にし、学習者の動機づけと なるようにするためです。 【評価基準の達成度の例】 「4 すばらしい!」 実践編 「3 できた!」…B1(B1.1)レベル (目標とするレベル) コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 60 「2 もう少し!」 「1 がんばって!」 表 2-6 評価基準のフォーマット例(達成度を記入したもの) 評価の観点 内容・活動 話題の展開 一貫性と結束性 流暢さ 語彙 文法 発音 1 2 3 4 がんばって! もう少し! できた! すばらしい! JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 4.「みんなの 「Can-do」 サイト」を利用して、 該当するレベルとカテゴリーの「Can-do」を選び、 選んだ「Can-do」をフォーマットに入れる ステップ1で選んだカテゴリーの A2と B1の「Can-do」を「みんなの 「Can-do」 サイト」から出力し、表 2-6のフォーマットの各欄に配置します。カテゴリーによっ ては、A2レベル、B1レベルが細かいレベル(A2.1、A2.2、B1.1、B1.2)に分か れていないため、2段階の達成度に「Can-do」が1つしかないこともあります。また、 ある1つの段階に複数の「Can-do」があてはまる場合もありますが、この段階では、 それらはそのままフォーマットに入れます。 次の表 2-7は、 「みんなの「Can-do」サイト」から出力した「Can-do」一覧の抜粋です。 表 2-8は、それらの「Can-do」をフォーマットに入れた例です。評価の観点の1 つ目の項目「内容・活動」は、サイトから選んだ「Can-do」そのものではなく、学 習目標を利用するので、「3 できた!」の部分に「仕事と職業」トピックの学習目 表 2-7 サイトから出力した「Can-do」一覧の抜粋 種別 CEFR A2.1 A2.2 種類 能力 能力 CEFR B1 能力 CEFR A2 能力 CEFR B1 能力 CEFR A2 能力 CEFR B1 能力 言語活動 語用能力 語用能力 語用能力 言語構造 的能力 言語構造 的能力 言語構造 的能力 言語構造 的能力 カテゴリー 一貫性と結束性 (ディスコース能力) 一貫性と結束性 (ディスコース能力) 一貫性と結束性 (ディスコース能力) Can-do 本文(日本語) 「そして」、“but” 「しかし」、“because” 「~だから」の “and” ような簡単な接続表現を用いて語句の間に繫がりをつけること ができる。 最も頻繁に出現する接続表現を使って、単純な文をつなげ、物 事を語ったり、描写することができる。 短めの、単純で、バラバラな成分をいろいろ結び合わせて、直 線的に並べて、繫がりをつけることができる。 話の相手から時々、繰り返しを求められることもあり、明らか 音素の把握 な外国語訛りが見られるものの、大体の場合、発音は理解でき る程度にははっきりとしている。 音素の把握 語彙の使いこなし 時には外国語訛りが目立ったり、発音の間違えもあるが、大体 よく理解できるくらいに発音は明瞭である。 具体的な日々の要求に関する狭いレパートリーの語を使うこと ができる。 複雑な考えや、非日常的な話題や状況に関して何かを述べよう 語彙の使いこなし CEFR A2.1 能力 言語能力 使用語彙領域 CEFR A2.1 能力 言語能力 使用語彙領域 CEFR A2.2 能力 言語能力 使用語彙領域 とすると、大きな誤りをすることがあるが、初歩的な語彙は使 いこなせる。 基本的なコミュニケーションの要求を満たすことができるだけ の語彙を持っている。 生活上の単純な要求に対応できるだけの語彙を持っている。 馴染みのある状況や話題に関して、日常的な生活上の交渉を行 うのに十分な語彙を持っている。 家族、趣味や関心、仕事、旅行、時事問題など、本人の日常生 CEFR B1 能力 言語能力 使用語彙領域 活に関わる大部分の話題について、多少間接的な表現を使って でも、自分の述べたいことを述べられるだけの語彙を持っている。 いくつかの単純な文法構造を正しく使うことができるが、依然 として決まって犯す基本的な間違いがある―例えば、時制を混 CEFR A2 能力 言語能力 文法的正確さ 同したり、性・数・格などの一致を忘れたりする傾向がある。 しかし、本人が何を言おうとしているのかはたいていの場合明 らかである。 61 CEFR B1.1 能力 言語能力 文法的正確さ 比較的予測可能な状況で、頻繁に使われる「繰り返し」やパター コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う CEFR レベル 実践編 標を入れます。 表 2-8 サイトから出力した「Can-do」を評価基準のフォーマットに入れた例 評価の観点 1 2 3 4 がんばって! もう少し! できた! すばらしい! A2 B1 新しく日本から赴任してき た人などに、自分たちの部 署の仕事内容について、日 本人が知っておいたほうが 内容・活動 いい情報や、日本の会社と の違いや共通点にふれなが ら、ある程度詳しく説明す ることができる。 話題の展開 ポイントを簡単に並べ上げる形で、物事を語ったり事 事柄を 直線的に 並べ て い っ て、比較的流暢に、簡単な 物を記述できる。(A2) 語りや記述ができる。(B1) “and” 「そして」 、“but” 「し 最も頻繁に出現する接続表 短めの、単純で、バラバラな成分をいろいろ結び合わせ か し 」、“because”「~ だ 現を使って、単純な文をつ て、直線的に並べて、繫がりをつけることができる。 (B1) 一貫性と結束性 から」のような簡単な接続 な げ、物事を 語っ た り、 表現を用いて語句の間に繫 描写す る こ と が で き る。 がりをつけることができる。(A2.2) (A2.1) 言葉に詰まったり、話し始 話し始めて言い直したり、 ある程度の長さの、理解可 自分の表現したいことを、 めて言い直すことが目立っ 途中で言い換えたりするこ 能な発話を行うことができ 比較的容易に表現できる。 て多いが、馴染みのある話 とが目立つが、短い発話で るが、制限を受けない自由 言語化する際に、間があい 題であれば、あまり困難な あ れ ば 自分の 述べ た い こ な発話で比較的長いものに た り、「 袋小路」に 入り 込 実践編 流暢さ く言いたいことを言葉に表 と を 理解し て も ら え る。 なると特に、談話を続けて んだりはするものの、他人 現でき、短いやり取りを行 (A2.2) いく時に文法的および語彙 の助けを借りずに発話を続 うことができる。(A2.1) 的に正確であろうとして間 けることができる。 (B1.2) があいたり、発話の修復を 行うのが目立つ。 (B1.1) ・基本的な コ ミ ュ ニ ケ ー 馴染みのある状況や話題に 家族、趣味や 関心、仕事、旅行、時事問題な ど、本人 ションの要求を満たすこと 関して、日常的な生活上の の 日常生活に 関わ る 大部分の 話題に つ い て、多少間接 ができるだけの語彙を持っ 交渉・取引を 行う の に 充 的な表現を使ってでも、自分の述べたいことを述べら ている。(A2.1 使用語彙 分な 語彙を 持っ て い る。 れるだけの語彙を持っている。(B1 使用語彙領域) 領域) コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 語彙 (A2.2 使用語彙領域) ・生活上の単純な要求に対 応できるだけの語彙を持っ ている。(A2.1 使用語彙 領域) 具体的な日々の要求に関する狭いレパートリーの語を 複雑な 考え や、非日常的な 話題や 状況に 関し て 何か を 使うことができる。(A2 語彙の使いこなし) いくつかの単純な文法構造を正しく使うことができる 比較的予測可能な状況で、 馴染みのある状況では、割 が、依然として決まって犯す基本的な間違いがある― 頻繁に使われる「繰り返し」 合正確にコミュニケーショ 例え ば、時制を 混同し た り、性・数・格な ど の 一致を やパターンのレパートリー ンを行うことができる。多 忘れたりする傾向がある。しかし、本人が何を言おう を、割合正確に使うことが くの場合高いレベルでの駆 文法 としているのかはたいていの場合明らかである。 (A2) できる。(B1.1) 使能力があるが、母語の影 響が明らかである。誤りも 見られるが、本人が述べよ うとしていることは明らか に分かる。(B1.2) 話の相手から時々、繰り返しを求められることもあり、 時には外国語訛りが目立ったり、発音の間違えもある 発音 明らかな外国語訛りが見られるものの、大体の場合、 が、大体よく理解できるくらいに発音は明瞭である。 (B1) 発音は理解できる程度にははっきりとしている。 (A2) 62 述べようとすると、大きな誤りをすることがあるが、 初歩的な語彙は使いこなせる。 (B1 語彙の使いこなし) JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 5.「Can-do」をわかりやすい文に書きかえる 評価基準のフォーマットに入れた「Can-do」を、もとの内容を活かしながら、学 習者にもわかりやすい文に書きかえます。学習者の母語が同じ場合は、母語を利用す ることもできます。達成できていないことや足りない点を書くのではなく、達成でき ていることを前向きな表現で書くことによって、学習者の動機づけとなります。 あるカテゴリーの、ある達成度で、複数の「Can-do」が当てはまる場合は、目標 に照らし合わせて、それぞれの「Can-do」から合う内容を抽出し、まとめます。また、 複数の達成度に対して「Can-do」が1つしかない場合は、内容を段階づけして分け ることが必要になります。 ※評価の観点のうち、「内容・活動」については、学習目標を利用することをステッ プ2で述べました。学習目標は B1レベルの MY Can-do になっているので、達成度 の「3」はこのままの記述を利用します。達成度の 「1」 「2」 「4」 への書きかえに ついては、もとになる「Can-do」がないので、「1.3「 Can-do」を理解する」を ☝書きかえにおける確認ポイント 実践編 参考にしてください。 • 目標に照らし合わせて、関係のない内容が含まれていませんか? • ある評価の観点の各達成度で、同じポイントについての記述になっていますか? • 否定的な表現を使っていませんか? 貫性と結束性】の「Can-do」は同じような内容を含んでいたので、2つをまとめて「談 話構成」としました。 完成した評価基準の例が、次の図 2-11です。図 2-11は、 「仕事と職業」トピックの、 「新しく日本から赴任してきた人などに、自分たちの部署の仕事内容について、日本 人が知っておいたほうがいい情報や、日本の会社との違いや共通点にふれながら、あ る程度詳しく説明することができる。」という目標と、それにもとづく学習活動をふ まえた内容になっています。 63 コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う ステップ4で作った表 2-8の中の「Can-do」を見ると、【j 話題の展開】と【k 一 図 2-11 完成した評価基準の例 【仕事と職業】 評価基準表 評価の観点 1 2 3 4 がんばって! もう少し! できた! すばらしい! 新しく日本から赴任してきた 新しく日本から赴任してきた 新しく日本から赴任してきた 新しく日本から赴任してきた 人などに、自分たちの部署の 人などに、自分たちの部署の 人などに、自分たちの部署の 人などに、自分たちの部署の 仕事内容について、日本人が 仕事内容について、日本人が 仕事内容について、日本人が 仕事内容について、日本人が 内容・活動 知っておいたほうがいい情報 知っておいたほうがいい情報 知っておいたほうがいい情報 知っておいたほうがいい情報 や、日本の会社との違いや共 や、日本の会社との違いや共 や、日本の会社との違いや共 や、日本の会社との違いや共 通点に少しふれながら、短い 通点に少しふれながら、事が 通点にふれながら、ある程度 通点にふれながら、順序だて 簡単な言葉で説明することが らを列挙して、ある程度詳し 詳しく説明することができる。 て、わかりやすく説明するこ できる。 く説明することができる。 とができる。 ポイントを簡単に並べ、 「~て」「それから」「しかし」などの 短いいくつかの要素を「まず」 要点の 組み 立て は 直線的だ 「~ が 」な ど の 簡単な 接続表 よく使われる接続表現を使っ 「~てから」「~場合」などの が、ある程度流暢にまとまり 談話構成 現を使って語句や簡単な文を て文をつなげて、何かを描写 接続表現を使ってつなげて、 のある話をすることができる。 つなげて話すことができる。 したり、語ったりすることが 直線的だが、単純な筋を語っ できる。 たり、描写したりすることが できる。 言葉に詰まったり、言い直す 間があいたり、言い直したり、 文法や語彙を正確に使おうと 言いたいことを比較的困難な ことがかなり多いが、なじみ 言い換えたりすることが多い して間があいたり言い直した く表現できる。間があいたり 流暢さ のある話題であれば、ある程 が、短い話であれば、言いた りすることはあるが、あまり 行き詰ったりすることはある 度言いたいことを表現でき、 いことを相手に理解させるこ 困難なく、ある程度の長さの が、人の助けを借りずに話を 実践編 短いやり取りを行うことがで とができる。 わかりやすい話をすることが 続けられる。 きる。 できる。 自分の仕事について、ごく基 自分の仕事に関する事がらに 自分の仕事に関する事がらに 複雑な考えを述べるのは難し 本的なコミュニケーションが ついて、日常生活上の交渉を ついて、多少回りくどい言い いが、自分の仕事に関する大 語彙 できる程度の語彙を持ってい 行える程度の語彙を持ってい 方をしても自分の述べたいこ 部分の事がらについて、自分 て、使うことができる。 て、使うことができる。 とを述べられる程度の語彙を の述べたいことを述べられる 持っていて、使うことができ 程度の語彙を持っていて、使 る。 うことができる。 いくつかの文型を使うことが 依然としてくり返される間違 比較的予測可能な 状況で、頻 母語の影響や誤りも見られる コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 64 できる。いつもくり返される いがあるが、簡単な文型であ 繁に使われる文型をだいたい が、なじみのある状況であれ 文法 基本的な間違いがあるが、何 れば正しく使うことができる。 正確に使うことができる ば、だいたい正確に文法を使 を言おうとしているのかはた うことができる。 いてい明らかである。 明らかな母語の発音の影響が 母語の発音の影響があり、少 ときどき母語の発音の影響が 多少母語の発音の影響があっ あり、相手が聞き返すことも しわかりにくいところもある 目立ったり、発音を間違える たり、発音を間違えることも 発音 あるが、短い簡単な語句や文 が、相手がだいたい理解でき こともあるが、相手が理解で あるが、相手にわかりやすく、 であれば、理解できる程度の る程度にははっきりした発音 きる程度にはっきりとした発 はっきりとした発音で話すこ 発音で話すことができる。 で話すことができる。 音で話すことができる。 とができる。 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 6.評価基準をもとに、評価シートを作成する ステップ5で完成した評価基準をもとに、教師用と発表者用の評価シートを作成し ます。 このコースでは、教師用も発表者用も、評価基準のフォーマットと記述内容をその まま利用し、あてはまる達成度にチェックする方法にしました。 評価シートには、学習者や教師が自由にコメントを記述する欄を設けました。 学習者は、自分のスピーチを録音したものを授業後に聞いて、チェックすることが できます。教師は、スピーチを聞きながらチェックすることもできるし、録音したも のを聞いてチェックすることもできます。 次の図 2-12と図 2-13は、評価基準を利用して作成した評価シートの例です。 実践編 コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 65 図 2-12 評価基準をもとに作成した評価シートの例(発表者用) 〈発表者用〉 【目標】 仕事と職業 新しく日本から赴任してきた人などに、自分たちの部署の仕事内容 について、日本人が知っておいたほうがいい情報や、日本の会社と の違いや共通点にふれながら、ある程度詳しく説明することができる。 名前 評価の観点 1 2 3 4 がんばって! もう少し! できた! すばらしい! 新しく日本から赴任してきた 新しく日本から赴任してきた 新しく日本から赴任してきた 新しく日本から赴任してきた 人などに、自分たちの部署の 人などに、自分たちの部署の 人などに、自分たちの部署の 人などに、自分たちの部署の 仕事内容について、日本人が 仕事内容について、日本人が 仕事内容について、日本人が 仕事内容について、日本人が 内容・活動 知っておいたほうがいい情報 知っておいたほうがいい情報 知っておいたほうがいい情報 知っておいたほうがいい情報 や、日本の会社との違いや共 や、日本の会社との違いや共 や、日本の会社との違いや共 や、日本の会社との違いや共 通点に少しふれながら、短い 通点に少しふれながら、事が 通点にふれながら、ある程度 通点にふれながら、順序だて 簡単な言葉で説明することが らを列挙して、ある程度詳し 詳しく説明することができる。 て、わかりやすく説明するこ できる。 く説明することができる。 とができる。 ポイントを簡単に並べ、 「~て」「それから」「しかし」などの 短いいくつかの要素を「まず」 要点の 組み 立て は 直線的だ 「~ が 」な ど の 簡単な 接続表 よく使われる接続表現を使っ 「~てから」「~場合」などの が、ある程度流暢にまとまり 談話構成 現を使って語句や簡単な文を て文をつなげて、何かを描写 接続表現を使ってつなげて、 のある話をすることができる。 つなげて話すことができる。 したり、語ったりすることが 直線的だが、単純な筋を語っ できる。 たり、描写したりすることが できる。 言葉に詰まったり、言い直す 間があいたり、言い直したり、 文法や語彙を正確に使おうと 言いたいことを比較的困難な 実践編 ことがかなり多いが、なじみ 言い換えたりすることが多い して間があいたり言い直した く表現できる。間があいたり 流暢さ のある話題であれば、ある程 が、短い話であれば、言いた りすることはあるが、あまり 行き詰ったりすることはある 度言いたいことを表現でき、 いことを相手に理解させるこ 困難なく、ある程度の長さの が、人の助けを借りずに話を 短いやり取りを行うことがで とができる。 わかりやすい話をすることが 続けられる。 きる。 できる。 自分の仕事について、ごく基 自分の仕事に関する事がらに 自分の仕事に関する事がらに 複雑な考えを述べるのは難し 本的なコミュニケーションが ついて、日常生活上の交渉を ついて、多少回りくどい言い いが、自分の仕事に関する大 語彙 できる程度の語彙を持ってい 行える程度の語彙を持ってい 方をしても自分の述べたいこ 部分の事がらについて、自分 て、使うことができる。 て、使うことができる。 とを述べられる程度の語彙を の述べたいことを述べられる 持っていて、使うことができ 程度の語彙を持っていて、使 コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 66 る。 うことができる。 いくつかの文型を使うことが 依然として繰り返される間違 比較的予測可能な 状況で、頻 母語の影響や誤りも見られる できる。決まって犯す基本的 いがあるが、簡単な文型であ 繁に使われる文型をだいたい が、なじみのある状況であれ 文法 な間違いがあるが、何を言お れば正しく使うことができる。 正確に使うことができる ば、だいたい正確に文法を使 うとしているのかはたいてい うことができる。 明らかである。 明らかな母語の発音の影響が 母語の発音の影響があり、少 ときどき母語の発音の影響が 多少母語の発音の影響があっ あり、相手が聞き返すことも しわかりにくいところもある 目立ったり、発音を間違える たり、発音を間違えることも 発音 あるが、短い簡単な語句や文 が、相手がだいたい理解でき こともあるが、相手が理解で あるが、相手にわかりやすく、 であれば、理解できる程度の る程度にははっきりした発音 きる程度にはっきりとした発 はっきりとした発音で話すこ 発音で話すことができる。 できたこと/よかったところ で話すことができる。 音で話すことができる。 とができる。 むずかしかったこと/これからがんばること JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 図 2-13 評価基準をもとに作成した評価シートの例(教師用) 〈教師用〉 【目標】 仕事と職業 新しく日本から赴任してきた人などに、自分たちの部署の仕事内容 について、日本人が知っておいたほうがいい情報や、日本の会社と の違いや共通点にふれながら、ある程度詳しく説明することができる。 名前 評価の観点 1 2 3 4 がんばって! もう少し! できた! すばらしい! 新しく日本から赴任してきた 新しく日本から赴任してきた 新しく日本から赴任してきた 新しく日本から赴任してきた 人などに、自分たちの部署の 人などに、自分たちの部署の 人などに、自分たちの部署の 人などに、自分たちの部署の 仕事内容について、日本人が 仕事内容について、日本人が 仕事内容について、日本人が 仕事内容について、日本人が 内容・活動 知っておいたほうがいい情報 知っておいたほうがいい情報 知っておいたほうがいい情報 知っておいたほうがいい情報 や、日本の会社との違いや共 や、日本の会社との違いや共 や、日本の会社との違いや共 や、日本の会社との違いや共 通点に少しふれながら、短い 通点に少しふれながら、事が 通点にふれながら、ある程度 通点にふれながら、順序だて 簡単な言葉で説明することが らを列挙して、ある程度詳し 詳しく説明することができる。 て、わかりやすく説明するこ できる。 く説明することができる。 とができる。 ポイントを簡単に並べ、 「~て」「それから」「しかし」などの 短いいくつかの要素を「まず」 要点の 組み 立て は 直線的だ 「~ が 」な ど の 簡単な 接続表 よく使われる接続表現を使っ 「~てから」「~場合などの接 が、ある程度流暢にまとまり 談話構成 現を使って語句や簡単な文を て文をつなげて、何かを描写 続表現を使ってつなげて、直 のある話をすることができる。 つなげて話すことができる。 したり、語ったりすることが 線的だが、単純な筋を語った できる。 り、描写したりすることがで きる。 言葉に詰まったり、言い直す 間があいたり、言い直したり、 文法や語彙を正確に使おうと 言いたいことを比較的困難な 流暢さ 度言いたいことを表現でき、 いことを相手に理解させるこ 困難なく、ある程度の長さの が、人の助けを借りずに話を 短いやり取りを行うことがで とができる。 わかりやすい話をすることが 続けられる。 きる。 できる。 実践編 ことがかなり多いが、なじみ 言い換えたりすることが多い して間があいたり言い直した く表現できる。間があいたり のある話題であれば、ある程 が、短い話であれば、言いた りすることはあるが、あまり 行き詰ったりすることはある 自分の仕事について、ごく基 自分の仕事に関する事がらに 自分の仕事に関する事がらに 複雑な考えを述べるのは難し 本的なコミュニケーションが ついて、日常生活上の交渉を ついて、多少回りくどい言い いが、自分の仕事に関する大 語彙 できる程度の語彙を持ってい 行える程度の語彙を持ってい 方をしても自分の述べたいこ 部分の事がらについて、自分 て、使うことができる。 て、使うことができる。 とを述べられる程度の語彙を の述べたいことを述べられる 持っていて、使うことができる。 程度の語彙を持っていて、使 いくつかの文型を使うことが 依然としてくり返される間違 比較的予測可能な 状況で、頻 母語の影響も見られるが、な できる。いつもくり返される いがあるが、簡単な文型であ 繁に使われる文型をだいたい じみのある状況であれば、だ 文法 犯す 基本的な 間違い が あ る れば正しく使うことができる。 正確に使うことができる いたい正確に文法を使うこと が、何を言おうとしているの ができる。 かはたいてい明らかである。 明らかな母語の発音の影響が 母語の発音の影響があり、少 ときどき母語の発音の影響が 母語の 発音の 影響が あ っ た あり、相手が聞き返すことも しわかりにくいところもある 目立ったり、発音を間違える り、発音を間違えることもあ 発音 あるが、短い簡単な語句や文 が、相手がだいたい理解でき こともあるが、相手に理解さ るが、相手にわかりやすく、 であれば、理解できる程度の る程度にははっきりした発音 れる程度にはっきりとした発 はっきりとした発音で話すこ 発音で話すことができる。 よかったところ で話すことができる。 音で話すことができる。 とができる。 これからがんばること 67 コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う うことができる。 以上、コース目標や授業活動にもとづいて、学習目標、自己評価チェックリスト、評価基準、評価シー トを作成する過程を紹介しました。 「JF スタンダードの木」や「Can-do」の6レベル、 「みんなの「Can-do」 サイト」を活用することによって、自己評価チェックリストや評価基準が作成しやすくなるでしょう。 評価シートについては、今回は、評価基準をそのまま利用したシンプルなものを紹介しました。どの ような項目を含めたものにするかについては、ここで述べたこと以外にも、口頭能力評価の先行研究な どを参考にして検討し、各教育現場の状況に合わせながら、評価したいことが測れるようなものを作成 してください。 今回は話す力を測るための評価基準や評価シートの作成手順を紹介しましたが、同じように、 書く力を測るための評価基準や評価シートを作成する場合にも、これらの作成手順は参考にな るでしょう。「1.4 ポートフォリオを理解する」で紹介している作文の評価基準や評価シートも 参考にしてください。 実践編 コースデザインに﹁ Can-do ﹂を使う 68 参考資料 参考資料 参考資料1:CEFR 共通参照レベル:自己評価表 A1 聞くこと 理解すること 読むこと やり取り 話すこと 表現 書くこと 書くこと 参考資料 70 A2 B1 はっきりとゆっくりと話しても (ごく基本的な個人や家族の情 仕事、学校、娯楽で普段出合う らえれば、自分、家族、すぐ周 報、買い物、近所、仕事などの) ような身近な話題について、明 りの具体的なものに関する聞き 直接自分につながりのある領域 瞭で標準的な話し方の会話なら 慣れた語やごく基本的な表現を で最も頻繁に使われる語彙や表 要点を理解することができる。 聞き取れる。 現を理解することができる。 話し方が比較的ゆっくり、はっ 短い、は っ き り と し た 簡単な きりとしているなら、時事問題 メッセージやアナウンスの要点 や、個人的もしくは仕事上の話 を聞き取れる。 題についても、ラジオやテレビ 番組の要点を理解することがで きる。 例えば、掲示やポスター、カタ ログの中のよく知っている名 前、単語、単純な文を理解でき る。 ごく短い簡単なテクストなら理 解できる。 広告や 内容紹介の パ ン フ レ ッ ト、メニュー、予定表のような ものの中から日常の単純な具体 的に予測がつく情報を取り出せ る。 簡単で短い個人的な手紙は理解 できる。 相手がゆっくり話し、繰り返し 単純な日常の仕事の中で、情報 たり、言い換えたりしてくれて、 の 直接の や り 取り が 必要な ら また自分が言いたいことを表現 ば、身近な話題や活動について するのに助け船を出してくれる 話し合いができる。 なら、簡単なやり取りをするこ 通常は会話を続けていくだけの とができる。 理解力はないのだが、短い社交 直接必要なことやごく身近な話 的なやり取りをすることはでき 題についての簡単な質問なら、 る。 聞いたり答えたりできる。 非 常 によく使 われる日常言語 や、自分の仕事関連の言葉で書 かれたテクストなら理解できる。 起こったこと、感情、希望が表 現されている私信を理解できる。 当該言語圏の旅行中に最も起こ りやすいたいていの状況に対処 することができる。 例えば、家族や趣味、仕事、旅 行、最近の出来事など、日常生 活に直接関係のあることや個人 的な関心事について、準備なし で会話に入ることができる。 ど こ に 住ん で い る か、ま た、 家族、周囲の人々、居住条件、 簡単な方法で語句をつないで、 知っている人たちについて、簡 学歴、職歴を簡単な言葉で一連 自分の 経験や 出来事、夢や 希 単な語句や文を使って表現でき の語句や文を使って説明できる。 望、野心を語ることができる。 る。 意見や計画に対する理由や説明 を簡潔に示すことができる。 物語を語ったり、本や映画のあ らすじを話し、またそれに対す る感想・考えを表現できる。 新年の挨拶など短い簡単な葉書 を書くことができる。例えばホ テルの宿帳に名前、国籍や住所 といった個人のデータを書き込 むことができる。 直接必要のある領域での事柄な ら簡単に短いメモやメッセージ を書くことができる。 短い個人的な手紙なら書くこと ができる:例えば礼状など。 身近で個人的に関心のある話題 について、つながりのあるテク ストを書くことができる。私信 で経験や印象を書くことができ る。 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック B2 C1 C2 長い会話や講義を理解することが できる。また、もし話題がある程 度身近な範囲であれば、議論の流 れが複雑であっても理解できる。 たいていのテレビのニュースや時 事問題の番組も分かる。 標準語の映画なら大多数は理解で きる。 たとえ構成がはっきりしなくて、 関係性が 暗示さ れ て い る に す ぎ ず、明示的でない場合でも、長い 話が理解できる。 特別の努力なしにテレビ番組や映 画を理解できる。 生であれ、放送されたものであれ、 母語話者の速いスピードで話され ても、その話し方の癖に慣れる時 間の余裕があれば、どんな種類の 話し言葉も難無く理解できる。 筆者の姿勢や視点が出ている現代 の問題についての記事や報告が読 める。 現代文学の散文は読める。 長い複雑な事実に基づくテクスト や文学テクストを、文体の違いを 認識しながら理解できる。 自分の関連外の分野での専門的記 事も長い技術的説明書も理解でき る。 抽象的で、構造的にも言語的にも 複雑な、たとえばマニュアルや専 門的記事、文学作品のテクストな ど、事実上あらゆる形式で書かれ た言葉を容易に読むことができる。 流暢に自然に会話をすることがで き、母語話者と普通にやり取りが できる。 身近なコンテクストの議論に積極 的に参加し、自分の意見を説明 し、弁明できる。 言葉をことさら探さずに流暢に自 慣用表現、口語体表現をよく知っ 然に自己表現ができる。 ていて、いかなる会話や議論でも 社会上、仕事上の目的に合った言 努力しないで加わることができる。 葉遣いが、意のままに効果的にで 自分を流暢に表現し、詳細に細か きる。 い意味のニュアンスを伝えること 自分の考えや意見を正確に表現で ができる。 き、自分の発言を上手に他の話し 表現上の困難に出合っても、周り 手の発言にあわせることができる。 の人がそれにほとんど気がつかな いほどに修正し、うまく繕うこと ができる。 自分の興味関心のある分野に関連 する限り、幅広い話題について、 明瞭で詳細な説明をすることがで きる。 時事問題について、いろいろな可 能性の長所、短所を示して自己の 見方を説明できる。 複雑な話題を、派生的話題にも立 ち入って、詳しく論ずることがで き、一定の観点を展開しながら、 適切な結論でまとめ上げることが できる。 興味関心のある分野内なら、幅広 くいろいろな話題について、明瞭 で詳細な説明文を書くことができ る。 エッセイやレポートで情報を伝 え、一定の視点に対する支持や反 対の理由を書くことができる。 手紙の中で、事件や体験について 自分にとっての意義を中心に書く ことができる。 適当な長さでいくつかの視点を示 明瞭な、流暢な文章を適切な文体 して、明瞭な構成で自己表現がで で書くことができる。 きる。 効果的な論理構造で事情を説明 自分が重要だと思う点を強調しな し、その重要点を読み手に気づか がら、手紙やエッセイ、レポート せ、記憶にとどめさせるように、 で複雑な主題を扱うことができる。 複雑な内容の手紙、レポート、記 読者を念頭に置いて適切な文体を 事を書くことができる。 選択できる。 仕事や文学作品の概要や評を書く ことができる。 状況にあった文体で、はっきりと すらすらと流暢に記述や論述がで きる。効果的な論理構成によって 聞き手に重要点を把握させ、記憶 にとどめさせることができる。 Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment . Cambridge: Cambridge University Press. 『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』初版第1刷、吉島茂、大橋理枝(訳、編) Council of Europe(2004) 朝日出版社(第二版作成にあたり参考資料中の漢字表記を一部修正した) 71 参考資料 参考資料 参考資料2: 言語能力と言語活動のカテゴリー一覧 分類 カテゴリー No. 1 2 3 カテゴリーの説明 聞くこと全般 聞くことに関する全般的な記述。 母語話者同士の会話を聞く 母語話者同士の会話を理解する。 講演やプレゼンテーションを聞く 講演やプレゼンテーションなどを、その場にいる聴衆として聞く。 指示やアナウンスを聞く 駅の構内放送など公共のアナウンスや、直接自分に向けられた指示を [CEFR: overall listening comprehension] [CEFR: understanding conversation between native speakers] [CEFR: listening as a member of a live audience] 4 聞く。 受容︵理解する︶ [CEFR: listening to announcements and instructions] 5 6 7 8 9 10 11 13 産出︵表現する︶ 活 動 コミュニケーション言語活動 12 14 15 16 17 18 19 21 相互行為︵やりとりする︶ 参考資料 20 音声メディアを聞く ラジオ番組などの音声メディアや録音された音声を聞く。 読むこと全般 読むことに関する全般的な記述。 手紙やメールを読む 手紙、ファックス、メールなどの通信文を読む。 必要な情報を探し出す 掲示、広告、資料などから、必要となる特定の情報を探し出す。 情報や要点を読み取る 新聞記事や専門的な資料の概要や要点を読み取る。 説明を読む 取扱説明書や規約など、指示や説明を読む。 テレビや映画を見る テレビ番組や映画など、映像を見ながら音声を聞く。 話すこと全般 話すことに関する全般的な記述。 [CEFR: overall oral production] 経験や物語を語る 自分が経験したこと、知っていること、物語などを語る。 論述する ディベートなどで自分の意見、理由や根拠を述べる。 公共アナウンスをする 公共の場でアナウンスをする。 [CEFR: public announcements] 講演やプレゼンテーションをする 講演、スピーチ、プレゼンテーションなど、聴衆に向かって話をする。 書くこと全般 書くことに関する全般的な記述。 作文を書く 自分が経験したこと、知っていること、物語などを書く。 レポートや記事を書く 情報をまとめて、レポート、報告書、記事などを書く。 口頭でのやりとり全般 口頭でのやりとりに関する全般的な記述。 母語話者とやりとりをする 母語話者を交えたやりとりをする。 社交的なやりとりをする 挨拶、社交辞令、世間話など、社会的な関係を維持するためのやりと [CEFR: listening to audio media and recordings] [CEFR: overall reading comprehension] [CEFR: reading correspondence] [CEFR: reading for orientation] [CEFR: reading for information & argument] [CEFR: reading instructions] [CEFR: watching TV and film] [CEFR: sustained monologue: describing experience] [CEFR: sustained monologue: putting a case (e.g. in a debate)] [CEFR: addressing audiences] [CEFR: overall written production] [CEFR: creative writing] [CEFR: reports and essays] [CEFR: overall spoken interaction] [CEFR: understanding a native speaker interlocutor] 22 りをする。 [CEFR: conversation] 23 24 インフォーマルな場面でやりとりをする 友人・知人とのインフォーマルな場面で、相談や意見交換をする。 フォーマルな場面で議論する 会議やディベートなどフォーマルな場面で議論をする。 共同作業中にやりとりをする イベントの企画や引越など、人との共同作業中にやりとりをする。 [CEFR: informal discussion (with friends)] [CEFR: formal discussion and meetings] 25 [CEFR: goal-oriented co-operation (e.g. repairing a car, discussing a document, organising an event)] 店や公共機関でやりとりをする 26 店や駅、役所、銀行などの公共機関で、商品やサービスを得るために やりとりをする。 [CEFR: transactions to obtain goods and services] 27 72 情報交換する 何かのために必要な、実質的な情報を交換する。 [CEFR: information exchange] JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 分類 カテゴリー No. 28 29 30 カテゴリーの説明 インタビューする/受ける インタビューをしたり、受けたりする。病院での診察も含まれる。 文書でのやりとり全般 文書を使ったやりとりに関する全般的な記述。 手紙やメールのやりとりをする 手紙、ファックス、メールなどでやりとりをする。 申請書類や伝言を書く 申請書類やアンケートなど、提示された書式に応じて記入したり、伝 [CEFR: interviewing and being interviewed] [CEFR: overall written interaction] [CEFR: correspondence] 31 言メモを書いたりする。 受容 [CEFR: notes, messages & forms] 32 33 意図を推測する 文脈から手がかりを発見し、意味や意図を推測する。 [CEFR: identifying cues and inferring (spoken & written)] 表現方法を考える 伝えたいことをどのように表現するか考える。 [CEFR: planning] 産出 (表現できないことを)他の方法で補う 34 適切に言い表せないことを、他の表現で言い換えたり、ジェスチャー で補ったりする。 方 略 [CEFR: compensating] 35 36 自分の発話をモニターする 自分の発話をモニターし、誤りを修正したり、言い直したりする。 [CEFR: monitoring and repair] 発言権を取る(ターン・テイキング) 適切に発言権(ターン)を取って、会話を始め、続け、終わらせる。 やりとり [CEFR: taking the floor (turntaking)] 議論の展開に協力する 37 相手の話に自分の話を関連づけたり、これまでの流れを確認したりし て、会話や議論の展開に協力する。 [CEFR: co-operating] 38 テクスト 説明を求める 理解できなかったことを確認したり、より詳しい説明を求めたりする。 メモやノートを取る 人の話を聞いてメモを取ったり、講義やセミナーなどでノートを取っ [CEFR: asking for clarification] 39 たりする。 [CEFR: note-taking (lectures, seminars, etc.)] 40 41 言語構造的能力 42 43 44 社会言語 能力 47 48 49 語用能力 50 51 テクストの内容を要約したり、重要な点を書き写したりする。 [CEFR: processing text] 使える言語の範囲 語彙、文法、音声、識字など使用可能な範囲について。 使用語彙領域 語彙知識の広さ。 語彙の使いこなし 語彙知識を使いこなす能力。 文法的正確さ 文法的な正確さ。 音素の把握 発音やイントネーションの知識とそれを使いこなす技能。 正書法の把握 つづり、書記法、句読点の使い方などの知識とそれを使いこなす技能。 [CEFR: general linguistic range] [CEFR: vocabulary range] [CEFR: vocabulary control] [CEFR: grammatical accuracy] [CEFR: phonological control] [CEFR: orthographic control] 社会言語的な適切さ 社会言語的な適切さ。 [CEFR: sociolinguistic appropriateness] 柔軟性(ディスコース能力) 場面や聞き手に応じて内容、話し方を調整する能力。 [CEFR: flexibility] 発言権(ディスコース能力) 発言を始め、続け、終わらせる能力。 [CEFR: turntaking] 話題の展開(ディスコース能力) 論点を並べたり、展開したりする能力。 [CEFR: thematic development] 一貫性と結束性(ディスコース能力) 接続表現や結合表現を使ってテクストを構成する能力。 [CEFR: coherence and cohesion] 機能的能力 話しことばの流暢さ(機能的能力) 52 はっきりと発音し、会話を続けたり、行き詰った時に対処したりする 能力。 [CEFR: spoken fluencey] 53 叙述の正確さ(機能的能力) 明確に考えや事柄を言語化する能力。 [CEFR: propositional precision] 参考資料 Council of Europe ( 2001 ) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment . Cambridge: Cambridge University Press. 73 参考資料 46 ディスコース能力 能 力 コミュニケーション言語能力 45 要約したり書き写したりする 参考資料3-1 Can-do のレベル別特徴一覧【受容(理解する) 】 条件 • 母語話者にかなり速いスピー + 話題・場面 • 幅広い分野にわたって ドで話されても + 対象 • 生であれ、放送であれ、あら ゆる種類の話しことば • かなり程度の高い口頭表現や + 行動 • 難なく理解できる • 実質的に理解して批判的に解 釈できる 方言的な慣用表現、馴染みの C2 薄い専門用語を利用した専門 の講義やプレゼンテーション • あらゆる形式の書きことば • 長い複雑なテクスト • 耳慣れ な い 話し 方の 場合に は、ときどき細部を確認する 必要があるが • いくつかの非標準的な表現が C1 あっても • 自分の専門分野に関連してい なくても • 社会、専門、学問の分野 • 自分の専門外の抽象的で複雑 な話題 • 難しい箇所を読み返すことが • 長い発話 • 容易に理解できる • 録音され、放送された広範囲 • 中身を詳細に理解できる な音声素材 • 相当数の俗語や慣用表現のあ る映画 • ある程度長い、複雑なテクス できれば ト • 辞書をときどき使えば • 幅広い慣用表現や口語表現の テクスト • 専門用語の意味を確認するた めに辞書を使うことができれ ば (専門外であっても) (B2.2) • 身近な話題でなくとも (B2.2) • 個人間、社会、専門、学問の 世界で普段出合う話題(B2.2) • 母語話者同士の活気に富んだ 会話(B2.2) • 非常に専門的な資料(B2.2) • 母語話者の会話についていく ことができる(B2.2) • 情報、考え、意見を読み取る ことができる(B2.2) • 話の方向性が明示的な標識で • 幅広い専門的な話題 示されていれば(B2.1) • 自分の興味のある分野 • 少し努力すれば(B2.1) • 具体的/抽象的な話題 • 自分の周りで話されているこ と(B2.1) • 内容的にも言語的にも複雑な B2 話 • 標準語で普通のスピードで話 されていれば • 学問的/ 専門的な プ レ ゼ ン • 難しい箇所を読み返すことが テーション できれば • たいていのテレビのニュース や時事問題の番組 • 流れを理解できる(B2.1) • 要点を理解できる • 独力で読み解くことができる • 重要事項を見定めることがで きる • 内容やその重要度をすぐに把 握できる • ドキュメンタリー、生のイン タビュー、トークショー、演 劇、大部分の映画 • 長い複雑なテクスト • 情報や記事、レポート • 聞き慣れた話し方で、発音も はっきりとしていれば (B1.2) • 毎日や 普段 の 仕事上 の 話 題 (B1.2) • 簡潔で明確な構成のプレゼン テーション、講義、話(B1.2) (B1.2) 参考資料 • 多く の テ レ ビ 番組( イ ン タ • 話し方がゆっくりとはっきり としていれば(B1.1) • 身近な話題(B1.1) • 仕事、学校、余暇などの場面 ビュー、短い講演、ニュース レポート)(B1.2) • 話が標準的なことばで、発音 柄(B1.1) • 自分の専門分野や興味のある 話題 • 重要点を取り出すことができ • 簡単な短い話(B1.1) • ラジオの短いニュースや、比 もはっきりとしていれば • 要点を理解できる(B1.1) る(B1.1) で普段出合う、ごく身近な事 B1 較的簡単な内容の録音された 素材(B1.1) • か な り の 映画、テ レ ビ 番組 (B1.1) • 日常の 資料( 手紙、パ ン フ レット、短い公文書) (B1.1) • 簡単な新聞記事(B1.1) • 簡単な専門的情報 • 詳細な指示 74 • 内容を お お か た 理解で き る • 理解できる • 出来事、感情、希望の表現を 理解することができる JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 条件 • 簡単なことばで表現されてい + 話題・場面 • 具体的で身近な事柄(A2.2) れば(A2.2) • 映像が実況のほとんどを説明 してくれるならば(A2.2) + 対象 • 日常の手紙やファックス(照 会、注文、確認)(A2.2) 理、雇用)(A2.1) れば • 具体的な必要性を満たすこと が 可能な 程度に 理解で き る • 短い個人の手紙(A2.1) 情報、買い物、その地域の地 • ゆっくりとはっきりと話され 行動 (A2.2) • 最も直接的な優先事項の領域 ( ご く 基本的な 個人や 家族の + • 内容を 大ま か に 理解で き る • 短い、はっきりとした、簡単 (A2.1) なメッセージやアナウンス • 予測可能な日常の事柄 A2 • 日常の看板や掲示(道路、レ • 話題が理解できる ストラン、鉄道の駅などの看 • 要点が理解できる 板、指示、危険警告などの掲 • 必要な情報を取り出すことが 示) できる • 日常の簡単な資料(広告、メ ニュー、時刻表) • 日常の簡単なテクスト(手紙、 パンフレット、新聞の短い事 件記事) • テレビのニュース番組 • 意味が取れるように長い区切 • 短い簡単な説明、指示、情報 • 非常に短い簡単なテクスト と注意深く発音してもらえれ • 簡単な掲示の中にある身近な • 一文一節ずつ理解することが できる • 概要を把握することができる 名前や語、基本的な表現 ば A1 • 日常のよくある状況で りをおいて、非常にゆっくり • 当人に向かって、丁寧にゆっ くりと話されれば • 必要であれば読み直したりし ながら • 視覚的な補助があれば *(括弧)内のレベルは、A2、B1、B2をさらに2つの詳細レベルに分けたものです。 参考資料 Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment . Cambridge: Cambridge University Press. Council of Europe (2004)『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』初版第 1刷、吉島茂、大橋理枝(訳、編) 朝日出版社 Council of Europe (2008)『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』初版第 2刷、吉島茂、大橋理枝(訳、編) 朝日出版社 参考資料 75 参考資料3-2 Can-do のレベル別特徴一覧【産出(表現する) 】 条件 + 話題・場面 • 話題について知識のない聴衆 + 対象 • 記憶に残るような経験談 に対しても • 論理的な構造を持った、流れ 行動 • 明瞭で滞りなく、詳しく話す /書くことができる のよいスピーチ • 読者に重点がわかるように、 • 複雑なテクスト 適切で効果的に論理を構成す • 明瞭で流れるような、複雑な レポート、記事、エッセイ C2 + • 実情説明、提案、文学作品の 批評文 ることができる • 聴衆の必要性に合わせて柔軟 に話を構造化できる • 自信を持ってはっきりと発表 できる • そのジャンルに適切な文体で 書き、読み手を完全に引き込 むことができる • 複雑な話題 • 明瞭かつ詳細な記述やプレゼ ンテーション • 明瞭な、きちんとした構造を 持ったプレゼンテーション、 テクスト C1 • 的確な構成と展開を持つ描写 文や創造的なテクスト • 論点を展開し、立証できる • 補助事項、理由、関連事例を 詳しく説明できる • 読者として想定した相手にふ さわしい自然な文体で書くこ とができる • 明瞭かつ詳細に述べることが できる • 下位テーマをまとめ、要点を 展開して、適切な結論で終わ らせることができる • 自分の関心のある分野に関連 した広範囲な話題 • 一般的な話題のほとんど • はっきりとした、体系的に展 • 適切に要点を強調し、補足事 開し た プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 項を詳しく取り上げて、整然 (B2.2) • 自分の関心がある専門分野の 多様な話題 • 事前に 用意さ れ た プ レ ゼ ン テーション(B2.1) • 映画、本、演劇の批評(B2.1) • 明瞭で詳しいテクスト B2 と論拠を展開できる(B2.2) • 非常に流暢に、楽に表現でき • エッセイやレポート る(B2.2) • 当該ジ ャ ン ル の 書式習慣に 従って詳細に記述することが できる(B2.2) • 根拠を提示しながら、利点と 不利な点、賛成や反対の理由 を挙げて、説明できる (B2.1) • いろいろなところから集めた 情報や議論をまとめることが 参考資料 76 できる(B2.1) • 明確で詳しく述べることがで きる • いろいろな情報や議論を評価 したうえで書くことができる JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 条件 • 練習しておけば • アクセントとイントネーショ + 話題・場面 • 自分の専門範囲の日常的/非 対象 • 極めて短い報告文(B1.1) • ある程度の自信を持って自分 し、報告できる(B1.2) • ある程度の長さの、簡単な記 述やプレゼンテーション • 自分の関心のあるさまざまな 話題 B1 行動 • 集めた事実情報をもとに総括 • 日常的な事柄(B1.1) • 意見、計画、行動(B1.1) + • 短い、簡単なエッセイ(B1.2) 日常的な事柄(B1.2) ンにはかなり耳慣れない部分 もあるが + • 本や映画の筋 • 単純につなぎあわせたテクス • 現実や想像上の出来事、経験 ト • 事故などの予測不能の出来事 • 物語 • 夢や希望、野心 の意見を提示できる(B1.2) • 事実を述べ、理由を説明する ことができる(B1.1) • 標準的な常用形式に沿って書 くことができる(B1.1) • 自分の感情や反応を描写する ことができる • 自分の考えを述べることがで きる • 夢、希望、野心を述べること ができる • 順序だてて詳細に述べること ができる • 比較的流暢に事柄を直線的に 並べて述べることができる • 聞き手が集中して聞いてくれ れば、練習したうえで • 自分の毎日の生活に直接関連 のある話題(A2.2) • 短い プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン (A2.2) • 計画、準備、習慣、日々の仕 事、過去の活動や個人の経験 (A2.2) • 家族、住居環境、学歴、現在 やごく最近までしていた仕事 (A2.1) • 要点を短く述べることができ る(A2.2) • 事柄を列挙して、簡単に述べ • 短い 基本的な プ レ ゼ ン テ ー ション(A2.1) • 単純な記述 • 短いアナウンス A2 ることができる(A2.2) • 好きか嫌いかを述べることが できる(A2.2) • 文を連ねて書くことができる (A2.2) • 簡単なことばで述べることが できる(A2.1) • 人物や 生活、職場環境、日 • 簡単な句や文を連ねて書くこ 課、好き嫌いなど とができる(A2.1) • 予測可能で身近な内容の事柄 • 簡単な字句や文を並べて話す ことができる •「そして」 「しかし」 「なぜなら」 て書くことができる • 人物や場所について A1 • 自分や想像上の人々について (どこに住んでいるか、何を しているか) • 非常に短い、準備して練習し た表現(話し手の紹介や乾杯 の発声) • 簡単な表現、句や文 • 読み上げることができる • 単純な字句を並べて、述べる ことができる • 単独に書くことができる *(括弧)内のレベルは、A2、B1、B2をさらに2つの詳細レベルに分けたものです。 参考資料 Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment . Cambridge: Cambridge University Press. Council of Europe (2004)『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』初版第 1刷、吉島茂、大橋理枝(訳、編) 朝日出版社 Council of Europe (2008)『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』初版第 2刷、吉島茂、大橋理枝(訳、編) 朝日出版社 77 参考資料 などの簡単な接続詞でつなげ 参考資料3-3 Can-do のレベル別特徴一覧【やりとり(相互行為) 】 条件 • 母語話者と比べても引けをと らず • 標準的でない話し方や言い方 に慣れれば + 話題・場面 • 社会や個人生活全般にわたっ て • 自分の専門分野を超えた専門 + 対象 • 慣用的な表現や口語表現 • 複雑な議論 • 明確で説得力のある議論 + 行動 •( 慣用的表現や 口語表現を ) 使いこなすことができる • 的 確 に 修 飾 を 加え、細 か い ニュアンスまで伝えることが 家の抽象的な複雑な話題 できる C2 • 堂々と、非常に流暢に話や対 話を組み立てることができる • 言語上の制限もなく、ゆとり をもって、適切に、自由に会 話ができる • 自己主張できる • 助け船を出さなくても • 馴染みのない話し方の場合に ときどき詳細を確認する必要 • 抽象的かつ複雑で身近でない 話題 • 自分の専門分野外の話題 はあるが • 専門家による抽象的な複雑な 話 • インタビュー • ディベートでの第三者間の複 雑な対話 • 個人的な通信 C1 • はっきりと正確に表現するこ とができる • らくらくと流暢に、自然に言 いたいことを表現できる •(インタビューに)完全に参 加することができる •(ディベートに)容易につい ていくことができる • なめらかに議論点を発展させ ることができる • 感情表現、間接的な示唆、冗 談などを交えて、柔軟に効果 的に対応することができる • 話し方を全く変えない複数の • 一 般 的、 学 術 的、 職 業 上、 母語話者との議論に加わるの 余暇に関する幅広い話題 は難しいかもしれないが、多 少の努力をすれば(B2.1) (B2.2) • 生活上のさまざまなトラブル • 複雑な情報や助言(B2.2) • 母語話者との活発な議論 (B2.2) • 自分の職業上の役割に関する あらゆる事柄(B2.2) て、自信を持って反応できる (B2.2) • インタビュー(B2.2) • うまく交渉の話し合いができ • 長い会話 •(インタビューを)なめらか に対して(B2.2) • 騒音のある環境でも • 議 論の複雑 な道筋を 理 解し る(B2.2) に効果的に行うことができる (B2.2) • たいていの話題 • 自分の専門分野に関連した事 柄 • 自分の考えや意見をはっきり と説明し、主張できる (B2.1) • 多く の 情報源か ら の 情報と B2 論拠を 統合し て 報告で き る 参考資料 (B2.1) • 代替案を評価すること、仮説 を立て、また他の仮説に対応 することができる(B2.1) •( 会話に )積極的に 参加で き る • 論点や問題の概略をはっきり と述べることができる • 効果的に書いて表現でき、他 の人の書いたものにも関連づ けることができる 78 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 条件 • 時には言いたいことが言えな いこともあるが • ディベートに参加するのは難 + 話題・場面 • 一般的な話題(B1.2) もあるが • 相手が 標準的な 言葉遣い で はっきりと発音してくれれば • 話が自分に向けられていれば 対象 文化的話題(B1.2) • 友人との非公式の議論(B1.1) • 代 案 を 比 較 し、 対 照 で き る 認できる(B1.2) (B1.1) • 身近で個人的関心のある事柄 (B1.1) • 日常生活に関連する話題(家 族、趣味、仕事、旅行) (B1.1) • 会話や議論 • 個人的な手紙 • 情報や意見 (B1.2) • 他人の見方に短いコメントを することができる(B1.2) • 個人的な意見を表明したり、 情報を交換したりできる(B1.1) • 信念、意見、賛成、反対を丁 寧に表現できる(B1.1) • 自分の専門分野に関する話題 • 理由をあげて説明することが • 身近な話題 B1 行動 • 情報を交換、チェックし、確 • 簡単 で 事 実 に 基 づ く 情報 • 興味のある話題(B1.1) + • 具体的な情報(B1.2) • 音楽や映画のような抽象的、 しいが • 時にはくり返しを求めること + できる(B1.1) • 具体的/抽象的な話題 • あまり日常的では起きない状 況(気に入らなかった品を返 •(会話に)参加し、続けるこ 品するなど) とができる • 旅行中に起きそうなこと • 驚き、悲しみなどの感情を表 現し、また相手の感情に反応 することができる • 自分が重要だと思う点を相手 に理解させることができる • 苦情を言うことができる •(旅行中に起こるたいていの状 況に)対処することができる • 必要がある場合に相手が助け てくれれば、 (A2.2) • 議論がゆっくりとはっきりと なされれば(A2.2) • 自分の周りで議論されている 話題(A2.2) • 旅行、宿泊、食事、買い物の • はっきり、ゆっくりと、自分 (A2.1) • 考えや情報(A2.2) • 非常に短い社交的なやりとり • 日常の課題に関して(A2.1) 近な毎日の事柄(A2.1) トを繰り返してもらえるなら ば(A2.1) • 地 図 や 図 を 参 照 し な がら (A2.1) •( 考 え や 情 報を )交 換し、 質問に 答え る こ と が で き る (A2.2) • 会話に参加できる(A2.2) • 簡単な情報(A2.1) • 他の人の意見に賛成や反対が できる(A2.2) (A2.1) • 仕事中や自由時間に関わる身 • 必要な場合に鍵となるポイン A2 • 簡単な説明や指示(A2.2) ような毎日の生活での普通の 状況(A2.2) に直接向けられた発話ならば • 短い会話(A2.2) • 会う約束をすることができる • 短い、簡単なメモや伝言 • ごく簡単な個人的な手紙 • 直接必要なこと (A2.1) • 好き嫌いを言うことができる (A2.1) • 日常品や サ ー ビ ス を 求め た • 予測可能な日常の状況で り、提供したりできる (A2.1) • 身近な話題 • 興味のある話題 (A2.1) • ときどきくり返しや言いかえ • 行き方を聞いたり、教えたり を求めることが許されるので することができる。切符を買 あれば うことができる(A2.1) •( メ モ、伝言、手紙を )書く ことができる A1 • こちらの事情を理解してくれ • 直接必要なこと るような話し相手から、はっ • ごく身近な話題 きりとゆっくりと、繰り返し • 自分自身や他人に関して(住 を交えながら、直接自分に話 まい、知人、所有物など) • 具体的で単純な必要性を満た すための日常の表現 • 短い簡単な質問、説明、指示 • 短い簡単なはがき が向けられれば • 簡単な方法でやりとりができる • 聞いたり答えたりすることが できる •(短い簡単なはがきを)書く ことができる *(括弧)内のレベルは、A2、B1、B2をさらに2つの詳細レベルに分けたものです。 参考資料 Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment . Cambridge: Cambridge University Press. Council of Europe (2004)『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』初版第 1刷、吉島茂、大橋理枝(訳、編) 朝日出版社 Council of Europe (2008)『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』初版第 2刷、吉島茂、大橋理枝(訳、編) 朝日出版社 79 参考資料 • 食事を注文することができる レベル A2.1 A2 A2.2 B1.1 B1 B1.2 B2.1 B2 B2.2 C1 C2 表現を知っている。 言語構造的能力 むことが多い。 り、あるいは誤解を生 ンが成り立たなかった は、コミュニケーショ しかし予想外の状況で な状況に対処できる。 していく上で予測可能 リーを駆使して、生活 や、限られたレパート 覚えた短い言い回し ケーションできる。 ど に 関し て コ ミ ュ ニ 特定の場所、持ち物な 他人について、職業、 を使って、自分自身や 単語や覚えた言い回し とができ、いくつかの 基本的な構文を使うこ けの語彙を持っている。 述べることができるだ 事問題などについて、 仕事、旅行、そして時 られない。 できる。発言内容を制 や、興味のあること、 範囲を利用することが トリーを持っている。 たり回りくどかったり 容に関しても考えを述 る。 限する必要は全く感じ る必要がほとんどない。 幅広く習熟した言語の 基本的な言語のレパー もあるが、多少詰まっ 画といった文化的な内 構造で使えるものもあ はしても、家族や趣味 べることができる。 き、その内容を制限す 括的で確実な、非常に 応するために必要な、 きなかったりすること 的な内容や、音楽や映 持っており、複雑な文 現が作れる。 要な、簡潔な日常的表 常的な状況に本人が対 かなか内容を言語化で することができ、抽象 能なだけの言語の幅を 欲求を満たすために必 あるが、予測可能な日 り返しが生じたり、な や問題の主要点を説明 の組み立てが充分に可 ることはそれほどない。 表現を 選ぶ こ と が で いたりするために、包 を満たすための単純な の請求など、具体的な を探したりする必要が のために発言内容に繰 る程度の正確さで考え 分の視点の表明、議論 限している感じを与え 言語の範囲から適切な たり、あいまいさを除 ことや、具体的な要求 要な事物、要求、情報 協・制限したり、言葉 る。語彙的な幅の狭さ の幅を持っており、あ に、明確な描写や、自 ができ、その内容を制 に、幅広い使用可能な を強調したり、区別し で、自分自身に関する して行われること、必 たいことを内容的に妥 の言語能力は持ってい きるだけの充分な言語 をそれほど感じさせず とを明確に述べること 明確に言語化するため 語化したり、特定の点 非常に 基本的な 範囲 身辺状況、毎日繰り返 たいていの場合、言い 何とか生活できるだけ 予想外の状況を描写で 言葉を探していること 自分自身が言いたいこ 自分が言いたいことを 正確に自分の考えを言 A1 参考資料 4 能力 Can-do 一覧 参考資料 80 使える言語の範囲 使用語彙領域︵語彙能力︶ 使いこなし 文法的正確さ︵文法能力︶ A2.1 A2 A2.2 B1.1 B1 B1.2 B2.1 B2 B2.2 C1 C2 けて、言い方を変えることができる。 使い方も上手である。 定型表現や口語表現の と分かることはない。 方略の使用がはっきり 識もある。 言葉を探したり、回避 テーションに対する意 ることがあるが、初歩的な語彙は使いこなせる。 を邪魔しない範囲である。 彙上の誤りはない。 て何かを述べようとすると、大きな誤りをす や間違った単語の選択もコミュニケーション いがあるが、大きな語 に語彙が使用できる。 があるが、その数は少 なく、後で見直せば訂 正できるものが多い。 能力があるが、母語の 影響が明らかである。 誤りも見られるが、本 のかはたいていの場合明らかである。 れば理解できる。 であれば、多少努力す き慣れている母語話者 とができる。 分を正しく強調するこ させたり、文の特定部 ントネーションを変化 済みの単語や言い回し の の、大体の 場合、発音は 理解で き る 程度に 音は明瞭である。 なら、当人の言語を聞 ははっきりとしている。 を表現するために、イ トリーの、学習・練習 ともあり、明らかな外国語訛りが見られるも えもあるが、大体よく理解できるくらいに発 ンを身につけている。 非常に限られたレパー 話の相手から時々、繰り返しを求められるこ 時に は 外国語訛り が 目立っ た り、発音の 間違 はっきりとした、自然な発音やイントネーショ より微妙なニュアンス る。 ることは明らかに分か 人が述べようとしてい な不備が見られる場合 ある。しかし、本人が何を言おうとしている 割合正確に使うことが 合高いレベルでの駆使 ことはできる。 できる。 然起こした誤りや些細 難しい。 文法構造や構文を使う 性・数・格などの一致を忘れたりする傾向が ンのレパートリーを、 とができる。多くの場 犯さない。 を維持している。 て常に高い文法駆使力 も、複雑な言葉につい 注意を払っている時で といった)他のことに ターしているような時 た、いくつかの単純な な間違いがある―例えば、時制を混同したり、 「繰り返し」やパター ニケーションを行うこ ながるような間違いは い」や、文構造での偶 なく、見つけることは や、他人の反応をモニ リーの中から、限られ ができるが、依然として決まって犯す基本的 で、頻繁に 使わ れ る は、割合正確にコミュ が見られる。誤解につ る。時には「言い間違 を維持する。誤りは少 うことを考えている時 学習済み の レ パ ー ト いくつかの単純な文法構造を正しく使うこと 比較的予測可能な状況 馴染み の あ る 状況で 比較的高い文法駆使力 高い 文法駆使力が あ 常に高い文法的正確さ (例えば、これから言 の語を使うことができる。 具体的な日々の要求に関する狭いレパートリー 複雑な 考え や、非日常的な 話題や 状況に 関し 語彙的な 正確さ は 一般的に 高い。多少の 混乱 時には些細な言い間違 一貫して正しく、適切 を持っている。 対応できるだけの語彙 生活上の単純な要求に ている。 持っている。 だしそれらの間の繋が りはない。 行うのに充分な語彙を 述べたいことを述べられるだけの語彙を持っ 現をすることもあるが、頻繁な繰り返しを避 埋めることができる。 うことができる。コノ リーを持っている。た 彙を持っている。 や言い回しのレパート ことができるだけの語 生活上の交渉・取引を て、多少間接的な 表現を 使っ て で も、自分の があるために、時々詰まったり、間接的な表 い換えで語彙の不足を 彙のレパートリーを使 関して、基本的な単語 ションの要求を満たす 題に関して、日常的な 本人の 日常生活に 関わ る 大部分の 話題に つ い し て、幅広い 語彙を 持っ て い る。語彙に 不足 を使いこなせるし、言 含め、非常に幅広い語 特定の具体的な状況に 基本的なコミュニケー 馴染みのある状況や話 家族、趣味や関心、仕事、旅行、時事問題など、 本人の 専門分野や 大部分の 一般的な 話題に 関 広い語彙レパートリー 定型表現や口語表現も A1 参考資料 レベル JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 語彙の ︵語彙能力︶ 音素の把握︵音声能力︶ 言語構造的能力 81 レベル A2.1 A2 A2.2 B1.1 B1 B1.2 B2.1 B2 B2.2 C1 C2 書くことができる。 文章を書くことができる。 にとって読みやすい。 統一されており、読者 て、ある程度の長さのはっきりと理解できる り、句読点の打ち方が 章を書くことができる。 違いがある以外は正確 である。 に書くことができる。 社会言語的な適切さ 言語構造的能力 社会言語能力 て 母語話者が お か し がったり、いらつくこ と は な く、ま た 母語 はあるが、効果的に交 際を維持することがで きる。 唆、冗談などを交ぜて、 会言語的な違いを考慮 社交上の目的に沿って、 しながら、目標言語の 柔軟に、効果的に言葉 話者と自分自身の生活 を使うことができる。 地域の言語の話者との 最も重要な違いに対する認識があり、それを いろいろな場面で自分 自身の述べたいことを 表現することができる。 配慮することができる。 ることができる。 間を、効果的に仲介す 感情表現、間接的な示 社会文化的、および社 慣習、言葉遣い、態度、価値観や信条について、 誤りを犯すことなく、 る。 切に応じることができ 味を充分に理解し、適 目標言語の 文化と 当人自身の 文化と の 間の、 言語化する際に深刻な てすむ。 違った話し方をしなく 母語話者同士の場合と 話者が当人と話す際、 使われている映画の筋 する際の社会言語的、 際、当人の意図に反し に従って、単純な形で を追うことができる。 および社会文化的な意 俗語や慣用句がかなり 母語話者が言語を使用 できる。 を維持できるが、その 信を持って言うことが 立することができる。 表現や、基本的な慣習 動できる。 身の述べたいことを自 要があるかもしれない。 基本的な社交関係を確 最も簡単な、一般的な 明示的な 礼儀慣習を 認識し て お り、適切に 行 母語話者との対人関係 い言葉遣いで、自分自 時々細部を確認する必 加することができる。 理解できる。礼儀正し 慣れない訛りの場合、 る丁寧な言葉遣いで、 ことができる。 くことができ、また参 葉遣いで、はっきりと る。しかし、特に聞き ません」などの、最も 提案、謝罪などを行っ でき、また応じること 簡単な日常的に使われ たり、それらに応じる ができる。 ループ討議についてい 加者に応じた適切な言 用域の変化も理解でき 分かっている。 you"「 ど う も あ り が い社交的な会話を行う したりするなどの、基 とう」、"sorry"「すみ ことができる。招待や 本的な言語機能を実行 的であっても、ある程 く だ け た 言葉遣い で や口語表現を認識する 現を う ま く 使い こ な 度の 努力を し て、グ も、その場や会話の参 ことができ、言葉の使 せ、コノテーションも 紹介、"please"「~し や呼びかけなど、礼儀 報を 交換、請求し た 言語機能を遂行し、対応できる。 てください」、"thank 正しい言葉遣いで、短 り、意見や態度を表明 挨 拶 や い と ま 乞 い、 日常的に使われる挨拶 例えば、簡単な形で情 中立的な、ご く 一般的な 言葉遣い で、幅広い 話の速度が速く、口語 公式の言葉遣いでも、 幅広い慣用句的な表現 慣用句的表現や口語表 割合に正確に文字化することができる。 他の個人的な情報を正確 (完全に標準的な綴りではない場合もあるが) の場合読者を混乱させない程度に正確である。 読点の打ち方はかなり正確である。 当人の住所、国籍やその 当人が話す語彙に含まれる短い単語の音声を、 綴りや句読点、レイアウトなどは、ほとんど 母語の影響を見せることもあるが、綴りや句 綴りは、時々些細な間 きる。 しを書き写すことがで みのある単語や言い回 う定型表現など、馴染 前、店の名前や普段使 指示、日常的な物の名 ができる。例えば、道順の説明など。 例えば、簡単な記号や 日常的な話題に関する短い文を書き写すこと 読者が 理解で き る、あ る 程度の 長さ の 文章を 標準的なレイアウトや段落切りの慣習に従っ レ イ ア ウ ト、段落切 正書法の誤りなしに文 A1 参考資料 82 正書法の把握︵正書法能力︶ 柔軟性︵ディスコース能力︶ 発言権︵ディスコース能力︶ 話題の展開 ︵ディスコース能力︶ 語用能力︵ディスコース能力︶ 83 A1 A2.2 B1.1 B1 B1.2 B2.1 B2 B2.2 つけることができる。 表現する仕方に変化を 自分が述べたいことを 葉遣いができる。 けることができる。 言葉に す る 間、時間を 稼ぎ、発言権を 保ち 続 題ですね…」等)を使って、言うべきことを 手持ちの言い回し(例えば「それは難しい問 なときに会話を終わらせることができる。 め る こ と、適切な と き に 発言権を取り、必要 必ずしもスマートとは言えないが、会話を始 終えることができる。 始め、続け、終えるこ とができる。 上手に 発言権を と っ て、談話を 始め、続け、 回しを適切に選び、発 簡単な対面での会話を 置きにふさわしい言い わらせることができる。 できる。 を維持できる。 えている間も、発言権 る。また話の内容を考 言の 機会を 獲得で き から、自分の発言の前 会話を始め、続け、終 からでも加わることが のいつでも使える範囲 た終えることができる。 なら、対面での簡単な についての議論に途中 たり事物を記述できる。 簡単な語りや記述ができる。 や語りをすることができる。 ることができる。 適切な結論で終わらせ 点の一つを展開して、 位テーマをまとめ、要 て 自分の 主要な 論点を 補強し て、明快な 描写 ができる。そして、下 ポイントを簡単に並べ上げる形で、物事を語っ 事柄を直線的に並べていって、比較的流暢に、 論拠と な る 詳細関連事項や 具体例などによっ 洗練された描写や語り る。 らかの言語行動をとれ 会話を始め、続け、ま 個人的興味のある話題 て、馴染みのある話題 ことができる。 発言権を得るために何 簡単なやり方で、短い 馴染みのある話題や、 適切な言い回しを使っ 適切な 表現を 使っ て 討論に 途中から入り込む ディスコース機能の中 る。 に合わせることができ ふさわしい丁寧さの言 がある。 言い直す幅広い柔軟性 形式を使って、発言を めに、さまざまな言語 あいまいさをなくすた きる。 しを使って特定の状況 でき、その場の状況に じて変化をつけたり、 を順応させることがで きる。 すことができる。 た、覚えている言い回 状況や聞き手などに応 強調したり、その場の C2 て、使える表現を増や 行 っ て、 充 分 練 習 し ことを多く表現できる。 あまり多用せず、表現 化に適応することがで し方を調節することが C1 しの組み合わせを変え 語 彙 的 な 差 し 替 え を 軟に使って、述べたい えも、型通りの表現を れ、話し方、強調の変 手に応じて、内容、話 既に学習済みの言い回 限られた範囲でだが、 簡単な言語を幅広く柔 難しい場面においてさ 会話で通常見られる流 その場の状況や、聞き A2.1 A2 参考資料 レベル JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック レベル A2.1 A2 A2.2 B1.1 B1 B1.2 B2.1 B2 B2.2 C1 C2 る。 作り上げることができ るが、長く話すとなる げることができる。 語用能力︵ディスコース能力︶ 取りができる。 母語話者と普通にやり で、無理なく自然に、 く、ある程度の流暢さ 互いに無理することな とする時だけである。 話しことばの流暢さ︵機能的能力︶ 叙述の正確さ︵機能的能力︶ 修飾語句をつけて、意 く、比較的正しく使う 見や叙述を精確に述べ ことによって、意味の ることができる。 ことができるが、その他の場面ではたいてい を伝えることができ、 自分が最も大切だと思 う点を、聞き手に理解 内容的に妥協しなければならない。 強調したり、区別した り、あいまいさを排し たりすることができる。 自分が主張したい主な 点を、聞き手が理解で きるような形で表現す ることができる。 えることができる。 させることができる。 微妙なあやを精確に伝 性、信頼性 / 疑問性、 や、限定を表す節など 可能性などに対応した の 修 飾 語 句 を、 幅 広 形で交換して、自分が述べたいことを伝える 分かりやすい形で情報 することができる。 参考資料 Council of Europe (2001) Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press. Council of Europe(2004)『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』、初版第 1刷、吉島茂、大橋理枝(訳、編)朝日出版社 語用能力︵機能的能力︶ ば、限られた情報を、簡単かつ分かりやすい については、簡単かつ を、比較的正確に表現 とができる。 馴染みのある事柄や型にはまった事柄であれ 直接関わりのあること 概念や問題の主要な点 信頼を得られる程度に情報を詳しく伝えるこ 内容の 確実性 / 不確実 例 え ば、 程 度 の 副 詞 目立つ。 切な例や説明を探そう れる。 として間があいたり、 を行うことができる。 発話の修復を行うのが な言葉の流れが損なわ な言葉を考えたり、適 語彙的に正確であろう 続けることができる。 てのみ、自然で滑らか を表現するために最適 いく時に文法的および 助けを借りずに発話を とは少ない。 め準備しておいた発話 を行うことができる。 見られる。 と特に、談話を続けて はするものの、他人の 立って長い間があくこ 現に余裕があることが 的に難しい内容に関し きる。滞るのは、考え い、単独の、多くは予 現でき、短いやり取り く あ く が、非常に 短 いたいことを言葉に表 理解してもらえる。 修復のために、間が多 ば、あまり困難なく言 自分の述べたいことを 比較的長いものになる 小路」に入り込んだり ることがあっても、目 も、非常に流暢で、表 能である。ただ、概念 に、表現することがで 「袋 や表現を探す際に詰ま な一連の発話であって せずに述べることが可 ら ず に、流れ る よ う とき、また話の流れの 染みのある話題であれ が、短い発話であれば 受けない自由な発話で に、間があいたり、 い言葉を言おうとする が目立って多いが、馴 り す る こ と が 目立つ とができるが、制限を できる。言語化する際 ができる。言い方の型 とができ、長く、複雑 自然に、ほとんど苦労 然で、苦労なく、詰ま り、あまり馴染みのな し始めて言い直すこと り、途中で言い換えた 解可能な発話を行うこ を、比較的容易に表現 保って発話を行うこと ニケーションを行うこ とを流暢かつ無理なく を、長い発話でも、自 適切な 表現を 探し た 言葉に詰まったり、話 話し始めて言い直した ある程度の長さの、理 自分の表現したいこと 比較的一定の 速さ を 無理なく自然に、コミュ 自分自身の述べたいこ 自分の 言い た い こ と があるかもしれない。 と若干の「ぎこちなさ」 を作り出すことができ のあるディスコースへ る。 いて単語や語句をつな て語句の間に繫がりを とができる。 話をすることができる。 結合性のあるテクスト 話を、明快な、結合性 果的に使うことができ された、明快で流暢な して、一貫性があり、 な並列の接続表現を用 簡単な接続表現を用い 語ったり、描写するこ つけることができる。 段を使って、自分の発 さまざまな結合語を効 段が使え、上手く構成 を充分かつ適切に利用 ような、非常に基本的 「~だから」のような な文をつなげ、物事を けることができる。 “then” 、 “because” 続表現を使って、単純 結び 合わ せ て、直線的に 並べ て、繫が り を つ が、さまざまな結束手 を明確にするために、 ン、接続表現、結束手 ンや、幅広い結束手段 「それから」の 「しかし」 “and” 「 そ し て 」や “and” 「そして」 、 “but” 最も頻繁に出現する接 短めの、単純で、バラバラな成分をいろいろ 限定的な範囲ではある 複数の考えの間の関係 さまざまな構成パター さまざまな構成パター A1 参考資料 84 一貫性と結束性 ︵ディスコース能力︶ JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック JF 日本語教育スタンダード 開発過程における主要な成果 〔書籍〕 国際交流基金(2007)『平成 17年度 日本語教育スタンダードの構築をめざす国際ラウンドテーブル 会議録』 、国際 交流基金 ――――(2009)『JF 日本語教育スタンダード試行版』、国際交流基金 〔シンポジウム〕 国際交流基金日本語国際セ ン タ ー20周年記念シ ン ポ ジ ウ ム「JF 日本語教育ス タ ン ダ ー ド ―そ の 活用と 可能性―」 (第 15回海外日本語教育研究会)、2009年 10月 4日 < http://jfstandard.jp/publicdata/ja/event/091004.html > 三原龍志「JF スタンダードの概要」 三矢真由美「JF 日本語教育スタンダードの試行を通した初級講座シラバスの見直し―教師の協働によるコース改善―」 大田祥江「上級コースにおける教師と学習者の学習目標の共有と教師の内省」 石井容子、熊野七絵「体験交流活動を中心としたコースにおける自律学習支援とポートフォリオ」 金孝卿、来嶋洋美「Can-do を活用した作文活動のポートフォリオ評価の試み―実践と課題―」 石司えり「全体のまとめ及び JF スタンダード第 1版について」 (司会:古川嘉子、全体ディスカッション:島田徳子、モデレーター:伊東祐郎) 〔論文〕 塩澤真季、石司えり、島田徳子(2010)「言語能力の熟達度を表す Can-do 記述の分析―JF Can-do 作成のためのガイ ドライン策定に向けて―」『国際交流基金日本語教育紀要』第 6号、23-39、国際交流基金 〔口頭発表・講演〕 高偉建、八田直美(2009)「中国大学教師研修における日本語と専門科目―JF 日本語教育スタンダードへの視点」パ ネルセッション「JF 日本語教育スタンダードの開発と運用」 、JSAA-ICJLE2009、国際研究大会 塩澤真季、島田徳子、石司えり、小松知子、金孝卿、渡辺愛、西森年寿(2009) 「Can-do を活用した日本語教育支援ツー ルの設計」『日本教育工学会第 25回全国大会講演論文集』 、717-718 島田徳子(2009)「JF 日本語教育スタンダードが目指すもの―その理念と開発過程―」 『神戸大学留学生センター第 22回「コロッキアム」報告書:日本語教育における評価と到達目標―日本語教育スタンダードを考える―』 、1524、神戸大学留学生センター 島田徳子、森本由佳子(2010)「Can-do を活用した日本語教育支援ツールの開発」 、ATJ 2010 Annual Conference 石司えり、島田徳子、古川嘉子、三原龍志、塩澤真季(2009) 「 『ドイツ語プロファイル( “Profile deutsch” ) 』の分析 から日本語能力記述への示唆」『日本語教育学会平成 21年度春季大会予稿集』 、121-126 石司えり、向井園子(2009)「ポートフォリオとその利用―European Language Portfolio の分析と JF ポートフォリオ の開発―」パネルセッション「JF 日本語教育スタンダードの開発と運用」 、JSAA-ICJLE2009、国際研究大会 古川嘉子(印刷中) 「「日本語教育スタンダード」の役割―JF 日本語教育スタンダードの構築を通して―」 、パネルディスカッ ション:「「日本語教育スタンダード」について考える」 『ヨーロッパ日本語教育』14、ヨーロッパ日本語教師会 古川嘉子、島田徳子(2008) 「国際交流基金、国立国語研究所の取り組み:JF 日本語教育スタンダードの開発と運用」 、 パネルセッション「日本語教育スタンダードの構想」 『日本語教育振興協会ニュース』No.103、39-46、財団法人 日本語教育振興協会 古川嘉子、島田徳子、塩澤真季、亀山知美、真鍋一史、伊東祐郎、平高史也(2008) 「JF 日本語教育ス タ ン ダ ー ド の 構築と 調査―日本語教育現場の 実践を 踏ま え た Can Do 記述の 開発―」 『 第 7回日本語教育国際研究大会予稿集』3、 85 参考資料 島田徳子、古川嘉子、三原龍志、塩澤真季、亀山知美、真鍋一史、伊東祐郎、平高史也、中原淳(2008) 「CEFR 能力 記述文に基づいた日本語能力記述の検討」『日本教育工学会第 24回全国大会講演論文集』 、595-596 269-272 古川嘉子、島田徳子、三原龍志、塩澤真季(2009) 「JF 日本語教育スタンダード試行版と現場の協働」 、パネルセッショ ン「JF 日本語教育スタンダードの開発と運用」 、JSAA-ICJLE2009、国際研究大会 古川嘉子、堀恵子(印刷中)「「国際交流基金日本語教育スタンダード」の構築・ 「日本語能力試験」の改定、及びその連 携」『ヨーロッパ日本語教育』14、ヨーロッパ日本語教師会 三原龍志(2009) 「教えること、学ぶこと:JF 日本語教育スタンダードは「連携」にいかに寄与するか」 、ラウンドテー ブル「「留学生 30万人計画」時代の日本語学校教育」 『日本語教育振興協会ニュース』No.108、12-16、財団法人 日本語教育振興協会 〔ワークショップ・研修〕 三原龍志、塩澤真季 「ポートフォリオ評価」、インターナショナルスクール日本語教師会、2009年 4月 25日 金孝卿、島田徳子 「Can-do を利用した作文活動のポートフォリオ評価を考える」 、日本語教育研修会、神田外国語大学 留学生別科主催、2009年 11月 19日 島田徳子、石司えり 「Can-do Statements を深く理解する―CEFR と JF 日本語教育スタンダードを通して―」 、AJALT 金曜セミナー、社団法人国際日本語普及協会主催、2009年 11月 20日 主要な参考文献 ARCLE 編集委員会、田中茂範(編)(2005)『ECF:幼児から成人まで一貫した英語教育のための枠組み』、リーベル 出版 伊東祐郎(2006)「評価の観点から見た日本語教育スタンダード」 『日本語学』vol.25、18-25、明治書院 Council of Europe(2004)『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』、初版第 1刷、吉島茂、大橋 理枝(訳、編)、朝日出版社 嘉数勝美(2005)「日本語教育スタンダードの構築―第 1回国際ラウンドテーブルの成果から―」 『遠近 第 6号』3641、国際交流基金 ――――(2006)「ヨーロッパの統合と日本語教育―CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)をめぐって―」『日本語学』 vol.25、46-58、明治書院 鎌田修・嶋田和子・迫田久美子(編)(2008)『プロフィシェンシーを育てる~真の日本語能力をめざして~』 、凡人社 国際交流基金(2006)『国際交流基金 日本語教授法シリーズ1 日本語教師の役割/コースデザイン』 、ひつじ書房 ――――(2008)『国際交流基金 日本語教授法シリーズ14 教材開発』 、ひつじ書房 国際交流基金、日本国際教育支援協会(2009) 『新しい「日本語能力試験」ガイドブック』 参考資料 シャクリー、B.D.、N. バーバー、R. アンブロース、S. ハンズフォード(2001) 『ポートフォリオをデザインする―教 育評価への新しい挑戦―』、田中耕治(監訳)、ミネルヴァ書房 田中耕治(2008)『教育評価』、岩波書店 田中真理・長阪朱美(2006)「第二言語としての日本語ライティング評価基準とその作成過程」 、 『第 2言語としての日 本語ライティング評価基準とその作成過程-国立国語研究所編-世界言語テスト』 、253-276、くろしお出版 谷口すみ子(2003)「日本語能力とは何か」青木直子・尾崎明人・土岐哲(編) 『日本語教育を学ぶ人のために』 、世界 思想社 當作靖彦(1999) 「アメリカの外国語教育における評価の動向―代替評価法を中心としてー」 『平成 11年度日本語教育 学会秋季大会予稿集』17-27、日本語教育学会 平高史也(2006)「言語政策としての日本語教育スタンダード」 『日本語学』vol.25、6-17、明治書院 牧野成一・鎌田修・山内博之・齊藤眞理子・荻原稚佳子・伊藤とく美・池崎美代子・中島和子(2001) 『ACTFL-OPI 入門』 、 アルク 村野井仁(2007)『第二言語習得研究から見た効果的な英語学習法・指導法』 、大修館書店 横溝紳一郎(2000)「ポートフォリオ評価と日本語教育」 『日本語教育』107号、105-114、日本語教育学会 86 JF 日本語教育スタンダード2010 利用者ガイドブック 和田朋子(2004)「TUFS 言語能力記述モデル開発のための試み : Common European Framework (of Reference for Languages) の考察(第二言語の教育・評価・習得)」『言語情報学研究報告5』89-102、東京外国語大学 Bachmann, Lyle F.(1990)Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford University Press. Bachmann, Lyle F. and Adrian S. Palmer(1996)Language Testing in Practice Designing and Developing Useful Language Tests. Oxford University Press. Byram, Michael(1997)Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Multilingual Matters Ltd. ――――(2008)From Foreign Language Education to Education for Intercultural Citizenship. Essays and Reflection. Clevedon: Multilingual Matters. Canale, M. and Swain, M.(1980)Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1; 1-47 Council of Europe(2001)Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press. ――――(2009)Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR): A Manual. Council of Europe Language Policy Division. Glaboniat, Manuela, Martin Müller, Paul Rusch, Helen Schmitz and Lukas Wertenschlag(2005)Profile deutsch. Niveau A1-A2・B1-B2・C1-C2. Berlin: Langenscheidt Verlag. Lenz, Peter and Günter Schneider(2004)A bank of descriptors for self-assessment in European Language Portfolios. Strasbourg: Council of Europe. Little, David(2006)The Common European Framework of Reference for Languages: Content、Purpose, Origin, Reception, and Impact. Language Teaching, 39: 3, 167-190 Hamp-Lyons, Liz and William Condon(2000)Assessing the portfolio:principles for practice theory and research. Cresskill, NJ;Hampton Press. North, Brian(2000)The Development of a Common Framework Scale of Language Proficiency. New York: Peter Lang. —————(2007)The CEFR Common Reference Levels: Validated Reference Points and Local Strategies. Intergovernmental Policy Forum “The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) and the development of Language Policies: Challenges and Responsibilities.” Council of Europe Language Policy Division. Weigle, Sara C.(2002)Assessing Writing. Cambridge: Cambridge University Press. 〈参考ウェブサイト〉 青木直子(2007)「日本語ポートフォリオ」 < http://www.let.osaka-u.ac.jp/~naoko/jlp >(2010年 3月 12日最終 アクセス) 参考資料 87 JF 日本語教育スタンダード 2010 利用者ガイドブック[第二版] 2010年 7月 初版 第一刷発行 2010年 9月 初版 第二刷発行 2011年 2月 初版 第三刷発行 2011年 6月 初版 第四刷発行 2012年 6月 第二版 第一刷発行 2013年 3月 第二版 第二刷発行 【編著・発行】 独立行政法人国際交流基金(ジャパンファウンデーション) 【担 当】 日本語国際センター事業化開発チーム 〒 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 5-6-36 TEL:048-834-1183 FAX:048-831-7846 ● JF 日本語教育スタンダードに関するその他詳しい情報は、ウェブサイト < http://jfstandard.jp > をご覧下さい。 ● 『JF 日本語教育スタンダード 2010 利用者ガイドブック』に対するご意見やご質問は、 < [email protected] > にご連絡下さい。 ©2010 The Japan Foundation 『JF 日本語教育スタンダード 2010 利用者ガイドブック』の著作権は、独立行政法人国際交流基金 が所有しています。 ISBN 978-4-87540-150-6