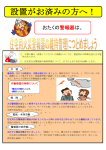Download 別紙(PDF:286KB)
Transcript
別 紙 住宅用火災警報器に関するアンケートの結果について * アンケートの設問及びその他回答の意見は原文のまま掲載しています。 【問1】 お住まいの住宅は、次のうちどれに該当しますか。 1.一戸建て 60件(58.8%) 2.共同住宅等(賃 貸) 19件(18.6%) 3.共同住宅等(持ち家) 23件(22.6%) 23件 19件 60件 一戸建て 共同住宅(賃貸) 共同住宅(持ち家) 【 問 2 】条 例 に よ り 住 宅 用 火 災 警 報 器( 以 下「 警 報 器 」と い う 。)の 設 置 が義務付けられている住宅の部分全てに警報器が設置されていま すか。 〔条例に基づき警報器の設置を義務付けられている住宅の部分〕 ・就寝の用に供する居室(寝室・子ども部屋) ・階段(寝室が2階以上の階にある場合) 1.設置している(全部設置) 6 7 件( 6 5 .7 % ) 2.一部設置している(一部設置) 2 1 件( 2 0 .6 % ) 3.設置していない(未設置) 1 4 件( 1 3 .7 % ) 自 動火災報知設備の感知器が室内に設置されている場合は1.としてください。 14件 21件 67件 全部設置 一部設置 未設置 ※ 住居形態毎の設置状況については次のとおりでした。 33件[55%] 一戸建て 共同住宅 (賃貸) 15件[79%] 共同住宅 (持ち家) 60件 13件[22%] 19件 4件[21%] 19件[83%] 0 14件[23%] 10 全部設置 [67件] 3件 1件 [13%] [4%] 20 23件 30 一部設置 [21件] 40 50 未設置 [14件] 60 【問3】問2において、2.もしくは3.とお答えいただいた方への質 問です。 警 報 器 の 設 置 に つ い て の 予 定 は 、次 の う ち ど れ に 該 当 し ま す か 。 1.購入により設置する 2.リースにより設置する 3.今のところ設置する予定はない 4.その他 ・購入したがまだ設置していない。 ・ 公 営 住 宅 な の で 自 分 で つ け る 必 要 が な い の で は ?と 思 う 。 ・賃貸住宅のため借りた時のままである。借りたときは居 間についていたが寝室にはついていない。 ※ 検討中の場合は3.としてください。 24件 20 10 5件 3件 2件 1件 0 1 2 3 4 未回答 【問4】問3において3.とお答えいただいた方への質問です。 警 報 器 を 設 置 が 進 ま な い 理 由 は 、次 の う ち ど れ に 該 当 し ま す か 。 1.警報器の値段が高い 2.販売店や取扱店がわからない 3.効果に疑問を感じている 4.今まで設置が義務づけられていることを知らなかった 5.家主等が設置してくれると考えている 6.その他(意見) ・火を使う場所のみと考えている。 ・あまり考えていなかった。台所にはある。 ・ 警 報 器 の 設 置 は 火 を 使 用 す る 場 所 (御 勝 手 )近 く で 良 い の で はないですが、各室では多く感じる。階段部分が入ってい ませんでしたか ・ 寝 室 全 て に 設 置 し な く て も 1・ 2 階 聞 こ え る 場 所 な ら 大 丈 夫かと思い。2 か所設置している。 ・誤作動が心配(長期出張などの) ・建替えのため ・自分で買いに行き、つけるのが手間。 ・火の取扱いには気を付けている。 ・記載なし 10 9件 5 4件 3件 3件 3件 1件 1件 0 1 2 3 4 5 6 未回答 【問5】問2において、1.もしくは2.とお答えいただいた方への質 問です。 設置した警報器が鳴ったことがありますか。 1.はい 18件(21.7%) 2.いいえ 65件(78.3%) 18件 65件 は い いいえ 【問6】問5において、1.とお答えいただいた方への質問です。 警報器が鳴った原因は、次のうちどれに該当しますか。 [複 数 回 答 可 ] 1.火災・ぼや・火気による煙・熱が原因によるもの 2.警報器の誤作動:燻煙式の殺虫剤を散布 3. 〃 :魚を焼いた煙やコンロで鍋を空焚きした煙など 4. 〃 :炊飯器、湯沸かし器、電気ポット等の湯気 5.警報器の電池切れや故障 6.その他(意見) ・良く判らなかった。エラーのようです。 ・焼肉をしたとき ・確認用のテストでならした。 10件 10 5 3件 3件 3件 2件 1件 0 1 2 3 4 5 6 【問7】問2において、1.もしくは2.とお答えいただいた方への質 問です。 設置した警報器の日頃の点検やお手入れはしていますか。 1.ほぼ毎日 2.週に1回程度 3.月に1回程度 4.半年に1回程度 5.年に1回程度 6.特に何もしていない 7.その他 53件 50 25 14件 0 0件 2件 4件 1 2 3 4 10件 5 6 0件 1件 7 未回答 【問8】問7において、6.と7.を除くお答えいただいた方への質問 です。 警報器の具体的な点検方法は、次のうちどれに該当しますか。 [複 数 回 答 可 ] 1.警報器に付いたホコリや汚れを布等で乾拭きしている 2.警報器のボタンを押して差動テストをしている 3.電池の交換時期を確認している 4.警報器の取扱いについて、取扱説明書で確認している 5.その他(意見) ・? ・警報器が作動している点滅ランプを確認 ・管理組合より定期的に点検が入る。 ・マンション管理の方が点検して下さっています。 ・業者年 2 回 ・記載なし 10 8件 7件 6件 5 4件 2件 0 1 2 3 4 5 【問9】警報器の義務化を知ったのは、次のうちどれに該当しますか。 [複数回答可] 1.新聞、テレビ、ラジオ等のメディアを通じて 2.市広報紙(広報ながくて、ホームページ)を通じて 3.警報器のポスターやパンフレット等を通じて 4.自治会や町内会などの回覧板を通じて 5.家族、友人、知人を通じて 6.防災講習会等で来た消防職員を通じて 7.インターネット等からの情報を通じて 8 . 市 が 開 催 す る イ ベ ン ト (市民まつり、消防出初式)を 通 じ て 9.その他 ・ 新 築 時 、 ハウスメーカーが 教 え て く れ た 。 ・家を建てる際。 ・マンション購入 ・この調査票で。 ・以前住んでいた社宅の管理事務所からの連絡と設置によ り知りました。 ・家主さんからのお知らせ ・住宅メーカーより ・新築の際住宅メーカーから説明を受けて ・家を建てる時に住宅メーカーより聞いた。 ・記載なし(7件) 50 49件 26件 25 17件 16件 12件 7件 0件 0 1 2 3 4 5 6 4件 7 1件 8 9 【 問 10】警 報 器 の 設 置 率 を 向 上 さ せ る に は 、次 の う ち ど れ が 効 果 的 で あ ると考えますか。[複数回答可] 1.価格が安くなる 2.公的助成(補助)がある 3.もっと宣伝や広報を行う 4.自治会や町内会等で共同購入できるようになる 5.業者が取り付けてくれる 6.性能が良くなる 7.その他 ・外出中、警報器が紗移動した時、消防所に直結する何ら かの方法が無いと、取り付ける意味が少ない ・誤作動の場合の機能 ・通報機能付きになる。 ・みんなの意識や危機管理が低い場合はどれでも効果ない のかも ・立入調査をして取り付けていない家庭を罰則化する。 →ここまでやらないと無関心な人たちは動きません。 ・ 賃 貸 マンションの 場 合 、 オーナーノ意 志 に よ り 左 右 さ れ る の で 、 し っかり全室つけるように指導してほしい。 ・無料にする。 ・罰則を与える ・目立たないものにする。 58件 53件 50 38件 25件 25 21件 11件 8件 0 1 2 3 4 5 6 7 【 問 11】 万 一 に 備 え て ご 家 庭 で ど の よ う な 準 備 を さ れ て い ま す か 。 [複数回答可] 1.消火器(住宅用消火器を含む) 2.エアゾール式簡易消火具 3.住宅用自動消火装置 4.水バケツ 5 . 避 難 器 具 ( 避難はしご等) 6 . カ ー テ ン や じ ゅ う た ん 等 に 燃 え に く い 素 材 (防炎品)の 使 用 7.安全機能付調理器具 8.ガス漏れ警報器 9 . 裸 火 ( 石油ストーブ・ろうそく・線香) を 使 用 し な い 10. 特 に 何 も し て い な い 11. そ の 他 ・火気を使用しない。 ・マンション対応。 50 46件 38件 33件 31件 25件 25 20件 16件 10件 5件 4件 2 3 2件 0 1 4 5 6 7 8 9 10 11 【その他】アンケートの他、次のコメントがありました。 ・日々、私たちの生活を守っていただき感謝します。隊員の 皆さまの健康をおいのりいたします。 調査結果のまとめ 本市における一戸建ての割合が58.8パーセント、共同住宅を含め た持ち家率は81.4パーセントと高いことがわかります。 また、住居形態で設置率を比較すると共同住宅における全部設置がお よそ80パーセントであるのに対し、一戸建ては55パーセントと低い 値を示しており、既存住宅における設置が進まないことが伺える。 さらに未設置世帯における警報器を設置する予定がない考えを示して いることと、かつ設置が進まない理由も様々であることから継続して警 報器の未設置世帯に対し引き続き設置促進を図る必要があります。 次に警報器の日ごろの点検やお手入れは特に何もしていないという意 見が最も多く、具体的な点検方法も様々であるため、いざという時に警 報器が適正に機能するよう維持管理の重要性を謳い、正しい知識の周知 を図る必要があります。












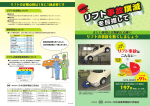
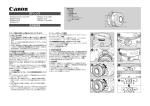




 - 四国経済産業局](http://vs1.manualzilla.com/store/data/006583273_2-1db21d5d5b330a430dbfd0a7b8a84e16-150x150.png)