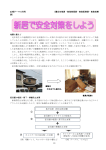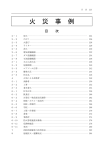Download PDF 13.1MB - 消防庁消防大学校 消防研究センター
Transcript
太陽電池モジュール燃焼時の生成ガスについて Degradation gas at the time of combustion of a photovoltaic generation module constituent material PVF N2 (Si-F結合) (H-F結合) N2 中での PVF の分解挙動 本文 4 ページ参照 Decomposition behavior of PVF in nitrogen atomosphere. See also page 4. EVA N2 (C-H結合) (C=O結合) (C-O結合) N2 中での EVA の分解挙動 本文 6 ページ参照 Decomposition behavior of EVA in nitrogen atomosphere. See also page 6. 消防活動時の太陽電池モジュールの感電危険性 Electric Shock with Photovoltaic Modules on the Fire Fighting 破壊する単結晶シリコンモジュールを含めモジュール 15 枚を並べた実験装置 本文 19 ページ参照 Experimental apparatus consists of the 15 monocrystal silicon photovoltaic modules including one module for destruction. See also page 19. 万能斧③ による単結晶シリコンモジュールの破壊。矢印の先に眩光が見える。 本文 20 ページ参照 Destruction of the monocrystal silicon photovoltaic module by the fire ax. The bright light was observed at the point showed by the arrow. See also page 20. 目 次 技術報告 太陽電池モジュール燃焼時の生成ガスについて 塚目孝裕、阿部 伸之、田村裕之、松島早苗、尾川義雄、 高梨 健一、河関大祐、志水 裕昭… …………(1) 消防活動時の太陽電池モジュールの感電危険性 松島 早苗、田村 裕之、阿部 伸之、高梨 健一、塚目 孝裕、 河関 大祐、尾川 義雄、志水 裕昭… ………(11) 解 説 火災の着火源について 所外発表論文 鈴木 健… ………(23) … ………(47) ─ Contents ─ [Technical Report] Degradation Gas at the Time of Combustion of a Photovoltaic Generation Module Constituent Material Takahiro Tsukame, Nobuyuki Abe, Hiroyuki Tamura, Sanae Matsushima, Yoshio Ogawa, Ken-ichi Takanashi, Daisuke Kozeki, and Hiroaki Shimizu …… 1 Electric Shock Danger of a Photovoltaic Module for the Fire Fighting Sanae Matsushima, Hiroyuki Tamura, Nobuyuki Abe, Ken-ichi Takanashi, Takahiro Tsukame, Daisuke Kozeki, Yoshio Ogawa, and Hiroaki Shimizu …… 11 [Article] Ignition Sources of Fires [Research Papers Presented in Other Journals or Proceedings] Takeshi Suzuki …… 23 …… 47 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 技術報告 太陽電池モジュール燃焼時の生成ガスについて 塚目 孝裕、阿部 伸之、田村 裕之、松島 早苗、 尾川 義雄、高梨 健一、河関 大祐、志水 裕昭 (平成 26 年 2 月 4 日 受理) 近年急速に普及している太陽光発電システムに関して、火災時における発電特性、構成部材による破 損形態、消防活動時における感電危険性などについて、いくつかの報告がなされている。その中でも構 成部材については、近年の技術開発やメーカーの工夫によって種々の材料が使用されており、その種類 が多いために燃焼時の生成ガスに関して系統的に検討された知見はほとんどない。本研究では、構成 部材単体での加熱分解挙動と生成ガスの確認、またそれらの生成メカニズム、及び実際に太陽電池モ ジュールを燃焼させた際に発生するガスの相関について検討した。 表1 使用モジュールの仕様 1.はじめに Photovoltaic modules 太陽光発電システムは発電効率を向上させるための技術 的進歩や、電力買取などの政策的な後押しから一般住宅に A B Manufacture Kyocera Corp. Sharp Corp. Model KC80S ND-114CA しては、知見がない。我々は、火災時の火炎による発電挙動、 W(mm) × H(mm) 979 × 656 990 × 856 及び太陽電池モジュール(以下モジュールと呼ぶ)本体が火炎 Normal maximum output(W) 80 114 Normal maximum voltage(V) 16.9 15.2 Normal maximum current(A) 4.73 7.52 Maximum system voltage(V) 600 600 も普及が進んでいる。また、大容量の発電が可能であるメガ ソーラーの建設も各地で進んでいる。しかし、このシステム が火炎を受けた時の感電や燃焼生成ガスの危険性などに関 を受けた場合の発電挙動について、既報により報告してい るが*1,2)、本報ではモジュールの構成部材から燃焼により生 成するガスを中心に、示差熱熱重量分析 (Thermogravimetry and Differential thermal analysis)−赤外分光分析装置 (Infrared spectrometer) (以下、TG-IR)、及び質量分析装 置(Mass spectrometer) (以下、MS)により考察したので報 告する。 表2 各モジュールの構成 2.試料 Photovoltaic modules 2.1 使用モジュール 使用したモジュールは、既報*1)での燃焼実験に用いた 2 1st Layer 種類のモジュール A 及び B の燃え残った部分を実験に使用 A B Glass(clear) Glass(clear) EVA(clear) EVA(clear) 2nd Layer (including Si cells)(Including Si cells) した。メーカー及び型式を以下の表1に示す。 2.2 使用モジュールの構造 モジュールにおいて、燃焼の可能性のある材質はその構造 から封止材とバックシートに使用されている高分子化合物で ある。封止材の材質は、エチレン−酢酸ビニル共重合体が 一般に用いられているが、 バックシートの材質は多種にわたっ 3rd Layer EVA(white) EVA(clear) 4th Layer PVF(white) PET(black) 5th Layer Aluminium(silver) PET(clear) 6th Layer PVF(white) − ており、使用されている材質によって燃焼状態や発生ガスが 異なる。モジュールの構造を顕微鏡下で観察し、使用されて 定した。各モジュールの構造と、その材質及び色を以下の表 いる各構成部材の材質を赤外分光光度計により測定して特 2に示す。表中に使用した略語は以下のとおりである。 ― 1 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 EVA: エ チ レン− 酢 酸 ビ ニ ル 共 重 合 体(Ethylenevinylacetate copolymer) 解と同時に生成する低分子量のガスを化合物同定能力の高 い IR に導入することで、どのような分解生成物が生じてい PVF:ポリフッ化ビニル(Polyvinyl fluoride) るかを検討し、TG/DTA で測定している対象物が、どのよ PET: ポ リ エ チ レ ン テ レ フタ レ ート(Polyethylene うなメカニズムにより分解しているのかをより詳細に検討で terephthalate) きる利点がある。更に、TG の測定雰囲気を窒素と空気に より別々に測定することで、窒素中では不活性雰囲気中で 3.実験経過 の化合物の加熱分解挙動が、空気中では酸素存在下での 3.1 モジュール構成材料の加熱分解実験 化合物の酸化分解、又は分解生成物の酸化反応をとらえる 構成部材の加熱分解挙動と、その際に生じるガスを検査 するために、構成部材単体での生成ガス測定を行い、更に ことができる。 3.2 モジュールの燃焼実験 それらの部材を組み合わせて作成されているモジュール全体 について炎による燃焼実験を行った。 ジュール A 本体及びモジュール B の一部切り取ったものを 消防研究センター・ルームカロリー試験室において燃焼させ、 モジュール A 及び B の焼け残っている部分を本体から一 その際に生成するガスを MS により採取し検査した。燃焼さ 部採取し、それぞれ材質の異なる層(モジュール A の第 3 せている様子を図1、図2に、使用した装置及び測定条件 層及び第 6 層、モジュール B の第 4 層及び第 5 層)を顕微 を表4に示す。モジュールの燃焼はルームカロリー試験室で 鏡下で分離して切り出し、TG-IR により測定した。ただし、 行ったため、可動型である下記 MS のみを生成ガス測定に モジュール B の第 4 層、第 5 層については、接着が強いこ 使用した。質量分析装置は、いろいろな検出法が存在する とと厚みが薄いため分離できず、2 層同時に測定した。測 が、今回使用した機器は、水銀・キセノンを用いた弱いイオ 定機器及び測定条件は表3のとおりである。 ン化法を採用しており、主に機器に導入された化合物の分 TG は、試料を一定の速度で加熱し、温度に対応した試 料重量変化を測定するものである。一般に高分子化合物は、 化合物ごとのある一定温度で分解し、重量が減少する。分 解生成物は低分子量のガスであり測定装置外へ排出され る。即ち測定対象物の加熱分解温度が分かる。DTA は、 試料の吸発熱をとらえることができ、試料の重量変化が吸 熱反応であるか発熱反応であるかということを、重量変化で ある TG と同時に測定できるものである。TG/DTA は単独 でも測定化合物の熱物性についての情報が得られるが、分 表3 測定機器及び条件(TG-IR) TG/DTA Instruments Hitachi Hi-Tech Science Corp. TG/DTA/7200 Temp. range Room temperature 〜 600℃ Heating rate 20℃ /min Atmosphere Nitrogen, Air (100mL/min) Sample weight 1.22 〜 3.30mg Ref. material Al2O3(4.08mg) 図1 モジュール A を燃焼させている状態 IR Instruments Thermofisher Scientific K.K. Fourier transform infrared spectrophotometer Model iS10 Attached TGA accessory Detector TGS Number of scan 32 times Interval of spectrum 41 sec correction 図2 モジュール B を燃焼させている状態 ― 2 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 表4 使用機器及び測定条件(MS) Instruments Ionization method を図3に示す。 V&F Analyse - und Messtechnik GmbH Ion-Molecule Reaction - Mass Spectrometer Air Sence 窒素雰囲気下では、約 250℃(13 分)から第 1 段階の減 量が始まり、この減量が穏やかになる約 390℃(19 分)から 第 2 段階の減量が続いて起こっている。一方、試料の熱の 出入りを示す DTA 曲線は、穏やかな変化はあるが、顕著 Ion molecule reaction method + な吸発熱のピークは認められない。TG-DTA 曲線と同時に + Hg , Xe Primary ion 測定している IR スペクトルで、400cm -1 から 4000cm -1 の範 Measured masses 囲での総吸収強度を時間に対してプロットしたものを図4に Possible compounds Molecular weight Name Formula 16 methane CH4 26 acetylene C2H2 42 propylene C3H6 54 butadiene C4H6 58 propanal C3H6O 60 acetic acid C2H4O2 butanal C4H8O ペクトル(以下 IR スペクトルと呼ぶ)を図5に示す。16 分の pentane C5H12 ピーク位置の IR スペクトルは、3500cm -1 から 4000cm -1 に benzene C6H6 現れている一連の吸収からフッ化水素(HF)と、1030cm -1 pentanal C5H10O 付近に現れている四フッ化ケイ素(SiF4)の混合スペクトル hexane C6H14 toluene C7H8 hexanal C6H12O 72 78 86 92 100 heptane C7H16 104 styrene C8H8 122 benzoic acid C7H6O2 示す。IR 吸収を持つ化合物は、約 13 分より発生し、16 分 をピークとしていったん減少する。その後、21 分から再び増 加し、24 分をピークとして減少し、その後 IR 吸収を持つ化 合物の生成はない。この増減は、TG 曲線の第 1 段階減量、 第 2 段階減量とよく一致している。この両者から、窒素中 で PVF は 2 段階のメカニズムを経て最終的に分解すること を示している。 総吸収強度プロットの 2 つのピーク位置での赤外吸収ス であり、24 分のピーク位置の IR スペクトルは、フッ化水素 と 2800cm -1 から 3000cm -1、及び 1400cm -1 付近の C-H 吸 収から炭化水素の混合スペクトルと認められた。また、共に 子イオンを生じさせ、検出するものである。同一分子量を持 つ化合物は多数あるため、分子イオンによる検出は、分子 を壊して検出するイオン化法よりは同定能力は低くなる。し かし、燃焼部位付近にガス吸引口を設置し、燃焼で生じた 混合したガス全体を分離せず同時に検出する場合は、分子 イオンによる解析が有効となる。 測定質量数は、表2に示した材質から、燃焼ガスとして発 生する可能性のある物質を推定し、選択イオンモニタリング 図3 TG-DTA 曲線(窒素中モジュール A 第 6 層) 法で測定した。また、加熱源としてブンゼンバーナーによる 都市ガスの炎を使用した。 同時に、モジュール表面温度を赤外線サーモグラフィー装 置(日本アビオニクス社製 TVS-500)により放射率 1.00 と して測定した。 4.結果と考察 4.1 TG-IRによる構成部材単体の測定結果 4.1.1 PVFの窒素及び空気中での加熱分解 モジュール A 第 6 層の PVF について、窒素雰囲気下で 測定した示差熱−熱重量曲線(以下 TG-DTA 曲線と呼ぶ) ― 3 ― 図4 総赤外吸収スペクトルの時間変化(窒素中モ ジュール A 第 6 層) 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 2400cm -1 付近に CO2 の吸収が認められるが、CO2 は分子 減量と、2 回の減量は窒素雰囲気中と同様の挙動を示して 吸光係数が大きく、空気中の CO2 を検出してしまうことが多 いる。 いため、評価の対象からは除外した。 IR の総吸収強度のプロットを図9に示す。窒素雰囲気下 総測定時間中の各波数の吸収強度を、時間、波数、強 と同様に 2 つのピークが認められ、これぞれのピークは TG 度で 3 次元表示したものを図6に示す。測定時間内では 13 曲線の第 1 段減量、第 2 段減量に対応している。また、各 分から 20 分にかけてのフッ化水素及び四フッ化ケイ素の強 減量に対応して、DTA 曲線に強い発熱ピークが認められ、 い吸収と 20 分から 27 分にかけての炭化水素の吸収のみし 空気中での燃焼分解を起こしていると考えられる。 か顕著な吸収は見られない。 2 つのピーク位置での赤外吸収スペクトルを図 10 に示す。 これらから、窒素中での PVF の分解挙動は、温度上昇 15 分のピークは窒素雰囲気下と同様に HF と SiF4 のスペク と共に置換基の脱離、直鎖の切断と図7に示すように進む トルであるが、25 分のピークは窒素雰囲気下で見られた炭 ことが確認された。この分解様式は、同一のモノマーを重 化水素の吸収が認められず、二酸化炭素の吸収のみであっ 合させたビニル化合物のホモポリマーで報告されている様式 た。総 測定時間中の各波数の吸収強 度を、時間、波数、 と同様である。 強度で 3 次元表示したものを図 11 に示す。測定時間内で 次に、モジュール A 第 6 層の PVF を空気雰囲気下で測 定した TG-DTA 曲線を図8に示す。 は 13 分から 16 分にかけての HF と SiF4 の強い吸収と 20 分から 28 分にかけての二酸化炭素の吸収のみしか顕著な 約 250℃からの第 1 段階減量、約 420℃からの第 2 段階 吸収は見られない。即ち、HF 脱離後の主鎖は、空気中の 酸素による酸化分解又は分解と同時に酸化が起こっており、 二酸化炭素に変化していると考えられる。 これより PVF は、火災時の火炎中においては約 300℃ で HF の生成が予想され、HF 脱離後は、酸化分解又は分 解と同時の酸化により、二酸化炭素の生成が予想される。 図5 約 16 分のピークでの IR スペクトル(上段) と約 24 分のピークでの IR スペクトル(下段) 図8 TG-DTA 曲線(空気中モジュール A 第 6 層) 図6 測定時間に応じた各波数吸収とその強度(窒 素中モジュール A 第 6 層) 図9 総赤外吸収スペクトルの時間変化(空気中モ ジュール A 第 6 層) 図7 PVF の分解挙動 ― 4 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 SiF4 は、PVF からは生成しないが、PVF 中に充填剤と て DTA 曲線は弱い発熱を示しているが、発熱量は小さい。 してケイ素を含む化合物が含有されているか、太陽電池に用 IR の総吸収強度をプロットしたものを図 13 に示す。IR 吸 いられているケイ素が混入した可能性がある。 収を持つ化合物は、約 15 分より発生し、18 分をピークとし 4.1.2 EVAの窒素及び空気中での加熱分解 ていったん減少する。その後、21 分から再び増加し、24 分 モジュール A 第 3 層の EVA について、窒素雰囲気下で 測定した TG-DTA 曲線を図 12 に示す。 をピークとして減少し、その後 IR 吸収を持つ化合物の生成 はない。この増減は、TG 曲線の第 1 段階減量、第 2 段階 窒素雰囲気下では、約 270℃(13 分)から第 1 段階の減 減量とよく一致している。この両者から、窒素中で EVA は 量が始まり、この減量が穏やかになる約 380℃(16 分)から 2 段階のメカニズムを経て最終的に分解することを示してい 第 2 段階の減量が続いて起こっている。双方の減量におい る。 総吸収強度プロットの 2 つのピーク位置での IR スペクト ルを図 14 に示す。18 分のピーク位置の IR スペクトルは、 3500cm -1 付 近の O-H、1800cm -1 付 近の C=O、1180cm -1 の C-O 等の各吸収から酢酸であり、25 分のピーク位置の IR スペクトルは炭化水素のスペクトルと認められた。 総測定時間中の各波数の吸収強度を、時間、波数、強 度で 3 次元表示したものを図 15 に示す。測定時間内では 18 分から 20 分にかけての酢酸の吸収と 21 分から 25 分に かけての炭化水素の吸収のみしか顕著な吸収は見られない。 これらから、窒素中での EVA の分解挙動は、PVF と同 図 10 約 15 分のピークでの IR スペクトル(上段) 様に温度上昇と共に置換基の脱離、直鎖の切断と既報*3) と約 25 分のピークでの IR スペクトル(下段) のとおり進むことが確認された。 次に、モジュール A 第 3 層の EVA を空気雰囲気下で測 定した TG-DTA 曲線を図 16 に示す。 図 11 測定時間に応じた各波数吸収とその強度(空 気中モジュール A 第 6 層) 図 13 総赤外吸収スペクトルの時間変化(窒素中モ ジュール A 第 3 層) 図 14 約 18 分のピークでの IR スペクトル(上段) 図 12 TG-DTA 曲線(窒素中モジュール A 第 3 層) ― 5 ― と約 25 分のピークでの IR スペクトル(下段) 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 図 17 総赤外吸収スペクトルの時間変化(空気中モ 図 15 測定時間に応じた各波数吸収とその強度(窒 ジュール A 第 3 層) 素中モジュール A 第 3 層) 図 18 約 17 分のピークでの IR スペクトル(上段) と約 22 分のピークでの IR スペクトル(下段) 図 16 TG-DTA 曲線(空気中モジュール A 第3層) 約 250℃からの第1段階減量、約 430℃からの第 2 段階減 量は窒素雰囲気中と同様の挙動を示している。双方の減量 共に、DTA 曲線は強い発熱を示しており、2 つのは減量共 に空気中の酸素による燃焼分解を起こしていると考えられる。 IR の総吸収強度のプロットを図 17 に示す。窒素雰囲気 下と同様に 2 つのピークが認められ、これぞれのピークは 図 19 測定時間に応じた各波数吸収とその強度(空 TG 曲線の第 1 段減量、第 2 段減量に対応している。 気中モジュール A 第 3 層) 2 つのピークでの赤外吸収スペクトルを図 18 に示す。17 分のピークは酢酸と二酸化炭素の混合したスペクトルであ り、22 分のピークは炭化水素鎖にカルボニルの吸収が認め えられる。 られ、アルデヒドのスペクトルと考えられた。また、二酸化 炭素の強い吸収も同時に認められた。 これより EVA は、火災時の火炎中においては約 300℃で 酢酸の生成が予想され、酢酸脱離後は、酸化分解又は分解 総測定時間中の各波数の吸収強度を、時間、波数、強 と同時の酸化によりアルデヒドが生じることが予想され、酢酸 度で 3 次元表示したものを図 19 に示す。測定時間内では の脱離と同時に二酸化炭素が生成することが予想される。 15 分から 20 分にかけての酢酸、二酸化炭素の強い吸収と 4.1.3 PETの窒素及び空気中での加熱分解 21 分から 23 分にかけてのアルデヒドと二酸化炭素の吸収の みしか顕著な吸収は見られない。即ち、加熱と同時に酢酸 モジュール B 第 4 層、第 5 層の PET について、窒素雰 囲気下で測定した TG-DTA 曲線を図 20 に示す。 の脱離が起こるが、同時に酸化分解又は酢酸の酸化が生じ、 窒素雰囲気下では、約 300℃(15 分)から減量が始まり、 脱離後の主鎖も同様に、酸化分解又は分解と同時に酸化が 約 500℃(25 分)まで1段階の減量が起こっている。DTA 起こっており、アルデヒドと二酸化炭素に変化していると考 曲線は減量時に弱い発熱を示している。 ― 6 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 TG-DTA 曲線と同時に測定している IR の総吸収強度を プロットしたものを図 21 に示す。IR 吸収を持つ化合物は、 約 20 分より発生し、23 分をピークとして減少し、約 35 分 程度まで弱く出続ける。この増減は、TG 曲線の減量とよく 一致している。この両者から、窒素中で PET は1段階のメ カニズムを経て最終的に分解することを示している。 総吸収強度プロットのピーク位置での IR スペクトルを図 22 に示す。ピーク位置の IR スペクトルは、カルボニル化合 物のスペクトルであるが、同定までは至らなかった。 図 23 測定時間に応じた各波数吸収とその強度(窒 総測定時間中の各波数の吸収強度を、時間、波数、強 素中モジュール B 第 4 層、第 5 層) 図 20 TG-DTA 曲線(窒素中モジュール B 第 4 層、第 5 層) 図 24 TG-DTA 曲線(空気中モジュール B 第 4 層、第 5 層) 度で 3 次元表示したものを図 23 に示す。 これらから、窒素中での PET の分解挙動は、PVF や EVA とは異なり、温度上昇と共に主鎖の切断が進行するこ とが確認された。 次に、モジュール B 第 4 層、第 5 層の PET を空気雰囲 気下で測定した TG-DTA 曲線を図 24 に示す。 分解開始温度は窒素中とほぼ同じ約 300℃から開始して 図 21 総赤外吸収スペクトルの時間変化(窒素中モ ジュール B 第 4 層、第 5 層) いるが、約 480℃からの第2段階減量が生じている。DTA 曲線は、双方の減量共に強い発熱を示しており、空気中の 酸素による燃焼分解を起こしていると考えられる。 IR の総吸収強度のプロットを図 25 に示す。窒素雰囲気 下と異なり 2 つのピークが認められ、これぞれのピークは TG 曲線の第 1 段減量、第 2 段減量に対応している。2 つ のピークでの赤外吸収スペクトルを図 26 に示す。22 分のピー クは窒素中での分解生成物に二酸化炭素がより強く混合し たスペクトルであり、28 分のピークはほとんど二酸化炭素の スペクトルである。 総測定時間中の各波数の吸収強度を、時間、波数、強 度で 3 次元表示したものを図 27 に示す。測定時間内では 図 22 約 23 分のピークでの IR スペクトル 19 分から 25 分にかけては、二酸化炭素以外の含酸素化合 物の生成が認められるが、それ以降は二酸化炭素のみが生 ― 7 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 4.2 MSによるモジュール燃焼生成ガスの測定結果 4.2.1 モジュールAの燃焼結果 ブンゼンバーナーでモジュールを加熱したところ、セル温 度は最高 450℃まで上昇した。表面温度が約 270℃から分 解生成物の検出が顕著になった。 検 出された 質 量 数は、16、26、42、54、58、78、92、 104 であり、EVA の空気中 TG 測定により検出された酢酸 の分子量に相当する質量数 60 は検出されなかった。その 反面、空気中の TG 測定により検出されなかった芳香族化 図 25 総赤外吸収スペクトルの時間変化(空気中モ 合物と思われる質量数 78(ベンゼン)、 92(トルエン)、 104(ス ジュール B 第 4 層、第 5 層) チレン)が検出された。PVF は、置換基のフッ素が隣接水 素とともに脱離すると、図7に示したような共役二重結合を 有する直鎖が生成するため、この主鎖の分解から六員環を 生成し安定化し、その置換体が生じたものと考えられる。 ガスが発生を開始してから約 5 分後には、接炎部分の燃 焼がほぼ終了し、バーナー火炎が第 1 層のガラス面裏面に 達しており、第 2 層から第 6 層までが燃焼、あるいは融解 しているのが観察された。 窒素中、及び空気中の TG 測定により検出された HF は、 MS 装置の機構上、検出はできなかった。 4.2.2 モジュールBの燃焼結果 図 26 約 22 分のピークでの IR スペクトル(上段) モジュール B では、表面温度が約 100℃程度からガスの と約 28 分のピークでの IR スペクトル(下段) 生成が開始した。 検出された質量数は、16、26、42、54、58、78 であり、 EVA の空気中 TG 測定により検出された酢酸の分子量に相 当する質量数 60 は、モジュール A 同様に検出されなかった。 検出された化合物は、PET の構造を考慮すると、熱分解生 成物として生成可能性のあるものと考えられた。加熱開始か ら 2 分 30 秒後には接炎部分の燃焼がほぼ終了し、バーナー 火炎が第1層ガラス面裏面に達しており、第 2 層から第 5 層 までが燃焼したのが観察された。 4.3 加熱分解と炎の燃焼による分解の比較 4.1 及び 4.2 の実験で検出された生成ガスの一覧を表5に 図 27 測定時間に応じた各波数吸収とその強度(空 示す。 気中モジュール B 第 4 層、第 5 層) モジュール構成の部材を単体で加熱分解した際の生成ガ スと、モジュール全体を炎により燃焼させた際の生成ガスに 成していることから、加熱と同時に PET 鎖のテレフタル酸 違いがみられた。TG による加熱分解は、窒素中では高分 部分の分解が生じ、同時に PET 鎖の酸化分解又は生成分 子化合物の構造に由来するものがほとんどであるが、空気 解物の酸化が生じていると考えられる。 中では酸化物や二酸化炭素がほとんどである。 空気中で これより PET は、火災時の火炎中においては約 350℃か ら何らかのカルボニル化合物の生成が予想され、その後二 の酸化物についても、窒素中での分解生成物がその後に酸 化されていると考えられるものが多い。 酸化炭素が生成することが予想される。 これに対して、炎を用いてモジュールを燃焼させた際に生 測定した 3 つの高分子化合物の全てにおいて、窒素中で じる生成ガスは、空気中の酸素により酸化されたと考えられ は高分子鎖の加熱のみによる分解挙動が、空気中では空気 るアルデヒドのような酸化物、また加熱分解により生成し酸 中に含有する酸素が関与した分解が認められ、それぞれに 化されずに検出されたアセチレン等の不飽和炭化水素、及び 対応した分解生成物が確認された。 ベンゼン等の分解後の再結合により生成したと考えられる 化合物が検出している。 ― 8 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 その中でも、 モジュール A、B 双 方 で 使 用されている モジュール燃焼の際の生成ガスは、TG による分解挙動よ EVA は、TG においては窒素中、空気中いずれからも分解 りも複雑なメカニズムによるものと推定された。これは、火 生成物である酢酸が検出しているのに対して、炎を用いてモ 炎の揺らぎにより生じる構成部材の温度むらから、分解が ジュール本体を燃焼させた場合、モジュール A、B どちらの TG の場合のように起こらないことや、分解後に更に炎に曝 モジュールからも酢酸は検出されない。EVA 主鎖からの酢 され高温になることから、その中での燃焼、再結合等が生 酸の脱離は約 300℃で生じており、主鎖の切断温度よりも じているものと考えられる。更に、バックシートにハロゲン 低いため、火炎に曝されて段階的に EVA 温度が上昇する過 化合物を含有する高分子化合物では、有害なハロゲン化水 程では、主鎖からの分解物の生成前に切断反応が生じ、酢 素等が生じる可能性がある。 酸が生成しているものと思われる。しかし、脱離後の酢酸 また、モジュール全体で燃焼させた場合、各層間に用い が周囲の炎に再び加熱されることにより熱分解や酸化分解 られている接着剤も同時に燃焼しており、この影響も無視で を起こし、更に小さい分子となることが酢酸が検出されな きない要因となっている可能性もある。今後モジュール全体 かった原因ではないかと考えられる。 の燃焼を考察する場合、この点も考慮する必要がある。 このように、火炎による分解挙動は、空気中の酸素や火 炎から常時与えられる熱により、分解・燃焼に複雑な挙動 参照、参考文献 を有しているものと考えられる。 1)阿部伸之、塚目孝裕、田村裕之、松島早苗、尾川義 雄、河関大祐、森井統正:火災時における太陽電池モ 5.まとめ ジュールの発電特性、消防研究所報告、No.114、pp.1- 太陽光発電モジュールの構成部材が燃焼の際に生成する ガスについて、単体の構成部材を TG-IR、モジュールを MS 8、2013 2)田村裕之、阿部伸之、松島早苗、河関大祐、塚目孝 により検査した。 裕、高梨健一、尾川義雄:種々の火炎光の分光スペク 構成部材単体では、温度に応じて構成部材特有の熱分 トルと太陽電池モジュールの発電特性、消防研究所報 解生成物が検出された。この生成物は、雰囲気により異な り、特に空気雰囲気下では酸化物の生成が認められ、構成 告、No.115、pp.12-17、2013 3)木下良一、武井義之他、第 29 回熱測定討論会要旨 部材の高分子化合物が酸化分解又は分解後の酸化反応を 集 ,32(1993) 起こしていることが認められた。 表5 各測定での検出ガス一覧 Without fire Modules Compounds Materials Atmosphere hydrogen fluoride silicon tetrafluoride acetic acid n-hydrocarbon* aldehyde* carbonyl compound** methane acetylene propylene butadiene propanal benzene toluene styrene PVF N2 ○ ○ × ○ × × × × × × × × × × Air ○ ○ × × × × × × × × × × × × EVA N2 × × ○ ○ × × × × × × × × × × Air × × ○ × ○ × × × × × △ × × × ○:検出、×:不検出、△:可能性あり、−:測定対象外 *:n-炭化水素及びアルデヒドの鎖長は不明 **:カルボニル化合物のカルボニル基以外の詳細構造は不明 ― 9 ― PET N2 × × × × × ○ × × × × × × × × Air × × × × × ○ × × × × × × × × With fire A B PVF PET EVA EVA Air Air − − − − × × × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × Report of National Research Institute of Fire and Disaster No.116(2014) Degradation gas at the time of combustion of a photovoltaic generation module constituent material (Abstract) Takahiro Tsukame, Nobuyuki Abe, Hiroyuki Tamura, Sanae Matsushima, Yoshio Ogawa, Ken-ichi Takanashi, Daisuke Kozeki, and Hiroaki Shimizu (Accepted February 4, 2014) Photovoltaic power systems, using solar energy as renewable energy, become now widely used on houses, mega solar power plants, and so on. We reported an electric danger of photovoltaic module when it burned and exposed to flame. In this strudy, thermal degradation products from each component polymers of photovoltaic module were identified by infrared spectrometer combined thermogravimetry(TG-IR). And the degradation gas when modules burned with fire was examined by mass spectrometer(MS). The result of TG-IR was compared with its of MS. From th result of measurement of TG-IR, fundamental degradation compounds which sample polymers heated under atmosphere of nitrogen or air were detected. However, in the case of burning the module by the flame, the combustion of constituent material of the module was shown different behavior from TG-IR. ― 10 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 技術報告 消防活動時の太陽電池モジュールの感電危険性 松島 早苗、田村 裕之、阿部 伸之、高梨 健一、塚目 孝裕、 河関 大祐、尾川 義雄、志水 裕昭 (平成 26 年 2 月 13 日 受理) 太陽電池モジュール火災の消防活動時における消防隊員の安全確保の観点から、感電危険性把握のた め、個人装備品としての手袋、靴と破壊器具の抵抗を調べた。手袋の抵抗については、水に濡れた状態 では絶縁性が悪く、感電の危険性が高くなることを定量的に評価した。 また、太陽光のもとで、モジュールを破壊して、発電状況を測定した。破壊器具を使ってモジュール を部分的に破壊しても、モジュールによっては発電の可能性があることから、消防活動時のモジュール の取り扱いには注意を要することがわかった。 1.はじめに 2.1 手袋の抵抗測定実験 再生可能エネルギーの普及促進により、一般住宅の屋根 2.1.1 手袋の種類 にも太陽電池モジュール(以下、モジュールと記述)の設置 実験対象としての手袋の選定に際しては、消防本部で実 が多数見られるようになってきた。このことは、火災が発生 際に使用されている手袋を調査し選択した。表 1 に示すよう した場合に、屋根に取り付けられたモジュールが、建物とと に、測定した手袋は全部で 11 種類である。主に牛皮革で もに火炎にさらされる可能性が高くなったことを意味する。そ 作られた手袋①、②、③、④、皮革とケブラー繊維で作ら のような状況の中、消防活動において留意すべき新たな危 れた手袋⑤、⑥、⑧、⑨、⑩、甲と掌にケブラー繊維を使っ 険の一つとして、消火活動中や残火処理中に、破損したモ た手袋⑦、この他に防水性のある一般の手袋⑪についても ジュールへの接触や漏電による消防隊員への感電が考えら 抵抗の測定を行った。 2) が報告されて れる。現実に、消防隊員が感電した事例1, 2.1.2 測定方法 いる。 人体への感電では、電流が手袋の内部を流れて人体に そこで、個人装備品( 手袋、靴 )および破壊器具の電 影響を与えることから、手袋の体積抵抗率を調べることとし 気抵抗(以下、抵抗と記述する) を測定するとともに、 モジュー た。体積抵抗率は、単位体積当たりの抵抗値で、物質に ルの破壊実験を行い、消防隊員の感電危険性を評価した。 固有の物理量であり、多くの材料の導電性の絶対的な尺度 あわせてモジュールの破壊時に、モジュールの種類によって、 として用いられている。 発電状況が異なったことについても報告する。 体積抵抗の測定には、抵抗測定装置(株式会社アドバ ンテスト、R8340A デジタル超高抵抗・微少電流計)を使用 2.個人装備品(手袋、靴)の抵抗 した。本来ならば、製品としての手袋の抵抗値を測定する 消防隊員は、活動中の安全性を高めるため、安全保護 ことが望ましいが、本装置では製品の状態で体積抵抗を測 具を装着している。特に、活動中の隊員への感電を防止す 定することはできない。実際の消防活動においては、手袋 るには、絶縁性の高い装備品であることが望ましい。また、 の掌でモジュールに接することが多いと考えられ、また破壊 消防活動に使用する破壊器具についても、感電防止のた 器具の使用時も、手袋の掌と破壊器具が接触すると考えら めには絶縁性が高い器具がよく、これらの装備品が、どのよ れる。このことから、手袋の掌の部分を中心に、ハサミを使 うな絶縁性能を持っているかを明らかにする必要がある。 用して、直径約 100mm の円形の試料を切り出し、図 1 の 消防活動時の感電防止策の資料とするため、活動中に ようにアルミシートで作成した測定用電極を用いて測定した。 モジュールに接触する可能性があるものとして、手袋、靴、 2 重円環の電極は、外側のガード電極と内側の主電極を使 破壊器具の抵抗を測定した。 用すると表面抵抗が測定でき、主電極と試料を挟んだ対向 ― 11 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 表1 手袋の種類 電極を使用すると、体積抵抗が測定できる。 した手袋は、すべて未使用品である。この試料を使用して、 各試料の厚さは、マイクロメータを使用して 5 か所を計測 乾燥状態と水に濡れた状態の体積抵抗を測定した。 測定 した値の平均とした。測定結果を表 1 に示す。測定に使用 時に試料を電極で挟む荷重は 2kg とした。 抵抗の測定を ― 12 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 行うと、測定開始からの時間により測定値が変化するため、 ケブラー繊維と組み合わせた手袋は 10 15 Ω・cm より大きい 測定開始から 3 分後の比較的安定した値を手袋の抵抗値 値であった。皮革の手袋よりも、ケブラー繊維を組み合わせ とした。試料に加える電圧(印加電圧)は、実際の屋根に た手袋の方が、10,000 倍以上大きい体積抵抗率を示した。 設置されるモジュールの総発生電圧の最大値をおよそ 300V 手袋の体積抵抗率は、石英ガラスの 10 18 〜 10 19 Ω・cm ほ と推定し、すべて 300V とした。 測定室内の温度は 18 〜 ど大きくはないが、乾燥木材 10 10 〜 10 13 Ω・cm と同程度 の抵抗率をもっており、新品の手袋ではかなり絶縁性が高 25℃、湿度は 33 〜 44% であった。 抵抗測定装置により、体積抵抗 Rv(Ω)を計測した後、 いことが分かった。 体積抵抗率 ρv( Ω・cm)を式⑴で求めた。 ⒝ 水に濡れた手袋の場合 体積抵抗Rv 体積抵抗率 ρv =S× … ……………… ⑴ 試料の厚さt 手袋が水で湿ることがある。そこで、手袋が水に濡れた状 S:直径5cmの主電極の面積19.63(cm 2) 消防活動時では、消火のために水を使用することから、 態では、どのように抵抗に変化があるかを調べた。 手袋の 2.1.3 測定結果 場合、撥水性があるなど手袋によって効果が変わると思わ ⒜ 乾燥した手袋の場合 れるため、試料を水でぬらす方法として、試料をぬらし指で 乾いた手袋の体積抵抗と体積抵抗率の結果をそれぞれ 図 2、図 3 に示す。 乾いた手袋の体積抵抗値は概ね 10 8 たたいて一様に湿潤した。試料がどれくらい水を含んだかは、 水をしみ込ませる前後の重量変化で表した。 〜 10 14 Ωである。この抵抗値を使って算出した手袋の体積 抵 抗 率は、 概ね 10 10 〜 10 16 Ω・cm の間であった。 牛 皮 革だけを使った手袋の体積抵抗率は、10 12 Ω・cm より低く、 図3 乾いた新品手袋の体積抵抗率 (横軸の丸数字は表1に対応) 図1 試料の抵抗測定用電極 図2 乾いた新品手袋の体積抵抗 図4 水に濡れた手袋の体積抵抗 (横軸の丸数字は表1に対応) (横軸の丸数字は表1に対応) ― 13 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 なお、水に濡れた試料の抵抗値の測定の際も、乾燥手 み込む時の荷重は約 20kg で、重量計の表示が約 20kg と 袋と同様に印加電圧を 300V とした。その結果を図 4 に示 なるようにして、靴底の抵抗を 1 回測定した。印加電圧は、 す。 300V である。測定は、抵抗測定装置で行った。 手袋にしみ込んだ水の影響を調べるため、丈夫で吸収性 2.2.3 測定結果 のあるふき取り紙(株式会社クレシア、ケイドライ ®ワイパー 図 7 に示すように、測定した靴の抵抗は、1 × 10 6 〜 1 132-S)を四つ折りにして、中央に水を含ませて同様に抵抗 × 10 12 Ωの値であった。その中の静電気帯電防止型の長 の測定を行った結果、約 22k Ωであった。水に濡れた手袋 靴②、編み上げ作業靴⑦と⑧の抵抗値は、およそ 10 6 Ωオー の抵抗値は 21 〜 60k Ωで、ふき取り紙を利用して測定し ダーであり他の靴よりも小さかった。 た値と同程度の値であり、乾いた手袋の抵抗値図 2 と比べ 2.3 破壊器具の抵抗測定実験 ると極めて小さい値となった。 水に濡れた手袋の含水量を 2.3.1 破壊器具の種類 図 5 に示す。試料の厚みが大きいと含水量は多くなる傾向 消防活動の際に、窓ガラスや家屋を壊すために使用され がみられた。この結果から手袋は水を含むと抵抗値が小さく る破壊器具として、ここでは人の手で扱う万能斧、とび口 なり、その値は含まれる水の抵抗値によると考えられる。図 の 2 種類を測定した。測定した破壊器具を表 3 に示す。 4の④、⑨は抵抗値が大きいが、④は試料の厚さ、⑨は防 2.3.2 測定方法 水仕様で水が通りにくい部分が影響しているのではないかと 破壊器具のグリップや柄にアルミテープを巻きつけて、抵 考えられる。 2.2 靴の抵抗測定実験 2.2.1 靴の種類 消防隊員が使用する作業靴として、表 2 に示すようにゴ ム製の長靴 6 種類と編み上げ作業靴 4 種類の計 10 種類 について抵抗を測定した。JIS T8101 の規格をもつ安全 靴、JIS T8103 の静電気帯電防止タイプの静電靴が主で ある。 2.2.2 測定方法 消火活動中に、人体が電気の流れているものに接触した としても、電気が人体を流れる通り道がなければ感電はし ない。そこで人体から電気が流れるときの通り道となる靴底 の抵抗を測定した。測定方法は図 6 に示すように、重量計 (ザルトリウス株式会社、LA34001S)の上に靴を置き、靴 の中敷きの上に幅 50mm のアルミ製のテープをのせた状態 で、片足を入れてテープを踏んだ。その状態で靴の下に敷 いた電極板とアルミテープ間の抵抗を測定した。テープを踏 図6 靴底の抵抗測定用電極 図5 水に濡れた手袋の含水量 図7 靴の抵抗値 (丸数字は表1に対応) ― 14 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 表2 靴の種類 ― 15 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 表3 測定に使用した破壊器具 ※抵抗測定箇所は、写真に示した2つの矢印の間 抗の測定を行った。抵抗の測定位置は、万能斧①〜④は かることが考えられる。特に破壊器具の柄が木製の場合は、 尖端とグリップの間、とび口①は尖端と尖端から 164cm の 水によって絶縁性が悪くなることが考えられる。 間、とび口②は尖端と尖端から 77cm の間であり、表 3 に そこで、水がしみ込みやすくするため、柄が木製であると 矢印で示す。塗装された尖端は複数回使用したことを想定 び口②の表面の塗料をサンドペーパーでこすり落とし、2 日 して、やすりで塗装を部分的に除去した。柄の測定箇所も、 やすり掛けを行った。 測定装置としては、抵抗値に応じて デジタルマルチテスター(Agilent 社、 U1252A)および抵 抗測定装置を使用した。 抵抗測定装置を使用した時の印 加電圧は 300V である。測定回数はそれぞれ 1 回である。 2.3.3 測定結果 ⒜ 乾燥した破壊器具の場合 破壊器具の抵抗の測定結果を図 8 に示す。万能斧のグ リップ部分の抵抗値は、概ね1× 10 4 〜1× 10 13 Ωまで幅広 い値を示した。万能斧①の抵抗値は、約 5k Ωと他の万能 斧と比べて、小さかった。とび口の抵抗値は、1× 10 9 Ω以 上あり、絶縁性は良いと言える。万能斧の金属部分の抵抗 は、ほぼ 0 であった。 図8 破壊器具の抵抗値 ⒝ 水に濡れた破壊器具の場合 破壊器具は、消防活動時の放水の影響により、水がか ― 16 ― (とび口② ’ はとび口②の柄を水でぬらしたもの) 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 表4 単結晶シリコンモジュールと CIS モジュール との仕様 5,6) 型式 NU-122CB SF160-S シャープ㈱ ソーラーフロンティア㈱ 単結晶シリコン CIS 122 160 会社名 セルの種類 最大出力 (W) 最大出力動作電圧 (V) 14.96 84 最大出力動作電流 (A) 8.16 1.91 開放電圧 (V) 18.77 110 990 × 856 × 46 1257 x977 x 35 11 20 外形寸法(幅 mm × 奥行 mm ×高さ mm) 質量 (kg) 図9 人体の感電モデル 間水に浸した。その後、素材が樫と推定して木材水分計(株 業やモジュールを破壊する作業を考慮しておかなければなら 式会社ケット科学研究所、MT-900)で水分を測定した結 ない。特に、太陽光の下では、モジュールが常に発電状態 果、約 32% であった。とび口尖端と柄の間の抵抗の測定 にあることから、モジュールの除去や破壊作業では、消防隊 結果を図 8(とび口② ’) に示す。水に浸した時の抵抗値は、 員に感電の危険が及ぶことが考えられる。そのため、 モジュー 乾燥時と比べておよそ 1000 分の 1 の 190k Ωまで低下した。 ルの種類によってどのような発電特性があるかを検討する必 乾燥している状態では、高い絶縁性を有する木製のとび口 要がある。そこで、 モジュール1枚を実験的に破壊し、 モジュー であっても、水の影響で抵抗値が低くなることが分かった。 ルによる電圧変化を測定した。 2.4 感電危険性の評価 3.1 モジュールの種類 住宅用やメガソーラー発電用のモジュールとしては、単結 人体の感電のモデルを図 9 に示す。ここで、破壊器具 の抵抗値が無視できるほど小さいものとし、モジュールから受 晶シリコン、多結晶シリコン、CIS(銅、インジウム、セレン) ける電圧を 300V とする。濡れた手袋を通じて、電気が片 が一般的に使用されている。 実験にはこれらのモジュール 方の手から人体に入り、もう片方の手から出ると想定する。 を使用した。単結晶シリコンと多結晶シリコンでは太陽電池 水に濡 れた手 袋の円 形 試 料( 主 電 極との接 触 面 積は そのものは異なるが、モジュール内部の電気回路構成は同 19.63cm )の抵抗値を 20k Ω、物を掴んだ時の手袋の掌 じである。 破壊器具による実験では、単結晶シリコン及び の接触面積を約 40cm 2 とする3)と掴んだ時の抵抗値は 10 CIS の 2 種類のモジュールを使用した。使用した単結晶シ k Ωとなる。 両手では直列となり 20k Ω、更に人体の抵抗 リコンモジュールは、シャープ株式会社製の NU-122CB モ 500 Ωが加わって合計 20.5k Ωとなる。 人体を流れる電流 ジュールである。CIS モジュールは、ソーラーフロンティア株 2 は 14.6mA と計算でき、可随電流(または離脱電流)は、 式会社製の SF-160S モジュールである。仕様は、表 4 の 直流で 20mA 4)といわれているが安全とは断定しにくい。 ようになっている。 万能斧①の抵抗値 5k Ωを考慮し、万能斧を通じて、斧 3.2 実験装置 を掴んでいる手袋、人体と電気が流れ、もう片方に電気が モジュールを固 定するため縦 100mm ×横 50mm ×厚さ 逃げていくとすると、抵抗は合計で、25.5k Ωとなり電流値 2mm の鋼製の軽溝形鋼を用いて、4 本脚の固定台を製作 は 11.8mA となった。 した。固定台の大きさは、縦 1100mm、横 1185mm、高さ 片手から電気が入り人体を通して両足に抜けたと仮定す 400mm である。破壊の衝撃によって、モジュールが固定台 る。抵抗値 4M Ωの靴(片方)を通して電気が流れる場合、 からずれないように、モジュールの四隅と固定台を小型のシャ 300V の電圧が両方の靴底にかかるため、両方では靴の抵 コ万力を使って固定した。さらに、破壊の衝撃による固定 抗値は 2M Ωとなる。人体の 500 Ωと片手の抵抗 10k Ωは 台の揺れを少なくするように、固定台に 10kg の砂袋を 2 か 2M Ωに比べて無視できるほど小さい。この抵抗値では、流 所取り付けた。 れる電流値は 0.15mA としびれを感じ始める電流値 2mA 4) 以下であり安全側である。 破壊するモジュールと破壊しないモジュールの出力電圧を 比較するため、図 10 のように破壊するモジュールの隣にブ ロックを置いて、破壊しない別の同型モジュールをブロック上 3.モジュール破壊時の発電確認実験 に設置した。モジュールの出力電圧変化を測定するために、 消防活動では、消防隊員が複数枚のモジュールが設置さ モジュールの出力端子に負荷抵抗に見立てた抵抗器を取り れた建物の屋根に上り、モジュールを屋根から撤去する作 付けた。単結晶シリコンモジュールは 2 Ω、CIS モジュール ― 17 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 図 11 万能斧①による破壊後の単結晶シリコンモジュール 図 10 単結晶シリコンモジュールの実験装置 には 50 Ωをそれぞれ取り付け、抵抗器の両端子をデータロ ガーに接続した。 照度の経時変化は、照度計(コニカミノ ルタセンシング株式会社、T-10W LA)で測定した。 3.3 単結晶シリコンモジュール 3.3.1 破壊方法 破 壊 実 験について、 消 防 研 究センターの本 館 屋 上で、 2013 年 8 月 21 日に行った。 天 候は晴 れ 気 温は、37 ℃、 湿度は 47% である。 破壊器具としては、表 3 の万能斧①を使用した。これを 使って、現役の消防隊員の手によって、モジュールの表面 図 12 単結晶シリコンモジュール破壊時の出力電圧比 のガラス面から裏面まで、尖端部が貫通するようにして破壊 した。 1 回目の打撃に引き続き、発電しなくなるまで万能斧①の ラスタごとに出力が出せなくなっている。破壊後に、モジュー 尖端部、斧部により同じモジュールを使用し、打撃を繰り返 ルに 2 回散水を行った。散水時と発電時期はずれており、 し行った。破壊場所は図 11 のように計 6 回か所である。こ 散水の影響は確認できなかった。 のモジュールは、3 つのクラスタ から構成されていた。1つ 3.4 CISモジュール のクラスタにつき 2 か所貫通破壊するように打ち付けた。そ 3.4.1 破壊実験 7) の後、水による影響を調べるために、モジュール破壊部分 実施日は、単結晶シリコンモジュールと同じ 2013 年 8 月 にバケツで水道水を流した。これらによりモジュール破壊時、 21 日である。単結晶シリコンモジュールと同じように、CIS モ 及び散水時のモジュール発電状況を調べた。 ジュールの表面から裏面まで、万能斧①の尖端部が貫通す 3.3.2 破壊時のモジュール出力電圧 るように打ち付けた。 モジュールの出力電圧は、日照により変化する。破壊実 破壊器具の尖端部がモジュールに貫通したところを表面か 験時の影の影響をなくした発電状況を見るため、縦軸に壊 ら観察すると、図 13 のように、万能斧①が貫通した部分か したモジュールと壊さないモジュールの電圧比をとって、破 ら直径約 20cm の広がりでクモの巣状に表面ガラスにヒビが 壊時の電圧比を時系列に示したものが図 12 である。 入った。それ以外のガラス面でも、モジュールの表面が強化 モジュールをセル間の配列を切るように破壊していくと、出 力電圧が減少していった。3 回の破壊で約 2/3、6 回の破 ガラスで覆われているため、ガラスに細かなヒビが入った状態 となった。 壊で約 1/3、その後に斧部で損傷部を 3 か所拡大したとこ モジュールの裏面からも観察すると、破壊器具の尖端が ろ出力電圧は 0V となった。破壊した時刻と出力電圧比の 裏面から突き出ていた。 変動時刻は一致してはいない。しかし、モジュールは3つの 3.4.2 破壊時のモジュール出力電圧 クラスタの構造を持っているので、出力電圧値が約 1/3 ず 実 験 時の太 陽 光の照 度は、70,000 〜 130,000 lx で、 つ減少している理由は、モジュールの構造に関係があり、ク CIS モジュール1枚の出 力 電 圧は最 大で約 82V だった。 ― 18 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 ンモジュール 14 枚を 2 列に並べ、破壊するモジュールをそ の端に設置し、合計 15 枚のモジュールを直列に接続した。 破壊時にモジュールが動かないように、いままでの破壊実 験と同様、固定台に固定した。破壊器具として、3 種類の 万能斧①、万能斧③、とび口①を使用した。1種類の破壊 器具について、1 枚のモジュールを破壊する実験を行った。 4.2 出力電圧の測定方法 破壊器具の尖端部に導線を取り付け、これを人体の抵 抗値に見立てた抵抗器 500 Ωに接続し、この抵抗器の端 子電圧を間接的に測定した。 電圧測定回路図を図 16 に 示す。15 枚のモジュールを直列に結線した場合、1 枚につ き開 放 電 圧 値は 18V 以 上あるので、15 枚 全 部を直 列に 図 13 万能斧①の尖端が貫通した CIS モジュール 接続すると約 270V の直流電圧値となる。データロガーが取 り扱える最大電圧値が 100V であったため、データロガーへ の入力のために、電圧を下げる必要があった。そこで、抵 抗器 470k Ωと抵抗器 33k Ωを直列接続した計測用合成抵 抗器を抵抗器 500 Ωに並列接続し、抵抗器 33k Ωの端子 電圧を測定することにより、抵抗器 500 Ωの端子電圧を算 出した。計測用合成抵抗器を並列に接続しても抵抗器 500 図 14 万能斧①による CIS モジュール破壊時の電圧 CIS モジュールを破壊した時の出力電圧は、破壊した瞬間 から図 14 に示すように 0V となった。実験で使用した CIS モジュールは、破壊器具の一撃で、尖端部が表面から裏面 まで貫通すると、直ちに発電が停止することが確認された。 CIS モジュールに比べて、単結晶シリコンモジュールの出力 図 15 破壊する単結晶シリコンモジュールを含め モジュール 15 枚を並べた実験装置 を抑えるには、徹底した破壊が必要である。 4.複数の単結晶モジュール接続時の破壊実験と出力電圧 消防活動中、直列に接続された複数のモジュールのうち 1 つを破壊器具で破壊し、消防隊員がその破壊器具の金 属部分に触れた場合を想定して、高電圧がかかった状態 での破壊実験を行った。また、破壊器具の種類を変えてモ ジュールの破壊実験を行い、破壊状況の観察、出力電圧 の測定を行った。 4.1 実験方法 消防研究センターの本館屋上で、2013 年 8 月 20 日に単 結晶シリコンモジュールの破壊実験を行った。天気は晴れ、 気温 35.5℃、湿度 45% であった。 一般住宅の屋根に設置した時と同程度の電圧を発生させ た状態で破壊実験を行うため、図 15 のように単結晶シリコ ― 19 ― 図 16 単結晶シリコンモジュール破壊実験の電圧 測定回路 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 Ωに流 れる電 流の変 化は、0.1% 程 度に抑えられるため、 ルに使用されている樹脂が熱分解して酢酸が生じたことによ 人体を模擬した抵抗を流れる電流への評価には影響はない ると考えられる。ガラスの破砕状況、接触部分については、 と判断した。 破壊器具の種類による違いは見られなかった。 4.3 破壊器具によるモジュールの破損状況 4.4 破壊時の出力電圧 万能斧③を使って、モジュールの表面ガラスから裏面に 万能斧③を打ち付けた時の出力電圧値の変化を図 18 に 破壊器具の尖端部が貫通するように、成人男性の力でモ 示す。実験時の太陽の照度は、70,000 〜 120,000 lx で ジュールを打撃した。 感触では、容易にモジュールを貫通 ある。打撃時には、抵抗器 500 Ωの端子電圧は、0V を示 することができたとのことである。万能斧③により破壊したモ していた。このことは、破壊したモジュールから万能斧には、 ジュールの様子を図 17 に示す。 電流は流れていないことになる。消防隊員の破壊動作中に、 破壊器具貫通後のモジュールの表面ガラスの状況を観察 破壊器具がモジュール内の発電回路に接触することを想定 すると、尖端部が貫通したところからクモの巣状にガラスが し、万能斧をモジュールに刺した状態で、えぐるように動か 割れ、貫通場所以外でも、ガラスにヒビが入った状態となっ したところ、抵抗器 500 Ωの端子電圧が約 240V を示した。 た。 万能斧③をモジュールに突き刺したまま動かすと、出力電圧 図 17 に示すように、万能斧③とモジュールとが接触して 値は 0V と約 240V の値を行き来するように変化した。 いる部分では放電と思われる眩光、火炎が見られ、その部 他の破壊器具でも同様に、刺したままで破壊器具を動か 分から煙の発生、刺激臭が観察された。これは、モジュー すことにより、電気が流れたり、流れなかったりする状況が 観測された。 破壊作業中も、破壊器具に 300V 程度の高 電圧の電気が流れることから、感電には注意を要する。 5.まとめ 消防活動時の消防隊員の安全確保の観点から、感電に 関連して個人装備品(手袋、靴)や破壊器具の抵抗を調 べた。また太陽光のもとでモジュールを破壊し、破壊時のモ ジュール出力特性、人体にかかる電圧の評価について考察 した結果、次のようなことが分かった。 ⑴ 手袋の抵抗を測定した結果、新品の乾いた手袋では、 しかし、水 体積抵抗率1×10 10Ω・c m以上の絶縁性がある。 がしみ込むと絶縁性が低下し、水の導電性と同じになる。 手袋に水がしみ込んだ場合、 モジュールを取り扱う際には、 図 17 万能斧③による単結晶シリコンモジュール の破壊。矢印の先に眩光が見える。 慎重に作業を行う必要がある。 ⑵ 万能斧のグリップ部分は、乾燥していても絶縁性が低い ものもある。柄が木製のとび口では、消火時に柄が水で濡 れると絶縁低下の恐れがある。 ⑶ 単結晶シリコンモジュールでは、 モジュールの数か所を太 陽電池セル間の配列を切るように破壊器具で破壊し続け ると、発電が止まった。一方CISモジュールでは、破壊器具 がモジュールを貫通した時点で発電が止まった。 ⑷ 複数の単結晶シリコンモジュールを連結して高電圧が発 生する発電状況のもとで、破壊器具でシリコンモジュールを 壊したところ、モジュール破壊部分と破壊器具との接触部 分で、眩しい光、火炎、刺激臭、煙が観察された。破壊器具 をモジュールに刺した状態で、 えぐるように動かしたところ、 人体を模擬した抵抗器500Ωの端子電圧が約240Vを示し 図 18 万能斧③により複数連結した単結晶シリコ ンモジュールを破壊した時の人体を模擬した 抵抗にかかる電圧の経時変化 た。 さらにモジュールに突き刺したまま動かすと、出力電圧 値は0Vと約240Vの間を変化した。 ⑸ 複数のモジュールが連結された場合では、モジュールの 一部を破壊しても、感電に十分な電気エネルギーの発生が ― 20 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 考えられることから、個人装備品、破壊器具が水によって 絶縁性が低下している場合には、感電への十分な配慮が 必要である。 謝辞 今回実験で使用した装備品の選択にあたっては、消防研 究センター火災災害調査部原因調査室の調整官、上席主 任調査官、主任調査官各位にご協力をいただきました。こ こに感謝の意を表します。 参考文献 1)小室 修 : 住宅用太陽光発電システムが設置された建 物 火 災の消 防 活 動について、 第 59 回 全 国 消 防 技 術 者 会 議 資 料、pp.127-131、 消 防 庁 消 防 研 究センター、 2011 2)柴田敬吾 : 太陽光発電システムからの出火事例につい て、第 61 回全国消防技術者会議資料、pp.155-167、 消防庁消防研究センター、2013 3) 高 野 剛、 山 本 仁、 原 利 昭:円 筒 物 体 の 握り 感覚の解明、日本機械学会論文集(C 編 )、Vol.63、 No.607、pp.311-317、(1997-3) 4)市 川 紀 充、 冨 田 一:感 電の基 礎と過 去 30 年 間の 死亡災害の統計、労働安全衛生総合研究所安全資料、 JNIOSH-SD-NO.25(2009) 5) ソ ーラー フ ロン ティア ウェブ ペ ー ジ : ア ク セ ス日 2013.09.08、http://www.solar-frontier.com/jpn/ products/commercial_modules/C009963.html 6)シャープウェブページ : アクセス日 2013.09.08、http:// www.sharp.co.jp/sunvista/product/module/ 7) 田 村 裕 之、 阿 部 伸 之、 河 関 大 祐、 松 島 早 苗、 塚目 孝裕、尾川義雄、高梨健一:太陽光発電システムの火 災と消防活動上の問題点、消防研究所報告、No.114、 pp.19-24、2013 ― 21 ― Report of National Research Institute of Fire and Disaster No.116(2014) Electric Shock with Photovoltaic Modules on the Fire Fighting (Abstract) Sanae Matsushima, Hiroyuki Tamura, Nobuyuki Abe, Ken-ichi Takanashi, Takahiro Tsukame, Daisuke Kozeki, Yoshio Ogawa, and Hiroaki Shimizu (Accepted February 13, 2014) Evaluation for the possibility of electric shock is important for firefighters to act on photovoltaic modules fire. We measured electric resistance of firefighter's gloves, shoes and demolition tools for the evaluation. On the basis of the resistances, we evaluated quantitatively that the wet glove had a higher risk than the dry one. We also perform an electric generation experiment of the single-crystal silicon module and the CIS module with striking them. The CIS module stopped generation at the moment of one strike with the firefighter's demolition tool. Electric generation of the single-crystal silicon module gradually decreased as the number of strikes increased. Therefore, we conducted that the firefighters should pay more attention to electric shock as they strike and touch the modules. ― 22 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 解 説 火災の着火源について 鈴木 健 (平成 26 年 2 月 18 日 受理) 火災が発生するための着火源として、以下の 9 種、すなわち、1 衝撃 ・ 摩擦、2 断熱圧縮、3 高温表面、 4 熱線、5 電気火花、6 静電気火花、7 裸火、8 自然発火、9 温風をあげ、災害事例を使って説明した。 1.まえがき 査の調査結果を、消防関連の雑誌等から幅広く収集し、説 火災が発生するためには、気体、液体、固体などの可燃 性物質が燃焼を開始することが必要となる。そのためには、 明に使用することにした。 多くの場合、何らかの着火源が必要である。着火とは、可 2.着火源 燃性物質が一定の条件の下で連続的な燃焼を開始する現象 2.1 衝撃、摩擦 である。発火とほぼ同じ意味である。着火源となるものには 様々なものがある。北川 は、着火源を以下の 8 種、すな 1, 2) 固体に摩擦、衝撃、打撃を加えると、その際の機械的エ ネルギーの一部は熱に変換されて、熱または火花を生じる。 わち、1 衝撃 ・ 摩擦、2 断熱圧縮、3 高温表面、4 熱線、 それが、周囲の可燃性予混合気、可燃性粉じんなどを着火 5 電気火花、6 静電気火花、7 裸火、8 自然発火に分類した。 させることがある。石炭鉱山での災害防止のために、この問 ここでは、上にあげた 8 種に、9 温風を加え、9 種とし、そ 題が熱心に調べられてきた。石炭鉱山では坑内でメタンが発 れぞれについて、災害事例を使って説明することとした。こ 生し、空気と混合して可燃性混合気を形成することがある。 の 9 種の着火源で、火災における着火源を全て説明できる そのため、金属が石炭や岩石を摩擦あるいは切削するときに わけではないが、これで多くを説明できる。 生じる火花または摩擦熱が、可燃性混合気を着火する危険 消防機関は、火災事例、火災原因調査の調査結果を消 性について調べられてきた。試験装置や測定結果が駒井ら3) 防関連の雑誌に掲載している。ここでは、火災原因調査を 、阿部ら4)、木下ら5)、高岡6)によりまとめられている。関係 する際の参考となるように、過去の火災事例、火災原因調 した事例を表 1 に示す。事例 1-1 の調査のために、東京消 表1 衝撃、摩擦が着火源となったと推定された事例 番号 年月 都道府県 概要 出典 7 11 12 1-1 1996.7 東京 首都高速を走行中の移動タンク貯蔵取扱所(タンクローリー)がカーブでバランスを崩し、車体左 側を下にして横転し、道路面を約 60 m 横滑りしながら停止し、炎上した。タンクローリーは、ガ ソリン 12 キロリットル、軽油 4 キロリットル、灯油 4 キロリットルを積載していた。焼損状況と しては、タンク右側胴板が火炎の熱により溶融欠損していた。タンク左側胴板の前部から後部にか けて著しい擦過痕が生じていた。タンクのガソリン収納槽の 4 カ所に亀裂が生じていた。巻き込み 防止枠等と舗装面の間の衝撃火花が、流出したガソリンの蒸気を着火させた。 1-2 1989.3 愛知 木工作業場で火災が発生し、倉庫兼用の作業場が全焼した。作業場の丸鋸盤鋸屑が堆積する場所が 出火箇所と考えられた。丸鋸盤により挽材中に、丸鋸の刃先に取り付けられている超硬チップ付近 が木材との摩擦により発熱し、このチップ付近の鋸屑が着火した。これが丸鋸盤下に堆積していた 鋸屑内に落下し、その後無炎燃焼を継続し出火に至った。 東京 11 時 5 分頃に木材加工の事業所で、自動旋盤(NC 旋盤)にアメリカ産の「栓の木」を切削のためにセッ トし、無人の状態で作業中に、切削くずの木くずが着火し、集塵機内に堆積した木くずに延焼し火 13 災となった。切削工具と「栓の木」との摩擦熱で木くずが発熱し、着火した。これが集塵機に移動し、 集塵機内で他の木くず等に延焼し、火災になった。 東京 複合用途ビル(耐火造 56/6)の 50 階のエレベータ機械室から出火し、火災階付近の階の在館者 851 名が避難した。原因は以下のようであると考えられた。エレベータのワイヤーロープを構成す る 8 本のストランドの内 1 本が摩耗して破断した。エレベータの昇降の際に破断したストランドが 剥離して付近の金属(ロープガード、シープガード)に接触したことにより火花が発生した。シー プガードに堆積していた油分を含むスラッジが、火花により着火した。 1-3 1-4 1991.11 2007.4 ― 23 ― 14 15 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 防庁では、炭素鋼板とアスファルトの間で発生する火花がガ ② 空気中での可燃性ガスの爆発範囲よりも、酸素中での ソリン蒸気を着火させうるかどうかを実験により検討した 可燃性ガスの爆発範囲の方が広い。 7, 8) 。また、日本自動車研究所では、自動車事故を想定し、摩 ③ 空気中での発火温度よりも、酸素中での発火温度の方 擦火花の温度を実験 9)と理論計算 10)により調べた。 が低い。 2.2 断熱圧縮 表2 空気の断熱圧縮による圧力および温度の上昇 一般に、容器に入れた気体を圧縮すると、圧縮に費やさ 圧縮前体積 圧縮後の体積 れた仕事は熱に変わる。圧縮が急速に行われると熱損失が 少なくなるので、容器内の気体の温度が上昇する 16,17)。空 気の場合の断熱圧縮による温度上昇を表 2 に示す。特に注 意すべきは、酸素ガスを断熱圧縮してしまった場合である。 酸素には以下のような特徴がある 18-20)。 ① 酸素は、他のものの燃焼を助ける性質(支燃性)があ る。空気中では不燃性とされているものでも、酸素中では 可燃性となることがある。 圧縮後の圧力 [atm] 圧縮後の温度 [℃] 1 1.0 20 5 9.5 284 10 25.0 462 20 66.0 698 空気を理想気体と仮定する 5 圧縮前の圧力を 1 atm (=1.01 × 10 Pa)、温度を 20 ℃ (293 K)、 比熱比を 1.40 とする 表3 断熱圧縮が着火源となったと推定された事例 番号 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 年月 1972.7 1979.8 1979.5 1971.9 2001.1 都道府県 概要 出典 静岡 消防署の新入職員を前に救急車から取り外した人工蘇生器の取扱い方法の説明を行った際に、酸素 容器のバルブを開いた瞬間に、圧力調整器の側面から火炎が噴出した。これにより、職員 3 名が火 傷を負った。原因は、圧力調整器内部又は周辺に油脂類、金属粉体等が付着していたことによると 推定された。 31 福岡 交通事故でけがをした幼児を救急車で搬送していた。酸素ガスを与えていたところ、容器の酸素ガ スが切れた。他の容器の切替えバルブを開けたところガス漏れが起きた。バルブを閉めたが火が噴 き出した。救急車内には患者を含め 6 人が乗っていたが全員無事だった。原因は、容器バルブに金 属粉が付着しており、温度上昇によって着火したと推定された。 31 東京 交通事故に出場した救急隊が、頭部に外傷を受けた 11 歳の男の子に酸素吸入をしようとし、装置 をセットし、ボンベのバルブを開くと、相当な異臭があり気分が悪くなるほどであった。また、こ の臭いは今までかいだことのないような臭いで、吐き気をもよおすような感じであった。そのため、 ボンベのバルブを閉めて、代わりに人工蘇生器を使い急場をしのいだ。帰署後、再び救急隊長が吸っ 32 てみたがまだ臭いは強かった。外見検査では、全く異常は認められず、弁の作動も正常であった。 そこで器具を分解したところ、ボンベのバルブシートが焼損していた。原因は、バルブシートにグ リースなどのオイルが付着していたか、ホコリなどのゴミがバルブ開閉時に着火したかのいずれか と推定された。 東京 救急車に積載の人工蘇生器(ミニットマンレサシテータ)の作動状況を点検するため、ケースから 蘇生器を取り出し、減圧弁が ADULT(大人)と INFANT(子供)の中間にあることを確かめた後、 ボンベのコックを 1/4 回転ぐらい開いた。開くと同時に減圧弁付近でシューという音と共に閃光を 発して 60 cm くらいの火炎が吹き出しはじめた。そこで粉末消火器を使いながらボンベのコックを 閉め、酸素の流出を断って消火した。ボンベ圧は 90 kg/cm2 であった。負傷者はなかった。焼損し 32 たのは減圧装置内部とその付近だけであったので、内部からの出火であると考えられた。そこでボ ンベ内部の腐食、酸素充てん時のスラッジの混入、オイルの付着、器具本体の性能、器具取り扱い 状況などを調査した結果、バルブを急激に開いた時局部的な断熱圧縮がおこり、減圧弁内のナイロ ンが酸素雰囲気中で過熱され出火したものと判断された。 栃木 119 番通報により、動悸、体の震えのあるお年寄りを病院に搬送した。患者は救急車に設置された 容器から酸素ガスの供給を受けた。病院内に運び込む際、携帯用酸素容器に切替えたところ、炎が 上がった。救急隊員 1 名がやけどにより重傷となった。また、患者と付添人 1 名も軽傷を負った。 31 原因は、圧力調整器内のフィルターにアルミ粉、鉄粉等の異物が入り、温度上昇等によって着火し たと推定された。 31 33 34 2-6 2007.6 長野 病院のドクターカーに配備されている医療用酸素供給設備の酸素容器の交換を行い、バルブを開い たところ、突然圧力計が破裂し、運転手 1 名が軽傷を負った。発災の約 3 週間前に圧力調整器 1 次 側の圧力計が交換され、以後発災当日までは問題なく使用されていた。酸素供給設備に使用される 圧力計にもかかわらず禁油処理が施されていなかったため、酸素容器の交換のためにバルブを開い た際、圧力計内の油脂類が着火し、破裂につながったと推定された。 2-7 2003.8 n 救急車が出動し、3 名の救急隊員の内の 1 名が酸素吸入を行うため、酸素蘇生器の準備作業をして いた。酸素容器のバルブを開けた瞬間、圧力調整器から着火し、酸素容器が 4 m ほど飛翔した。隊 員 1 名が重傷、1 名が軽傷を負った。原因は不明とされたが、圧力調整器の定期的なメンテナンス は行われていなかった。 n: 記載無し ― 24 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 ④ 高濃度の酸素中では、金属粉、ほこり、石油類、グリー 着火源になりうるほど電球表面の温度が高くなる 41-44)。電 ス、油脂、皮脂等は容易に発火する可能性がある。 球は本来、照明器具であり、発する光を遮るような物で覆っ 酸素容器の圧力調整器の内部に油脂があったり、接続口 たり、囲ったりすることは想定されていない。本来の用途で のパッキンに可燃物を使用しているとき (例えば、 ビニールテー あれば、表面温度が高くても問題はないはずである。しか プなどをパッキンの代用品としている場合)、酸素容器の元 し、厚手の布団のような断熱材として作用するもので電球を 弁を急激に開けると、圧力調整器内にあった酸素が、容器 覆えば、放熱が抑制され、電球の表面温度がさらに上昇する。 内から流れてきた高圧の酸素により急速に圧縮される。こ その結果、電球を覆っている物を着火させることがある。 の断熱圧縮により圧力調整器内の酸素が高温となり、油脂 木材に関しては、長期加熱と低温着火により出火するこ 。関係した事例 とがあると指摘されている 45)。木材が、長期間にわたり発 や可燃物が加熱され着火することがある 21-25) を表 3 に示す。事例 2-7 については、原因は不明であるが、 火温度以下の低温度で加熱されると、徐々に炭化されて無 救急活動中の負傷事例であるので、参考のために表 3 に加 炎燃焼を開始し、その後発火する現象を低温着火という。 えた。 出火危険場所としては、次のような場所があげられている。 薩佐ら は、異臭を伴ったパッキンの燃焼事故について 26) ① 煙突等が貫通している壁体あるいは屋根 報告している。充てん済みの人工蘇生器用酸素ボンベのそ ② こんろ、レンジ類が近接している壁体、底面の台等 く止弁を救急隊員が開放し、酸素の臭気を確認したところ、 ③ 乾燥室内、スチームパイプの接触部分 通常無色無臭であるはずの酸素が強い刺激臭を有しており、 ④ サウナ室内のヒーター等の熱源周辺 さらに、パッキンが焼失していた。パッキンに用いられてい 煙突の内部には、高温の燃焼ガスが流れる。木造家屋の るフッ素系樹脂である三フッ化塩化エチレン樹脂が酸素加圧 内部に、煙突を要するような燃焼機器を設置する際に、施 下で燃焼することにより、人体に有害な塩素、塩化水素、 工に問題があると、壁体貫通部付近の木材が加熱され出火 テトラフルオロメタンが発生することを確認した。 することがある 45-48)。 走行中またはアイドリング中の内燃機関を搭載した自動車 パッキンに使用されているフッ素樹脂が加熱され熱分解す ると、有毒なガスが発生することは内藤 、武島 27) も指摘 28) している。フッ素樹脂の熱分解生成物については、森崎 29, も報告している。 には、高温の部分が各所にある 49-51)。高温の部分が可燃 物と接触すると火災となる危険性があることが指摘されてい る。 30) 2.3 高温表面 鉄板の片面で溶接をしていると、鉄板の内部を溶接の熱 工事中に、溶接器等のスパッタが火災原因となることは が伝わり、溶接している箇所の近くだけでなく、反対側の面 以前から指摘されてきた 35-39)。JIS Z 3001-2:2008 によると、 も熱くなる。溶接している箇所の近く、または、反対側の面 スパッタとは、 「アーク溶接、ガス溶接、ろう接などにおいて のすぐ近くに可燃物があると、可燃物が加熱され出火するこ 溶接中に飛散するスラグまたは金属粒」である。スラグとは、 とがある 21,52)。 「溶接部に生じる非金属物質」である。溶接中に発生する火 2.4 熱線 花もスパッタに含まれる。図 1 に工事に関連した火災におけ 十分に大きな凸レンズで太陽光を集光すれば、焦点に置 る溶接 ・ 溶断機から着火物までの飛散距離を示す。スパッ いた紙が焦げる。これは小中学校の理科の実験として行わ タは、遠くまで届き、かつ、可燃物を着火させることがある れている 58)。また、凹面鏡で光を集め、火をおこすことは ことがわかる。表 4 に関係した事例を示す。切削中に発生 古くから行われてきた 59)。同様に、凸レンズまたは凹面鏡 する切りくずも火災原因となりうることが指摘されている 。 の作用をするものがあり、それが太陽光を集光し、焦点に ワット数が大きく明るさが強い電球では、条件によっては 可燃物があり、焦点に十分なエネルギーを集めることができ 40) ると、可燃物が着火されることがある。収れん火災と呼ば れる。表 5 に収れん火災の出火箇所を月別、時刻別に示し た。1980 年から 1983 年の間に東京消防庁管内で発生した 23 件の収れん火災を分類した。天候は、2 件が曇りだが、 その他の 21 件は晴れまたは快晴であった。出火箇所の後ろ に⑵がついているのは 2 件であることを示し、出火箇所のみ で( )がついてないのは 1 件であることを示す。2006 年から 2011 年の間における東京消防庁管内における出火源別、月 別の収れん火災の件数を表 6 に示す。表 5 と表 6 から、以 図1 工事に関連した火災における溶接 ・ 溶断機か ら着火物までの飛散距離 53) 下のようなことがみてとれる。 ① 晴れの日に起きやすい。 ― 25 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 表4 高温表面が着火源となったと推定された事例 番号 年月 都道府県 概要 出典 東京 百貨店 ( 耐火造 15/4、延 137,670 m ) の 2 階階段室から出火した。出火原因は、2 階階段手すりの 補修工事で、工事作業員が手すりを電気溶接器で溶接中、スパッタが約 2 m 下の階段下スペースの ごみくず上に落下し、出火したことによる。作業員が溶接工事終了後、階段下から煙と炎が出てい るのを発見し、立会いの警備員に知らせるとともに、警備員が防災センターに報告後、2 人が協力 して粉末消火器等 8 本を使用、その後駆けつけた他の警備員も屋内消火栓を延長し初期消火にあたっ た。出火した百貨店は休業日であったため、客は無く避難誘導等は行われなかった。溶接作業にお いては、スパッタの飛散防止のため難燃性シートを使用していたが、シートには所々穴があいてい た。 53 東京 16 時 52 分ごろに、無届けの少量危険物貯蔵取扱所 ( 簡易耐火 1/0、延 330 m2) から出火した。全焼 2 棟、 363 m2 焼損、傷者 2 人となった。潤滑油製造業の作業場で経営者が、オイルパンを作るために電気 溶接器で作業をしていた際、スパッタが約 2 m 離れた所のオイルが染み込んだウエスに飛んで出火 53 した。付近には、こぼれているオイルや油の染み込んだダンボールや灯油等があり、それらに燃え 移って一気に燃え上がった。 東京 17 時 40 分頃に住宅の敷地内のごみから出火し、住宅の 1 階外壁 8 m2、軒裏 5 m2 等焼損した。出 火建物の西隣でマンションの新築工事が行われており、出火当日も 15 時ごろから 17 時ごろまで 3 階の鉄筋溶接工事が行われ、この溶接作業中にアセチレンガス溶接器のスパッタが、住宅の敷地内 のごみ屑に飛び散り、着火して出火した。出火建物の北側にすむ主婦(54 歳)が外から「パチパチ」 53 という音がしたので窓を開けると、住宅の外壁が燃えていたので大声で「火事だ」と知らせた。マ ンション工事現場で作業中の作業(男 35 歳)が、「火事だ」という声を聞き、工事現場事務所の電 話で 119 番通報をした。マンション工事現場で作業中の作業員(男 23 歳)と他 3 名が、「火事だ」 という声を聞き、工事現場設置の粉末消火器 6 本と水道水につないだゴムホースで消火した。 2 3-1 3-2 3-3 1999.8 1992.1 1995.9 3-4 1992.11 東京 11 月 19 時 37 分ごろに倉庫 ( 防火 2/0、延 80 m2) から出火し、半焼 1、ぼや 2 の計 3 棟、40 m2 焼 損となった。アセチレンガス切断器のスパッタが解体中の倉庫の木ずり部分に落下し、無炎燃焼し て出火した。タクシー会社の倉庫を解体中の社員(男 50 歳)が外壁の鉄製角パイプをアセチレン ガス切断器で切断していた際、モルタル壁が剥がされ露出していた木ずりにスパッタが落下し、約 53 3 時間後に出火した。同一敷地内にある事務所棟で休憩を終えて出庫しようとした運転手(男 35 歳) が、倉庫の 2 階部分が燃えているのを発見し、事務所にいた営業課長(男 45 歳)が 119 番通報を した。なお、発見時は 2 階全体が延焼中で、初期消火はされなかった。 3-5 2003.8 愛知 工場の従業員が、ポータブルグラインダーで鉄板を切削加工した際に発生した火花が、付近にあっ た灯油のしみ込んだ布を着火させた。さらにドラム缶から漏れだした乾燥炉の燃料(灯油)に延焼 した。 東京 共同住宅(耐火 6/0)の十畳の居室に小学生の兄弟 2 人が布団を敷いて寝ており、兄が両親の部屋 からもってきた白熱灯スタンドを布団のそばに置いて 21 時 30 分頃から弟と寝ながら本を読んでい た。本を読んでいるうちに寝てしまった。兄が息苦しくなってせきが出て目が覚めて、布団から煙 が出ていることに気がついた。これにより、21 時 45 分頃に、火災を発見した。死傷者はでなかった。 41 寝返りをした際に白熱灯スタンドが倒れ布団に接触し、布団が無炎燃焼したと考えられた。白熱電 球の表面温度を測定したところ、最高温度は、40 W の電球では 171 ℃、60 W では 190 ℃、100 W では、237 ℃、200 W では 275 ℃であった。 3-6 1983.6 54 3-7 1989.4 神奈川 鉄筋コンクリート造の共同住宅の居室において、居住者の留守中に消灯していたタッチセンサーラ イト(100 V、40 W の電球を使用)が何らかの原因により点灯した。電球を覆う球形の白色のプラ スチック製セード(直径 18 cm)がはずれていたため、電球に接触した衣類が着火した。電球の天 頂部の表面温度を測ったところ、消費電力が 39 W では点灯後 5 分後には 225 ℃に達し、その後は 定常状態になった。 3-8 2002.10 東京 共同住宅のベランダに立て掛けてあった折り畳み椅子に挟んだセンサライト(白熱球、100 W、一 灯式)が何らかの原因により、下に敷いてあったすのこの上に落下し、点灯した。付近にあった繊 維製品に接触し出火した。 東京 20 時 44 分ごろにホテル(耐火 4/0、延 415 m2)から出火した。ぼや 1 棟、布団 1 枚焼損となった。 3 階の客室の清掃をした際、従業員(女 63 歳)他 2 名が天井からの水漏れを発見し、ベッドが濡 れるのを防ぐためにベッドと布団を移動した。その際に布団が白熱灯の電球に直接触れたのに気付 かずその場を離れたために時間の経過とともに、電球の熱により布団が加熱され出火した。同従業 員が 1 階にいたところ、何かが燃える臭気を感じたので消火器を持って 3 階の窓から煙が出ていた 53 のでフロントの係員に各客室の宿泊客に内線電話をして避難を促すよう指示した後、フロントから 119 番通報した。宿泊客 20 人全員はフロントからの内線電話により火災を知り、避難した。なお、 自動火災探知機は設置されていたが、出火室では水漏れがあったために感知器を外しており、自動 火災報知設備は作動しなかった。 3-9 1994.1 ― 26 ― 55 56 57 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 東京 13 時 23 分ごろに作業所併用住宅(準耐火 3/0 、延 16,388 m2)の 3 階住宅部分の台所の内壁から 出火した。部分焼 1 棟、内壁 2 m2、天井 1 m2 の被害がでた。3 階台所のガステーブルが置かれて いる背面壁体が、ガステーブルの火炎の発する熱により長い間加熱され、壁体内部が炭化状態とな り着火し火災となった。ガステーブルを最後に使用して約 1 時間後に内壁より、火災となった。出 火したガステーブル背面の内壁はベニヤ板張りで、ガステーブル周囲はステンレス板が張られてい た。また、ガステーブルと背面の内壁との間は出火時 16 cm 離れていたが、ガステーブルが据え付 53 け型でないことから、しばしば内壁に近寄った状態で使用されることもあった。ガステーブルの使 用状況をみると、出火する 1 時間程前に、この家の主婦が 15 分程フライパン(直径 24 cm)を使用 して調理を行ったが、この時は内壁の異常に気づかず、そのまま 1 階の作業所に戻って作業をした。 近隣者は自宅にいると外で「火事だ」という声がしたので、外に出て見ると出火した建物の 3 階か ら煙が出ていたので粉末消火器をもって出火建物に行き初期消火をしたが、内壁から出火したため 消火できなかった。 3-11 1992.12 東京 13 時 35 分ごろに、飲食店(防火 2/0、延 96 m2)の 1 階調理場のガスロースターが設置されてい る側面の内壁から出火した。半焼 1 棟、50 m2 焼損となった。ガスロースターと内壁との距離が 9 cm と狭かったため、約 4 年間使用している間に、ガスロースターの熱が壁内に伝わって内部の炭化 が進み、焼き鳥を焼いているうち壁内から出火した。店員から店内が焦げ臭いと知らせを受けた料 理長が、1 階調理場のタイル壁の亀裂の隙間から炎が出ているのを発見し、消火器で初期消火をし たが消えなかった。店員から火災の知らせを受けた事務所の社員が、119 番通報した。 53 3-12 1985.1 石川 17 時 43 分頃に建築後 3 ヶ月の木造 2 階建住宅で、石油給湯器の煙突壁体貫通部のめがね石(30 cm × 4630 cm ×厚さ 10 cm)を固定してあるぬきが煙突に接触していたため、出火した。焼損程度 は部分焼(壁体等若干焼損)であった。 46 3-13 1985.1 石川 19 時 40 分頃に建築後 5 年の木造 2 階建住宅で、石油給湯器の煙突壁体貫通部のめがね石(30 cm × 30cm ×厚さ 10 cm)を固定してあるぬきが煙突に接近していた(3 ~ 7 cm)ため出火した。焼 損程度は、半焼(1 階内壁等 20 m2、2 階 26 m2 焼損)であった。 46 東京 自動車整備工場から所有者に小型自動車(平成元年式、排気量 3000 cc)を納車するために国道を 走行していた。車のボンネットの隙間から白煙が出てきた。急いで車を道路脇に停めたところ、煙 は黒い色に変化し、エンジンルーム下部からも煙が吹き出し始めた。エンジンルーム内に置き忘れ た、タオル地の繊維状のものが走行時の振動により、高温になった排気管の上に落下した結果、時 間の経過とともにタオル地が着火したと考えられた。 49 3-10 3-14 3-15 1996.5 1995.7 1988.6 神奈川 H 埠頭の岸壁に貨物船(9,431 トン)が停泊していた。9 時半頃に、2 号船倉内で 3 人の業者が荷 崩れ防止用の固定用リングを、3 号船倉との境の隔壁に、電気溶接をした。隔壁の厚さは 11 mm で あった。12 時 45 分頃に、3 号船倉の内壁に隙間無く接して積まれていた煙草草の梱包から出火した。 52 人的被害はなかったが、煙草草約 1 千トンの内、約 2 百トンが焼損した。溶接の熱が、隔壁内を熱 伝導で伝わり、隔壁の反対側の温度が上昇した。そのため、内壁に接した積まれていた梱包が着火 した。 表5 収れん火災の出火箇所 61,62) 時刻 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 時~ 10 時 10 時~ 11 時 10 11 12 居室 ベランダ(2) 居室(2) 11 時~ 12 時 居室 ベランダ ベランダ ベランダ 建物外周部 12 時~ 13 時 居室 13 時~ 14 時 居室 ベランダ ベランダ 外壁 廊下 縁側 敷地内 16 時~ 17 時 敷地内 居室(2) 居室 14 時~ 15 時 居室 15 時~ 16 時 居室 (2)は 2 件であることを示し、出火箇所のみで ( ) がついてないのは 1 件であることを示す。 1980 年から 1983 年の間に東京消防庁管内で発生した 23 件の収れん火災を分類した。 天候は、2 件が曇りだが、その他の 21 件は晴れまたは快晴であった。 ― 27 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 表6 収れん火災の件数 53) 件数 種類 年 凸 凹 2006 1 1 2007 2 3 2008 月 反射板 1 2 3 4 5 6 1 1 3 7 8 9 1 1 3 4 2 2010 3 3 2 2011 3 3 1 11 12 1 1 2009 10 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 凸 : 凸レンズまたは凸レンズと同様の作用をしたもの 凹 : 凹面鏡または凹面鏡と同様の作用をしたもの ② 季節にかかわらず、起こりうる。 ㉓ テレビに取り付けられた画面拡大鏡54) 重要なのは、太陽光を集光できる形状をしていて、焦点に ③ 昼ごろが起こりやすいが、昼の前でも、昼の後でも起こ 十分なエネルギーを集められるかどうかである。人間がどの りうる。 ④ 居室またはベランダで起こることが多いが、可燃物が置 ような用途で使用しているかではない。なお、太陽の高度と かれている場所であれば、どこでも起こりうる。 方位を知りたい場合、計算による方法 87)と、Internet 上の 凸レンズまたは凹面鏡の作用をするものとしては、以下の ソフトウェアを利用する方法 88)がある。太陽光以外にも、レー ように様々なものが報告されている。 ザーのビームが着火源になることがある。レーザーのビーム ① マスコットをガラスにつけるための透明なカーアクセサ には以下のような特徴がある 89)。 リーの吸盤 ① 単色性がよい。単色性とは、いろいろな光が混ざり合っ 60-62) ② 透明プラスチック製肩叩き棒 63) ③ 出窓に置かれたリンゴ形のガラス製置物 ておらず、どのくらい純粋な1つの光であるかをいう。 ② 指向性がよい。指向性とは、光が一定方向にどのくらい 64) ④ 筋力トレーニング用のウォーターアレイ65) ひろがらずに進むかをいう。 ⑤ 温室の透明フイルムに雨水が溜まってできた半球状の ③ 干渉性がよい。干渉とは、位相の相違によって、明暗の 水たまり66-69) 縞を発生する現象である。 ⑥ 自動車用アルミホイール ④ エネルギー集中度および輝度性がよい。太陽の光をレン 70) ⑦ 中に水の入った透明な円筒形容器71-75) ズで集めても紙や木を焼く程度だが、レーザーの場合に ⑧ 球形の金魚鉢 はエネルギーの集中度がよいため、鉄板を切ることもでき 61,62) ⑨ 水栽培びん71) る。 ⑩ 化粧鏡(片面が凹面鏡になっており顔が大きく映る両面 太陽光線では、レンズの焦点でなければ着火は難しいが、 鏡) レーザーのビームであれば、もともと指向性とエネルギー集 76-78) ⑪ 太陽熱ゆで卵作り器79) 中度がよいので、離れたところにあるものでも着火させるこ ⑫ スチール製ボール とがある。鉄板を切ることができるようなパワーのある加工 80) ⑬ ステンレス製ボール容器81) 用レーザーの普及が進んでいることもあり、レーザーによる ⑭ アクリル製ミラー電気傘 労働災害等を防止するための安全対策については、いくつ 61) ⑮ 装飾用ミラーボード61,62) かの資料がある 90-92)。表 7 に関係した事例を示す。なお、レー ⑯ 炊飯器、なべの蓋61,62) ザー加工機からでる火花が着火源になることもある。レー ⑰ よく磨かれた鍋 ザーは医療現場でも広く使われている。レーザーのビームが 61,62) ⑱ 石油ストーブ反射板71) 手術で使われるプラスチックチューブに照射されると、プラ ⑲ 鏡面仕上げの外壁板 スチックチューブを発火させる危険性があることが指摘され ⑳ 凹面状外壁の熱線反射ガラス84,85) ている 93,94)。また、手術で使用されるレーザーが、布、シー 82,83) ㉑ サンルームの屋根の内側に貼られた銀色の視線防止 フィルム83,86) ㉒ 拡大鏡付き虫かご61,62) トを着火させ、患者も火傷を負ったことが報告されている 。レーザーは、可燃性予混合気 98)、可燃性粉じん 99)を 95-97) 着火させるためにも使用されている。可燃性予混合気や可燃 ― 28 ― 消防研究所報告 第 116 号 番号 年月 4-1 表7 熱線が着火源となったと推定された事例 都道府県 n 2014 年 3 月 概要 出典 京都 炭酸ガスレーザーを利用するレーザーカットマシンで、ABS 樹脂の加工をしていた。自動運転であっ 103 たために、従業員がその場を離れていた。レーザーのビームの波長は、10.6 μ m で、レーザーの出 104 力は 500 W であった。加工材の切り屑がワークテーブル上に堆積し、レーザーのビームの照射によ 105 り着火した。レーザーカットマシンが焼損した。 4-2 1995.7 愛知 大学で学生が研究開発中の光デバイスの評価実験をしていた。YAG レーザー発振装置によりレー ザーのビームを発振し、実験試料にレーザーのビームを入射させるために反射鏡により光軸を調整 106 していた。レーザーのビームの波長は、1.06 μ m で、レーザーの出力は約 4 W であった。反射鏡 から 4.2 m 離れたところにある暗幕にレーザーのビームが照射されて燃えだした。 4-3 1990 東京 共同住宅の玄関ホールとリビングルームを仕切る木製の長尺扉の子扉を開放していた。子扉がダウ ンライト(80 W)の直下であったために、子扉の上部が円弧状に焼損した。ダウンライトと扉の上 100 部の間隔は 2 cm であった。 n: 記載無し 性粉じんのある場所の近くでの使用にも注意が必要である。 ② 放電のエネルギーの大きさが、周囲に存在する空気と可 電球のように、本来、光が散乱するようにつくられている ものでも、電球のすぐ近くに可燃物があれば、電球の表面 燃性液体の蒸気の混合ガスの着火に十分であること ③ 周囲に存在する空気と可燃性液体の蒸気の予混合気の に触れなくても、可燃物の温度が上昇し着火に至ることもあ る。例えば、ダウンライトから 2 cm 離れたところにあった板 濃度が可燃範囲内にあること ④ 可燃範囲内にある予混合気が存在するところで火花放 がダウンライトの発する熱で火災になったことが報告されて 電があること いる 100,101)。劇場用の照明装置が 5 cm 離れたところにあっ 北川 122)は、爆発火災の原因が静電気であることを証明す た舞台幕を着火させたという報告もある 102) 。 るには、 次の 3 条件すべてが必要であると述べている。さらに、 2.5 電気火花 安易に着火源を静電気にしてしまうことを戒めている。 電気回路等から電気火花が生じた場合、そのエネルギー ① 静電気が発生し、それが蓄積する条件がそろっているこ が十分に大きければ、周囲の可燃性予混合気、可燃性粉塵 などを着火しうる。どのような条件であれば、電気火花が可 と ② 静電気の荷電が放電を起こすのに適当な電極となるもの 燃性予混合気、可燃性粉じんを着火するのかについては、 多くの研究があり、本にまとめられている 107-110)。電気機器 が具体的に存在すること ③ 静電気の放電エネルギが、着火エネルギーを与えるのに ・ 電気配線が着火源にならないようにするための対策につい 十分な大きさであること ては、解説 111)、指針 112-115)にまとめられている。 炭谷と北川は、表現は異なるがほぼ同じ内容のことを述べ なお、萩本ら によると、電気配線の短絡時には、次の 116) 要素が着火に寄与する。 ている。どのような作業により静電気が蓄積され、静電気に よりどのような災害が生じるかの詳細については、文献 123 ① 溶断前の素線の赤熱 から 132 を参照されたい。工場 ・ 事業所における静電気によ ② 溶断後におけるアーク放電の周囲に生じる高温ガス る災害の防止対策については、指針 133,134)を参照されたい。 ③ 溶融飛散する火花粒子 2.7 裸火 萩本ら は、どのような条件で固体が着火されるのか 燃料の種類、火炎の形態(拡散火炎か予混 合火炎か) 、 116-118) について、実験と解析により検討している。 火炎の用途、火炎を保持するための方法により、裸火は様々 2.6 静電気火花 なものがある。最初に、ろうそくについて説明する。表 8 に 二つの物体表面の密接な接触とそれに続く分離またははく 離により、静電気が帯電する。二つの物体のうち一方または 関係した事例を示す。幅広い年齢層の人が、宗教上の行為、 礼拝等に使用するため、ローソクによる火災は比較的多く発 両方が絶縁体であるか、または大地から絶縁された状態にあ 生している。また、明かり取りの目的で使用されることもある。 ると、電荷が蓄積する。その結果、電圧が数千 V から数万 図 2 に、ろうそくの使用目的を示す。ろうそくを灯明や照明に V に達する場合がある。条件によっては、静電気火花が生じ 使用することは昔から行われてきたが、ある時期からアロマテ る。静電気火花は、可燃性予混合気を着火しうるだけのエネ ラピー用ろうそくが使われるようになってきた。アロマテラピー ルギーをもつことがある 119,120)。 が一般的になってくるにつれて、アロマテラピー用ろうそくが 炭谷 121)によると、可燃性液体の火災が静電気によりおこる 火災原因となることも一般的になった。 には以下の 4 条件すべてが必要である。 ろうそくは、以下の①から④のサイクルが維持されるときに ① 帯電し、電荷がある程度以上蓄積し、火花放電が起こる こと 燃焼を継続する 135)。 ① パラフィンやエステルからできたろうが加熱され溶けて、芯 ― 29 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 表8 裸火が着火源となったと推定された事例 番号 年月 都道府県 概要 出典 東京 耐火造共同住宅(2/0)の 2 階の居室から出火し、建物部分焼 1 棟、25 m 焼損となっ た。居住者がアロマテラピー用ロウソクをテーブル上に直接立てて使用していた状態 53 で、炎を消し忘れて就寝してしまったために炎がテーブルクロスに着火して出火した。 東京 防火造店舗併用住宅(2/0)の 2 階の居室から出火し、建物半焼 1 棟、ぼや 1 棟計 2 棟、70 m2 焼損となった。居住者がプラスチック製の衣装ケースの上にアロマテラピー 53 用ロウソクを立てて使用していたため、その場を離れているうちにロウソクが転倒し、 衣装ケースに着火した。 東京 防火造住宅(2/0)の 1 階の居室から出火し、建物全焼 1 棟、42 m2 焼損となった。居住 者がガラス製の灰皿にアロマテラピー用ロウソクを立てて使用したが、ロウソクの火を消さ 53 ずに外出したため灰皿が熱により割れ、火の着いたろうが床に飛び散ったために出火した。 東京 23 時 05 分ごろ倉庫併用住宅(耐火 3/0、延 308 m2)の 2 階居室から出火した。着衣が若 干焼損し、負傷者は 2 人であった。火元者の母親(90 歳)が、仏壇のローソクの火を消 53 そうとした時、ローソクの炎が着ていたパジャマに触れたため着衣に着火し、火災となった。 2 7-1 7-2 7-3 7-4 2006.10 2005.6 2004.12 1996.7 20 時 20 分ごろに共同住宅(耐火 2/0、 延 464 m2)の 2 階の風呂場から出火した。被害は、 ぼや 1 棟、負傷者 1 人であった。居住者の外国人(女 29 歳)が、入浴のため、浴槽に お湯を入れている最中に照明の電球がきれ、予備の電球がなかったことから、ローソク 7-5 1996.11 東京 を洗面台のプラスチック製の棚に立てて入浴し、ローソクを消し忘れたまま外出したた め、ローソクが燃え尽きプラスチック製の棚に着火して火災となった。帰宅後、室内に 濃煙が充満し、プラスチック製の棚が燃え尽きているのを発見した。通報は当初行われ 53 ず、 火元からの水漏れを知らせにきた建物の所有者(男 62 歳)が、 火災を発見し通報した。 複合用途建物(物品販売店舗 ・ 共同住宅、耐火造 2/0、延 240 m2)の 1 階物品販売店 舗から出火した。店員が、レジカウンター脇の流しで洗い物をしていると臭いがした ので商品陳列棚を見て、棚上方に煙と炎を発見し、店内の消火器を使用して消火した。 7-6 7-7 7-8 2011.10 2010.10 2003.4 東京 さらに来店した男性客 3 人がポリバケツやゴムホースで水をかけて消火した。バック 53 ヤードで休憩していた別の店員が、火災を発見した店員から火災の知らせを受け、自 分の携帯電話で 119 番通報した。店員が使用したセロハンテープ台を商品陳列棚に戻 した際、陳列棚に置いてあった電子ライターのスイッチが押されて着火したため、ラ イターの火が陳列棚に着火したことによる。 福岡 移動タンク貯蔵所(容量 :3,600 リットル)のタンク内部に付着した油分を、パーツクリー ナー ( 第 4 類第 1 石油類 ) で除去した。2 から 3 時間経過後に、タンク内部を確認するた 155 めに照明としてライターを着火したところ、タンク内に残在した可燃性蒸気と空気の可燃 性予混合気に着火し、 爆発した。火災現場にいた自動車整備工 1 名が負傷した(中等症) 。 広島 ガソリンスタンドの営業時間終了後の 21 時頃、従業員が地下貯蔵タンク(内容物 : ガ ソリン、容量 :10 キロリットル)の残量を確認するため、タンク上部のマンホール内 の液面計を覗こうとした。暗くてよく見えなかったため、明かり取りにライターを着 156 火したため、マンホール内に滞留していたガソリン蒸気と空気の可燃性予混合気に着 火した。従業員 1 名が顔面に熱傷を負った(軽傷)。 12 時 06 分ごろに、共同住宅(防火 2/0、延 146 m2)から出火し、小屋裏 15 m2、壁 7-9 1996.12 東京 体 5 m2 が焼損した。居住者の会社員(女 33 歳)が 18 時頃、布団をたたむ際にくわえ たばこをしていたが、たばこの火種が布団上に落下したのに気づかずに外出してしまっ たため、 長時間無炎燃焼を継続して翌日の 12 時 06 分ころ(約 18 時間後)に火災となっ た。同じ共同住宅 2 階居住者(男 29 歳)が、前日 22 時ころからきな臭いにおいを感 じていたが特に気にせず就寝し、翌日 12 時すぎに目を覚ますと、きな臭いにおいが激 しくなっているとともに、自室の壁付きコンセントのすき間から煙が出ていたので火 災に気付いた。初期消火は行われなかった。 ― 30 ― 53 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 ③ そうそくの炎は、燃焼とともに下に動くことから、周囲に 可燃物を置かない。 携帯用簡易ガスライター(通称、ライター)が、消火操作を したはずなのに火が完全に消えずに、着火源となったことが ライターに使用者が意図しない何らかの力が加わっ ある150-153)。 て点火し、周囲の可燃物を着火させたこともある 154)。また、 ライターは本来着火具であるが、照明装置の代用として使用 する人もいる。可燃性予混合気のある場所の近傍で、照明と して使用することにより、可燃性予混合気を着火させることも ある 128,155,156)。なぜこんなことをするのだろうかと不思議に 思うだろうが、事例 7-7 、7-8 のような火災は、昔も今も起き 図2 ろうそくによる火災における使用目的 53) ている。 たばこは慣例により裸火として扱う。消防庁の昭和 44 年 のまわりにたまる。 度の統一防火標語は、 「今捨てたタバコの温度が 700 度」で ② 芯に吸い上げられ、芯の中を移動する間に加熱され、気 化して、気相中にでる。 あった。たばこの燃焼温度は、たばこの種類(紙巻きタバコ か、パイプか) 、銘柄、たばこの向き(上向きか、水平向きか) 、 ③ 空気中の酸素との間で燃焼反応を起こし、火炎が形成さ 通気状況(口にくわえて吸引しているか、静置しているか)な を示す。 どにより異なる。表 9 にたばこの燃焼温度の測定例 157) れ、熱を発生する。 燃焼温度は、表 9 を見る限りにおいては、 700℃前後ではある。 ④ 火炎からの熱により、ろうが加熱される。 さらに、火炎、芯、溶けたろうの位置関係が変わらないと しかし、条件によりばらつくこともわかる。過去の火災実験の きに、ろうそくは安定して燃焼を継続する。芯が変形して火 結果 158-164)からみると、火のついたタバコが着火源となるかど 炎がロウに近づくなどのことにより、ろうが受けとる熱が増加 うかは、通気状態、タバコの銘柄、可燃物の種類、可燃物 すると、多量のろうが溶けて、液面燃焼になることがある。こ の湿り具合、可燃物との接触の仕方など様々な条件に依存す の場合、安定に燃焼しているときに比べ、火炎が大きくなるこ る。たばこによる火災では、図 4 に示すように、たばこが原 とがある。このことは、小学校の燃焼に関する授業の題材に 因となった火災では、出火に至るまでの時間がばらついてい もされている 136)。 アロマポットの中でろうそくを燃焼させた場合、条件によっ ては、火炎が異常に大きくなることが報告されている 137-144)。 アロマポットとは、上部が皿状になっており、その部分に芳香 材料を数滴垂らした水を入れ、下部の空洞状の部分にろうそ く等を置き燃焼させることで芳香を発散させるものである。素 焼きの容器の中でろうそくを燃焼させた場合でも、火炎が異 常に大きくなることが報告されている 145,146)。 ろうそくによる火災の経過を図 3 に示す。ろうそくの火から 火災に至るには、接炎、落下、転倒など様々な経過をたどる。 実験を行った結果 147,148)をみると、どのようなろうそくがどの 図3 ろうそくによる火災における火災の経過 53) ように落下したか、どのように転倒したかにより、燃焼が継 続するかどうかは変化した。 ロウソクを燃焼させる際には、適切なろうそく立てが必要で ある。火のついたろうそくをプラスチック上に放置すると、プラ スチックが着火されることがあるという報告がある 147-149)。 どのような目的にせよ、ろうそくに火をつける際には、以下 の基本的な事項 53)を忘れてはならない。 ① ろうそくは、不燃性のお盆や台上で使用し、使用中はその 場を離れない。 ② ろうそくは、燭台の大きさに合ったものを使用し、倒れる ことのないようにする。 図4 たばこによる火災における出火に至るまでの時間 ― 31 ― 53) 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 表9 たばこの燃焼温度 157) 自然燃焼時の内部 の最高温度 [℃] 燃焼の方向 水平に固定され て燃焼 鉛直に固定され て下から上に燃 焼 新生 (8 本) バット (13 本) 最高 平均 最低 最高 平均 最低 光 (8 本) ピース (8 本) 745 617 560 685 650 600 720 669 605 750 724 715 785 741 710 755 712 640 770 706 695 810 744 670 ( ) 内の数値は、各銘柄ごとの試料の数 る。事例 7-9 のように、18 時間要している事例もある。これ が放散しないで、さらに温度上昇を促し、十分に温度が高く らのことが示すように、たばこ火災の再現実験は、時間がか 。身の回りにあ なると燃焼を起こす現象が自然発火である 119) かるだけでなく、多くの条件に依存するので、多大な労力を る多くのものが条件がそろえば自然発火しうる。例えば、京都 伴うことが予想される。 。 市消防局では、56 品目の自然発火性を解説している 167) 2.8 自然発火 2.8.2 節では、自然発熱を発熱の速さという観点から分類 2.8.1 自然発熱と自然発火 してみる。2.8.3. 節では、自然発熱を反応の種類から分類し 自然発熱とは、他からなんら熱を与えないで、物質が常温 の空気中において自然に発熱する現象である。例えば、使い 捨てカイロは鉄粉の自然発熱を利用している 。その熱 165,166) てみる。反応の種類として、酸化反応、分解反応、発酵作用、 水との反応、混触による反応、重合反応があげられる。関係 した事例を表 10 に示す。 表 10 自然発火が着火源となったと推定された事例 番号 年月 都道府県 8-1 2000.6 大阪 昼頃、塗装用刷毛の軟化剤として使用していたボイル油を小型貨客自動車の荷台にこぼしたので、 178 これをウェスで拭き取った。ウェスをビニール製の土のう袋に入れ、車両後部の荷台に放置した。 179 翌日の夜に荷台から出火した。調査したところ、ボイル油のヨウ素価は 148 で、乾性油であった。 神奈川 午前中に中学校の工作室(鉄筋プレハブ平屋建)で、チークオイルをタオルに染みこませ木製折り 畳み椅子のつや出し作業を行った。18 時 46 分頃、無人の工作室から出火し、工作台、ウェス等を 焼損した。チークオイルを木部に塗布後、ウェスを丸めて通風の悪い条件で放置したため、ウェス 180 に染みこんだチークオイルが酸化発熱し、蓄熱が進み、約 6 時間後に出火した。 使用されたチークオイルの組成は以下の通りであった。 油性ワニス(アマニ油)60%,乾燥剤 1%,油剤(テレピン油)39% 8-2 1988.1 概要 出典 8-3 1998.4 大阪 木製品塗装工場においてウェスにチークオイルをしみ込ませて塗装の仕上げ作業を実施後、このウェス をポリ容器に入れそのままにしておいた。約 9 時間後に火災が発生し、このウェスとポリ容器、付近の 181 塗料缶、天井、側壁を焼損した。チークオイルのヨウ素価は 109 で、半乾性油であった。チークオイル の組成はアマニ油が 74.5 % を占め、他は溶剤と乾燥剤であった。 8-4 1997.7 大阪 水産物卸店で、鯨を解体する際に包丁をふいたタオル約 20 枚を発泡スチロール製の箱に入れ、そのま まにしておいた。約 10 時間後に火災が発生し、このタオル数枚と発泡スチロール製の箱が焼損した。鯨 182 油のヨウ素価は、2 回測定したところ 137、136 であり、乾性油であった。 大阪 エステティックサロンにおいて、スイートアルモシド油を痩身美容に使用した後、その油を拭き取っ たタオルを洗濯機で洗浄後、電気乾燥機に一杯に詰め込んでスイッチを入れて帰宅した。約 12 時 192 間後に電気乾燥機から出火した。調査したところ、スイートアルモシド油のヨウ素価は 102 で、半 乾性油であった。 東京 耐火造(9/1)の複合用途の建物 3 階の従業員室から出火した。床 1 m2、乾燥機 1、洗濯機 1、バス タオル等が焼損した。出火した場所は、マッサージ店従業員室の乾燥機内部からであった。出火し た日は、従業員が洗濯後のバスタオル 5 枚程度をおよそ 40 分間乾燥機で乾燥させた。その後、乾 燥機の電源を切り蓋を開けた状態で退社したが、タオルからの放熱が十分ではなく、約 2 時間後に 余熱により自然発火した。 8-5 8-6 8-7 1999.5 2005.7 2003.11 東京 53 3 時ごろに、クリーニング業者の雑品倉庫 1 階(準耐火造 3/0、延 362 m2)から出火した。建物部分 焼 2 棟 70 m2、外壁等 53 m2 が焼損した。乾燥機の担当者が休みだったので、代わりの従業員(外国人) がアーモンドオイルの染み込んだタオル 150 枚を乾燥機の中に入れて乾燥させ、高温のまま山積み状 53 態で 1 階倉庫内に置いていたため、洗濯では十分に落ちなかったアーモンドオイルがタオルの余熱に より着火した。出火建物建物 2 階に居住する従業員が就寝中、煙と匂いで目を覚まし、窓を開けてみ ― 32 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 ると 1 階から炎が上がっているのを発見した。すぐに自分の携帯電話で 119 番通報した。なお、初期 消火は行われなかった。この倉庫では、通常アーモンドオイルの染み込んだタオルは、別工程で洗濯 乾燥し、1 枚ずつ袋に入れるという作業を行うことで余熱をとり出火防止を行っていたが、 担当者が休 みで、別の従業員に行わせたため出火した。 8-8 8-9 8-10 8-11 8-12 8-13 1989.4 2003.5 1984.9 1967.4 1969.5 1988.1 8-14 1988.12 8-15 1977.10 東京 病院食堂の厨房で出火した。天井 1 m2、ラック 1 個、プラスチック容器 1 個、揚げ玉 3kg が焼損した。 原因は揚げ玉の自然発火とされた。経過は以下のようなものであった。17 時から 18 時 10 分ごろまで、 調理師がそば種に使用する揚げ玉約 3 kg をふたのないプラスチック容器(44 cm x 28.5 cm、深さ 196 28 cm)に移した。空調の風に 40 分間当てて冷ました。 19 時 15 分頃、厨房内のスチール棚の上段に揚げ玉を入れた容器を置き帰宅した。 21 時 59 分頃、自動火災報知器のベルが鳴動し、病院の警備員が火災を発見した。 神奈川 木造 2 階建ての店舗併用住宅の 1 階がお好み焼き店であった。アルバイト店員が調理場内のフライ ヤー(設定温度 180 ℃)で、出火前日の 16 時 30 分頃から 19 時 30 分頃までに、接客などの他の 業務をしながら揚げ玉を揚げた。その後、調理場内に置かれた。出火当日の 0 時頃に店を閉め、施 錠し、店内は無人となった。居住者が 2 階において、焦げた臭いを感じ、屋外に出て、1 階お好み 197 焼き店の換気口から白煙がでているのを見て、2 時 58 分頃に火災を発見した。現場に到着した消防 隊が窓ガラスを破壊し、お好み焼き店に進入したところ、調理場内の金ザルに入れられた揚げ玉が 赤熱していたため、調理場の水道ホースを使用して消火した。金ザル内に多量に作り置きされた揚 げ玉が自然発火したとされた。 東京 9 月初めに、美術館のフィルムセンターの 5 階、映画フィルム専用の保管庫から出火し、同保管庫 および廊下など 83 m2 を焼損した。庫内には外国の映画フィルムが約 3,000 巻保管されていた。保 管庫内のフィルムは、昭和 27 年以降に収集したもので、ほとんどが不燃性のものであったが一部 199 にセルロイドベースのものが混入していたと考えられた。庫内は専用の空調機により、温度は 20 200 ~ 25℃、湿度は 50 ~ 60% に保つようにし、フィルムの変質を防止することになっていたが、休館 日は常にオフにされ、出火前日から当日までも空調機はオフにされていた。同保管庫内奥の棚上に 保管されていた 16 mm セルロイド映画フィルムが悪環境下(高温)で自然発火した。 広島 卓球台脚を製造する工場(木造 2 階建、建築面積 125 m2)において、ガスボンベ置き場で発炎して いるのを、溶接作業中の作業員が発見、通報した。到着時にはボンベから猛烈に噴炎中で、延焼阻 止を行った。アセチレンボンベ 3 本を屋外に運び出し、残り 1 本を捜索中に、ボンベが爆発した。 人的被害は以下の通りであった。 死亡 消防吏員 2 名 1 名両大腿切断により死亡 1 名内臓露出断裂により即死 209 重傷 消防吏員 1 名(右大腿骨折、全身打撲) 消防団員 4 名(顔面火傷、視神経 ・ 鼓膜損傷) (顔面火傷、左下肢打撲) (顔面火傷、左手 ・ 左下肢打撲) (顔面 ・ 右肩・両手 ・ 左下肢爆創) 中傷消防吏員 3 名、消防団員 1 名、他 3 名 軽傷消防吏員 1 名、消防団員 4 名、他 6 名 兵庫 作業場(木造 2 階建)より出火した。作業場内にノコギリの目立用として置いてあったアセチレンと 酸素ボンベ各 1 本があった。火災の熱により酸素ボンベの安全弁から火を出し、それがアセチレンボ 31 ンベを加熱した。その結果、アセチレンボンベが破裂した。ボンベの破裂により飛んできた調整器が、 約 5 m 離れて消火活動をしていた消防士の保安帽につきささり死亡した。他に 1 名傷者を出した。 富山 22,000 m2 の燃料開発会社の敷地の大部分に、約 20 m の高さで、28 万トンのバークを野積みしてあっ たもので、この堆積したバークの内部から自然発火したと推定された。消火作業のためバークの山 を掘削すると表層より内部の焼き範囲が広大な状況であった。火災原因調査のため敷地内に野積み 215 されたバークの内部温度について表面から 70 cm の深さまで 7 箇所を測定すると、40 ~ 60 ℃で、 最も高いところは 74 ℃であった。 石川 バークコンポスト製造業者が、山間の落差 30 m の谷間を利用してコンポストを作る目的で約 32,000 トンのエゾマツのバークを投棄した。谷間に大量に堆積したバークの内部から自然発火した と推定された。翌年 4 月に現地調査した時点では、自然発火による燃焼箇所から離れた、新たなバー 215 ク投棄箇所から盛んに水蒸気が立ち上っており、この部分のバーク内部温度を測定すると、表面か ら 30 cm までの探さでは 40 ~ 60 ℃、70 cm では 73 ℃、1 m の探さでは 79 ℃であった。 北海道 焼損建物は牧草収納庫 * 一棟、焼損物件は、牧草のロールベーラ **608 個及び大型巻取機 *** 等であ る。牧草、しかも一個 700 kg もある機械で強く巻きあげたロールベーラは、水の浸透が悪く、表面 の燃焼を押えたかに見えても、僅かな残り火で次々と燃え出した。このロールベーラが、収納庫内に、 三段積みで、608 個収納されていた。放水しながら、柱にワイヤーをかけ、トラクターで除去した。 217 屋根、壁も除去した。放水しながら、大型湿地用ブルドトーザーでロールベーラを突き崩し、踏み 218 つぶした。さらに、大型ユンボを使い穴を掘って埋めた。 出火原因は自然発火と推定された。 ― 33 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 * 木造平屋、波トタン外壁、トタン葺、1,320 m2、約 15 m × 91 m。 ** 乾燥した牧草をロール状に巻いたもの。形状は、直径長さとも約 1.5 m で、一個 700 kg。 *** 外国製で、牧草をロールベーラにする機械。 8-16 1989.4 8-17 2005.12 8-18 1967.9 福岡 東京 サイロ内部で火災が発生した。火災が発生したのは、牧草をサイロに入れて乳酸発酵により乳牛飼育用 の飼料を作るのに使用される気密サイロで、形状は縦型円筒形タンク(鋼板、両面ガラスコーティング、 有効容積 293 m3)であった。消防ポンプ自動車 2 台、指揮車 1 台、救急車 2 台、人員 16 人、消防団、 消防ポンプ自動車 1 台、人員 20 人が出動した。消火活動中、突然轟音と共に爆発した。消防職員 3 人 (重症 1、中等症 2)が負傷した。 出火原因は自然発火と推定された。畜産用サイロ(密閉式)に、水分含有率 30 ~ 40 %と推定される へイレージ(低水分飼料)が約 100 m3 が貯蔵されていた。2 日前 19 時頃、サイロの飼料取出口の蓋を 開け開放状態で放置した。前日 12 時頃、 サイロルーフのセンターハッチ(直径 60 cm)とサブハッチ(直 径 43 cm) を開け開放状態で放置した。サイロに空気が流入しヘイレージが変敗し発熱したと推定された。 また、サイロ内のヘイレージが不完全燃焼し、それによって発生した可燃性気体がサイロ内に存在して いた。噴霧注水によりサイロ内に流入した空気と可燃性気体が混合し、可燃性混合気が形成され、爆発 したと推定された。 経過は以下のようなものであった。 所有者から「サイロの上部から煙がでているので調べにきてほしい」との通報により第 1 分隊 4 人で警 戒出動した。 13:06 現場到着後所有者から状況を聴取すると、 「煙が上がって中が燃えているようだが他の事は何も わからない、 ルーフのマンホールから確認できる。 」 との返答を得て、 分隊長がルーフに登り確認を急いだ。 ルーフには、メインとサブのハッチがあり両方とも開放状態で、内部は白煙が充満し状況は見分できな かった。 219 再度質問すると、 「飼料取出口から内部が見えるかも知れない。 」とのことで、そこから内部を覗くと中 央部付近が広範囲に燃焼していた。 13:16 飼料取出口から燃焼物を取り出しながらの消火を試みたが、周囲に可燃物が集積され、取出口 が狭く内部機器が注水を妨げ効果が期待できないため、サイロ内部での消火を実施することとした。 注水は、ルーフハッチからと決定、高所であるため無人注水を行うこととし、A 隊員がルーフに登り作 業を実施した。 13:17 隊員の増強と豊富な水量を確保のため第 2 分隊の出動を要請 13:29 第 2 分隊現場到着 13:35 第 2 分隊への中継送水を開始した。 13:36 第 2 分隊の B 及び C 隊員の 2 人がルーフ上で作業中の A 隊員と協力し新たにホースをルーフ へ延長するとともにすでに注水中の第一線ホースの結着補強を行った。 13:39 作業を完了して降下を開始した直後、飼料取出口から突然「ブォー」という低い音と共に黒煙 と灰塵が吹き出してきた。続いて「ズボー」という大きい音がしてサイロ上部が黒煙に包まれた。 13:40 サイロは、ルーフが吹き飛び胴板は、内側へ歪んでいた。サイロのステップ上部に A 隊員、そ の横の垂れ下がったサイロルーフステップに C 隊員が確保ロープに吊り下がり、B 隊員は、サイロ直下 の飼料倉庫スレート屋根を突き破り地面へ落下していた。 爆発後のサイロの消火には、被災を免れた隊員と消防団が当たり、倒壊による二次災害を防ぐため筒先 を固定して無人放水を実施した。 21:00 鎮火 作業場(耐火造 3/0、延面積 3,113 m2)で火災が発生した。産業廃棄物処理施設の 1 階作業場内で 最終処理された混合可燃ごみ(産業廃棄物)から出火した。 出火原因は、火災発生前日に施設へ持 ち込まれた生石灰 3 袋(約 1.5 トン)が破れて散乱したうえに粉塵防止装置等で散水したため、時 間の経過とともに生石灰が水分と反応し発熱して周囲の可燃物に着火して火災に至った。敷地内の 隣接する建物に宿直中の従業員が 1 階から作業場付近が明るく感じたので、窓越しに作業場内を見 ると、混合可燃ごみから炎が約 30 ㎝上がっているのを発見した。すぐに従業員は自分の携帯電話 から 119 番通報したが、初期消火は行わなかった。 53 神奈川 木材、ボンベなどとともに、塩酸(藤巻びん入り、20 ㍑)1 本、および、硝酸(かめ入り、20 ㍑)1 本を、 滋賀県から、東京都まで輸送するため、国道を走行中に、5 トン積みトラックの荷台から出火し、硝酸 約 1/8 流出し、荷台の一部を焼いた。 硝酸のかめは、肩口にひび割れを生じた程度で、内容物が、周囲の木っ端、わらなどに漏れてしみていた。 226 かめの中の残留物は、比重 1.45 以上、濃度が約 80 % 程度の発煙硝酸と認められた。容器が損壊して、 硝酸が漏れだし、周囲にある充てん物、あるいは緩衝材としての、ワラ、木毛などの、可燃性の有機物 質に浸透すると、急激な酸化作用のために、著しく発熱をする。これらの物質に保温効果が加わると、 熱の拡散が妨げられるため自身が加熱されて分解発火する。このようにして出火したと考えられた。 8-19 1954.7 神奈川 シアン化水素中間試験場のドラフト室内を工事中、同室内に置いてあったシアン化水素ボンベ(内 容積 46 ㍑)7 本のうち 1 本が突然破裂したので、工事中のもの 2 名のうち 1 名は室外に逃れたが、 262 1 名が室内に倒れ死亡した。原因は、シアン化水素の一部が重合し、この重合熱により残余のシア ン化水素が熱分解し、異常圧力を生じたものと考えられた。 8-20 1953.7 群馬 化学工場において、塩化ビニル溶液重合缶の冷却水が停電のため止まった。重合缶内で急激な圧力 上昇があり、安全弁から噴出を始めた。全員が待避した後、重合缶が破裂し、重合缶の蓋の一部(約 272 400 kg) は約 200 m 飛んだ。重合の反応熱により爆発したと考えられた。 ― 34 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 2.8.2 発熱の速さからの分類 2.8.3 反応の種類からの分類 2.8.2.1 発熱の進行が速いもの 2.8.3.1 酸化反応によるもの 急激に発熱するものが該当する。爆発を伴うこともあり、 油脂の酸化熱による自然発熱は一般的なものである。次 危険性も大きい。しかし、その危険性の発生条件が、水分 のような条件を満たすときに、油脂が自然発熱しやすい。 の接触とか他薬品の混入とかいった単一的なものであれば、 ① 油脂が酸化されやすい性質である。一般に、二重結合を 試験などの実験で確認することが比較的容易であり、また、 有するものが酸化されやすい。二重結合の多さを示す数値 法規制なども含めた予防対策も講じやすい。例えば、金属 がヨウ素価175)である。 ナトリウム、カーバイドは、水と触れると発熱し、可燃性ガ ② 空気との接触面積が大きい状態にある。 は空気中で自然 ③ 酸化反応を促進するのに必要な温度にある。温度が低 発火する。いずれも消防法などの国内法による規制を受け いと化学反応が進行しにくく、また、放熱しやすい。夏の暑 ている。ただし、国内法による試験で自然発火することが い日が続くと自然発火が起きやすいとは言われるが、ボイ 確認されなかったからといって、自然発火しないというわけ ラーの近くやエンジン部など、季節に関係なく熱源がある スを発生させる。黄リン、モノシラン 168-172) ではない。 場所も自然発火の原因となりやすい。 2.8.2.2 発熱の進行がゆるやかなもの ④ 反応熱が蓄積されやすい状態にある。 最初は緩慢な発熱反応を続けるにすぎず、数時間から数 このように、自然発火するかどうかは、油脂がどの程度酸 日、ときには数週間にわたってゆるやかな発熱が進行し、 化されやすいかと周囲の環境に依存する。人間が、どのよう 蓄熱により温度上昇して反応も加速され発火にいたるもの な用途に使用しているか、人間に対してどのような効能があ が該当する。自然発火を促進する条件としては高温、多湿、 るか、原材料は何か、ではない。常温における酸化されや 換気不良、たい積状態、異物の混入などがあるが、これら すさを示す指標の一つとして、ヨウ素価が使われている。一 の中のある一つの条件のみの作用によって発火に至るとい 方、自然発火のしやすさを知るための方法の一つとして、マッ うことは少なく、各種の条件が相乗的に長時間作用しては キー試験がある。清水 176)はヨウ素価とマッキー試験の結果 じめて発火する。以下のような特徴がある。 の比較を行っており、その結果を表 11 に示す。マッキー試 ① 発熱条件が単一でない。 験の測定を開始する前の温度は 28℃から 32℃の間であっ ② 発熱より発火に至るまで長時間かかる。 た。開始から 120 分で終了とした。実験を通して、マッキー ③ 発熱部分は見えにくい場所が多いなどのため、危険性の 試験で 150℃まで温度上昇するのに要した時間を自然発火 実態が把握しにくく、不注意に取り扱われがちである。 の目安とし、大豆油のような例外はあるが、ヨウ素価が 100 ④ 早期発見が困難であり、火災の規模を大きくしがちで を超えるものを自然発火の危険性ありとした。 油脂を含んだウェスは、上記の②と④を満たしており、自 ある。 ⑤ 少量の試料を用いた、短期間の試験では、危険性を十 然発火した事例は以前から報告されてきた 177-186)。 油脂がしみ込んだ作業着、軍手、タオルなどの洗濯物に、 分に把握できないことがある。 このようなことにより、法規制なども含めた予防対策が 洗濯後も油脂が残留することがある。衣類乾燥機で乾燥さ 困難な場合がある。しかしながら、法規制がないということ れた後にその中に放置された場合、または、衣類乾燥機か はユーザーが何をしてもよいということではない。ユーザー ら取り出した後にかごの中に収納され放置された場合、上記 が自分で考えて、調べて、気をつけて使うべきである。 の②、③、④の条件を満たし、出火することがある 187-194)。 発熱する物質が断熱された容器に入れられたとすると、 ただし、乾燥機の故障により衣類乾燥機内の洗濯物が燃え 放熱することがないために物質自体の発する微小な熱でも 表 11 ヨウ素価とマッキー試験の結果の比較 176) 温度を上昇させることになる。アレニウス式が示すように、 発熱量は温度が上昇するにつれて指数関数的に増加する。 そのため、物質の温度が上昇すると、急激に発熱量が増加 する。このようにしてわずかな発熱によって、物質を自然 発火させる。このような断熱された容器は現実には存在し ないが、もし、大量の物質が山積みされていたとすると、 山の中心部は近似的に断熱系を構成することになり、自然 発火を引き起こすことになる。典型的な例が石炭 であ 173,174) る。山積みの状態に限らず、繊維状、粉末状、または発泡 状などの保温効果を持つ状態にあっても、自然発火は起こ ヨウ素価 マッキー試験の結果 大豆油 89.6 41 分 28 秒で 150 ℃に達した アマニ油 184.8 43 分 45 秒で 150 ℃に達した イカ油(原油) 186.2 67 分 50 秒で 150 ℃に達した イカ油(精製油) 186.2 67 分 58 秒で 150 ℃に達した 3 号ワニス 108.1 87 分で 150 ℃に達した 長須鯨油 105.7 110 分 20 秒で 150 ℃に達した 抹香鯨油 75.8 120 分後に 97.2 ℃に達した ひまし油 89.0 120 分後に 95.8 ℃に達した る。 ― 35 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 裂することも考慮する必要がある。例えば、98 ~ 100% のギ 酸が貯蔵中にゆっくりと分解し、一酸化炭素が発生して、密 封ガラス容器が破裂したことがある。ガス漏れがないと、2.5 リットルのびんには 25℃、1 年間で 7bar 以上の圧力が発生 。 する 214) 2.8.3.3 発酵作用によるもの 適度な水分と通気があれば、微生物の作用する発酵により 温度が上昇する。それにより 70 ~ 80℃程度まで温度が上昇 すると言われている。温度が上昇すると水分が蒸発するので、 微生物は不活性になるか死滅する。温度が十分に高くなって いれば、空気との酸化反応が起こる。条件によっては、さら 215,216) 、牧草 216-219)は、発 に温度が上昇する。樹皮(バーク) 酵作用により自然発火したことがあると報告されている。 図5 揚げ終わってから出火までの時間 196) 牧草に関しては、予防対策として以下のことがあげられてい 。 る 218) た事例も報告されている ので、衣類乾燥機の中で衣類が 195) 出火した場合に、自然発火を原因とする際には注意を要す ① 発酵しない様に乾燥を良くして梱包する。 ② 野積みで発酵熱を放散させ、2 週間以上経過してから収 る。 納する。 高温の揚げ玉または揚げかすを山盛りにすると、上記の ②、③、④を満たす 196,197)。揚げ玉、揚げかすの自然発火 ③ 収納庫は空気の流通を良くし湿気を排除する。 ④ 高く段積みする場合、桟木等で重圧及び空気の滞溜を防 による火災について、揚げ終わってから出火するまでの時間 を図 5 に示す。長い場合で、発火まで 14 時間近く要して ぐ工夫をする。 196) ⑤ 収納後は発酵の湯気や刺激性の臭いに注意する。 いる。このことが示すように、仮にどこかの料理店で営業 ⑥ 収納庫に機械類を乾草と一緒に収納しない。 時間中に揚げ玉または揚げかすを高温のまま山盛りにしたと ⑦ 大型収納庫より分散収納庫を考える。 して、営業時間終了までに煙をあげたりしなかったとしても、 営業時間終了後に煙をあげはじめないとは限らない。 上にあげた予防対策は、バーク、堆肥等にも応用可能と思 われる。 2.8.3.2 分解反応によるもの 発酵作用による自然発火は、長期間にわたり、大量に堆積 分解熱により自然発熱するものが該当する。夏に暑い日 された場合に、まれに起こる現象である。野積みしたものの が続いたりすると、セルロイドでつくられていた古い映画フィ 火災の原因を、発酵熱による自然発火とするなら、最低でも、 ルム等が自然発火することがある 198-202)。セルロイドは、ニト 以下のことを確認する必要があると思われる。 ロセルロースに樟脳を配合し、混和、圧搾、裁断、乾燥など ① 野積みした場所の地勢 。元来は無色透明であるが、 熱、 の工程を経てつくられる 203-205) ・地形、 日照、風 光、酸素の影響で透明性を失い、黄色化し脆弱になる。き 日当たりが悪く、風がよく当たるなら、熱が逃げやすくなるの わめて燃えやすい。温度、湿度、紫外線などにより自然に分 解し、分解熱が蓄積すると自然発火することがある。セルロ で、 自然発火に不利になる。 ・水はけ、降水量 イド製のフィルムの自然発火は過去の出来事ではない。2012 水分が多すぎると、発酵は阻害される。 。圧 年 9 月に東京都内の住宅で発生したという報告がある 53) ② 野積みした場所の履歴 縮酸素とともに、溶接や切断に用いられているアセチレンは、 ・積み始めからの期間 加圧下では極めて不安定で火花、加熱、摩擦などにより自己 。火災現場で、加熱されたアセ 分解を起こしやすい 203,206-20) 発酵による自然発火には、長期間を要する。 ・これまでに積んだもの チレンボンベが爆発し、活動中の消防職員が殉職した事例も 。有機過酸化物は、産業において広く使われてい ある 31,209) るが、熱、衝撃、異物との接触などにより爆発的に分解反応 油類、 または、油分を含んだものは酸化発熱の原因となるこ とがある。 ・これまでに起きたこと を起こすことがある。福山 210)、幅 211-213)が有機過酸化物の事 発酵が起きたなら、 なにかしらの発酵臭があったはずであ 故事例をまとめ、分析をしている。分解とともに発生する化 る。発酵が起き、温度が上昇したなら、湯気が発生する。発酵 学物質の中には、毒性があるものもある。また、分解反応に 熱による温度上昇で、乾燥した後に、通常の酸化反応が開始 より気体が発生する化学物質は、内圧の上昇により容器が破 される。酸化反応が開始されたなら、 タールが生成し、焦げ臭 ― 36 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 いにおいがする。酸化反応が継続したなら、発煙する。酸化反 応がさらに継続したなら、発火する。発酵熱による自然発火な 解する。このため、酸素発生剤としても利用されている。 ④ 溶解熱あるいは希釈熱により発熱するもの らば、火が出る前に、湯気、発酵臭、焦げた臭い、煙が出てい 濃い酸やアルカリを水で希釈または溶解して試薬溶液を たはずである。 調製する際には、発熱を伴うことが多い。急激な発熱を避け ・圧密の状態 るために、ガラス棒などでかき混ぜながら試薬を少しずつ静 圧密すれば、空気が通りにくくなり、自然発火に不利 かに水に加える必要がある。例えば、硫酸の場合、強く発熱 して沸騰する場合もあるので注意する必要がある225)。 になる。 2.8.3.5 混触による反応 ③ 出火場所の状況 2 種またはそれ以上の物質が混合または接触したために、 ・発火した位置 自然発火なら、野積みの山の内部から発火したはずで 発火の危険を生じることである。以下のように分けることがで きる。 ある。 ① 化学物質との混触による発熱・発火 ・発火した位置の周囲 強酸である濃硝酸は、強力な酸化剤でもある。濃硝酸が 消火活動、火災調査の際に、以下のような発火の前の 有機物と触れると、有機物が発火することがある226)。 現象が見えたか。 野積みの山の内部に、焦げて激しく発煙する場所は ② 化学物質の混触による発火・爆発危険性混合物の生成 あったか。焦げて激しく発煙する場所を取り囲むように、 複数の化学物質を混合すると、熱、火炎、打撃、摩擦、 焦げてはいるが、発煙が弱い場所があったか。焦げては 衝撃に対して鋭敏な混合物ができることがある。典型的 いるが発煙が弱い場所を取り囲むように、乾燥し、多少 な例が花火である227-230)。学園祭の準備あるいは学園祭 焦げているような場所はあったか。 での実演などのために、花火の製作中に発火した事例が ある231,232)。 野積みの山の断面を露出させたような写真があれば、 ③ 空気との接触による発熱・発火 一目瞭然である。 常温の空気と接触した場合に、空気による酸化反応が急 ④ 発災事業者の情報 速に進行するものである。黄リン、 モノシランが該当する。一 ・火災履歴 部の金属は、ある程度以上の大きさの塊であれば、空気中 これまでに火災を起こしたことはないか。 で発火しないが、粉末の状態であれば、空気中で発火する ・業態 ことがある。 事業者はどのような業態か。廃棄物の不法投棄を、販 ④ 水との接触による発熱・発火 売用の在庫と称していたりしてないか。 2.8.3.4ですでに説明した。 なお、発酵作用による自然発火を小規模の実験で再現す 地震火災の原因の中には、化学薬品が原因となったものが るのは困難である。 2.8.3.4 水との反応によるもの ある。その多くは、化学薬品の混触による発火であると思わ 水との反応により著しい発熱反応を起こすものである。禁 。表 12 に過去の地震における化学薬品による火 れる 233-238) 水性物質にあたる。次の 4 種類に分類することができる。 災の件数を示す。ただし、大きな地震が発生した直後の火災 ① 単に発熱するもの の件数は資料により異なる。 生石灰(CaO)は、水分と反応し発熱する220)。十分な量 化学薬品が原因となった火災の多くは、化学実験室等の の生石灰が発熱し、かつ、周囲に引火しやすい可燃物があ 薬品貯蔵庫や戸棚に置かれている薬品容器が地震動により ると、火災になることがある203)。生石灰は土質安定剤とし 転倒、落下、破損、流出し、上記の①から④の他に、引火 ても使用されており、水との反応で火災の原因となること 表 12 化学薬品が原因となった火災の件数 235,236) がある221)。 化学薬品が原因と なった火災件数 全出火件数 関東大地震 (1923) 27 88 福井地震 (1948) 5 27 新潟地震 (1964) 3 12 十勝沖地震 (1968) 5 24 宮城県沖地震 (1978) 2 7 兵庫県南部地震 (1995) 2 157* ② 反応により水素などの可燃性ガスを発生するもの アルカリ金属である金属ナトリウムは水と反応し水素を発 生する222-224)。また、カルシウムカーバイド(炭化カルシウム) は以下のように水と反応しアセチレンを発生する。この反応 は発熱反応であり、反応熱は、128 kJ/mol である。 CaC2 +2H2O → CH ≡ CH + Ca(OH)2 ③ 反応により酸素などの支燃性ガス(酸化剤)を発生する もの 過酸化ナトリウムは、水により酸素を発生しながら発熱分 地震名 * 神戸市内における建物火災件数 ― 37 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 表 13 温風が着火源となったと推定された事例 番号 年月 9-1 都道府県 1985.1 9-2 1987.2 9-3 1991.6 概要 出典 東京 7 時 13 分頃に耐火造 6 階の建物の 1 階車庫で、化粧品会社社員がワゴン車のエンジン を手動チョークをひいて始動し、暖気運転を行った。ワゴン車は、ガソリンを燃料と するもので、排気量は 1800 cc であった。エンジンが暖まった後、アイドリング回転 270 にして、 その場を離れた。自動車の排気管後方約 12 cm の所に、化粧品の箱が積んであっ た。排気の熱が当たり続けたことにより、ダンボールの温度が上昇し、ついに着火した。 東京 9 時 42 分頃にマンション建築現場において、コンクリート作業車運転手は作業者を脇 の道路上に駐車させ、車載のポンプを用いて生コンクリートの輸送作業を行っていた。 エンジンは稼働しており、回転はアイドリング時より高まっていた。作業者の脇には 270 ベニヤ板が積まれており、車体横腹に出ている排気口がごく接近していた。排気の熱 が当たり続けたことにより、合板の温度が上昇し、ついに着火した。 東京 建築工事現場で乾燥トイレの排気口付近から出火する火災があった。このトイレは、移動可能なも ので、建築現場にレンタルされていた。尿を一次乾燥室で撹拌 ・ 乾燥させた後、2 次乾燥室に送り 再加熱し、粉末状の残存物として集積し、一般ゴミとして処理する。処理工程で発生するアンモニ 101 ア等のガスをヒーターで加熱し、触媒を通して無臭のガスとして大気に放出する。排気温度は、最 271 高で 375 ℃に達した。乾燥トイレの設置場所上部の内壁に貼られていたダンボール紙が落下し、ト イレの排気口をふさいだため、排気の温風によりダンボール紙が着火した。 性のある化学薬品の蒸気が、ガスバーナー、ガスストーブなど よりも大きいと、可燃物の温度が上昇し、発火することがあ の裸火により着火されたことによると考えられる る 270,271)。関係した事例を表 13 に示す。 。 233) 大学の化学系の学部の研究室では、化学薬品以外に、装 置類、ボンベ類、ガラス器具、書棚、OA 機器、実験動物な 3.おわりに 火災の着火源として、以下の 9 種、すなわち、1 衝撃 ・ 摩 どが置かれている。大きな地震が起こると、 様々な被害が出る。 被害に関する報告には、体験者にしか書けないことが掲載さ 。 れており、参考になる 239-256) 擦、2 断熱圧縮、3 高温表面、4 熱線、5 電気火花、6 静電 気火花、7 裸火、8 自然発火、9 温風をあげ、事例を使って 農薬の混 合による発火危険性を指摘した報告もある 257- 説明した。また、参考になりそうな資料もできるだけ引用した。 。農薬を安易に混合せずに、取扱説明書をよく読むことが 火災原因調査の役に立てば幸いである。 259) 期待される。 火災原因調査の参考とするために、多くの文献を引用した 混触による発火が予測される化学物質の組み合わせにつ が、一般の消防職員が、引用された文献に興味を持ったとし いては、文献 260 に整理されている。ただし、全ての組み合 ても、 入手が困難かもしれない。ここでは、 日本火災学会の「火 わせが記載されているわけではないので、注意されたい。化 災」誌から多数の文献を引用した。 「火災」誌に掲載された全 学物質名で分類されているので、商品名しかわからないもの 記事は、会員になるだけで Internet 上から読むことができる についても注意が必要である。混触により、発火しなくても、 ことを付記しておく。 毒性のあるガスを発生させる組み合わせもある 。 27) 4.参考文献 2.8.3.6 重合反応 重合反応により発熱する化学物質の中には、火災 ・ 爆発 1.北川徹三 : 化学安全工学,pp. 95-129,日刊工業新聞社, の原因となったものもある。 1969 シアン化水素は保管中に、発熱を伴った重合し、爆発性 。そのため、高圧ボ の固形物質を形成することがある 261,262) 2.北川徹三 : 基本安全工学,pp. 94-106,海文堂,1982 3.駒井武,梅津実 : 摩擦火花によるガスへの着火,採鉱 ンベは長期間保存できない。塩化ビニルは発熱を伴って重合 と保安,27(12),pp, 642-657, 1981 する。容器内で重合が急激に進むと、加速的に蒸気圧が上 4.阿部与,木下重教,中島巌 : 金属と岩石の摩擦による 。ポリエステル樹脂の がり、容器が爆発する危険性がある 208) メタンガスの着火に関する研究(第 1 報),日本鉱業会 重合熱による火災 、エポキシ樹脂の重合熱による火災 誌,835(9),No. 953, pp. 1077-1082, 1967 263-266) も報告されている。 5.木下重教,中島巌,岡本博之 : 金属と岩石の摩擦によ 267-269) 2.9 温風 るメタンガスの着火に関する研究(第 2 報),日本鉱業 可燃物が温風(高温の気体の流れ)に曝され続けた場合、 可燃物が温風から受ける熱が、可燃物が周囲へ放出する熱 会誌,85(5),No. 973, pp. 325-332, 1969 6.高岡三郎 : 衝撃火花の着火危険性,安全工学,4(4), ― 38 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 pp.10 255-261, 1965 資機材の安全使用(酸素を知る),月刊消防,31(10), 7.東京消防庁渋谷署調査課 : 主任調査員からの報告 No. 201 タンクローリーの横転により出火した火災,東京 pp. 40-43, 2009 26.薩佐之久,鈴木豊 : 酸素に起因する事故事例 2 件の 消防,76(10),pp. 109-111, 1997 紹介,平成 3 年度日本火災学会研究発表会概要集,pp. 8.東京消防庁予防部調査課 : 金属の火花等によるガソリ ンへの着火実験について,火災,47(3),pp. 31-35 , 191-194, 1991 27.内藤裕史 : 中毒百科 - 事例 ・ 病態 ・ 治療 -,改訂第 2 版, 1997 南江堂,2001 9.鈴木仁治 : 擦過火花によるガソリンの発火,平成元年 28.武島玲子 : 病院内の医療ガス事故,茨城県立医療大 度日本火災学会研究発表会概要集,pp. 21-24, 1989 学紀要,5, pp. 13-19, 2000 10.鈴木仁治,田村陽介 : 車両火災の摩擦による発火に 関する一考察,平成 9 年度日本火災学会研究発表会概 要集,pp. 200-203, 1997 29.森崎繁 : フッ素樹脂の酸化および燃焼,安全工学,18 (4),pp. 199-204, 1979 30.森崎繁 : エチレン - およびプロピレン - テトラフル 11.名古屋市消防局(東消防署): 木工丸鋸に起因する出 オロエチレン共重合物の熱分解,日本化学会誌,No. 3, 火事例摩擦熱による出火機構の考察,月刊消防,3 月号, pp.6-21, 1990 pp. 364-369, 1979 31.高圧ガス保安協会 : 事故事例データベース(http:// 12.名古屋市消防局(東消防署): 木工丸鋸に起因する出 火事例 - 摩擦熱による出火機構の考察 -,東海望楼,2 www.khk.or.jp)(Accessed on 25 June 2013) 32.東京消防庁予防部調査課 : 酸素を使う器具からの出 月号,pp.61-64, 1990 火 - 酸素吸入装置ボンベのバルブ焼損 -,近代消防,8 13.東京消防庁予防部調査課 : NC 旋盤からの火災 2 例, 火災,45(2),pp. 58-60, 1995 月号,pp.146-149, 1979 33.赤塚広隆 : 事故に学ぶ酸素の容器弁 ・ 調整器の発火 14.東京消防庁麻布署調査課 : 主任調査員からの報告 No. 319 エレベータワイヤーロープが一部破断して出火し 事故,高圧ガス,44(3),24-29, 2007 34.赤塚広隆 : 高圧ガスの事故に学ぶ,p.118,高圧ガス た火災,東京消防,86(8),pp. 92-95, 2007 保安協会,2012 15.柴田功一(東京消防庁麻布消防署): エレベータのワ 35.樋川貞夫,渡辺弘吉,池田恒彦,星野藤六 : 溶接火 イヤーが一部破断して出火した火災,第 55 回全国消防 花の飛散範囲とガス着火,安全工学,5(2),pp.112- 技術者会議資料,pp. 21-26, 2007 119, 1966 16.成田善雄,伊藤博 : 断熱圧縮による高圧酸素ガスの 36.東京消防庁調査課 : 溶接器等の火花による出火の危 災害と防止対策,安全工学,6(4),pp. 278-283, 1967 険性,近代消防,3 月号,No. 144, pp. 123-127, 1975 17.中村宏行,長坂徹,土屋茂 : 断熱圧縮現象によるガス 37. 石井勇五郎,加藤昇 : アーク溶接による火災について, 火災,32(5),pp. 1-7, 1982 温度上昇に関する数値解析とその検証 , 大陽日酸技報, 38.萩原隆一,山野寛治,西田佳嗣 : 溶接火花による可 No. 24, pp. 28-33, 2005 燃物の着火危険,火災,32(5),pp. 8-12, 1982 18.駒宮功額 : 過剰酸素中の燃焼危険性と安全対策,産 39.木下勝博,渡辺憲道,萩原安昭 : アーク溶接の際の 業安全研究所安全資料,RIIS-SD-72-1, 1973 可燃物への着火原因粒子の特定と着火特性,平成 7 年 19.高圧ガス保安協会 : 高圧ガス事故に係る注意喚起 - 酸 度日本火災学会研究発表会概要集,pp. 232-235, 1995 素の取り扱いについて(http://www.khk.or.jp) (Accessed 40.切削工の使用上の注意事項,三菱マテリアル安全 on 25 June 2013) パ ン フ レ ッ ト(http://www.mitsubishicarbide.com) 20.橋井一雄 : 酸素の基本的な性質と安全性,紙パ技協誌, (Accessed on 19 June 2013) 39(6 ), pp. 538-550, 1985 21.ガス熔接 ・ 溶断作業の安全,第 4 版,中央労働災害 41.東京消防庁予防部調査課 : 特異火災事例,防災,No. 227, pp. 24-30, 1985 防止協会,2006 22.土屋茂 : 高圧酸素ガスの発火特性について - 試験及 42.神戸市消防科学研究所 : 電熱器具等による出火危険 び解析の報告 -,高圧ガス,43(8),pp. 646-651, 2006 性について,消防科学と情報,No. 43, pp. 52-56, 1995 23.土屋茂 : 高圧酸素中のバルブ開時の有機材料の発火, 43.柘植佑好他 : ミニクリプトン電球のガラス表面温度 および着火危険性について,平成 8 年度日本火災学会 安全工学,46(3),pp. 144-149, 2007 研究発表会概要集,pp. 276-279, 1996 24.駒宮後額 : 酸素調整器の発火事故とその原因,火災, 44.柘植佑好,高尾基晴 : 大型照明電球のガラス表面温 39(3),pp. 3-8, 1989 25.徳永和彦 : 初心者でもわかる救急のポイント第 7 回 ― 39 ― 度および着火危険性について,平成 9 年度日本火災学 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 会研究発表会概要集,pp. 394-397, 1997 月号,pp. 170-173, 1968 45.東京消防庁予防部調査課 : 暮らしに生かした火災の 67.福島市消防本部福島消防署 : ビニールハウス屋根の 原因 - ケーススタディー 119-,東京法令出版,1985 雨水〈凸レンズ作用〉による出火危険,近代消防,5 46.金沢市消防本部予防課 : 煙突火災の実態と対策,月 刊消防,9 月号,pp. 69-79, 1986 月号,pp. 95-104, 1987 68.福﨑悟 : 収れん火災の調査について,第 58 回全国消 47.東京消防庁予防部予防課 : 特異火災事例,防災,No. 233, pp. 26-30, 1986 防技術者会議資料,pp. 116-122, 2010 69.相馬地方広域消防本部 : 無人のビニールハウス内で 48.東京消防庁予防部予防課 : 低温着火による火災,防災, 発生した「収れん」による火災事例,近代消防,4 月号, No. 224, pp. 13-17, 1985 pp. 72-75, 2013 49.火災調査研究会 : 火災から学ぶ - 安全へのアプロー 70.国民生活センター : アルミホイールによる収れん火 チ -(車両火災事例集),東京法令出版,1996 災に注意! - メッキ処理された凹面鏡のようなホイー 50.相川潔 : 消防職員のための車両の構造と車両火災調 ルについて -(http://www.kokusen.go.jp) (Accessed on 査のポイント第 2 回「高温の排気系統」,月刊消防, 32 (2), pp. 49-52, 2010 1 Aug 2013) 71.東京消防庁調査課 : 太陽熱による火災,近代消防,5 51.東京消防庁予防部調査課 : 車両の燃料漏れによる発 火機構,東京消防,74(11),pp. 20-24, 1995 月号,pp.124-131, 1972 72.東京消防庁予防部調査課 : ペットボトルが太陽光を 52.荒井康彰 : 電気溶接の伝導熱による船舶火災,横浜 収束し発生した収れん火災,火災,60(6),pp. 58-61, 消防,12 月号,pp. 28-30, 1988 2010 53.東京消防庁予防部調査課 : 火災の実態 73.廣田勲 : ペットボトルが太陽光を収束し発生した 54.名古屋市消防局 :2003 名古屋の火災,2004 収 れ ん 火 災, 第 59 回 全 国 消 防 技 術 者 会 議 資 料,pp. 55.横浜市消防訓練センター研究開発課 : タッチセンサー 86-90, 2011 ライトによる火災,月刊消防,7 月号,pp. 56-64, 1992 74.東京消防庁調査課 : 主任調査員からの報告 No. 171 反 56.東京消防庁予防部調査課 : センサライトに起因した 響を呼んだペットボトルの火災ほか 1 件,東京消防,74 火災,火災,53(3),pp. 66-69, 2003 (5),pp. 183-185, 1995 57.上田和功 : センサライトに起因する火災について,第 75.福岡市消防局南消防署 : ペットボトルの「収れん」 51 回全国消防技術者会議資料,pp. 27-31, 2003 による火災事例について,消防科学と情報,No. 94, 58.福地孝宏 : 中学理科の物理学,pp. 96-97,誠文堂新 光社,2011 pp. 56-64, 2008 76.福岡県瀬高町外二町消防組合 : 化粧用凹面鏡が発火源, 近代消防,5 月号,pp. 145-147, 1976 59.小口正七 : 火をつくる - 発火具の変遷 -, p. 23, 裳華房, 77.豊中市消防本部北消防署 : 冬至特有の火災について, 1991 ほのお,12 号,pp. 16-17, 1985 60.東京消防庁東村山署 : マスコット用吸盤による出火 78.鈴木直美 : 凹面鏡の収れん作用による出火事例につ 危険,東京消防,57(7),pp. 50-51, 1978 いて,横浜消防,3 月号,pp. 19-24, 1987 61.東京消防庁予防部調査課 : 特異な火災事例 3 題,建 79.千葉市消防局警防部予防課 : 留守中に太陽熱ゆで卵 築防災,3 月号,pp. 13-24, 1984 作り器から出火,近代消防,3 月号,pp. 68-70, 1995 62,東京消防庁予防部調査課 : 特異な火災事例,防災,4 80.東京消防庁池袋署調査課 : 主任調査員からの報告 No. 月号,pp. 26-30, 1984 302 スチール製ボールによる収れん火災,東京消防,3 63.大槻忠義(神戸市消防局): 火災事例透明プラスチッ 月号,pp. 93-97, 2006 ク製肩叩き棒による収れん火災,月刊消防,23(6), 81.川崎市消防局 : ステンレス製のボール容器の収れん pp. 35-40, 2001 による火災事例について,消防科学と情報,No, 77, pp. 64.東京消防庁目黒署調査課 : 主任調査員からの報告 No. 70-74, 2004 241 出窓に置いたガラス製置物による収れん火災,東京 82.東京消防庁調査課 : 主任調査員からの報告 No. 96 鏡 消防,80(2),pp. 111-113, 2001 面仕上げの外壁板に起因する収れん火災,東京消防,68 65.東京消防庁世田谷署調査課 : 主任調査員からの報告 No. 123 ウォーターアレイ(筋力トレーニング用)によ (2),pp. 137-138, 1989 83.東京消防庁予防部調査課 : 収れん火災,消防科学と る収れん火災,東京消防,70(4),pp. 173-174, 1991 情報,No. 21, pp. 36-40, 1990 66.福島県警察本部鑑識課 : 雨水が放火の犯人であった とはビニール ・ ハウスの特異火災事例,近代消防,10 84.東京消防庁予防部調査課 : 主任調査員からの報告 No. ― 40 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 161 凹面状外壁の熱線反射ガラスによる収れん火災 , 東 京消防,73(6),pp. 157-159, 1994 年報,No. 23, pp. 19-28, 1994 103.京都市消防局警防部消防防災課 : 最近の特異火災 85.東京消防庁予防部調査課 : 太陽光線の収れんによる から(その 2)(レーザービームによる火災について), 火災,火災,44(4),pp. 57-60, 1994 消防科学と情報,No. 10, pp. 26-27, 1987 86.東京消防庁予防部調査課 : 主任調査員からの報告 No. 104.京都市消防局警防部消防防災課 : レーザービームに 84 サンルームの屋根内面に貼られたフィルムによる収 れん火災,東京消防,67(2),pp. 141-142, 1988 よる火災(上),近代消防,11 月号,pp. 141-146, 1987 105.京都市消防局警防部消防防災課 : レーザービームに 87.東京消防庁(監修): 新火災調査教本,第 6 巻,p. 135,東京防災指導協会,2003 よる火災(下),近代消防,12 月号,pp. 146-151, 1987 106.名古屋市消防局消防部 : レーザーによる長距離照 88. 国 立 天 文 台(http://www.nao.ac.jp)(Accessed 3 射火災事例について,近代消防,11 月号,pp. 50-53, August 2013) 1995 89.大竹祐吉 : 増補改訂版市販レーザ装置活用のための 107.熊谷清一郎 : 火,岩波新書(黄版)92,岩波書店, レーザの使い方と留意点,オプトロニクス社,1989 1979 90.厚生労働省 : レーザー光線による障害の防止対策に 108.新岡嵩 : 燃える - ろうそくからロケットの燃焼まで -, ついて,基発第 0325002 号,平成 17 年 3 月 25 日(http:// www.mhlw.go.jp)(Accessed on 29 July 2013) オーム社,1994 109.平野敏右 : 燃焼学 - 燃焼現象とその制御 -,海文堂, 91.レーザ製品の安全基準,JIS C6802:2005 1986 92.日本鍛圧機械工業会 : レーザ加工機取扱作業者用安 110.榎本兵治他 : 粉じん爆発 - 危険性評価と防止対策 -, 全講習テキスト(http://www.j-fma.or.jp) (Accessed on 29 July 2013) オーム社,1991 111.藤田嘉美 : 可燃性ガスの対策,電設技術,11 月号, 93.大橋直樹他 : レーザーの挿管チューブに対する安全 性の検討,日気食会報,35(5),pp. 361-365, 1984 pp. 35-38, 2003 112.労働省産業安全研究所 : 工場電気設備防爆指針(ガ 94.法貴昭 : レーザー適応の問題点,日気食会報,38(2), ス蒸気防爆 1979),産業安全研究所技術指針,RIIS- pp. 140-145, 1987 TR-79-1, 1979 95.医薬品医療機器総合機構 : 平成 21 年度第 3 回医薬品 113.労働省産業安全研究所 : 新 ・ 工場電気設備防爆指 ・ 医療機器安全使用対策検討会結果報告(http://www. 針(ガス防爆 1985) ,産業安全研究所技術指針,RIIS- pmda.go.jp)(Accessed on 29 July 2013) TR-85-1, 1985 96.医薬品医療機器総合機構 : 平成 22 年度第 1 回医薬品 114.労働安全衛生総合研究所 : 工場電気設備防爆指針(国 ・ 医療機器安全使用対策検討会結果報告(http://www. 際規格に整合した技術指針 2008),労働安全衛生総合 pmda.go.jp)(Accessed on 29 July 2013) 研究所技術指針,JNIOSH-TR-No. 43, 2008 97.医薬品医療機器総合機構 : 平成 23 年度第 3 回医薬品 115. 労 働 安 全 衛 生 総 合 研 究 所 : ユ ー ザ ー の た め の 工 ・ 医療機器安全使用対策検討会結果報告(http://www. 場 防 爆 設 備 ガ イ ド, 労 働 安 全 衛 生 総 合 研 究 所 指 針, pmda.go.jp)(Accessed on 29 July 2013) JNIOSH-TR-No. 44, 2012 98.中山崇他 : 層流予混合気におけるレーザ着火過程の 116.萩本安昭,渡邉憲道,岡本勝弘,千明慎臣 : 電気配 高時間分解光学計測,日本機械学会論文集(B 編),74, 線の短絡箇所から飛散する火花粒子による可燃物の着 pp. 1633-1640, 2008 火危険,平成 19 年度日本火災学会研究発表会概要集, 99.谷口正行他 : レーザで着火した微粉炭粒子群の燃焼 特性,日本機械学会論文集(B 編),62, pp. 3481-3487, pp. 140-141, 2007 117.萩本安昭,渡邉憲道,岡本勝弘,政野亮二 : 火災原 因としての短絡火花エネルギー,平成 18 年度日本火災 1996 学会研究発表会概要集,pp. 404-407, 2006 100.東京消防庁東調布署調査課 : 主任調査員からの報 告 No. 115 ダウンライトに起因する火災,東京消防,69 118.萩本安昭,渡邉憲道,岡本勝弘,三浦仁 : 火災原因 としての電気火花と位相制御回路による再現性改善, (10),pp. 151-152, 1990 平成 17 年度日本火災学会研究発表会概要集,pp. 310- 101.東京消防庁火災調査研究会編 : 火災から学ぶ - 安 313, 2005 全へのアプローチ - 電気火災事例集,東京法令出版, 119.安全工学協会 : 改訂安全工学便覧,コロナ社,1980 1992 102.河合晴夫 : スポットライトによる舞台幕及び大道具 120.堤井信力 : 静電気の ABC,ブルーバックス B-1213, 類の燃焼性試験について,名古屋市消防局消防研究室 ― 41 ― 講談社,1998 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 121.炭谷不二男 : 可燃性液体ハンドリング工程における 141.桂敏美 : 突然燃え上がる ! 茶香炉(アロマセラピー) 静電気対策,安全工学,20(6),pp. 340-345, 1981 のナゾ解明(上),月刊消防,25(6),pp. 15-23, 2003 122.北川徹三 : 爆発火災原因としての静電気,静電気学 142.桂敏美 : 突然燃え上がる ! 茶香炉(アロマセラピー) 会誌,2, p. 1, 1978 のナゾ解明(中),月刊消防,25(7),pp. 15-21, 2003 123.松原美之 : 静電気災害 ・ 障害第 I 講災害 ・ 障害につ 143.桂敏美 : 突然燃え上がる ! 茶香炉(アロマセラピー) ながる静電気現象の基礎,静電気学会誌,12(1),pp. 61-68, 1988 のナゾ解明(下),月刊消防,25(8),pp. 55-60, 2003 144.神戸市消防局予防部予防課調査係 : 茶香炉からの火 124.松原美之 : 静電気災害 ・ 障害第 IV 講静電気放電と 着火 ・ 爆発,静電気学会誌,12(4),pp. 292-299, 1988 災事例,消防科学と情報,No. 82, pp. 62-66, 2005 145.名古屋市消防局守山消防署 : アロマセラピー関連製 125.松原美之 : 可燃性液体充填時の静電気危険と対策, 品の出火危険について,近代消防,9 月号,pp. 64-71, 静電気学会誌,15(2) ,pp. 117-124, 1991 1999 126.松原美之 : 可燃性液体ハンドリング時の静電気災害, 146.名古屋市天白消防署消防第二課 : 素焼きキャンド 静電気学会誌,18(3),pp. 254-255, 1994 ルに起因する火災事例,月刊消防,6 月号,pp. 85-88, 127.松原美之 : 危険物の取扱いと静電気災害,KHK だ より,No. 51, pp. 2-11, 1996 1997 147.東京消防庁予防部調査課 : ローソク火災の調査につ 128.相田和男 : 給油取扱所の事故事例について(その 1), KHK だより,No. 43, pp. 32-43, 1994 いて,東京消防,59(9),pp. 155-156, 1980 148.京都市消防局 : ローソクの燃焼性状等について,京 129.浅野和俊 : 静電気を原因とする火災 - セルフスタン ド事故を例として -,火災,54(1),pp. 48-55, 2004 消研究レポート集,7, pp. 51-77, 1987 149.研究課 : 実験室レポート No. 8 ろうそくの怖さ,京 130.浅野和俊 : 静電気を原因とする火災 - セルフスタン ド事故を例として -,Safety & Tomorrow, No. 99, pp. 都消防,10 月号,pp. 32-33, 1998 150.東京消防庁予防部調査課 : 大量生産 ・ 大量販売製品 7-16, 2005 の火災調査,東京消防,59(11),pp. 139-140, 1980 131.Ulrich von Pidoll(長谷川和俊訳): 自動車の静電気 151.名古屋市消防局緑消防署 : 携帯用簡易ガスライター 着火危険 - 発生,検知および回避 -(抄訳),Safety & の出火危険について,近代消防,8 月号,pp. 121-130, Tomorrow, No. 99, pp. 17-24, 2005 1993 132.山隈瑞樹 : 最近の静電気による爆発 ・ 火災事例,静 152.国民生活センター : やけど等につながる簡易ライター 電気学会誌,36(3),pp. 116-121, 2012 からの発火(http://www.kokusen.go.jp)(Accessed on 133.労働省産業安全研究所 : 静電気安全指針,産業安全 研究所技術指針,RIIS-TR-87-1, 1988 1 Aug 2013) 153.国民生活センター : 危害情報から見たライターの事 134.労働安全衛生総合研究所 : 静電気安全指針 2007, 故~突然火が出た、やけどをしたなど~(http://www. JNIOSH-TR-NO.42, 2007 kokusen.go.jp)(Accessed on 1 Aug 2013) 135. 樺 山 紘 一 他( 編 集 ): 火 の 百 科 事 典 火 ・ 熱 ・ 光 - 154.大阪市消防局 : 調査鑑識レポートライターに起因 プロメテウスからロケットまで,pp. 603-606, 丸善 , する火災事例について,大阪消防,9 月号 , pp. 14-15, 1999 4 2009 4 136.島谷晴朗 : ろうそくのろう は燃えているの? - 子ど 155.消防庁 : 危険物に係る事故事例(平成 22 年)火災編, もの発想を燃焼授業の導入に -,化学と教育,42(1), pp. 6-8, 1994 pp. 136-137 156.消防庁 : 危険物に係る事故事例(平成 15 年)第 1 分冊, 137.研究課 : 実験室レポート No.11 アロマセラピーの謎, 京都消防,4 月号,pp. 38-39, 1999 pp. 274-275 157.新居六郎 : 種々の条件におけるたばこの燃焼特性に 138.京都市消防学校研究課 : アロマセラピーの謎,月刊 消防 , 22(1),pp. 81-86, 2000 ついて,消防研究所報告,6(1),pp. 1-11, 1955 158.萩本安昭,木下勝博 : たばこ火による可燃性混合気 139.片桐勝治 : 身近な出火危険 - 天然油脂ワックスの自 然発火性及びアロマセラピーの異常燃焼メカニズム -, への着火危険性,安全工学,20(4),pp. 197-202, 1981 159. 萩 本 安 昭 : た ば こ は 発 火 源 に な る か, 予 防 時 報, 第 47 回全国消防技術者会議資料,pp. 91-96, 1999 134 号,pp. 38-43, 1983 140.奥谷博司,片桐勝治 : アロマセラピーの異常燃焼 160. 増 尾 裕 : た ば こ の 燃 焼, 予 防 時 報,91 号,pp. メカニズムについて,京消研究レポート集,17, pp. 25-30, 2000 19-25, 1972 161.名古屋市消防局 : たばこ火災の防止について,消防 ― 42 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 研究室年報,No. 11, pp. 8-20, 1980 182.消防学校防災研究係 : 鯨油のしみ込んだタオルの自 162.田中三宏 : 無風時における煙草の危険性について, 火災,9(2),pp. 92-95, 1959 然発火,大阪消防,7 月号 , p. 40, 1998 183.東京消防庁高輪消防署 : 油絵用絵の具がしみ込んだ 163.樫村利明,後藤繁,伏見英 : たばこによる着火機構 布(タオル)の自然発火はあり得るか~鑑定および実 について,東京消防庁消防科学研究所報,7, pp. 34-45, 1970 験を実施~,月刊消防,9 月号,pp. 72-77, 1996 184.勝倉忠男 : 油絵具の画溶液を拭き取った布から出火 164.奥谷博司 : たばこ火のダンボール紙への着火性 ・ 燃 した火災,第 48 回全国消防技術者会議資料,pp. 123- 焼性について(その 1),京消研究レポート,17, pp. 54-66, 2000 127, 2000 185.東京消防庁予防部調査課 : 主任調査員からの報告 165.園田悟朗 : 使い捨てカイロ,日本機械学会誌,112, No. 178 切削油として使用された醤油油の自然発火,東 pp. 474-475, 40 2009 京消防,74(12),pp. 105-106, 1995 166.吉田利三郎 : 発熱体の概要,繊維と工業,36(7), 186.山本祐子 : 廃棄した植物油が自然発火した火災,第 pp. 286-289, 1980 55 回全国消防技術者会議資料,pp. 15-20, 2007 167.京都市消防局 : 自然発火について,京消研究レポー 187.東京消防庁調査課 : 梅雨時のコインランドリー乾燥 ト集,15, pp. 27-51, 1997 にご用心コインランドリーの乾燥機が起因する出火事 168.東京消防庁予防部調査課 : 特異出火原因の事例と対 策①モノシランの火災事例,近代消防,2 月号,pp.29- 例,ほのお,6(6),No. 60, pp. 9-10, 1980 188.東京消防庁消防科学研究所第二研究室 : 加熱衣類の 34, 1995 自然発火について - コインランドリー火災からの考察 169.東京消防庁予防部調査課 : 特殊材料ガス(モノシラン) の災害事例,火災,40(6),pp. 28-33, 1990 -,火災,30(4),pp. 50-53, 1980 189.東京消防庁本田署 : 加熱乾燥衣類の自然発火実験, 170.大岩守(名古屋市南消防署): 特殊材料ガスの安全 (上),月刊消防,4 月号,pp. 140-151, 1986 東京消防,59(8),pp. 34-41, 1980 190.東京消防庁予防部調査課 : 主任調査員からの報告 171.大岩守(名古屋市南消防署): 特殊材料ガスの安全 No. 308 魚油の酸化発熱反応により出火した火災,東京 (下),月刊消防,5 月号,pp. 85-93, 1986 消防,85(9),pp. 109-112, 2006 172.高圧ガス保安協会 : 事故事例で学ぶ特殊高圧ガス(モ 191.渡辺正道 : 綿繊維の自然発火事例及び実験結果につ ノシラン等)取扱中の爆発 ・ 火災とその教訓,2000 いて,横浜消防,8 月号,pp. 20-23, 1990 173.美浦義明 : 石炭の風化および貯炭,燃料協会誌,58, 192.消防学校 : 鑑識レポートエステティックサロンの pp.112-122(1979) タオルが自然発火した火災,大阪消防,4 月号,p. 49, 174.星沢欣二,小谷田一男,小野哲夫 : 石炭貯蔵時の 炭じん飛散および自然発火,燃料協会誌,64(4),pp. 2000 193.老沼康弘 : エステサロンで使用されたタオルの火 224-239(1985) 災 に つ い て, 第 53 回 全 国 消 防 技 術 者 会 議 資 料,pp. 175.原田一郎 : 改訂増補油脂化学の知識,第 3 版,幸書房, p. 132, 1992 33-38, 2005 194.京都市消防局 : エステオイルの発熱の可能性につい 176.清水忠男 : 動植物油(亜麻仁油,いか油(原油),鯨油) の自然発火について,火災,6(1),pp. 43-44, 1956 て,京消研究レポート集,22, pp. 31-38, 2005 195.東京消防庁監修 : 火災原因調査 - 主任調査員からの 177.西岡博治 : 塗料用油の浸みた繊維類の自然発火につ いて,色材協会誌,33(4),pp. 180-182, 1960 報告 -,p. 43, 東京防災救急協会,2010 196.東京消防庁神田消防署 : 揚げ玉・揚げかすの自然発火, 178.大阪市消防学校防災研究係 : ボイル油のしみ込ん だウェスからの出火,防災研究レポート,pp. 25-26, 月刊消防,11(8),pp.72-76, 1989 197.石田純,佐藤清仁 : 揚げ玉の自然発火に関する調 2001 査研究,第 51 回全国消防技術者会議資料,pp. 51-56, 179.消防学校防災研究係 : ボイル油のしみ込んだウエス からの出火,大阪消防,7 月号,p. 71, 2001 2003 198.東京消防庁予防部調査課 : 特異火災事例,防災,12 180.横浜市消防局災害調査課 : 自然発火事例 2 題,火災, 39(1),pp. 44-45, 1989 月号,No. 221, pp. 22-27, 1984 199.東京消防庁調査課 : セルロイドの自然発火例,火災, 181.消防学校防災研究係 : チークオイルのしみ込んだ ウエスの自然発火による出火,大阪消防,8 月号,pp. 37(1),pp.36-42, 1987 200.東京消防庁京橋署 : 東京国立近代美術館フィルム 36-37, 1999 センター火災の概要,東京消防,53(11),pp. 20-27, ― 43 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 1984 JAERI6019, 1968 201.東京消防予防部調査課 : 主任調査員からの報告 No. 225.飯田他 : イラストで見る化学実験の基礎知識,丸善, 114 セルロイドの自然発火火災,東京消防,69(9),pp. 147-148, 1990 2003 226.宮下繁 : 硝酸による出火事例について,火災,18(1), 202.駒宮功額 : 技術発展と事故 -21 世紀の「安全」を探る -, p. 111,中災防新書 006, 2002 pp. 33-37, 1968 227.小勝郷右 : 花火 - 火の芸術,岩波新書(黄版)237, 203.14303 の化学商品,化学工業日報社,2003 岩波書店,1983 204.厚木勝基 : セルロイド,有機合成化学協会誌,9(8), 228.細谷政夫,細谷文雄 : 花火の科学,東海大学出版会, pp. 144-148, 1951 1999 205.岡田秀則 : ナイトレート ・ フィルムの保存,マテリ 229.吉田忠雄,丁大玉 : 花火学入門,プレアデス出版, アルライフ学会誌,16(2),pp. 41-46, 2004 2006 206.神奈川県高圧ガス協会 : 高圧ガス要覧,2004 230.吉田忠雄,丁大玉 : 花火学の科学と技術,プレアデ 207.東京都高圧ガス保安協会 : 高圧ガスの取扱いかた, 3 版,2006 ス出版,2013 231.橋本孔作(東京消防庁予防課): 化学実験室の災害, 208.日本化学会編 : 化学防災指針集成,丸善,1996 安全工学,7(4),pp. 329-334, 1968 209.広島市消防局 : 広島山上産業火災ボンベ爆発事故 232.竹林保次他 : 学校における化学実験事故とその対策, 概況死のアセチレンボンベ,近代消防,7 月号,pp. 66-70, 1967 化学教育,13(3),pp. 373-395, 1965 233.東京消防庁防災部防災課 : 化学薬品の出火危険度評 210.福山郁生 : 有機過酸化物の事故例,Explosion, 2(2), 価と地震対策 - 火災予防審議会答申の概要(その 1)-, pp. 119-127, 1999 火災,31(3),pp. 43-51, 1981 211.幅道雄 : 有機過酸化物の火災事故例の推移と分析, 234.大内博史,吉田忠雄 : 地震時における薬品等の混触 発火の危険性,予防時報,131 号,pp. 32-37, 1982 安全工学,41(3),pp. 190-198, 2002 212.幅道雄 : 有機過酸化物の火災事故の調査と対策, 235.吉田忠雄編 : 化学薬品の安全,大成出版社,1982. 236.神戸市消防局 : 神戸市における地震火災の研究,東 Safety & Tommorrow, No. 91, pp. 55-62, 2003 京法令出版,1996 213.幅道雄 : 樹脂製造工場における有機過酸化物事故事 例の調査と対応策 , 安全工学,43(2),pp. 89-95, 2004 237.樫村利明他 : 地震による危険物の混合危険等に関す る実験報告,消防科学研究所報,7, pp. 46-73, 1970 214.ブレズリック(田村昌三監訳): 危険物ハンドブック, 238.川茂隆 : 薬品の混触による発火実験,防火管理,3 第 5 版,丸善,1998 月号,pp. 43-46, 1973 215.林俊勝,張田俊宏 : 発酵熱からの出火に関する考察, 239.池上雄作 : 速報 “ 化学実験室の地震 ”- 宮城県沖地 近代消防,7 月号 , pp. 28-33, 1989 震の被害を取材して -,化学と工業,31(7),pp. 558- 216.駒宮功額 : 事例に見る意外な火災 ・ 爆発,火災, 43 (2), 560, 1978 pp. 13-19, 1993 217.南十勝消防本部 : 牧草の自然発火,ほのお,6(8), 240.池上雄作 : 化学実験室の地震対策 - 宮城県沖地震 の教訓を生かして -,化学と工業,31(12),pp. 1001- No. 62, pp. 14-16, 1980 1005, 1978 218.南十勝消防事務組合大樹消防署 : 自然出火による干 241.瀬恒潤一郎 : 激震地神戸からの報告 - 神戸大学化学 草収納庫火災,近代消防,1 月号,pp. 164-167, 1978 系教室での事例 -,化学と工業,48(6),pp. 699-700, 219.糸島郡消防厚生施設組合 : サイロ火災による爆発火 1995 30 災,ほのお,17(1),No. 187, pp. 9-11, 1991 220.青木繁樹,中原万次郎 : 生石灰の水和と自硬性,石 242.佐々木宗夫,辻治雄 : 激震に見舞われた化学教室 - 神戸市 ・ 甲南大学 -,化学と工業,48(6),pp. 704- 膏と石灰,No. 73, pp. 227-232, 1964 705, 1995 221.金坂武雄 : 土質安定剤の火災危険性,安全工学, 13 (1), 243.海崎純男 : 化学実験室における地震対策の有効性と pp. 48-56, 1974 限界 - 阪神淡路大震災から何を学べるか - 大阪大学理 222.古川和男,井口八枝 : 原子力開発のための液体ナト 学部 -,化学と工業,48(6),pp. 708-709, 1995 リウム技術と防災,安全工学,6(1),pp. 1-11, 1967 223.北川徹三,小木曾千秋 : 液体ナトリウムの発火およ 244.指方研二,尾形孝輔 : 石巻専修大学の例 - 一体何が び燃焼現象の研究,安全工学,7(1),pp. 31-36, 1968 大学を守ったのか -,化学,12 月号,pp. 12-16, 2011 224.日本原子力研究所 : 液体ナトリウム安全取扱指針, 255.現代化学編集グループ : 研究室を地震から守には - ― 44 ― 消防研究所報告 第 116 号 2014 年 3 月 東日本大震災の教訓 -,現代化学,9 月号,pp. 30-41, 2011 256.笠井憲雪他 : 体験者が伝える実験動物施設の震災対 策,アドスリー,2011 257.小木曾千秋,北川徹三,野尻忠弘,上原一雄 : 農薬 の混合による発火危険性の研究,安全工学,9(6),pp. 339-349, 1970 258.東京消防庁警防部調査課 : 農薬の火災危険について, 火災,20(4),pp. 209-222, 1970 259.横浜市消防局 : 火災現場に残存した農薬の自然発火 について,防災研究,No. 15, pp. 74-77, 1985 260.東京消防庁編,吉田忠雄,田村昌三監修 : 化学薬品 の混触危険ハンドブック,第 2 版,日刊工業新聞社, 1997 261.数森敏郎 : 新版高圧ガス工学,日刊工業新聞社, 1965 262.日本化学会 : 防災指針 No.81 シアン化水素(改訂版), 化学と工業,31(2),pp. 155-162, 1978 263.宇佐見晃 : ポリエステル樹脂塗料と硬化剤の混合発 火危険,名古屋市消防局消防研究室年報,No. 29, pp. 44-47, 2000 264.東京消防庁予防部調査課 : 防水用塗料の重合熱によ り出火した火災,火災,49(4),pp. 63-66, 1999 265.東京消防庁予防部調査課 : 防水用塗料の重合熱によ る火災,火災,53(1),pp. 61-64, 2003 266.小清水雄二 : 防水用塗料の重合熱による火災につい て,第 51 回全国消防技術者会議資料,pp. 15-20, 2003 267.横浜市消防局計画課 : 火災発生事例,火災,40(1), pp. 60-61, 1990 268.東京消防庁予防部調査課 : エポキシ樹脂の火災,火災, 46(4),pp. 58-59, 1996 269.東京消防庁青梅署調査課 : 主任調査員からの報告 No. 190 エポキシ樹脂の火災,東京消防,75(11),pp. 107-108, 1996 270.東京消防庁予防部調査課 : 危険を読む⑬自動車の排 気熱による火災,近代消防,1 月号,pp. 153-155, 1988 271.東京消防庁渋谷署調査課 : 主任調査員からの報告 No. 129 簡易式乾燥トイレの火災,東京消防,70(10), pp. 161-162, 1991 272.通商産業省立地公害局(監修),高圧ガス保安協会(編 集): 高圧ガス事故事例集,高圧ガス保安協会,1982 ― 45 ― Report of National Research Institute of Fire and Disaster No.116(2014) Ignition Sources of Fires (Abstract) Takeshi Suzuki (Accepted February 18, 2014) It is necessary to know a fire's source of ignition for fire investigation. Such knowledge also enables prevention of future fires from the same or similar causes. A list of ignition sources follows: 1. Heat from impact and friction 2. Adiabatic compression 3. Heated surface 4. Energy of light 5. Electric spark 6. Static electricity 7. Open flame 8. Spontaneous ignition 9. Hot gas flow Details of ignition sources are described. It is hoped that this report is of help for fire investigation. ― 46 ― 所外発表論文 目 次 Evaluation of Thermal Decomposition Hazards by Differential Adiabatic Calorimeter Yusaku Iwata …… 49 -おことわり- ここに掲載されている論文は、他機関の発行する雑誌等から転載されたものであるためイ ンターネット上では公開しておりません。 これらの論文の閲覧を希望される方は消防研究センターまでお問い合わせください。 ― 47 ― Articles of Staff of NRIFD Published by Outside Organizations Contents Evaluation of Thermal Decomposition Hazards by Differential Adiabatic Calorimeter Yusaku Iwata …… 49 NOTICE The papers listed here are unavailable in this cite because their copyrights belong to other organizations. Contact us if you are interested in a paper in the list. ― 48 ―

























































![消研輯報第65号[PDF 8.6MB]](http://vs1.manualzilla.com/store/data/006587069_2-710ed5d741a66438e3252984898d028d-150x150.png)

![事例№K-T1 [ 天ぷら油過熱放置 ]](http://vs1.manualzilla.com/store/data/006547464_4-92010994635e3018c53aefa4645bea0c-150x150.png)