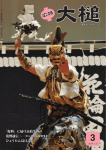Download 概要版(PDF形式:151KB)
Transcript
世界最高水準の省資源社会 の実現に向けて ∼グリーン化を基軸とする次世代ものづくりの促進∼ ー産業構造審議会 基本政策ワーキンググループ報告書の概要ー 平成20年1月 経済産業省 産業技術環境局リサイクル推進課 1.取り巻く状況の変化 ○国際的な資源制約の高まり(需要増大、価格高騰、資源ナショナリズム) ○国際的な資源制約の高まり(需要増大、価格高騰、資源ナショナリズム) 特に、自動車、電気・電子機器といった高度なものづくりに不可欠な レアメタルの供給リスクが増大 特に、自動車、電気・電子機器といった高度なものづくりに不可欠なレアメタルの供給リスクが増大 一般的な金属資源も、2050年を見通せば、資源制約が顕在化するとの学術研究も存在 一般的な金属資源も、2050年を見通せば、資源制約が顕在化するとの学術研究も存在 ○洞爺湖サミットを見据えた 3R対策と温暖化・省エネルギー対策の連携強化の要請 3R対策と温暖化・省エネルギー対策の連携強化 ○洞爺湖サミットを見据えた3R対策と温暖化・省エネルギー対策の連携強化の要請 ○経済の ○経済の 基礎力 基礎力 向上を図る方策の一つとして、投入資源の有効利用を通じた資源生産性向上への要請 向上を図る方策の一つとして、投入資源の有効利用を通じた資源生産性向上への要請 ○循環資源の国際流通の活発化(それに伴う国内での逆有償物の有償化) ○循環資源の国際流通の活発化(それに伴う国内での逆有償物の有償化) ・「21世紀環境立国戦略」(平成19年6月1日閣議決定) ・資源制約の高まりの状況 インジウム、ネオジム、ジスプロシウム等は、02年から07年比で 4∼8倍に高騰 各種資源の価格の推移 2002年3月 2007年5月 273.3 2.7 7.4 2.2 710.0 52.2 44.0 165.0 120.0 41,465.5 % 370% 196% 459% 441% 835% 798% 603% 467% 353% 251% レアアース生産国の推移 140,000 120,000 ・3R対策と、温暖化・レタメタル対策・競争力強化対策との連携 3R・省資源対策 連携 73.9 1.4 1.6 0.5 85.0 6.5 7.3 35.3 34.0 16,517.7 連携 US$/t US$/kg US$/kg US$/kg US$/kg US$/kg US$/kg US$/MTU(*) US$/kg US$/kg 連携 鉄スクラップ アルミ 銅 鉛 インジウム ニッケル レアアース(ネオジム) タングステン(鉱石) レアアース(ジスプロシウム) プラチナ 「21世紀環境立国戦略」において、例えば、3Rを通じた地 球温暖化対策への貢献など、低炭素社会、循環型社会、自 低炭素社会、循環型社会、自 然共生社会の3つの側面の相互関係を踏まえ、統合的な取 組を展開していくことが不可欠であると提言。 組を展開していくことが不可欠 レアメタルの 安定供給確保 対策 地球温暖化 対策 競争力強化 対策 ○資源外交を通 じた探鉱開発 ○代替材料開発 ○備蓄 ○革新的技術 の開発 ○省エネ対策 の強化 ○国民運動の 展開 等 ○成長力底上げ 戦略 ○サービス革新 戦略 ○成長可能性拡 大戦略 等 REO(酸化物量,t) 中国バイユンオボ鉱山;1980年代半ばから生産開始 100,000 米国マウンテンパス鉱山:1998年の生産休止 80,000 60,000 中 国 40,000 20,000 米国 中国の安値攻勢 その他 0 1979 1984 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 年 出典:Mineral Commodity Summaries 2007 1 2.目指すべき将来像と対応の方向性 生産・消費活動での資源利用に際して徹底的に 無駄を最小化 投入資源の利用効率の最大化 枯渇性資源の新規投入量を最大限抑制 「世界最高水準の省資源社会」の実現 ・資源生産性のコンセプトを国レベルから個々の資源や製品レベルに展開 ・製品ライフサイクル全体を視野に入れた産業構造全体での新たな連携強化 ・省資源の観点からグリーン化を基軸としたものづくりや社会システムへのパラダイム転換 ・レアメタル対策、地球温暖化対策及び競争力強化対策との連携強化 ライフサイクルの視点から3Rの一層の高度化を図り、世界に対するリーダーシップを発揮 ・部分最適から全体最適へ ・関係主体の拡大 【現行制度に基づく取組】 ●製造工程で生じる副産物のリデュース・ リサイクル(事業所のゼロエミッション対策) ③国際資源循環の 活発化を踏まえた 国内の取組の実 効性確保 【排出段階】 素材 ①製品ライフサイク ル全体での最適 化・効率化 【製造段階】 部品 排出 製品ライフサイクル 製品 消費 ②消費者の3R意識の向上と 事業者との連携の強化 【流通段階】 流通 【現行制度に基づく取組】 ●製品の環境配慮設計 (軽量化、再生材の回収容易化等 に配慮した設計) ●使用済製品の回収・リサイクル 等 市場原理と自主的取組を基調とする3R政策の基本的考え方を踏襲 2 3.具体的な取組方策① 製品ライフサイクル全体での最適化・効率化 【製造段階】 サプライチェーン企業間での摺合せ再強化によるものづくりの高度化 (リデュース対策) ●部品等の製造時に生じる副産物の発生抑制は、コスト削減メリットもあり国 際競争力に直結するものの、近年発生量は横ばい。 ●サプライチェーンの川上・川中企業の取組だけでは、川下企業との取引関 係上十分な効果が期待できない場合があり、全体最適化が必要。 (川下企業の設計・仕様により副産物低減の取組に制約/厳しい品質確保要求に伴う歩留まり悪化) ●投入原材料の抑制は、生産工程での省エネやレアメタル対策としても有効。 【先進的な省資源型のものづくりの例】 ・省資源化の観点から原価低減活動(VA/VE活動)を発展させ、製造・調達と一体となった設計 思想の抜本的見直し ・サプライヤーの資源投入量情報の可視化(マテリアルフローコスト会計の活用等)を通じた調達・設計 改善 1200 0.1200 1000 0.1000 800 0.0800 600 0.0600 400 0.0400 200 0.0200 0 0.0000 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 (対象範囲の例:自動車、電気・電子製品) ○国は、モデル事業等を通じた優 良事例の蓄積、情報伝達ルール の整備等を推進。 ・プラスチックくずの発生量及び発生量原単位 ・鉄加工スクラップの発生量及び発生量原単位 H10 ○川下企業において、グリーン化を 基軸に、川上・川中企業との摺 合せ再強化による省資源型の次 世代ものづくりの取組を推進。 世代ものづくりの取組を推進 ※2003年度の加工屑発生実態調査による見 直しにより、2003年度以降ではデータが不 連続となった。 ※発生量原単位=加工ロス/生産量 ※日本鉄源協会の資料をもとに作成 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 0.0640 0.0620 0.0600 0.0580 0.0560 0.0540 0.0520 ※発生量原単位=加工ロス/生産量 ※社団法人プラスチック処理促進協会の資 料をもとに作成 0.0500 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 再生資源の「高度リサイクル」の促進 (リユース・リサイクル対策) ●従来のリサイクルでは、品質グレードを下げるカスケード利用が主流。 ●二酸化炭素の低減の観点からも、再生資源を新たな製品に利用する「高度 リサイクル」が期待されるが、取組は限定的。 【先進的取組の例】 ・洗濯機でのポリプロピレンの繰返し利用、複写機での再生プラスチックのサンドイッチ利用 ○製品メーカーにおいて、製品への 再生資源の投入に配慮した設計を 促進。 促進 (対象範囲の例:自動車、電気・電子製品) ○使用済製品からレアメタルを効率 的に抽出する技術の開発も必要。 3 3.具体的な取組方策② 「製品」に着目した消費者の3R意識の向上と事業者との連携の強化 【流通段階】 製品環境性能の「可視化」による製品市場の拡大 ●製品のリデュース対策やリサイクル性向上の取組が消費 者に十分伝わっていない。 ●省エネ製品と異なり、統一的な評価指標がなく比較困難 であるなど、消費者への訴求が困難。 ・3R情報に関する消費者のニーズ等 環境情報に対する消費者のニーズは高く、93.6%が「必要」も しくは「あったほうがよい」と考えている。 しかしながら、これら環境情報は消費者にほとんど提供されて おらず、わかりやすい形で情報提供する手法が求められている。 必要 リサイクル (3R)に関 する情報 リサイクル( 3R) に関する 情報 0% あった方がよい 45.4% 20% 48.2% 40% 60% 無回答 0.8% 不要 80% 届いている 6.1% 6.4% 100% 出典:経済産業省委託調査『製品の環境配慮情報 提供の在り方に関する調査』 ○事業者が、製品に関する3Rの取組内容を、標準 的な項目に従って、消費者に情報提供することが 必要。 ○小売段階での情報提供の方策を検討すべき。 ・3Rに関して望まれる環境情報の内容 わ か らな い 環境への配慮の程度 が 1つ星 ∼ 5つ星 な ど で ランク付 さ れ た 情 報 29% 第 三 者 による評 価 結 果 11% 製品間での比較がで き る一 覧 表 18% 出典:日経BP調査 ■ 冷 蔵 庫 ○ ○ 社 製 品 A ○ 省 エ ネ ★ ★ ★ ★ ○ 3R ★ ★ ★ ○ 化 学 物 質 ★ ★ ★ ★ リサ イ クル 材 の 利 用 率 な どの 定 量 的 な 情 報 18% 環 境 情 報 の 見 方 ・読 み 方 に関 する解 説 10% 届いていない 93.1% 5% 【例】 【例】 製品 省エネ 3R 化学物質 A社製品A ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ B社製品B 判 断 基 準 や データ の 算 定 方 法 な どに関 す る詳 し い説 明 9% ・・・・・ 出典:経済産業省委託調査『製品の環境配慮情報 提供の在り方に関する調査』 自主的な回収・リサイクルの一層の促進 ●有用な金属等を含有する携帯電話、オートバイ等では、自 主的に回収・リサイクルが行われてきたが、消費者・排出 者の認知度が低水準に止まり、回収実績が低調。 ※携帯電話については、金、銀、銅のほか、パラジウムといったレアメタルが高 濃度で含有。また、国内出荷台数が約5000万台(平成18年度)である中で、 回収台数は年々減少してきており、平成18年度では、約600万台程度。 ※オートバイについては、国内出荷台数が約70万台(平成18年度)で、近年、 中古車輸出(平成18年度 49万台)を含むリユース市場への流通量が増加 する中、回収台数は、平成18年度では、4000台程度。 ○携帯電話、オートバイといった自主回収製品につい て、流通段階における消費者等への情報提供によ り、製品の引渡しを促進すべき。 【取組の例】 ・カタログ・取扱説明書、ウェブサイト等での、製品の資源性の高さ 等に関する情報提供 ・製造事業者と販売事業者が連携した効果的な情報提供 ・適切なマーク表示の在り方の検討 等 4 3.具体的な取組方策③ 国際的な循環資源の取引の活発化を踏まえた国内の取組の実効性確保 【排出段階】 リサイクル目的の輸出等への対応 ●法制度に基づき回収・リサイクルされてきた使用済 物品等が、有価で取引される状況に。この結果、排 出者が海外その他のルートに引き渡す状況が出現。 ●国内リサイクル制度の安定的実施や、海外での適 正処理・再資源化の実効性への懸念。 ○従来の製品メーカー等による回収・リサイクルでは十分な 効果が期待できない場合は、排出事業者においても、一 定水準の再資源化の取組を進めることが適当。 ○使用済物品等について、①我が国国内での再資源化、又 は②海外で処理を行う場合、国内と同等の処理が行われ ること、を排出事業者自らが確認するべき。 ・例えば、パソコンでは、取扱量の多いリース事業者において、引渡先での 処理実態を把握する等トレーサビリティを確保する取組を進めるべき。 その他の事項 素材産業等の副産物の再生利用の促進 ●素材産業等の副産物(スラグ、スラッジ、石炭灰)について、 原材料である鉱石の品位低下等により、発生抑制が困難化。 ○品質規格(JIS、団体規格等)の策定等により、製品としての利用 を一層促進すべき。 ●これら副産物の主な利用先であるセメント等の需要減少によ り、将来における有効利用の確保に懸念。 ○副産物の新規用途拡大のための技術開発やアジア諸国への輸出 円滑化等の取組(規格の普及等)を進めるべき。 地球温暖化対策等との関係 ●3Rに関し、地球温暖化や化学物質対策といった他の環境 負荷低減対策とのトレードオフが指摘される中、より一層の 一体的な取組の推進が課題。 ○ライフサイクルアセスメント等の評価手法の活用により対策間のバ ランスを勘案。 ○新たな評価手法の研究等を進めるべき。 関連制度との関係 ●廃棄物処理法等の資源循環と関連する他の制度と3Rとの 両立を図ることによって、より効果的・効率的に循環型社会 構築を進めるべき。 ○循環型社会の構築に適切な場合には、引き続き制度や運用に関 して積極的に検討。 5