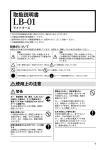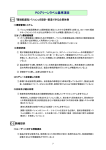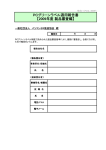Download PCグリーンラベル制度 実施要領 - 一般社団法人 パソコン3R推進協会
Transcript
PCグリーンラベル制度 実施要領 (2008 年度版) 2008 年 2 月 有限責任中間法人 パソコン3R推進センター 目 次 1.PCグリーンラベル .PCグリーンラベル制度 グリーンラベル制度の 制度の概要--------------------------------------------------------------概要 2 2.PCグリーンラベル .PCグリーンラベル制度 グリーンラベル制度の 制度の運営体制 -------------------------------------------------------- 3 3.PCグリーンラベル .PCグリーンラベル基準項目 グリーンラベル基準項目-----------------------------------------------------------------基準項目 7 4.PCグリーンラベル .PCグリーンラベル適用申請書 グリーンラベル適用申請書【 適用申請書【2007 年度 企業審査編】 企業審査編】 ---------------------- 12 チェックリスト ------------------------------------------------------------------------ 13 記入マニュアル ------------------------------------------------------------------------ 16 5.PCグリーンラベル .PCグリーンラベル適用報告書 グリーンラベル適用報告書【 適用報告書【2008 年度 製品審査編】 製品審査編】 ---------------------- 19 チェックリスト ------------------------------------------------------------------------ 20 記入マニュアル ------------------------------------------------------------------------ 25 6.PCグリーンラベル .PCグリーンラベル製品審査合否判定 グリーンラベル製品審査合否判定の 製品審査合否判定の運用報告書【 運用報告書【2008 年度】 年度】 ------------ 30 7.PCグリーンラベルロゴマーク .PCグリーンラベルロゴマークの グリーンラベルロゴマークの使用に 使用に関する規程 する規程 -------------------------------- 36 1 PCグリーンラベル PCグリーンラベル制度 グリーンラベル制度の 制度の概要 1 ラベルの ラベルのコンセプト 環境に対するパソコンの包括的取組みを表現するもので、3つのコンセプトから構成されてい る。 環 境経 営を実 践す る企業 が作 った「 環境 配慮型 パソ コン」 A B 使用済後も 使用済後も、引取り 引取り・リユース/ リユース/ リサイクル・ リサイクル・適正処理がなされて 適正処理がなされて いる 環境( )に配慮した 環境(含 3R) 配慮した設計 した設計・ 設計・ 製造がなされている 製造がなされている C 環境に 環境に関する適切 する適切な 適切な情報開示が 情報開示が なされている 環境だけでなく、3R も含めて環境に関する企業体制~製品設計/製造面に亘る広範囲 な取組み姿勢を表現 ライフが極めて短いという商品特性を踏えて、自己宣言型とする トップランナー方式ではなく、業界全体での環境への底上げを目指すというアプローチ 2 ユーザから “企業も ユーザから見 から見たラベルの ラベルの魅力: 魅力: 企業もパソコンも パソコンも共に環境面で 環境面で安心” 安心” パソコンを選択(及び使用)する上で、環境に関する情報開示が適切になされている パソコンを使用する上で、省エネルギー性、安全性など環境に十分配慮された設計・ 製造がなされている 使用済パソコンとして引取られた後も、適正処理がなされている 3 ラベルの ラベルの意味づけ 意味づけ 循環型社会の形成を促進する意志を表明すると共に、業界共通の自主的指針(目 標)を満たしたラベル 4 制度の 制度の対象製品 デスクトップ型パソコン、ノート型パソコン、ディスプレイ一体型パソコン及びデ ィスプレイを対象とし、添付品を含むものとする。(以下「パソコン」という。) パソコンベースのシンクライアント(ハードディスク装置を内蔵していなく、かつ 単体では機能しない端末)は、パソコン扱いとする。 尚、販売形態がサーバとして分類されるもの及びワークステーションは除く。 2 PC グ リ ー ン ラ ベ ル 制 度 の 運 営 体 制 1 運営体制 下記の「PCグリーンラベル運営委員会」(以下「運営委員会」という。)を中心 に運営を図る。 パソコン3R推進運営委員会 PC グリーンラベル 審査基準審議委員会 PC グリーンラベル運営委員会 ・ ・ 2 運営委員会の 運営委員会のタスク ① PCグリーンラベル制度(以下「ラベル制度」という。)の運営・普及促進を図 ることがタスクとなる。 ② 具体的推進内容は下記の4点。 (a) 「基準内容の 基準内容の最終決定」 最終決定」及び「審査」 審査」 (b) ラベル制度 ラベル制度の 制度の運営 (c) ラベル制度 ラベル制度の 制度の定期的見直し 定期的見直し (d) ラベル制度 ラベル制度の 制度の普及促進 ③ 特に、(a)(b)(c)の諸々の基準作りについては、中立性、透明性、客観性をキー プすることが重要であり、学識経験者を中心にした「PC グリーンラベル審査基 準審議委員会」 (以下「審議委員会」という。)を特別に設置して、基準案の策定 をする。 (委員長:慶應大 石谷教授、期間は、2年間を目処とする) 3 具体的な 具体的な活動内容 (1)「 (1)「基準内容 基準内容の 内容の最終決定」 最終決定」及び「審査」 審査」 ① 審査基準の策定については、「審議委員会」がチェックリストを含めて、主 体的に案をとりまとめ、その諮問案を最大限尊重して、最終的には「運営委 員会」が決定する。なお、「運営委員会」の決定には、委員の過半数の同意 を必要とする。 具体的な審査基準は、必要エビデンス資料などを明記した「チェックリ スト記入マニュアル」に記載する。 ② 審査については「企業審査」と「製品審査」があるが、前者については、① に定めた審査基準に適合しているかを客観的に判断をし、「運営委員会」に て合否の最終決定を行う。同時に、「審議委員会」へ合否の判断結果につい て報告する。また、後者については、ISO14020 シリーズのタイプⅡ環境ラ ベルの精神を尊重し、各パソコンメーカサイドで所定のチェックリストによ り、合否を決定できる形とする。 3 ③ 「企業審査」について (a)新規参画メーカは、所定のチェックリストにより、事業責任者名にて申請 をし(申請は随時受け付ける) 、「運営委員会」が審査基準との適合性から合 否を判断する。申請後、1.5ヶ月以内を目処に、合否回答書を発行する。 尚、不合格の場合は、理由も指摘する。 基本的には、チェックリストの「必須」項目が全てクリアされているこ と。但し、チェックリストの最終の補足事項で、事由が明らかに妥当 と判断される場合を除く。 左側の「選択」項目については、その関連アイテムについて、1個以 上クリアされている必要がある。 (b)既企業審査合格メーカは、1回/2年、実施要領発行後 2 ヶ月以内を目処 に、更新のための申請をし、審査を受ける。 (c)追加項目/変更項目が発生し、かつ「運営委員会」が必要と認めた場合は、 再審査を受ける。企業審査合格後、申請内容(連絡責任者も含む)に変 更が生じた場合は、速やかに「運営委員会」に届け出るものとする(様式 自由)。 (d)条件付で合格となった場合は、条件がクリアされた段階で、必要に応じ てエビデンス資料を含めて、「運営委員会」に報告をする(様式自由)。 (e)審査費用 新規に企業審査を受ける時、及び1回/2年の更新申請を受ける時、以 下の審査費用を徴収する。 パソコン3R推進センター正会員: 無料 パソコン3R推進センター準会員: 5万円/審査 パソコン3R推進センター会員以外:10万円/審査 ④ 「製品審査」について (a)上記「企業審査」で合格となった場合に、基本的には、自己宣言型ラベ ルであるので、各パソコンメーカが所定のチェックリストにより、合否 を客観的に判断して、ラベルを利用できる。ただし、出荷製品を対象と する。 (b)実際の合否判断については、必須項目では全項目満足されていることが 大前提となる。 (c)合格判定をした場合は、各パソコンメーカは速やかに下記の対応が必要 となる。 所定の審査基準をクリアした内容を「運営委員会」に報告をする。 (事務局宛、製品審査の連絡責任者から、PDF または MS-Word ファイル にて電子メールで送付する) 「製品審査」は実施要領が発行され、企業審査に合格した以降、申請 することが可能。ただし、4 項のラベル制度適用製品の出荷に定め る製品審査の条件を満足する製品が対象となる。 4 合格した機種/モデルを自社ホームページに掲載する。 但し、個々の機種/モデル毎のチェックリストのチェック結果は、サイ トには掲載しないこととする。 (基準項目/チェックリストそのものの掲載は可) 合格した機種/モデル名については、出荷開始後10年間をメドに、ユー ザからの問合せに対して確認できるように配慮をする。 合格と判断した際のエビデンス資料などについては、マネージメント を的確に実施し、ユーザなどからの諸問合せに対応できる体制を有する こと。 ⑤ 「PCグリーンラベル製品審査合否判定の運用報告書」について 各メーカは合否判定が適切に行われていることを証明するために、 「PC グリーンラベル製品審査合否判定の運用報告書」を事務局に提出し、 「運 営委員会」の審査を受けなければならない。審議の結果、改善を求めら れたメーカは修正案を再提出しなければならない。 「PCグリーンラベル製品審査合否判定の運用報告書」の提出時期は以 下の通り。 新規参画し、「企業審査」に合格したメーカは、「製品審査」を提 出後、2ヶ月以内を目処に提出する。 その後、下記改訂・変更があった場合は、当該改訂・変更項目について 製品審査基準が改訂された時、 「製品審査」提出後2ヶ月以内を 目処に提出する 製品審査方法に変更があった時、 「製品審査」提出後2ヶ月以内 を目処に提出する 審議結果は、資料提出後1.5ヶ月以内を目処に事務局より通知される。 ⑥委員会事務局としての役割 (a)有限責任中間法人 パソコン3R推進センター(以下、「PC3R」という。 ) のホームページ内に、ラベル制度及び運営などに関するサイトを作り、ラベ ル制度の「チェックリスト」及び「記入マニュアル」の公開とともに、各 社の合格した機種/モデルがわかるようにポータル機能も持たせる。 (b)同時に、ユーザからメールなどにて、種々の問合せも受け付けられるよ うな配慮をする。 (c)また、各メーカからの申請の仕方などに関する問い合わせ内容を FAQ 化し て、便宜を図る。 (d)「企業審査」と「製品審査」の申請または報告をする時に使用する「チ ェックリスト」を電子データで参加メーカに提供する。 (2)ラベル ラベル制度 ラベル制度の 制度の運営 ①ラベルに関する問合せなどへの対応は、下記を基本スタンスとする。 ラベル基準内容との相違について、問合せなどがあった場合には、そのメー カは自社の責任により、対応を図る。特にクレームについては、速やかに 5 是正のための処置を図り、その内容・経過・対策・結果などについて、 「運 営委員会」に報告をするものとする(様式自由)。 その際、著しくラベルの認定基準に満たないと認められた場合は、注意勧 告をし、それに従わない場合は、ラベルの使用を取消すなどの措置をする と共に、その内容をマスコミにも開示する。 ラベル制度そのものについての問合せなどがあった場合には、PC3R の関 連事務局が対応するが、必要に応じて「運営委員会」内のテーマとして審 議し、速やかな対応を図る。 ②本資料末尾の「ロゴマークの使用に関する規程」により遵守を義務づける。 (3)ラベル (3)ラベル制度 ラベル制度の 制度の定期的見直し 定期的見直し 「企業審査基準」は1回/2年、 「製品審査基準」は1回/年をメドに項目・内容の 見直しを図る。基準の見直し案は、「審議委員会」が策定する。 (4)ラベル (4)ラベル制度 ラベル制度の 制度の普及促進 効果的なラベル制度の普及促進策を継続的に検討・推進してゆく。 4 ラベル制度適用製品 ラベル制度適用製品の 制度適用製品の出荷 ① ラベル制度は、2001年10月1日出荷製品(新製品とは限らない)から適用 ② 2008年度版の基準については、次のように適用する。 企業審査:2007年1月1日以降 製品審査:2008年4月1日以降 ただし、2008年5月末までは2007年度の基準による「製品審 査」を提出できる。 5 ラベル制度 ラベル制度に 制度に関する PC3R 窓口 有限責任中間法人 パソコン 3R 推進センター 推進センター P C グ リ ー ン ラ ベ ル 担 当 〔電話〕 - 5282 - 7820 〔FAX〕 〕03 - 3233 - 6091 電話〕03〔電子メール 電子メール〕 メール〕[email protected] 〔住所〕〒 東京都千代田区神田小川町3 住所〕〒101-0052 〕〒 東京都千代田区神田小川町3丁目8 丁目8番地 中北ビル 中北ビル7 ビル7階 以上 6 PCグリーンラベル PCグリーンラベル基準項目 グリーンラベル基準項目 C-1 「環境配慮型パソコン 環境配慮型パソコン」 パソコン」を設計・ 設計・製造できる 製造できる企業体制 できる企業体制 (1)環境管理 (1)環境管理システム 環境管理システム ① パソコンの製品開発または最終製造(組立)にかかわる事業所(企業)は、ISO 14001(環 境マネージメントシステム)または同等のシステムが構築・運用されていること (2)オゾン (2)オゾン層破壊物質 オゾン層破壊物質 ①オゾン層保護法に規制される化学物質が、パソコンの直接製品納入業者及び最終製造 (組立)工程でも洗浄剤として利用されていないこと ②使用済パソコンのリユースやリサイクル工程でも使用されていないこと (3)事前評価 事前評価 ①電子情報技術産業協会(以下、 「JEITA」という。 )の「情報処理機器の環境設計アセ スメントガイドライン(JEIDA-G-19-2000)」 (以下、 「環境設計ガイドライン」という) に準拠して、あらかじめ、パソコンの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を 定めていること ② 製品を設計する際、使用済パソコンの発生量の抑制を図ると共に、再生資源または再 生部品の利用の促進を図るなど、製品の事前評価を行うシステムが構築されているこ と ③ 評価を行うに際し、必要な記録をすること (4)リデュースを リデュースを配慮した 配慮した体制 した体制 ① 修理に係る技術者を確保し、自社製品の修理を行う体制が整っていると共に、製品を 出荷後、当該製品について、少なくとも5年間、修理が受けられるよう体制が整備さ れていること (5)回収及び 回収及び適正処理 ① 資源有効利用促進法及び廃棄物処理法に合致したリサイクルシステムを有すること 事業者もしくは家庭から排出されるパソコンに関して、排出者から回収拠点まで、回収 拠点から中間処理施設(再生処理施設を含む)や最終処分場までの円滑な収集・運搬シス テムが構築されていること 適切な再資源化処理ができるような施設・システムを有すること 実際に使用済パソコンのリユース・リサイクルを担当する企業が、適切な環境管理シス テムを構築していると共に、その企業に対して定期的に委託内容に関する実態把握をし ていること 7 C-2 情報提供 (1)ユーザ (1)ユーザに ユーザに対する情報提供 する情報提供 ① 環境配慮製品としての基準がクリアされていることについて、ホームページなどを 活用して、ユーザが理解できるように情報開示がなされていること ② 製品の安全な使用方法、使用済となった時の問合せ窓口・処理方法などを、取扱説明 書に記載するなどの情報提供ができていること ③ 修理及びアップグレード性の条件に関する情報提供が適切にできており、問い合わせ窓 口が容易に分かるようにしていること ④ 使用済パソコンの回収及び処理・再資源化の状況について、毎年度、公表すること ⑤ 製品審査に合格したものは「PCグリーンラベルロゴマークの使用に関する規程」に 従い、ロゴマークを表示すること (2)自治体 (2)自治体に 自治体に対する情報提供 する情報提供 ① 使用済パソコンの引き取りに関する情報を公表すること (3)保守関連企業 (3)保守関連企業( 保守関連企業(部門) 部門) に対する情報提供 する情報提供 ① リデュースを促進する観点から、修理・保守を容易にするためのマニュアルを提供す るなどの情報提供が出来ていること (4)リサイクル (4)リサイクル・ リサイクル・処理企業に 処理企業に対する情報提供 する情報提供 ① リサイクル・処理企業が、使用済パソコンを適正処理できるように解体・処理の手順 などに関する適切な情報提供が出来ていること 特に有害/危険物質に関して、処理安全性などの観点から適切な情報が提供されてい ること P-1 環境に 環境に配慮した 配慮した設計 した設計・ 設計・製造 (1)省 (1)省エネルギー性 エネルギー性 ① 日本の省エネ法、または国際エネルギースタープログラムの適用年度の基準に準拠した 設計となっていること ② 消費電力などの情報をカタログ/取扱説明書、または製品本体に記載していること 8 (2)取扱 (2)取扱い 取扱い安全性及び 安全性及び電磁波影響 ① 機器の安全性については、下記に準拠していること 「JEIDA-37 または JIS C6950」、 「J60950」などの安全規格 ② 電磁波影響については、下記に適合していること JEITA の「情報処理機器用表示装置の低周波電磁界に関するガイドライン(JEITA ITR-3004)」 「VCCI(情報処理装置等電波障害自主規制協議会)」 (3)人 (3)人と環境に 環境に影響をおよぼす 影響をおよぼす恐 をおよぼす恐れのある化学物質 れのある化学物質 ① 日本の関連法規制を遵守し、グリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI)の「電気・ 電子機器製品に関する含有化学物質情報開示(JIG-101)」を準用して含有化学物質を 管理していること ②質量 25g 以上のプラスチック製筐体部品(本体、キーボード、マウス、ディスプレイ) には、IARC(国際がん研究所)の発ガン性物質に分類されている物質(レベル 1、2A) を使用しないこと ③ オゾン層保護法に規制される化学物質が、パソコンの構成部品、消耗品、保守部品、 包装材などに使用されていないこと ④バッテリー・パック用電池セル、バックアップ用コイン型電池には、カドミウム、鉛 及び水銀を処方構成成分として使用していないこと ⑤ 包装材用プラスチックについては、有機ハロゲン化合物を使用していないこと ⑥包装材は、鉛、カドミウム、六価クロム、水銀の4物質合計で100ppm 以下の含有 基準であること ⑦ 鉛、カドミウム、六価クロム、水銀、特定臭素系難燃剤(PBB、PBDE)の特定化学 物質は、製品中で含有率が基準値以下であること ⑧鉛、カドミウム、六価クロム、水銀、特定臭素系難燃剤(PBB、PBDE)が含有率の 基準値以下の場合、 「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法(JIS C0950)」 または申請時点で有効な業界ガイドラインに基づき、グリーンマークを表示すること。 また、除外項目に該当する部位がある場合は、Web サイトに含有情報を掲載すること ⑨特定の揮発性有機化合物の放散量は、申請時有効な JEITA の「パソコンに関するVO Cガイドライン」に定める指針値以下であること ⑩液晶バックライトの光源には、水銀含有量5mg未満/本の冷陰極管を使用している か、または水銀を使用していないこと 9 P-2 3R に配慮した 配慮した設計 した設計・ 設計・製造 (1)リデュース (1)リデュースを リデュースを配慮した 配慮した設計 した設計 ① 小型化、省資源化、長寿命化など、製品の機能を損なわない範囲で、リデュースを 追求した設計であること ・部品の共通化、部品点数の削減などにより、部品、部材の減量化を図ること ・修理・保守作業が容易な構造とすること ・製品の長寿命化に資する材料・部品の使用をすること ・リユース部品または再生材を使用していること ・植物原料プラスチック(バイオプラスチック)を使用し、省資源化をしていること ② 製品の品質保証ができる範囲で、アップグレードが容易で、かつ安全性を確保できるよう な構造設計がされていること ・アップグレードは、一般的に利用可能な道具を使用して実行できること (2)リユース (2)リユースを リユースを配慮した 配慮した設計 した設計 ① ハードディスク装置(HDD)、フロッピーディスク装置(FDD)、ディスプレイ、光ディ スク装置、メモリモジュールなどに、リユース可能なユニットを使用していること ②リユース可能な部品/ユニットは、機能破壊されることなく分離できる構造とすると共に、 汚れにくいまたは清掃しやすい材料を使用すること ③ パソコンのリユース対象部品の寿命または製造年月が把握できていること (3)リサイクル (3)リサイクルを リサイクルを配慮した 配慮した設計 した設計 ① リサイクルを容易にするため、機能を損なわない範囲で金属材料の統一、リサイクル を困難にする表面処理を行った材料の回避、リサイクル可能なプラスチックを採用し ていること ② 機能を損なわない範囲で、25g 以上のプラスチック材料については、種類の削減、また は統合していること ③ 25g 以上かつ 200 ㎜ 2 以上のプラスチック部品には、 「JIS K6899/K6999」または「ISO 1043/11469」に従った材料表示し、分別のための工夫をすること ④ マテリアルリサイクルが容易になるように、材料毎に解体できる構造であること ⑤リサイクル時に、二次電池(バッテリパック)が明確になるような表示がなされ、容易 に分別できること ⑥ 製品の回収及び運搬が容易な構造とすること ⑦ 一次/二次電池、蛍光管など事前選別と適正処理を必要とする部品、ユニット類について も、取り外しが容易な構造設計とすること 10 (4)取扱説明書及 (4)取扱説明書及び 取扱説明書及び包装・ 包装・梱包材に 梱包材に対するリデュース するリデュース、 リデュース、リサイクルの リサイクルの配慮 ① リデュースが配慮されていること ・取扱説明書及び包装・梱包材については、質量を削減すること ・取扱説明書は、再生紙または環境に配慮したバージンパルプを使用した紙であり、か つ無塩素漂白紙を使用していること ・包装・梱包材については、再生プラスチック、植物原料プラスチック(バイオプラス チック)、または再生紙を使用し、省資源化をしていること ② リサイクルが配慮されていること ・包装・梱包材は、安全性、機能性、経済性その他の必要な事項に配慮しつつ、段ボー ル及び発泡スチロールのリサイクル可能な材料を使用すると共に、段ボールと異種材 及び発泡スチロールと異種材などの分離が容易であること ・紙製及びプラスチック製の容器包装には、資源有効利用促進法に準拠した識別表示を していること ③ 包装材に関し、収集・運搬が容易な形態とすること 以上 11 PCグリーンラベル PCグリーンラベル適用申請書 グリーンラベル適用申請書 【2007 年度 企業審査編】 企業審査編】 有限責任中間法人 パソコン3 パソコン3R推進センター 推進センター 殿 申請日 年 月 日 PCグリーンラベル制度の趣旨を充分に理解し、適用申請を行います。 社印 申請会社名 (英語社名 ) 〔申請責任者〕 申請責任者〕 事業所名/ 事業所名/役職名 氏 名 印 ○ 〔連絡責任者〕 連絡責任者〕 事業所名/ 事業所名/部署名 役 職 名 氏 名 印 ○ 電 話 / FAX 電子メール 電子メール 12 PCグリーンラベル PCグリーンラベルチェックリスト グリーンラベルチェックリスト 【 2007 年 度 企業 審 査 編 】 C-1 「環境配慮型パソコン 環境配慮型パソコン」 パソコン」を設計・ 設計・製造できる 製造できる企業体制 できる企業体制 項 (1) 目 選択 必須 環境管理システム 環境管理システム ① パソコン パソコンを を開発または (環境マネージメ 開発または製造 または製造する 製造する事業所 する事業所で 事業所で、ISO 14001( 環境マネージメ ントシステム) ントシステム)が構築・ 構築・運用されている 運用されている ② パソコンを (環境マネージメ パソコンを開発または 開発または製造 または製造する 製造する事業所 する事業所で 事業所で、ISO 14001( 環境マネージメ ントシステム) ントシステム)認証取得中である 認証取得中である ③ 上記① 上記①と同等の 同等の環境マネージメントシステム 環境マネージメントシステムが マネージメントシステムが構築・ 構築・運用されている 運用されている (2) オゾン層破壊 オゾン層破壊物質 層破壊物質 (3 ) ① オゾン オゾン層保護法 層保護法に 層保護法に規定される化学物質 される化学物質を 化学物質を、パソコンの パソコンの直接製品納入業 者及び 者及び最終製造 最終製造( ( 組立) 組立 ) 工場で 工場 で 洗浄剤として 洗浄剤 として利用 製造 として利用し 利用していない ② 使用済 使用済みパソコンの パソコンのリユースや リユースやリサイクル工程 リサイクル工程でも 工程でも使用 でも使用されていな 使用されていな い 事前評価 C h C h C h C h C h ① アセスメント アセスメントの評価項目・ 評価項目・評価基準・ 評価基準・評価方法が 評価方法が定めてある C h ② アセスメントを アセスメントを実施する 実施するシステム するシステムが システムが構築してある 構築してある C h ③ アセスメントの アセスメントの結果は 結果は記録・ 記録・保管している 保管している (4 ) C h リデュースを リデュースを配慮した 配慮した体制 した体制 ① 製品を出荷後、 出荷後、少なくとも5 なくとも5年間修理を 年間修理を実施する 実施する体制 する体制を 体制を整備している 整備している (5 ) C h 回収及び 回収及び適正処理 ① 資源有効利用促進法及 資源有効利用促進法及び び 廃棄物処理法に 廃棄物処理法 に 合致した 合致 したリサイクルシステ した リサイクルシステ ム a 事業者もしくは家庭から排出されるパソコンに関して、排出者から 回収拠点まで、回収拠点から中間処理施設(再生処理施設を含む)や 最終処分場までの円滑な収集・運搬システムが構築されている b 適切な再資源化処理ができるような施設・システムを有している c 実際に使用済パソコンのリユース・リサイクルを担当する企業が、 適切な環境管理システムを構築していると共に、その企業に対して 定期的に委託内容に関する実態把握をしている 13 C h C-2 情報提供 項 (1) 目 選択 必須 ユーザに ユーザに対する情報提供 する情報提供 ① 当制度 当制度の の審査により 審査により、 により、基準を 基準をクリアしている クリアしている機種 している機種/ 機種/モデル名 モデル名がホーム ページなどを ページなどを活用 などを活用して 活用して情報開示 して情報開示されている 情報開示されている ② 取扱説明書に 取扱説明書に記載するなどの 記載するなどの情報提供 するなどの情報提供 a 製品の安全な使用方法が適切にできている C h b 使用済パソコン回収の問合せ窓口・処理方法が適切にできている C h ③ 修理条件と 修理条件とアップグレード性 アップグレード性の条件の 条件の情報提供 a 修理条件に関する情報提供が適切にできている C h b アップグレード性の条件に関する情報提供が適切にできている C h c 問合せ窓口が容易に分かるようにしてある ④ 公表 a 使用済パソコンの回収状況について、毎年度、公表している b 処理・再資源化の状況について、毎年度、公表している ⑤ 製品 製品審査 審査に 審査に合格したものは 合格したものは「PC したものは「PCグリーンラベルロゴマーク 「PCグリーンラベルロゴマークの グリーンラベルロゴマークの使用に 使用に 関する規程 する規程」 」 に 従 い 、 ロゴマーク表示 ロゴマーク 表示をしている をしている 規程 表示 (2) C h 自治体に 自治体に対する情報提供 する情報提供 ① 使用済パソコン 使用済パソコンの パソコンの引き取りに関 りに関する情報 する情報を 情報を公表している 公表している (3) 保守関連企業( 保守関連企業(部門) 部門) に対する情報提供 する情報提供 (4) ① リデュースを促進する観点から、修理・保守を容易にするためのマニ ュアルを提供するなどの情報提供が出来ている リサイクル・ リサイクル・処理企業に 処理企業に対する情報提供 する情報提供 ① リサイクル・処理企業が、使用済パソコンを適正処理できるように解 体・処理の手順などに関する適切な情報提供が出来ている ② 有害/危険物質に関して、処理安全性などの適切な情報が提供されてい る 14 C h C h C h C h 【補足】 補足】 「△」回答の 回答の部分については 部分については、 については、下記にて 下記にて、 にて、事由を 事由を明確にする 明確にする 15 PCグリーンラベル PCグリーンラベル適用申請書 グリーンラベル適用申請書 記入マニュアル 記入マニュアル 【2007 年度 企業審査編】 企業審査編】 「基準を 基準を満たす」 たす」場合は 場合は✔、 「条件付で 条件付で基準を 基準を満たす」 たす」場合は 場合は△を記入し 記入し、△部分につ 部分につ いては補足説明 いては補足説明をする 補足説明をする。 をする。小項目で 小項目で△を1個以上記入した 個以上記入した場合 した場合は 場合は、中項目でも 中項目でも△ でも△と評 価する。 (空欄) する。また、 また、選択項目で 選択項目で関連のない 関連のない項目 のない項目は 項目は「 空欄)」とする。 とする。 申請責任者欄 申請会社名:自社ブランドで日本国内に出荷する会社の名称 社印:公式の法人登録印とする 申請責任者名:本制度に関して何らかのトラブルが発生しても、対外的に責任 がとれる人 (当該企業で取締役以上の事業責任者が望ましい) 下記を添付資料として提出する 会社の登記簿謄本(パソコン3R 推進センター会員は不要) 「製品審査」を申請する予定のある事業所(企業)一覧(様式自由) C-1 (1) 下記のいずれかに適合していることを示す資料を添付のこと 申請会社のパソコンの開発または最終組立を担当する事業所名(OEM 生産会社を含 む)を明示すると共に、全事業所が ISO 14001 を取得していれば、基準を満たして いると判断する。尚、登録証(申請時に有効期限内であるもの)の写しを添付する こと。 ISO 14001 を取得していないが、それと同等レベルの環境マネージメントを構築・ 運用している場合は、その内容を示す環境報告書などの資料を添付すること(日本語 /英語どちらでも可) ISO 14001 を取得していないが、初回申請に限り、取得計画があれば「△」とし、 その計画書を提出すること。また、取得後は、速やかにその登録証の写しを提出する こと C-1 (2) 「直接製品納入業者」というのは、OEM 先のことを意味する。 オゾン層保護法で規制される化学物質とは、CFC、HCFC、臭化メチル、ハロン、HBFC、 四塩化炭素、1.1.1-トリクロロエタンを指す。 16 製造工程及びリサイクル工程での使用とは、洗浄剤などの部品や製品の製造・リサイク ルのために直接使用されるものを対象とする。 C-1 (3) 「環境設計ガイドライン 環境設計ガイドライン」 ガイドライン」に準拠した 準拠したアセスメント したアセスメントの アセスメントの実施 下記のいずれかの資料を添付のこと アセスメントを実施していることを示せる資料を添付のこと 「環境報告書」「デザインチェックリスト」などでの代用も可 「環境設計ガイドライン」準拠ではなく、独自に実施している場合には、実施内容を示 す資料を添付のこと(様式自由) 「環境設計ガイドライン」は下記 URL からダウンロードできる。 http://it.jeita.or.jp/document/publica/guideline/summary/g-19-2000.html C-1 (4) 5年間以上の修理体制をもっていることを示す資料を添付のこと 例えば、「取扱説明書」 「マニュアル」などの写しでも可 C-1 (5) 家庭系及び事業系パソコンについて、下記のいずれかの許認可が取得できていれば 「✔」とし、そのエビデンスを添付する 「廃棄物処理法の広域再生利用指定制度又は広域認定制度の認定証」 「廃棄物処理法の収集・運搬及び処理の許可証」 上記の許認可証のうち、前者については、初回申請に限り、既に申請中で、且つ、 未だ取得出来ていない場合は「△」とし、申請中であることの適切なエビデンスを 添付する 後者については、全国をカバーできることを証明できるエビデンスを添付する また、業務提携などにより、対応する場合は、提携先が上記のように許認可証を取得 できているというエビデンスを添付する リサイクル処理の委託先企業については、定期的に監査または確認を行うというこ とを明示している資料を添付すること(一次委託先の範囲で可) C-2 (1) ①については、基準をクリアしている機種/モデル名が掲載されているホームペー ジなどの写しを添付する。未だ情報開示していなくても、対応する予定があれば 「△」とし、その旨、補足事項として記入する ②a については、製品の安全な使用方法が記載されている取扱説明書の該当ページ の写しなどを添付する ②b については、使用済みパソコン回収の問合せ窓口、処理方法が掲載されているホ ームページなどの写しを添付する ③については、修理条件、アップグレード、問合せ窓口が記載されている取扱説明 書あるいはホームページの写しなどを添付する。尚、③b のアップグレード性につ いては、ディスプレイは対象外とすることも可 17 ④については、使用済パソコンの回収状況処理、再資源化の状況は掲載されている ホームページの写しを添付する。未だ実施していなくても、対応する予定があれば 「△」とし、その旨、補足事項として記入する ⑤については、ロゴマークが表示されているホームページあるいはカタログの写し を添付する。未だ実施していなくても、対応する予定があれば「△」とし、その旨、 補足事項として記入する C-2 (2) 自治体に適切な情報(引取条件)が提供されていることを明示する資料を添付する C-2 (3) 情報提供内容を示す資料を添付のこと 修理マニュアルが存在するという該当部分を資料として添付する C-2 (4) ①については、リサイクル・処理企業が使用済パソコンを適正処理できるように、解 体・処理の手順などに関する適切な情報提供が出来ていれば「✔」とし、関連書類 を添付する。 情報提供方法は、各社ホームページでの情報公開あるいはリサイクル・処理企業から の要求に応じての情報(資料)提供のいずれかとする。 未対応の場合、その計画があれば「△」とし、その旨、補足事項に記入する。 ②については、鉛、カドミウム、六価クロム、水銀、特定臭素系難燃剤(PBB、PBDE) に関する含有情報が、 「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法(JIS C0950)」 に基づき、ホームページに掲載されていれば「✔」とし、ホームページの写しを添付 する 18 PCグリーンラベル PCグリーンラベル適用報告書 グリーンラベル適用報告書 【2008 年度 製品審査編】 製品審査編】 有限責任中間法人 パソコン3 パソコン3R推進センター 推進センター 殿 報告日 年 月 PC グリーンラベル制度で決められた製品審査基準により、厳格に審査をし、 合格となりましたので報告をいたします。 報告会社名 タイプ 機種/ 機種/モデル名 モデル名 比較従来 機種名 掲載予定 URL http:// 〔報告責任者〕 報告責任者〕 事業所名/ 事業所名/役職名 氏 名 〔連絡責任者〕 連絡責任者〕 事業所名/ 事業所名/部署名 役 職 名 氏 名 電 話 / FAX 電子メール 電子メール 19 1.デスクトップ型 2.ノート型 3.ディスプレイ一体型 4.ディスプレイ 日 PCグリーンラベル PCグリーンラベルチェックリスト グリーンラベルチェックリスト 【 2008 年 度 製品 審 査 編 】 P-1 環境に 環境に配慮した 配慮した設計 した設計・ 設計・製造 (1) 省エネルギー性 エネルギー性 項 目 ① 当該基準への 当該基準への適合 への適合( 適合(対象カテゴリー 対象カテゴリーの カテゴリーの選択欄 選択欄をチェック) チェック) 選択 ノートブック型 デスクトップ型 ディスプレイ一体型 ディスプレイ 日本の省エネ法(経済産業省告示第 50 号 平成 18 年 3 月 29 日)の 2007 年度達成目標である基準エネルギー 消費効率を達成している 申請時点で有効な国際エネルギースターロゴ使用製 品の届出を完了している シンクライアント型 日本の省エネ法および国際エネルギースター対象外 である ② 消費電力などの 消費電力などの情報 などの情報提供 情報提供 必須 C h C h a カタログ/取扱説明書に記載している C h b 製品本体に記載している C h (2) 取扱い 取扱い安全性及び 安全性及び電磁波影響 項 目 ① 機器の または JIS C6950」、 」、「J60950」 」などの 機器の安全性については 安全性については、「 については、「JEIDA-37 、「 安全規格に 安全規格に準拠している 準拠している ② 電磁波影響( 電磁波影響(対象カテゴリー 対象カテゴリーの カテゴリーの必須欄を 必須欄をチェック) チェック) ディスプレイ ノートブック型 デスクトップ型 ディスプレイ一体型 ディスプレイ 選択 C h 「情報処理機器用表示装置の低周波電磁界に関するガ イドライン(JEI JEIT JEITA ITRITR-3004)」に適合している 3004 「VCCI(情報処理装置等電波障害自主規制協議会)」に 適合している (3) 人と環境に 環境に影響を 影響を及ぼす恐 ぼす恐れのある化学物質 れのある化学物質 項 目 ① 日本 日本の の製品に 製品に関する関連法規制を 関連法規制を遵守し 遵守し、JGPSSI の「電気・ 電気・電子機器製品に 電子機器製品に 関する含有化学物質情報開示 する含有化学物質情報開示(JIG 含有化学物質情報開示(JIG(JIG-101)」 101)」を準用し 準用して含有化学物質を 含有化学物質を管理し 管理して いる ② 質量 25g 以上の 以上のプラスチック製筐体部品 プラスチック製筐体部品( 製筐体部品(本体、 本体、キーボード、 キーボード、マウス、 マウス、ディ スプレイ) (国際がん スプレイ)には、 には、IARC( 国際がん研究所 がん研究所) 研究所)の発ガン性物質 ガン性物質に 性物質に分類されている 分類されている 物質( 、2A) ) を使用していないを 物質(レベル 1、 使用していないを採用時点 していないを採用時点で 採用時点で確認している 確認している 20 必須 C h C h 選 択 必須 C h C h ③ オゾン オゾン層保護法 層保護法に 層保護法に規制される 規制される化学物質 される化学物質が 化学物質が、パソコン パソコンの構成部品、 構成部品、消耗品、 消耗品、保守 部品、 部品、包装材などに 包装材などに使用 などに使用されていない 使用されていない ④ バッテリー・ バッテリー・パック用電池 パック用電池セル 用電池セル、 セル、バックアップ用 バックアップ用コイン型 コイン型電池の 電池の管理 C h a バッテリー・パック用電池セル、バックアップ用コイン型電池には、カド ミウム、鉛及び水銀を処方構成成分として使用していない b バッテリー・パック、バックアップ用コイン型電池を使用していない C h ⑤ 包装材用プラスチ 包装材用プラスチック プラスチックについては ックについては、 については、有機ハロゲン 有機ハロゲン化合物 ハロゲン化合物を 化合物を使用していない 使用していない C h ⑥ 包装材 包装材は は、鉛、カドミウム、 カドミウム、六価クロム 六価クロム、 クロム、水銀の 水銀の4物質合計で 物質合計で100ppm 100ppm 以下 の含有基準である 含有基準である ⑦ 鉛、カドミウム、 カドミウム、六価クロム 六価クロム、 クロム、水銀、 水銀、特定臭素系難燃剤( 特定臭素系難燃剤(PBB、 PBB、PBDE) PBDE)の特定 化学物質は 化学物質は、製品中で 製品中で含有率が 含有率が基準値以下である 基準値以下である 鉛、カドミウム、 カドミウム、六価クロム 六価クロム、 クロム、水銀、 水銀、特定臭素系難燃剤( 特定臭素系難燃剤(PBB、 PBB、PBDE) PBDE)は、含 有率の 有率の基準値以下の 基準値以下の場合、 場合、「電気 「電気・ 電気・電子機器の 電子機器の特定の 特定の化学物質の 化学物質の含有表示方法 C0950)」または 」または申請時点 申請時点で で 有効な 有効 な 業界ガイドライン 業界 ガイドラインに づき、グリーン ⑧ (JIS C0950) または申請時点 ガイドラインに基づき、 マークを マークを表示する 表示する。 する。また、 また、除外項目に 除外項目に該当する 該当する部位 する部位がある 部位がある場合 がある場合は 場合は、Web サイト に含有情報を 含有情報を掲載する 掲載する ⑨ 特定の 特定の揮発性有機化合物の 揮発性有機化合物の放散量は 放散量は、申請時有効な 申請時有効な JEITA の「パソコンに パソコンに関 するVOC するVOCガイドライン VOCガイドライン」 ガイドライン」に定める指針値以下 める指針値以下である 指針値以下である C h C h ⑩ 液晶バックライト 液晶バックライトの バックライトの水銀管理 a b c バックライトには、水銀を使用していない C h バックライトには、水銀含有量5mg未満/本の冷陰極管を使用している C h バックライトを使用していない P-2 3R に配慮した 配慮した設計 した設計・ 設計・製造 (1) リデュースを リデュースを配慮した 配慮した設計 した設計 項 目 選 択 ① 小型化 小型化、 、省資源化、 省資源化、長寿命化など 長寿命化など、 など、製品の 製品の機能を 機能を損なわない範囲 なわない範囲で 範囲での、リデ ュースを ュースを追求した 追求した設計 した設計 a 部品の共通化、部品点数の削減などにより、部品、部材の減量化をしてい る b 修理・保守作業が容易な構造とする c 製品の長寿命化に資する材料・部品の使用をしている d リユース部品または再生材などを使用している e 植物原料プラスチック(バイオプラスチック)の素材を使用し、省資源化 をしている 21 必須 C h C h C h C h C h ② 製品 製品の の品質保証ができる 品質保証ができる範囲 ができる範囲で 範囲で、アップグレードが アップグレードが容易で 容易で、かつ安全性 かつ安全性を 安全性を確 保できるような構造設計 できるような構造設計 a メモリ増設が出来る C h b 性能向上のためのユニットや部品の増設・追加、交換が可能である C h c 外部機器との接続性が確保されている C h d アップグレードは、一般的に利用可能な道具を使用して実行できる C h (2) リユースを リユースを配慮した 配慮した設計 した設計 項 目 選 択 必須 ① ハードディスク装置 ハードディスク装置( )、フロッピーディスク装置 フロッピーディスク装置( )、ディスプレイ、 ディスプレイ、 装置(HDD) 装置(FDD) 光ディスク装置 ディスク装置、 装置、メモリモジュールなどの メモリモジュールなどのリユース などのリユース可能 リユース可能な 可能なユニットの ユニットの使用 a リユース可能なユニット、部品を採用している C h b リユース可能なユニット、部品情報を明示している C h リユース可能 可能な 可能な部品/ 部品/ユニットの ユニットの、機能破壊されることなく 機能破壊されることなく分離 されることなく分離できる 分離できる構造 できる構造と 構造と共 ② リユース に、汚れにくいまたは清掃 れにくいまたは清掃しやすい 清掃しやすい材料 しやすい材料の 材料の使用 a リユース対象部品などが取り外し易い構造になっている C h b 清掃可能か、清掃しやすい構造になっている C h ③ リユース対象部品 リユース対象部品の 対象部品の寿命または 寿命または製造年月 または製造年月の 製造年月の把握 a ユニット、部品の寿命(MTBF)が明確である C h b ユニット、部品の製造年月が明確である C h (3) リサイクルを リサイクルを配慮した 配慮した設計 した設計 項 目 選 択 必須 ① 使用材料への 使用材料への、 への、リサイクルを リサイクルを容易にするための 容易にするための配慮 にするための配慮 a 機能を損なわない範囲で、金属材料を統一している b プラスチック材料にリサイクルを困難にする金属メッキ、塗装、樹脂コー ティングなどの表面処理を回避している c リサイクル可能なプラスチックの採用をしている ② 機能を 機能を損なわない範囲 なわない範囲で 以上のプラスチック材料 プラスチック材料については 種類の 範囲で、25g 以上の 材料については、 については、種類の 削減、 削減、または統合 または統合してい 統合している している 22 C h C h C h C h ③ 25g 以上かつ K6899/K6999」 」ま 以上かつ 200 ㎜ 2 以上の 以上のプラスチック部品 プラスチック部品には 部品には、「 には、「JIS 、「 たは「 」に従った材料表示 たは「ISO 1043/11469」 った材料表示を 材料表示を図り、分別のための 分別のための工夫 のための工夫を 工夫を行う ④ リサイクルが リサイクルが容易になるような 容易になるような、 になるような、材料毎に 材料毎に解体できる 解体できる構造 できる構造 C h a 再資源化原料としての利用が可能な材料、部品にするための解体・分離が 容易である b 異種材料の分離が容易な構造である C h C h c リサイクルを阻害する材料、部品が容易に分離できる構造である C h d リサイクルのための解体・分離方法が確立され、その工数の削減している C h e 部品数、ねじなどの削減している C h f 作業者にとって分別のための材料、部品などの材質判別が容易である C h ⑤ 資源有効利用促進法対象二次電池 資源有効利用促進法対象二次電池への 二次電池への表示 への表示 a 対象二次電池には資源有効利用促進法に準拠した識別表示がされ、ユーザ が容易に分別できる b 対象二次電池を使用していない C h ⑥ 製品の 製品の回収及び 回収及び運搬が 運搬が容易な 容易な構造とする 構造とする C h ⑦ 一次 一次/ /二次電池、 二次電池、蛍光管など 蛍光管など、 など、事前選別・ 事前選別・適正処理が 適正処理が必要な 必要な部品・ 部品・ユニットな ユニットな どは取 どは取り外しが容易 しが容易な 容易な構造である 構造である (4) 取扱説明書及び 取扱説明書及び包装・ 包装・梱包材に 梱包材に対するリデュー するリデュース リデュース、リサイクルの リサイクルの配慮 項 目 C h 選 択 必須 ① リデュースの リデュースの配慮 a 取扱説明書などの質量削減をしている b 包装・梱包材について、質量削減をしている c 取扱説明書は再生紙または環境に配慮したバージンパルプを使用した紙で あり、かつ無塩素漂白紙を使用している d 包装・梱包材について、再生プラスチック、植物原料プラスチック(バイ オプラスチック) 、または再生紙を使用し、省資源化を図っている ② リサイクルの リサイクルの配慮 a 包装材・梱包材は安全性、機能性、経済性その他の必要な事項に配慮しつ つ、段ボール及び発泡スチロールのリサイクル可能な材料を使用すると共 に段ボールと異種材及び発泡スチロールと異種材などの分離が容易である b 紙製及びプラスチック製の容器包装には、資源有効利用促進法に準拠した 識別表示をしている 23 C h C h C h C h C h C h ③ 包装材に 包装材に関し、収集・ 収集・運搬が 運搬が容易な 容易な形態とする 形態とする 24 C h PCグリー PCグリーンラベル グリーンラベル適用報告書 ンラベル適用報告書 記入マニュアル 記入マニュアル 【2008 年度 製品審査編】 製品審査編】 自己宣言型ラベル 自己宣言型ラベルであるので ラベルであるので、 であるので、必須項目については 必須項目については、 については、全て満足する 満足する( する(✔印を記入) 記入)こと が大前提となる 大前提となる。 となる。尚、選択項目についは 選択項目についは、 についは、対応できるもの 対応できるもの( できるもの(✔印を記入) 記入)が1個以上必 要であり、 (空欄 空欄)」 であり、選択しない 選択しない項目 しない項目は 項目は「 空欄 」とする。 とする。 「デスクトップ型 デスクトップ型」のディスプレイを ディスプレイを含めたセットモデル めたセットモデルでは セットモデルでは、 では、「パソコン 「パソコン本体部分 パソコン本体部分」 本体部分」 と「ディスプレイ部分 ディスプレイ部分」 部分」に分けて各 けて各々報告書を 報告書を提出する 提出する。 する。 但し、パソコン本体部分 パソコン本体部分と 本体部分とディスプレイ部分 ディスプレイ部分の 部分の消費電力を 消費電力を別々に測定することができ 測定することができ なく、 なく、かつ1 かつ1本のACケーブル ACケーブルで ケーブルでコンセントに コンセントに接続するものは 接続するものは( するものは(ディスプレイは ディスプレイはパソ コン本体 コン本体から 本体から電源供給 から電源供給)、 電源供給)、セット )、セットで セットで報告書を 報告書を提出する 提出する。 する。 各々の製品の 製品の性格を 性格を配慮し 配慮し、下記の 下記のチェックリスト項目 チェックリスト項目は 項目は審査対象外とする 審査対象外とする。 とする。 デスクトップ型 デスクトップ型及びディスプレイ一体型 ディスプレイ一体型パソコン 一体型パソコン: パソコン: P-2 (3) (3) ⑤ ディスプレイ: ディスプレイ: P-2 (1) (1) ②、 P-2 (2)、 (2)、 P-2 (3) (3) ⑤ 報告者欄 報告会社名:「企業審査」で承認されている会社名(グループ会社含む)を記載 機種/モデル名:欄内に全て記入できない場合は、添付(様式自由)資料とする 比較従来機種がない場合は、「―」を記入する 報告責任者:評価結果について、対外的に責任がとれる人 (日本国内の、製品の開発・設計責任者あるいは製品を評価した責任者で、部長 クラス以上が望ましい) 連絡責任者:適用報告内容について、上記責任者との連絡窓口となる人 (パソコン3R推進センター連絡担当者及び運営委員会メンバーが 望ましい) P-1 (1)① エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、 省エネ法で定める複合理論性能で除したものである。アイドル状態と低電力モード の消費電力の平均値を複合理論性能で除した数値をトップランナー基準として、 2007 年度達成目標としている。 国際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成19年7月施行)は下記 URL からダウンロードできる。 http://www.eccj.or.jp/ene-star/prod/data_outline/rules_pubcom_2007_07.pdf 25 P-1 (1)② 「消費電力などの情報」とは「消費電力」「エネルギー消費効率」「省電力機能」の説明 を示す。(全てが書かれている必要はない) P-1 (2)① 同等の規格には、IEC60950、UL60950、CSA60950 などがある。 P-1 (2)② 「JEITA ITR-3004」はディスプレイについて、 「VCCI」はデスクトップ型、ノート型、ディ スプレイ一体型及びディスプレイについて判断をする。 「JEITA ITR-3004」は下記 URL からダウンロードできる。 http://www.jbmia.or.jp/~tc/gl-lowfreq-3.pdf P-1 (3)① 関連法規を遵守し、また JGPSSI の「含有化学物質情報開示(JIG-101)」を準用していれば 「✔」 。ただし、 「含有化学物質情報開示(JIG-101)」は、当面のあいだ、構成部品などの購入 時ドキュメント( 「購入仕様書」 、 「メーカ確認書」など)で確認していればよい。 「化学物質の使用」とは、素材、部品製造時に性能、機能を出すために必要な化学物質 を意図的に添加することをいう。したがって、想定しない物質(不純物)が混入する場合や、 生産工程で使用されても理論的に素材や部品に残らない場合は、化学物質の使用に当たらな い。 「含有化学物質情報開示(JIG-101)」は下記 URL からダウンロードできる。 http://210.254.215.73/jeita_eps/green/greendata/JIG200601/JIG_Japanese060105.pdf 〔ご参考〕 参考〕 化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)第 1 種特定化学物質及び安衛法 (労働安全衛生法)で で製造などが禁止される有害物質を使用していないこと。 P-1 (3)② プラスチック製筐体部品とは、パソコン本体、キーボード、マウス、ディスプレイの 外装ケースに使用されるプラスチック製部品を指し、内部のユニットや部品は対象外。 IARC の指定物質の中で、高分子材料の原料として使用されているものは対象外。 「六価クロム」、 「カドミウム」は P-1(3)⑦で、また「ホルムアルデヒド」は P-1(3) ⑨で規定しているので対象外。 購入時に「発ガン性物質が使用されていない」ことをドキュメント(「購入仕様書」 「メ ーカ確認書」など)で確認していれば、当面は「✔」という判断をする。 IARC の発ガン性物質については下記を参照。 http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/ListTable.do P-1 (3)③ 構成部品などの購入時に「オゾン層保護法で規定された化学物質が使用されていな い」ことをドキュメント(「購入仕様書」 、 「メーカ確認書」など)で確認していれば「✔」 とする。 26 P-1 (3)⑤ 有機ハロゲン化合物とは、ポリ塩化ビニルなどのプラスチック、プラスチックの難燃 剤、プラスチックの発泡剤などを指す。 P-1 (3)⑦ 製品に含まれる特定化学物質の除外項目及び含有率の算出の考え方は、申請時に有効 な「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法 (JIS C0950)」を参照すること。 P-1 (3)⑧ グリーンマークは、製品、包装箱、カタログ類、ホームページ、取扱説明書のうち、 一つ以上に表示すること P-1 (3)⑨ タイプ群(製品区分)のなかで放散量の多い製品(容積、質量、ディスプレイサイ ズ、熱分布、材料データなどから判断)を選定し、この測定結果が指針値以下である なら、タイプ群のなかの製品は全機種適合と見なす。ただし、ロットばらつきなどを 考慮し、指針値に対しマージンが少ない場合は、複数台の測定を行い判断すること。 「製品審査」提出までに測定出来ない場合は「△」として提出できる。ただし、測 定後速やかに「製品審査」を再提出する。測定結果が適合なら「✔」として再申請、 非適合なら対象の申請機種の申請日、機種/モデル名をフリーフォーマットで報告す る。 「VOCガイドライン」は下記 URL からダウンロードできる。 http://it.jeita.or.jp/infosys/committee/environ/0509VOCguideline/index.html 「VOCガイドライン」が改版された時、新版の有効日から半年間は旧版に基づく測定の 結果で判断することができる。 P-2 (1)① 「環境設計ガイドライン」をベースに判断をする。 (従来モデルと比較して同等以上であれば「✔」とする) リサイクル材には、再生プラスチックも含まれ、その定義は JIS「Q 14021」による。 [ご参考] リサイクル材料含有率及びこれに関連する用語の定義は,次による。 a) リサイクル材料含有率 リサイクル材料含有率 製品又は包装中に含有するリサイクル材料の質量比。プレコンシューマ材料及び ポストコンシューマ材料だけをリサイクル材料とみなさなければならない。 なお,これらの材料は,次の用語の定義による。 1) プレコンシューマ材料 プレコンシューマ材料 製造工程における廃棄物の流れから取り出された材料。その発生と同一の工程 で再使用できる加工不適合品,研磨不適合品,スクラップなどの再利用を除く。 2) ポストコンシューマ材料 ポストコンシューマ材料 家庭から排出される材料,又は製品のエンドユーザとしての商業施設,工業 施設及び各種施設から本来の目的のためにはもはや使用できなくなった製品として発生する材料。これ には,流通経路から戻される材料を含む。 b) リサイクル材料 リサイクル材料 製造工程において回収[再生]材料から再加工され,更に最終製品,又は製品へ組み込 まれる部品に使用される材料。 c) 回収〔再生〕材料 廃棄物として処分されるはずの材料,又はエネルギー回収の目的に供されるはずの材 料ではあるが,代わってリサイクル又は製造工程のために,新規の原料に替わる原料として収集及び回収 [再生]される材料。 27 P-2 (1)② メモリの増設など、メーカが保証できる範囲で、お客様がアップグレードできるような 配慮がなされているかどうかにより判断する。 「一般的に利用可能な道具」とは一般に購入可能な道具をさす。 P-2 (2)① 「環境設計ガイドライン」をベースに判断をする。 〔ご参考〕 参考〕 「リユース」とは、ユーザから使用済みとなり、回収された製品などから、リユ ース可能なものを選択し、そのまま、もしくはリペアなどを施した上で修理部品 などに使用することである。 リユース可能な部品などの情報は、修理業者や再資源化業者などが利用できるよ うに、リユースする部品には型番号などの部品情報を明示すること。 P-2 (2)② 「環境設計ガイドライン」をベースに判断をする。 具体的には、製品設計段階でリユース対象部品などを取り付けているねじなどの数、 種類、工法などが、取り外し容易な構造になっているか、また、解体・分離する際に 使用する工具の種類や数が、必要最小限になっているかを評価して判断する。 〔ご参考〕 参考〕 「リユース対象部品など」とは、 「リユース可能な部品/ユニット」のことである。 P-2 (2)③ 「環境設計ガイドライン」をベースに判断をする。 P-2 (3)① 「環境設計ガイドライン」をベースに判断をする。 具体的には、この製品が将来、使用済みとなった時に、リサイクルが可能と判断され る部品や材料の質量割合を定量的に推定、評価していることを確認して判断する。 P-2 (3)③ 「環境設計ガイドライン」をベースに判断をする。 但し、25g 以上かつ 200 ㎜ 2 以上のプラスチック部品であっても、機能を損なうおそ れのある部品は除く。(例:導光板など) 28 P-2 (3)④ 「環境設計ガイドライン」をベースに判断をする。 原則的にリユース、マテリアルリサイクルを優先とするリサイクル可能率の向上が 重要であり、特にプラスチック部品では、ラベル貼り付け、金属インサート、接着 などの回避または削減がされていることを確認して判断する。 「異種材料」とは、製品/部品の組立工程での加工で異種材料が部分的に接着・接合 され、解体時に物理的な力で単一材に分離できるものを示す。 例)プラスチック部品へのインサートネジ埋め込みなど P-2 (3)⑤ ユーザが容易に分別できるとは、「環境設計ガイドライン」のA、B、Cレベルであ れば「✔」という判断をする P-2 (4)① 取扱説明書は、自社の責任にて製作したものを示す。 「環境を配慮したバージンパルプ」とは、紙の原料(木材など)が原料産出地の法律、 規則を守って生産されたもの、または森林環境に配慮した森林認証材などで生産された ものを示す。 質量については、従来モデルに比較して同等以下となっていれば「✔」とする。 P-2 (4)② 「資源有効利用促進法」に準拠しているかどうかで判断をする。 〔ご参考〕 参考〕 上記法律の中で、分別回収のための「指定表示製品」として、紙製容器包装とプラスチッ ク製容器包装が指定されており、容器包装への識別表示が義務づけられている。識別表 示のための識別表示マークは、上記法律で規定されているマークである。 下記 URL に事例がある。 http://www.aeha.or.jp/02/a02.html http://www.aeha.or.jp/02/hyoujijirei.pdf P-2 (4)③ 主に段ボールを対象とし、「環境設計ガイドライン」をベースに判断をする。 以上 29 PCグリーンラベル PCグリーンラベル製品審査合否判定 グリーンラベル製品審査合否判定の 製品審査合否判定の運用報告書 【2008 年度】 年度】 有限責任中間法人 パソコン3 パソコン3R推進センター 推進センター 殿 PC グリーンラベル制度で決められた製品審査基準により、製品基準合否判定の 運用について報告をいたします。 報告日 報告会社名 ○○○○年○○月○○日 ○○○株式会社 〔報告責任者〕 報告責任者〕 事業所名/ 事業所名/部署名 氏名 役職名 電話/ 電話/FAX 電子メール 電子メール 報告製品タイプ 報告製品タイプ △△△△事業本部□□□□事業部○○○○部 ○○○○ 部長 123-456-7890 [email protected] ■デスクトップ型 ■ノート型 ■ディスプレイ一体型 ■ディスプレイ 30 P-1 環境に 環境に配慮した 配慮した設計 した設計・ 設計・製造 (1) 省エネルギー性 エネルギー性 項目 ① 当該基準への 当該基準への適合 への適合 日本の省エネ法(経済産業省告示第 50 号 平成 18 年 3 月 29 日)の 2007 年度 達成目標である基準エネルギー消費効 率を達成している 申請時点で有効な国際エネルギースタ ーロゴ使用製品の届出を完了している 合否判定方法 ・省エネ法の測定方法に基づく消費電力 測定データまたは製品仕様書、製品カ タログへの記載を確認。 ・エネルギー消費効率を算出して該当す る区分の基準値以下であるため適合と 判断。 ・代表機種による国際エネスタ申請書を確 認。 ・該当する製品の基準値以下であるため適 合と判断。 エビデ ンス ○ 例:製 品カタ ログな ど ○ 例:申 請書な ど 日本の省エネ法および国際エネルギースタ ー対象外である ② 消費電力などの 消費電力などの情報 などの情報提供 情報提供 a カタログ/取扱説明書に記載している ・製品カタログ及び取扱説明書を確認。 ・消費電力値、エネルギー消費効率を 記載しているため適合と判断。 b 製品本体に記載している ○ 例:製 品カタ ログな ど (2) 取扱い 取扱い安全性及び 安全性及び電磁波影響 項目 合否判定方法 ① 機器の 機器の安全性については 安全性については、「 については、「JEIDA-37 、「 または JIS C6950」、 」、「J60950」 」などの安 などの安 全規格に 全規格に準拠している 準拠している ② 電磁波影響 ・IEC60950 に準拠した社内規定による 設計、評価データを確認。 ・基準を満足しているため適合と判断。 「情報処理機器用表示装置の低周波電磁波 に関するガイドライン(JEITA ITR-3004)」 「VCCI(情報処理装置等電波障害自主規制 協議会)」 ・基準を満足しているため適合と判断。 ・VCCI に基づく測定データまたは届出 書を確認。 ・基準を満足しているため適合と判断。 ・ディスプレイは「JEI JEIT JEITA ITRITR-3004」に準拠し 3004 た社内規定による測定データを確認。 エビデ ンス VCCI のみ○ 例:届 出書な ど (3) 人と環境に 環境に影響を 影響を及ぼす恐 ぼす恐れのある化学物質 れのある化学物質 項目 合否判定方法 ① 日本の 日本の製品に 製品に関する関連法規制 する関連法規制を 関連法規制を遵守 し、JGPSSI の「電気・ 電気・電子機器製品 電子機器製品に 機器製品に関す る含有化学物質情報開示 含有化学物質情報開示(JI 学物質情報開示(JIG (JIG-101)」 101)」に準用 して含有化学物質を 含有化学物質を管理し 管理している ・「電気・電子機器製品に関する含有化学 物質情報開示(JIG-101 101)」に準用した社 101 内規定の評価結果を確認。 ・禁止物質の未使用及び抑制物質の管理 をしているため適合と判断。 31 エビデ ンス ② 質量 25g 以上の 以上のプラスチック製筐体 プラスチック製筐体 部品( 部品(本体、 本体、キーボード、 キーボード、マウス、 マウス、ディ スプレイ) (国際がん スプレイ)には、 には、IARC( 国際がん研 がん研 究所) 究所)の発ガン性物質 ガン性物質に 性物質に分類されている 分類されている 物質( 、2A) ) を使用していないこ 物質(レベル 1、 使用していないこ とを採用時点 とを採用時点で 採用時点で確認している 確認している ・「環境設計ガイドライン」に準拠した社 内規定の評価結果を確認。 ・禁止物質の未使用であるため適合と判 断。 ③ オゾン層保護法 オゾン層保護法に 層保護法に規制される 規制 される化学物質 される化学物質 ・同上 が、 パソコンの パソコン の構成部品、 構成部品、 消耗品、 消耗品、 保守部 品、包装材などに 包装材などに使用 などに使用されていない 使用されていない ④ バッテリー・ バッテリー・パック用電池 パック用電池セル 用電池セル、 セル、バッ クアップ用 クアップ用コイン型 コイン型電池の 電池の管理 ・同上 a バッテリー・パック用電池セル、バック アップ用 用 コイン型 コイン 型 電池には、カドミウ ム、鉛及び水銀を処方構成成分として使 用していない b バッテリー・パック、バックアップ用 用コ イン型 イン型電池を使用していない ⑤ 包装材用プラスチ 包装材用プラスチック プラスチックについては ックについては、 については、有 機ハロゲン化合物 ハロゲン化合物を を 使用していない 使用 していない 化合物 ・同上 ⑥ 包装材は 包装材は、鉛、カドミウム、 カドミウム、六価クロ 六価クロ ム、水銀の 水銀の 4 物質合計で 物質合計で 100ppm 以下の 以下の含有 基準である 基準である ・ 「環境設計ガイドライン」に準拠した社 内規定の評価結果またはグリーン調達 結果を確認。 ・合計の含有が基準値以下のため適合と 判断。 ⑦ 鉛、カドミウム、 「環境設計ガイドライン」に 準拠した カドミウム、六価クロム 六価クロム、 クロム、水銀、 水銀、 ・ 特定臭素系難燃剤(PBB 社内規定の評価結果またはグリーン調 特定臭素系難燃剤(PBB、 (PBB、PBDE PBDE)の特定化学物 質は、製品中で 達結果を確認。 製品中で含有率が 含有率が基準値以下である 基準値以下である ・対象物質の一部(PBB,PBDE)は 未使用。その他の物質は基準値以下の 含有のため適合と判断。 ⑧ 鉛、カドミウム、 水銀、 、 ・JIS C 0950:2005 に規定する特定物質の カドミウム、六価クロム 六価 クロム、 クロム、 水銀 特定臭素系難燃剤( 含有表示を、機器本体、機器包装箱、 特定臭素系難燃剤(PBB、 PBB、PBDE) PBDE) は、含有 率の基準値以下の 「電気 カタログ類、WEB サイトで確認。 基準値以下の場合、 場合、 「電気・ 電気・電子機器の 電子機器の 特 定 の 化 学 物 質 の 含 有 表 示 方 法 ( JIS C0950) C0950)」または 」または申請時点 有効な業界ガイ 業界ガイ または申請時点で 申請時点 で有効な ドラインに ドラインに基 づき、 づき、グリーンマークを グリーンマーク を表示 する。 する 。また、 また、 除外項目に 除外項目に該当する 該当する部位 する部位があ 部位があ る場合は 場合は、Web サイトに サイトに含有情報を 含有情報を掲載する 掲載する ⑨ 特定の 特定の揮発性有機化合物の 揮発性有機化合物の放散量は 放散量は、 ・JEITA の VOC ガイドラインに基づく放 JEITA の申請時有効な 散速度の測定データを確認。 申請時有効な「パソコンに パソコンに関するV するV OCガイドライン OC ガイドライン」 ガイドライン」に定める指針値以下 める指針値以下で 指針値以下で ・JEITA 指針値の放散速度以下であるた ある め適合と判断。 32 ○ 記 載 WEB サイト の URL の提示 ⑩液晶バックライト 液晶バックライトの バックライトの水銀管理 ・社内規定の評価結果を確認。 ・液晶 液晶バックライト 液晶バックライトの バックライトの光源には水銀を使 用しないものを使用しているため適合 a バックライト バックライトには、水銀を使用していな と判断。 い b バックライトには、水銀含有量5mg未 バックライト 満/本の冷 陰極管を使用している c バックライトを使用していない バックライト P-2 3R に配慮した 配慮した設計 した設計・ 設計・製造 (1) リデュースを リデュースを配慮した 配慮した設計 した設計 項目 ① 小型化、 小型化、省資源化、 省資源化、長寿命化など 長寿命化など、 など、製 品の機能を 機能を損なわない範囲 なわない範囲で 範囲で、リデュース を追求した 追求した設計 した設計 a 部品の共通化、部品点数の削減などによ り、部品、部材の減量化を図る b 修理・保守作業が容易な構造とする 合否判定方法 エビデ ンス ・「環境設計ガイドライン」に 準拠した社内規定の評価結果を確認。 ・リデュースを考慮した設計をしている ため適合と判断。 c 製品の長寿命化に資する材料・部品の使 用を図る d リユース部品または再生材などを使用し ている e 植物原料プラスチック(バイオプラスチッ ク)の素材を使用し、省資源化を図って いる ② 製品の 製品の品質保証ができる 品質保証ができる範囲 ができる範囲で 範囲で、アッ プグレードが プグレードが容易で 容易で、かつ安全性 かつ安全性を 安全性を確保で 確保で きるような構造設計 きるような構造設計 a メモリ増設が出来る ・「環境設計ガイドライン」に準拠した社 内規定の評価結果,製品カタログ,取扱 説明書などを確認。 ・アップグレードが容易な設計をしてい るため適合と判断。 b 性能向上のためのユニットや部品の増設 ・追加、交換が可能である c 外部機器との接続性が確保されている ○ 例:製 品カタ ログま たは取 説など d アップグレードは、一般的に利用可能な道 具の使用で実行できる (2) リユースを リユースを配慮した 配慮した設計 した設計 項目 合否判定方法 ① ハードディスク装置 )、フロッピ ハードディスク装置( 装置(HDD) ーディスク装置 装置( )、ディスプレイ、 ーディスク 装置(FDD) ディスプレイ、光 ディスク装置 ディスク装置、 装置、メモリモジュールなどの メモリモジュールなどのリ などのリ ユース可能 ユース可能な 可能なユニットの ユニットの使用 ・「環境設計ガイドライン」に準拠した社 内規定の評価結果,取扱説明書などを確 認。 ・リユース可能な部品/ユニットの採用 をしているため適合と判断。 a リユース可能なユニット、部品を採用し ている b リユース可能なユニット、部品情報を明 示している ・設計図面などに記載してあることを確認 33 エビデ ンス a のみ ○ 例:製 品カタ ログま たは取 説など ② リユース可能 リユース可能な 可能な部品/ 部品/ユニットの ユニットの、機能 ・ 「環境設計ガイドライン」に準拠した社 破壊されることなく 破壊されることなく分離 されることなく分離できる 分離できる構造 できる構造と 構造と共に、 内規定の評価結果を確認。 汚れにくいまたは清掃 れにくいまたは清掃しやすい 清掃しやすい材料 しやすい材料の 材料の使用 ・リユース可能部品の分離が容易な構造 a リユース対象部品などが取り外し易い構造 としているため適合と判断。 になっている b 清掃可能か、清掃しやすい構造になって いる ③ リユース対象部品 リユース 対象部品の 対象部品 の 寿命または 寿命 または製造 または 製造 年月の 年月の把握 a ユニット、部品の寿命(MTBF)が明確であ る b ユニット、部品の製造年月が明確である ・リユース対象部品の仕様書を確認。 ・MTBF、製造年月日が明確であるため 適合と判断。 (3) リサイクルを リサイクルを配慮した 配慮した設計 した設計 項目 合否判定方法 ① 使用する 使用する材料 する材料への 材料への、 への、リサイクルを リサイクルを容易 にするための配慮 にするための配慮 ・「環境設計ガイドライン」に準拠した社 内規定の評価結果を確認。 ・リサイクルを配慮した設計としている ため適合と判断。 a 機能を損なわない範囲で金属材料の統一が 図られている b プラスチック材料にリサイクルを困難に する金属メッキ、塗装、樹脂コーティン グなどの表面処理を回避している c リサイクル可能なプラスチックの採用を している ② 機能を 機能を損なわない範囲 なわない範囲で 範囲で、25g 以上の 以上の プラスチック材料 プラスチック 材料については 材料 については、 については 、 種類の 種類 の 削 減、または統合 または統合を 統合を図る ③ 25g 以上かつ 以上かつ 200 ㎜ 2 以上の 以上のプラスチ ック部品 K6899/K6999」 」また ック部品には 部品には、「 には、「JIS 、「 は「ISO 1043/11469」 」に従った材料表示 った材料表示 を図り、分別のための 分別のための工夫 工夫を を のための工夫 行う ④ リサイクルが リサイクルが容易になる 容易になるよう になるような ような、材料 毎に解体できる 解体できる構造 できる構造 ・同上 ・同上 ・同上 a 再資源化原料としての利用が可能な材料、 部品にするための解体・分離が容易であ る b 異種材料の分離が容易な構造である c リサイクルを阻害する材料、部品が容易 に分離できる構造である d リサイクルのための解体・分離方法が確 立され、その工数の削減を図っている e 部品数、ねじなどの削減を図っている f 作業者にとって分別のための材料、部品 などの材質判別が容易である ⑤ 資源有効利用促進法対象二次電池へ 資源有効利用促進法対象二次電池 へ の表示 ・資源有効利用促進法に基づく社内規定 の評価結果を確認。 34 エビデ ンス a 対象二次電池には資源有効利用促進法に準 拠した識別表示がされ、ユーザが容易に識別で きる b 対象二次電池を使用していない ・二次電池使用製品は表示有り、分別が 容易であるため適合と判断。 ⑥ 製品の 製品 の 回収及び 回収及 び 運搬が 運搬 が 容易な 容易 な 構造と 構造 と する ・「環境設計ガイドライン」に準拠した社 内規定の評価結果を確認。 ・回収、運搬を配慮した構造としている ため適合と判断。 ・「環境設計ガイドライン」に準拠した社 内規定の評価結果,取扱説明書などを確 認。 ・事前選別、適正処理を配慮した構造と しているため適合と判断。 ⑦ 一次/ 一次/二次電池、 二次電池、蛍光管など 蛍光管など、 など、事前選 別・適正処理が 適正処理が必要な 必要な部品・ 部品・ユニットなど ユニットなど は取り外しが容易 しが容易な 容易な構造である 構造である (4) 取扱説明書及び 取扱説明書及び包装・ 包装・梱包材について 梱包材について、 について、リデュース、 リデュース、リサイクの リサイクの配慮 項目 ① リデュースの リデュースの配慮 a 取扱説明書などの質量削減を図っている 合否判定方法 エビデ ンス ・「環境設計ガイドライン」に準拠した社 内規定の評価結果を確認。 ・リデュースを考慮した取扱説明書及び 包装材としているため適合と判断。 b 包装・梱包材について、質量削減を図っ ている c 取扱説明書は再生紙または環境に配慮 したバージンパルプを使用した紙であ り、かつ無塩素漂白紙を使用している d 包装・包装材について、再生プラスチック、 植物原料プラスチック(バイオプラスチ ック)または再生紙を使用し、省資源化 を図っている ② リサイクルの リサイクルの配慮 a 包装材・梱包材は、安全性、機能性、経済 性その他の必要な事項に配慮しつつ、段ボ ール及び発泡スチロールのリサイクル可能 な材料を使用すると共に段ボールと異種材 及び発泡スチロールと異種材などの分離が 容易である b 紙製及びプラスチック製の容器包装には、 資源有効利用促進法に準拠した識別表示 を図る ③ 包装材に 包装材に関し、収集・ 収集・運搬が 運搬が容易な 容易な形 態とする ・「環境設計ガイドライン」に準拠及び資 源有効利用促進法に基づく社内規定の 評価結果を確認。 ・リサイクルを配慮した包装材設計及び 識別表示がされているため適合と判断。 ・「環境設計ガイドライン」に準拠した社 内規定の評価結果を確認。 ・収集、運搬を考慮した設計をしている ため適合と判断。 注意:本運用報告書の表紙及び合否判定方法の欄において、赤色で記述しているものは 記入例を示しています。報告書作成時は赤色の箇所を削除し、黒色で記入し、P C3Rに報告をお願いします。 35 b のみ ○ (例:識 別表示 の画像) PC グリーンラベルロゴマークの グリーンラベルロゴマークの使用に 使用に関する規程 する規程 1 目 的 本規程は、有限責任中間法人 パソコン3R推進センター(以下、PC3R)「PC グリーンラ ベル運営委員会」が定めた「PC グリーンラベル基準項目」を満たしていることを示す「PC グリーンラベルロゴマーク(以下、ロゴマーク)」(別添)の使用に関する規程である。 本規程を正しく運用することにより、「PC グリーンラベル制度」を健全に普及させることを 目的とする。 2 使用範囲 ロゴマークの使用範囲は、 「PC グリーンラベル基準項目」を満たしている対象製品のカタロ グ、マニュアル、梱包箱、広告印刷物及びこれらに類するものを対象とする。尚、対象製品 本体に貼付してはならない。 3 ロゴマークの ロゴマークの使用資格 PC3R は、 「PC グリーンラベル適用申請【企業審査】」合格企業に対してのみ、ロゴマークの 使用を許諾することができる。 「PC グリーンラベル適用申請【企業審査】 」合格通知を受けた 企業は、直ちにロゴマークの使用を許諾されたものとする。尚、使用を許諾された企業は、 ロゴマークを使用するに当たって、該当製品が「PC グリーンラベル製品審査基準」を満たし ていることを検証しておかなければならない。 4 使用規程違反の 使用規程違反の取り扱い (1)ロゴマークを使用した製品が「PC グリーンラベル基準項目」を満たしていないことが判明し た場合、当該ロゴマーク使用企業は、直ちにロゴマークの使用を停止しなければならない。 (2)ロゴマークを表示した製品が、 「PC グリーンラベル基準項目」を満たしていないことが判 明したにもかかわらず、前項の処置を取らない場合、PC3R は、当該ロゴマーク使用企業 に対し、その使用資格を剥奪することができる。 5 使用資格の 使用資格の消滅について 消滅について 「PC グリーンラベル基準項目」の見直しなどにより、 「PC グリーンラベル適用申請【企業審査】 」 合格の効力を失った企業は、同時にロゴマークの使用資格も消滅する。ただし、再申請により、 改めて「PC グリーンラベル適用申請【企業審査】」に合格した場合は、この限りでない。 6 ロゴマークに ロゴマークに付随する 付随する文言 する文言 (1)ロゴマークを使用する場合は、次の文言を付記しなければならない。 『本製品は PC3R「PC グリーンラベル制度」の審査基準(××××年度版)を満たしてい ます。詳細は、Web サイト http://www.pc3r.jp をご覧下さい。』 ただし、文言のみとして、ロゴマークを付記しないことは可能である。尚、一つのカタ ログに、旧基準と新基準に適合した製品を掲載する場合、該当年度と対象機種を明確にす ること(例:PC-ABC:XXXX年度版) (2)上記(1)に掲げる文言は、必ずロゴマークに付随していなくてはならない(梱包箱を除く)が、 必ずしもロゴマークに隣接して記載する必要はない。広告印刷物などにおいては、脚注等 に記載しても良い。 (3)上記(1)以外の文言をキャプションとしてロゴマークに隣接して記載してはならない。 (4)ただし、環境ラベルの説明やリンクを張るために使用する場合は上記(1)以外の文言を使 用してもよい。 36 基本デ ザイン デジタル・データを直接、または拡大・縮小 したものを使用して下さい。 複写機などで縮小・拡大しての使用は避けて 下さい。 基本カ ラー カラー使用時 特色の場合 4色分解の場合 特色の場合 4色分解の場合 DIC:638 シアン 90%+イエロー100% DIC:163 マゼンタ 50%+イエロー100% 単色使用時 100% アミ 60% 背景色との関係 背景色が黒の場合 背景色がロゴの色と近い場合は、近い色を白ヌキ 背景色との関係で認識しづらい場合は白ヌキ 37 最小使 用サイズ 右記の最小(上下 8 ㎜×左右 13 ㎜)のものを限度として、 このサイズ未満の縮小使用は認められません。 使用禁 止例 変形 基本色以外の使用 バランスの変更 書体の変更 デザイン的加工 認識しづらい背景のデザイン処理 文章中のマークの使用 分断 38 カラー 使用時 カラー使用時 特色の場合 4色分解の場合 特色の場合 4色分解の場合 DIC:638 シアン 90%+イエロー100% DIC:163 マゼンタ 50%+イエロー100% 単色使用時 100% アミ 60% 最小使用サイズ 右記の最小(上下 8 ㎜×左右 13 ㎜)のものを限度として、 このサイズ未満の縮小使用は認められません。 39